第三章 合同評価
1 フランスとの合同評価:フィリピン
(現地調査期間:1995年12月11日~22日)
<評価調査団の構成>
(日本側)
大林 稔 龍谷大学経済学部教授
重光 哲明 医学博士、他
(フランス側)
ジャン=ベルナール・ティアン フランス経済協力省情報課課長
モーリス・フィエスキ ティモーヌ病院医学情報サービス室長
エリック・モラン 在チャード協力省事務所駐在専門家
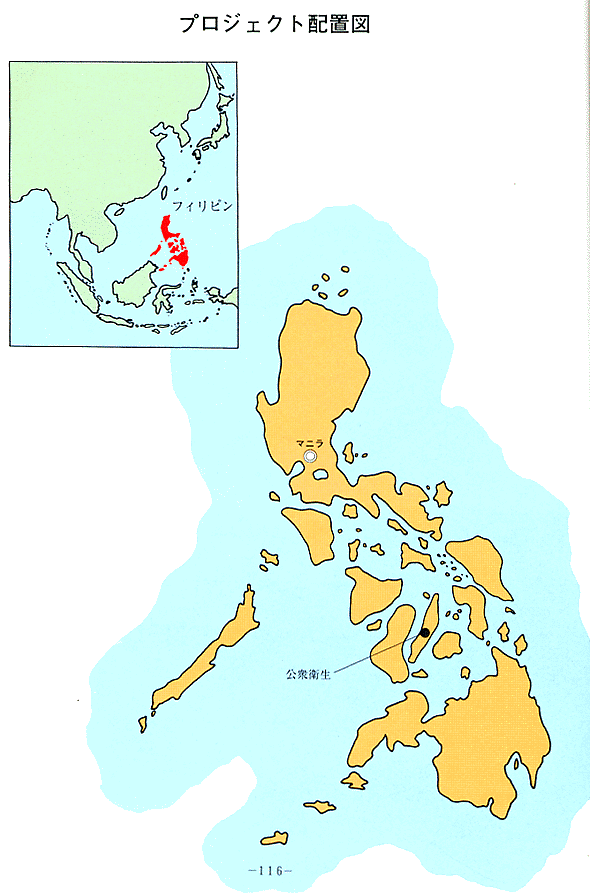
評価対象プロジェクトの概要
| 案件名 | 協力形態 | 協力期間 | 案件概要 |
| 公衆衛生 |
プロジェクト方式 技術協力 |
1992年9月~1997年8月 | セブ州における結核対策強化を通じ、フィリピンにおける公衆衛生活動のモデルを開発することを目標として、検査体制・患者指導の充実、関連情報教育活動の強化等のための技術協力を実施。 |
本評価は二重の意義を有している。すなわち日本の協力プロジェクトの中間評価でもあると同時に、日仏協力の新しい試みでもある。最初の日仏合同評価として、1995年3月にマダガスカルにおいてトアマシナ中央病院への支援を含むフランスの公衆衛生プロジェクト(技術協力)に対する合同評価が実施された(報告書は第14回経済協力評価報告書に掲載)。本評価はこのマダガスカルにおけるフランスの協力への評価と対をなすものである。
1 プロジェクトの概要
1.1 プロジェクト対象地域と期間
プロジェクトの対象地域は第7地方(中部ビサヤ地方)に属するセブ州(州都はフィリピン第二の都市セブ市)である。なお、第7地方はセブ島を中心としてボホール島、ネグロス島東岸及び周辺島襖を含む地域である。
プロジェクトの実際の活動は、マンダウェ市、ラプラプ市及びセブ州内の6郡から始められ、評価当時も右の地域内に限定されている。
また、このプロジェクトの協力期間は5ヵ年で1992年9月から開始されている。
1.2 プロジェクトの目的
本プロジェクトは疾患として結核を対象とする、公衆衛生計画のパイロットプロジェクトであり、その目的は以下の3点である。
(1) 対象地域における結核の患者発見及び治療を強化する。
(2) 地方自治の中における公衆衛生のモデル的なあり方を明らかにする。
(3) 全国の公衆衛生行政の機構・戦略・人員配置等について提言する。
1.3 プロジェクトの戦略
(1) プライマリー・ヘルスケア・サービスの中での患者発見・治療を向上させ、これにより存在する塗抹陽性患者の65%を発見し、発見された患者の85%以上を治療完了に導く。
(2) 結核対策の末端における実施を特に記録・報告、監督、評価及び要員の研修等の各方面を通して強化する。
(3) 結核対策及び関連領域における情報教育活動の強化及び必要な資機材の供給を行う。
(4) 結核対策の疫学的影響及び実施運営面での評価のためのサーベイランス体制を確立する。
(5) 結核菌検査の精度向上のためレファレンス検査機能を確立する。
(6) 適切な計画実施を定式化するために地区を定めてオペレーショナル・リサーチを行う。
(7) 要員や政策決定者に対する動機付け、プロジェクトの総合評価、技術向上のため計画 的な各種セミナーの開催や研修を実施する。
1.4 プロジェクトの活動計画
(1) 末端施設の指導・支援の強化
(2) 実績評価の体系を整備
(3) 資機材(薬剤・消耗品)供給・維持機構の確立
(4) 結核対策他における情報教育活動の強化及び必要な資機材の供給
(5) 結核対策の疫学的影響及び実施運営面での評価のためにサーベイランス体制を確立
(6) オペレーショナル・リサーチの実施
(7) 技術向上のための計画的な研修実施
(8) 地区セミナー実施
(9) 全国ワークショップの開催
1.5 日本側のインプット
1.5.1 専門家
長期専門家は2名(結核対策医学専門家、プロジェクト調整員)とその数は限定されており、短期専門家派遣への依存度の高い構成となっている。(プログラム運営専門家年3人、検査技師年3人、疫学専門家年3人、健康教育専門家随時、公衆衛生看護専門家随時)
1.5.2 研修
研修生受け入れ数は医師、検査技師を対象に年間2名であるが、短期専門家派遣による現地セミナーに重点が置かれている。
1.5.3 機材
検査用機材、研修用機器及び自動車4台とモーターバイク22台、総額1億300万円(1992-1995)。
1.5.4 胸部センター・レファレンス検査所
以前から存在していたセブ胸部センターを拡張。プロジェクト基盤整備事業として1993年11月起工、1994年8月に開所している。
1.6 フィリピン側のインプット
1.6.1 保健省
事務用スペース及び協力要員(州保健部)、資機材(国)、薬剤及び試薬、事務所・検査室・自動車の維持(国及び州政府)。
1.6.2 地方政府
人員、保健施設、薬剤・資材の追加供給。
2 プロジェクトのデザインについての評価
2.1 プロジェクト・デザインの過程
プロジェクト形成と発足までの過程は、比較的円滑に進捗したと考えられる。また事前調査が十分に行われたことが、プロジェクトのデザインに大きく寄与している。ただしレファレンス検査所の強化の細目が、事前調査の段階で明確に合意されなかったのは、後述する同検査所の完成の遅れに影響したのではないかと推測される。
なお、プロジェクト形成へのフィリピン側の参加の度合いについては、今回の評価で知ることができなかった。
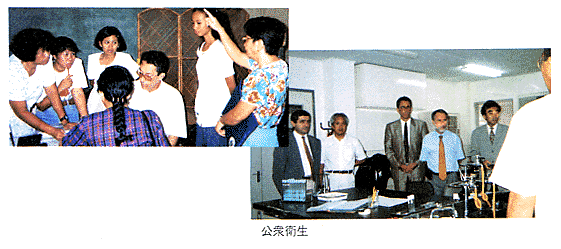
2.2 結核対策計画とセブ州の選定
結核対策は保健省の中期計画の中でも優先課題の一つとされており、プロジェクトが支援する全国結核対策計画(NTP、1969年~)がフィリピン政府にとって優先度の高いプログラムであったことは明らかである。地理的には、ルソン島以外が選択されたのも合理性がある。なぜなら、保健衛生資源はこれまでルソン島を中心に、不均衡に配分されていた。さらに、メトロ・セブはメトロ・マニラに次ぐ大都市であり、人口約百万のうち53%はスラム居住者である。またマンダウェ、ラプラプの2都市も大規模なスラムを抱えている。結核がスラムで特に猛威を振るう病気であることを考慮すれば、セブ地域における結核プログラム支援が決定されたのは妥当と考えられる。
2.3 プロジェクトの目的
本プロジェクトの三つの目的の設定は妥当である。まず、第一のセブ州における結核対策の重要性については、上述の通りである。第二、第三の目的はやや重複しているが、地方分権化に対応して公衆衛生サービスをどのように再編すべきかは、フィリピンの保健政策の最大の問題の一つであり、これをプロジェクトの目標に掲げることは、きわめて時宜にかなったものと判断される。
2.4 プロジェクトの戦略、活動計画
プロジェクトの第一の目的を実現するための戦略、活動計画は適切に記述されている。ただし活動計画のうち、(5)サーベイランス体制確立および(6)オペレーショナル・リサーチの内容は十分とはいえない。
デザインの段階で本プロジェクトの最大の問題は、他の二つの目的に対応した戦略・行動が、ほとんどあげられていないことである。地方分権体制と垂直的結核対策計画との調整、結核対策と他の疾患対策との公衆衛生体制における調整の両面について、考察、試行、オペレーショナルなモデルの策定(文書、マニュアル化)のための行動計画が規定されるべきであった。
2.5 プロジェクトのインプット
前項で述べた問題は、当然のことながら、インプットの構成にも波及している。対象地区における結核対策計画の強化という目的に限定すれば、適切なインプットである。しかし、その他の二つの目的実現のためのインプットは(行動が規定されていないのであるから)、挙げられていない。
2.6 民間・NGOとの協力
民間・NGOとの協力について、実施計画の目標・戦略・行動計画は全く触れていない。NGOについては、調整委員会(実施計画)、タスクフォース(Minutes)への参加をうたっている。
2.7 他のドナーとの協調
結核対策の分野における世銀、イタリアの協力はかなりの規模に達している。したがって他のドナーとの交流、協調、調整は、プロジェクトの進捗のみならず、全国結核対策計画の成果にも重要な影響を持ちうると考えられる。しかし、プロジェクト・デザインにおいて、この点はプロジェクトの本来の活動に組み入れられなかった。ただし、事前調査団の報告書では末尾の「提言」の一つとして、他のドナーとの情報交換の緊密化に言及している。他のドナーとの調整は、プロジェクトの補足的な活動とみなされたのであろう。
2.8 全国結核対策計画とプロジェクトの医学的・疫学的整合性
このプロジェクトが支援対象としている全国結核対策計画(NTP)の疫学的原則について、プロジェクトの立場が明確に述べられていない。途上国の結核対策における検痰の優位性とX線検査の実効性の低さについては、すでに70年代から国際的に認められてきている。本プロジェクトの基本的立場も検疫優位主義であり、プロジェクト実施計画は検疫と短期化学療法を基礎とすると明確に述べている。他方、プロジェクト開始当時のNTP指針(その後WHO勧告により改訂)はX線検査と長期療法に依然大きく依存している。ではどのような原則にたってプロジェクトを進めるのか、この点についての言及は見あたらない。
3 全国結核対策計画新指針
プロジェクト発足後、プロジェクトが支援対象としている全国結核対策計画(NTP)の基本指針(ガイドライン)が変更されることになった。この変更はプロジェクトの運営に重大な影響をもたらすものであり、また新指針の作成、実施はプロジェクトが関与すべき問題と考えられる。
3.1 実施状況
上述のように、プロジェクト開始時点では、NTPは1980年代に採用された旧来の指針に従っている。その後、1993年、WHOの策定公表した途上国向けのディストリクト・レベル要員訓練モジュールにならって、NTP指針の全面改訂が行われ(注)、本プロジェクトの役割もこの路線に沿うことになる。本プロジェクトでは、具体的には、保健省からの委嘱により1994年6月から強化サービス地域のうち2地区でこの新指針が取り入れられ、パイロット地区として実験試行されることになる。
(注)この改訂は、保健省、WHO太平洋事務局、本プロジェクトの連携の中で行われた。
3.2 評価
NTP新指針は、組織、要員養成などを緻密化し改善した。さらに重要なのは、新登録患者については連続3回の検疫を義務付けており(従来は1回のみ)、X線検査所見に対する検疫の優位性を確認したことは大きな進歩である。しかし、国際機関(WHOなど)や世界結核協会の、途上国での公衆衛生政策としての戦略原則、すなわち喀疲検査主導による結核診断治療に全面的に踏み切った訳ではない(注)。
この新NTP指針を一気に強化サービス地域全体に適用せずに、実施の可能性を探るため限定されたフィールドヘの試験導入から慎重に始めた事は、プロジェクトの記録報告業務の技術的領域の推進と混乱を防ぐという観点からは理解できる。また、これを通じて、新指針の問題点として、民間医療機関におけるX線による診断・治療を巡る問題点、結核治療薬の選択・投与量(投与量の不十分性、一括ブリスターによる投与で調節不可能なこと)に関する問題などが明らかにされた事は以降のプロジェクト推進のために貢献する肯定的な要素となっている。
新指針は治療原則の面では、短期化学療法を広範に取り入れた点で大きな前進と言えるが、菌陰性の患者の扱いでは、フィリピン保健省とこのプロジェクトの日本側との医学的立場は明確ではない。
新指針で治療成績がコホート分析で報告されるようになったことは、改善点である。残念ながら、実際の報告の作成、監督、モニタリングを行う行政上の役割分担、業務内容ははっきりしない。
最後に、NTP指針改定において本プロジェクトの果たした役割については、疑問が残る。本プロジェクトは、結核対策に関してはパイロット・プロジェクトとして全国に先駆けて新しい試みを実施し、そのノウハウを全国的政策に反映、全国的結核対策の改善を牽引していかねばならないはずである。保健省中央の結核対策課長も、本プロジェクトの専門家のカウンターパートに指名されており、こうしたチャネルは確保されている。ところが、NTP指針の改訂に際しての問題点、特にX線検査に対する暖昧性について、プロジェクトで十分な議論がなされた形跡はない。
(注)WHOは1994年に結核対策の基本政策を確立し、加盟国にその施行を勧告。その内容は、1)主に喀痰の顕微鏡検査陽性者を治療すること、2)結核治療を全国的な一般医療サービスに組み込むこと。但し、X線陽性菌陰性患者に対する治療も否定していない。
4 プロジェクトの実施状況とその評価
4.1 評価上の諸問題
4.1.1 プロジェクト・デザインにおける暖昧さ
評価の基礎は実施計画である。ところが、本プロジェクトに限らず、日本の経済協力プロジェクトに特徴的なのは、プロジェクトの全体が理解できるプロジェクト・ドキュメントが作成されないことである。本評価にあたっては、もっとも包括的な記述がなされている事前調査団報告書の「実施計画」を基盤としたが、評価基準に関する全ての情報が書かれているわけではない。
さらに本プロジェクトの実施計画の記述はいくつかの点で明瞭さに欠けるため、評価の基準はある程度主観的にならざるを得ず、評価項目も「戦略・活動計画」に対応させることができなかった。不明瞭であった例としては、戦略と活動計画のレベルの錯綜及び両者が正確に照応していない場合があること、プロジェクトの運営の主体、調整委員会・タスクフォースの権限と任務などをあげることができる。
これらの問題点については、現場で専門家の業務内容に関する規定、プロジェクトの定期報告書、成果物等を参照することによって補われるべきものであるが、主に時間的な制約からこうした資料を十分に入手することができなかった。
4.1.2 プロジェクト・デザインに関する日比双方の合意の不鮮明さ
国際協力プロジェクトは、供与側・受益側双方が共有する目標に向けて一体となって努力するものである。しかしこの基本合意文書にあたるThe minutes of discussions(事前調査団が合意したもの)は「活動計画」が省略されるなど、上記実施計画を簡略化したものである。さらに両者の間で、プロジェクトの目的の叙述方法(minutesではobjevtives、targetに分割)、調整委員会とプロジェクト・レベルのタスクフォースの構成におけるズレなど、必ずしも正確に照応していない箇所が見受けられる。実際の評価にあたっても、両者の合意がどこまで形成されているか、確認することができなかった。なお、本評価はもっぱら日本側の事前調査団が作成した実施計画に照らして行われた。
4.1.3 アウトプットの評価基準・指標の不備
本プロジェクトの目標の中で、最も具体的に記述されているのは、患者発見、治癒率の改善である。実施計画書では「塗抹検査陽性患者の65%を発見して、短期化学療法で治療しこれらの患者の治癒率を85%とする」と数字による目標が挙げられている。だが、この数値目標を基礎に計量的な評価を行うのは、現状のままでは困難である。
第一に、実施計画は、検疫と短期化学療法のみでの結核対策を予定している。しかし実際の本プロジェクトの活動はフィリピン側の指針(新・旧)にそって実施されているため、仮に信頼性のあるデータが入手できたとしても、プロジェクトの効果の評価は行いにくい。
第二に、統計データの信頼性に対し、日本側専門家は疑問を呈している。従来のフィリピン保健省の旧指針によるFHISIS(保健所運営報告システム)に基づくデータが本プロジェクトの評価には利用できないことは上に述べた。さらに、統計様式が確立されていないため、調査時点で妥当性の高いアウトプット指標(コホート方式による母集団ごとの治療評価など)を得られるのは、新指針の施行地域のみである等の問題がある。
第三に、統計処理がフィリピン側に一任されているため、プロジェクトの評価に必要な形のデータが得られていない。
第四に、本合同言乳価実施時期が第1強化サービス地域で新指針が実施された直後であったこともあり(注)、日本側の要員から、当面する技術的問題には適切な回答があるにもかかわらず、数量的な評価に必要な資料、指標などについては明確な回答がほとんど得られなかった。
(注)新指針の実施以降、プロジェクトには、州または市を通じ数量的モニタリング・データが四半期毎に報告されている。この報告の基礎となるデータ(四半期毎の活動実績)は、日本側専門家の指導の下、各地域保健所が作成している。
4.2 プロジェクトの組織
日本側の現地構成員は、実施計画にあるとおり、長期専門家(医師)1名、プロジェクト調整員1名が常勤しており、他には2名の助手(保健婦)と1名の秘書がいる。
フィリピン側の地方の結核対策計画関係スタッフは以下の通りであった:
―地方保健局:他の疾病対策も担当するが結核対策を担当する医官管轄下の結核調整医師、 保健婦の2名が結核計画を担当。
―州保健局:結核対策は医師1名、看護婦2名が担当、さらに巡回指導の検査技師がいる。
―さらにセブ市には結核調整医師がいる。
現行では、末端の業務は各保健所のスタッフにより行われている。
プロジェクト・タスクフォースの構成員は、第7地方保健局(保健省の地方出先機関)、セブ州、強化サービス地域2市の結核対策調整官(医官・保健婦)、郡監督保健婦、州検査技師他であり、プロジェクトの活動を実施する上での調整・連絡機関として機能している。
4.3 強化サービス地域(Intensive Service Area,lSA)の選定
4.3.1 実施術兄
特別のインプットを行う地域を「強化サービス地域」(ISA)とし、これを3段階に分けて、漸進的に拡大するという実施方式に基づき、まず初期の強化サービス地域を定めた。これはセブ州の人口の約3分の1をカバーしており、希望を表明した自治体から選ばれている。プロジェクト活動基盤整備に時間を要したため、現在は、当初計画より6ヵ月遅れで95年4月からISAの拡大に着手している。1997年のプロジェクト終了までに全域へ拡大する構想となっている。
4.3.2 評価
強化サービス地域の段階的拡大の方式を取ったことは、プロジェクトの始動期の人材や能力の面での制限や、地域へのゆるやかな適応を考えて妥当である。強化サービス地域の選択は、統計学的疫学的な必要性や、地域住民の需要に基づいてなされたと言うよりは、自治体との関係を考慮した政治的判断によるものと推定される。
4.4 対象地域の基礎調査(ベースライン・サーベイ)
4.4.1 実施状況
現地の問題把握と関連要因の分析のため対象地域の基礎調査と、さらに患者発見に焦点をあてた社会学的調査をプロジェクト開始早期に行っている。
この基礎調査は二つの部分から構成されている。第一は、強化サービス地域内の29保健所について、地域の一般的な背景要因、職員、機材の配置状況をはじめとする、政府の結核対策マニュアルの履行状況を中心とした調査である。
第二の構成要素は、公的保健機関に限った有症状患者やそれに対する検査実施状況調査、新登録結核患者調査が実施された患者発見過程についての社会学的調査と、疫学的調査及び一般住民のプライマリー・ヘルス・ケア、結核対策に関する意識調査である。
4.4.2 評価
この調査のうち第一の調査の成果は、当該地域の従来の結核対策の問題点をよくとらえている。これは本プロジェクトのロジスティックの技術的綿密さ及び喀痰塗抹検査の精度管理の面で大きな貢献をしている。
第二の調査は、プライマリー・ヘルス・ケアに重点を置き、新しい結核対策を導入しようとする本プロジェクトに先だって、ぜひ実施されるべきものであった。しかし、ここでの調査が、一般住民の結核に対する意識調査と、公的保健機関に限った有症状患者やそれに対する検査実施状況調査、新登録結核患者調査に留まっているのは残念である。社会学的調査としては、一般住民の有症状時の行動追跡調査についても必要だったのではないだろうか。とりわけ、フィリピンの保健医療の中で質のうえでも量のうえでも重要な役割を果たしており、大多数の地域の住民が有症状時に質のうえで第一選択として信頼している、民間セクター(NGOを含む)の存在が見落とされるか、全く無視された点は重要である。疫学的観点からは、これにより基礎指標の数字から民間セクターへ流れている大量の患者数が抜け落ちるため、プロジェクトの治療評価に困難が生じてくる。
最近は、日本からの専門家によるミッションが、強化サービス地域の拡大予定地域で、事前に住民患者の行動調査に力を入れはじめたのは改善点である。また、本プロジェクトでは基礎調査の不十分さを是正するための必要を感じており、補助的調査を適宜実施している(たとえば1995年5-6月)。
4.5 記録・報告システム・支援体制の強化
4.5.1 実施掛兄
強化地域において、統計学、疫学的情報の基礎となる記録・報告システムが強化されている。そのために必要な関連機材の供与が行われる一方、報告書式の記入方法なども改善が加えられ、簡略化、効率化が図られている。
また巡回監督制強化のための交通事情に配慮した自動車、モーターバイク、サイドカーつき自動二輪車などが供与され、地方保健機関の監督、調整保健婦などによって利用されている。
4.5.2 評価
報告システムの改善は全体として実効があがっている。収集されたデータも良質で、統計学的にも信頼性がある。治療患者のフォローアップも強化されている。
機材の供与は、機種選択、量、質、技術レベルの点で全体として適当であり、よく機能している。また管理保守も良好であった。ロジスティクス支援体制についても、地域事情にあった移動用車両選択、短期化学療法用の結核治療薬の本プログラム独自の予備的確保システム(郡監督看護婦による備蓄)などの面でよく配慮されている。 プロジェクトチームによる巡回現場指導は適切かつ順調に行われており、末端の保健施設
の保健婦などの本プロジェクトに対する士気、協力関係も非常に良好である。郡監督保健婦を通しての監督の強化も適切に行われている。
4.6 研修、養成
4.6.1 実施伐兄
結核菌検査技術及び検査業務に関する現地研修(セミナーなど)が、セブ胸部診療所レファランス検査所で年平均3回、実施されている。現在の研修の内容はNTP新指針の内容に重点が置かれている。本プロジェクト関連地域の結核関連の保健要員(村落保健ユニット、バランガイ保健ステーションも含む)が対象で、既にのべ約650名が参加し、そのうち医師は約90名である。
他方、中央政府保健省から医師、検査技師(第7県担当官)を中心に毎年2名が日本(結核研究所、JICAなど)に派遣されている。
4.6.2 評価
研修はシステマティックに実施され順調に効果を上げている。研修の内容、スケジュールは適切であり、NTP新指針採用後はとりわけ効果的で、参加者の士気も高い。視察時の聞き取りでは特に日本での研修に人気が集まっている。
また、同様に本プロジェクトで、日本での研修を維持し続けるのが適当かは疑問なしとしない。本プロジェクトの検査技術、研修養成、レファレンス検査所の精度監督の大部分の業務を依然として日本側に大きく頼っている。フィリピンでは保健医療要員(医師、看護婦、保健婦、検査技師)の質は比較的高く量も十分である。都市を中心にして、治療レベルの高い大学病院や民間病院などの保健医療施設も多数ある。さらに、実施計画書付随資料によると、本プロジェクト以前にも、この20年間にJICA関連だけで、フィリピンから70名を超える結核対策の研修生が来日している実績もある。このような事実を考えると、フィリピン側への業務委譲はより促進できる可能性があるのではないか。本プロジェクトの後半では、現地の研究機関、施設、人材を用いて、早めにフィリピン側に移行させることに努めるのが望ましい。見聞を広め、交流を深めるためなら、第三国研修への転換も考えられる。
4.7 保健衛生教育
4.7.1 実施状況
住民の結核に対する正しい知識と、衛生問題についての啓蒙のための情報教育のために、日本のビデオの現地語版、現地教育映画、教育漫画などが作られた。また、スピーカーなどの衛生教育用器材も既に末端の村落保健ユニット(PHU)やバランガイ保健ステーション(BHS)に配備されている。
4.7.2 評価 ハード、ソフト共に準備が整い、またタスクフォースなどで実施内容も討議されているが、活動そのものはまだ端緒についたばかりである。このプロジェクトとして独自の住民への直接の働きかけはまだ不十分であるものの、公的保健医療施設のフィリピン側スタッフの教育は十分に行われているので、彼らを通して日常の活動の中で間接的には行われているのだと理解することができる。
4.8 プロジェクト基盤整備事業(レファレンス検査所他)
4.8.1 実施状況
末端の顕微鏡センターや検査室の精度向上のため、1993年、セブ胸部疾患センターの検査棟新築をプロジェクト基盤整備事業として計画、1994年8月、フィリピンで最初の全国結核対策専門のレファレンス検査所として業務を開始した。ここでは外来検査、研修、精度管理、染色薬などの品質管理、培養検査などが行われている。このさい、老朽化したレントゲン撮影装置を入れ替えるため、新装置の供与も行われている。
同センターは地方分権化政策に沿ってセブ州保健部に移管される事が検討されたが、本プロジェクトヘの配慮から、保健省中央の指示に基づき第7地方保健局が州移管を留保したいきさつがある。検査所新設とともに、プロジェクト実施地域内の顕微鏡センター(一定数の村落保健ユニットごとに設置されている)33カ所に結核検査用の双眼顕微鏡が供与されている。
胸部センターは日常の外来の喀痰検査と同時に、このプロジェクトの研修、レファレンス機能としておこなわれる培養検査をこなさなければならない。このため検査技師の業務が過重となってきており、増員が必要となっている。しかし、毎年1名程度の増員が確約されているが抜本的改善には至っていない。
4.8.2 評価
上記基盤整備事業は1993年8月に口上書交換が行われ、検査所が開所したのはプロジェクト開始2年後の翌年8月である。同検査所は検を中心とする本プロジェクトの重要なコンポーネントであるだけに、こうした遅延が避けられなかったのは残念である。
検査所の諸装置、機器は本プロジェクトの目的にかなっている。機種の選択も現地の職員の技術レベルに適合しており、維持保守管理も非常に良好であった。また、職員の質、士気は順調に上がっていると判断できる。供与されたレントゲン撮影措置稼働状況についてもほぼ同様なことがいえる。
本プロジェクト要員の話では、検査技術的な面からみると、このような完備した設備と高い技術水準の結核菌レファレンス検査施設はフィリピンでは初めてということである。それだけに、これを制度的モデルとするには、施設や人事などの問題を、例外的扱いではなく、一般的に解決する方策をも提案しなけれはならない。
喀痰レファレンス検査所の設置されたセブ胸部センターへのレントゲン装置の供与は、従来の結核診断治療における胸部レントゲンヘの偏向に対して、喀痰検査を優先し、これを患者発見治療の基礎としている本プロジェクトの趣旨からみると問題がある。
4.9 治療薬
4.9.1 実施状況
地方分権化以降、結核治療薬の供給配布については、短期化学療法薬は中央政府に、標準化学療法薬は地方政府にゆだねられている。以前には、末端の保健施設では医薬品の在庫切れがしばしば見られたということだが、当該地域では現在解消されている。しかし本プロジェクトでは、緊急時を想定して備蓄体制をとっている。他の染色試薬、機材についての備蓄のモニタリング制度は、今のところ確立されていない。
4.9.2 評価
地方自治体の財政力には限界があり、本プロジェクト実施に当たって緊急時を想定して備蓄体制をとっているのは賢明である。他の染色試薬、機材についても備蓄及びモニタリング体制をとることが望ましい。
4.10 専門家派遣と技術移転
4.10.1 実施状況
長期専門家としては1992年以来チーフアドバイザー(医師)1名、調整員1名が赴任している。
日本からの短期専門家は主として日本の結核研究所からの専門家を迎えて、長期専門家への助言、現地研修の支援を行っている。内訳は、92年1名、93年8名、94年6名、95年8名であった。この中には医学疫学以外の社会学の専門家も含まれている。
カウンターパートは中央レベルでも地方レベルでも明確な指名はフィリピン側からなされていないが、日本側は保健省結核対策課長及び地方保健局長をカウンターパートとみなしている。
4.10.2 評価
長期専門家2名のうち、チーフアドバイザーが技術的指導、監督を、調整員が事務一般の処理任務を行っているが、より高度なプロジェクト管理、マネージメントの分野が手薄となっている。
他方で、医療専門家の役割には変化が起こっているようにみえる。本プロジェクト開始準備に当たりフィリピン側の行政関係者、特に実施地区の州政府、自治体首長などの説得において、長期専門家の果たした役割は重要であった。しかし、すでに医学的検査技術、機器操作維持管理、記録報告技術についてはフィリピン側に任され、医療専門分野で必要なのは定期的なスーパーバイズだけとなっている。
現時点で短期専門家派遣の回数、間隔、人選には問題は見られない。
他方、地方レベルのカウンターパートである第7地方の地方保健局長への技術移転は、意識的に推進されているとはいえない。
4.11 分権化との調整・モデル策定:現状と評価
実施計画の目的とされている「地方分権下の全国公衆衛生のモデル」づくりの進展状況は、すでに2.4で述べたように、具体的な行動が明示されていないため、評価することができない。しかしながら分権化はプロジェクトの今後について、決定的な意味を持つ問題であるため、以下に現況を報告しプロジェクトにとっての意味を分析する。
1992年に地方分権制が導入され、保健衛生部門も実際の業務は自治体に移管されることとなった。しかし実際にはセブの保健衛生分野においては、フィリピン保健省は市、州、郡に固有の人員を依然保持しており、これが結核対策計画その他の全国計画を動かしている。法的には地方分権によりこれら人員はすでに地方政府に移管されているはずである。特に郡は法的にはすでに存在していないはずであるが、セブの保健局は依然機能し続けている。資金は各種全国計画より捻出している。
上記のような例外は、分権化に関する法制(Local Government Code)が、外国援助を得たプログラムに限り、従来の縦割りの機能と人員を維持することを認めているため可能となっている。
セブの地方結核対策体制が例外的状況にあることは、それ自体問題ではない。問題は、単なる便法として実施されているところにある。もしプロジェクトが新しいモデルの提案を行わないならば、日本の支援が終了した時点で、結核対策は自治体に移行される可能性が高い。しかし、自治体には充分な準備がなく、日本も移行準備のための支援は行っていない。この点については、7.1で詳述する。
最後に、結核対策を公衆衛生活動に統合する努力は、プライマリー・ヘルス・ケア推進の観点からも重要であることを述べる。このプロジェクトの最終受益者との接点は、フィリピン保健医療行政の末端底辺施設である村落保健ユニット、バランガイ保健ステーションである。日本の協力で結核対策が強化された結果、他の活動が低下するようなことは避けなければならない。さらに他の活動とバランスをとるだけでなく、それらをも支援することが必要である。
4.12 民間医療網、NGOとの連携:現兄と評価
民間医療網・NGOとの連携、援助調整については、実施計画は具体的な行動は示していないものの、プロジェクト実施にあたって提言、注意喚起等の形で行動を促している。民間セクターの存在と、そこで行われている結核診断とその治療方針はプロジェクトの進捗に大きな影響を及ぼしている。まず、有力なNGOであるフィリピン結核協会(Philippine Tuberculosis Society,PTS,1910年設立)がセブでも活動しており、WHO資金で大規模な調査も実施している。またフィリピンでは、民間医療網がきわめて発達しており、結核についても、患者の発見から治療まで民間医療機関への依存度は、貧困層も含めて高い。
したがって検疫を中心に据える結核対策プログラムを推進するためには、民間・NGOのプログラムヘの統合は不可欠である。しかしこれまでこの方向での取り組みは、きわめて不十分であったとみられる。実施計画で唯一明記されていた行動、すなわち調整委員会、タスクフォースヘのNGOの参加も実現していない。
このため、強化サービス地域に加えられたマンダウェ市の場合のように、このプロジェクトでは既に民間で治療を受けた患者を特別扱いをするという傾向が出てきている(この問題については既に日本からの専門家による調査団によって、指摘されている)。
4.13 援助調整:現況と評価
WHOとの関係は良好で、特にここ2年間改善されている。しかし他のドナーとの協調は、実施計画に組み込まれていないため(事前調査団の提言はあるものの)、行われていないといっても過言ではない。
日本の経済協力関係者内部の調整・協議は活発とは言えない。120~130人の専門家と55~60名の協力隊が駐在しているが(その中にはプライマリー・ヘルス・ケアに関与するものもいる)、交流、懇親を目的とした活動があるのみで、政策的な協議、調整はない。
5 モニタリング
これまで検討してきた諸問題のうち大半(地方分権化との調整、統計手法、民間セクターとの関連)については、モニタリングの文書(計画打ち合わせ調査団報告、実施協議調査団報告)でも指摘されている。特に地方分権化は「プロジェクトにも深甚な影響を与えうる」ものとして、深刻に憂慮している。
しかし(1)各種報告書は、自ら指摘した諸問題について、根本的な解決への提言を行っておらず、(2)また、プロジェクトもその後これらの問題の解決に取り組んでいない。
6 プロジェクトに関連する諸問題とプロジェクトの波及効果
地域住民への波及効果と住民参加
現在のところ、稗益者は、結核有症状患者で公的保健医療施設を利用している者に限定されており、民間セクター、私的保健医療施設利用者はこのプロジェクトの対象となっていない。ただし、セブ胸部センターでは、結核症以外の呼吸器疾患患者もこのプロジェクトの検査施設、供与レントゲン設備を利用することができる。
本プロジェクトの稗益人口の拡大は、二つのチャンネルによって可能となる。第一は、プロジェクトが公的セクターでの結核診療の質の向上(患者発見、治療率の改善)、住民患者の経済的負担を軽減することにより、従来民間で受診していた患者を吸収する道である。第二は本プロジェクト実施地域での医学的疫学的な改善が、民間セクターで実施されている欠陥のある結核治療の改革を促す道である。もちろん、私的医療機関は営利上の問題(レントゲン撮影料、治療薬の売上など)もあるので、プロジェクトの側からの民間セクターへの説得、協力の働きかけが必要である。
このような稗益人口の増加を実現するためには、医学疫学的に根拠のある、患者発見、治療の原則を日本側で決定するだけでなく、これをフィリピン側に提示して新NTP指針の欠陥を改善しなければならない。この点をフィリピン側に十分指摘せず、曖昧性を残してプロジェクトを進めるならば、逆に波及効果を阻害する要因となりうる。
本プロジェクトにおける住民の参加に関連して特筆すべきは、末端でのボランティアの活動である。バランガイ保健センターは、しばしば地域ボランティアによってその活動の一部を支えられている。ボランティアは医薬品を無料で提供される他に、しばしば、各種全国計画より若干の謝礼を受けている。謝礼は最低賃金を大きく下回るものの、この状態はボランティアにとって完全な失業状態より望ましいと考えられている。
7 プロジェクトの持続可能性に関する評価
7.1 制度的持続可能性
このプロジェクトの持続性を考えるうえで最大の問題は、地方分権政策との関係である。実施計画の最終段階で政府の政策変更が進んでいたが、結局はフィリピン側の明確な分権方針が出る前に本プロジェクトが実施に踏み切られている。本プロジェクトの中では、分権化との対応が考慮されておらず、多くの分野で支障が起きている。
プロジェクト終了後、仮に結核計画に分権化の枠組みを字義通り当てはめた場合は、自治体は独自の保健政策の策定実施、州レベル以下のスタッフの雇用・配置、州レベルでの検査所、病院の運営等大きな負担と責任を負うこととなる。
現状では、財政面もさることながら、制度的能力から見ても自治体がこれらの条件を全て満たすのは難しい。この点は本プロジェクトの終了後、その成果の持続における最大の問題となろう。分権化が行われた多くの国でも、通常全国的な疾患別の対策計画(垂直的計画)は中央政府に維持されるのが通常であり、フィリピン政府に対して、日本はこの点をどのように解決していくのかをアドバイスしてゆかなければならない。そもそも「地方自治の中における公衆衛生活動のモデル的あり方を明らかに」する(実施計画より)とは、この点を指していたはずである。
7.2 財政的持続性
フィリピンとの協力事業では、通常内貨手当の遅れ、不足などの例があるとされているが、地方保健局からの資料によれば、本プロジェクトの引継ぎに要するフィリピン側の追加支出は、フィリピン政府の財政能力からみて、充分負担可能と考えられる。ただし、フィリピン政府に追加的予算配分を行う政治的意思があることが前提であり、また右は中央政府の財政能力に関して述べたのであり、地方自治体への移管の問題はここでは捨象した。
7.3 医学疫学的原則に関連する持続可能性
結核対策の指針についての、全国結核対策計画(NTP)と本プロジェクトの矛盾についてはすでに述べた通りである。
もちろん、各国にはそれぞれの条件に特殊性があり、国際的に確立された原則を、そのままの実施方式として適用できないことがあることは理解できる。しかし、フィリピン側と日本側の結核対策関係の保健医療専門家間での医学疫学的な、保健衛生学的な正当性についての論理的、学問的な一致の確認なしには、医学疫学的な、保健衛生学的な原則の持続性はなく、たとえ、技術面、物質面での改善や緻密化があったとしても、目標とされる保健衛生上の効果を得ることはできないのではないだろうか。その点、現場でのタスクフォース研修などの内容が検査技術、実施技術面に偏っていて、原則的問題を曖昧にし、避けているようで持続性のうえで不安が残る。
7.4 技術的持続可能性
技術的持続可能性は、本プロジェクトの中で最も確実に定着しつつある分野である。特に医学的検査技術に関しては、検査ラボを中心にした技術移転で大きな成果を上げているのは疑いようがない。
しかし、この成果は、既にフィリピン側には技術的(質)にも人材的(数)にもこれを実現する潜在的能力が存在しており(民間や医学教育機関のレベルも充分高度である)、日本の技術面、財政面、機材面でのインプットによってこれが開花したものとみるべきであろう。結核菌検査や、培養技術、疫学的な情報処理技術はこれまで保健行政に欠陥があり(結核対策の非優先性、財政的処置の不十分、行政システムの未整備など)、公的保健施設の中では適切に活用されていなかったものと考えられる。したがって、このプロジェクトが実施されているのと同じ制度的・財政的条件、技術的能力、行政的能力さえ整えることができれば、この評価ミッションで視察し得た現行の高水準の技術レベルは維持することができると考えられる。
制度的・行政的条件については既に述べた。技術的能力については、フィリピン側に潜在能力が既にある以上、この領域における引継ぎをできるだけ早期に行うため、日本での養成、研修や、日本からの専門家の派遣を早めに現地化するべきである。行政的能力については、専門家とカウンターパートの関係を明確にし、前者から後者への技術移転を計画的に図る必要がある。
8 結論と提言
8.1 結論
本プロジェクトの活動計画の実施状況、成果については、全体的に見て(特に技術的分野では)、高い評価を与えることができる。このプロジェクトによって、強化サービス地域内では、結核症の患者発見、治療に関する技術的な改善、強化が進み、プロジェクトの拡大準備も順調である。記録情報の記入、報告などの体制も整ってきており、喀痰検査の精度管理でもめざましい成果をあげている。要員の養成研修も十分行われている。機材などの供与も問題はない。このプロジェクトは技術的な面では今のところ成功していると言ってよい。もし、このプロジェクトの目的が結核患者の発見、治療のみであれば、少なくとも今までの強化サービス地域では、ほぼ目的を達成したとみなすこともできる。
これはひとえに日本側とフィリピン側のプロジェクト関係者の、緊密でなおかっ友好的な活動運営の努力に負うところが多い。往々にして、厳格すぎるプロジェクトが、現場での援助側と被援助側との緊張した関係の中で実施されがちであるのに対して、このプロジェクトでは、双方の信頼関係の中でよく連携しながら生起する諸問題を解決している。
他方、制度的、医学・疫学の原則的領域では問題がある。具体的には、公衆衛生行政のモデル策定、民間・NGOとの協調、喀痰検査の優位徹底が最も重要な点である。以上の諸問題は、専門技術の指導と機材供与に努力を集中し、制度的問題や医学的原則に関わる問題については、その重要性を十分認識しながらも、これをフィリピン政府の専管事項とみなし、これに「干渉しない」という日本側のアクター全てに共通する傾向によって、及びそれを放置したフィリピン側によって醸成されたものである。。
以上は、プロジェクトの本来の目的「公衆衛生モデルの策定」からみて正当化されない。また、仮にプロジェクトの目的を対象地区の患者発見、治癒率の向上に限定しても、上記の欠陥があるかぎりプロジェクトの終了後の成果の持続可能性はきわめて脆弱なものとなるのであり、やはり正当化されない。したがって、早急にプロジェクトの活動の再編成のためのアクションがとられねばならない。
8.2 提言
8.2.1 全国公衆衛生行政のモデル策定
・本プロジェクトの実施計画に掲げてある第三目的である「全国の公衆衛生行政の機構・戦略・人員配置について提言する」の具体化のため、直ちに必要な戦略、行動計画、インプットのリストを策定し、実行に移す。
この提言は、単にプロジェクトの本来の趣旨を貫くためばかりでなく、本プロジェクトの持続可能性の確保のために不可欠の作業である。
8.2.2 医学・疫学的合意の形成
・フィリピン側と日本側は医学・疫学的に同一の立場と戦略をとるよう、討論を組織し、合意を形成する。合意すべき課題には、全国結核対策計画(NTP)の新指針の評価、プロジェクト対象地域における指針とプロジェクトの方針との調整が含まれる。
・新しい合意が形成されれば、それに基づき、研修内容、記録、報告、統計処理の手法、 サーベイランス体制、各種調査をはじめ、プロジェクト全体の内容を再編する。
8.2.3 民間・NGOとの協調関係の樹立
・プロジェクトの戦略・行動を、民間・NGOとの関係を統合した、(公的医療施設に関与していない住民を含む)全ての住民の結核対策へと拡張する。
・民間の保健医療機関、医師、医療関係者との恒常的な連絡機関を設ける。
・情報交換、研修、研究会などを組織し、プロジェクトの目的を理解させる。
(注)プロジェクトでは、本件合同評価調査団による調査後、公的医療機関の結核サービスの確立にともない、保健省と共同でWHOの協力を得て全国セミナーを開催し、民間医療機関、NGO、地方自治体からの参加も得るなど、民間機関、NGOとの連携強化が図られている。
8.2.4プライマリー・ヘルス・ケアの他の分野の活動との統合
・プロジェクト対象地域にある公的保健施設の結核対策以外の活動との調整、統合を追及する。
民間セクターとの協力に加え、実施現場の公的施設の結核対策以外の、他の日常の諸活動(プライマリー・ヘルス・ケア、ワクチン摂取などの予防医学、家族計画など)の質を向上し、これと調整しあって、地域住民の公的施設への信頼度を増し、アクセスを改善し、地域住民を動員参加させなければならない。
8.2.5 全国結核対策計画本部の強化
・保健省内の全国結核対策計画本部へ保健・公衆衛生行政の専門家を派遣する。その業務はつぎのようである:
・8.2.1のモデル策定に中央レベルで参加する。
・保健省中央での結核対策に関する制度的能力を強化する。
・同じく他の垂直的保健衛生計画との調整に関する制度的能力を強化する。.
(注)第2フェーズでは、チーフアドバイザーが保健省本省の結核対策課に常駐することが予定されている。
8.2.6 プロジェクト管理の強化
・プロジェクト管理を強化する。具体的には、プロジェクトの目的達成、戦略の実現、行動計画の実施の管理、アウトプットのモニター等を組織的、体系的に強化する。必要とあれば、専任の専門家を派遣する。
・ロジスティック、事務的業務はできる限り現地職員に責任を委譲する。
8.2.7 評価指標の導入とデータの整備
・プロジェクトの活動の数量的評価指標を厳密に定義し、早急に導入する。
・統計の手法、データの加工・処理の流れと手法を改善する。
☆強化サービス拡大予定地域の基礎調査をさらに綿密に行う。これには、統計学、疫学、
公衆衛生学、保健経済学、保健地理学などの観点からの調査を加える。
8.2.8 カウンターパートヘの技術移転:TORの再定義
・プロジェクトの戦略、活動計画の変更に伴い、専門家のTORを再定義する。
・技術移転に関する専門家、カウンターパート双方のTORを再定義し、定期的な評価対象とする。とりわけ制度的な能力に関する技術移転に注意を払う。
・日本から派遣する短期専門家を、フィリピン側の教育機関、研究施設などの結核専門家等に漸次転換する。
(注)第2フェーズの専門家のTORには政策提言的活動も含まれる予定。また、第2フェーズでは、日本からの短期専門家派遣、機材供与等日本側投入について徐々にフィリピン側への転換が図られる予定。
8.2.9 援助調整の強化
・他のドナーとの援助調整を強化するため、フィリピン保健省の制度的能力を改善する。
・日本の経済協力関係者間の調整、交流を強化する。とりわけ、他の地域保健プロジェクト(家族計画など)との交流が、公衆衛生行政全般のモデルづくりには必要である。
(注)第2フェーズでは、保健省本省に派遣されるチーフアドバイザーによる他のドナーとの調整や、保健省の制度的能力改善への寄与が期待される。
また、現在実施中の他のプロジェクト(家族計画・母子保健、エイズ対策)との交流を通じ、公衆衛生行政全般のモデル策定に寄与しうる体制づくりを行うことも可能と考えられる。
8.2.10 他地区への拡大を
・以上の提言が実現され、結核対策においてセブ州が他地区のモデルとみなされる条件を満たした場合は、本プロジェクトを段階的に他地区へと拡張する。
(注)記録・報告方式、喀痰検査制度管理、患者発見率・治癒率などの改善についてのセブ州での成果を踏まえ、第2フェーズでは他地区への拡大が予定されている。
8.2.11 一般的提言:プロジェクト・ドキュメントの整備
・プロジェクトの全貌と詳細が把握でき、日本と受益国側がその全てについて合意し、かっ主要な部分は公開されるプロジェクト・ドキュメントを導入するべきである。これは、関係者の主観に左右されないプロジェクトの管理運営とより客観的な評価の基礎となる。
・上記プロジェクト・ドキュメントを基礎に、プロジェクトの実施を許可するプロジェクト審査委員会を設置すべきである。これによりプロジェクト・デザイン段階での問題をチェックすることができる。
(注)第2フェーズについては、開始前に日比双方の関係者間で協議を行い、プロジェクトの目標、活動、投入、前提条件等について合意し、評価のための指標等を含むプロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)が作成される予定である。なお、PDMは公開されるドキュメントとして位置付けられている。

