第二章 特定テーマ評価
1. 貧困問題・生活改善(バングラデシュ)
社団法人世界経営協議会
(現地調査期間:1995年9月2日~9月17日)
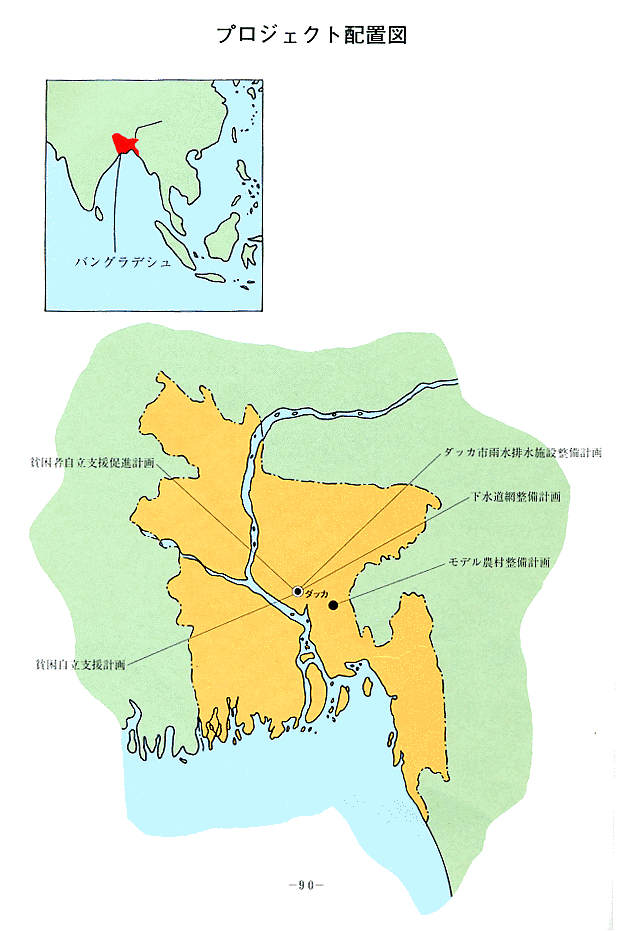
評価対象プロジェクトの概要
|
案件 |
協力形態 |
協力期間、金額 |
案件概要 |
|
モデル農村整備計画 |
無償資金協力 |
1991年度:7.23億円 |
ダッカ市の東方約50キロメートルに位置するコミラ県ホナム郡、ダウドガンディ郡で生活道路の確保、農業生産のための灌漑施設建設等総合的な農村開発を行い、農村地域における貧困の軽減と収入機会の拡大を図る。 |
|
ダッカ市雨水排水施設整備計画 |
無償資金協力 |
1990年度:6.26億円 |
ダッカ市は低地に位置するため恒常的に雨水による浸水被害を受け、生活環境悪化、伝染病に'悩まされていたが、こうした状況を改善する。 |
|
下水道網整備計画 |
無償資金協力 |
1988年度:16.3億円 |
ダッカ市の下水道施設は急速な人口増に追いついておらず、また、下水道施設は老朽化している。こうした状況を改善する。 |
|
貧困層自立支援計画 |
草の根無償資金協力 |
1989年度:37,643米ドル |
被供与団体:Bangladesh Rural Advancement Committee NGOによる貧困女性自立支援活動を支援するため、養鶏卵孚化器及び発電機のための資金供与を行う。 |
|
貧困層自立支援促進計画 |
草の根無償資金協力 |
1993年度:38,693米ドル |
被供与団体:Food for The Hungry International NGOの貧困者自立支援プログラム活動における巡回指導のためのワゴン車及び部品の資金供与を行う。 |
1 貧困問題の「再」発見
―――ポスト冷戦時代における開発援助政策の新たな座標軸―――
1-1貧困問題の「再」発見
1993年度のDAC(開発援助委員会)『報告書』(Development Cooperation)は、「転換期の援助」と題し、米ソ(東西)冷戦構造の弛緩・崩壊に対応して、Global Donor Commnityは開発援助政策を根本的に見直し、改革を図ることを訴えた。すなわち、(1)「南」の開発途上国のなかには、既に「卒業」を達成した国と、依然として「貧困の緩和」が重要な課題である国とが存在しており、援助は後者に対して重点的に行われるべきであること、(2)「人間」こそが開発の中心に位置づけられるべき存在であり、「人間開発」(Human Development)に援助努力が傾注されなければならないこと、(3)被援助国も教育・保健衛生・人口・環境の分野にさらなる資源配分を行うこと、などが強調された。これは開発援助をめぐる国際的閉塞状況からの離脱を目指すものであった。こうしたDACによる,<貧困問題の「再」発見>は、1990年代前半の開発援助政策の基本潮流を反映するものである。
1-2貧困問題と国際社会の対応一歴史的変遷過程
1960年代、国際社会は東西問題と並方蓮大な課題として南北問題を「発見」し、開発途上国における貧困問題を国際社会全体の課題とした。とはいえ、開発途上国の貧困問題は、開発途上国の経済成長が加速することによりおのずと解消される(「トリックル・ダウン」仮説)と楽観的であった。人的資本(Human Capital)は軽視され、貧困問題はあくまでも開発過程のひとつの「結果」(負の副産物)として理解されていたのである。
1970年代、開発途上国は経済成長にもかかわらず、失業、貧困、所得格差に悩まされた。それは「トリックル・ダウン」仮説そのものの妥当性を問うものとなった。ごうして国際社会は、開発途上国における貧困問題を新たな視角から再検討する方向を模索し、ILOが先鞭をつけた雇用指向開発戦略、再配分指向開発戦略が登場した。こうした新しい方向は、世界銀行総裁ロバート・マクナマラが提起した「BHNアプローチ」(1973年)と連動し、国際社会の強い関心を集めた。
1980年代は、「失われた10年」とよばれる。東アジア諸国を唯一の例外として、多くの開発途上国の経済的パフォーマンスは軒並み悪化した。南北関係をめぐる政治ドラマは、「構造調整」と「安定化」を軸として展開されていった。
Global Donor Communityは、「南」に対して力づくで「体質改善」(ショック療法)を迫った。これに対して、開発途上国は「構造調整」・「安定化」の処方筆がきわめて画的であり、開発途上国の特殊性を十分に考慮していないと反発した。とりわけ、「構造調整」・「安定化」路線が、限界を強く露呈したのが貧困問題であった。
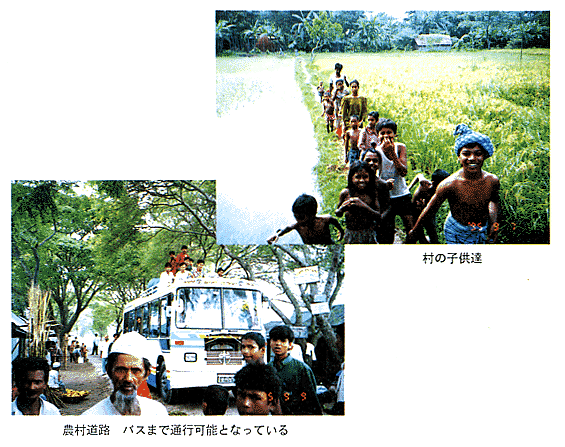
1-3 原点への回帰――再編原理としての「貧困の緩和・撲滅」
1990年、Global Donor Communityは「貧困問題元年」を迎える。世界銀行は1990年版『世界開発報告』のテーマを「貧困」とし、貧困克服へ向けて「労働力」という貧困層が最も潤沢に保持する資源の生産的な活用を可能とするような政策環境の創出、貧困層に対する「基礎的社会サービス」の提供を訴えた。同じくUNDPは報告書『人間開発報告』を創刊し、「人間」を中心に据えた開発援助政策の推進を主張した。これらは、「人間」の「貧困問題」に焦点を当てた開発援助戦略推進の提起であり、開発援助の「原点」への回帰である。さらにこれら二つの報告書に共通しているのは、<貧困は、諸悪の「結果」ではなく、諸悪の「原因」であり、貧困を緩和・撲滅するためには貧困そのものをターゲットとの基本認識である。との基本認識である。
1993年12月、国連総会は「開発途上国における貧困撲滅へ向けての国際協力」の推進を決議し、1996年を「国際貧困撲滅年」と定めた。貧困問題に対する国際社会の取り組みは、1995年3月にコペンハーゲンで開催された「世界社会開発サミット」で頂点に達した。
2 わが国経済協力プロジェクトの事後評価調査――貧困の視点から
2-1 バングラデシュの概況
バングラデシュは1億2,220万人(1994年)と、ほぼ日本に匹敵する人口が日本の2/5にすぎない狭い国土に居住している。しかも、ガンジス川等のデルタに位置するため、年間降雨量の約80%が集中する6月から10月の時期には、国土の約20%が冠水する。1人当たりGNPは224ドル(1993年)、乳児死亡率84(出生1,000人当たり、1993年)、識字率32.4%(1991年)と、経済指標、社会指標いずれも低い最貧国である。4次にわたる5カ年計画で、経済の成長を図り、貧困の解消が目指されてきたが、達成率は高いとはいい難い。就業人口の65%が農業に従事し、GDPの約35%を農業が占める(1993/94年)が、洪水等の自然災害に左右され、農民の収入も十分ではない。このため国民の約半数が絶対的貧困状況(1人当たり1日摂取カロリー2,122カロリー以下)にある。
バングラデシュに対して我が国は農村開発等で経済協力を行っており、1994年度は我が国の援助対象国のうち第8位の受取国、無償資金協力は第1位の受取国(援助額216.10億円、うち73.8%が債務救済)である。有償資金協力では、家内工業に従事する女性を想定したハウジングローンとして、グラミン銀行へ借款が予定されるなど新しい動きがみられる。
2-2 ケース1:小規模(草の根)無償資金協力
2-2-1 小規模無償資金協力(SSGA)スキームの概要
1985年12月、「ODA実施効率化研究会」は「……我が国の援助は大プロジェクト指向であるとの批判があるが、現地の実状に即した小規模、地道な案件も積極的に取り上げていくべき」と提案した。こうした提案を受けて、外務省は1989年度予算において、小規模(草の根)無償資金協力の実施に必要な経費として3億円を計上した。
それは開発援助における新たな国際的潮流を取り入れたものでもあった。アメリカの場合は2種類の小規模援助スキームが設けられている。これらは1件当たり年間1万ドルを上限として、開発途上国に対して無償資金協力(贈与)を行うものである。イギリス、オランダ、カナダ、ドイツ、フランス等も開発途上国で活動する在外公館に権限を委譲した、足回りの早い小規模援助スキームが存在している。こうした小規模援助スキームは世界銀行等の国際援助機関でも行われている。
我が国のSSGAスキームは、資金供与額は1件当たり500万円前後である。案件選定・承認の主導権は、現地に精通している在外公館に委ねられており、申請から1年未満、数カ月で実施が可能である。1989年度に発足し、初年度の草の根無償は3億円であったが、1994年度では15億円と5倍にまで拡大した。援助対象国は、1989年度(初年度)の32カ国から、1994年度では56カ国/1地域(パレスチナ占領地)へと2倍近くの伸びを記録し、援助対象プロジェクト件数は、1989年度の95件から1994年度では331件と3.5倍に伸びている。
2-2-2 バングラデシュにおける実施体制
SSGAスキームによる資金援助の対象は、バングラデシュの場合、「貧困の緩和」を基本戦略として、「最底辺の貧困層」に対する基礎生活分野(保健・医療、上下水道、人口対策等)の整備・拡充に対する貢献が重要なメルクマールとされている。1件当たり資金援助額の上限は500万円とされているが、柔軟な対応がとられている。1995年度予算ではバングラデシュ向けSSGAスキーム資金割当額は3,000万円と倍増されている。
ところで、バングラデシュにおけるSSGA実施体制には、次の問題点が指摘される。バングラデシュの場合、毎年平均で200件前後の問い合わせがあり、そのなかから可能性のある案件を発掘・選別するためには、数次にも及ぶスクリーニング作業が必要となる。インタビューや現地調査(訪問)等の作業が不可欠であり、多大の時間および資金を伴う。申請書類に必要事項を正確に記入してもらうためには書類の作成指導が必要であり、こうした業務を1名の大使館員のみで行っている。
2-2-3 貧困層自立支援計画(1989年度)
バングラデシュにおけるSSGAスキーム適用第1号案件である。被援助団体はバングラデシュ最大の開発NGOであるBRAC(Bangladesh Rural Advancement Committee、バングラデシュ農村開発委員会)であり、総額37,643米ドルの資金供与が行われた。
BRACは1972年2月に設立され、農村における「最貧困層」をターゲットとした活動を行っている。貧困緩和、貧困層に対する能力付与が二大目標である。1994年現在、BRACは約1万2,000人の常勤スタッフを擁し、年間予算は6,400万米ドルである。収入の約30%はBRAC自身による印刷、冷凍倉庫、縫製等多岐にわたる企業活動から得ている。SSGAスキームによる資金援助の対象とされた貧困層自立支援計画は、マニクガンジ県(ダッカの西隣)で、BRACがバングラデシュ政府やWFP(World Food Programme)と共同で推進してきたIGVGD(Income Generation for Vulnerable Group Development)プロジェクトの一翼を担うものである。BRACは、(1)農村の貧困女性を対象として2年間にわたり小麦を毎月無料で提供し、(2)節約された食料費を貯蓄するよう勧奨し、(3)2年間にわたり貯蓄された資金を元手として貧困女性が現金収入の手段を確保し、生計を立てることを支援する。貧困層自立支援計画は、このような観点から、貧困女性に養鶏技術を修得させ、さらに経済的自立に向けて、養鶏関連機材を供与しようとするものである。日本が資金援助の対象としたのは、艀化機1台、および艀化機用発電機1基である。
2-2-4 貧困者自立支援促進計画(1993年度)
被援助団体はFHI/B(Food for the Hungry International/Bangladesh〔国際飢餓対策機構/バングラデシュ〕)である。日本は同案件に対して38,693米ドルの資金を供与した。
FHIは、1971年に設立された本部をスイスのジュネーブに置く国際的な開発NGOである。最貧困層をターゲット・グループとし、教育プログラム、診療・保健プログラム、小規模事業融資プログラムを行っている。1993年現在、FHI/Bは約100人の常勤スタッフを擁しており、バングラデシュで活動するNGOのなかでは、中堅クラスの存在である。
SSGAスキームにより資金援助の対象とされたのは、FHI/Bが貧困者自立支援促進計画の重要な支柱として推進している、最貧困層へ低利の融資を行う小規模事業融資プログラムである。融資対象事業の経済的成功、波及効果・触媒効果を高めるためには、融資のアフター・ケア、被融資者の活動を継続的にモニターすることが必要である。SSGAスキームは巡回用車両として12人乗りマイクロバス1台、およびスペアパーツー式を供与した。
2-2-5 評価
BRACは、バングラデシュ最大のローカルNGOであり、Business Enterprise的な様相を呈している。SSGAスキームの適用第1号にBRACを選んだことは、日本の新たな援助スキームの存在を周知させるデモンストレーション効果を果たしたといえよう。ただし、バングラデシュには活動資金不足にあえいでいるNGOが多数存在している。年間予算規模6,400万米ドルの組織に対する約4万米ドルと、資金不足にあえぐNGOへの支援とでは、そのインパクトは比較にならないほど異なる。これは、「受け皿」となるNGOの「適正規模」という問題を提起するものである。
FHI/BはBRACとは異なり、国際的なネットワーク(FHI)に属するNGOである。事務処理能力は効率的で、プロジェクト・サイトの運営も規律正しく行われていた。事業用巡回車両(12人乗りマイクロバス)の購入は、被融資者に対する監督・指導業務を飛躍的に向上させた。小規模事業融資プログラムの管理・運営をより充実したものとし、被融資者に対するきめの細かいアフター・ケアを可能とした。購入以来1年以上を経過したマイクロバスの管理状態はきわめて良好であった。
2-2-6 発展性のあるSeed Capital
「草の根プロジェクト」は、開発途上国社会の最底辺の人々(最貧困層)をターゲット・グループとするものでなければならない。そして、最貧困層(農民)相互間のヨコの連携強化や協同活動の推進をもたらし、持続可能性を備えたものでなければならない。
1993年度、日本はバングラデシュのローカルNGOであるシェヴァ・ションゴにSSGAスキームに基づき資金援助を行った。シェヴァ・ションゴは、歴史もそれほど古くなく、規模も小さなNGOである。しかし、行政サービスの範囲外、NGOの支援活動からも取り残された地域で活動しており、インパクトは大きく、プロジェクトの波及効果も大きい。それは、草の根無償資金協力の指向すべき新たな方向性を指し示すものといえる。
3 ケース2:モデル農村整備計画
3-1 プロジェクト形成の背景と経緯
コミラ県のホムナ郡、ダウドカンディ郡は、首都ダッカから直線距離で約80キロメートル、チッタゴンと結ぶ国道沿いにある。日本の援助によるメグナ橋(1991年)、メグナ・グムティ橋(1994年)の完成により、農村からの出稼ぎ者、移住者等による人口が増加し、社会・経済的に重要な位置を占めるようになってきた。しかし、地域は雨期には面積の3分の2が水に浸かり、乾期はほぼ全域的に水が干上がる。こうした状況は農業生産を低下させる要因となり、貧困からの脱却を困難としている。
バングラデシュ国政府は、農村経済改善のため、(1)農村基盤の整備、(2)灌概排水と洪水防御施設の整備、(3)貧困層の生産増加および雇用機会の増大、の3点を中心とする農村開発を進めており、1986年に日本政府に対して『モデル農村整備計画』への協力を要請した。
3-2 プロジェクトの概要
本事業は、コミラ県のホムナ郡とダウドカンディ郡を対象とし、1991年度から1994年度に総額約24億7,000万円が供与された農村地域における貧困の軽減と収入機会の拡大を目的とするモデル農村整備計画である。バングラデシュ側受け入れ機関は、地方自治開発局と農業開発公社である。計画地区における低所得層(土地なし農民と小農〔0.2ヘクタール~1.0ヘクタールの耕地所有〕)は、1983/84年調査では全世帯数の91.3%に当たる。
プロジェクトは農業、内水面漁業、農村工業の生産拡大により、雇用と所得機会を創出することにある。このため社会的基礎資本の整備と農民組織の強化が重要とされ、農村道路、橋梁新設、灌漑排水施設、小型ポンプ(その他付属機具)、農産物集荷場(肥料・穀物倉庫)、市場(鉄筋コンクリート、屋根付き)農村研修所、小学校等が建設供与された。なお、本事業のほか、1994年度から5カ年計画で、JICA青年海外協力隊チーム(1995年9月現在18名)による同地域の住民に対する各種技術支援が実施されている。その内容は農業協同組合活動、農村開発、農業機械、稲作、野菜栽培、家畜飼育、在庫管理、手工芸、保健婦、家政婦等を対象とした収入の向上のための技術支援、保健・衛生、社会教育、灌漑用ポンプ管理等の指導である。
3-3 計画・実施段階における効果・課題
事業は予定期間内にほぼ完了し、工事期間に以下のような効果が認められた。建設に当たって地元の住民に就労の機会が与えられ、農外事業収入の増加が生活の向上に寄与した。建設従事者をあてこんだ日用品販売・雑貨商・喫茶店・食堂・加工食品店等もでき、商業が活発化した。さらに、建設時の技術・手順・工法等は地元の建設業者と建設従事者の技術を向上させ、技術移転に貢献し、建設過程における日本人技術者の存在は、本プロジェクトが日本の経済協力によるものであることを住民が知る機会となった。
揚水ポンプ(灌漑用)の選択・取扱い・利用については課題がある。供与した142台のエンジンのうち、12台に部品不足でトラブルがある。トラブルの原因については日本側の調査では無理な利用、粗悪なエンジンオイルの使用、不純な燃料の使用が指摘されている。ただバングラデシュ側は、原因はベアリングなどの機械部品の不良にあるとしていた。
これまで実施された農業省関連の別のプロジェクトでは、一見新しいオイルと見分けがっかない再生油に問題があるバングラデシュの状況を踏まえ、早期オイル交換を行うなどの対応がなされていたようであるが、今回のプロジェクトでは担当省庁も違い、こうしたノウハウが生かされなかったといえる。エンジンの限界容量を越える過度な使用、燃料や潤滑油の品質等についての農民に対する研修・指導が必要であったと思われる。貸し出し管理の仕組みも、初めから制度化しておくことが必要であった。
バングラデシュ側備えつけ予備部品希望数量と供給数量に、かなりの数量上のギャップが認められた。計画段階で資・機材の選定、機器保守のための必要部品の確保、相手国側への引渡し方法等に検討がなされていたが、それでも部品の補充に問題が生じていたことを考えれば、更に十分な注意が必要である。部品不足によるトラブルは、日本側企業負担による対応がなされ、解決される見通しである。また、日本側企業は使用法についても指導を行うことを検討している。
3-4 プロジェクトの総合的評価
プロジェクトの効果の一つとして道路の整備があげられる。農村道路として149キロメートル幹線舗装道路と35.7キロメートル支線道路、5カ所で計180メートルの橋梁が完成した。道路の改善により交通・輸送の便益が著しく増大し、交通量の増大を可能にしたことは、地域の社会・経済に大きく貢献した。
プロジェクトで建設された幹線舗装道路は、ダッカとチッタゴンを結ぶ主要幹線道路からホムナの村へ入っていく道路である。以下の効果をもたらしている。(1)道路の整備により主要幹線道路へのアクセスが容易になり、ダッカへ日帰りが可能となった。(2)主要幹線道路からバスやミニバスが直接地域内に入ってきて、地域内の交通拠点(バスの乗降地)での人力車の数が増加し、交通が便利になった。交通需要の増加は雇用機会も増し、流出していた若年労働者がこの地域へ戻ってきた。(3)積載能力の大きなトラックによる農産物や生産資材、機械等の運搬も可能になった。新鮮なうちに農作物をダッカで販売できるようになり、現金収入が増加した。(4)路面が水に浸ることもなくなり、輸送効果が高まった。ただし、道幅は広くないために、車、人力車などの追越しやすれ違いについては支障や危険もある。舗装された部分とそうでない道路の両脇部分に段差が生じているところ、部分的に降雨による浸蝕や水たまりがあって、道路の補修や維持・管理がよくない箇所もある。側面保護のための植林は、ごく一部に浸水の影響を受けた箇所もあるが、植林も根付き、十分役割を果たしている。
小学校の校舎も建設されたが、バングラデシュ側の準備が整わず、村への移管業務が行われていない。3~5ヵ月間の手続きの遅れがあり、改善が望まれる。
農業生産面では以下のような効果がみられた。(1)乾期にポンプによる揚水が可能となったため、作付け体系は1作から多毛作に拡がり、販売用ならびに自給用の野菜作(ポテト、チリ等)が導入された。(2)灌厩が可能になったため、営農技術が改善された。(3)作物の生産性は向上し、農民は異口同音に所得が向上したと述べ、2倍に増加したと答えた者もいた。(4)農産物加工(特に食品加工)が地域で試みられるようになった。(5)農産物の輸送・運搬において、労力が軽減され、不便は解消し、農産物の有利な販売と農業生産資材の安価な購入が可能となった。
次のような農外事業の活性化がうかがえる。(1)竹・木の加工、縫製に従事する人の増加。(2)道路が舗装されたことにより人力車の労力は軽減され、利用価格(料金)の相場は安くなった。しかし、利用回数が増えたために人力車従事者の収入は以前に比べ、同じか、増えたという。こうした結果、人力車従事者も増え(仕事の機会が増え)、利用価格が安くなったため住民も人力車を利用しやすくなり、便益が増した。(3)商店・食堂、茶店等の小規模事業が増加し、道路整備により仕入れも便利となり、商品を安く供給することができ、扱う商品の種類も増加した。そして彼らの売上げも増えたという。
このように、農外事業の専業者の増加、営業の活発化がうかがえる。この結果、住民は資金の供与を求めていた。資金の使用目的は、男性では農業あるいは農外の施設や機械の購入のため、女性ではミシンの購入など縫製あるいは加工のためとしていた。しかし、農村金融はいくつかのNGOが本地域内で部分的な資金供給活動を行っている程度で、従来とあまり変化しておらず、改善は今後の課題である。
上記のようなインフラの整備に加え、1994年度より行われている青年海外協力隊の地域住民に対する技術支援が大きな効果を上げている。ハード面とソフト面の協力がかみ合い効果を上げている例である。青年海外協力隊はショミィテイ(小グループ)の指導を行い、10グループ余りのなかで、すでに3グループが終了している。男女平均80%が非識字者という地域のなかで、識字・計算教育、組合活動の啓蒙、栄養、産児制限、保健衛生等に意義ある協力である。また、農業技術、手芸、縫製等の職業訓練も行われている。ただし、水産物の販売が積極的になっているにもかかわらず、水産領域の協力隊員が含まれておらず、今後必要と思われる。
3-5 改善が望まれる課題
プロジェクトは地域内の住民の生活の向上、貧困層への就労機会提供、土地や魚資源の利用を可能にするなどの利益をもたらした。ただし、住民の自立心が弱く、プロジェクトヘの期待と感謝はあるが、自己資金計画も含め次にどうするのかという意見が聞かれなかった点は残念である。今後、プロジェクトの効果を高めるため、次の改善が望まれる。
(1) 道路、ポンプ、その他各種施設・機械類の維持・管理に留意(道路の浸蝕防止措置の完全実施、車両のすれ違い場所を数カ所につくる。農民に供与した機器の正しい利用、純正オイル、部品の補充に注意を喚起し、保守のための予算措置に万全を期する)。(2) 現地側の実施予定部分の完全実施(市場の建屋はできたが、そこへ至る道路は狭く、車両の出入りはできない。商品を市場へ直接運び込めるような道路、市場の周辺整備が必要である)。(3) 早急に欠員となっている長期派遣専門家をBRDBへ補充すること。青年海外協力隊員の活動が評価されているので、郡内の一般農家にまで指導活動を広げることを考慮すべきである。
4. ケース3:ダッカ市雨水排水施設整備計画と下水道網整備計画
4-1 ダッカ市雨水・排水施設整備計画
4-1-1 プロジェクトの概要と背景
1941年のダッカの人口はわずか13万人にすぎなかったが、1971年に独立して首都となり、人口は急速に増加した。現在、ダッカ首都圏の人口は約700万に達している。しかし、こうした人口増加に対応した都市の生活基盤整備はできておらず、貧困を理由として農村からダッカに出てくる出稼ぎ人や移住者は後をたたず、劣悪な居住環境のもとで暮らしている。計画された都市開発プロジェクトの大半は財政的な制約から実施されていない。1988年9月4日に歴史的な洪水がバングラデシュを襲い、ダッカ市街地域の約58%が冠水し、被災人口は182万人に達した。この大規模な洪水を契機として、政府はダッカの洪水対策を真剣に検討し始め、その主要プロジェクトに対し、日本政府に無償資金協力を要請した。
ダッカ市雨水・排水施設整備計画は内水対策を対象としたプロジェクトである。プロジェ クトの内容は、ミルプール・カラヤンプール地区にポンプ場ならびに水門(樋門)を建設し、カラヤンプール排水路の俊渫(3,300メートル)と道路橋カルバート(47メートル)建設を行い、ベグンバリ排水路にボックスカルバート(799メートル)を設置することである。工事は1990年度に開始され、1993年3月2日に完工した。供与金額は計21.8億円である。
4-1-2 計画・実施過程における問題点
雨期における降雨が工事遂行を困難にするため、工期の設定にあたって季節が極力留意されている。しかし、実施段階においてダッカ上下水道公社の準備不足により、土地収用等の問題があった。また、ダッカ上下水道公社の輸入税支払いが遅れたため、建設機材は約6カ月港に凍結され、工事の進行を妨げた。
4-1-3プロジェクトの評価
工事においては現地の労働者が雇用され、雇用効果を生んだ。また、可能な限り現地の資材が利用され、国内市場の活性化に貢献した。
カラヤンプール排水路の俊渫とポンプ場・水門の建設の目的は、ミルプール地区の内水を雨期に効果的に堤防の外に出すことである。ポンプ場では内水の水位を3.7m以内に保つことが計画され、1993年と94年の運転記録によれば目的は達成されている。
全長3,347メートルのカラヤンプール排水路の改修は、ミルプール地区の雨水をポンプ場まで流すことを目的としている。カラヤンプール排水路の末端に広大な遊水池がある。建設後はミルプール地区では般住宅地は冠水化しておらず、目的を達成している。ただし、遊水池の大半は私有地であり、宅地開発が大規模に行われれば、遊水池に蓄積できる水量が減り、ポンプ場の排水に対する負荷が増加する。ダッカ上下水道公社は、私有地の収用を急いでいるが、かなり厳しい状態に直面している。
ベグンバリ排水路はダッカ新市街地の中心部にあり、かってこの地域は雨水によって冠水化したが、排水路を暗渠方式に切り換えることで、そうしたこともなくなり、再開発が期待される。しかし、一部の空き地(ショナルガオン道路近く)はボックスカルバート敷設後の土盛り・埋め立てが行われておらず、低い空き地のままの状態であり、不法占拠住宅と考えられる家屋が建っている。ここは雨期には雨水が溜り、ボウフラの生息や水系感染症などの病原菌の温床になりかねない。ダッカ市役所の土地利用計画が問われる。
プロジェクトは雨水を市域外に適切に放出し、雨期に冠水化していた土地の利用価値を大幅に増したといえる。全般に低地では冠水化した水が引かず、水系感染症や蚊の発生源になっていたが、プロジェクトにより改善され、保健衛生上好ましい効果をもたらした。
4-2 ダッカ市下水道網整備計画
4-2-1 プロジェクトの概要と背景
ダッカ市の下水道関連施設はイギリス植民地統治期の1923年に造られた。市街地の拡大に伴う形で下水道網が整備されなかったため、今日ではダッカ市中央部から北側の地域(いわゆる新興住宅地)には全く下水道網が完備されていない。1950年代にマスタープランが作成されたが、プロジェクトのすべてを実行に移すことはできなかった。こうした状況を改善するため、既存下水道管渠網の補修ならびに下水処理場の拡張を含む既存施設の緊急改善計画に対し、日本政府に無償資金協力が要請された。
プロジェクトの対象は、パグラ下水処理場の処理部門の新設と一部補修、ポンプ場の補修とポンプ場周辺の下水管渠の部分的補修である。1989年度に実施され、1992年3月完工した。供与額は計50.22億円である。
4-2-2 プロジェクトの評価
パグラ下水処理場は、ダッカ上下水道公社の技術水準を考慮し、維持・管理面で容易である通性ラグーン式を採用した。この方式は電力消費量も少ないとされている。処理水のBOD5(生物学的酸素要求量)とSS(浮遊固形物質)の値は目標基準値に適合しており、下水処理場での処理施設の新設・一部補修は生活環境改善に貢献している。
下水溝からリフト・ステーションやナリンダのポンプ・ステーションを通過して、汚水は最終的には下水処理場に流入する。下水処理場の整備により処理能力は従来の30,000㎡から116,000㎡まで増加した。完成後に予想されていた流入下水量は、予測量の50~70%にすぎない。原因としては、管渠のひび割れやゴミ等の体積によって管渠が詰まったことによる漏水があげられる。本プロジェクトでは管渠の漏水処置は含まれていない。汚水をパグラ下水処理場まで適切に送り込むため、中継ポンプ場=リフト・ステーションの役割は重要である。プロジェクト以前は、汚水中に廃棄物や土砂がポンプの閉塞を引き起こしていたし、一部のリフト・ステーションでは供給電力容量の不足のため、揚水能力に支障をきたしていたが、これらも改善された。
下水処理場が整備されたため、運営経費は1994年度は1992年度と比較すると約13%上昇している。汚泥ラグーン、通性ラグーンの清掃も必要となる。予算措置が適切に講じられる必要がある。徴収料金がダッカ上下水道公社の主要な収入源であり、1992年度までの過去5年間の収支状況は、1990年度を除いて収入のほうが支出を上回っている。しかし、パグラ下水処理場の運営・維持を適切に行うためには、より多くの予算が組まれるべきである。ダッカ上下水道公社はシステム・ロスが多く、この改善により大幅収入増加が可能である。「システム・ロス」とは給水量と請求不能な給水量の比で、漏水の修理、各世帯へのメーターの設置、違法な水道管接続の探査により減らす努力が行われ、1979年度の75%から、現在は46%となっている。
下水処理場での処理水の向上により、放流先であるブリガンが川への栄養塩類の排出を相対的に少なくし、河川の水質悪化を防止する効果をもたらしている。
4-3 教訓と将来への提言
雨水・排水事業、下水道処理事業とも過去にマスター・プランが作成されても、適切な予算措置がとられず、大半のプロジェクトが延期されている。これらは、総合的なインフラ整備が行われて、初めて軌道に乗る性格の事業である。部分的に実施・完工されても効果は薄く、総合的に実行される必要がある。また、都市開発、都市行政に関与する行政機関間のコーディネートが必要である。
下水処理場には、ダッカ市内の工場の産業排水も流れ込んできており、有害化学物質の検査のノウハウが今後提供される必要がある。
5 貧困問題への協力のあり方
貧困対策プロジェクトにおいては、長期的対策として民生向上を図ること、直接的対策として、貧しい地区・層を対象としたプロジェクトを実施することが大切である。そして、貧困層に直接届くような小規模のプロジェクトを数多く実施する必要がある。地域住民は計画の初期の段階から参加できるよう組織化する必要がある。貧困問題への取り組みに対しては画一的・共通的な解決手法はなく、経験を積み実施していく過程が必要であり、援助する側にも多くの人手の投入が求められる。広範な課題であり、他の援助機関、NGOとの連携活動体制の確立が重要である。この点、NGOは農村の貧困者の自立的組織の発展を目指し、草の根レベルにおける開発促進に努めてきたが、政府と協力して全国的な展開をするようになってきている。政府におていも各NGOの独自活動との連携が課題となってきている。
貧困は、その国の政治構造・経済戦略・社会制度に深く根ざすものであり、長期的で根気のいる取り組みときめ細かい機動的な対応が求められ、NGOとの連携は重要である。保健・医療、教育、農村・農業開発など、貧困層にかかわる分野を増やすことも必要である。そして地域住民の参加を促進し、自立した開発意欲を高める必要がある。
被援助国とともに貧困地域の社会・経済・自然環境に即した総合的な調査研究体制の整備を図り、人材養成を含め総合的に取り組む必要がある。
(本件評価は、西村博行近畿大学農学部教授、・大隈宏成城大学法学部教授、三宅博之北九州大学法学部助教授、中畝義明世界経営協議会研究調査部課長のチームにより行なわれた。)

