2 ペルー
(現地調査期間:1996年4月6日~4月18日)
<団員構成>
堀坂 浩太郎 上智大学外国語学部教授
櫻井 敏浩 日伯紙パルプ資源開発株式会社取締役企画調査部長
(元OECFペルー駐在員事務所駐在)
山崎 圭一 横浜国立大学経済学部助教授、他
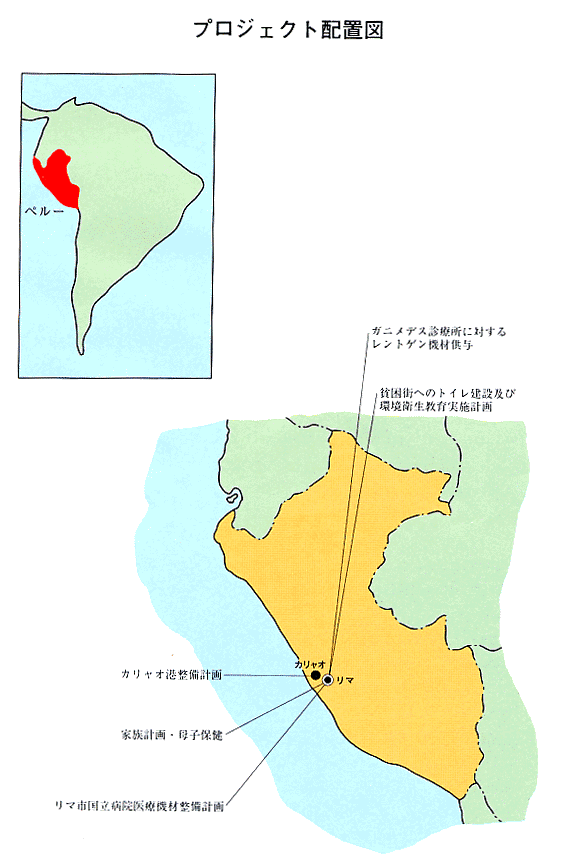
I 評価調査の概要と手法
I-1 はじめに
「国別評価」は一国を対象として実施する最も包括的な評価であり、「当該国への我が国の援助を総合的に評価し、今後の我が国の援助政策への提言を行う」ことを目的にしている。
このことに照らして、本評価団としては本件の評価調査を実施するに当たり、
(1) 評価対象国ペルーの国としての特性および近年における同国の政治、経済情勢の変化を十分に捉え、評価の前提にすること、
(2) ペルー国に対する日本の経済協力全般を念頭において、同国に対するODA・ODA外交を総合的に評価すること、を基本姿勢とした。
I-2 評価のタイミング
本評価は1996年4月に行われたものであり、評価のタイミングとして以下の諸点が特筆される。
・日本のペルーに対するODA供与が対中南米1位(1991年)となってから5年が経過。
・軍事政権から文民政権移管後15年が経過し、「民主体制」の安定化がみられる。
・フジモリ政権第1期(1990年7月~95年7月)中に経済の安定化、治安の回復が図られた。
・2期目のフジモリ政権は貧困対策を主たる国家目標としており、国民のニーズが明確になりつつある。
・米州諸国および先進国との外交関係がいずれも修復され、国際金融界との関係も改善された。
・1991年7月に発生した日本人農業技術者殺害事件(いわゆる「ワラル事件」)で中断したODAに伴う日本の人的派遣が94年より派遣地域及び派遣期間を限定して再開され、95年には資金協力面でもプロジェクト・タイプの円借款も再開された。
I-3 評価の視点および手法
本評価団による評価対象は1990年以降に実施されたODA案件およびODA外交であり、以下の4点を念頭において、ペルー、日本、米国でのインタビュー、現地視察および各種調査・評価報告書を含めた文献・資料・データの分析により、総合的な評価を行った。
・「フジモリ政権下でのペルー(国際環境を含む)の状況変化」との整合性・妥当性
・「ペルーの社会的なニーズ」との整合性・妥当性
・「日本のODA政策および対中南米政策」との整合性・妥当性
・「個別プロジェクトの目的」の達成度
II 日本のペルーに対するODAの概要
II-1対ペルーODAの概要
本評価対象期間(1990~95年度の6年間)における日本の対ペルーODA(債務繰り延べを除く)は総額1333億1900万円であり、95年度までの供与累計額2183億7100万円の61%が集中的に援助されている。
その形態別構成は、1989年度までは有償資金協力が全体の51%を占め、無償資金協力18%、技術協力31%の比率であったのに対し、90~95年度は有償資金協力が76%、無償資金協力18%、技術協力6%と有償資金協力に大きく傾斜し、技術協力の比率が低下している。有償資金協力では構造調整融資が登場し、無償資金協力でも国際収支対策を意図したノン・プロジェクト援助が初めて実施された。また、技術協力については、91年7月に発生した「ワラル事件」までは累計で専門家648人、協力隊203人、調査団1417人が派遣された。「ワラル事件」後、専門家及び協力隊が全員引き上げ、新規派遣が中止されていたが、その後、安全確認のための調査団の派遣を経て、派遣期間と地域を限定して派遣が再開され、専門家の95年度の派遣実績は4名である。
研修員受入人数は増加傾向にあり、1990~95年度の6年間で1193人(89年度までの累計は1722人)となっている。プロジェクト方式技術協力は93年度まで年間4件のペース(94年度は1件)で継続されている。
このほか金額的にはそれほど大きくないものの、世銀やIDBに日本が創設した日本特別ファンドからの資金の流れがあり、間接的な貢献を果たしている。
(1) フジモリ政権以前の対ペルー援助
ペルーに対する日本のODAは、中南米諸国の中でも早い時期に本格化しており、1959年度には技術協力が開始され、79年には技術協力協定と青年海外協力隊派遣取極めが締結された。
有償資金協力は、「リマ~チンボテ間送電線」に対する長期・低利の円借款がOECFより供与されたのが最初であり、1972年には輸出信用供与の変型の形をとって肥料工場およびマイクロウェーブ建設に日本輸出入銀行から円借款が出された。その後80年代まではペルーはインフラストラクチャー整備のための中南米への円借款の主要供与相手国の一つであった。しかし、1980年代後半になると債務返済不履行が障害となり、円借款は中断された。
円借款の中断後も、無償資金協力と技術協力は毎年3000万ドル前後の規模で継続され、プロジェクト方式技術協力は11件実施され、人材育成、技術移転で成果を上げた。
(2) フジモリ政権第1期―「ワラル事件」前
1990年7月のフジモリ政権発足後、「チャンカイ・ワラル谷灌漑施設復旧計画(第2期)」、「食糧増産援助」と「リマ市清掃機材整備計画」に対する無償資金協力の供与が決まった。さらに干ばつ被害に対する「災害緊急援助」の供与、極度の国際収支困難、財政逼迫という状況下で経済再建を支援するためのノン・プロジェクト無償資金援助の供与も行われ、技術協力も活発化した。
しかし、1991年7月にはテロ組織による「野菜生産技術センター」での派遣専門家3名の計画的な殺害事件(「ワラル事件」)の発生により、派遣専門家、協力隊員の一斉引き上げが決定され、翌年度以降の技術協力は減少した。さらに専門家派遣ばかりでなく調査団の派遣も停止された結果、開発調査の実施も不可能になり、ペルーにおける案件形成に大きな影響が及ぼされた。無償資金協力については機材供与型の案件が多くなり、有償資金協力については国際機関との協調による構造調整融資以外の供与が難しくなった。
中断されていた有償資金協力については、ペルーの国際金融界との関係改善が進んだことから、1991年12月にはプログラム型の貿易セクターローン(IDBとの協調融資)が決定し、実施された。
(3) フジモリ政権第1期一「ワラル事件」後
1992年4月にはフジモリ大統領による非常措置が発生し、対ペルー援助の停止ないし延期措置をとる国が続出する中で、日本は総理メッセージなどを通じ民主化の必要性を強調しつつ(注)援助継続の姿勢を堅持し、人的派遣が困難という制約条件の中でも、研修員の日本への受入れ強化措置がとられ、機材供与型の協力も増加し、トップ・ドナーとしての地位を占めるようになった。
技術協力のうち、研修員受入は1992年度から3年間に500人を目標として実施されたが、これを上回る成果があげられた。またプロジェクト方式技術協力は4件が継続実施され、既存のセンターを活用した第三国研修もペルー側の手によって継続実施され、周辺中南米諸国からの研修員受入が行われた。
無償資金協力では、継続案件のほか、道路修復のため「道路建設機材整備計画」、リマ市の低所得者層居住地域への上水供給のための「給水車配備計画」が実施された。1994年には、「リマ市国立病院医療機材整備計画」、「第2次地方小水力発電復旧計画」、「食糧増産援助」等が実施され、過去2年間の規模を上回る規模になった。
89年度から始められた「草の根無償資金協力」は、91年度まで年間1~3件程度であったものが92年度は5件、93年度4件、94年度8件と急増した。分野別には保健衛生、教育訓練が多いが、そのほか地方自治体による文化財保護や自然保護、選挙の公正化と効率化のための投票集計用コンピュータ設備など、特色のある使い方がされた。
有償資金協力では、IDBとの協調融資による金融セクターローンが実施された。その後、パリ・クラブの合意に基づいて「債務繰り延べ」が1993年に実施され、さらに94年3月にはIDBとの協調融資で、プロジェクト型に近い「厚生サービス強化借款」の供与も決定された。しかし、実行手続き面での調整に時間を要したこともあり、翌94年度は債務繰り延べだけにとどまっている。
1993年には同国の治安状況は急速に改善され、94年には「ワラル事件」後初のJICA調査団(給水車整備計画)が派遣された。以後、93年度3件、94年度5件、95年度19件のペースでJICA関連の調査団派遣が増えており、これらを含めた経済協力関連調査ミッションも「ワラル事件」前のペースに回復しつつある。
(注)同年5月、フジモリ大統領は制憲議会選挙を含む民主化復帰案を発表。11月には民主的・平和裡に議会選挙が実施され、同議会が採択した新憲法が翌93年10月に国民投票により承認され、ペルーは民主化プロセスに復帰した。
(4) フジモリ政権第2期
フジモリ大統領の第2期がスタートした1995年度には、「カリャオ港整備借款」と、世銀との協調融資による「リマ・カリャオ上下水道整備借款」に久々の大型プロジェクト借款の承諾が行われた。なお、カリャオ港借款については、そのフィージビリティ・スタディの見直しのため、融資機関であるOECFがその費用で追加調査を行う「案件形成促進調査(SAPROF)」が適用され、ペルーのプロジェクト形成を助けた。
さらに両国政府間では、ペルーの水利組合を対象としたツー・ステップ・ローンの「灌厩サブセクター整備借款」(世銀との協調融資)が取り決められた。このほかペルー政府からは、インフラストラクチャー整備の遅れを取り戻すためのプロジェクト借款の要請が寄せられ、いくつかは実現の方向で検討が進められている。
無償資金協力では、フジモリ政権が推進している海岸部と内陸部を結ぶ地方道路の改良工事に必要な機材の修理整備を行う「道路建設機材整備工場設備改善計画」、また91、92年度に引き続き各地の「教育施設修復計画」のための亜鉛鉄板購入資金の供与が決定された。このほか「食糧増産援助」、「カリャオ市清掃機材整備計画」、「国営放送機材整備計画」など、計36億円の無償資金協力が決定された。
草の根無償資金協力は、1995年度は前年度に比べ倍増し、都市部の貧困層居住地域での医療機材やトイレ資材などの供与、社会的弱者のための施設、農村女性支援、植林などの援助案件が含まれている。
一方、技術協力については、開発調査は1件実施され、専門家派遣は限定的に再開された。専門家のうち1名は大統領府国際技術協力局(SECTI)へのコーディネーターであり、協力案件の発掘や日本の協力スキームに関する助言を行うことを主たる任務としている。
II-2 0DA以外の経済協力
ODA以外の経済協力を政府・政府関係機関によるものと地方自治体・民間団体等によるものとに分けてみると、前者では、日本輸出入銀行(輸銀)の役割が大きい。輪銀は、フジモリ政権成立以降1996年4月までの間に1000億円を上回る融資(貸付契約ベース)を通じ、ペルーの国際金融社会への本格的復帰のための支援(国際機関に対する延滞債務解消のための日米ブリッジローン、93年)や民間部門育成等支援、経済ンフラ整備支援を行ってきた。
また、日本政府は、1993年5月以降2年間で2億ドルという付保枠の下で貿易保険を引き受けた。
他方、日系人大統領の誕生ということで地方自治体、政党、民間団体、個人からの寄付金、トラックの寄贈、衣料(古着)や物資の支援、小学校の校舎建設や保健センター建設などのための資金援助(注1)などが行われ、Basic Human Needs(BHN)に密着したODAを補完する援助として注目された。
なお民間企業による直接投資は低位にとどまっており(注2)、ODAあるいは上記地方自治体や民間団体、個人の協力の増勢とは対照的である。
(注1)1991年11月~96年4月に開設された校舎のうち名称から日本の援助によると思われるものは41件(1,084万ドル)保健センターは3件(4万6,000ドル)。
(注2)ペルー側統計によれば、1994年9月末現在で対ペルー外国投資残高に占める日本の割合は1%(11位)。
II-3 日本のODAに対するペルー側及び第三者の見解
(1) 調査の態様
今回の調査におけるヒアリングは、日本国内で3件、海外(ペルーおよび米国)にて40件以上実施した。調査は次のような方法で実施した。
第1に、短時間のヒアリングから最大限の効果を得るため、事前に在ペルー日本大使館を通じて、各訪問機関へ質問書を伝達した。また、効率よく多方面の機関・専門家に接触すべく、調査団は適宜2ないし3のグループに分かれて行動した。
第2に、ヒアリングは援助機関の専門家や中央政府の行政官のみならず、民間研究所の研究者、新聞記者、地方自治体職員、NGOのスタッフに対しても行った。また援助サイトの視察は、保健医療プロジェクト(「リマ市国立病院医療機材整備計画」、「家族計画・母子保健」)及び港湾整備プロジェクト(「カリャオ港湾整備計画」)、ならびに草の根無償資金協力(「貧民街へのトイレ建設及び環境衛生教育実施計画」、「ガニメデス診療所に対するレントゲン機材供与」)について行った。いずれも今後の対ペルー援助において重要と考えられる分野ないし形態である。
(2) ヒアリング結果の概要
(イ) 日本の対ペルー援助については、「資金協力」、「技術協力」、小規模な「草の根無償資金協力」のいずれも次のようにほぼすべてのヒアリング対象者がプラスの評価を与えている。
(1) ノン・プロジェクト型資金協力(有償・無償)
貿易セクターローン、金融セクターローンをはじめとする本援助形態は、専門家引き上げの関係でプロジェクト型の協力が停止したのちも協力が継続され、有効かつ効果的であったとともに、日本の援助の継続により他国があとに続く契機にもなった(91年9月に「支援国グループ」結成)。
(2) プロジェクト型有償資金協力
インフラ整備への円借款は、資金協力の面だけでなく、F/S見直しに関わる案件形成調査支援(例えばSAPROF)が得られたことも評価されている。
(3) プロジェクト型無償資金協力
無償資金協力による機材供与は、医療機材の供与に代表されるように「単なる機材供与だけではなく診療の質が底上げされた」、「財政難のため実現に長い時間を要するような機材更新の投資が短期間で実現された」等の評価とともに感謝の意見表明を多く受けた。
(4) 技術協力
プロジェクト方式技術協力(プロ技協)による日本人専門家からの技術移転効果が高く評価されている。確実な技術移転を促進するためにも日本人専門家派遣の本格的再開が待たれるとの指摘が多かった。
(5) 草の根無償資金協力本援助はプロジェクト・サイトでも効果が評価されており、日本大使館と現地住民組織及びNGOの三者間の連絡・調整が円滑に進められた成功例ということができよう。
(ロ) 手続き期間やプロジェクト形成など個別の課題については、改善や工夫を求める声が少なくない。手続き期間については、ペルーの社会経済の変化が早まりつつあるのに対して、日本の援助システムの対応が遅れがちになっているという指摘が多く聞かれた一方で、手続きの進捗状況等をペルー側に早めに知らせるということによって、ペルー側でのより適切な対処が可能になるとの指摘もあった。また、プロジェクト形成に関してペルー側の能力の限界と日本側の予算枠の制約が指摘されている。
(ハ) ペルー側は日本の援助の継続・拡大を強く期待しており、特に地方開発に対する展開が要望されている。
(ニ) 日本との経済協力関係全般については、官民投資のアンバランスが指摘され、民間企業による投資、民営化プロジェクトの入札への参加等、民間の積極的な進出を望む声が大きい。
(ホ) 欧米における対ペルーの主要な援助国である米国(USAID)、カナダおよびドイツ(GTZ)の各国の政府援助機関は、民主主義の発展や市民生活への寄与等の明確な方針に基づき援助を実施しているほか、以下のような援助面での特徴を有しており、日本の援助の質を向上させる上で参考となるものがあると思われる。
(1) USAID
130名の専門職員を有しており、多くの草の根援助に関わっている。そこでは、住民リーダーやNGOなどと連携しながら、「コカ経済」からの脱却を中心に捉えた「代替的」な地域経済の構築を目指した取り組みを支援している。また、地域コミュニティと地方自治体との連携も模索している点が特筆される。
(2) カナダ
Fondo Peru-Canada(ペルー・カナダ基金、1989年設立)では、貧困撲滅を主旨として、地方の住民が主体的に行っているプロジェクトに対して、現地側からの要望を受けて同基金が協力している。プロジェクトの実施主体があくまでもコミュニティの住民・農民であり、当事者がプロジェクトの意義を理解して参加・協力していることが成果をあげている理由とされている。
(3) GTZ
GTZでは援助の優先分野を保健医療、零細企業支援及び上下水道整備とし、地域としては、特にシェラ(山岳地域)とセルバ(森林地域)に集中している。
(へ) フジモリ大統領政権下でのペルーの「国づくり」の方向性については、厳しい批判を含めて多様な見解が存在するが、ペルー社会における日本人のイメージはきわめて良好であり、現政権に批判的な見解を有する人々も日本およびペルーの日系人に対しては好意的なイメージを抱いているように思われる(注)。
(注)95年、中南米の世論調査機関である「ラチノバロメトロ」が中南米8ヵ国(アルゼンティン、ブラジル、チリ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、ウルグァイ、ベネズエラ)の国民を対象に日本のイメージ調査を実施した。このうち、ペルーでは以下のような回答結果が得られた。
・回答者(1226名)の80%が日本を「よいイメージの国」とみている。
・回答者の61.7%が関係がさらに強化される」との期待を表明している。
・これらの数値は8ヵ国の平均(各57.3%、21.8%)を大きく上回った。
・ペルー国内における他国のイメージについての数値は以下のとおりであり、日本に対する好
イメージは他国の数値を大きく上回る結果となっている。米国に対する「よいイメージの国」69.0%、「関係がさらに強化される」13.5%、欧州に対する「よいイメージの国」63.0%、「関係がさらに強化される」5.1%・「外国投資の受入れで選ぶとするとどの国か」との質問結果では、米国19.9%、欧州6.6%、日本58.4%であり、日本が圧倒的に高い結果となっている。
III 日本の対ペルーODAの特質と評価
III-1 対ペルーODAにみられた特異な促進要因と障害要因
1990年代前半のペルーに対する経済協力、なかんずくODAは、日本の対外援助において極めて特異な条件のもとで進められたケースであり、日本が持つさまざまなODA手法を駆使して協力関係を促進した点で、示唆に富んだ事例を提供している。
中南米諸国に関しては一般に、日本との摩擦要因が少なかったこともあり、ODAが重要な外交手段として認識されてはいても、その手段を駆使して日本が積極的な役割を担うといった事例は少なかった。
ところが1990年代に入ると、日系出身の大統領の誕生によりペルーに対する日本国民の関心が特段に高まり、それがペルーに対する日本政府のODA施策を大きく後押しする形となった。しかも「ツナミ現象」とまでいわれたその劇的な当選過程もあって、米国をはじめ諸外国からも強い関心を呼び、日系大統領の誕生はペルーにおける日本のプレゼンスの高まりを示すもの、といった論調すらみられた。またペルー側にも、フジモリ大統領が選挙運動において自ら日系人であること、自分の当選によって日本からの援助が期待されることを強調したこともあって、日本からの経済協力に特別な関心がはらわれた。
ペルーに対する「日本国民の関心」は、政治的、経済的な問題、あるいは歴史的な背景を持つものではなく、旧系出身の大統領が初めて誕生した」ことによる国民感情に結びついた心情的な色彩の強いものであり、ODAとは別途に国民レベルあるいは地方自治体レベルでの支援も増加した。
以上のように1990年以降のペルーに対して、日系大統領の登場によって日本に対する協力要請が高まり、しかも日本国民による同国への関心が高かったことから、本来ならば経済協力を進めやすい条件にあったといえる。しかしながら実際には、
(1) 前アラン・ガルシア政権下での対外債務返済停止(債務支払額を輸出額の10%に制限)によって同国が国際金融界に受け入れられない“孤児"的存在にあったこと(「国際金融界からの孤立」)、
(2) 1991年7月に日本人農業技術者3名がゲリラによって殺害され(「ワラル事件」)、技術協力の要となる人的派遣が困難になったこと(「人的派遣の困難性」)、
(3) 1992年4月のフジモリ大統領による憲法部停止を含む非常措置によって、その後日本の「ODA大綱」(1992年6月発表)でうたわれることとなる「民主主義」原則と抵触しかねない事態が発生したこと(「民主主義原則との低触可能性」)――から、従来の対応では援助を円滑に実施し得ない状況が現出した。
日本のODAに対する供与相手国における「ニーズ」の高まり、日本国内における「支援気運」の発生にもかかわらず、上記のようにODA供与の障害要因が多数発生した点も従来のODAにはみられないものであった。
(注)ODA大綱2.(4)「開発途上国における民主化の促進、市場指向経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払う。」
III-2 対ペルーODA及びODA外交にあらわれた特質
(1) 状況変化への対応力
ODA供与に際して上述の障害要因にもかかわらず、「状況変化への(外交およびODAの)対応力」が個別局面で発揮され、結果的に有効な手段が採用されたことによって、日本はトップ・ドナーの地位を占めるに至った。
「国際金融界からの孤立」に対しては、名古屋で開催されたIDB総会の機を捉えて「支援国グループ」結成のために積極的なイニシアティブをとり、さらにIDBとの協調でOECFが構造調整融資(貿易セクターローン)に応じることによって、逼迫していたペルーの国際収支の改善に寄与すると同時に、国際金融機関によるペルーへの資金供与に先鞭をつけ、同国の“孤立"状態の終焉に手助けした。さらに、IMFによる拡大信用供与及び世界銀行の構造調整融資に当たっても、その前提条件づくりのため、輪銀が米国と共同でブリッジローンの供与に応じている。
農業技術者殺害事件(「ワラル事件」)による「人的派遣の困難性」についてみると、専門家等人の派遣を伴う協力の中断にもかかわらず、それを補うような形でODAのさまざまな手段を用いることによって支援の幅を広げた過程がみてとれる。それらを列挙すると、
(1) 構造調整融資に加えて国際収支対策に主眼をおいたノン・プロジェクト(経済構造改善努力支援)無償援助(1990、91、93、94年)の実施、
(2) 機材供与型の無償援助の増額、
(3) 研修員の受け入れ増員(1992年度より3年間に500人受入計画)、
(4) 草の根無償資金協力の受諾件数の引き上げ、
(5) 第三国研修による実行ずみプロジェクト方式技術協力の活用などがある。さらに、
(6) 資金還流措置の一環として日本が世界銀行やIDBに創設した日本特別ファンドの資金も、世界銀行やIDBの主体性のもとで活用され、ペルーの再建計画の立案やそのためのFONCODES(社会補償開発基金)といったファンド設立の呼び水的資金として利用された。
特に先に述べたIDBとの協調融資による円借款供与及び(6)の還流資金の利用は、ペルー政府および国際金融機関から、急速な状況変化への「即応性」(クイック・レスポンス)が高い手段として評価を得ている。
第3の「民主主義原則との抵触可能性」との関連では、フジモリ政権による1992年4月の非常措置後、日本は「(同政権による)改革プロセスの果実を一挙に無に帰せしめることなく早期に民主体制を回復せしめることこそが重要との観点から、静かな外交努力を行った」(93年7月19日、コロンビアのロス・アンデス大学で行われた寺田輝介中南米局長=当時の講演「日本の対中南米外交」)。具体的には「現地大使を通じて国際社会の厳しい反応を5回にわたり直接フジモリ大統領に伝え、また総理、外相メッセージの発出、さらには、(同年)5月のOAS特別外相会合の直前に日本政府は私(中南米局長)をリマへ派遣して同大統領のOASの意見を尊重する必要性を訴え、民主化プロセスヘの早期復帰の働きかけ」(同上講演)を行った。フジモリ大統領は5月15日にバハマで開催されたOAS特別外相会合に自ら出席し憲議会選挙の実施を含む民主化復帰計画を表明しており、「民主主義原則」への抵触といった事態は回避された。
(2) 国際社会復帰への支援
以上(1)の「状況変化への対応力」で述べた第1点および第3点は、ペルーの「国際社会への復帰」の観点からも特筆される日本の貢献といえる。「ペルー支援国グループ」への日本の積極的な関与やIDBとの協調融資による貿易セクターローンの供与は、同国の国際金融機関との関係を修復し金融調達面で国際社会に復帰する契機をつくり、ペルー政府およびIDB、世銀から高い評価を得ている。
IDBのペルー融資担当官は「貿易セクターローン」への日本の協調融資について、
(1) 緊急的な対応を必要としていたペルーの資金不足を補填したこと、(2)(融資にともなうコンディショナリティの付加によって)同国の対外貿易面での構造調整を促進させたこと、(3) 金融界からの資金調達に道を開いたこと一一の3点を指摘している。また世銀のペルー担当のエコノミスト及び融資担当官は、日本の円借款が遅滞していたペルーへの資金供与の進展に契機を与えたこと、さらに資金還流措置による日本特別ファンド「Policy and Human Development Fund(PHDF)」が、同国政府への助言やコンサルタントの派遣、プロジェクト形成等で極めて有効に働いたと評価している。
フジモリ大統領による非常措置以降行われた日本政府による精力的な「民主化プロセスヘの早期復帰への働きかけ」は、国際社会からの政治的な孤立の回避に寄与し、ペルー国内において評価されるとともに、国際的にも注目された。
ペルー国際研究所(Centro Peruanode Estudios Internacionales=CEPEI)の所長であるEduardo Ferreiro Costa氏は、「Autogolpe(『自主クーデター』)は支持しないものの、ペルーとは対立しなかった日本の姿勢は、欧米諸国とは異なりバランスのとれたものであった」と述べ、フジモリ政権だけではなく同国全体が日本を重視するようになる重要な契機になったと指摘している。また、これが援助停止に踏み切った欧米諸国に援助の早期再開を促す上でも役立っている。
(3) 「人的派遣」不在の開発援助
評価対象期間のペルーは、1991年7月のゲリラによる日本人農業技術者殺害事件(「ワラル事件」)を契機とした経済協力関係者の総引き上げによって、「人的派遣」不在の援助という、日本のODAにおいて極めて特異なケースとなった。この措置によって、専門家及び青年海外協力隊の滞在はもとより、開発調査等に従事する調査団、折衝・交渉等に従事する使節団等の派遣もできなくなった。「人的派遣」不在による開発援助への影響については、(1) 「人的派遣」不在による既存プロジェクトヘの影響、(2) 「人的派遣」に代わる協力態勢の形成、(3) 新規プロジェクト形成上の問題の3点から、およそ以下の諸点が指摘される。
まず(1)の既存プロジェクトヘの影響は、とりわけ「専門家」の不在が重要な意味を持った。「専門家」は供与相手国への政策アドバイス、プロジェクトの発掘・推進、技術移転等の面で日本のODAにおいては現地にあって直接参与、推進する役割を担っている。日本政府による技術協力の中心となっているプロジェクト方式技術協力による支援を進める上でも、「専門家」派遣は不可欠な要素となっている。
ペルーの場合、「専門家」の不在によっても、日本人農業技術者が殺害された野菜生産技術センターをはじめ、事業そのものはいずれも中断されることなく継続された。さらに既設のセンターの中には、ペルー側専門家の努力によって第三国研修に活用されるケースも出てきている。
「専門家」不在でも既存プロジェクトが継続し得た理由としてリマのJICA事務所では、(a)当初ペルー側関係者は派遣中断が短期間で終了すると思っていたことから、専門家復帰の時点で中断していては「恥ずかしい」との意識がペルー側に働いた、(b)テロが理由でプロジェクトが失敗するような事態は避けたいとの意地がペルー側関係者にあった、(C)フジモリ政権のプロジェクトヘの認識が高く、政策、人事、機構などに一貫性があった、(d)日本への技術協力研修員の増加が新規の知識・技術を吸収する上で寄与したの4点を挙げている。さらに、ペルー側のヒアリングで、現場における人的な接触や時間をかけての技術移転を重視する日本の技術協力の進め方そのものに、他の国のプロジェクトと比べて、「専門家」不在のような事態に陥ってもある程度はプロジェクトを自立的に継続し得る理由が含まれているとの指摘があった。ただし、日本およびペルー双方の援助関係者から、「専門家」の派遣が中断したことによって新しい技術の取り入れが大幅に遅れた点が指摘され、「専門家」不在によっても既存プロジェクトが継続し得たことが「専門家」不要論を意味するものではない点が強調されていた。
(2)の「人的派遣」に代わる協力態勢の形成は、III一2(1)の「状況変化への対応力」ですでにみたように、「人的派遣」の不在を補うべく、結果的には広範な分野のODA手段が動員され、駆使された。
(3)の「人的派遣」不在による新規プロジェクト形成上の問題点としては、「専門家」がいないことによって、(a)援助に対する被援助国の長期的な社会ニーズの把握が困難である、(b)ペルー側のODA執行態勢や法制度の急速な変化に立ち遅れる、(c)現地における援助パートナーの発掘や人材育成ができない――等の諸点が指摘された。さらに、使節団や調査団の派遣中断によって、案件として採択されていたプロジェクトに対する円借款の実行や新規のプロジェクトの形成が阻害されるという問題も生じた。「人的派遣」不在によるODA実施上の影響は大きく、ペルーのケースをもとに、派遣中断及び再開の仕方について詳細に検討を加えることが重要である。
(4) Basic Human Needsに立脚した協力
フジモリ政権期の対ペルー援助環境は、同国内の政治・経済状況及び対外関係の激しい変化によって大きく変動したが、日本の援助はほぼ一貫してBasic Human Needs(BHN)の視点から案件形成に努力してきた。
無償資金協力では、貧困層の居住地域での医療・保健施設の拡充と衛生改善関係の案件が多く取り上げられており、この5年間、食糧増産援助も一貫して続けられた。またフジモリ政権は、将来のペルーの発展は教育の普及による人的資源の育成にかかっているとの信念から、これまで教育機会に恵まれなかった地域での学校の建設・設備改善に多大なエネルギーを注いでいるが、これにも日本からの無償資金協力による学校の屋根修復資材(亜鉛鉄板)が継続的に供与され、施設改善に役立てられた。さらに教育の面では、日本の地方自治体及び非営利団体や個人による校舎建設の協力もODAを補完する援助として効果をあげた。
1990年度から95年度の間に計36件、合計2億円の草の根援助が実施された。これらは金額こそ小額ではあるものの、直接住民に届く援助であり、その内容も社会ニーズに即したものが多く、このタイプの援助もペルーにおいて6年余の経験を積み、その基準を貧困の克服と地域開発に置き、他の援助機関やNGOとの協調をこれまで以上に強化することによって、「末端まで届く援助」という観点から有効であった。したがって、実施態勢を整えることによって積極的に対応していくとともに、この援助が草の根の努力を刺激するものであると同時に、本格的な技術協力、無償資金協力等による支援のテストケースともなり、さらにこのタイプを有償資金協力も含め他の形態でも応用することを検討する価値があるという点でも、重要な意味合いを持っている。
有償資金協力でも、IDBとの協調融資で実施している「厚生サービス強化計画」への借款は、病院施設の改善を目的としたものであり、産業インフラ等への協力が多い円借款の中にあって、今後増やすことを検討してもよいモデル的なケースといえる。
フジモリ政権はその2期目の重点施策に貧困対策と雇用問題を置いているが、市場メカニズム重視のネオ・リベラリズム(新経済自由主義)の導入によって貧富の格差が拡大し社会的弱者へのしわ寄せが高まる状況を考えれば、Basic Human Needsに立脚した援助案件の形成は今後ますます重要性を増し、この視点の継続とその援助内容の質的向上を図るべく努力する必要がある。
(5) 「民間投資」不在の経済協力
広義での「経済協力」は、実施主体の観点から、政府開発援助(ODA)、その他の政府資金協力、民間資金による協力、および非営利団体による贈与の4形態によって構成される。この中でペルーに対しては「ODA」が卓越しているが、「その他の政府資金協力」は日本輸出入銀行によるブリッジ・ローンや経済インフラ整備支援等の融資の形で、また「非営利団体による贈与」は地方自治体や民間団体、個人による支援の形で一定の水準を維持し、日本の対外援助の中でその役割を果している。
これらに対して「民間資金による協力」、中でも民間企業による直接投資は非常に低位にとどまっており、日系進出企業数は1991年に40社あったものが現在では25社に減少し、ペルー政府が進める国営企業の民営化に参加する日本企業もほとんどない。証券投資などの形で同国への資金還流が発生し欧米銀行の相次ぐ進出がみられるが、邦銀は88年の東京銀行(現東京三菱銀行)の撤退によって進出ゼロの状態が続いている。経済危機や治安の悪化が日本企業の撤退の理由であったが、回復後も同国のこうしたイメージが容易に消しがたいこと、アンデス諸国やブラジルなどの周辺国を含めた市場としての同国の価値や資源国としての同国の存在に対する認識が日本では確定していないこと――などが消極的な企業行動の要因として働いている。
外国資本の中でも日本企業への進出期待は58.4%(米国19.9%、欧州6-6%)と圧倒的に高い(前出の世論調査機関「ラチノバロメトロ」によるインタビュー調査による)にもかかわらず実態が伴っていないことは、日本はトップ・ドナーでありながらも「ペルーにおける日本のプレゼンスは低い」といった同国経済界やマスコミに強く残る日本に対する消極的な評価の一因になっている。
III―3 まとめ
1990年代前半のペルーに対する日本のODAおよびODA外交は、同国内外の急激な状況変化の中でODAの執行を難しくする障害がいくつも発生したにもかかわらず、「民主化」、「市場経済改革」のODA原則を基本に据えながら、さまざまな形態のODA手段を駆使して機動的に対処したことによって、フジモリ政権が進める国際社会への復帰・民主化・経済改革への後押しと、「人的派遣」不能の制約要因のなかで限られてはいたものの、同国の社会ニーズに沿った援助を行い得た。同国に対する一連のODA外交は、ペルーにおける日本の「よいイメージ」形成に寄与するとともに、国際金融機関において経済再建支援策としての有用性と即応性について評価された。
しかし、ペルーの政治、経済情勢が安定した状態となった中で、2期目に入ったフジモリ政権が大胆に推し進める各方面での構造改革に対して、現在の日本の経済協力のシステムが機動的に対応し有効なODAを実施することができるかどうかが、今後の課題として残されている。
IV 提 言
(1) 長期的視点にたった国民的なニーズ掌握に基づく冷静なODA外交
――ペルーに対する開発援助を今後とも進めていく上で、両国の友好関係を増進するという大局的な見地から外交の常道である「フリーハンド」(行動の自由)を維持しつつ、ペルーの国民的ニースに沿った援助姿勢を堅持すること――
日系大統領に対する日本国内の共感が高いことや、フジモリ政権1期の成果に対するペルー内外の評価が高いだけに、この点は十分に留意しておかなければならない。実際に非常措置の際には、政治的フリーハンドを持ち得たからこそフジモリ政権に対して率直に意見を述べることができ、それが米州諸国に対して一定の重みを持ち、独自外交の発揮につながり、ペルーの民主化に一定の寄与を果たすことができた。
そのためには、(1) 長期的な視点のもとでペルーの国民的なニーズを把握し、案件を選択していくこと、(2) 国内世論、国際世論の動向を常に見極めながらフジモリ政権の位置づけを把握していくこと、(3) ペルーがアジア・太平洋および隣接ラテンアメリカ諸国・米州との経済協力・統合に強い関心を持っていることに鑑み、多国間の国際協力を視野において判断すること一が重要といえる。
フジモリ大統領は政権第2期の目標を貧困対策に置いているが、日本およびアジアの経験、国際社会におけるペルーの位置づけ等を踏まえて、雇用や環境、産業政策の重要性等を政策対話の中で日本側が逆提案することがあってもよいと思われる。
(2) 相手国政府の制度改革に対応し得る日本側のODA能力の強化
――ODAは相手国の要請に基づいた政府間の協力を本質としているが、ペルーの「中央政府・政府関係諸機関」のあり方がフジモリ政権による構造改革や新たな政策運営方針の採用によって急速に変わりつつあることに鑑み、迅速な対応および柔軟な制度運用を可能とするような日本側のODA能力の強化を図ること――
フジモリ政権は構造調整や行政改革、民営化を通じて政府組織のスリム化および効率化を急速に進めている。その結果、従来ODAの受け手となってきた政府組織・国営企業などの政府諸機関が縮小されたばかりか、これまで政府の機能と考えられてきた職務の多くが、民間企業、地方自治体、FONCODESなどの特殊法人、住民組織や生産者グループなどのコミュニティ団体へと移管されている。こうした変化はネオ・リベラリズムのもとで構造改革を進める中南米諸国に共通ないしは先取りする現象といえるが、ODAを促進するためには、新規プロジェクトの発掘だけにとどまらず、相手国の制度改革、政策運営の変化に踏み込んで検討する必要がある。
1990年代前半のペルーに対しては実にさまざまなODA手段がとられてきたが、日本が取り得るODA手段全体を把握して総合的に活用していく方策を考えなければ、ODA分野そのものが縮小される可能性すら出てきている。同時に、ペルー政府による政策運営のスピードアップや同国をとり巻く国際環境の急速な変化を念頭に入れたプロジェクトの形成や、その執行の加速化が必要といえる。その場合、
(1) 日本の諸官庁が実施する各種基礎調査の情報を集中させ、総合的な判断ができる態勢をつくること、
(2) 研究機関やNGO、企業などの民間諸機関、地方公共団体からのアイディア発掘や情報収集能力を高めること、
(3) 海外経済協力基金(OECF)が有する「案件形成促進調査」(SAPROF)等のプロジェクト形成を支援する手法を有効活用すること、
(4) 既存のODA要員だけでなく、現地の情勢に通じた日本、ペルー、あるいは第三国のコンサルタントの積極的な活用を検討すること、
(5) 従来の制度にとらわれずに相手国のニーズや状況に照らし、有償資金協力と技術協力の組合せ等、ODA手法の有機的連携を一層積極的に検討すること、
(6) 無償資金協力の見返り資金を原資として設立されたFondo Peru-Japonの活生化や、ペルーの第三セクター、地方自治体などODA執行チャンネルの多角化を図ること、
(7) ペルーの公的機関を媒介としたツー・ステップでの資金協力や技術協力を図ること、一が検討課題として考えられる。
(3) 「草の根」型援助拡大のための態勢づくり
――ペルー政府が貧困対策を重視し、日本政府の「草の根」支援が急増している中で、「草の根」形援助を経済協力の一つの重要な柱に育てるため、その効果および有用性についての基礎研究、実施方法の検討をすること――
1990年代前半、ペルーにおける草の根無償資金協力は、ニーズの増加、NGOの活動活発化、現地日本大使館の努力等により、件数、金額とも急激な増加をみせた。社会の底辺層に密着した支援という点で「草の根」型支援は重要であり、その意味付け、社会や文化に及ぼす影響、伝統や慣習なども考慮に入れた実施手法、NGOとの協力のあり方、案件の判定および評価態勢、JICAなど他のODA実施機関の有効活用、といった諸点について検討すべき段階に達している。
現行の大使館による対応には人員上限界があり、予算規模や応募団体が増えれば不適切な案件や組織を選んでしまうリスクが出てくることが懸念され、日本政府として、無償、有償での「草の根」型援助を拡大する体制を構築する必要がある。
(4) 官民が参加してのすそ野が広い一国間関係の構築
――日本の政府、民間が一体となってのすそ野が広い二国間関係の強化――
ペルーに対しては、広義の「経済協力」の観点からみた場合、政府レベルでの協力(ODAとその他の政府資金協力)及び地方自治団体や民間団体、個人レベルでの協力(非営利団体による贈与)では特筆すべきものがあったが、民間企業レベルでの協力は極めて低位な水準にとどまっている。企業レベルでの関係強化は、技術や経営ノウハウの移転、あるいはペルー産品の対日輸出の振興に不可欠といえる。世論調査においてペルーが日本企業の進出に大きな期待を寄せているのもこのためだが、ペルー側における投資環境の整備とともに、日本側においても貿易保険、輪銀等幅広い公的スキームの活用、民間企業活動を支援する形となる日本貿易振興会(ジェトロ)や金属鉱業事業団などの活動強化、経済団体の交流促進、ペルーの後背地である南米とアジアとの関係緊密化への支援、報道活動や研究機関の交流による情報量の蓄積と分析力の強化一などの努力が必要である。
さらに、文化団体や地方自治体、日系人社会や日本へのペルー人出稼ぎ者も念頭において交流のすそ野を広げる努力が不可欠であり、ODAの施策においてもぞうした点への認識が重要といえる。

