第一章 国別評価
1. タンザニア
(現地調査期間1995年11月24日~12月8日)
<団員構成>
犬飼一郎 国際大学大学院国際関係学研究科教授
杉山隆彦 国際協力事業団国際協力専門員
菊地剛 社団法人海外コンサルティング企業協会開発研究所所長、他
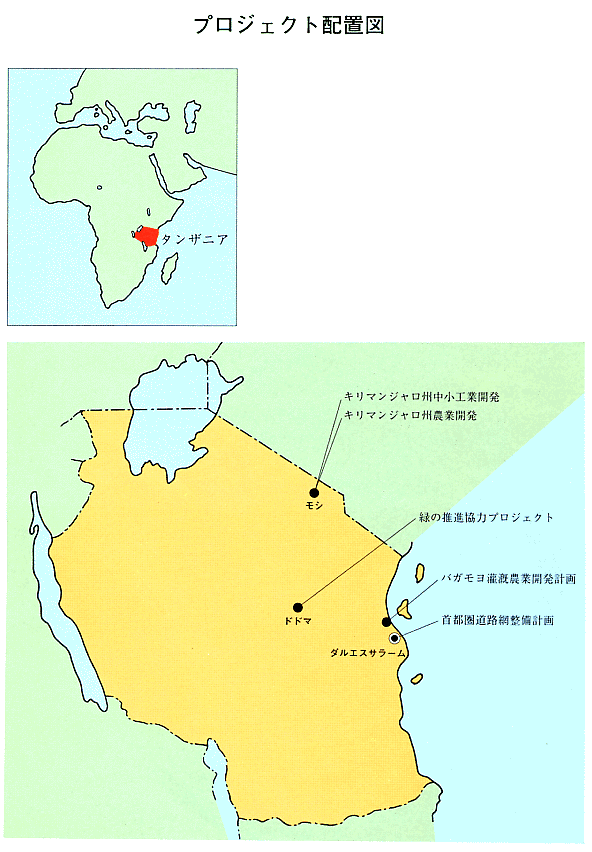
はじめに
1. タンザニア国別評価の背景・経緯
我が国では、タンザニアとの極めて友好な関係、タンザニアが市場指向型経済政策及び民主化努力を推進していること等から、タンザニアを我が国の対アフリカ援助の重点国の一つと位置付けており、1994年度までの我が国援助累計実績は、有償資金協力は387億円でアフリカ地域内第6位、無償資金協力は740億円で同第1位(E/Nベース)、技術協力は293億円で同第2位となっている。
さらに、我が国援助の1994年の支出純額は104.8百万ドルで、我が国は対タンザニア二国間援助におけるトップドナーとなっていることから、今回、タンザニアにおいて国別評価を実施することとした。なお、国別評価は1987年度に開始して以来、これまで16ヶ国で実施し、タンザニアは17ヶ国目にあたる。
2. タンザニア国別評価の視点
国別評価においては、対象国に対する我が国援助を総体として捉えて評価することが目的であることを踏まえ、以下の視点から評価を行うこととした。
1) 市場経済移行への我が国援助の貢献
(1) マクロ経済レベルでの市場経済化の移行状況
(2) 市場経済化を支援する工業分野への我が国援助の貢献
2) 貧困緩和への我が国援助の貢献
(1) 国家の基盤産業である農業分野における我が国援助の貢献
(2) 所得水準向上への我が国援助の貢献
第1章 タンザニアの市場経済化と我が国援助の貢献
1 我が国との関係
我が国は1961年にタンザニアの独立を承認し、1966年には駐タンザニア日本大使館を開設、またタンザニアも1970年に駐日タンザニア大使館を開設した。こうして両国間には緊密な友好関係が保たれてきている中で、我が国はタンザニアを対アフリカ援助の重点国として支援を行なってきている。1994年度までの累計を交換公文ベースでみると有償資金協力は387億円でサハラ以南アフリカ諸国中で第6位、無償資金協力は740億円で域内第1位であり、JICA経費実績ベースでみた技術協力は293億円であり域内第2位となっている。また青年海外協力隊員の派遣数は766人で域内第3位であった。さらに注目すべきこととして、1990年代に入り我が国の対タンザニアODA純支出額は年々増加を続けており、1990年の約4,100万ドルから1994年には約1億500万ドルヘと2倍以上に拡大している。
当初の我が国の対タンザニア援助はタンザニア政府の意向もあって主としてキリマンジャロ州に集中しており、この意味で全国的なインパクトはほとんどなかったとも考えられる。また、イギリスや北欧3カ国などと違い、我が国は政策決定レベルにアドバイザーを派遣する協力を行わず、開発戦略や政策の立案過程に関与することはなかった。またタンザニア人の高級官僚・大学教員・知識人の大部分は欧米での留学経験者であり、冷戦時代にはソ連・東欧での留学も多かった。したがって、タンザニアでは非ヨーロッパ世界での唯一の先進工業国である我が国の経済発展に関する知識は未だに極めて乏しい。
タンザニア政府が日本を含めたアジア諸国の開発の経験にかなり明確な関心を抱くに至ったのは1990年代に入ってからのことである。それには三つの理由があったと考える。第一は、1993年10月に東京で開催されたTICADが我が国の対アフリカ援助・外交に画期的とも言える積極さを明示したことである。第二は、アフリカ諸国の経済的衰退と東アジア諸国のダイナミックな経済成長との対称的な相違が、アカデミックな場を離れて、アフリカ諸国の政策決定者レベルの間に関心を喚起したことである。TICADの一つの目的はまさにこの点にあった。すなわちアフリカ諸国に対して「ルック・アジア・ポリシー」を考慮する機会を提供することである。第三に、欧米諸国の「援助疲れ」症候が現われるなかで我が国は援助大国としての地位を確立した。積極的に途上国援助を持続させる我が国の政策がアフリカ諸国に改めて日本への関心を強める結果となった。我が国の途上国支援はこのような拡大した期待に応えねばならないのである。
2 タンザニアのマクロ経済概況
タンザニアの独立以来の経済発展の動向は次の4局面で示すことができる。
(1) 植民地市場経済(強い規制・統制経済)から社会主義的計画・統制経済への移行
1960年代初期から1967年のアリュウシャ宣言とそれに続く社会主義的国家主導型の経済開発は1973年までは比較的順調な成長期であった。1967-73年では、年平均GDP成長率は56%、一人当りGNPは2.5%で増加しており、輸出・輸入もそれぞれ年当り6%で増加していた。インフレ率は一桁に押さえられていた。この原因としては、世界経済が未だに第2次大戦後の「黄金期」的拡張過程にあり、またニエレレ元大統領の開発理念に対する世界的共感からタンザニアは世界銀行やスカンジナビア諸国からの多くの援助を受けていたことが考えられる。
(2) 社会主義的計画経済の破綻
1974-84年の10年間において、計画的・強制的集村化による農業開発は農村経済を疲弊せしめ、基幹産業国有化政策と輸入代替工業化の失敗が明らかになり、再度のオイルショックの影響と先進国の経済不況による輸出の不振とが重なり、GDP成長率が加速的なマイナスに転じた。一人当たりGDPの年平均成長率は1974~78年にはマイナス0.9%、1979-81年にはマイナス1.1%、1982~84年にはさらにマイナス2.9%となった。他方、この期間のインフレ率は15%から31%へと高騰し、とくに1984年には過去最高の36%に達した。実質家計所得は1970年代始めと比較して1984年には半減したといわれる。
(3) 市場経済への移行模索
1986年7月に新政権が誕生し1986-88年経済復興計画(ERP)を作成し、IMFのコンディショナリティーを受け入れて開始した構造調整計画の結果、GDPに占める財政収支赤字の比率が1980年の11.4%から1988年の6.0%にまで縮小した。IMFから6,420万SDR、世銀から1億ドルの融資を得るに至った。また1986年9月のパリクラブでも債権国から7億ドルの債務繰延べを認められた。1986~87年の2年間にGDP成長率は4%に回復し、一人当たりGDPの成長率も0.7%というわずかながらもプラスに転じた。インフレ率も低下傾向に転じていた。ERPはその後ERP-2として継続され、この間に1989年には経済社会行動計画(ESAP)が策定された。
1989~93年には構造調整がかなりの成果をあげ、タンザニアはその実施の成功例と称賛された。特に農産物流通の自由化、農産物価格の政府統制撤廃、為替レートの単一化、貿易の自由化等の改革に尽力した。GDP成長率は1989年に7%を越えたがその後1990-92年には3%に低下し、1993年には6%以上に回復した。対GDP財政収支の赤字比率は1990年初頭には約3%にまで低下した。しかし経常収支赤字の対GDP比率は1986年の2.7%から1989年には9.0%に増加、1993年にはさらに12%程度に増加した。インフレ率も15%という目標は実現できなかったが(1991年を除く)20~22%台になった。製造業部門にはかなりの問題が残された。1990年と1991年には貿易自由化による国内産業への圧迫、1993年には旱魃による水位低下のために電力供給が減少・不規則になり、製造業の成長率は2.5%に留まった。
1992年に国営部門改革委員会(PSRC)を設けて国営企業の改組に着手し、1993年末までに20の国営企業払下を実施し、1993/94年に128企業の民間化を計画したが計画通りには進展していない。また、政府雇用改革として1992/93年に1万人の雇用削減を実施した。1993/94年にはさらに2万人の雇用削減が計画され、3年間で計5万人の削減が予定された。解雇手当資金の調達や解雇労働者の再雇用の難しさが深刻な失業問題ともからんで社会問題化してきている。
(4) 移行過程の危機:経済行政能力の不足
1994年に至りドナーとタンザニア政府との関係は再び危機的状況に直面した。その最大の原因は財政収支赤字の増加であった。GDPに対する歳入の割合は1988年の19.5%から1991年の23.5%へとにかけて着実に微増し続けたが、1992年には一挙に16.8%に落ち込んだ。他方、GDPに対する歳出の比率は1991年の26.4%から1992年には30.8%に増大した。その結果、財政赤字の対GDP比率は1991年の3%から1992年には14%に激増した。1994年度もこの傾向が続いた。歳入の赤字を借入で補填したために政府債務は1993年度末の938億シリングから1994年6月末には1,257億シリングに増加した。またインフレ率は1994年10月には37%にまで高まり、輸出の不振は著しく、貿易赤字は1994年には7億8,200ドルに拡大した。輸出稼得額は輸入のわずか3分の1を充たすのみであった。貿易収支、経常収支、国際収支のすべてが著しい悪化をきたしていた。
ドナーの輸入支援援助に対する見返り資金積み立ての遅延は長年の懸念となっており、歳入不足による見返り資金の不透明な流用がからんでタンザニア政府の財政赤字の増大が改めて問題化した。さらに歳入欠陥の原因が歳入管理の失敗、脱税の横行、税の減免措置の拡大、および歳出管理能力の欠陥によるものであることが明らかになるにともない、世銀・IMFはESAPに対する構造調整融資を“凍結"し、他の主要ドナーもノン・プロジェクト融資を延期する事態となった。かくして構造調整の優等生とみなされたタンザニアとドナーとの関係は危機的状況になった。
3. タンザニアにおける工業セクターの概況
(1) 国家経済における位置付け
タンザニアは農業国であり、農業セクターが、GDP、輸出、就業労働人口への寄与率において、それぞれ、50~60%、50%以上、80%を占め、工業セクターや、サービスセクターを大きく引き離している。しかし今後、タンザニア政府は、一次産品依存型の経済・輸出からの脱却を推進する方針であり、また、経済や貿易の自由化や公社・公団の民営化の推進など、新しい経済環境が生まれてきたこともあって工業セクターの役割への期待がこれまで以上に高まっている。
工業セクターのGDPへの寄与率は過去10年間平均約10%であった。また、輸出に占める工業製品の割合は、1989年から1994年の間をみると14~20%を推移し、賃金労働人口については全賃金労働人口の約18%を占めている。
工業セクターは、規模により大企業と中小企業と零細なインフォーマル・セクターに分けることができる。大企業は国営企業か外国資本との民間合弁企業、中小企業はインド人も含まれるがタンザニア人によるものが多い。インフォーマルセクターは殆どはタンザニア人である。
タンザニア政府は、生産部門の民営化を進めており、国営工場の殆どをその対象としている。一方、中小企業については、雇用機会の創出、所得機会の向上、ひいては貧困緩和や地域格差の是正に大きな役割を果たすものとして、今後にますます期待がかけられている。タンザニアの中小工業振興の歴史は新しくない。1964年の独立以来、政府は中小企業の振興に力を注ぎ、1973年には中小工業開発公社(SIDO)を設立した。SIDOは、タンザニアの中小企業の振興のために技術サービス、経営指導、技術訓練サービス、クレジットサービスを提供し、各州に工業団地を設置・運営、さらには工業共同組合の設立・運営指導を行ってきた。SIDOのこのような役割と機能、全国に張り巡らせたネットワークは、中小工業振興の一つのモデルとして途上国各国からの視察が多い。但し、最近の公社・公団の民営化により、SIDOもその対象となり、今後SIDO本部はもちろん、各州にある地方支部並びに工業団地は、政府からの財政的支援が少なくなってきている。この意味からも、タンザニアの中小企業は、かつてのような低廉なサービスをSIDOに期待できなくなる。いづれにしても、中小工業に対してGDPや雇用への貢献の面から今後ますます期待が高まっていくことは確かである。
(2) 工業セクターの諸問題
工業セクターは、本来国家経済において、発展の推進力あるいは牽引力としての重要な役割を担うべきであるが、現在のところ、タンザニアの工業セクターは多くの問題を抱えており、その役割を果たすまでには至っていない。
タンザニアの工業セクターが現在直面している問題は次のとおりである。
1) 工業開発政策の不在
タンザニアのように、未だ市場経済が未成熟で、民間セクターも全般的に活発でないところでは、明確な工業開発政策を打ち出さない限り、工業セクターの振興は難しい。政策不在がタンザニアの持つ工業潜在力を活用できないでいるといって過日でない。
2) 工業省・関係機関が弱体
工業省及びSIDOは、いずれの組織も中堅クラス、若手スタッフの人材不足という印象である。工業省の局長でさえ工業の政策や実態について明確に回答できず、また、SIDOにおいては、中堅クラス10人程が経済の自由化、民間企業の活性化に伴い待遇の良いところに移るため退職したということであった。
但し、SIDO本部(ダル・エス・サラーム)に比し、地方のSIDOの方が活気が感じられた。モシのSIDOオフィスの場合、本部からの支援が当てに出来ないということで、リージョナル・マネジャーが独立採算性を目指して積極的な経営を進めていた。
3) 中小工業・裾野産業の未発達
SIDOは各州に支部を置き、各州の中小企業のための工業団地の運営・指導を図ってきたが、長く続いた国の外貨不足、部品・材料の調達力の弱さ、指導に当たるSIDOスタッフの能力不足などが重なり中小企業が充分育っていないのが実情である。このため大手工場への部品・材料を提供できる裾野産業も発達していない。また、経済の自由化によって比較的安く品質の良い外国製品の輸入が活発となり、国内の中小企業の製品が太刀打ちできない状況になっており、企業が倒産、不振に陥っているといわれる。
4) 大企業(主に国営企業)の設備の低稼働率
工場の稼働率はきわめて低い。1992年の場合、鋼板、アルミニウムおよび製油関係だけが75%以上で良い方だが、タバコやビールは60%以下、セメントが35%、繊維は15%である。農機具や食用油などは繊維と同様瀕死の状態といわれる。その大きい理由として、貿易の自由化や密輸などで品質が比較的良く、安い製品がタンザニアに入っていることが掲げられる。
5) 農業と工業の弱いリンケージ
タンザニアは言うまでもなく農業国であるが、農業セクターが工業セクターに対して原材料の安定的な供給者になっていないのが実情である。自国の農産物を材料に使っている工場が、しばしば原材料不足に陥っている。
6) 産業インフラの不整備
しばしば起こる停電による工場の生産活動の停止、通信設備の不備、運搬網の未整備、あるいは工業用水の供給不足などインフラの不備により生産活動並びに生産流通が影響を受けている。これはタンザニアが長年抱えてきた問題でもあるが、改善が遅々として進んでいない。
7) 工業統計の不備
タンザニアは1989年に工業センサスを行ったが、その後体系だった工業統計は整備されていない。工業開発政策の不在は、工業統計の不備にも一因がある。工業の実態を示す統計が不十分であることは、同国の政策担当者にとってはもちろんのこと、援助する側にも頼るべき判断材料のひとつを欠くことになる。
4 市場経済化と工業セクター
(1) 公社・公団の民営化の現況
1964年の独立以来、社会主義国家を歩んできたタンザニアも、1986年、世銀・IMFの条件を受け入れ経済自由化を進めることになった。そして5年後、経済自由化のひとつの大きな計画が公社・公団の民営化である。タンザニア政府は約400にものぼる公社・公団の民営化推進のために1991年末に「公社・公団改革委員会」を設置、1992年1月に「公社・公団改革に関する声明」を発表、そして1993年8月に「公社・公団民営化基本計画」を打ち出した。タンザニア政府は、これにより公社・公団の売却、清算、合弁企業の形成、経営委託(リース)の具体化を図ってきた。民営化には、各公社・公団の資産評価に時間がかかり、また、予算不足のため退職者への退職金の支払が出来なかったり、あるいは遅れたりして、必ずしも順調に進んでいない。公社・公団の民営化は5カ年計画で進められており、既に2年経過したが、365社のうち100社程度で未だ全体の30%しか民営化(売却、清算も含む)が進んでいない。比較的売却しやすい、つまり買客からみて魅力のある企業から民営化が進んでいると考えられるので、今後そのスピードはダウンしていくことが予想される。
(2) 中小企業への貿易自由化の影響
貿易自由化の進展によって、国産品より安くしかも比較的品質の良い外国製品が輸入されるようになり、痛手を受けている中小企業が多くなっている。SIDOの資料によれば、例えば、食用油、繊維、農具等は、倒産したりあるいは経営不振になっている企業が少なくないといわれている。直接的ではないにしても、中小企業が、貿易の自由化、経済の自由化によりマイナスの影響を受けている面もある。
例えば、中小企業の振興を担っているSIDOの中堅スタッフはより良い待遇を求めて退職し、民間に移っている。また、SIDOの幹部の話では、政府は公社・公団の民営化に関心がゆき、中小企業の振興は重要といいながら、それがリップサービスに終り、実質的な支援がされていないとのことである。
このような点から、タンザニアの中小企業は貿易の自由化や経済の自由化の波を直面に受け、育たないうちに沈んで行くことが危倶される。
5 市場経済化支援への我が国協力の評価
タンザニアに対する本格的な政府開発援助はタンザニア政府の要請を受けてキリマンジャロ州地域開発を支援することから始まった。同時にKR関連援助や構造調整との関連で国際収支支援の商品輸入援助(CIS)をノンプロ無償援助で実施し、運輸関連インフラ基盤整備についても無償援助を行ってきている。我が国のタンザニア援助は社会主義的前政権のころに始められ、また移行過程のタンザニアに対する援助は1986年に始まった。
CIS(広義でKR関連援助を含む)は見返り資金の積立により政府の歳入として開発支出を支える効果をもっている。外貨不足で原料は部品輸入が困難になり製造業は著しい低稼働率(20%程度の企業すら認められた)に陥っていたが、CISの効果的利用により稼働率のかなりの改善をもたらした。しかし見返り資金の積立とその用途については問題が指摘されておりドナーの間に強い批判が起こっている。特に政府関連企業においては見返り資金の積立がほとんど不履行のものが多く、また主として民間企業が行った政府への見返り資金積立分が使途不明のまま流用されていると懸念されている。タンザニア側による見返り資金積立の管理・運用の能力整備・拡充が緊急事態となっている。
構造調整は貧困層に対して概して好ましい影響をもたらしたと世銀は主張している。その根拠として平価切り下げと食糧作物の流通規制の撤廃が農村での所得を増加させたと論じている。しかし食糧流通を自由化すると同時に輸送費が高くつく僻地へは個人の買付け商人は入って行かない場合が多く、また買付けにいっても輸送費を見込んでやすく買い叩く傾向があることも報告されている。世銀は輸入自由化の結果、生活必需品が市場に出回るようになり殆どの都市住民は生活水準を向上させ、インフォーマルセクターでの労働需要が高まり低所得者層に雇用機会を提供したとも論じている。しかし低所得・不完全就業の増加だけで貧困の緩和への効果を断言することはできないだろう。
6 今後の方向性
民営化の事務局は「公社・公団改革委員会」であるが、前述したように民営化は必ずしも順調に進んでいない。これは、公社・公団を売りに出すにも、整理するにも、まずその組織の持つ資産が正しく評価されなければならないが、同委員会がそういった評価をするスタッフを抱えていないことが一つの理由である。結局コンサルタントを雇って個々の公社・公団の資産評価を行っているのが現状である。同委員会の会長は、資産評価のための協力を日本に期待していた。
しかし、我が国でこのような経験を持ったコンサルタントや専門家を探すのは容易でないと思われる。とすれば、タンザニア政府がコンサルタントを雇う経費をファイナンスするか、あるいはタンザニアで試算評価できる外国のコンサルタントを雇って派遣すること等が考えられるが、それでは財務補填的色彩が強く、r日本の顔が見えない援助」になる恐れもある。このように、民営化への協力については、タンザニア側のニーズはあるものの我が国として如何なる協力を行うことが効果的であるのか検討し、慎重に対応していくべきであろう。
第2章 貧困緩和・所得水準向上への我が国援助の貢献
1. タンザニアの貧困
タンザニアでは、1991年に世銀と共同で貧困状況を調査し、実態を把握し貧困緩和に対する社会開発政策を策定した。当時、貧困ラインは年収46,173シリングとされ、全タンザニア人の約50%は貧困下にあり、36%は最下層の貧困にあるとされた。そこでは、タンザニアの貧困は低い経済成長率と不平等な収入の配分と密接に関係があると分析され、少なく見積っても全人口の約5割は一日の収入が1ドル以下であり、この状況を改善するには、経済成長を加速させなければならないとしていた。そして、貧困の85%が農村部、15%の貧困が都市部に存在し、地域間格差が大きく、農村部の一人当たりの収入は都市部のそれの半分以下と推計され、特に首都ダルエスサラームとの差は大きく、首都では貧困全体の2%が存在しているにすぎないと報告されている。また、農村の人口の90%は一日の収入が0.75ドル以下という状況であり、タンザニアの貧困は農村の貧困として捉えられている。
1994年度の国連開発計画の人口開発指数において、タンザニアは173カ国中148番目にあるが、経済的状況に比較すると、高い位置付けになっている。このことは、独立後の社会サービス拡大政策の影響と見ることができるが、現在のサービスの内容的悪化を考慮すると、もっと指数は下がるはずである。1970年代以降、当国の社会分野、特に医療と教育の目標達成には目を見張るべきものがあった。幼児死亡率は1965年の1000人あたり138人から1990年には同115人となったし、寿命も1960年の42歳から1991年には51歳に上昇した。成人職字率も独立当時の10%から1991年には68%を達成した。そして、1970年代末には人口の4分の3は診療所の5キロ以内に居住していると言われた。保健医療分野での問題としては、エイズの急速な蔓延があり、1990年には15~29歳の国民の7~8%が陽性であると報告されている。
食糧確保の観点からは、国民一人当たりの平均カロリー摂取量は1965年の1,931キロカロリーから1989年には2,205キロカロリーになった。栄養障害は農村部で頻度が高い。農村の5歳以下の児童の40~60%が平均体重の80%以下であると報告され、乳児、5歳未満幼児死亡率も農村部で圧倒的に高いと報告されている。また、妊婦及び授乳中の婦人は貧血症に罹っている割合が高い。蛋白質・カロリー栄養失調、ビタミン欠乏症、ヨウ素欠乏症等もトウモロコシ、カッサバ、ソルガム等を基調にする食事に依存する地域では、多くの子供がこれら栄養障害に陥っている。
農村の婦人は、農業の商業化と共に社会における地位が下がってきた。特に、土地所有制限が集団から個人所有に変わり、所有権が男子に認められるようになり、女性の社会における役割は低下した。憲法では男女同権が保証されているが、慣習法的に女性の土地所有権が認められない状況が生じている。現在では、女子の就学、共同組合等結社の自由、世帯主としての権利等法的に女性の地位向上措置が執られてきているが、必ずしもその成果は十分達成されて無く、未だ農村部において女性は弱者の地位にある。
タンザニアの貧困の特徴を貧困に関与する諸要因をもとに表1に示した。この表から、富裕層による搾取というよりは、国民の大半が生産性の低い小規模農業に生計を依存していることが貧困の源となっていることがよくわかり、また、教育の重要性も理解できる。
| 貧困層 | 非貧困層 | |
| 読み書きできる成人 | 59% | 75% |
| 水場へ30分以上要する世帯 | 23% | 16% |
| 扶養率 | 1.31 | 1.01 |
| 世帯人員 | 6.8 | 5.9 |
| 女性世帯主率 | 9.30% | 9.50% |
| 一人当たり耕作面積 | 0.62 | 0.62 |
| 土地所有世帯 | 93% | 73% |
| 食糧自給率 | 32% | 34% |
タンザニアでは、教育の荒廃も著しく、そこでは初等から高等教育、さらに職業・技術教育分野でのリハビリ・拡充が必要とされている。初等教育はBHNとして、社会主義時代に目覚ましい普及を遂げたが、財政の悪化と共に教育レベルは低下し、また、就学率も低下した。中等及び高等教育は、他のアフリカ諸国と異なり、エリート教育としてそれらの量的拡大は行われなかった。現在、初等、中等教育では教育施設、教材不足、教員の質の低下が指摘され、初等教育から中等教育への進学の枠が極めて狭いことから、中等教育の量的拡大が計画されている。また、高等教育の質的改善が教育分野では高い優先度が与えられている。教育の質的低下は、配分される予算が教員の人件費にほぼ全て費やされ、教育・研究費が確保できなかったことが大きな原因となっている。職業教育は、職員研修機関として官公庁が独自に教育機関を有したこともあり、教員省傘下でのこの分野の開発は遅れている。従って、教育分野では、施設・機材の整備、教員養成と共に新しい政治・経済環境に適する人材の供給を考えたカリキュラム開発や教育行政官の養成をも含めたかなりトータルな開発戦略を策定することが必要になる。
ノンフォーマル教育としては、識字教育、特に農村婦人の教育は新しい政治・経済環境に対する適応とエイズ問題を含む保健衛生意識向上の観点から不可欠となろうし、初等教育修了者に対する技能訓練の枠の拡大も必要であろう。
貧困問題については、その原因が多要因的であり、緩和に対するアプローチもそのことを念頭に置かねばならない。しかも、全国的に調査された現在も、タンザニアの貧困の実態が正確に把握できない状況にある。従って、貧困緩和に対する投資を考える際には、既存情報に依存するだけではなくかなり詳細な調査を必要とし、貧困とそれを取り巻く諸因子を十分理解することが重要になる。一般に、貧困を取り巻く諸因子は悪循環を作っていることから、悪循環を断つ切り口を作り、連鎖的に次から次の貧困要因を断つことが必要となり、クロスセクトラルなアプローチが必要とされることを十分認識しておくことが必要である。さらに、問題は地域住民と密接に結びついていることから、住民の参加無くしては貧困緩和を考えることはできない。住民が話し合い、コンセンサスを得るプロセスは時間を要するし、プロジェクトの実施段階を考える場合、時間を十分取り、息長く協力することが必要になることを認識しておかねばならないであろう。
2 農業・農村開発を通じた貧困緩和への我が国協力
(1) タンザニアの農業の現状
1) 農業技術の後進性
タンザニアの農業はかなり機械化が進んだ大規模農業と手作業に依存する小規模農業に分類される。前者の多くは、未だ国営企業の農場として存在しているが、今後経済の自由化と共に民営化されるであろう。後者は、約350万世帯(全人口の約80%)あり、これら農家の平均作付面積はα88ヘクタールである。この大多数の農家が小規模農家である事実は、後述する農業の生産性と大きくかかわっており、小規模農家の農業技術の近代化が農業の生産性向上に不可欠な要因となっている。小規模農家における技術改良は、農民が負担しなければならない投入財と新しい技術に求められる農民の維持管理能力を十分配慮したものでなければならない。また、タンザニアの農業は、地理的要因により非常に多様性に富むものであることを念頭に入れ技術開発がなされることが、技術の持続的発展の観点から不可欠である。農業生態的研究を通し、農業の地域特性を明確にし、環境保全との関わりから土壌の肥沃度を向上・維持する技術の導入も必要とされている。また、タンザニアでは有畜農業が普及していることから、農耕と牧畜の有機的活用を支援する技術導入が必要であろう。
2) 農業の低生産性
農業生産を向上するには、一般論として、単純に耕地面積を増大させること、単位面積当たりの収量を増加させること、あるいは生産過程及び収穫後の損失を防ぐことの3方法が考えられる。
しかし、タンザニアの農業は天水依存型であるため生産が不安定であり、生産性の安定化が農業開発の重要な要因となっている。そこでは、水の利用の可能性が鍵となっており、その観点から灌概農業の整備が望まれている。しかし、灌概事業は利用者により運営・管理可能な規模で且つ持続性のある技術が導入される必要がある。現状から見ると、既存伝統的灌概方式の改良・普及が資本・高度技術集約型灌厩への移行期として考えられなければならない。
一部では、タンザニアには未だ未利用の可耕地が多く存在し、その有効利用により農業生産を増大することが可能であるとする見方もある。しかし、これまでの人口増加による必要食糧生産を耕地面積の増大により確保してきた方法の結果は、裸地面積が増加し、農業生産を長期的に持続させることができないばかりか自然破壊をもたらしてきている。従って、今後も耕地面積を増加させる方向は、さらなる自然破壊をもたらすことになり、この方途による農業生産の増大は抑制されるべきであろう。
研究・開発の成果を活用することによる農業技術の改善や品種改良による収量の増加や農産物の損失を防ぐことが考えられなければならない。
土地利用と労働力の利用は密接な関係があるが、機械化により生産性向上を図る場合にも、前述したように有畜農業が普及していることから、畜力の有効利用とそれに適応する農機具開発が推進されることが必要であろう。
3) 流通機構
市場経済への移行は農産物流通機構の変革をもたらしている。かつては、あらゆる農作物は公社・公団や協同組合を通して売らなければならなかったが、現在では民間商人の参画を許し、農民は自由に農作物を売ることができるようになった。しかし、価格統制が撤廃されたことから、生産者価格は産地と市場間の道路条件や距離が価格設定の大きな要因となり、輸送コスト分生産者価格が低下する現象を社会主義時代の視点から搾取との見方も多い。経済自由化は産地間に新しい形態の地域格差をもたらしていると言えるわけである。このような状況から、食糧の主産地が大消費地である首都等から遠隔の場合は、市場が国外であろうと交易を自由化しているわけで、天候の良好な国内需要を満足し得る収穫年でも、国内流通の不均衡から食料輸入(食糧援助を含む)をせざるを得ない状況も発生している。
農業投入財がタイミング良く入手できないことも生産性向上を妨げる一因となっており、強力な組合組織の結成と農民に対する融資制度の確立が必要となっている。特に後者は、国営市中銀行の構造改革以降、農民の金融機関利用可能性が大幅に減少したことに対する改善策として考えられねばならない。
このような状況から、戦略的食糧確保や輸出振興政策を念頭に置いたプライオリティ付けに基づく農村インフラ整備が必要とされている。さらに、経営能力を有する農民の育成と市場経済化での農業協同組合活動を支援し得る官僚機構の整備も必要とされている。
4) 農村インフラ
タンザニアの農村インフラはほぼ全国的に荒廃しており、それらの修復は遅々としている。インフラ整備を農村の生業を支え且つ住民のBasic Human Needsを満たすものと考えると、タンザニアでは、道路、給水、保健、教育のリハビリと新規拡充が貧困緩和と関連して当面緊急性の高い重点分野であろう。しかし、これらのサービスの維持管理は受益者負担が原則であり、住民参加を不可欠の要素としている。従って、住民の公益事業に対する意識改革(これらは社会主義下では政府が無料で与えるものと認識されていた)が必要であろうし、地域間の貧富の格差と受益者負担を如何に均衡させ全国的底上げを可能にし得るかの戦略策定が必要になる。
(2) 貧困緩和への我が国協力の評価
我が国は現在まで、貧困緩和及び所得水準向上に直接・間接に貢献し得る協力を継続してきた。貧困緩和に関連して、食糧援助や災害援助は直接禅益者にインパクトを与える支援であり、自然災害や天候異変による緊急事態を救援する観点から十分感謝される援助であったと評価し得るし、今後も緊急事態に対し人道的見地よりこの形態の支援は行わねばならないであろう。また、所得向上についても、道路網整備、配電網整備といった経済インフラ整備は産業の生産性向上を通し所得の増加に貢献したと想像することは容易であるし、センター方式の協力も技術移転を通し、生産性の向上に貢献したと考えられる。しかし、タンザニアの現状は、独立以降30数年を経て、その経済は向上するより悪化しており、我が国を含む多くのドナーの協力の成果を見ることが困難な状況にある。従って、我が国の協力の成果も点的に見ることは可能かもしれないが、マクロレベルでインパクトを見ることは極めて困難である。経済政策の失敗、人口増加等、国内要因と石油ショックや農産物価格の国際市場での低下等、外的要因がタンザニア経済の成長阻害の源として挙げられるが、ここでは援助との関係で、経済発展の阻害要因となる事項に焦点を当てると以下のように説明できる。
1) 援助を受け、それを活用し、持続的発展を確立し得る人的資源と組織・制度が十分育成されていない。これは、今後の協力を考える際に留意しなければならない分野であると同時に、ハンドオーバーが可能になるまで長時間を要することの認識も必要とされるであろう。
2) セカンドエコノミー或いはインフォーマルセクターと言われる裏の経済の存在が経済指標を正しく分析・理解することを不可能にしている。これは、個人の経済活動を制限する方向ではなく、活動が把握できるような制度造りが必要であろう。
3) 統計資料が整備されていないことと、仮に資料が存在しても、信頼性が低いことであり、このことが計画の立案・評価を困難にしている。現実に国勢調査の実施が自国で困難な状況であり、戸籍や住民票が存在しないといっても過言でない状況は、早急に改善される必要がある。
農業・農村開発に焦点を当てると、上述したとおり、我が国はタンザニアの要請により、キリマンジャロ州の開発を中心に協力を実施してきた。同州での協力の評価を技術移転の観点からすれば、その成果は大いに評価できるものであるが、生産性、所得向上或いは貧困緩和の観点からはセカンドエコノミーの存在により、統計的有意差は見いだせないのが現状であり、それは、やはり上述したタンザニアの組織・制度の脆弱性に起因していると言える。
タンザニアにおいて、貧困緩和は農業開発の中の重要な課題の一つとして捉えられている。従って、農業開発や輸出振興等の協力を考える場合には、農村の貧困の緩和を通して行われねばならないし、逆に生活水準の向上や、保健・教育水準の向上を考えるとき、農業生産の向上に基づく所得の向上が期待されなければならないことになる。そして、貧困緩和は包括的且つマルチセクトラルなアプローチが必要とされる分野であることも良く知られている。
(3) 貧困緩和への我が国援助の方向性
農業分野において、生産・商業部門から政府関係機関はできるだけ関与を少なくし、規制緩和と民営化を促進する方向にある中で、援助分野を策定すると、長期的にも民営化の可能性が少なく政府機関の管理下にある経済・社会インフラ整備、教育・研究・訓練、普及、公益事業等限定された分野になるであろう。従って、感慨事業のように直接生産に関わる施設設備分野は、生産体系に政府が関与しないという前提から、農民の自主的共同体が組織され、農民により施設が管理運営される見通しがない場合は、案件として採り上げることは困難になると考えられる。さらに、農・工業における生産性向上を目的とする援助は今後住民参加を前提として援助が考えられることが不可欠となり、大規模な生産システムに対する援助は融資(有償資金協力)に依存することになるであろう。それ故、タンザニアの農業のように、小規模農業が主体となっている国では、援助の規模は農民の管理・運営能力内の援助が妥当なものとなろうし、このことは見直しされた農業政策の中でも指摘されている。このような視点に立つと、キリマンジャロ農業開発プロジェクトは、段階的に州政府の管理から直接生産に関わる農民の自主的運営・管理に移行する方途を策定・実施することが望ましい方向であろう。そこでは、プロジェクトの歴史的経緯は無視できないであろうが、周辺農民で当初計画に参加していなかったが後に稲作農民に転向し、プロジェクト外で非合法稲作農民と見なされている集団を技術移転のインパクトであると評価し、彼らをも取り込み持続性のある生産体系の確立を目指す計画策定が必要であろう。他方、農業技術協力が、国家的レベルでの視点に立ち、農業技術向上に貢献しようとする姿勢は、長期的に見た場合、我が国の農業分野支援に対するインパクトの広がりからも大きな成果が期待できるものである。
住民参加を通しプロジェクトに対するオーナー意識を向上させ、持続性のある発展につなげるには、技術的にも財政的にも運営管理能力内での適正規模の援助が望ましいであろうし、伝統農法に対する認識を科学的実証により深め、終局目標としての持続性ある農業生産システムを確立・伝播することも重要であろう。しかし、いずれも時間を要する協力であり、息長く協力することの必要性が関係者により理解されなければならないであろう。さらに、農村の貧困問題は、その原因がセクター横断的で多因子に由来しているので、マルチセクトラルアプローチが必要となり、その意味からも小回りの利く援助が農村の貧困緩和には必要とされている。かかる観点から、アグロフォレストリー的性格のある援助は、包括する分野が地域の環境教育、女性の参加、収入源の多様化、エネルギー源の確保等多岐にわたり、多重要因的である小規模農業の貧困緩和に有効なアプローチの一つと見ることができる。
ローカルコスト負担が困難な状況にあるタンザニアでは、食糧増産援助(2KR)の見返り資金が積み立てられ、それが有効に活用される場合、則ちA㏄ountabilityとTransparencyが確保されるなら、ノンプロ無償と同様に非常に足の速い有効な援助であり、2KR見返り資金と技術協力をリンクさせることで援助の効率性を高めることができよう。ローカルコスト負担の困難さと共に、人材育成や効率的組織・制度の確立が遅れているタンザニアでは、無償資金援助のみでハードを供与することは供与されたものが持続性を持ち活用され得るかという観点から妥当性には疑問符がっきまとう。従って、ソフト面の協力と連携した形態での協力の可能性を検討することが必要であろう。
農業技術向上が重要であることは言うまでもないが、経済改革による市場自由化、金融制度改革、行政改革等、多種多様の改革がタンザニアでは実施されており、改革に1順応し得る人材の養成・訓練は緊急に必要とされている。従って、援助する側においても、同様に被援助国の政治・経済政策の変換を理解し、新たな展開に対応していくことが必要であり、援助戦略の方向性の見直しが必要となる。
独立以来の政策の余子余屈折の結果、タンザニアでは殆ど全ての経済及び社会分野のインフラは荒廃している。また、政府もドナーに対し、過去に州別開発援助を要請した政策を現在は持たないし、各ドナーもその政策から離れているので、我が国もキリマンジャロ州重点の援助を見直す時期にきていると考えられる。従って、これからは相手国との政策対話を重ね、援助の緊急性と分野のプライオリティを整理し、我が国のタンザニアに対する援助の方向付けを新たに策定することが必要であろう。特に、貧困が全国的問題として存在し、貧困緩和を国全体の底上げとして対処する場合には、ドナー間の連絡を密にし、必要と認められるならば、複数ドナーの協調やNGOとの連携によるアプローチを積極的に策定することも必要であろう。

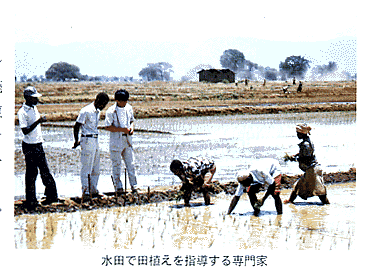
3. 中小企業育成を通じた所得水準向上への我が国協力
(1) 中小企業の振興と所得向上・雇用機会創出
中小企業は、小資本、簡単な技術、ローカル資源の活用で起業が可能である。しかも労働集約型のものが多い。このため、中小企業の振興は、その身軽さ故に、経済発展への、いわば手っ取り早い貢献が期待できる部門である。つまり、個々の貢献は微々たるものであっても、数により経済発展への無視できない存在となり得ることは、インフォーマル部門の活躍を見てもわかる。起業登録していない産業グループをインフォーマルセクターと呼んでいるが、そのセクターの労働人口は、1991年の統計で約2,370,000人(農漁業従事者については都市部のみ)に及んでいる。この中で製造業の従事者は50万人以上である。
また、製造業の付加価値についてみても、表2に示すように、インフォーマルセクターの方がフォーマルセクターを上回っており、この点を見てもインフォーマルセクター(製造業)が所得向上を図る上で重要な貢献をしていることが明らかである。
| (1)インフォーマル | (2)フォーマル | |
| 農漁業(都市部のみ) | 20,447 | 358,693 |
| 鉱業 | 1,159 | 6,975 |
| 製造業 | 29,800 | 20,680 |
| 建設業 | 10,864 | 14,416 |
| 貿易・食堂・ホテル | 104,727 | 83,325 |
| 運輸 | 6,114 | 47,017 |
| コミュニティ/パーソナル・トビス | 10,307 | 3,619 |
| その他 | 0 | 38,811 |
| 計 | 183,417 | 573,536 |
(2) 工業分野における我が国協力の評価
1) 工業セクターの場合、「技術移転」は(1)習得(2)改良(3)普及の三段階に分けられる。
厳密には、これら3段階の前に、技術協力のニーズの発掘及びプロジェクト形成の段階、また3段階の後に事後評価、あるいはフォローアップの段階があるが、上述の3段階が「技術移転」のコアの部分であり、その中でも「普及」が最も重要であると言える。
我が国のタンザニアに対する工業セクターの協力は多くない。有償資金協力プロジェクトは、1966年にカシューナッツエ場が2件、紡績工場が1件あるが、それ以降、実施されていない。技術協力としては、キリマンジャロ州中小工場開発(KIDC)があり、このプロジェクトは、フェーズI、フェーズII合わせて14年半に亘って実施された。フェーズIでは、キリマンジャロ地域総合開発計画事業の一環としてキリマンジャロ工業開発センターを設立し、鋳造、鍛造、機械加工、窯業、オガ炭製造の5分野において最適技術の導入と技術の改良、技術の普及と指導等を実施することにより、同州の中小企業の振興を図ること、フェーズIIでは、フェーズIの協力実績を発展・充実させるべく、工場経営を含む応用技術の移転を図りタンザニア側による自立運営、そしてキリマンジャロ州の中小企業開発に寄与することを目的としていた。このプロジェクトの他に、研修生の受入、専門家の派遣もあるが、KIDCプロジェクトが主な技術協力プロジェクトであるといってよかろう。
2) KIDCプロジェクトの評価
前述した「習得」「改良」「普及」という視点からKIDCプロジェクトを見てみると、本プロジェクトではセンター内における技術移転の「習得」と「改良」の段階は達成されたが「普及」の段階には至っておらず、このため本プロジェクトが最終的に目標としていたキリマンジャロ州の中小企業を振興するまでに至っていない。
本プロジェクトがキリマンジャロ州の中小企業の振興に資することを目標とするならば、R/Dの中で、KIDC内部への技術移転(「習得」「改良」)に加えキリマンジャロ州の中小企業家までの技術移転(「普及」)についても配慮される必要があり、これが欠けていたとしたら、当初のプロジェクトデザインに十分でないところがあったと言えるかもしれない。(注)
また、本プロジェクトのフェーズIIの目的はタンザニア側によるKIDCの自立運営を目指すところにあったが、フェーズII終了後のタンザニア側によるKIDCの自立運営について、現在、必ずしも満足できる状態ではないと思われる。
本プロジェクトのカウンターパートが州政府であったということで、プロジェクト期間中の活動にも制約があった。また、プロジェクト終了後のタンザニア側への移管も、相手がキリマンジャロ州政府であったために、KIDCの維持管理面において同州政府が財政負担をすることになった。もし、国レベルヘの移管が可能であれば、公社・公団の民営化の時期であるため政府からの財政的支援はそれ程期待できないとしても、工業振興機関との合併等、何等かの協調を期待できたかもしれない。
以上のことから、KIDCプロジェクトは「技術移転」「自立運営」の点で課題を抱えているということができる。
(注)JICAの報告書によれば、周辺地域への技術移転に関しては、我が方もフェーズIの頃からタンザニアと協力して普及活動やPR活動を実施していた、とある。
他方、KIDCプロジェクトのプラスの効果については、以下のような点が推定できる。
KIDCのスタッフに限られたこととはいえ、プロジェクト期間の14年半の間に鋳造、鍛造、機械加工、窯業、オが炭製造の技術が移転された。これらの技術によって、農機具、ポンプ、エンジン、テーブルウェア、碍子、オガ炭等が試作、あるいは製造された。それらの技術は時間と共にKIDCの外に普及されていく可能性がある。その意味でプロジェクト期間内にKIDCの外への技術の普及が十分でなかったとしても、やがてキリマンジャロ州だけでなく、他のタンザニアの地域に技術が普及していくことが期待できる。
KIDCプロジェクトの14年半の間に、長期専門家、短期専門家合わせて延べ50名以上が派遣され、ある時は100名以上に及ぶタンザニア人スタッフと共に仕事をし、またタンザニア人35名の研修生が来日したことは、単なる狭い意味での技術の移転だけではなく、我が国の技術に対する考え方、製造に対する考え方、研究開発に対する姿勢等、無形のものの移転もなされたはずである。その価値は極めて大きいものがある。それこそ我が国の経験の移転と言って良かろう。勿論我が国の経験はそのままではタンザニアあるいはキリマンジャロ州に適合しないものもあるかもしれないが、時間を経て、彼らなりに咀嚼して行くに違いない。
(3) 工業セクターへの我が国援助の可能性
1) 中小企業振興への支援
中小工業の振興については、タンザニアの我が国に対する期待は大きい。我が国としてはKIDCプロジェクトの経験から、貴重な教訓を得ることができる。中小企業の援助には様々な内容が考えられる。この中でも、中小企業振興の指導機関への協力がタンザニアにおいても波及効果が期待でき、また中小企業振興の豊かな経験を持つ我が国としても取り組みやすいように思われる。中小企業の振興機関としては、現在タンザニアには全国的な組織としては、農業機械化・農村技術センター(CAMARTEC)がある。この組織は、主として農村向けの適正技術の研究開発試作を行い、さらに地域の中小企業家に技術移転し、中小企業の振興を行うと共に、農村の生産性向上を推進している国の組織である。
前述したような評価あるいはプロジェクト形成の考え方からいうとCAMARTECは始めから「普及」を前提に、「習慣」及び「改良」を一貫して行っている適正技術の開発普及センターである。援助は、全くゼロから出発するものに与えるよりは、自らが自らの力をベースにどうにか運営しているところに与える方が自立心への支援という点で大きな効果が期待できる。その意味で、CAMARTECのような組織の強化のための協力はひとつの可能性として挙げられる。
もうひとつ、必ずしも中小工業のためではないが、機械の設計、部品の設計、さらに試作をしているタンザニア技術製造設計機関(TEMPO)という政府組織がある。タンザニアの工場は、その設備機械の多くを輸入しており、従って部品等も海外からの輸入に頼っていることが多く、TEMPOはそのような部品のデザインから試作、販売まで行っている。また独自の機械の研究の開発、さらには研修サービスをも行っている。TEMPOのような組織の強化は我が国の得意な分野でもある。CAMARTECやTEMPOは例として挙げたが、我が国が援助する場合は、KIDCのように全て新しく組織を作るよりは、既に理想や目標を持ってまがりなりにもタンザニア人の力で運営している組織に対して、しかも彼らの力不足の部分を支援していくという姿勢で援助プロジェクトを形成することが望ましい。
2) 工業振興政策策定への支援 タンザニアは現在、明確な工業開発政策、工業振興策が策定されていない。政策のないところに良い結果は期待できない。我が国は産業振興策、中小企業振興策につき様々な経験を持っている。その経験をタンザニアの工業政策造りに活かすべきであり、あるいは長期にわたる政策については、我が国単独で援助するよりは国連工業開発機関や世界銀行等、国際機関と協同で参加してはどうであろうか。
3) 工業統計整備への支援
統計やデータのないところに有効な政策造りは期待できない。統計整備あるいはデータベース造りへの支援は検討する価値ある分野である。これも、国際機関の経験を活用するという意味においてUNIDO等と協同で実施してはどうであろうか。
4) これらは、工業セクターのインフラ部門、あるいはソフト部門と言っても良いかもしれない。「組織造り」、「政策造り」そして「統計データ造り」等、我が国としては民営化や市場経済化が進められる中で、このような工業インフラや工業ソフト部分に支援すべきである。なお、個々の業種の振興は、特定の業種を除いては市場メカニズムの中にある民間部門に委せることが原則であろう。ここでの特定の業種とは、経済あるいは工業全体にとって重要でありながら、国の指導あるいは誘導がなければ振興できないような業種で、例えば金属加工分野である。金属加工技術の振興は、従来よりその重要性は認識され、公団・公社に設備機械は設置されたが、社会主義体制でありながら必ずしも全体の調整がなされていた訳でもない。個々には経済効率的に稼働しておらず、国全体の金属加工分野の見直しが必要である。
第3章 我が国の対タンザニア援助動向及び援助形態別分析
1. 我が国援助の動向
我が国では、タンザニアが(1)東・南部アフリカ諸国の指導国家として積極的に活動していること(2)構造調整・市場指向型経済政策を着実に推進していること(3)民主化努力を進めていること(4)我が国との関係が極めて良好であること等の理由により、我が国外交の最重点国として位置付け、(1)基礎生活分野(2)農業(3)基礎インフラ(4)構造調整支援(5)人口・エイズを重点分野として取り上げ、積極的な支援を行っている。本章では、各援助形態毎にその援助実績や援助を取り巻く状況について概観し、若干の分析を加えて行くこととしたい。
2. 無償資金協力
(1) ノンプロ無償
我が国では1987年に支援を開始し、1994年度までの累計で120億円のノンプロ無償を供与している。ノンプロ無償については、タンザニアの公的債務残高、総合収支、対日債務の返済額の3項目の評価結果に基づき供与額を決定しているが、タンザニアについては、1993年までは25~35億円の間で安定的に推移していた。しかし、見返り資金の積み立て等において実績が上がっていないこと等から、1994年度の供与については15億円を第一次承認分とし、タンザニアの努力次第で第二次承認分について供与する形態をとっている。タンザニアについては、近年、見返り資金積立委員会を発足させる動きが出る等、前向きに改善を進めてゆこうという動きがある反面、他のドナーの間でもタンザニアの努力に懐疑的なところもあり、今後もタンザニア側へ積極的に働きかけてゆく必要がある。
このように、ノンプロ無償については見返り資金が十分に積み立てられていないという問題や政府のA㏄ountabilityの問題は残っているが、全般的には民間セクターの資本強化や産業育成の観点からは効果的であったと考えるのが妥当であろう。
今後の方向性としては、見返り資金積立実施率の改善や、供与先選定への参画等の改善が考えられるが、いずれにしても積立資金は開発予算の内貨分として極めて貢献度が大きい資金であると考えられるので、今後もこのような協力の精度を上げてゆくことは重要である。
(2) 一般無償資金協力
無償資金協力においては、累積実績でサハラ以南アフリカ地域内一位の実績を持ち、農業分野、保健医療分野を中心に、通信放送分野、交通網整備のインフラ分野等に支援を行っている。近年では首都圏道路交通網整備計画や電話網改修計画等、数次に亘る大型のインフラ整備案件を実施し、市場経済化を指向するタンザニア経済の発展の基盤整備に力を注いでいる。
また、貧困緩和の観点からも、農村地域からの農産物輸送の効率の上昇、コスト低下を目的とした農業輸送力増強計画を実施している他、同国の重要課題であるマラリアの克服のため、我が国では初の試みとして5期に亘るマラリア抑制無償を実施している。
このように、我が国ではタンザニアの開発のネックとなる市場経済化推進のためのインフラ整備に加え、8割を越す農村地域住民の生活改善を目的とした協力を実施してきており、相当の効果があったものと考えられる。
(3) 草の根無償資金協力
タンザニアでは、1989年度に供与されて以来、1994年度までの累計で17件を実施している。
タンザニアにおいては、草の根無償の効果的実施を図るため、同種の援助プログラムを有する他のドナー国の大使館の担当官による会議を1994年にスタートさせており、これまでに数回の会合を開催している。同会議では、供与を避けた方がよい団体に関する情報交換等を実施しているとのことであり、我が国としてもこのような会合への積極的参加が必要となろう。
草の根無償については、現状の我が国大使館の体制では、人員的にも事前に十分な調査を行った後に供与するという訳にはゆかず、いきおい資金力があり、実績のあるNGOへの供与が増えてしまう傾向は否めない。
他の援助スキームとのコーディネーションについては、場合に応じプロジェクトや個別派遣専門家、青年海外協力隊員への効果的なサポートとして活用することは考えられよう。協力隊員のネットワークを活用することも検討に値する。
3 技術協力
(1) プロジェクト方式技術協力技術協力全体としては、サハラ以南アフリカ地域内2位の援助供与国である。プロ技の多くはキリマンジャロ州に集中しており、キリマンジャロ州開発公社にも個別派遣専門家が赴任している。キリマンジャロ州には無償、有償、技術協力が一体となって実施した農業開発案件があり、大変大きな効果をあげている。カウンターパート配置問題については、我が国援助では人件費をサポートしてまでカウンターパートを確保することは原則として行っていないが、これはタンザニア側の自助努力の原則からも、今度とも継続して良い基本的な認識であると考えられる。
ローカルコスト負担については、多くの国と同様、タンザニアにおいても大きな問題となっている。
各国の数多くの協力、そしてタンザニア政府の財政状況を考慮すると、ローカルコストの負担についてタンザニア側の充分な理解を得られないまま大型の協力を投入することは効果的とは言い難い。それ自体は効果的なプロジェクトであっても、タンザニア側への財政負担が極めて大きくなる可能性がある。今後は、プロ技を実施する場合には、ニーズが高く、事前調査でタンザニア側の負担能力にっき十分調査を行った上で、ある程度のローカルコスト負担を覚悟しつつ協力をしてゆく必要があろう。また、専門家チーム派遣(ミニプロ)や個別専門家の効果的活用をさらに図っていく等の検討も必要であろう。
(2) 個別専門家派遣及び研修員受入
首相府の経済顧問いわく「いくらinvestmentがあっても、それを維持させるinstitutionが無ければ効果は発現しない」。このためには、個別専門家の役割は大きいと考えられる。そこでは、技術的な側面はもちろんのこと、意識改革的な側面での貢献も含まれる。この背景には、タンザニアが植民地時代から独立を通して、自らマネジメントし、責任を果してゆくという考え方が低下したということがある。
その側面では、研修員として我が国で受け入れることのみならず個別派遣専門家を様々な分野に派遣し、違った考え方に触れる機会を提供することは重要であろう。その観点からは、我が国の過去の個別専門家派遣はその技術そのものの移転のみならず、大きな成果をあげているものと考えられる。他方で、各国ドナーも多くのアドバイザーを各省に投入しており、重複を避ける等の配慮は必要であることは言うまでもない。
(3) 青年海外協力隊
協力隊員については、1994年までの累計で766名が派遣され、草の根の協力形態としてタンザニア側に高く評価されており、今後も活躍が期待されている。他方で草の根の開発ニーズや開発ノウハウ、タンザニアの文化風習等、通常の調査では把握困難な情報については、協力隊員が有しているケースも多く、我が国援助案件選定時に十分情報を吸収するようなシステムが必要となろう。
その他に、協力隊OBの活用も効果的であると考えられる。現地語が話せて、ある程度草の根のニーズや行動様式を把握している協力隊OBを専門家として登用することは効果的であると言えよう。
また、協力隊が展開している緑の協力推進プロジェクトは、首都移転を含めた開発計画の一環として実施されている事業であり、首都開発公団の事業予算が不足している中で、我が国援助が着実な成果を上げているものと評価できよう。このようなプロジェクト型の協力隊派遣事業は、大変効果が高いものと考えられる。
4 開発調査
開発調査については、1969年度より実施しており、農業分野をはじめ運輸交通、エネルギーなどのインフラ整備等、幅広い分野で実施してきた。現在までに28件を実施済である。その中でも、特に地域総合開発調査は大変重要であると言える。現在までに地域総合開発調査として実施されたのは、70年代のキリマンジャロの総合開発のみであるが、その結果、モシで効果的な援助が実施されたことからも、今後も同様のニーズがあると考えられる。特に、貧困の緩和への協力については、(1)地域の特性への配慮(部族の風習、地形、産業、生産物等)(2)包括的、クロスセクター(農業、教育、保健医療、基礎インフラ、中小工業等)アプローチ(3)最終受益者を念頭に入れた協力(4)他の援助機関との連携、といったことが極めて重要になってくるため、開発調査による総合開発計画の策定は重要であると言えよう。
5 有償資金協力
有償資金協力は1994年度までの累計で387億円を供与しているが、債務繰り延べを除き、1982年以降供与されていない。これは、タンザニアが債務削減措置が執られている状況に鑑み、新規円借款については慎重に検討していくとの我が国方針によるものである。
第4章 総合評価
1 我が国援助の総合評価
(1) 1967年から社会主義開発線路を選んだタンザニアは1980年代初頭に深刻な経済危機に直面した。その解決を求めて1980年代半ばから構造調整計画を行って市場経済の導入による民間部門主導型の経済体制へ移行を図り、1990年代に入り複数政党制の民主的政体への移行を模索している。我が国はタンザニアをアフリカ地域における重点国と位置付けたうえで政府開発援助を続けてきており、タンザニアにとって我が国の援助は不可欠なものとなっている。
タンザニアは我が国のアフリカ外交における最重点国として位置付けられてきたが、今後もこの関係は続けられるべきである。これまで要請主義に基づいて基礎生活分野、農業、基礎インフラ、構造調整支援および人口・エイズ対策を重点として行なってきた政策は正しかったといえる。しかしこれらの援助案件の策定並びに実施はタンザニアが移行経済局面に入る前になされたものであり、現在及び将来のタンザニア支援には新たな視点が模索されねばならない。
タンザニアでは1996年初頭を目処に、タンザニア人のみで、2015年までの開発計画と戦略を策定する計画があり、方向性としては非常に前向きで、タンザニア人の自立への決意として高く評価できる。これに対し我が国はまずタンザニアの移行経済局面の本質を明確に把握し、タンザニアが策定する開発のビジョンに積極的に聞き入るべきであろう。そのビジョンが構想する短期的開発問題と長期的開発問題とを識別し、短期的には経済安定化と制度政策改革とに直接関連する政策的支援とを強化し、長期的には市場経済の基盤整備形成を通じての貧困緩和に貢献する戦略的援助を策定することが望ましい。この長期的戦略的援助の三つの要になるものが「人造り」であり、「制度造り」であり、「運輸・通信のインフラ造り」であるといえよう。
過去の支援の効果を数量的に計測することは困難であるが、とりわけ道路リハビリ援助は確実にタンザニア国民の間に高い評価を得ている。雨期に泥棒のあふれるダルエスサラーム市の最大の卸流通センター周辺はトラックやピックアップのような輸送手段をもたない零細業者は極めて困難な状況におかれていたが、道路修復により営業が容易になった。モロゴロ道路の補修はその沿線に無数の路上店舗の輩出をもたらし、貧困者層の買い物の中心地の一つとなった。道路インフラ基盤整備支援が間接的ながら貧困対策としての効果をもっていたといえる。さらにこれらの道路リハビリ援助は建設の段取りから建設機材の使用にいたるまでタンザニア人の訓練を同時進行で行った結果、効果的な技術移転の成功例ともなっている。
KR関連援助、特に2KRはキリマンジャロ州における食料生産に多大の効果をもたらした。今後の課題は2KRの使途を地域集中的なものから全国的なものへと拡大することであろう。
キリマンジャロ農業開発センターやキリマンジャロ工業開発センターはタンザニア側の自主管理がうまく機能していない。過去に常にローカルコスト負担の不履行が問題となっていた。加えてタンザニア政府の財政赤字改革政策の結果、これらの機関に対する資金手当が不十分になり職員の俸給すら遅配する事態となっている。根本的にはタンザニア側の行政能力の弱体が原因であるが、今後の援助においては相手国の行政能力を超える規模での組織を必要とするような大型プロジェクト支援には慎重であらねばならない。
我が国はタンザニアに対し30年以上協力してきたが、マクロレベルで評価し得る定量的・定性的インパクトを認めることは前述したように困難であった。実際、マクロ経済指標に顕著な成長が見られないことから、我が国のみならずタンザニアの援助に関わった多くのドナーもマクロレベルでの評価に困難を感じているのが実状である。
我々は従来はタンザニアに関する経験や知識が不足していると考えてきた。もちろんそれは決して十分ではないが、我が国がタンザニアに派遣した766人に及ぶ青年海外協力隊員や多くの派遣専門家の経験の累積を過小評価してはならない。さらに人類学を含めた社会科学の分野でも我が国の研究者による業績は質・量ともにかなり大きくなっている。今後の対タンザニア援助の実施にあたり過去の経験や知識を十分に利用する体制を整えることがわが国の重要課題であるともいえる。
2 LDCにおける効果的な援助形藩―対タンザニア援助評価を通じて―
(1) 援助の意義再確認
タンザニアは世界最貧国の一つとして、今後も重点援助対象国であり続けようし、その産業構造からすると中長期で見ても順調な経済成長が望める国とは言い難い。対タンザニア援助の意義についてこの機会に再考することは非常に重要であろう。我が国にとって援助の便益、例えば市場として成長するとか、稀少資源を有しているとか、地政学的に重要であるといった意味あいの薄い国への援助は人道主義的色彩が強くなってくる。人道主義と国力に応じた援助責任以外の理由付けを再確認するために、サブサハラ最貧諸国の中でなぜタンザニアが重点国であり続けるか、ニエレレ時代からは数度の政権交代を経ながら、また周辺諸国では南アの民主化やルワンダ、ブルンジの内乱といった様な政治環境の変化があり、タンザニアの立場や役割などを確認する必要があるといえる。
(2) 援助対象地域と地域間格差の問題
地域間格差の緩和・是正はタンザニアにおいてのみならず、地域開発の大きなテーマであるが、サブサハラの最貧国群の経済規模からすると、各国地域内である程度の都市(市場)集積を促すことは重要である。タンザニアはダルエスサラーム及びザンジバルの都市集積を拡張すべく、ドドマに首都移転を計画したり、各州の開発計画を援助国、機関に依頼して開発を進めてきた。我が国もタンザニア側の意向を重んじキリマンジャロ州に援助資金を傾斜配分し農・工業案件を進めてきた。キリマンジャロ州への傾斜配分は本当にキリマンジャロ州地域開発に資したのか真摯に再考されねばならない。
(3) プロジェクトの選択
一般的には「政府援助大綱」「国別援助方針あるいは政策対話の結果」「相手国の国家開発方針」を満たしていることは最低の条件となるがそれ以外にも次のような選択のための前提条件が考えられる。
・援助期間内に技術移転が完結できるように配慮されていること。
特にLDCにおいては相手国の技術水準を考慮し、技術移転に十分な期間が配分される必要がある。従ってLDCにおけるプロジェクト方式技術協力については長めの期間設定と、移転技術項目の厳選が前もって準備されるべきであろう。
・実施に当たり相手国に組織的、人的、財政的に援助受け入れ能力があること。
プロジェクトがスタートしてから、相手国あるいはカウンターパート側で予算措置とか十分な人的配置が出来ない場合がしばしばあるので、特にLDCでは日本側の事情だけでプロジェクトの資金規模を決めるのではなく、相手国の財政負担能力に応じたプロジェクト規模でスタートすることも重要である。
・援助終了後において、相手国独自で組織的、人的、財政的に維持管理能力の確保が可能であること。特にプロジェクトマネージャーの管理能力は非常に重要であり、援助終了後もプロジェクトに対し強くコミットするような責任感のある人材を育成することが最も重要である。さらには、財政基盤が弱くなることを想定した、民営化のシナリオや、規模縮小後の有効な存続方法についても前もって検討されるべき課題であろう。
また、案件発掘に関しては現地政府のみならず、現地研究機関や地域の草の根レベルの情報に通じているNGO、ローカルコンサルタントの活用なども役立っであろう。
(4) 要請主義
タンザニアのような独自の中長期産業政策がない国において要請主義を貫くのは難しく、このような国に援助プロジェクトの優先順位をつけさせても、政治や権力が1順位に現れてきたり、他の援助機関(世銀やUNDP)の開発メニューの写しが現れてくる可能性が高い。従って、援助側の責任としてタンザニアの産業構造変化をある程度予測し、産業開発の方向付けについて適宜両者の合意のもと開発援助プロジェクトは進められるべきである。この点でタンザニア・ドナー間の調整や政策対話はさらに積極的に、これまで以上に日本のイニシアチブのもとに進められるべきではないだろうか。
(注)1997年3月にタンザニアに経済協力総合調査団及びプロジェクト確認調査団を派遣した際、右政策対話において、日本側のイニシアチブによりドナー会合等が実施された。
対タンザニア援助は他の援助国にとっても人道援助の意味が強く、それ以外の理由はあまり見つからない。また、各国の援助予算が削減されている中で日本の対タンザニア援助が持つ意味は大きくなる一方である。従ってタンザニア政府内のみならずドナーコミュニティの中で議論に耐えるようなタンザニア産業開発政策を提言することは非常に重要で、また日本が自ら踏襲すべき援助指針を得るためにも是非とも早急に実施されるべきものである。
(5) 貧困緩和
貧困緩和は非常に重要なテーマでタンザニアのように国民の半数以上が貧困ライン以下の生活を維持している地域では人道的にも重要な意味を持つ。但し貧困緩和はあくまでも市場経済化支援と、経済規模の拡大、都市化、都市機能の集積を通じて進められるべきであり、貧困地域にスープキッチンと臨時居住用のシャックを建設するような方向へ進むのは考えものである。
タンザニアのみならずサブサハラ地域おけるインフォーマルセクターの役割は非常に大きく、これは体制の如何に関わらず大きな役割を果してきている。市場経済化というよりも経済の活性化のためにはインフォーマルセクターへの参入を促し、その分野での蓄積を活用しつつフォーマルセクター化できるような方策の支援は望まれるところである。
(6) 見返り資金の積み立て
見返り資金については世界中のノンプロ無償、2KRの受入国で不明瞭になっている。
タンザニアにおいても先に実施されたノンプロ無償評価報告によると、公社公団関係の見返り資金の流用、特に職員人件費や会議費などへの流用が指摘されている。エンドユーザーがノンプロ援助で購入した物資によって生産活動を行いそれによって得られる利潤が見返り資金として積み立てられることから、援助資金の支出から実際の見返り資金積み立てまで、多少の時間的ギャップが生じることは認められる。しかし見返り資金はあくまで中央政府で管理され開発予算として再投資されるものとして両国政府とも合意のもとの援助であることから、この問題に関しては厳重に注意が払われる必要がある。他の援助国に比べると日本の見返り資金積立義務率は低く、またなんらのペナルティーも課されていない。従って、早急に積み立て状況に関する監査組織の設置、そのシステムの構築、義務率の上昇、ペナルティー措置の実施などが進められるべきであろう。
他方、これだけ見返り資金が積み立てられないのは積み立て方法自体に無理がないか確認する必要がある。ノンプロ無償や2KRの援助物資を取り扱う機関は限られており、その売却の状況や資金の動きを追うのは関係者が意図的に流用していないとすれば、大きな問題とはならないはずである。見返り資金は年間数億円規模にもなるもので、積み立て状況の管理については第三者機関に委託するなどして厳密に取り扱われなければならない。
(7) 市場経済化支援
日本にとってタンザニアのみならず市場経済化支援は重要なテーマであるが、ノンプロ無償に巨額の援助資金をさいてきだわりにはそれ以外に明示できるものは特に無く、今後ノンプロ無償以外でタンザニア側の産業構造変化に直接資するようなにプロジェクトを進めて行くべきである。
例えば市場経済化支援を民間活力の導入と民間セクター自身の活性化中心に進めていくためには、民間セクター間接支援となるようなプロジェクトが期待される。例えば、業界団体活動や調査研究事業といった経営管理指導の実施受け入れ機関となる組織、財団の設置を促進する。また、民営化か予想されるような国営事業に関しても、民営化を促進するような技術協力などは進められるべきである。

