第5章 評価結果
本章では、わが国のガーナ教育セクターにおけるODA事業の集合体を、第1章で示した評価の枠組みに従って、「目的」、「プロセス」、「結果」の3つの視点から総合的に評価を行う。なお、本評価にあたり、ガーナ教育セクターにおけるわが国のODA事業を概観して、「目標体系図」(後述)にとりまとめ、「目的」と「結果」の評価ツールとして活用していく。
5-1 目標体系図
本評価調査は、セクターレベル評価と位置づけられる。セクターレベル評価では、対象セクターにおけるODAの集合体を、できるだけ総合的に評価することが求められる。そのため、本評価では、評価対象案件を概観して、それらの協力がどのような活動をして何を目標としていたのか、また相互にどのような関係があるのかを検証した。その結果、わが国のODA事業が目指していたものは、図 8のように整理された。これを、目標体系図Aと呼ぶ。以下、この目標体系図Aについて簡単に説明する。

わが国のガーナ教育セクターにおけるODA事業の主な案件は、目標体系図Aの「投入案件」の欄に示したとおりである。これらの案件がどのような活動をして、何を目標としていたのかを確認したところ、大きく分けて、基礎教育に関する「成果1」~「成果3」と、ポスト基礎教育に関する「成果4」~「成果7」に整理することができた。
また、基礎教育に関するこれら3つの成果は、相互に関連しながら、「すべての子どもが質の高い基礎教育を受けられるようになる」という中期的な目標の下に実施されていたとみることができる。他方、ポスト基礎教育に関する4つの成果は、「産業に不可欠な人材養成の基盤を拡充する」という中期的な目標の下に実施されていたとみることができる。
さらに、これらの2つの中期目標は相互に影響し合いながら、10年以上の長期的なスパンで「ガーナの社会経済開発を担う人材を育成する」という大きな目標に向かって実施しているとみることができよう。
以上、わが国のODA事業の集合体はこのような目標をもって、相互に関連しあいながら実施されてきたと整理することができる。以下、この目標体系図Aを評価ツールとして活用していく。
5-2 目的
(1) 日本のODA基本政策との整合性
1)政府開発援助大綱(ODA大綱)と政府開発援助に関する中期政策(中期政策)との整合性
評価対象期間においては、わが国のODA事業は、ODAの基本政策である「政府開発援助大綱(以下、ODA大綱)」とその中期的な政策である「政府開発援助に関する中期政策(以下、中期政策)」の下に実施されてきた(図 9)。そこで、まず最初に、日本のガーナ教育セクターにおける協力(目標体系図A参照)が、これらの基本政策に沿っているかどうかを確認していく。
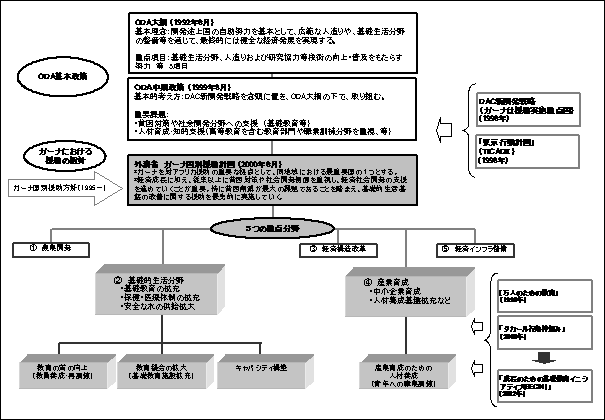
1992年6月に策定されたODA大綱82では、開発途上国の自助努力を基本として、広範な人造りや、基礎生活分野の整備等を通じて、最終的には健全な経済発展を実現することを基本理念として掲げている。また援助の「重点項目」として、1)地球的規模の問題への取り組み、2)基礎生活分野等、3)人造りおよび研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力、4)インフラストラクチャー整備、5)構造調整等、の5項目を挙げている。これらの内容は、人造りの上で、教育、特に基礎教育の重要性を謳ったものである。従って、日本がガーナにおいて教育セクターへの包括的な協力を実施していることは、これらODA大綱の理念、方向性とも合致しているといえる。
日本政府は、さらに1999年8月に「中期政策」を策定した。これは、ODA大綱の理念・原則等に則り、内外の情勢をかんがみて、より効果的かつ効率的な援助を推進することを目的とし5年程度を念頭におきODAのあり方を示したものである。この中期政策は、わが国がその策定に主導的な役割を果たしたDAC新開発戦略用語(1996年)を踏まえて、新しい援助の方向性を明示した点が特徴である。中期政策では、DAC新開発戦略を踏まえ、他の援助国や国際機関との協調・連携の強化、パートナーシップ構築に努めていくことを、基本的考え方としている。ガーナ教育セクターにおいては、他の開発パートナーと協調しながら、セクター・プログラムを支援してきており、この基本的考え方に沿ったものとなっている。
また中期政策では、従来以上に貧困削減や社会開発の側面および人材育成等ソフト面での協力を重視するとしている。そして具体的な「重要課題」として5つの課題を設定しているが、その一番目に“貧困対策や社会開発分野への支援(基礎教育等)”を挙げ、さらに三番目に“人材育成・知的支援(高等教育を含む教育部門や職業訓練分野を重視、等)”を挙げている。日本がガーナの教育セクターに対して、基礎教育・ポスト基礎教育・職業教育訓練・高等教育まで幅広く協力を展開し(図 8参照)、特に2000年以降は基礎教育に重点をおいてきたことは、中期政策で設定した重要課題とも整合している。
さらに中期政策では、「地域別の援助のあり方」を示しているが、その中でアフリカ地域に対しては、1998年の「第2回アフリカ開発会議(TICAD II)」において策定された「東京行動計画」の具体的実施を求めている。「東京行動計画」では、基本原則として、アフリカ諸国自身のオーナーシップと国際社会のパートナーシップの重要性を提唱している。その中で具体的な行動計画として、「社会開発と貧困削減」を優先分野とし、中でも教育開発を加速させる必要があるとしている。対ガーナ教育セクターにおける日本の協力は、東京行動計画を十分に踏まえて実施されており、中期政策の方向性と合致しているといえる。
以上みてきたように、日本の対ガーナ教育セクター支援は、日本のODA大綱や中期政策と、理念、方向性において整合しており、妥当であるといえる。
2)対ガーナ国別援助方針・国別援助計画との整合性
わが国のODAではODA大綱と中期政策の下、国別の援助指針が策定されている。ガーナに対する日本の援助指針としては、1995年に策定された「ガーナ国別援助方針」(1995~1999年版)と、2000年の包括的な政策協議をもとに策定された「ガーナ国別援助計画」がある。以下、対ガーナ教育セクターにおける協力(図 8参照)が、これらの指針に整合しているかどうかを確認していく。
わが国は、1995年3月に経済協力総合調査団を派遣し、それまでのガーナにおける開発の現状と課題に関する調査・研究結果、およびガーナ側との政策対話等を踏まえて、ガーナ国別援助方針を策定した。以後、毎年、現地の情勢の変化に応じて改訂されているが、基本的な原則、方向性は継承されている。すなわち、1995~1999年のガーナ国別援助方針では、「わが国の援助の重点分野」として、1)「基礎生活の向上」、2)「農業」、3)「道路・電力」の、3つを設定している。この1)「基礎生活の向上」において、貧困問題解決のための基礎造りとして基礎教育の充実を掲げている。この時期においては、基礎教育への直接的な援助は実施されていないが、1996年のガーナ側の「基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム(fCUBE)」支援の要請を受けて、1997年から小中学校を対象とする技術協力プロジェクト「ガーナ小中学校理数科教育改善計画」(以下、技プロ)の案件形成を始めており、同援助方針を反映した展開となっている。
その後、2000年5月に政策協議(対ガーナ経済協力政策協議)が実施され、より包括的な国別援助指針である「ガーナ国別援助計画」83が2000年6月に策定されている。このガーナ国別援助計画は、中期政策を踏まえており、従ってDAC新開発戦略やTICAD IIの東京行動計画を反映したものとなっている。
同援助計画では、日本はガーナを対アフリカ援助の重要な拠点とし、同地域における最重点国の1つとして援助していく方針を打ち出している。また「わが国援助の目指すべき方向」として、「経済成長に加え、従来以上に貧困対策や社会開発側面を重視し、経済社会開発の支援を進めていくことが重要。特に貧困削減が最大の課題であることを踏まえ、基礎的生活基盤の改善に関する援助を優先的に実施していく」としている。
さらに、ガーナ国別援助計画(図9)では、「重点分野」として1)農業開発、2)基礎的生活分野、3)経済構造改革、4)産業育成、5)経済インフラ整備、の5項目を定めている。このうち、2)基礎的生活分野の中に「基礎教育の拡充」が明記され、4)産業育成の中で「人材養成基盤拡充」が盛り込まれている。
他方、わが国の協力は、目標体系図A(図 8)にみるように、長期的目標「ガーナの社会経済開発を担う人材を育成する」の達成のために、教育セクターを支援しており、特に基礎教育(中期目標1)とポスト基礎教育(中期目標2)を重点的に支援していることから、前述してきたガーナ国別援助方針やガーナ国別援助計画の、目標や重点分野と合致しているといえる。
なお、ガーナ国別援助計画では、これらの政策的方向性に加えて、「援助実施上の留意点」として3)援助受け入れ体制・能力の強化、2)債務問題への対応84、3)セクター・プログラム・アプローチ、4)南南協力推進85、の4点を指摘している。これら「援助実施上の留意点」が援助実施中に考慮されてきたかどうかは、5-3「プロセス」の「(1)策定過程における妥当性」の「1)協力の発展プロセス」の「4)日本の協力全体としての方向性」および5-4「結果」の「(1)有効性」の「1)ドナー全体における日本の位置づけ」で検証する。
3)日本の教育支援策「BEGIN」との整合性
2002年6月、日本政府は新たな教育支援策として、「成長のための基礎教育イニシアティブ(Basic Educatiion for Growth Initiative:BEGIN)」用語(表 21)を発表した。このBEGIN発表は本評価対象期間のかなり後半であり、それとの整合性を厳密に検証してもあまり意味がないという見方もあるが、現在および今後のガーナにおける教育セクター協力の方向性を考える上でBEGINと整合しているかどうかをみることは重要な視点と考え、ここで確認しておきたい。
BEGINは、1990年の「万人のための教育に関する世界会議」用語で国際的な目標となった「万人のための教育(FEA)」や、2000年の「世界教育フォーラム」用語で採択された「ダカール行動枠組み」用語など、教育セクターにおける国際的な援助潮流や日本の援助経験などを踏まえて策定されている。その構成は、表 21に示すように、「支援に当たっての基本理念」、「重点分野」、「わが国の新たな取り組み」の3つの枠組みからなされている。以下、この3つの枠組みごとに、日本の対ガーナ教育セクター協力を照らし合わせていく。
| 1. 支援に当たっての基本理念 |
| ||||||||||||
| 2. 重点分野 |
| ||||||||||||
| 3. わが国の新たな取り組み |
|
|
注:太字はガーナにおいて、特に実践していると考えられる部分。 出所:外務省『2002年版政府開発援助白書』。 |
まず「支援に当たっての基本理念」であるが、これは表 21にみるように、6項目が挙げられている。基本理念(1)~(3)は、前述したODA大綱や中期政策の基本的理念であり、ガーナにおいても十分尊重されている。特に、(1)と(3)は、現在の教育セクター協力の基本姿勢が、オーナーシップとパートナーシップであることから、高い整合性を示しているといえる。(4)の「地域社会の参画促進と現地リソースの活用」に関しては、技プロにおいて現地の教員養成校を活用するなど配慮されている。また、(6)の「わが国の教育経験の活用」は、「わが国の新たな取り組み」で後述するとおり、特に基礎教育における協力を開始して以来、積極的に実践されている。ただし(5)の「他の開発セクターとの連携」は、今回の評価調査では特に確認されなかった。
次に「重点分野」についてみていく。ここに挙げられている項目(7)~(9)は、基本的に目標体系図A(図8)の、中期目標1(基礎教育)の成果1~3と一致している。特に(8)「教育の『質』向上への支援」は最重点分野となっており、整合性は高い。ただし、細かいレベルでみれば、(7)の2)「ジェンダー格差の改善のための支援」、3)「ノンフォーマル教育への支援(識字教育の推進)」、4)「情報通信技術の積極的活用」はガーナでは実施されていない。また(9)の2)「教育行政システム改善への支援」については、技プロによって副次的に支援されている程度である。
3番目の「わが国の新たな取り組み」であるが、ここに挙げられている3項目のうち(12)はガーナにおいては該当しないため、(10)と(11)をみていく。(10)の「現職教員の活用と国内支援体制の強化」については、技プロ専門家への現職教員の活用や、プログラム的支援における大学コンソーシアムの構築など、ガーナにおける協力の大きな特徴(4章の4-2(2)1)参照)となっており、積極的に取り組まれているといえる。また、(11)「国際機関等との広範囲な連携の推進」については、中期政策(5-2(1)1))のところでも述べたとおり、積極的に推進しているところである。
このように、これまでの対ガーナ教育セクター支援は、日本の新たな教育支援策であるBEGINとも概ね整合して実施されてきているといえる。しかし、BEGINが発表されてから2年弱しか経過しておらず、これまで取り組まれてこなかった部分に関しては、今後の検討課題である。
以上みてきたように、これまでのガーナにおける教育セクター協力は、日本のODA大綱や中期政策などのODA基本政策および新しい教育支援策であるBEGINとも、ほぼ整合しており、妥当であると判断することができる。
(2) ガーナの開発政策との整合性
1)ガーナの国家開発計画(Vision2020とGPRS)との整合性
ここでは、ガーナの国家開発計画と、日本のガーナ教育セクターにおける協力との整合性を確認していく。最初に、ガーナの国家開発計画を、2章の2-5国家開発計画や3章の3-1教育政策と重複する部分もあるが、再度、時系列で総合的にみていくこととする。
図 10の下方部に、ガーナの国家開発計画を時系列に整理した。この時系列図にみるように、ガーナ政府は1995年に「長期国家開発計画(Vision2020)」を策定し、「2020年までに中所得国家の生活水準に達成すること」を目指し、「全国民の参加による経済成長」を目標に掲げた。この目標の達成のために、すべての国民に対して適切な教育を提供することを強調している。
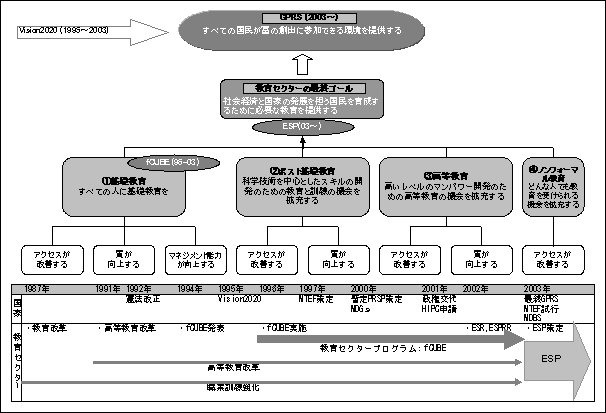
続いて、2001年に誕生したクフォー政権も、基本的にVision2020の目標を踏襲しつつ、「経済成長による富の創出およびその平等な分配を通じての貧困削減」を最終ゴールとする「ガーナ貧困削減戦略(以下、GPRS)」を2003年に策定した。現在、これがガーナの国家開発計画となっている。GPRSでは、5つの優先課題、1)インフラ整備、2)農村開発のための農業近代化、3)保健・教育を重視した社会サービスの強化、4)グッド・ガバナンス、5)民間セクター育成、を設定し、教育を優先課題とすることを示している。また、GPRSでは2000年8月の国連総会で決定されたミレニアム開発目標(MDGs)用語を政策目標として取り込んでおり、教育セクターにおける数値目標(BOX 9)も明記されている。このように、GPRSにおいては、“国造りは人造り”という理念のもと、教育セクター重視の姿勢を明確に打ち出している。
以上のようなガーナの開発計画に対して、日本としても目標体系図A(図 8)にみるように、長期目標として「ガーナの社会経済開発を担う人材を育成する」ことを掲げ、積極的に教育セクターを支援しており、その目指すところは妥当であったといえる。
| BOX 9 ミレニアム開発目標(MDGs)における教育分野の数値目標 ・2015年までに初等教育の完全普及 ・2005年までに初等教育におけるジェンダー間格差解消 ・2015年までにすべてのレベルの教育において男女均等の機会を確保する |
2) ガーナ教育セクターにおける開発計画との整合性
ガーナの教育セクターにおける開発計画は、1987年の教育改革以来、教育開発における世界的潮流や開発パートナーの援助動向を反映する形で、変遷している。ここで、ガーナ教育セクターの開発計画を、再度時系列図(図 10下方部分)を参照しながらみていくこととする。
ガーナでは1987年に広範な教育改革を実施し、現在の6-3-3制を導入した。この際、従来のアカデミック偏重の教育から実用的な教育への転換を目指して、技術職業教育の拡充を打ち出し、中学校のカリキュラムの中に職業教育科目を取り入れるなど、技術職業教育の整備・拡充の模索が始められた。これに続いて、1991年に高等教育改革を打ち出し、高等教育へのアクセスの拡大に着手した。さらに、翌1992年には1990年の「万人のための教育」世界宣言を取り入れる形で、憲法が改正され、この中で基礎教育の義務化・無償化の理念が謳われた。これが、1996年のfCUBEの実施につながっていく。その後は、基礎教育の拡充を最大の開発課題としながらも、高等教育機会の拡大が細々ながら実施されてきた。しかし技術職業教育については、国の意向とは裏腹に学生のニーズは普通科高校から大学への進学であり、技術職業教育を受講する学生の数は増えず、サービス提供体制の整備もほとんど進まなかった。
これに対して、1990年代後半の開発パートナーの動向としては、ほとんどのドナーがfCUBEへの支援、つまり基礎教育支援に集中した。その結果、前述したように、基礎教育以外のサブセクターの整備はほとんど進まなかった。この頃、fCUBEを支援する世界銀行やDFIDなど影響力のあるドナーが中心となって、コモンバスケットを伴ったセクター・ワイド・アプローチ(SWAP)用語の構築を模索する動きが始まる。しかし、ドナー間の調整が難航し、調整疲れが見られるようになり、結局、2000年までSWAPの構築に至らないままに終わる。ところが、2001年のクフォー政権誕生によって新しい風が吹き、クフォー大統領の技術職業教育訓練(TVET)の強化や就学前教育の導入という意向を踏まえ、教育セクター全体を包括的に取り入れたSWAP構築の気運が、再びドナー間で高まってくる。その最初の一歩が、「教育セクターレビュー(ESR)」や「教育セクター政策レビュー(ESPRR)」の実施であり、この実施には多くのドナーが支援した。この後、全開発パートナーの参加によって教育セクターにおけるSWAPの策定が進み、2003年5月に教育SWAPである「教育戦略計画(ESP)」が完成した。ESP策定後最初の拡大ドナー会議となった2003年11月の会議では、ESPの本格的な実施に向けて全開発パートナーが力を合わせていくことが再確認された。
これらの変遷から、1987年以降、ガーナ側が教育セクターにおいて目指してきたものをまとめたのが、「ガーナ側 教育セクター開発課題体系図」(図 10の上方部分)である。まず、1987年の教育改革で1)2)3)の枠組みが確立した。さらに、1991年の高等教育改革で3)が推進された。続いて1992年の憲法改正を踏まえて1996年からfCUBEによって1)が重点的に進められてきた、と整理することができる。その後、クフォー政権の誕生によって、2)の重要性が再認識され、教育セクターを包括的に開発していくためのESPの策定が進められた。その際、GPRSの目標でありかつESPの最終ゴールである「社会経済と国家の発展を担う国民を育成するために必要な教育を提供する」を達成するために、“すべての国民の参加”を重要視し、4)のノンフォーマル教育のサブセクターも盛り込まれた。以上の変遷を経て、現在3)~4)の開発課題がESPに取り込まれている、と整理することができる。
このようなガーナ側の教育セクターにおける開発課題に対して、わが国は1998年から2000年までは、目標体系図A(図 8)に示したように、中期目標2のポスト基礎教育と技術職業訓練を中心として協力してきた。その後、fCUBEに対応するため2000年に技プロが開始されると、中期目標1の基礎教育への協力が積極的に推し進められるようになった。このように、振り返ってみると、日本の協力はガーナ側の教育セクターの開発課題に対応することによって、結果的に、他ドナーが基礎教育に集中している時代から、今日のガーナ教育セクターの開発課題の1)~3)に対して広く、先行する形で支援してきたとみることもできる。
このように、これまでのわが国のガーナ教育セクターにおける協力は、ガーナの開発計画と整合しており、妥当であると判断することができる。
3)ガーナ国家開発体系と援助モダリティの急激な変化
これまでみてきた「目的」に関する評価は、2000年に策定されたガーナ国別援助計画に基づいている。しかしながら、2章で詳述したように、2000年以降、ガーナにおいては、政権交代、拡大HIPCイニシアティブ用語申請、GPRSの策定といった大きな政策的変化が生じている。さらに、ドナーコミュニティの援助戦略においても、MDGsによる目標値設定、セクターごとのSWAP策定の加速、GPRSと中期支出枠組み(MTEF)用語の連動、セクターを支援するコモンバスケット方式から一般財政支援方式(MDBS)へのシフト、など目まぐるしい変化が生じている。
2004年1月からは、国家計画(GPRS)と財政(MTEF)および各省庁の行財政(SWAP)が一体化した、新しい総合行財政システムが始動した。各ドナーの援助モダリティも、ガーナ側のオーナーシップを尊重する意味から、一般財政支援(MDBS)へと大きくシフトしつつある。従って、今後は教育セクター協力を考える際にも、このようなガーナの開発体系や援助モダリティを抜きには考えられない状況にきている。日本の今後の教育セクター協力を考える前提として留意すべき点である。
以上、「目的」という視点から、「日本のODA基本政策との整合性」と「ガーナの開発政策との整合性」の2つの評価項目で評価してきた。その結果、ガーナの教育セクターにおけるこれまでの日本の協力は、日本側およびガーナ側の上位政策と概ね整合しており、妥当であると判断することができる。ただし、ガーナ開発体系や援助モダリティは急激に変化しており、教育セクター協力においてもこれらの変化への対応をあらためて検討する時期にきているといえる。
5-3 プロセス
(1) 策定過程における妥当性
1)協力の発展プロセスの適切さ
日本の対ガーナ教育セクター協力は、その案件策定の背景において日本の援助戦略やガーナ側の開発政策などを反映しながら、また個々の案件が相互に作用しながら、発展・拡大してきている。そこで、ここでは、主な案件の策定の背景、その案件開始のタイミング等を確認し、日本の対ガーナ教育セクター協力の“発展プロセス”の適切さを検証することとする。
最初に、ガーナの教育セクターにおける「日本の協力」、「ガーナの開発政策」、「日本の援助政策」、「国際的潮流」を時系列に整理して、「案件策定プロセス図」(図 11)を作成した。評価対象期間は1998~2003年度上半期であるが、案件策定の背景となった事象はそれ以前にも存在することから、プロセスを確認する期間をやや遡って「初期の協力(1995年度以前)」から、「本格的協力への準備(1996~1999年度)」と「本格的協力の開始(2000年度以降)」の3期に分けた。以下、この案件策定プロセス図を参考にしながら、それぞれの期における案件策定の背景、その案件開始のタイミング等をみていく。
図 11 案件策定プロセス図(PDF)
| 1) | 初期の協力(1995年度以前) 日本のガーナ教育セクターにおける協力のなかで最も長い歴史を持つのは、高等学校に派遣された理数科教師としての青年海外協力隊(以下、JOCV)である86。これまで派遣されてきた多くの理数科隊員が、高等学校の生徒の基礎計算力や基礎学力のレベルが著しく低い87実態に直面し、小中学校などもっと早い段階への支援の必要性を指摘してきたことが88、後に技プロが開始される1つの背景となっている89。 また1990年代初頭、東西冷戦終焉に伴い国際社会のアフリカに対する関心が低下する中、わが国は1993年に第1回の「アフリカ開発会議」(TICAD I)を開催し、これ以降アフリカ諸国における開発に積極的に取り組んできた。このTICAD Iにおいて、わが国はアフリカの人材育成を積極的に支援することを表明したが、その姿勢を具体的に示すために創設されたのが、1996年度より始まるアフリカ青年招聘計画である。その初年度の対象国として、従来わが国がアフリカの援助の重点国の1つとして位置づけてきたガーナ90が選ばれている。 |
| 2) | 本格的協力への準備(1996~1999年度) わが国が1996年DAC新開発戦略でガーナを援助実施重点国に定めたことを受けて、ガーナにおける援助促進と日本側の調整役として、1997年より教育省・政策アドバイザー型専門家(以下、政策アドバイザー型専門家)を教育省内に、また援助協調対応の企画調査員をJICAガーナ事務所に派遣した。これらの人材派遣は、プロジェクト型支援からSWAPや援助協調へと援助のアプローチが大きく変容するこの時期のガーナにおいて、大きな役割を果たした。 政策アドバイザー型専門家は、同時にfCUBEのための案件策定促進の任務も担った。そのため、数多くの現地調査、実態調査を実施し、技プロの案件形成や実施に貴重な情報を提供した。また当時、「教員養成プログラム」政策の改定の必要性が指摘され、教育省、ガーナ教育サービス(GES)、援助機関(USAID、DFID、GTZ)が約2年間におよぶ協議を実施してきたが具体策に至らず、教員養成を柱とする技プロの実施にも大きな問題となっていた。そこで同専門家はその改定に向けて教育大臣はじめ教育省関係者に積極的に働きかけ、その結果、1999年の教員養成プログラム政策の改定・施行へと導いたことは、大きな貢献であった。 他方、先に述べたアフリカ青年招聘計画は、日本のガーナ教育セクターへの協力姿勢を示す機会としてより効果的に活用するために、政策アドバイザー型専門家の助言によって、1998年度から選定・運営方法に改良が加えられた。すなわち、まずガーナ側が「年間ベスト教員」を選出し、その受賞者を日本に招聘するという仕組みとし、その授賞式は日本の資金援助によって教育大臣以下ガーナの教育関係者を招き盛大に開催するというものである。これは狙い通り、受賞式が日本の教育セクター協力の姿勢を示す場として定着している91。さらに、2000年度以降は招聘枠を、理数科教育強化支援に重点を置き理数科教員枠を2名、またジェンダーに配慮し女性教員枠を2名と設定しており、目的を明確にしている点が評価できる。 当時は、fCUBEというセクター・アプローチが開始され、世界銀行、DFID、USAIDなどリーディングドナーが参入し始めた時期で、いわば“教育セクター援助の黎明期”であった。この時期、定期・不定期の援助協調会議がほぼ毎日のように開催されていたが、日本が政策アドバイザー型専門家を投入したことによって、ドナーコミュニティの会議に参加することができたことは、その後の教育セクター内における発言権や存在感の確保に結びついたといえよう92。 さらに、同専門家は、直接の任務に含まれない業務ではあるが教育セクターにおける協力であるという理由により、開発調査の準備段階のプロセスにも関わっている93。このように、教育セクター全体を視野に入れた活動が可能な人材が配置されていたことによって、日本の協力はその後のESPのほぼ全分野を対象とする協力枠組みへとスムーズに拡大していくことが可能となったと考えられる。 以上のように政策アドバイザー型専門家は、援助協調が進み、セクター内において包括的なビジョンをもった取り組みが求められる国においては、非常に有効であることが分かる。ただし、これまでの取り組みは専門家の個人的努力によるところが大きかった。初代の政策アドバイザー型専門家によると、当時、教育セクターだけで公式・非公式会議等が連日開催されて、他ドナーが3~6人体制で業務を行っているなか日本側は1人で対応せざるを得ず、ガーナ教育セクターが援助協調の中でプログラム的に展開している状況においては、体制が不十分であったと指摘している94(後述、2)ステークホルダーの関与の適切さの2)ガーナの日本人関係者、も参照のこと)。 |
| 3) | 本格的協力の開始(2000年度以降)
2000年度以降は、これまで投入されてきたスキームによって準備が整い、日本の本格的な教育セクター協力が始まった時期である。この期を特徴づけるのは、より投入額の大きい技プロや開発調査などの案件であることから、まずこれらの案件の策定過程を確認する。 ・技プロ関連案件の策定過程 技プロは、fCUBEを支援することを目的として、2000年度より実施されている。1996年にガーナ側から要請を受け、1997年に基礎調査を、1998年に事前調査を、1999年に実施協議調査を順次実施し、2000年より協力を開始している。要請を受けてから開始まで4年が経過しており、多少時間がかかりすぎたという意見95もあるが、ガーナの教育セクターにおける初めての技プロであり、かつ日本のODAとしても基礎教育への協力実績が多くなかったことから、時間をかけて慎重に現状とニーズを把握し、さらに日本国内のバックアップ体制を構築していったものと推察される。 また、前述したように、1997年に派遣された政策アドバイザー型専門家(初代)が、技プロの案件形成に中心的役割を果たした。さらに同専門家は、当時基礎教育レベルの理数科教育支援で数少ない先行事例であったフィリピン(1994年~)、ケニア(1998年~)、南アフリカ(1999年~)等の情報を収集し、その経験をガーナにおいて役立てるべく、同専門家の総合調整の下、1999年1月にガーナ側の教育行政官をフィリピンへ「第三国研修員」として送り、さらに同年7月、同専門家自身が「技術移転交換プログラム」のスキームでケニアと南アフリカを視察している96。 さらに技プロは、第4章の4-2で詳述したように、計画段階から構想された技プロを中心とした多様なスキームによるプログラム的展開をみせている。これは図11の網掛け部分に相当するもので、具体的には教育省・GESの高官を研修員受入で日本に招き信頼関係を構築することに始まり、さらに技プロの協力対象地域である北アクアピン郡を中心として、集中的に研修員受入(2000年~)、ノンプロ無償見返り資金(以下、見返り資金)97、草の根無償(1件)などの案件が策定されていった。特に研修員受入は、カウンターパート研修(行政官と教員教育者対象)と国別特設(理数科教員教育セミナー)の2コースが実施され、JICA本部・JICA中国国際センター・大学コンソーシアム・ガーナ送り出し側、の4者の緊密な連携のもと、計画策定・実施・帰国後のフォローアップ・翌年へのフィードバックが実施されており、本邦研修のあり方に多くの示唆を与えるものである。 さらに、このプログラム的展開は、2000年のガーナ国別援助計画およびJICAガーナ国別事業実施計画の策定など、政策的後押しも受け、進展が加速された。 以上のように、このプログラム的展開の策定過程は、ODAの既存スキームを柔軟に活用しながら、かつさまざまな連携と調整の下で発展し、それが案件運営にも効果的に働いていることが確認された。 ・「開発調査」の策定過程 次に、技プロとほぼ同時期に開始された、「開発調査」の策定過程について確認する。ガーナ政府は1995年にVision2020を発表し中所得国入りを目標に掲げて以来、国内産業の育成は不可欠の課題であるとの認識の下、人材育成に強い関心をもっていた。このような背景から、ガーナ側はわが国に対して、TVET分野への支援をたびたび要請していた。これに対して、わが国は当初1996年に始まったfCUBEへの支援を優先させてきたが、TVET分野におけるガーナの現状の把握と案件形成の可能性を探ることを目的に、2000年3月より「開発調査」を開始した。TVET分野は、本評価調査時点においても全貌が正確に把握されておらず、他ドナーもほとんど支援の実績がなかったことから98、まず開発調査によって詳細な現状把握とフィージビリティ調査を実施した。また、同開発調査のマスタープランの策定にあたっては、ガーナの現状とニーズに即して、「産業界のニーズに直接呼応する人材育成」と「持続可能な人材育成制度」という2つのテーマの下にまとめられた。 その後、ガーナ側から案件要請に関する具体的な動きが見られなかったため、2003年2月から政策アドバイザー型専門家の現地業務費によって、「技術教育に係るポリテクニックの現状調査」が実施された。2004年初旬にはJICAによる案件形成調査団が派遣され、本格的な案件形成に向けて動き出したところである。 ・その他の注目すべき点 以上の協力に加えて、政策アドバイザー型専門家はガーナにおいて本格的に教育SWAPが策定されようとした時期に、その作成支援やSWAPに関するドナー間の会議開催の支援等により援助協調を促進するなど、大きな役割を果たした。また援助協調対応の企画調査員は、DFID主導でMDBSが導入されようとするこの時期に、各種ドナー会議に出席するなどして情報を収集し、この新しい援助モダリティに対して日本がどのように関与すべきかその判断材料を提供した。また、JOCVは継続して高等学校等への派遣実績を積み上げてきており、草の根無償は基礎教育を中心として案件数は増加傾向にある。日本の協力は、全体として分野および量的に厚みを帯びてきたといえよう。 |
| 4) | 日本の協力全体としての方向性
以上みてきたように、一連のわが国の協力の計画策定の背景、その案件開始のタイミング等は、ガーナ側の要請と日本の援助政策に呼応して展開してきており、相互に連携もみられる。また、JOCVのニーズ把握や、政策アドバイザー型専門家の実態調査および多くの関係機関の調整などから始まり、現在の協力分野は基礎教育を中心としながら後期中等教育や科学技術教育までカバーするものへと変化してきたわが国の協力はESPとの整合性も高い。これは、わが国がガーナのニーズに適宜対応してきた結果と判断される。従って、ガーナ教育セクターにおける日本の協力の発展プロセスは適切であったといえる。 ここで、5-2「目的」のところで言及した、国別援助計画で案件策定において留意するべき点として挙げられた4つの「援助実施上の留意点」( 1)援助受け入れ体制・能力の強化、2)債務問題への対応、3)セクター・プログラム・アプローチ、4)南南協力推進)の観点から検証する。特に教育セクターの協力に密接に関係する、1)援助受け入れ体制・能力の強化、3)セクター・プログラム・アプローチ、4)南南協力推進について検証していく。 ガーナ国別援助計画によると、1)援助受け入れ体制・能力の強化については、「DAC新開発戦略に適応した案件の発掘と実施の観点から鑑みれば、政策立案・援助調整・モニタリングといった分野での能力向上も今後の課題となる」と明記している。教育セクターにおける案件発掘や援助調整は、前述のように政策アドバイザー型専門家に負うところが大きく、その体制は十分とはいえなかった。また、日本側の援助策定・実施体制に十分な配慮がなされなかったために、日本としての教育セクター全体のモニタリングが十分になされなかった点も今後の課題である。 3)セクター・プログラム・アプローチについては、「ガーナが、世界銀行の包括的開発アプローチであるCDFアプローチのパイロット国であることを踏まえ、ガーナをサハラ以南アフリカにおけるセクター・プログラム実施の重点国、また、保健、教育セクターを重点セクターとして、他の援助実施国・機関との有機的な連携を強化しつつ、その中で主導的な役割を果たしていく」と指示している。この点に関して、他の援助実施国・機関との有機的な連携についてはある程度実現できているものの、“主導的な役割を果たしていく”という観点は全体の投入規模と援助実施体制において不十分であり、達成できているとは言いがたい。保健セクターが1969年以来の援助の歴史と実績があることと比べると、“主導的な役割”の達成度の差は顕著である。 4)南南協力の推進については、現在、保健セクターでこれまでの援助の成果を踏まえ、第三国研修による南南協力が実施されているが、教育セクターにおいてはまだ具体的に検討がなされていない。しかし、この点に関しては本格的な技術協力が始まってまだ4年目であり、その成果を他へ移転するには時期尚早であり、特に問題とはいえない。今後、2005年に技プロが終了する頃には一定の成果が期待できること、また2003年に理数科教育のアフリカ地域ネットワーク「SMASSE-WECSA」の会合において、アフリカ全域の理数科教育関係者にガーナの技プロの取り組みを紹介し、情報交換したことによって、ガーナ教育セクター関係者に大きな刺激と自信を与えたことなどを考えると、今後の南南協力の実現の可能性が高まっているといえる。 |
協力の策定過程においては、さまざまなステークホルダーが関与している。ここでは、その主なステークホルダーを、国レベル、ガーナの日本人関係者、大学関係者、現場レベルという4つに分けて、その関与の適切さを検証する。
| 1) | 国レベル 1995年に、わが国の外務省とガーナ教育省関係者による政策協議(経済協力総合調査)が実施された。さらに2000年には、日本とガーナの間で包括的な政策協議(対ガーナ経済協力政策協議)がもたれた。同政策協議は、両国間初の包括的な政策協議となり、豊富な資料に基づきトップレベルの関係者による緊密な対話がもたれた。この結果、ガーナの長期的ニーズに沿ったガーナ国別援助計画が策定された。 この時期、ガーナ側には暫定版「貧困削減戦略書(PRSP)」用語を策定するなど援助受け入れ体制に変化があり、世界の援助コミュニティでも国連総会でMDGsが策定されるなど新しい進展がみられたことから、タイミング的にも適切であったといえる。 | |||||||||||||||||
| 2) | ガーナの日本人関係者 1996年のfCUBE開始に伴い、ガーナ側を含むドナー会合が頻繁に開催されるようになった。この時期、政策アドバイザー型専門家が投入され、連日(時には1日に数回)開催されるドナー会合に参加し、積極的に情報を収集・共有してきた。しかし、初代の同専門家の時代は、ほとんど一人で教育セクターの援助協調の動きに対応しており、組織的な対応はなされなかった。このような状況に対して同専門家は、人員のサポートシステムの充実と今後の人材育成および有効活用の観点から、ガーナJICA事務所のローカルスタッフの活用(学術的・現場経験を備えた)、他の可能な専門家の派遣協力体制の強化が必要であると提言している99。このような貧弱な体制の中ではあるが、歴代の同専門家ポストの個人的努力と、同ポストのカウンターパートが教育省幹部でありかつ執務室が教育省内にあるという立地に恵まれ、主要な業務である教育省内における情報収集・援助促進には一定の成果を上げている。 また、本評価調査時においては、教育セクターのみならず、すべてのセクターにおいてSWAP化が進み、さらにMDBSなど国家レベルでの協調が進んでおり(2章の2-6参照)、連日さまざまなセクターの開発パートナー会議が開催されている。これらの対話の場に、在ガーナ日本大使館とJICA関係者(JICAガーナ事務所、企画調査員、政策アドバイザー型専門家、技プロ専門家等)が協力し、相互調整をしながら対応し、情報交換が行われる流れができあがっている100。 こうした日本人関係者の個人的な努力や相互の連携によって、案件の策定を実施していることは評価に値する。しかし、今後ESPの枠組みによる援助体制が本格化するにあたり、日本の協力について全開発パートナーの同意が必要となることから、より説得力のある案件形成が求められる。 | |||||||||||||||||
| 3) | 大学関係者 技プロの案件策定段階では、基礎調査、事前調査、実施協議調査が実施されているが、これらの調査にガーナ側からはケープ・コースト大学関係者の参加を得て、また日本側も大学コンソーシアム(4章の4-2参照)の中核となった大学関係者や教育開発の専門家が参加し、ガーナの教育に対する総論から指導法に至る各論まで集中した意見交換が行われ、案件計画に反映された。この策定段階で築かれたガーナと日本の教育関係者の間の信頼関係は今日まで継続され、実施においても、客観的な意見を提供してくれる不可欠な情報提供源となるなど、円滑な協力実施の促進および質の向上につながっている。 また、日本側の国内支援体制として、大学コンソーシアムを構築し、教育行政、教育教授法(理科、数学)、数学理論など、幅広い分野の専門家が案件形成段階から参画したことは、プロジェクトの効果を高めることに寄与している。 | |||||||||||||||||
| 4) |
現場レベル
現場レベルにおいては、技プロの策定過程において、協力対象地域の協力機関(教員養成校と郡教育事務所等)との十分な対話がもたれた。さらに、これらの機関の主要なスタッフに対して、プロジェクト初期の段階に本邦でのカウンターパート研修を実施したことは、プロジェクトの趣旨、JICAの協力の基本的スタンスなどの理解や、プロジェクトへのオーナーシップの高まりにもつながり、その後のプロジェクト運営に大きく貢献している。 他方、JOCVもガーナ教育セクターの案件策定において重要な役割を担っている。JOCVは学校現場の問題やニーズをよく把握しており、これらの情報が、公式・非公式のチャネル(JOCVの帰国報告会や、各種JICA報告書、大使主催のレセプションや各種イベント時など)を通じて在ガーナ大使館やJICAガーナ事務所に提供され続けたことが、技プロや開発調査の案件策定につながっている101。また、草の根無償の案件形成にもJOCVは大いに貢献している。特に雇用促進地域職業訓練センター(ICCES)などでは、配属されているJOCVによって案件形成支援が積極的に行われており、所管している人材開発雇用省ICCES局の評価は非常に高い102。このように、JOCVは教育現場の案件策定において、不可欠な存在ということができる。ただし、それは体系的になされているわけではなく、どちらかといえば個人的努力に負うところが大きい。 次に、草の根無償とJOCVの案件策定過程において住民の参加がどの程度あったのかをみるために、今回実施したインパクト調査(詳細は巻末資料参照のこと)の結果を用いる。学校運営委員会に対する「日本の援助の計画・策定の際、十分な協議の場があり、住民の意向が反映されたか」という問に対して(表 22)、反映されたという人の割合は、裨益の種類別に、草の根無償(81%)、草の根無償+JOCV(86%)、JOCVのみ(48%)となっている。 表 22 日本の援助の計画・策定の際、住民の意向が反映されたか(学校運営委員会の評価)
JOCVのみの場合は住民参加が不足しており改善が必要であると思われるが、草の根無償に関しては概ね住民参加を得ながら案件策定がなされているといえよう103。なお、草の根無償+JOCVが住民の意向が反映されたとする割合が一番高いことは、前述したように多くのJOCVが草の根の案件形成に関わっていることから、地域住民の巻き込みにもJOCVが積極的に関与してきた結果と推察される。 以上のように、さまざまなレベルで多くのステークホルダーが関わっているが、そのメンバー、関わったタイミング、関与した内容、などの点に関しては、概ね適切であったといえる。 |
ここでは協力案件策定過程において、他ドナーとの対話があったかどうか、また対話があった場合それは適切であったかどうかについて検証する。
前述したように、1996年のfCUBE開始に伴い、ドナー会合が頻繁に開催された。これに政策アドバイザー型専門家が積極的に参加し、情報を共有するだけでなく、日本の立場を表明しドナー間の合意を取り付けていったことが、1990年代末財政支援の圧力が強まる中で、技術協力をスムーズに開始できた背景となっている。また初代の同専門家は、ドナー協調の場において、受動的に参加するのではなく、自発的に調整役を担うなど積極的に関与しており、これが後述する他ドナーとの連携案件の形成にもつながっている。その後、2代目・3代目の同専門家も引き続き、ドナー会合に積極的に参加している。
加えて、2代目の政策アドバイザー型専門家が着任した2000年当時、ドナー間の対話がほとんど失われていたところ、同専門家と技プロ専門家が協力し、ドナー間をまわって対話の場作りに奔走した。その下地の上に全開発パートナーによるSWAP策定プロセスが進展していったこと104、また日本のプレゼンスが高まったことは非常に高く評価される。
以上のように、他ドナーとの対話は、援助協調が進む中で積極に行われ、適切であったと判断される。加えて、個人的な努力によってではあるが、SWAP策定プロセスで日本のプレゼンスを高めた点も評価される。
(2) 実施過程の妥当性
1) 実施体制の適切さ
ガーナ教育セクターにおける日本の協力の実施体制の適切さを検証するために、まず日本側の実施体制を概観し、次にガーナ側のカウンターパート体制を整理して、総合的な実施体制図(図 12)を作成した。そして、この実施体制図を参照しながら、日本の協力の実施体制の適切さ検証していく。
ガーナ教育セクターに対する日本側の実施体制は、図 12のように在ガーナ日本大使館とJICA関係者(JICAガーナ事務所、企画調査員、政策アドバイザー型専門家、技プロ専門家等)との、緊密なコミュニケーションと連携に基づいている。特に、2003年春以降は、在ガーナ日本大使館とJICA関係者でタスクフォースを結成し、めまぐるしく変容するガーナの援助現場へ対応するために、定期的な協議の場を持ち、包括的な指針づくりの議論を積み上げている。このような在ガーナ日本大使館とJICAガーナ事務所の密な連携体制は、協力の実施の効率性に寄与しているものと思われる。
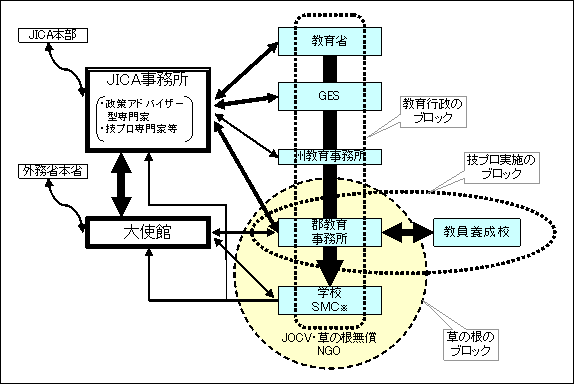
ガーナ側のカウンターパートとの連携体制は、図 12の実施体制図に示すように、大きく3つのブロックに対して実施されている。1つ目のブロックは、「教育行政のブロック」で、これはガーナ教育行政の縦系列で、教育省-GES-州教育事務所-郡教育事務所-学校―コミュニティで構成される。2つ目のブロックは、「技プロ実施のブロック」で、これは技プロの協力対象地域における協力機関(主に郡教育事務所、教員養成校)を中心に構成される。3つ目のブロックは、「草の根のブロック」で、実際に教育が提供される現場の関係機関(主に郡教育事務所、学校、学校運営委員会、JOCV、現地NGO)などで構成される。
以上の3つのブロックに対して、日本の協力は相手方のオーナーシップを尊重し緊密な関係を保ちながら、それぞれに直接的に働きかけているのが特徴である。「教育行政のブロック」に対しては、政策アドバイザー型専門家が教育省から郡教育事務所までを総合的に見て教育省に対してアドバイスを行っている。また技プロや他ドナーと柔軟に連携し、相乗効果を図っている。また、技プロは、「教育行政のブロック」と「技プロ実施のブロック」の両方に軸足をおいて、直接協力機関と連携をとりながら展開している。政策アドバイザー型専門家の執務室が教育省の中にあることや、技プロの事務所がGES教師教育局と北アクアピン郡の教員養成校内にあることによって、各ブロックのカウンターパート機関とのコミュニケーションを深め、柔軟でタイムリーな協力を可能にしている。「草の根のブロック」に対しては、在ガーナ日本大使館が、大使館援助のスキームである草の根無償の案件策定・実施に際しては、直接働きかけている。JICAガーナ事務所は、JOCVの計画・支援という形で「草の根のブロック」の協力に関わっている。また、JOCVを通じて草の根無償の案件形成・実施のフォローアップにも間接的に関与している。
これらの各ブロックにおいて特筆すべき点は、各ブロックの主要カウンターパートを本邦研修に参加させることによって、日本の教育制度に対する尊敬と共感、JICAの支援体制やプロジェクトの協力方針への理解が深まり、日本の協力やプロジェクトの運営に積極的に関わるようになる姿勢が顕著となり、プロジェクト実施の効率性を高めているということである105。
次に、現地サイドと本邦との関係、すなわち現地サイドへの権限委譲の状況をみる。JICAにおいては現場への権限移譲の必要性が強く認識されており、徐々に現地事務所の裁量も拡大され、柔軟な対応が可能となっているところであるが、今回の調査ではまだいくつかの課題が指摘された。例えば、政策アドバイザー型専門家が現地業務費の活用によって協力促進や他ドナーとの連携促進を行っているが、この実施にあたっては、申請と精算に煩雑な事務手続きが必要であり、またJICA本部の承認に時間がかかるといったようなことが、実施の効率性を下げる要因となっている106。さらに、年度内精算という制度上の制約によって、ガーナ側カウンターパートの自助努力による実施を待つ時間的余裕がなく、日本側の主導で実施せざるを得ないなどの状況も発生している107。しかし、このような現状の課題は、2004年度に実施されるJICAの機構改革において、現場への権限移譲が加速されることが計画されていることから、早急に改善されるものと期待される。
以上みてきたように、ガーナ教育セクターにおける日本の協力の実施体制は非常に包括的であり、効果的・効率的に運営されていると判断される。さらに、日本側関係者間および対ガーナ関係機関ともに、各関与者が信頼関係と綿密なコミュニケーションに基づいて、相互に適切に連携している点も評価される。以上により、やや改善すべき点があるものの、総じて実施体制は適切であり、妥当であると判断される。
2)他ドナーとの連携
「(1)策定過程における妥当性」の「 3)他ドナーとの対話」のところでも触れたとおり、ガーナ教育セクターにおける他ドナーとの対話は、fCUBEというセクター・アプローチの実施、およびSWAPの策定過程において、非常に密であった。また、このような密な対話に基づき、4章・表15に見られるように、活発な連携を行っている。
例えば、援助協調促進プロセスにおいては、ESP会議経費(世界銀行、DFID、USAID、UNICEFと分担)、ESP地方説明会開催費(DFID、UNICEFと分担)などへ、資金提供および技術提供を通じて連携している。また、UNICEFのスクール・マッピング事業においては、北アクアピン郡の事業の一部を受け持った実績がある。この他、初代の政策アドバイザー型専門家の時代にはUNICEFと北部地域の小学校建設支援に対する連携協議を進めた。
また、世界銀行は、開発調査で策定したマスタープランにおいて提唱したCBT手法に着目し、新規プロジェクトにおいてCBT手法を活用したポリテクニック支援(予算1,100万ドル)を計画している108。さらに、評価調査団ヒアリングの折には、世界銀行からJICAの技プロとの連携に対する関心が示されており、世界銀行とさまざまな連携が行われる可能性が高まっている。
このように、ガーナ教育セクターにおける他ドナーとの連携は、規模はそれほど大きくはないが、確実に実績を積み上げており、援助の効率性の向上に貢献している。さらに、わが国のガーナ教育セクターにおけるプレゼンスを発揮することにも貢献している。加えて、これまでの他ドナーとの連携が、今後SWAPが本格的に展開する中で必要となる援助協調の基盤をつくっている点も、評価に値する。
以上、「プロセス」という視点から、「策定過程における妥当性」と「実施過程の妥当性」の2つの評価項目で評価してきた。その結果、ガーナの教育セクターにおけるこれまでの日本の協力のプロセスは、日本の戦略やガーナ側の開発課題に対応しながら、ODAの既存スキームを柔軟に活用し、相互に連携と調整を繰り返しながら発展しており、妥当性は高い。また実施体制についても、関係機関の緊密な連携のもと実施している。また、他ドナーとも連携案件が実施されている。このように、総じて、プロセスは包括的かつ柔軟であり、効率性も高く、妥当であると評価することができる。
5-4 結果
「結果」では、「有効性」、「インパクト」、「自立発展性」の3つの評価項目によって評価する。有効性では、本章の5-1で示した目標体系図A(図8)に、達成度を計る指標を設定し(目標体系図B、図 13)、これを基にセクター全体の達成状況と、その中での日本の貢献度を、可能な限り定量的に把握する。インパクトでは、ガーナおよび日本における上位政策への影響、関係者への影響を確認する。自立発展性では、ガーナ教育セクターの自立発展性を検証し、さらに自立発展への日本の貢献の度合いを確認する。
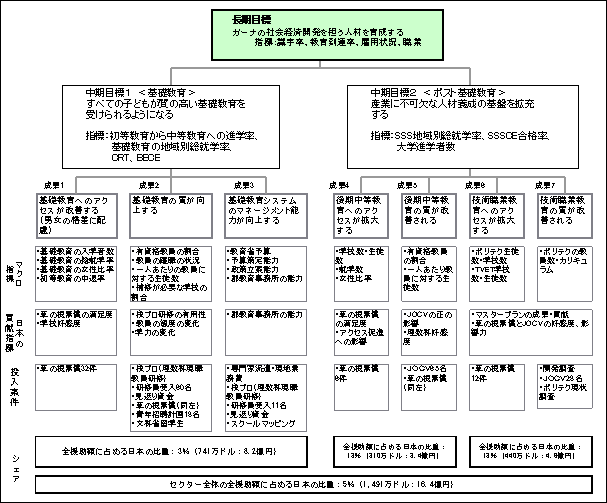
| 注: | 日本の投入のうち、ノンフォーマル教育(84万ドル)、セクターワイド(9万ドル)は、本図には含まれていない。詳細は、3章・表11を参照のこと。 |
| 出所: | 3章・表11、4章の日本の実績より作成。 |
(1) 有効性
有効性では、目標体系図B(図 13)を活用し、目標体系図Bのそれぞれの目標・成果の進捗状況を把握するために、独自に指標を設定した。指標には、セクター全体の進捗状況を計るための「マクロ指標」と、セクターの中で特に日本の協力による効果や貢献の度合いを計るための「日本の貢献指標」がある。
これらの指標は、評価対象期間において入手可能なデータの中で、各目標・成果の進捗状況を示すものとしてより適切なものを選定した。また、定量的なデータを補うために適宜定性的な指標も設定した。日本の貢献指標については、日本の投入量が非常に限定的であり必ずしも日本の協力効果と見なされない部分があることや、データの取り方に統計的に問題があることなどにより、ここでの分析・考察の結果はあくまで一側面を表しているに過ぎないことをお断りしておく。
最初に、ガーナ教育セクター全体における日本の協力の位置づけを把握するために、ドナー全体の援助額とその内訳などを概観する。その後、目標体系図Bに示す各指標の達成状況について、成果1~7、中期目標1~2、長期目標の順で検証していく。
1) ドナー全体における日本の位置づけ
fCUBE以降の、主なドナーの教育セクターへの援助総額を、把握できた範囲で試算したところ、約3億3,246万ドルとなった(詳細は3章・表11参照)。一方、評価対象時期(1998~2003年度上半期)における日本の援助総額は1,585万ドル(17.4億円)であった。そのうち、目標体系図Bに該当する投入は1,491万ドル(16.4億円)であった。
ドナー別の内訳をみると(図 14)、世界銀行29%、英国28%、米国20%、ドイツ8%、オランダ6%、日本5%の順となっている。英国と世界銀行で全体の6割近くを占めており、その影響力の大きさがうかがえる。他方、日本は6番目で、5%のシェアを占めるに過ぎない。
また、教育レベル別(図15)にみると、基礎教育73%、後期中等教育7%、高等教育7%、職業訓練3%、ノンフォーマル教育10%となっており、fCUBE支援を中心とする基礎教育を重点的に支援してきたことが明らかである。各レベルにおける日本のシェアは、基礎教育3%、後期中等教育13%、高等教育13%、職業訓練13%、ノンフォーマル教育3%となっており、全レベルに比較的まんべんなく支援してきた状況が分かる。こうした状況は、日本の協力が基本的に要請主義であったことの反映であると同時に、特定のサブセクターに援助を集中させる戦略を採用しなかったという結果であるともいえよう。
図 14 ドナー別援助内訳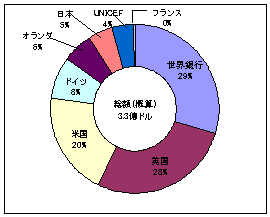 |
図 15 教育レベル別内訳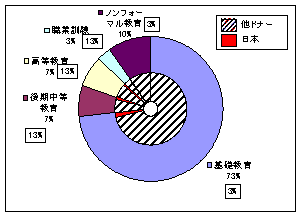 |
| 出所:3章・表11より作成。 | 注:総計は、左図と同じ。□内のパーセントはそれぞれの分野における日本の協力の占める割合。 出所:3章・表11より作成。 |
このように、ガーナ教育セクター全体における日本の援助額のシェアは総じて小さい。日本は、5-2「目的」のところで言及した「ガーナ国別援助計画」の「援助実施上の留意点」として、ガーナをサハラ以南アフリカにおけるセクター・プログラム実施の重点国として、教育および保健セクターを重点セクターとして主導的な役割を果たしていくよう促しているが、実績から判断すると、この留意点に十分に配慮しているとはいえない状況である。援助規模が小さい理由としては、4章で述べたように、政策上は教育協力の重視を強調しながらも、ODA実額ベースではなかなか大きくならなかった109日本のODA全体の動向がある。さらに、ガーナにおいては、一般無償による学校建設など規模の大きな投入を実施しなかったことがある。これは、ガーナの教育セクターの開発パートナーが日本の一般無償による小学校建設の高コストや住民参加不足に対して強い難色を示してきた結果で、今後も無償による小学校建設の可能性は低い。
このような教育セクターへの協力実績を踏まえ、日本がどのような役割を果たしてきたのか、その貢献の度合いを、以下詳細にみていくこととする。
2) 成果1「基礎教育へのアクセスが改善する」
<マクロ指標>
評価対象期間における基礎教育へのアクセスの改善状況をみるための指標として、入学者数、総就学率、女性比率、中退率を設定した。
入学者数の推移をみると(表 23)、1998~2001年の4年間で、小学校については約21万人の増加、中学校では約7,500人の増加となっている。小学校の増加人数の内訳割合を公立・私立別にみると、私立が74.6%であるのに対して、公立は25.4%と大きな開きがある。この私立における入学者数の増加傾向は、中学校においてより強くなる。また小学校・中学校ともに2000年で一旦減少しており(私立は不明)、必ずしも順調に増加しているとはいえない。これらのデータから1998年以降基礎教育へのアクセスは概ね改善傾向にあるといえるが、その多くの部分は私立における生徒数の増加によるものといえる。
表 23 公立・私立別の入学者数の推移
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 増加人数 (増加率%) |
割合 | ||
| 小学校 | 合計 | 2,377,444 | 2,560,880 | - | 2,586,434 | 208,990 (9) |
100.0% |
| 公立 | 2,060,744 | 2,114,981 | 2,048,229 | 2,113,749 | 53,005 (3) |
25.4% | |
| 私立 | 316,700 | 445,899 | - | 472,685 | 155,985 (49) |
74.6% | |
| 中学校 | 合計 | 790,684 | 833,019 | 699,741 | 865,636 | 74,952 (9) |
100.0% |
| 公立 | 729,276 | 736,251 | 699,741 | 741,895 | 12,619 (2) |
16.8% | |
| 私立 | 61,408 | 96,768 | - | 123,741 | 62,333 (102) |
83.2% | |
| 注: | 「-」はデータなし。 |
| 出所: | "Evaluation of the Education Sector Support Programme (ESSP) 1998-2003"(DFID)より作成。 |
次に、総就学率と女性比率(総就学者に占める女性の占める割合)をみる(図 16・ 17)。小学校では、総就学率は1998年の72.8%から2002年には79.9%とゆるやかな上昇傾向にあるが、2001年以降は80%程度で停滞気味である。また、女性比率は、1998年の47.0%から2002年の47.2%とほぼ横ばいである。
中学校では、総就学率は1998年の58.1%から2002年の66.0%と着実に上昇している。一方、女性比率は1998年以来45%を前後しており、停滞している。
図 16 小学校の総就学率・女性比率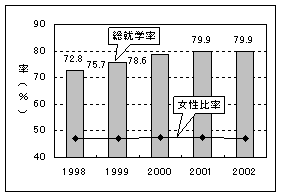 |
図 17 中学校の総就学率・女性比率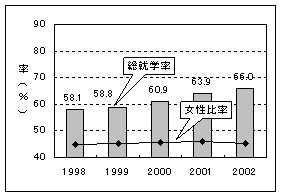 |
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 | 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 |
基礎教育における中退率(図 18)は、小学校6年生・中学校1年生ともに、1998年以降増減しており改善傾向にあるとはいえない状況である。
図 18 基礎教育の中退率 |
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 |
以上の結果から総合的に判断すると、基礎教育へのアクセスについては、大きな傾向としては徐々に改善傾向にあるものの、やや伸び悩んでいる状態であるといえよう。
<日本の貢献指標>
これらのマクロの状況に対して、日本の投入は草の根無償のみである(図8)。草の根無償の実績は、32案件、約1億円(約92万ドル)である。他方、他ドナーの援助状況をみてみると(3章の3-5も参照)、USAIDは354校の増改築、EUが年間260校ずつ建設110という状況であり、マクロ的にみるならば日本の裨益度は非常に小さいといわざるをえない111。
しかし、草の根無償の基本的な意図は「草の根の人々への直接的な裨益」であることから(BOX 8参照)、本評価調査では最終裨益者に対するインパクト調査を実施した。その結果、草の根無償によって建設された施設について、生徒では「非常に満足」「ある程度満足」を合わせて92%が、また教員では同95%が満足している(表 24)。
表 24 草の根無償による施設の満足度
| 非常に満足 | ある程度満足 | どちらともいえない | 満足でない | |
| 生徒 | 80% | 12% | 5% | 2% |
| 教員 | 78% | 17% | 0% | 6% |
|
注:回答数は生徒41、教員18。四捨五入により計が100%にならない。 出所:インパクト調査より作成。 |
また、ほとんどの生徒が「新しい施設によって学校が好きになった」(95%)と感じている(表 25)。さらに、このような状況によって、教員の全員が「就学率の改善に寄与した」とみている。
表 25 学校が好きになったどうか
| 非常にそう思う | ある程度そう思う | どちらともいえない | そう思わない |
| 95% | 0% | 2% | 2% |
|
注:回答数は生徒41人。四捨五入により計が100%にならない。 出所:インパクト調査より作成。 |
一般に学校が新設されると地域住民の関心が集まり、就学促進の効果があるが、上記のインパクト調査からも、日本の草の根無償によって、就学促進に効果があったとみることができる。
以上の結果より、教育へのアクセスの向上における日本の貢献は、マクロレベルでは小さいものの、協力を実施した地域においては、裨益者に満足を与え、アクセスの向上に寄与しているということができる。
3) 成果2「基礎教育の質が向上する」
<マクロ指標>
基礎教育の質をみるための指標として、教員に関すること(有資格教員の割合、教員の離職の状況、教員のパフォーマンス)、教育環境に関すること(一人あたりの教員に対する生徒数、補修が必要な学校の割合、その他の要因)を設定した。
教員に関する状況は、3章で詳述したように、ガーナの教育の質の改善のための大きな障害の1つと認識されている。その一因として、慢性的な教員不足を補うために無資格の教員を雇用しているという実態がある。教員全体に占める有資格教員の割合は、小学校・中学校ともに1998年から2000年では低下傾向で、2000年において小学校で8割弱、中学校では9割弱となっている(図 19)。この傾向は、農村地域において特に深刻である112。
また、教員不足の一因としては、教員の離職率の高さがある。全国的な離職率に関する統計はないが3章の3-4で詳述した「有給進学休暇制度」の利用者の数(表10)だけをみても、相当割合の教員が離職していることが想像される。教員が定着しない背景として、教員養成校卒の基礎教育レベルの教員の社会的ステータスの低さ、低い給与、昇進の難しさなどの実態がある。従って多くの教員養成校卒の教員が、有給進学休暇制度を利用して学位を取得しより待遇のよい職種へと転職していく。このような構造的な問題が解決されない限り、基礎教育レベルの教員に対してさまざまな施策を実施しても、基礎教育の質の改善にはつながりにくいであろう。
さらに、教員のパフォーマンスの低さの問題がある。公立と私立の教育の質の差は、教員のパフォーマンスの差(規定の授業時間に教壇に立っているかどうか、年間のシラバスを消化しているかどうか等)によるという分析結果(3章の3-4参照)がある。同分析では、教員のパフォーマンスの差は一般に考えられている「資格の有無」や「給与の差」ではなく、校長の監督能力によるところが大きいとみている。
図 19 有資格教員の割合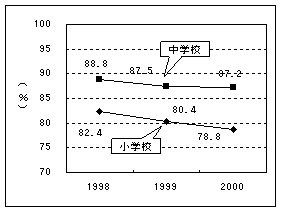 |
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 |
教育環境に関する指標として、一人あたりの教員に対する生徒数をみると、2000年においては小学校で32.6人、中学校で18.2人であった(図 20)。これは学習環境という観点から見れば良好であると考えられるが、世界銀行は教育マネージメントの効率性の観点から35人(小学校)を適正配置としており、少なすぎることを問題としている113。確かに、3章で詳述したように教員数の慢性的不足や教員の待遇の低さが教員の質の低さを招いていることを考えると、一人あたりの教員に対する生徒数の少なさは、教育の質の低さの遠因と考えることができる。
図 20 一人あたりの教員に対する生徒数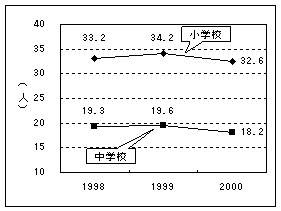 |
図 21 補修が必要な学校の割合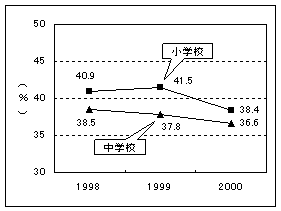 |
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 | 注:30%以上の教室に補修が必要な学校の割合。 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 |
また、補修が必要な学校の割合をみると(図 21)、1998年以降減少傾向にあるが、2000年において小学校38.4%、中学校36.6%と、どちらも約3分の1強の学校において補修が必要な状況であり、学校施設改善のニーズはいまだ大きいといえる。
さらに、施設関連以外では、3章で詳述した教授言語の問題、教科書不足、教授用教材(シラバス等)の不足114などが、教育の質の改善を妨げている教育環境として挙げられる。
このように、基礎教育の質については、教員を取り巻く構造的問題や教育環境など、依然さまざまな課題がある。
<日本の貢献指標>
上記のようなマクロの状況に対して、日本は、技プロを中心としてプログラム的に、研修員受入(60名)、草の根無償、見返り資金、アフリカ青年招聘計画(18名)等のスキームを投入して、主に理数科教育の質の向上を通じた基礎教育の質の向上を支援している。基礎教育レベルの投入の主軸となる技プロは開始されてから4年目であり、まだ全体的に貢献の度合いを判定するのは難しいが、これまでの実績についてみていくこととする。
プログラム的支援の投入額は、2000~2003年度で約7.1億円(詳細は巻末参照)であり、他ドナーに比べると投入規模においては決して大きくない。また主な協力対象地域は全国110郡中3郡(北アクアピン郡、西アダンシ郡、タマレ郡)のみであり、裨益地域は限定的である。
技プロの中間評価におけるインパクト調査(以下、中間インパクト調査。詳細は巻末参照)によると、現職教員研修を受講した教員は「指導案の準備」、「教授方法の改善」、「教材の準備」、「生徒の興味喚起」の点において、研修の有用性を高く評価している(図 22)。また、研修後に実施されたモニタリング調査でも、研修前に比べて授業時の態度や技術に改善がみられた(図 23)。
ただし全国的な傾向と同様に、教員の離職率は高く、現職教員研修を受講した教員のうち26%が同地域内の小中学校の教職から離れており、協力の裨益効果を低下させる要因となっている115。
図 22 教員からみた研修の有用性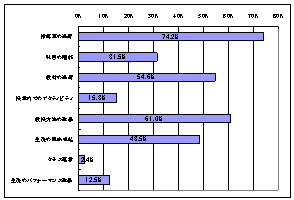 |
図 23 教員の態度の変化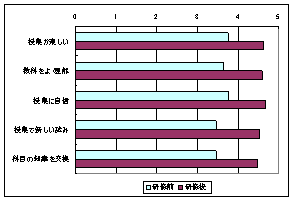 |
| 注:研修を受けた教員にするインタビュー調査。 出所:中間インパクト調査より作成。 |
注:研修を受けた教員に対して、研修前後での教員の授業の態度について5段階評価でモニタリングしたもの(詳細は巻末参照)。 出所:中間インパクト調査より作成。 |
技プロがモニタリングのために実施している学力テストの変化をみると、2000年のベースライン調査時と比較して2002年の調査では、数学については小学校、中学校ともに平均点は上昇している。一方、理科については小学校、中学校ともに平均点は低下している(表 26)。現時点では数学においては成果が上がり、理科においては成果がみられないという結果116となったが、このことは理科の学力の向上には時間がかかるという事情を反映したものとみることができる。また、生徒の学力の向上については、技プロ終了後5~10年後に達成することを目標としていることから、本来の意味での評価結果がでるには、今後10年近く待つ必要がある。
表 26 学力テスト総合点の比較
| 数学 | 理科 | ||||||||
| ベースライン2000 | 中間評価2002 | ベースライン2000 | 中間評価2002 | ||||||
| 対象者数 | 平 均 | 対象者数 | 平 均 | 対象者数 | 平 均 | 対象者数 | 平 均 | ||
| 小学校 | 男子 | 129 | 32.3 | 138 | 34.7 | 129 | 27.0 | 138 | 26.0 |
| 女子 | 197 | 32.0 | 165 | 33.4 | 197 | 28.2 | 165 | 25.9 | |
| 合計 | 326 | 32.2 | 303 | 34.1 | 326 | 27.5 | 303 | 26.0 | |
| 中学校 | 男子 | 99 | 24.2 | 84 | 24.2 | 99 | 24.3 | 84 | 19.4 |
| 女子 | 72 | 20.8 | 94 | 23.9 | 72 | 21.6 | 94 | 21.5 | |
| 合計 | 171 | 22.7 | 178 | 24.0 | 172 | 23.2 | 178 | 20.5 | |
|
注:網掛け部分はベースライン時と中間評価時とで5%水準で統計的に有意な差が認められた部分。 出所:中間インパクト調査より作成。 |
これらの定量的な変化に加えて、ガーナ政府の新しい動きが特筆される。これまでガーナ政府は外国人が基礎教育現場に直接入ることを拒否してきたが、2003年度タマレ郡においてサーキット・スーパーバイザー(3章の3-2(2)参照)を支援するJOCV派遣を要請してきており、基礎教育現場へ日本人の参加を認めるガーナ側の方針の転換とみることができる。これは、これまでのタマレ郡における日本の協力を高く評価している結果と受けとれる。
以上の裨益エリアにおける成果に加えて、教育省や他ドナーは、オーナーシップを基調とし、パートナーシップを大切にした日本の姿勢を高く評価している。特に教育省は「他のローンパートナー(世界銀行等)が口癖のようにオーナーシップを持ち出す割には成果が上がっていないのに比べて、日本の技プロによる協力は実質的に自立発展につながっている」117と、高く評価している。
以上のような結果から、基礎教育の質の向上については、主な裨益エリアでは目に見える効果が現れており、オーナーシップを大切にした日本の援助姿勢は自立発展性にもつながっているといえる。しかし裨益エリアは小さく、教員の離職による裨益効果の低下も見られ、裨益効果は限定的であるといわざるをえない。
4) 成果3「基礎教育システムのマネージメント能力が向上する」
<マクロ指標>
基礎教育システムのマネージメント能力をみるための指標として、教育省予算、予算策定能力、教育省の政策立案能力、郡教育事務所の能力を設定した。
2004年ESP予算のうち教育省予算は総額約5億ドル(図 24)118で、そのうち89%が給与に支出され、管理費と事業費はわずか5%、設備投資にいたっては1%しか分配されていない。マネージメントのための管理費や教育を行うための事業費が少なすぎることは大きな問題である。教育省予算に占める給与以外の支出割合は1999年以降減少傾向にあり119、ESPとGPRSによって抜本的な改革に向けて検討される必要がある。
図 24 教育省の予算内訳(2004年ESP予算)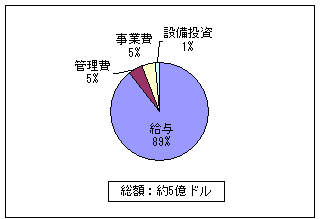 |
| 注:教育省予算のGETファンド、ドナー援助を除く。 出所:AESOP2004-2006予算書(2003)より作成。 |
また2003年から、各省が政策と予算案を出し、財務省がこれを査定した後に各省と折衝することによって予算案が決まるという、MTEFによる財政プロセスがとられた。しかし、これに対しては財務省から各省内の施策・予算案形成プロセスの不適切さ、財政支出の不適切さなど、多くの初歩的な問題が指摘されている120。2004年1月よりGPRS・MTEF・SWAPが連動した本格的な行財政体制が始動しているが、財務省・教育省ともに試行錯誤の状態が続くと思われる。
他方、教育省の政策立案・実施能力についてみると、優秀な人材(海外留学経験者、国際的企業の経営経験者など)が多く、今回面談した他の省庁幹部や他の後発開発途上国(LDC)の行政官などと比べるとかなり高いと判断される121。またESP策定過程において政策立案能力が強化され、ガーナ側も自信を深めているように見受けられる。ただし、教育省次官が2003年11月の拡大ドナー会議において、幹部職員のリーダーシップを喚起する発言を繰り返していたことから、さらなる意識面の高揚が求められていると推察される。
GESに関しては、GES本部―州―郡―学校―コミュニティの教育行政のラインのうち、実際に執行する立場にある郡教育事務所の能力は、地域差が非常に大きい122。このような中、郡議会コモンファンドが直接郡議会に投入されるようになり、教育行政に関する郡議会の裁量が広がりつつあることを背景として、郡のキャパシティの差が教育の質を大きく左右してきている123。さらに、現在改正が審議されている地方自治法が施行されると教育行政は完全に郡議会に委ねられることになるので、ますます格差が拡大することを懸念する声が多い124。
さらに3章の3-4「教育セクターの現状と課題」の「(4)教育マネージメントの問題」のところで述べたように、現在のガーナの教育行政システムにおいては、教育省―執行機関(GES他)―州教育事務所―郡教育事務所―学校―コミュニティの縦のラインをつなぐ連携が弱い。中央の政策や情報を確実に末端まで浸透させ、また末端の声を中央へ届ける仕組みが整備されていない。このため中央においては現場の実態を正確に把握できておらず、現場においては校長や教員の一人一人にガーナの教育を改善していこうという気概が希薄である125。
以上のように、教育省においては他の省庁に比べてマネージメント能力は高いものの、まだ改善の余地がある状況とみられる。他方、GESの地方レベルの執行能力は、地域によって大きな格差があり、また中央と現場をつなぐ縦のラインの仕組みが構築されていないなどの構造的な問題が浮かび上がった。
<日本の貢献指標>
以上のようなマクロの状況において、日本の協力は、図12にみるように政策アドバイザー型専門家による「教育行政のブロック」への支援、技プロによる「教育行政のブロック」と「技プロ実施のブロック」への支援、「教育省・GES・郡教育事務所の行政官の研修員受入(11名)」、などが実施されてきた。
政策アドバイザー型専門家は「教育行政のブロック」を通じて、教育行政を本省から郡教育事務所まで一括して捉え提言すると同時に、現地業務費によってスクール・マッピング事業を支援するなど郡教育事務所へも直接的な技術指導を行っている。技プロは、GES教師教育局から現場までを一括して捉える「教育行政のブロック」と現職教員研修を実施する「技プロ実施のブロック」を通じて支援している。また、特に郡教育事務所には技プロの活動を通じて直接教育マネージメントに関する技術移転が行われている。
2003年11月の拡大ドナー会議での、教育省高官や他ドナー関係者の発言を聞く限り、他のドナーはこのラインを総合的にみる視点が希薄で、その結果現場からの生の声や実態に関する情報が不足している印象を受けた。一方、日本側は、現場を比較的よく見聞しており、実感を伴って教育行政の実態を把握している印象が強かった。このような差は、日本人専門家が現場と同じ目線で実態を把握する姿勢が強いことに加えて、日本の協力が一部の行政レベルではなく、教育省の上層部から草の根レベルまでの「教育行政のブロック」を一貫して、緊密なパートナーシップを保ちながらそれぞれのレベルに直接支援しているところが大きいと考えられる。この点も教育省次官が日本の協力はガーナ側の自立発展につながっていると指摘している根拠とみることができる。
さらに今回の現地調査の観察を通じて、日本の援助の成果は、本邦研修を受講した11名が教育行政の運営を主導的に進める人材として育っていることからも確認された。視察したタマレ郡・北アクアピン郡において、郡レベルの帰国研修員(技プロカウンターパート、郡教育事務所幹部)は、日程調整、会議準備、会議運営、統計整理、業務実績の把握能力などから判断するとマネージメント力が一定のレベルに達している様子が確認された。さらに、技プロ関係者(GES教師教育局、プロジェクトスタッフ、郡教育事務所職員、教員養成校教官等)においても、教育現場の運営等において基本的な能力を有している様子であり、日本の協力の効果とみることができる。
これらの帰国研修員が離職することなく定着していることは、投入の成果が定着していることを示している。また、研修員受入先の大学126によると、研修員の意気込み・問題意識・講義の吸収力ともに年々上昇しているということで、帰国研修員による伝達の効果、あるいは帰国研修員自身の活動が現場全体的の能力向上に波及しているとみることもできる。
以上のように、日本の基礎教育システムのマネージメント能力の向上に対する協力は、他ドナーに比べると裨益エリアは小さいが、「教育行政のブロック」全体に対して包括的に実施している点や各レベルの執行機関とパートナーシップを保ちならが実施している点がユニークであり、ガーナ側のキャパシティ向上に貢献している。また、直接裨益エリアである協力対象地域においては、高い人材育成効果がみられた。
5) 成果4「後期中等教育へのアクセスが拡大する」
<マクロ指標>
後期中等教育へのアクセスの状況をみるための指標として、学校数、生徒数といった提供状況をみる指標と、時系列で唯一入手できた就学者数と女性比率を設定した127。
後期中等教育(高等学校、技術学校)のうち普通科の高等学校数(表 27)は、2001年現在、510校(公立474校、私立36校)で、生徒数は公立だけで約25万人である。総就学率は18%である。また、この後期中等教育レベルでは、GES所管の技術学校が23校あり、生徒数は17,934人となっている。
表 27 高等学校の提供状況(2001年)
| 学校数 | 生徒数 | 総就学率(%) | |
| 高等学校 | 510 | 18 | |
| 公立 | 474 | 249,992 | - |
| 私立 | 36 | - | - |
| 技術学校 | |||
| 公立 | 23 | 17,934 | - |
|
注:「-」は入手できなかった数値。 出所:ESP(2002)。 |
高等学校の就学者数を時系列でみると(表 28)、1998年の約14万人から、2000年の約21万人へと、50%近く増加している。また、女性比率も、同期間で41.9%から43.0%へと増加している。
表 28 高等学校の就学者数と女性比率の推移
| 1998年 | 1999年 | 2000年 | 増加率 | |
| 就学者数 | 138,714 | 204,626 | 207,249 | 49.4% |
| 女性比率(%) | 41.9 | 42.7 | 43.0 | - |
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)。 |
ESRによると、現在中学校の総就学率は61%であり、その結果毎年約23万人が中学校を卒業し、そのうち約7万人が高等学校へ進学し、約14,000人が公立のTVET機関に進学し、それ以外は私立の技術職業教育訓練学校へ入学するか、就業しているとみられる。また、ESRの別の統計では、後期中等教育レベルの何らかの教育機関へ進むものはその学齢人口の17%で、中学修了者の約35%にあたる。さらにESRでは、公立の高等学校への進学希望者が圧倒的に多く、基礎教育認定試験(BECE)でよい成績をとるために、小中学校から私立に行く傾向が強まっていると指摘されている。このように、今後ますます中学修了者が増えることが予想されるため、中学修了者の受け皿整備、それに続く高等教育制度の抜本的な改革が急務である128。
このように、後期中等教育へのアクセスに関しては順調に伸びてはいるものの、今後中学修了者がますます増えることを考えると、需要が拡大することが予想されることから、かなりの数の高等学校や技術職業訓練機関を増やす必要がある。
<日本の貢献指標>
このようなマクロの状況に対して、日本の協力は草の根無償のみである。その実績は評価対象期間において、6件、総額3,400万円である。6件の内訳は、学生寮建設4件(うち1件は女子寮)、校舎・設備整備2件である。ガーナの後期中等教育はほとんど寄宿制であり、学生寮の絶対的な不足が進学率の伸びの障害になっているという指摘もあることから129、学生寮建設のニーズは高い。また、他ドナーがあまり参入していない分野でもあることから130、規模は小さいが日本の支援のインパクトはある。
今回実施したインパクト調査結果によると、草の根無償によって新設された施設に対して、88%が「満足」と回答しており、生徒の満足度は高いことが分かる(表 29)。
また施設の新設によって、「生徒の就学継続の意思」や、「父母の学校への関心」などにも正の影響が現れており(表 30)、アクセス向上の促進要因となっているとみることができる。
|
表 29 草の根無償による施設の満足度 (生徒の評価)
|
表 30 草の根無償によるアクセス向上への影響力 (教員の評価)
|
さらに、本評価調査対象外であるが、ガーナではJOCVによる「ガーナ青年海外協力隊奨学金制度」が1997年に設立され、理数科隊員派遣校の生徒で成績・性向とも優秀でありながら経済的理由によって学業を続けることが困難な者に、1年間の学費と後期中等教育認定試験(SSSCE)131受験料を給付している。2003年度は31名(総額18万円)に給付された。この支援も規模は小さいが、後期中等教育へのアクセスを促進する一助となっている。
このように、後期中等教育へのアクセス向上における日本の協力は、量的なインパクトは小さいながらも、裨益者の満足度は高く、裨益校においてはアクセス促進要因となっており、効果が確認された。
6) 成果5「後期中等教育の質が改善される」
<マクロ指標>
後期中等教育の質の改善状態をみるための指標として、有資格教員の割合、一人あたりの教員に対する生徒数を設定した。
高等学校における有資格教員の割合は(図 25)、1998年以降50%台前半で推移しており、まだまだ改善の余地がある。
一人あたりの教員に対する生徒数は(図 26)、ほぼ20人で横ばいである。これは学習環境という観点からは良好であると判断されるものの、成果2の基礎教育のところでも言及したように、教育マネージメントの観点からみると、改善すべき水準という見方が妥当であろう。
図 25 有資格教員の割合
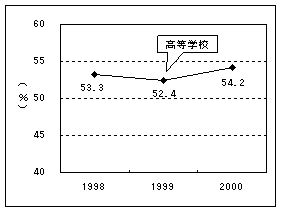
|
図 26 一人あたりの教員に対する生徒数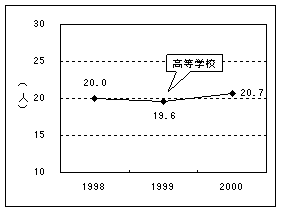
|
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 | 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 |
総じて後期中等教育の質については、現状を分析するのに十分な情報を集めることはできなかった。このことは、この分野の全ドナーの援助総額が2,310万ドルで基礎教育の10分の1であることからも分かるように(3章・表11参照)、これまでほとんどのドナーがあまり関心をもってこなかったことの反映でもある。今回の現地調査においても後期中等教育に関する話は聞かれず、ESPにおいてもまだ具体性のある計画は打ち出されていないと推察される。
<日本の貢献指標>
このような後期中等教育の教育の質の向上に対して、日本は評価対象期間において、計65名の理数科隊員を普通科高等学校へ派遣してきた。ガーナのJOCVは26年の派遣実績があり、当初は都市部のモデル校への派遣が主であったが、これらの学校が一通り一定レベルに達した現在、比較的貧しい州の学校、また教員が不足している学校など、よりニーズの高い学校へ派遣されるケースが多くなってきている132。
ガーナの理数科隊員の場合、多くが教員免許をもっておらず、また大学を卒業したばかりで社会経験もない者も多い133。しかし、隊員同士で自主的に研修を行うなど教授法の向上に努めており134、工夫のある質の高い授業が提供できている。
その結果、教育現場においてさまざまな正の影響を与えていることが観察された。例えば、タマレ郡のJOCV派遣先の高等学校校長は、「JOCVは新しい教授法をもたらしたことに加えて、教員、生徒および地域社会における、時間厳守・規律・勤勉などという生活態度の模範を示している。特に、授業法では教授用教材を使いながら、グループディスカッションを重視した方法を導入し、生徒たちの数学への関心を高めている。また、サッカーや柔道など課外活動にも熱心である」とその貢献度を高く評価している。また、現在理数科隊員が派遣されているいくつかの学校では、1クラス内の学力の格差が大きく135、一緒に授業をできる状態ではないと隊員が判断した場合には、クラスを分けて学力に応じた授業を行うなどきめの細かい取り組みを行っている136。しかし、そのようなきめ細かく工夫に満ちた取り組みは、ガーナ人教師には受け継がれていないという137。
インパクト調査によっても、理数科隊員の協力成果を確認することができた。JOCVの裨益校では、教員の目からもみても「JOCVによって生徒の学習意欲が高まった」と評価されている(表 31)。また、生徒も「JOCVによって理数科が好きになった」とする者が半数、「ある程度そう思う」も合わせると6割が、理数科への好感度を高めている(表 32)。
表 31 JOCVによって生徒の学習意欲は高まったか(教員の評価)
出所:インパクト調査より作成。 |
表 32 JOCVによって理数科が好きになったか (生徒の評価)
出所:インパクト調査より作成。 |
成果2の基礎教育の質のところ( 3)成果2)で言及したように、タマレ郡においてサーキット・スーパーバイザーを支援するJOCV派遣を要請してきたことは、このようなJOCVのこれまでの実績に対するガーナ側の高い評価の表れと受け取れる。
さらに、ガーナにおけるJOCVは、5-3「プロセス」の評価のところで言及したように、技プロ、開発調査、草の根無償などの案件発掘・形成に貢献してきている。これは、JOCVが協力の実施体制の「草の根のブロック」で主に活動しており、最終裨益者の問題点とニーズを肌で感じ、それをJICAガーナ事務所へ伝えてきた結果である。
以上のように、後期中等教育の質の向上に関する日本の協力の効果は、量的インパクトとしては小さいながらも、長年の伝統の上に築かれた隊員の自主的な工夫と努力によって、草の根レベルで教員や生徒に直接的に影響を与えており、少なからず教育現場に正の変化をもたらしていることが確認された。
|
BOX 10 青年海外協力隊(JOCV)の目標とは 青年海外協力隊(JOCV)事業を評価するにあたり、その目標の設定にはしばしば議論が分かれる。JOCVはボランティアでありその目標はあくまで青年の人材育成であるという考え方がある一方で、ODAの一環で行われるのであるからあくまで派遣国に経済社会的利益を与えなければならないという考え方もある。今回の評価では、あくまで教育セクターの向上に資するODAの一環であるという立場から後者の考え方に立って評価した。 |
7) 成果6「技術職業教育へのアクセスが拡大する」
目標体系図B(図 13)にも示したとおり、成果6~成果7については、マスタープランというこの分野の上位政策の改善に資する協力を実施していたり、多くの草の根無償がJOCVによって案件形成されたうえで実施されているなど、協力効果を適切に分割することが難しい。従って、日本の貢献については成果7のところで、成果6~成果7を一緒に検証することとする。
<マクロ指標>
技術職業教育へのアクセスの拡大の指標として、ポリテクニックの入学者数、その他の技術職業教育の機会を設定した138。
1991年の高等教育改革を経て、ポリテクニックの入学者数は、1992年度の1,299人から2000年度の18,470人へと、14倍にも増加している(図 27)。この増加は、高等教育改革によって各州1校にポリテクニック設置を目指して、州内の技術高校をポリテクニックに格上げした結果であり、学校によってはまだポリテクニックの体裁をなしていないところもある139。男女比は男:女=78:22と格差が大きい140。
図 27 ポリテクニックの入学者数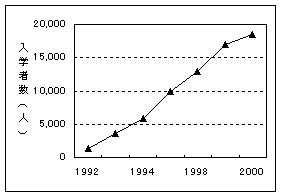 |
| 出所: NCTE資料より作成。 |
また、ポスト基礎教育の技術職業教育の機会としては、2002年時点で、非公式な見習い制度、公式な見習い制度、職業訓練校(公立・私立)、技術高校、農業高校の5つのコースがある。しかし、そのうち政府として把握しているものは、3章・表6にまとめたものだけである。主なものでは、技術学校(23校、17,256人)、見習い訓練センター(公立19校、私立22校)、国家職業訓練校(29校)、雇用促進地域職業訓練センター(ICCES)(72か所)などである。
このような状況の中、新しいTVET政策として、教育省と人材開発雇用省は共同で、2001年に「ガーナTVET政策フレームワーク・ドラフト」を完成させた。1987年の教育改革以降アカデミック志向から実用的な技術職業教育への見直しを打ち出してきたが、国民のニーズと合わずほとんど成果がみられなかったことから、従来の方針をやや転換し、技術高校、見習い制度、農業高校等などを再整備し、普通科高等学校に代わる優良な進学先として、前期中等教育卒の生徒たちの受け皿を広げる方策を打ち出している141。
以上のように、政府としては1987年の教育改革以降方策を打ち出していたものの、基礎教育を優先させてきたために余力がなく手付かずの状態であったが、クフォー政権になってから、少しずつ改革に着手しつつあるという状況である。ESPが本格的に開始され、今後さらにその動きが加速するものと予想される。
8)成果7「技術職業教育の質が改善される」
<マクロ指標>
技術職業教育の質の改善に関する指標として、ポリテクニックの教員の数、カリキュラムを設定した142。しかし、全国的な情報は得られなかったため、ここでは、調査団が訪問したアクラポリテクニックを例にとり、この分野の質の現状について検証していきたい。
現在、ガーナには、ポリテクニックが各州に1校、全国に10校あるが、アクラポリテクニックはその中でも、教育の質・設備においてトップといわれる学校である。学生数4,748名で、3学科があり、エンジニアリング学科(学生割合26%)、応用数理学科(同19%)、ビジネス管理学科(同56%)となっている。教官数は非常勤も含めて131名、教官の最終学歴は博士2名(うち1名は校長)、修士レベル66名、学士レベル75名となっている。
カリキュラムの具体的内容については入手できなかったが、校長へのヒアリングの際校長自身がESPについて認識していなかったことは、高等教育機関の長としての資質・マネージメント能力に疑問を感じさせるものであり、引いては学校全体の教育の質についての疑問を禁じ得なかった。また、アクラポリテクニックの校内を視察したところでは、エンジニアリング学科の棟にも実験室などの設備は見当たらず、“中堅技術者を養成する高等教育機関”としてのインフラ整備がなされているとはいえない印象を受けた。他方、ビジネス管理学科と思われる棟は、夕方にもかかわらず学生が多く、授業が行われている教室は学生でいっぱいで、熱心に講義を聴いている学生の姿が印象的であった。「就職に有利なビジネス系の方が、人気がある」という校長の言葉を裏付けるような校内の状況であった。
以上、非常に限定的な情報ではあるが、ポリテクニックの中でもトップといわれるアクラポリテクニックにおける観察、および国家技術職業教育訓練調整委員会(NACVET)・人材開発雇用省におけるヒアリング等から判断すると、現在のガーナの技術職業教育の質は相当低いといわざるをえない状況である。
<日本の貢献指標>
成果6「技術職業教育へのアクセスの拡大」および成果7「質の改善」に対する日本の協力は、開発調査(約3億円)、草の根無償(12件、総額5,200万円)、JOCV(職業訓練21名、高等教育7名、計28名)、政策アドバイザー型専門家の現地業務費によるフィージビリティ調査(340万円)がある。開発調査の3億円は、日本の投入としては大きな規模であるが、世界銀行の「職業訓練・インフォーマル」プロジェクト(960万ドル)(3章の3-5参照)に比べると決して大きくない。
開発調査は、高等教育レベルにおける技術教育の改善に資するマスタープラン策定を目的とした。そして、策定過程では、ガーナ側のオーナーシップを高めるために参加型アプローチを取り入れ、多くのポリテクニック関係者を巻き込んだ。その点について、ガーナの国家高等教育評議会は、関係者の知識・意識面でキャパシティビルディングにつながったと評価している143。また、マスタープランで採用されているCBT手法(産業界のニーズに直結した適切な教育を提供するために企業を活用しようという先駆的な技術教育の手法)にはガーナ側関係者の関心が高く、その結果、ESPのTVET分野にその考え方が採用された。また、世界銀行が同手法を取り入れた新規案件を立ち上げるなど他ドナーも注目しており、今後のガーナのTVET分野の方向付けに影響を与えた。
しかし、その後ガーナ側からマスタープランを実施するための具体的なアクションが起こされなかったため、2003年4月にJICA主導で政策アドバイザー型専門家の現地業務費によるフィージビリティ調査「技術教育に係るポリテクニックの現状調査」が実施されている。その後2004年にはJICAによりマスタープランに基づく新規案件の形成調査が実施された。このように、日本はマスタープラン策定以降、積極的に技術職業教育分野における協力を進めて、他ドナーからも注目されている。
草の根無償の12件の内訳は、職業訓練校等6件、ICESS5件、その他が地域団体1件である。技術職業分野の草の根無償の多くは、JOCVによって案件発掘・形成されている。コミュニティが運営する最末端の職業訓練機関であるICCES144は、全国に72施設あるが、このうちの12施設(総施設の17%)が草の根無償の支援を受けていることになる。ICCESを所管する人材開発雇用省のヒアリングによると、同省の予算は少なく145、ドナーの支援もほとんど入っていないため、日本の草の根無償は非常に大きな貢献となっていると高く評価している。また、JOCVは建設された施設を有効に活用し、職業訓練プログラムの量・質を充実させるなど大きなインパクトをあげている例が多く146、この分野において日本はプレゼンスを発揮している。
さらに、最終裨益者による評価をインパクト調査の結果で確認する。「アクセスへの拡大」に関しては(表 33)、教員は「学習環境に正の影響を与えた」と感じている人が83%、「父母の学校への関心が高まった」と感じている人が61%と、草の根無償やJOCVがアクセス促進効果になっていることを示している。その結果「就学率に改善がみられた」と感じている人も86%(表 34)と高い割合となっている。
| 表 33 草の根無償とJOCVによる影響 (教員の評価)
出所:インパクト調査より作成。 |
表 34 草の根無償とJOCVによる影響 (教員の評価)
出所:インパクト調査より作成。 |
「質の改善」については、教員では「生徒の学習意欲の向上」を感じている人が94%と多い(表 35)。また、学校運営委員会の評価では「教員の仕事に対する姿勢」へ何らかの効果を感じている人が100%、「好ましい学習環境づくり」へ何らかの効果を感じている人が93%となっている(表 36)。このように、JOCVや草の根無償によって生徒を取り巻く環境にさまざまな正の変化が起こっていると推察される。
表 35 草の根無償やJOCVによる影響 (教員の評価)
出所:インパクト調査より作成。 |
表 36 草の根無償やJOCVによる影響 (学校運営委員会の評価)
出所:インパクト調査より作成。 |
以上のように、「技術職業教育へのアクセス・質」に係る分野での日本の協力は、規模は小さいながらも、政策レベルで影響を与えている。また、草の根レベルでは、直接裨益者の教育機会促進の効果や学習意欲向上の効果がみられる。それぞれのレベルで、それぞれのスキームの特徴を生かして、寄与している。
9)中期目標1「すべての子どもが質の高い基礎教育を受けられるようになる」
<マクロ指標>
基礎教育に対するわが国の協力の中期目標1「すべての子どもが質の高い基礎教育を受けられるようになる」の現在の達成度を計る指標として、小学校から中学校への進学率、州別の総就学率、小学6年生と中学1年生の学力テストの結果を設定した。
最初に、小学校から中学校への進学率をみると(図 28)、1998年以降の傾向としては、90%前後を上下しているものの、近年は低下傾向にある。また、州別の小中学校総就学率をみると(図 29)、ノーザン、アッパーイースト、アッパーウエストの北部3州は特に低さが目立つ。
図 28 小学校から中学校への進学率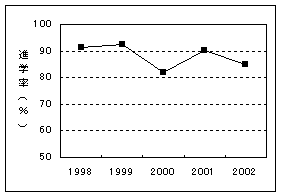
|
図 29 小中学校の総就学率(2000年)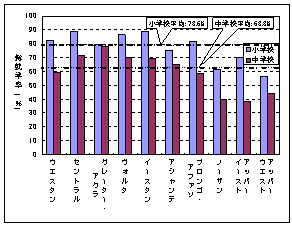 |
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)、およびESP(2003)のAnnexより作成。 | 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)、およびESR(2002)より作成。 |
ガーナの小学生の学習到達度を計るための学力テストとしては、「標準参照テスト(Criterion Reference Testing:CRT)」148がある。図30・31にみるように、CRTの結果は、1994年以降改善がみられるが、公立と私立の差は大きい。例えば、2000年における合格率は、公立校では英語9.6%、算数4.4%と依然非常に低く、同年の私立校の英語77.9%、算数53.7%と比べると、公立校の低迷は深刻な状況であるといえる。
図 30 小学校6年生のCRTにおける合格率(英語)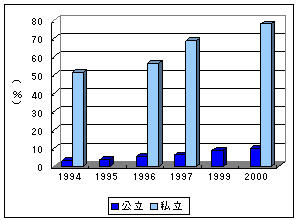
|
図 31 小学校6年生のCRTにおける合格率(算数)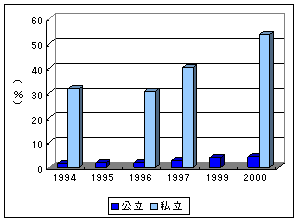
|
| 出所:“Report on the Administration of CRT”(教育省)(2002)より作成。 | 出所:“Report on the Administration of CRT”(教育省)(2002)より作成。 |
中学校の修了テストとして「基礎教育認定試験(Basic Education Certificate Examination:BECE)」149が実施されている(図 32)。BECEでは英語、理科、数学、社会の4科目が実施されているが、2001年においては数学の合格率が一番低い。2001年の合格率は、社会以外は6割を切っている。また社会以外は総じて、低下傾向にあるのが懸念される。
図 32 BECEの合格率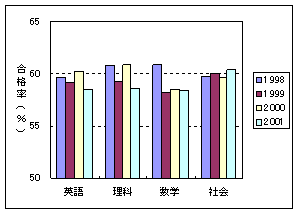
|
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 |
以上の指標に基づく検証によると、fCUBE以来ガーナがもっとも集中して取り組んできた基礎教育の質の改善については、総じてここ数年低下している傾向がみてとれ、憂慮されるところである。
<日本の貢献指標>
日本としては、中期目標1「すべての子どもが質の高い基礎教育を受けられるようになる」を目指して、成果1~成果3のコンポーネントによって一丸となって取り組んできている。特に主軸となる技プロを中心としたプログラム的展開は、成果2と成果3の達成のために、現場レベルで確実に成果を上げている。しかしながらマクロ指標でみてきたとおり、特に成果2の「教育の質」に関する分野でガーナ全体の状況はどちらかというと悪化傾向にあり、これが中期目標1の達成を遅らせる可能性は否定できない。
しかし、中期目標1は、技プロの上位目標「小中学校生徒の理数科の学力が向上する」とほぼ同じ達成目標レベルであり、技プロの上位目標は技プロ終了後5~10年後、つまり2010~2015年に達成することを目指していることから、成果2の達成に向けて今後その貢献が成果として表れることを期待したい。しかも、技プロとしては2002年12月の中間評価を踏まえ、上位政策への働きかけと、校内研修など波及効果の面的拡大を強める方針を打ち出しており(4章の4-2参照)、今後、本目標達成に向けて、さらに大きく貢献することが予想される。また、成果1~成果3に関する郡や草の根レベルでの協力は、各レベルのキャパシティの向上に確実に貢献しており、裨益規模は小さいながらも重要な貢献をしていると評価できる。
10)中期目標2「産業に不可欠な人材養成の基盤を拡充する」
<マクロ指標>
中期目標2「産業に不可欠な人材養成の基盤を拡充する」の現在の達成度をみるための指標として、後期中等教育の地域別総就学率、後期中等教育認定試験結果、大学の入学者数を設定した。
後期中等教育における全国の就学率は17.6%であるが、地域別にみると(図 33)、6州で平均以下であり、特に低い州はウエスタン州(12.1%)、ブロンゴ・アファソ州(13.3%)、グレーター・アクラ州(14.1%)などとなっており、格差が目立つ。
図 33 後期中等教育の地域別総就学率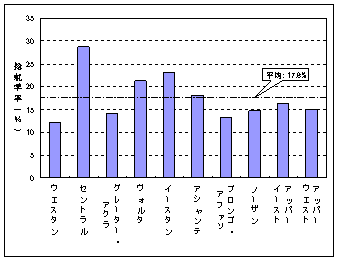
|
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)、および“2000 Population & Housing Census”より作成。 |
大学入学資格試験となる「後期中等教育認定試験(Senior Secondary School Certificate Examination:SSSCE)」150は、後期中等教育の最終年に実施される。1998年以降のSSSCEの成績をみると(図 34)、英語に関しては1998年以降順調に伸びているが、理科の成績は総体的に低く、数学は2001年の落ち込みが激しく、合格率50%を割っている。
また、SSSCEの結果は地域格差が大きく、総就学率がもっとも高いセントラル州(28.7%)ともっとも低いウエスタン州(12.1%)では大きな開きがある。また、女性比率は、北部3州で20%台から30%台(アッパーウエスト23.1%、ノーザン29.6%、アッパーイースト35.3%)と低く、男女格差が顕著である。
図 34 SSSCEの合格率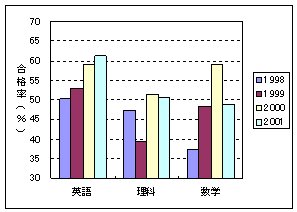
|
図 35 大学入学者数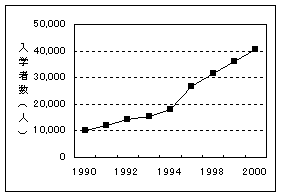
|
| 出所:“Education Indicators at a Glance”(2002)より作成。 | 出所: NCTE資料より作成。 |
大学の入学者数(図 35)は、1990~2000年で約4倍に急増している。これは、1991年の高等教育改革によって、既存の大学の受け入れ枠を拡大したことによるものである。なお、ESRによると、国立大学やポリテクニック以外の高等教育機関への入学者数の把握は困難であるが、概ね当該年齢人口(18~22歳)の約3%しか高等教育に入学できておらず、非常に狭き門であるとされている。大学における男女比は、男:女=70:30となっており、依然格差が大きい151。
<日本の貢献指標>
この中期目標2「産業に不可欠な人材養成の基盤を拡充する」を目指して、日本としては、成果4~成果7のコンポーネントを実施している。特に成果6~成果7に関する投入である開発調査によるマスタープランの考え方は、ESPに取り入れられ、上位政策に影響を与えている。草の根レベルでは、JOCV、草の根無償がコミュニティレベルで確実に実績をあげ、最終裨益者にもプラスの効果が発現している。このように、中期目標2の達成のために、上位レベルと草の根レベルにおいて効果的に寄与しているといえる。この分野はこれまで他ドナーの参加が少なく、現段階では日本のプレゼンスは高いといえる。
11)長期目標「ガーナの社会経済開発を担う人材を育成する」
<マクロ指標>
長期目標「ガーナの社会経済開発を担う人材を育成する」は、ガーナ政府がVision2020やGPRSで掲げた最終目標と同程度の目標であり、2020年頃の達成を目処とするのが妥当である。従って、本評価においては参考程度に確認するにとどめる。この長期目標の現在時点での達成度をみるための指標として、識字率、教育到達度152(15歳以上人口がどの教育レベルまで到達しているかを表す指標)、職業、雇用状況を設定した。
識字率に関しては(図 36)、2000年の非識字率は45.9%と依然高い。教育到達度は(図 37)、2000年においては基礎教育修了率はわずか10%以下、初等教育修了率は33%、まったく就学経験なしが32%となっており、「万人のための教育」という最終目標にはまだ程遠い状況である。
図 36 2000年・識字率(15歳以上人口)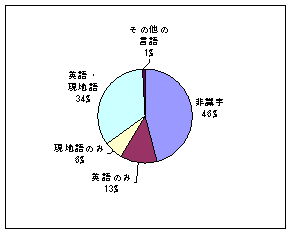
|
図 37 2000年・教育到達度(15歳以上人口)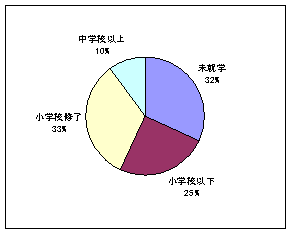
|
| 注:母数=11,105,236。 出所:“2000 Population & Housing Census”(2002) より作成。 |
出所: GPRS(2003)より作成。 |
また、職業については(図 38)、7歳以上で就業中の者では、農業等が49%と約半数を占める一方、高度な知識や技能を必要とする専門・技術分野は9%に留まっている。さらに雇用状況については(図 39)、民間企業は8%と少なく、特別なスキルを必要としない民間自営(行商や縫製など)が80%と圧倒的に多い。これらの統計から、民間産業の育成が遅れていると同時に、それを担える人材が輩出されていないことがうかがえる。
図 38 2000年・職業(7歳以上で就業中のもの)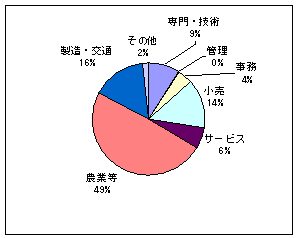
|
図 39 2000年・雇用状況(7歳以上)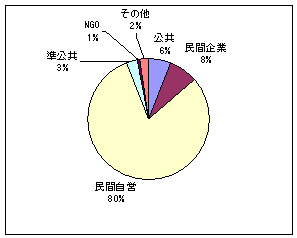
|
| 注:母数=9,039,318。 出所:“2000 Population & Housing Census”(2002)より作成。 |
注:母数=9,039,318。 出所:“2000 Population & Housing Census”(2002)より作成。 |
<日本の貢献指標>
この長期目標「ガーナの社会経済開発を担う人材を育成する」は、前述したように達成時期は2020年頃が妥当であり、ここでは今後の貢献発現の可能性について検証する。この長期目標の達成に向けて、日本はガーナ国別援助計画の下、本セクターのみならず他セクターも含めて、オールジャパンとして取り組んでいる。
教育セクターについてみると、中期目標1~2の貢献指標でみてきたように、中期目標1ではこれから技プロを中心として上位レベルへのアプローチを開始している。中期目標2ではすでに政策レベルに貢献しており、今後マスタープランに基づいて新たな協力を立ち上げる準備をしている。従って、中期目標1~2ともに、比較的近い将来に大きな貢献に拡大することが予想され、それが長期目標の貢献に資する可能性は十分に高い。
(2) インパクト
「インパクト」では、ガーナ・日本双方の上位政策へ影響があったかどうか、また双方の関係者に正負のインパクトがあったかどうかの視点から考察する。
1) 上位政策への影響
・ガーナにおける影響
ガーナの上位政策への影響として、技術教育分野において開発調査で策定されたマスタープランの新しい考え方や手法がESPに反映された点が挙げられる。また、同マスタープランに基づく協力の案件形成がJICAによって実施されており、今後技術教育分野において日本の協力が開始されると、同分野における日本のイニシアティブが強まることが予想される。
・日本における影響
外務省のBEGIN策定においては、文部科学省の「国際教育協力懇談会」での議論が活用されている。同懇談会には、ガーナ協力の中核をなす広島大学教育開発国際協力研究センターの関係者が情報提供を行っており、間接的にガーナにおける協力経験が、BEGINの策定に影響を与えていると考えることができる。またBEGINの骨子が、ガーナでの協力の基本方針と共通する部分が多いことなどからもその影響はうかがえる。
また、今後BEGINが遂行される際には、特に「わが国の新たな取り組み」における「大学コンソーシアム方式」の成果と、技プロにおける現職教員の活用などの点において、同様な教育分野の協力に影響を与えると思われる153。
2) 関係者への影響
・ガーナ側
アフリカ諸国の理数科教育関係者のネットワークであるSMASSE-WECSA(詳細は4章の4-2参照)の第3回会議が、2003年、首都アクラで開催された。アフリカからの参加は18か国と過去最大となり、アフリカ大陸全体の理数科教育会合の体裁を整えつつある。この会議をケニアと共同で主催することによって、ガーナ国内の理数科教育関係者の士気が高まり、ガーナ側も「ケニアにならって自分たちの経験を周辺諸国に伝えていく段階にきている」という認識を持ち始めた154ことは特筆に価する。
・日本側
SMASSE-WECSA会議は、回を重ねるに従って、全アフリカ域内における日本の理数科教育支援に対するプレゼンスを高めてきている155。特に今回のガーナでの成功によって「アフリカ教育開発連合(Association for the Development of Education in Africa:ADEA)」への加盟とADEAの理数科教育の分科会立ち上げへの期待がさらに高まった156。これによって、BEGINの「わが国のあらたな取り組み」の分野の「国際機関との広範な連携と推進(ADEAへの参加等)」と謳った目標の遂行に一歩前進したといえる。
また、ガーナ教育セクターにおける協力は、本邦研修を通じて、研修員を受け入れている日本の大学関係者(教員、学生)や、受け入れ地域の県教育委員会、地方自治体、住民、視察先小中学校児童・生徒等において、国際交流や国際理解の場を提供しており、大きな正のインパクトを発現している157。日本の途上国協力が、協力実施をしている国だけでなく、日本国内の人々にも大きな正の影響を与えている好例である。
さらに2004年度から国立大学が独立法人化する中で、ODAに対する取り組みは国立大学の今後のひとつの方向性を示していることから、これらの大学が積極的にODAに関わろうとする姿勢を引き出している158。また、ガーナでの教育セクターでの協力経験は、文部科学省が進めている教育開発国際協力センター(広島大学と筑波大学に設置)の活動を通じて、外務省と文部科学省の積極的な相互交流を深め、ODA関係機関や文部科学省主催により国際教育協力に関するさまざまなシンポジウムやセミナーが活発に開催されており、教育セクターにおけるODA事業に関する議論が活気づいている。
(3) 自立発展性
「自立発展性」は、ガーナ教育セクターの自立発展性を予測し、またその自立発展に対する日本の協力の貢献について考察する。
1) ガーナ教育セクターの自立発展性
ガーナでは今後本格的に教育SWAPであるESPが展開していく。ESPでは、4つの重点分野「教育機会へのアクセスの拡大」、「教育の質の向上」、「教育マネージメントの強化」、「技術職業教育訓練(TVET)の推進」を設定している。有効性のところで考察してきたとおり、この中でも特に「教育の質の改善」と「教育マネージメントの改善」が停滞している。加えて、MDGsの目標「2015年までの初等教育就学率100%」や「2005年までに初等教育におけるジェンダー格差解消」などはアクセス拡大の観点からも順調に進捗しているわけではない。このような背景には、ガーナの国家予算の絶対的な不足がある。2004年度予算では国家予算の27%を教育省予算に費やしているが、そのほぼ9割が人件費に消費され、事業費が捻出できないということは、そもそも国家予算が必要量を満たしていないためである。ESRでも「しばらくは経済成長による歳入増加は見込めない」という予測がある中、教育セクターにおいても急激な予算増は望めず、従って、教育セクター全体の自立発展についても、財政的な自立を含めた自立発展は、国家予算が増えない限り期待できないといわざるをえない。
また、2003年春に省庁再編を実施したが、それでも人口2,010万人規模の国でまだ39省庁を抱えていることや、中央省庁から直接110郡を監督する行政システムなど、国家全体の行政システム自体にもまだ改善の余地があり、そのしわ寄せが教育セクターにきているともいえる。
ただし、教育省の人材については、有効性でみてきたとおり、他のLDC諸国やガーナの他省庁と比べると格段に政策立案能力が高い。ESPが本格的に始動したことから、オーナーシップが高まることによって、さらにそのキャパシティが向上することが予想される。
2) 日本の貢献の度合い
有効性の成果3のところで検証したように、日本の協力はパートナーシップを基調としてガーナ側のオーナーシップの下で、互いに協力しながら積み上げていくプロセスを重視しており、この方法は人材育成に確実に結びついている159。人材育成は自立発展のための必要条件であり、日本の協力が自立発展の一端に貢献しているということができる。今後も、わが国がODA政策やBEGINの理念の下、このスタンスで「人づくり」を支援することは、ガーナの自立発展性を高めることに有効に働くものと思われる。
以上、「結果」という視点から、「有効性」、「インパクト」、「自立発展性」という3つの評価項目で評価してきた。簡単に振り返ると、ガーナの教育セクター全般については、基礎教育の質の向上については停滞気味でありまだまだ改善すべき点が多く、ポスト基礎教育についてはガーナ側としてはまさにこれから本格的に着手といった状況である。これに対して日本としては、基礎教育については直接裨益レベルにおいては協力効果が出ているが、今後はより大きな波及効果が求められる。また、ポスト基礎教育については、高等学校や技術職業教育分野など、日本が地道に支援して道筋をつけてきた分野だけに、今後イニシアティブをとっていくことが期待される。加えて、ガーナ側・日本側の双方によい意味での正のインパクトも発現している。また、ガーナ教育セクター全体の自立発展性については、国家予算全体が増えない限り、財政的な自立を含めた自立発展は当面難しいものの、人材は確実に育ってきているといえる。
5-5 まとめ
(1) 目的
日本のガーナにおける教育セクター協力は、ODA大綱や中期政策などのODA基本政策および新たな教育支援策であるBEGIN、さらにはガーナ国別援助計画とほぼ整合している。また、ガーナ側の1990年代後半の開発計画であるVision2020や、現在の国家開発計画であるGPRSなどとも整合しており、妥当であると判断される。
しかし、ガーナ国別援助計画は2000年に策定されたものであり、2001年以降、ガーナにおいては政権交代、拡大HIPCイニシアティブ申請、GPRS策定といった大きな政策的変化が生じている。さらに2004年1月からは、GPRS、MTEF、ESPそしてMDBSのすべてリンクした総合的な行財政システムと援助モダリティの変化が生じている。
(2) プロセス
日本の協力の策定過程は、日本の戦略やガーナ側の開発課題に対応しながら、ODAの既存スキームを柔軟に活用し、かつ案件同士が相互に連携と調整を繰り返しながら発展しており、総じて適切であったと判断される。特に政策アドバイザー型専門家、日本・ガーナ双方の大学関係者、JOCVの参加が、案件の質の向上に寄与している。加えて、90年代後半からfCUBEの実施やSWAPの策定プロセスが進展し、ドナー間の調整会議が頻繁に開催される中で、日本としてもこれらに積極的に参加し、日本の協力案件の策定もスムーズに行われてきた。
実施体制については、図 12のように、在ガーナ日本大使館とJICAガーナ事務所が緊密な連携がとられてきた。また、「教育行政のブロック」、「技プロ実施のブロック」、「草の根のブロック」というガーナ教育セクターにおける3つのレベルの異なるブロックに対して包括的に対応してきたことが、協力の効果を高めている。また主要なカウンターパートのほとんどを本邦研修に参加させたことによっても協力の実施の効率性を高めている。他ドナーとの連携については、ドナーコミュニティの対話の過程でいくつかの連携案件が実施されており、適切であったといえる。
(3) 結果
評価対象期間(1998~2003年度上半期)における日本の援助総額は概算で17.4億円である。このうち目標体系図に該当する部分の投入は16.4億円で、ドナー援助全体のおおよそ5%に過ぎない。日本はガーナを教育セクターの援助重点国と位置づけているが、それにしては投入規模が少ないといわざるをえない。他方、このような援助規模の下で、日本は基礎教育、ポスト基礎教育(後期中等教育、技術職業教育)を支援しており、他のドナーの協力が基礎教育に集中しているのに対して全レベルに比較的まんべんなく支援してきた。
基礎教育の質の向上は、ガーナの教育セクターの最大の課題である。特にその根幹である教員の質の向上が最優先課題である。日本は技プロを中心としたプログラム的展開(援助総額7.1億円)で、教員の「質の向上」と教育行政の「マネージメントの向上」を重点に支援しており、直接裨益した人・地域においては大きな成果をあげている。また、日本のODAはパートナーシップ・オーナーシップを大切にしつつ、前述の3つの異なる教育レベルに対して働きかける包括的な実施体制と本邦研修を受けた関係者を活用することなどによって、その促進効果をあげている。これまでは110郡中3郡へ集中的に投入してきたが、今後は政策への働きかけや校内研修の実施の強化などによってより波及効果を高めていく計画である。また、草の根無償ではハードの整備というだけなく、地域社会の教育への関心を高めるという点においても効果を上げている。
ポスト基礎教育においては、産業振興に資する人材養成がこれからの大きなテーマとなっているが、他ドナーの参入もまだ少ない。日本は、この分野にJOCV(援助総額5億円)、草の根無償(援助総額1億円)などで以前から協力してきており、後期中等教育以上の学校現場に直接新しい指導法の導入などにより刺激を与えており、裨益者から高く評価されている。加えて1999年より、技術教育分野で開発調査を実施しマスタープランを作成し、教育SWAPであるESPのポリシーとして取り入れられるなど、同分野において存在感を示している。現在、同マスタープランに基づく具体的な案件が形成されつつあり、今後さらにこの分野への協力が拡大していくことが期待されている。
インパクトとしては、上位政策への影響として、開発調査のマスタープランの基本的考え方がESPに採用されていることがある。また、アフリカ域内で、日本が理数科教育協力のイニシアティブをとる気運が生まれてきている。日本の国内においては、大学がODAに積極的に参加していくという1つのモデルも提示している。さらに研修員受入を通じて、国内の関係者に正のインパクトを与えている。
ガーナ教育セクターの自立発展については、財源難という根本的な問題が解決しない限り難しいというのが実情である。しかし、日本のオーナーシップを大切にした協力姿勢は、実質的に人造りに寄与しており、自立発展の観点から高く評価される。
82 2003年8月改定。
83 外務省では、2000年度から国別援助計画の策定を開始しているが、ガーナはその初年度の対象国となっている。
84 この時点で、ガーナは拡大HIPCイニシアティブへの申請をしていなかったため、「わが国としてもガーナの自助努力を高く評価し、今後ともガーナの債務負担能力を勘案しつつガーナへの支援を検討していく」としている。
85 TICADIIにおいても域内協力の重要性が取り上げられていることに触れ、「これまでのわが国の協力実績を踏まえ、ガーナに対して、西アフリカ地域の発展と安定に資する南南協力を推進していくことが必要である」としている。
86 ガーナ政府の方針により、これまでは基礎教育分野へJOCVを派遣することはできなかった。
87 派遣中の隊員によると、高校生で九九ができない生徒も珍しくない、といった状況である。
88 臼井(2002)による。
89 横関他(2003)による。
90 『政府開発援助白書1994年版』による。
91 ガーナJICA事務所元所長、GES職員スタッフ、ヒアリングによる。
92 多くのJICA在外事務所では、職員のマンパワーは本来業務をこなすだけで精一杯の体制であり、援助協調のためのドナー会議の出席依頼がきても、対応できる職員がおらず、「日本は欠席」となるケースが少なからずみられる。このような状態が続くと、そのドナーコミュニティにおける日本の存在感は非常に小さくなり、他方で、情報量が限定的となり、ますます、日本の参加できる機会が狭まってくるという悪循環に陥る、というケースがみられる。
93 案件形成、調査団の受け入れ・協議等。
94 我喜屋(1999b)による。
95 元GES副総裁ヒアリングによる。
96 我喜屋(1999b)による。
97 2001年教育省が財務省へ申請、2003年1月活用開始。詳細は4章4-2(2)8 参照。
98 この分野では、オランダが、後期中等教育の技術学校に対して、2,000万ドルの援助を実施。支援内容は、教室の増改築、実験室等ハードの整備と、教材供与、教員研修、カリキュラム改訂等のソフト支援。実施時期は不明。
99 我喜屋(1999b)による。
100 在ガーナ日本大使館、JICAガーナ事務所に対するヒアリングによる。
101 元専門家、元JICAガーナ事務所長にアリングによる。
102 人材開発雇用省ヒアリングによる。
103 なお今回の調査時に主にUNICEFより、草の根無償の案件形成にもっと住民参加を取り入れるべきであると指摘されている。、これは一般論としてコミュニティベースの学校を作るドナーは、もっと住民参加を強化するべきであるという主旨のコメントである。他方、評価団のタマレ郡教育事務所におけるヒアリングでは、多くのNGOが郡教育事務所を通さず直接住民団体を支援し、郡教育事務所もNGOが建設する学校を把握していないという状況があり、問題である。
104 元JICAガーナ事務所長ヒアリング、奥川(2002)、GTZヒアリング等による。
105 大学コンソーシアム関係者ヒアリング、技プロ専門家ヒアリング、現地視察時のカウンターパートの直接観察による。
106 松田専門家ヒアリングによる。
107 松田専門家ヒアリングによる。
108 松田専門家コメントによる。
109 黒田(2004a)による。
110 3-5で触れたように、EUは年間5,000万ドルを一般財政支援しており、そのうち毎年約500万ドルが学校建設に活用されている。奥川専門家の試算(奥川2002)によると年間約260校が建設されているという。ただし協力期間が不明のため、総建設数は不明。
111 今回ヒアリングした5つのドナーのうち、日本のハード面に対する支援を知っていたのは1ドナー(UNICEF)だけであった。
112 ESR(2002)による。教員養成校卒業生は都市出身者が多く、農村に行きたがらない。また農村部の学校には教員住宅が完備していないことも不人気の原因であるため、教員用住宅の建設も援助の主要な分野である。日本のノンプロ無償見返り資金でも、2003年度の活用で北部3州に40棟の教員住宅が建設される予定である。
113 World Bank(2003)による。同報告書によると、1994年のベースライン調査時点では小学校の30.7人で国際的な基準と比べると極めて低かったが、2001年現在32.9人で、2.2人改善しているとしている。
114 UNICEF (2003)による。
115 国際協力事業団(2003)。
116 中間評価時の学力テストの測定方法について、プロジェクト内部でも、学力テストの対象となる生徒の選択の方法、テスト問題等、改善点が指摘されている。
117 教育省次官、元GES副総裁ヒアリングによる。
118 第3章・表8にあるように、その他の財源として、ドナー、その他(GETファンド、郡議会コモンファンド)があり、総額は約7億ドル。
119 ESR(2002)、UK Department for International Development(2003)による。
120 省内のコンセンサスを経ないで予算案が出されており、財務省に提出された後、提出した省内からクレームがでるなどのトラブルが多かった。また、施策も国民のニーズというよりも特定の人々の利害を反映しているものがみられ、問題である(2003年11月の拡大ドナー会議における財務省副大臣のスピーチより)。
121 豊吉(2002)でも指摘されている。
122 2003年11月拡大ドナー会議による。
123 2003年11月拡大ドナー会議および、教育省・GESのヒアリングによる。
124 2003年11月拡大ドナー会議および、教育省・GESのヒアリングによる。
125 JOCVヒアリング、調査団観察による。
126 福岡教育大学・中村教授、宮崎大学・中林教授等のヒアリングによる。
127 総じてポスト基礎教育の統計データは整備されておらず、入手困難であった。
128 教育基本法改正でも議論されているが、教員養成校卒の資格を高等教育レベル(ポリテクニックと同等)へ格上げすることや、ポリテクニックの教育の質を向上することなどの方策が考えられている。
129 ESR(2002)による。特に女性にその傾向が強い。
130 オランダがリソースセンター整備(2,000万ドル、協力期間不明)を実施しているのみである。
131 詳細は、中期目標の項を参照のこと。
132 JICA協力隊事務局、JICAガーナ事務所協力隊調整員のヒアリング、臼井(2002)等による。
133 派遣中の隊員、JICAガーナ事務所協力隊調整員のヒアリングによる。
134 派遣中の隊員、JICAガーナ事務所協力隊調整員、JICA協力隊事務局、協力隊OB/OGのヒアリングによる。
135 派遣中の隊員によると、小学校レベルの学力の生徒も混じっている場合があるという。派遣先の校長も同じ認識であった。
136 派遣中の隊員のヒアリングによる。
137 派遣中の隊員のヒアリングによる。
138 総じてポスト基礎教育の統計データは整備されておらず、入手困難であった。
139 パシフィックコンサルタントインターナショナル(2001)による。
140 NCTE2001。
141 この点に関しては、ESR(2002)p.40でも言及されている。
142 総じてポスト基礎教育の統計データは整備されておらず、入手困難であった。
143 国家高等教育委員会事務局長ヒアリングによる。
144 ICCESには、長期コース(2~3年)と短期コース(2~6か月)の中に多様なプログラムがあり、入所資格・年齢制限などはない。修了生の多くは手に職をつけて自営業を営むものが多い。男女比は、長期が男:女=7:3、短期が男:女=4:6。これまでの修了者は14,800人。GPRSの下で、農村から都市への人口移動の歯止めの役割も担っている(ICCES局ヒアリングによる)。
145 2003年の実質支出額は約6万ドル、2004年の予算要求額は約30万ドル。
146 例えば、調査団が訪問したアゴメダICCESでは、かつて10名以下であった訓練生が、草の根無償で施設を整備し、さらにJOCVが積極的に地域に働きかけた結果、現在では70名規模に増加しているという。ただし、JOCV+草の根無償のケースの反響が大きすぎ、ガーナ側はJOCV=ハード支援という間違った認識をしている部分もある。
147 実際の回答者は1名。理由は確認できなかったが、一般に草の根無償を受けた学校ほどさらに追加支援を望む声が高く、その不十分な支援に対する不満の表れと推察される。
148 標準参照テストは、1992年より実施されている。これは、小学6年生の5%を対象として、英語と数学の2教科で実施するものである。英語では聴解力・文法・語彙・読解力・筆記の5分野が、数学では基礎的な数字の概念・基礎計算・文章問題・幾何の4分野が問われる。英語で60%、数学で55%以上が合格と定められている(ESR 2002のP.15による)。
149 BECEの結果は、1~9グレードに分けられ、1~5グレードが合格。この成績によって後期中等教育への進学先が決定される。
150 SSSCEの結果は、A~Fグレードに分けられ、A~Eグレードが合格ライン。
151 NCTE2001による。
152 Educational Attainmentの訳。
153 広島大学黒田教授・JICA中国センター研修担当者ヒアリングによる。
154 GES職員、JICA専門家ヒアリングによる。
155 横関他(2003)。
156 同上および教育省ヒアリングによる。
157 福岡教育大学・中村教授、宮崎大学・中林教授、信州大学・吉田教授ヒアリングによる。
158 広島大学・黒田教授、福岡教育大学・中村教授ヒアリングによる。
159 教育省次官、元GES副総裁、ケープコースト大学・アチャンポン教授等のヒアリングによる。

