第4章 日本の援助動向
4-1 教育セクターにおける世界の援助潮流と日本の援助戦略
わが国の教育セクター協力は、世界の援助潮流に呼応し、日本の援助戦略を打ち出す中で実施されてきた。ここでは最初に、それらの動向を概観しておく。
(1) 1990年代
1990年代に入って、世界の援助コミュニティは貧困削減の一環として社会開発重視へと大きく方向転換した。このような中、1990年3月に「万人のための教育に関する世界会議」が開催され、「万人のための教育」の理念の達成が、教育セクターにおける世界の最優先課題となった。
その後、表12にみるように、さまざまな国際会議の場で、「万人のための教育」の理念が繰り返し強調され、90年代においては主要な開発パートナーは基礎教育拡充に集中的に援助を実施してきた。
表 12 1990年以降の教育セクターに影響を与えた国際会議と日本の政策・戦略
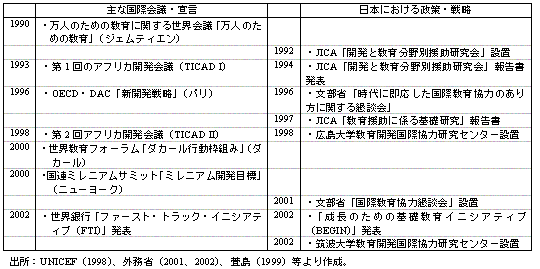
わが国においても、このような世界的な援助潮流に呼応し、1990年前後から教育援助に関する議論が活発化していった59。具体的には、1990年の「万人のための教育に関する世界会議」を契機として、1992年にJICAに「開発と教育分野別援助研究会」が設置され、1994年1月にその報告書が発表された。この報告書で、わが国の教育セクター協力の量的拡大と基礎教育重視という方向性が初めて打ち出され、以後わが国の教育援助を論じる際には度々引用されるものとなっている。これを受けて、1990年代前半は、無償資金協力による小学校建設が急増し、初等教育への協力実績が伸張した。
並行して技術協力の可能性として、日本に比較優位があり60かつ社会的文化的な差異を乗り越えやすい理数科分野での協力が検討され、1994年のフィリピンの理数科分野における教員再訓練を目的とした技術協力プロジェクトを皮切りに、1998年のケニア、インドネシア、1999年の南アフリカと同種の技術協力プロジェクトが相次いで開始され61、理数科教育を通じた基礎教育の質的向上に協力してきた62。
なお、日本の教育セクター協力における比較優位性に関しては現在さまざまな議論があるが、日本の理数科教育については日本の経済成長の一因として諸外国の関心も高く、前述したように比較優位性のある分野の1つとみなされている。例えば、米国のWalberg(1991)は、多くの理数科達成調査で日本がトップにランクある理由は日本の理数科教育の成功にあるとして、その要因を(1)科学者や数学者の養成を目的とするよりもむしろハイレベルの数理科学リテラシーを目指したこと、(2)統一された学習指導要領の影響、と分析している63。
このような背景の下、JICAにおいては1994年に「開発と教育分野別援助研究会」報告書によって、教育援助をODA全体の15%程度に増大させることや基礎教育を重視することなどの提言がなされた。さらに1997年には「教育援助に係る基礎研究」報告書が発表され、その中で、「高等教育・職業訓練から基礎教育へのシフト、ハードからソフトへのシフト、アジアからアフリカへのシフト」64という3つのシフトが打ち出されるなど、この時期は日本の教育援助におけるひとつの転換期となった。こうした方針を受けてJICAの基礎教育案件数は飛躍的に増加したものの、日本の教育協力は結果的にODA援助総額の5~9%を推移するにとどまり65、「開発と教育分野別援助研究会」で提言された15%程度という目標には至らなかった66。
(2) 2000年代
2000年4月、「世界教育フォーラム」がセネガルで開催された。これは、1990年の「万人のための教育に関する世界会議」のフォローとして開催されたものである。世界教育フォーラムでは、1990年の「万人のための教育」への努力が一定の成果をみせているものの、いまだその達成にははるか及ばないとの厳しい認識の下、目標達成のために、今後の目標と戦略として「ダカール行動枠組み」を採択した。ダカール行動枠組みでは、6つの「目標」と、12の「戦略」を掲げた(BOX 7)。ダカール行動枠組みでは、従来の就学機会の拡大に加えて、教育の質的向上の重要性が強調され、2015年までにすべての子どもが良質な無償の義務教育を修了できる環境をつくることを宣言している。6つの目標のうち2つは、同年8月の国連総会において、MDGsの目標としても採用されている。
|
BOX 7 ダカール行動枠組み
<目標>
<戦略>
|
「ダカール行動枠組み」を契機として、日本においては、教育援助強化のための国内体制整備が進められた。文部科学省は2001年10月より「国際教育協力懇談会」を設置し、初等教育における教育援助などに関する検討を行った。2002年7月に提出された同懇談会最終報告では、わが国の国内資源を効果的に活用しながら国内体制の抜本的な整備(知的インフラ構築)を推進していくことを提言している。具体的には、広島大学と筑波大学を拠点として「拠点システム」を構築し、わが国の大学が有する知的資源を広く国際開発協力に活用するための基盤を整備することなどが盛り込まれている。
このような文部科学省における国際協力分野への積極的な対応を活用しながら67、外務省は「成長のための基礎教育イニシアティブ(Basic Education for Growth Initiative:BEGIN)」(5章の5-2(1)3)参照)を策定し、カナナスキス・サミット(2002年6月)において発表した。BEGINは、国際教育協力分野ではわが国初の援助戦略である。
このように、国内教育行政を担当する官庁が、教育分野の国際協力戦略において一定の役割を果たす国は例外的であり、文部科学省が外務省と連携しながら国際協力において積極的に関与していることを高く評価する声は多い68。
以上のように、1990年代以降、世界の教育セクターの援助方針は国際的コンセンサスによって動いており、わが国としてもこれらの動きに呼応しながら、オールジャパンの体制で取り組んでいるところである。
4-2 ガーナにおける援助状況
(1) 全体的動向
わが国がガーナに対する援助を開始した1973年度から1999年度までの援助実績は、有償資金協力1,251億円、無償資金協力560億円、技術協力228億円であり、1988年からはガーナにおける最大の二国間援助国であった。しかし2001年に誕生したクフォー新政権が同年3月に拡大HIPCイニシアティブの適用を申請したことを受け、日本政府の方針により新規円借款の供与が中止されたことで最大の二国間援助国ではなくなった。
教育セクターにおいては、評価対象期間以前では、1977年に開始された青年海外協力隊事業において理数科隊員を中心に多くの隊員を派遣し、実績を上げている。しかし、大型案件としては1995年に無償資金協力「ケープ・コースト大学理科教育機材整備計画」(2.81億円)が実施されているだけで、実績は少ない。無償による小学校建設については、DFIDや世界銀行などをはじめとする援助コミュニティが、日本の無償の高コスト体質や住民参加の不足などの観点から強い難色を示しているという背景があり、ガーナにおいては実施できない状況で、投入規模が小さい直接の要因となっている69。
(2) 教育セクターにおける協力実績
| 1) | 技術協力プロジェクト「ガーナ小中学校理数科教育改善計画」
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 研修員受入
本邦における研修員受入は、前述した技プロのプログラム的展開の一部として位置づけられている。評価対象期間の1998年度以降の実績は、カウンターパート研修(2000~2003年度)計21名、国別特設(1999~2003年度)計39名である。その他、教育省に派遣されている個別専門家のカウンターパート研修(2001~2002年度)計5名、学位取得を目的とする長期研修(2000年度~)計6名が実施されている(表 13)。 カウンターパート研修には、技プロのプロジェクト実施に係わる行政担当官向けの「教育行政」コース(2週間)と、教員養成校の教員向けの「教員教育」コース(1.5~2か月)がある。前者の主な受入先は広島大学、後者の主な受入先は、信州大学と宮崎大学である。国別特設(約2か月)は、3パートに分かれており、パートIはイントロダクション(JICA中国国際センター担当)、パートIIは日本の教育制度やJICAプロジェクトの概論(広島大学担当)、パートIIIは理数科教育のカリキュラム・教授法等の各論(福岡教育大学担当)という構成となっている。 表 13 研修員受入実績(1998~2003年度)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) |
アフリカ青年招聘計画
アフリカ青年招聘計画は、1993年10月に開催された第1回の「アフリカ開発会議」(TICAD I)の理念を受けて、わが国が教育セクター支援を重点分野としている意思を示すために創設されたJICAのスキームである。第1回招聘(1996年度)にガーナから女性教員1名が参加して以来、毎年教育省による優秀教員として表彰された教員の中から数名を、本邦へ招聘している。評価対象期間の1998~2002年度75の教育セクターの実績は、計18名(女性教員9名、中等・高等学校の理数科教員9名)となっている(表 14)。女性教員枠は、当初は理数科教員を対象としたが、当該女性教員が限られているため、実際は理数科教員、GESスタッフ、職業訓練教員、小中学校校長などさまざまな教科・所属機関のものが選ばれている。 表 14 JICAアフリカ青年招聘計画(1998~2002年度)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 教育省・政策アドバイザー型専門家
DAC新開発戦略を受けて、1997年度より、ガーナ側の政策支援および援助協調促進を目的として、教育省に政策アドバイザー型専門家(以下、政策アドバイザー型専門家)が計3名派遣されている。 主な業務内容は、派遣時期によってやや異なるが、援助協調(ドナー会合への参加)、fCUBE・教育SWAP実施促進、新規案件形成、ノンプロ無償見返り資金の活用促進、カウンターパートの本邦研修の送り出し支援などである。また、同専門家の現地業務費の活用によって、援助協調促進が進み、教育省や他ドナーから高い評価を得ている。具体的には、表 15のような現地業務費による事業を実施している。 表 15 現地業務費で実施した事業の一覧
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) |
青年海外協力隊
ガーナにおける青年海外協力隊(以下、JOCV)派遣は、1977年以来2002年4月末までで累計730名(うち女性189名)となっており、長い伝統と堅実な活動で高い評価を得ている。 教育セクターにおける1998~2003年度の派遣実績は表 16のとおりで、計108名が派遣されている。これまでの協力総額は試算によると約5.1億円である76。 分野別にみると(表 16)、高等学校への理数科隊員を中心とする後期中等教育(60.2%)、職業訓練(19.4%)の順となっている。 表 16 教育セクターの青年海外協力隊派遣実績(1998~2002年度派遣分)
地域別の実績をみると(表 17)、ヴォルタ州(28.7%)、イースタン州(15.7%)、セントラル州(11.1%)の南部地域への派遣に加えて、貧困地域であるアッパーイースト州(9.3%)、ノーザン州(8.3%)などの北部3州へも派遣されている。当初は北部への派遣はなかったが、近年需要の高さに応じ、北部へも継続して派遣されるようになった。なお、北部や辺境地に派遣する場合、安全管理の点から複数隊員を同時に派遣しているため、地域が偏る傾向がある。 表 17 教育セクターの青年海外協力隊地域別実績(1998~2002年度派遣分)
特に理数科隊員は、ガーナの教育セクターにおいては長い伝統と実績があり、ガーナ側のニーズも高い。近年大学新卒者など教職経験のないものが理数科隊員となるケースが増えているが、着任後任意で近隣の先輩隊員の授業を視察したり、お互いに模擬授業を実施するなどの方法により教授スキルを向上させている。これらの日常的な努力に加えて、年1回隊員の自主参加による合宿研修(通称アコソンボ研修)が実施されている。近年、この合宿に技プロの専門家やカウンターパートが参加するなど、技プロとの連携が強まってきている。このように隊員自身によって、派遣校のニーズに応える努力が行われている。 また、システムエンジニアの隊員が中心となって、隊員が配属されている高等学校を中心にパソコン研修ツアーを実施したり、理科実験の教授法を披露するサイエンスツアーを実施している。 さらに、1995年度2次隊員によって、タンザニアの奨学生制度を参考に、1997年に「ガーナ青年海外協力隊奨学金制度」が設立された。以来、理数科分科会奨学金運営部会を中心に、募金、奨学生選考、奨学金給付を行っている。理数科隊員の派遣校に在籍している生徒を対象に、1年間の学費と卒業試験料を給付している。2003年度は計31名に総額約18万円を給付した。 このように、やる気のある隊員による発案と工夫で、隊員による多彩な活動が展開されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | 開発調査「ガーナ国技術教育計画開発調査」
評価対象期間においては、「ガーナ国技術教育計画開発調査」(1999~2001年度)が実施されている。協力総額は3億円である。フェーズI調査(2000年5月~7月)、フェーズII調査(2000年8月~2001年3月)、フェーズIII調査(2001年4月~10月)が、参加型アプローチを用いて実施された。同開発調査の目的は、ガーナにおける技術教育セクターの改革によって、自立的な発展メカニズムを持ち、政府財政負担を軽減し、労働市場の変化にも柔軟に対応できる技術教育システムを構築することである。そのための技術教育改革マスタープランが策定された77。このマスタープランでは、技術教育機関とフォーマル・インフォーマル両部門を含む産業界の効率的な協力関係構築のために、CBT(Competency-Based Training)システム78が提案された。 このマスタープランの基本的考え方は、ESPのTVETで取り入れられている。しかし、マスタープラン策定後から2年が経過してもガーナ側に具体化についての動きがなく、2003年4月教育省政策アドバイザーの現地業務費によってフィージビリティ調査79を実施し、その後の足がかりを提供した。また2004年になって、本邦調査団による案件形成調査が実施された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) |
草の根無償資金協力
草の根無償資金協力(以下、草の根無償)は在ガーナ日本大使館が中心となって資金協力を行う事業で、小規模であるが草の根レベルに直接裨益することを目的とした協力スキームである(BOX 8参照)。ガーナにおいても積極的に支援している。 評価対象期間においては、教育セクターで計55件が実施され、協力総額は約2億円となっている(表 18)。1999年度に大幅に増加し、全体的に概ね増加する傾向がみられる。1案件あたりの平均額は250~600万円程度とばらつきがある。 表 18 草の根無償の実績(1998~2003年度)
分野別実績をみると(表 19)、金額では基礎教育が48.3%と全体のほぼ半分を占め、以下、職業訓練(25.0%)、後期中等教育(16.2%)の順となっている。 表 19 草の根無償の分野別実績(1998~2003年度)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | ノンプロ無償見返り資金(参考)
ノンプロ無償見返り資金(以下、見返り資金)80は、日本政府が裨益国に贈与した物資を現金化したものをプールし、自由に使える資金であり、本来的には現金化した時点で裨益国側のものであると認識されるのが普通である。しかし、ガーナ側はESPの日本分予算として計上しているため、本評価では参考として見返り資金も考察することとした。
見返り資金は2003年1月より実際の活用が始まったが、技プロを中心としたプログラム的展開の一環として活用された実績は、北アクアピン郡において、技プロでの研修受講教員のモニタリング費・研修における講師謝金、およびプロジェクト事務所までの道路の舗装(約200m)、教員養成校教官用の宿舎(4室)で、総額419万円(2003年承認額)である。さらに今後も、2004年5,513万円、2005年4,827万円が、それぞれ教育省から財務省へ申請されている81。
なお、教育セクター全体の見返り資金の活用実績は、表20のとおりである。
表 20 教育セクター全体のノンプロ無償見返り資金の活用実績
|
59 萱島(1999)による。
60 同上
61 技プロ以外では、専門家チーム派遣で、ホンジュラス、エジプト等にも実績あり。
62 萱島(1999)による。
63 隅田他(2000)による。
64 黒田(2004b)による。
65 OECD "Development Coorperation" 各年版による。
66 黒田(2004a)による。
67 黒田(2004a)による。
68 黒田(2004a)による。
69 一般的に、世界銀行や経済協力開発機構(OECD)をはじめとする国際社会において、1990年代半ばから、日本の一般無償資金協力による小学校建設は、単価の高さや住民参加の欠如から、厳しい批判の対象となっている(黒田2004a)。
70 供与機材、現地業務費、専門家派遣、研修員受入。
71 プロジェクト対象地域の選定は、ガーナ側から提示された3郡に対して、日本側でカウンターパートの実施体制や専門家の安全面において大きな問題がないことを確認して、決定された。(a)教員再研修プログラムの策定等を行うプログラム地区、(b)再研修システムの確立と拡大を図るプログラム地区、に分けて段階的に協力が実施されていった。(a)には、GES教師教育省のあるアクラから陸路2時間の距離であり、プロジェクト内のコミュニケーションが良好に保たれることが期待され、北アクアピン郡が選定された。
72 横関他(2003)による。
73 従来から参加していた、ケニア、タンザニア、マラウイ、ウガンダ、ルワンダ、ブルンディ、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ、モザンビーク、レソト、南アフリカ、ナミビア、ガーナに加え、新たにセネガル、ニジェール、ナイジェリア、エジプトが参加した。
74 GES職員、技プロ関係者ヒアリング、横関他(2003)による。
75 2003年度は評価実施中には確定データなし。
76 2003年度実行計画ベースの海外派遣隊員費用単価235.9万円(一年あたり)で算出。ただし、これは派遣経費のみで、派遣前・後の訓練費用や広報費などの協力隊派遣にかかるその他の費用は含まれていない。因みに2002年度の決算額から計算すると、一人あたり555.2万円の事業費となる(青年海外協力隊事業費総額は22,643百万円であり、同年の派遣隊員数は4,078人)。これを隊員一人あたり単価として、ガーナにおける投入額を計算すると、約12億円となる。
77 同開発調査では、「技術教育」の定義を教育省管轄の狭義のフォーマルな学校教育訓練プログラムにとどめず、また「教育」と「訓練」という枠にとらわれず、「さまざまな分野の経済活動に必要な技能・知識を習得させるノンフォーマルな教育訓練まで含む広義なもの」として捉えている。
78 産業界が必要としている職務遂行能力・技術標準(Competency)の習得を目的とした教育訓練手法で、受講者は習得した能力・技術を実証することによってのみ、その成果を証明できる。このシステムでの訓練モジュールは、産業界のニーズに直結した技術訓練を多く含んでいるため、企業がその手法を提供する機会が増えることが予想される。CBTシステムでは産業界が、職務遂行能力・技術標準、評価方法、資格を決め、これらをもとに技術教育機関が「訓練パッケージ」と呼ばれるカリキュラムと教育訓練手法を開発する。「訓練パッケージ」はすべてモジュール化されており、技術教育機関のみならず認定された企業・個人によっても提供することができる。
79 正式名称は「CBT方式技術教育に係るポリテクニックの現状調査」。
80 従来、ノンプロ・セクター無償とも呼ばれていた。
81 この申請額が承認されるかどうかは2003年11月末時点で未定(JICAガーナ事務所)。

