第3章 ガーナの教育セクターの概況
3-1 教育政策
(1) 教育政策の変遷
1) 1960年代から1980年代
1957年に独立を達成したガーナは、1961年「教育基本法」を制定し、「基礎教育(小中学校)は無償であり、義務である」と定めた。その後、順調な経済成長に支えられて、1960年代に48%であった就学率が1980年代には73%に改善し、西アフリカで最も進んだレベルに達した。
しかしながら、1970年代後半から1980年代の初めの経済的低迷により、中央政府依存型のガーナの教育体系は大きな打撃を受ける。政府の教育予算は1976年から1985年にかけて実質66%削減され、教科書は絶対的に不足し、校舎は荒廃の一途をたどり、訓練を受けた多くの教員が隣国へ出国するなど、ガーナの教育制度は全般的な麻痺状態に陥った。
このような状況を受け、ガーナ政府は1980年代に構造調整政策を受け入れ経済の立て直しに努めると同時に、教育においても1987年に広範な「教育改革」に着手した。この改革は、従来のアカデミック重視の姿勢を転換し実用的な教育を目指したもので、さらに職業教育の重視の姿勢を打ち出し、教育制度の抜本的見直しを行った。
学校制度は、従来の大学入学まで17年を要していた制度(6-4-5-2制)を12年間(6-3-3制)に短縮した。また、職業教育機会の拡大のために、中学校から選択制で職業訓練の授業を取り入れ、さらに中学校卒業後の職業訓練機関の拡充を目指した4 。教育マネージメントの効率化も図られ、学校事務員の給与削減、高等学校向け補助金の大幅削減、教員一人あたりの生徒数の見直しなど、経費節減のための方策が試みられた。このような教育改革を経て、基礎教育の学校数と就学者数には増加がみられたが、教育の質的向上は大きな課題として残った。
2) 1990年代:基礎教育の義務化・無償化・普遍化に向けて
1990年代に入って、世界の援助コミュニティは貧困削減の一環として社会開発重視へと大きく方向転換した。これに伴って教育セクターの援助戦略においても新しい戦略が打ち出された。そのきっかけは、1990年の「万人のための教育に関する世界会議(World Conference on Education for All:WCEFA)」用語である。この会議で、すべての子どもが2000年までに小学校就学率100%を目指すという新しい理念「万人のための教育(Education for All:EFA)」が提唱された(BOX 3参照)。これにより、世界の教育援助の重点課題は基礎教育とする合意が形成された。
このような世界的な教育セクターにおける潮流と、ガーナ国内における教育の質の低下に対する建て直しの必要性の声を受けて、1992年に憲法が改正され、“基礎教育(小学校・中学校)の義務化・無償化”の理念が明記された。さらに、1994年に、ガーナ政府は基礎教育の政策枠組みとして「基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム(Free Compulsory Universal Basic Education:fCUBE)」を発表した。この動きは、「万人のための教育に関する世界会議」で提唱された「万人のための教育」に応えるものであった。
|
BOX 3 「万人のための教育に関する世界会議」によって設定された主要目標
1)幼児ケアの強化 2)2000年までに初等教育の普遍化 3)学習成果の重視 4)女性の識字の重視 5)青年・成人のための基礎教育・訓練の拡大 6)生活向上や持続可能な開発に必要な学習 |
fCUBEの概要を、表 4に示した。目標として、「基礎教育の無償による完全普及を2005年までに目指す」を掲げている。その下に、3つの目的、すなわち1)教育の質の向上、2)教育マネージメントの強化、3)教育へのアクセスの拡大、を設定している。また、すべてのステークホルダーが参加する調整会議の場(表4、調整会議の項の3)と4))を設定していることも、大きな特徴である。特に、全ステークホルダーが参加する、4)拡大ドナー会議(Consultative Panel Meeting)が開催されるようになったことは大きな進展である。
表 4 fCUBEの概要
| 目 標 | 基礎教育の無償による完全普及を2005年までに目指す | ||||||||
| 期 間 | 1996~2005年 | ||||||||
| 3つの目的と その活動内容 |
|
||||||||
| 運営事務局 | ガーナ教育サービス(GES) | ||||||||
| 実施計画 | 上記の活動内容に対し、詳細な実施計画(全部で約900以上)を設定。計画を支える戦略方法としてロジカル・フレームワーク、段階的実施計画、戦略レベルでの実施計画を設定。 | ||||||||
| 実施体制 |
|
||||||||
| 調整会議 |
|
この時期、世界銀行によって複数ドナーによる特定セクターにおける援助調整の最初のフレームワークである「セクター投資計画(Sector Investment Program:SIP)」(BOX4参照)が、サハラ以南アフリカにおいて導入され始めた。この流れの中で、1996年以降、ガーナにおいても各ドナーによってfCUBEに対する援助調整や、SWAP策定、セクター・コモンファンドの創設等の議論が進められ、教育セクターにおけるコモンファンドの創設に向けたドナー間の調整が進められた。
他方、ガーナにおいては1987年の教育改革の流れを受けて、1991年に「高等教育改革」が打ち出された。しかし、上記のような世界と援助コミュニティの圧倒的な基礎教育重視の流れの中で、高等教育への投資は思うように拡大されなかった。
|
BOX 4 セクター投資計画
冷戦構造崩壊後、DAC援助機関の多くは、いわゆる援助疲れの状況に陥った。そのため、より少ない資金をより有効に活用する必要性が生じた。また、構造調整で公務員数の削減を行っている途上国においても援助の受け入れ体制の効率化が求められた。このような状況の中で導入されたのがセクター投資計画(Sector Investment Program:SIP)である。SIPは、特定セクター全般において、複数ドナーと被援助国が共同で策定したセクター戦略に基づき、複数年度の公共支出計画を策定し、各ドナーの資金援助が1つの口座に集められたコモンファンドによって援助が実施されるというフレームワークである。SIPは、1995年のタンザニアの道路セクターを皮切りに、主にサハラ以南アフリカにおいて導入されていった。SIPはその後、セクター・プログラム、セクター・ワイド・プログラムなどと名前を変えて、アフリカのみならずアジア諸国にも広がっている。 今日、PRSP+MTEFが国家の援助調整フレームワークとして導入されているが、そのセクター版ともいえよう。 参考:国際協力事業団・国際協力総合研修所『貧困削減に関する基礎研究』(2001年4月) |
3) 2000年以降:教育セクター全体への展開
1990年代、「万人のための教育」を目指し、fCUBEの推進によって基礎教育の量的拡充が優先された。しかしその一方で、教育の質、地域格差、ポスト基礎教育の確保などの課題は後回しにされた。その結果、2000年代に入っても、初等教育における学力は低く、これが中等教育・高等教育レベルにまで影響を与えている。また、就学率・学力・進学率などのさまざまな教育指標において地域格差が大きいことが鮮明になっている。さらに基礎教育就学率が上昇するのに伴って、行き場のない基礎教育修了者の存在が顕著化するようになっていった5 。
他方、世界においても、2000年4月に「世界教育フォーラム(World Education Forum)」用語がセネガルで開催され、「ダカール行動枠組み(Dakar Framework for Action)」用語が採択された。ダカール行動枠組みでは、就学機会の拡大のみならず教育の質的向上の重要性も強調され、2015年までにすべての子どもが良質な無償の義務教育を修了できる環境をつくることを宣言した。
こうした状況の中、ガーナ国内でも教育セクター全体の見直しを求める声が強くなった。そこで、教育省は2002年2月より教育セクターの分析研究「教育セクターレビュー(Education Sector Review:ESR)」を開始し、2002年10月にその結果を発表した。またこの分析研究と並行して、クフォー大統領の意向により大統領諮問機関による「教育セクター政策レビュー(Educacation Sector Policy Review Report:ESPRR)」も実施され、2002年8月に発表された。
他方、2-5で触れた世界銀行のFTIの受給条件を満たすために、教育SWAPの策定が急務となっていた事情もあり、先述の2つのレビュー結果を基に、教育省を中心として全開発パートナー参加による協議が加速され、2003年5月「教育戦略計画2003-2015(Education Strategic Plan 2003-2015:ESP)」(3-4(2)参照)が策定された。ESPは、同月、教育省/ドナー会合の場で承認され、教育SWAPとして正式に適用されるに至った。ESPでは、fCUBEが基礎教育のみを対象としたのに対して、教育セクター全体を視野に入れ、特に「科学・技術・職業教育の拡充」が追加されているのが特徴となっている。
さらにガーナ政府は、1961年に制定されて以来一度も改正されていない「教育基本法」の見直し作業も進めている。現在議論されている主な改正点は、1)教員養成校の高等教育レベルへの格上げ(有給進学休暇制度による弊害の解消)(3-4参照)、2)義務教育の推進(子どもを学校にやらない親への法的措置)、3)地方分権化の推進(教育省から郡議会への権限移譲、郡教育事務所を郡議会の下部組織として位置づける等)である6。なお、ESPにおいて、同法案は2004年中に成立するよう明記されている。
(2) 教育戦略計画(ESP)
すべての開発パートナーによって承認された「教育戦略計画2003-2015(Education Strategic Plan 2003-2015:ESP)」は、教育SWAPであり、同時に2015年までのガーナ教育セクターの長期開発計画である(巻末資料参照)。
ESPは教育省の使命(Mission Statement for Education)として、「ガーナ国民全員に、全レベルにおいて国民の能力を引き出す技術を修得するための教育を提供し、貧困削減を促進し、社会経済、ひいては国家の発展を推進すること」を掲げている。この「教育省の使命」を果たすべく、「教育セクターの目標(Goals for the Education Sector)」を定めている。その目標には、教育省が提供すべきサービスとして、1)全国民の実用的な識字力と自立を確保するための施設、2)万人のための基礎教育、3)万人のための開かれた教育機会、4)科学技術に重点を置いた技能開発のための教育と訓練、5)中間・高度な人材開発のための高等教育の保証、が設定されている。
ESPの戦略目標は、基本的に2002年8月発表の大統領諮問機関によるESPRRに基づいており、ESPRRで示された8つの戦略目標に、HIV・AIDSと女子教育の促進の2項目を加えた、合計10の戦略目標が設定されている。この10の戦略目標を、4つの重点分野に分類したものが、表5である。これがESPの骨格となっている。
表 5 ESPの4つの重点分野と10の戦略
| 重点分野 | 10のゴール |
| 1.教育へのアクセスの拡大 | ・ 就学前教育の拡充 ・ 教育と訓練へのアクセスと参加の促進 ・ 女子就学の改善 |
| 2.教育の質の向上 | ・ 生徒、学生の学習到達度を高めるための教授法と学習法の質の改善 ・ 学究的研究プログラムの推進 ・ 学校および高等教育機関における健康と衛生環境の改善 ・ エイズの予防と管理を推進する教育プログラムの策定と奨励 |
| 3.教育マネージメントの強化 | ・ 教育の計画と運営の改善と強化 |
| 4.技術職業教育訓練(TVET)の推進 | ・ 技術職業教育と訓練の拡大と促進 ・ 科学・技術教育と訓練の拡大と促進 |
表 5にみるように、ESPは教育セクター全体を視野に入れた包括的な計画であることが、fCUBEと大きく異なる。特に、大統領の強い意向によって加えられた「技術職業教育訓練(Technical and Vocational Education and Training:TVET)の推進」が追加されたことが大きな特徴となっている。また、幼稚園の義務化・無料化も初めて明文化された。このESPは、ガーナ側のオーナーシップのもとで、すべての開発パートナーが参加して策定された点において、関係者の間で評価が高い7。
ESPを実施するための具体的な年間行動計画である「Annual Education Sector Operation Plan 2003-2005:AESOP」も、同じ時期に策定されている。現在、その本格的な実施に向けて動き出したところで、2004年5月に初の進捗レビューを実施する予定である。
3-2 教育制度
(1) 学校制度
現在の学校制度は、基本的に、6年間の初等教育(日本の小学校に相当)、3年間の前期中等教育(日本の中学校に相当)、3年間の後期中等教育(日本の高等学校に相当)と、その後の高等教育(日本の短大・大学に相当)という仕組みになっている(図 3)。
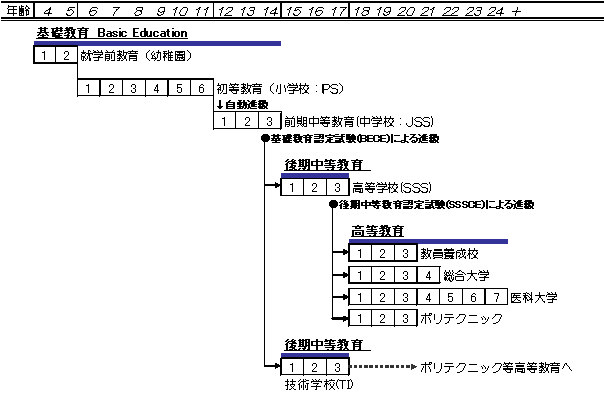
就学前教育、初等教育および前期中等教育をあわせた基礎教育期間は、義務教育であり、無償である。従って、小学校から中学校へは無試験で進学できる。就学前教育はクフォー大統領の強い意向により、ESPに義務化・無償化が明示された。
後期中等教育についてガーナ政府は、現在、図 3にみるように整備しようとしている。大きくはアカデミックコースと職業コースの2つに整理することを目指している。アカデミックコースは、普通科の高等学校(Senior Secondary School:SSS)から教員養成校や大学等へ進学するのが一般的である。また職業コースは、技術学校(Techinical Institute)、国家職業訓練校(National Vocational Training Insitute:NVTI)からポリテクニック等へ進学するコースとして整備しようとしているが、なかなか進展が見られないのが現状である。後期中等教育への進学は、前期中等教育修了時に受ける「基礎教育認定試験(Basic Education Certificate Examination: BECE)の成績によって決定される。
高等教育については、総合大学(4年制)、医科大学(7年制)、教員養成校(3年制)、ポリテクニック(3年制)8がある。現在は、教員養成校卒に授与されるのは高等教育前(Pre-tertiary)資格で、大学卒資格よりも低いことが、有給進学休暇制度を利用するものが多い原因となっている。そのため、現在審議中の教育基本法改正案では、この教員養成校卒の資格を高等教育卒と同レベル9に格上げすることが、大きな改正点の1つとなっている。高等教育への進学は、高校3年次に実施される「後期中等教育認定試験(Senior Secondary School Certificate Examination:SSSCE)」によって選別される10。また、本来、ポリテクニックには技術学校や国家職業訓練校から進学することが建前とされているが、実際にはこれらの職業コースのカリキュラムがSSSCEに配慮されていないこと、また学生の学力も低いことに加えて、普通科の高等学校の学生にとっても、大学等の受け皿の絶対的不足と、学生自身の実力不足等の実態によって、SSSからポリテクニックへ進学するものが多い11。
TVETに関しては、教育省のほか、人材開発雇用省(Ministry of Manpower Development and Employment)、地方政府・農村開発省(Ministry of Local Government and Rural Development)などが管轄する各種技術職業訓練機関が多数ある(表6)。
表 6 ガーナの技術職業教育訓練機関
| 省庁 | 訓練機関 | 備考 |
| 教育省/GES | 技術学校(23校) | 推定学生数17,256名(2000年) |
| 見習い訓練センター(公立19校、私立22校) | 3か月の見習い訓練、2~3週間の主任技術者養成コース | |
| 青少年リーダーシップ研修センター(7か所) | 基礎教育修了者、学校中退者等(2年間で国家職業訓練校修了資格) | |
| 人材開発雇用省 | 国家職業訓練校(29校) | 基礎教育修了者、後期中等教育修了者、見習い訓練修了者、学校中退者等(国家職業訓練校修了資格) |
| 雇用促進地域職業訓練センター(ICCES)(72か所) | 基礎教育修了者、学校中退者等 | |
| OICセンター(3か所) | 基礎教育修了者に11の職業訓練コース | |
| リハビリテーションセンター(14か所) | ||
| 協同組合局が管轄する短大(1校) | ||
| 地方政府・地域 開発省 |
女性訓練機関(18か所) | 基礎教育修了者、学校中退者等(国家職業訓練校修了資格) |
| 地域産業センター(4か所) | 基礎教育修了者、後期中等教育修了者、学校中退者、非識字者等(国家職業訓練校修了資格) | |
| 地域住宅局管轄する深堀井戸技術プログラム(18) | 6~12週の研修、優良資格 | |
| 交通・通信省 | 政府技術訓練センター、Kaneshie技術センター | 基礎教育修了者(1年間で国家職業訓練校修了資格、中級観光ガイド資格) |
その全貌はガーナ側も一括して把握できていないが、主なものでは教育省ガーナ教育サービス(Gahna Education Service:GES)の管轄する「技術学校」(23校)、教育省の国家技術職業教育訓練調整委員会(National Coordination Committee for Technical and Vocational Education and Training:NACVET)が管轄する「見習い訓練センター」(公立19校、私立22校)などがある。また、人材開発雇用省が管轄するものでは、「国家職業訓練校」(29校)、雇用促進地域職業訓練センター(Integrated Community Canter for Employable Skills:ICCES)(72か所)などがある。その他、地方政府・地域開発省の管轄する女性訓練機関(18か所)、地域産業センター(4か所)、深井戸技術プログラム、さらに交通・通信省が管轄する政府技術訓練センターなどがある。以上の政府が管轄する機関以外にも、私立のコンピュータ専門学校などが多数ある。
なお、これらのTVET教育によって取得できる諸資格は、管轄する機関によって異なり、その基準も明確でないことから、今後改善すべき課題の1つとなっている。
(2) 教育行政
ガーナの一般的な行政制度は、国の下に10の州(Region)があり、110の首都・市・郡(Metropolitan/Municipal/District)があり、さらにその下に町(Sub-district)と村(Community)がある。
教育行政に関しては、2003年3月従来の教育省を改組し、「教育・青年・スポーツ省(Ministry of Education,Youth and Sports:MOEYS 以下、教育省)」となった。図4は、2003年9月現在の教育省の組織図である。
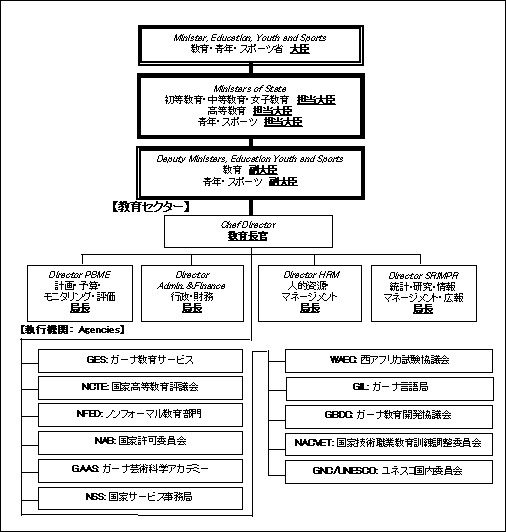
|
注:2003年4月9日現在 出所:教育省資料より作成。 |
教育省の役割は、政策立案、各執行機関の調整・監督、に限られている。従って、教育行政の執行は、傘下の11の執行機関(Agency)が行っている。
この執行機関の中で人員・予算ともに一番大きな組織がガーナ教育サービス(Ghana Education Service:GES)で、就学前教育、初等教育、中等教育、技術職業教育訓練(Technical and Vocational Education and Training:TVET)の一部12を管轄している。GES本部には総裁と2名の副総裁の下に、基礎教育局、後期中等教育局、カリキュラム局、教師教育局、特殊教育局、ガイダンス・カウンセリング局、財政・行政局がある。GESは、現場の出先機関として、州教育事務所(Regional Education Office)、郡教育事務所(District Education Office)を有している。現在、郡教育事務所はGESの直接の監督下でサービスを執行している。ただし、現在審議中の地方分権法が施行されると、郡教育事務所は完全にGESから切り離され、郡議会の管轄におかれることになる。高等教育については、「国家高等教育評議会(National Council for Tertiary Education:NCTE)」が、またノンフォーマル教育については「ノンフォーマル教育部門(NFED)」が、それぞれ管轄している。
さらにTVETについては複数の省庁間が管轄しているため、全体の調整機関として、国家技術職業教育訓練調整委員会(National Coordination Committee for Technical and Vocational Education and Training:NACVET)が、教育省内に設置されている13。1998年から世界銀行の支援も受けているが、権限・予算ともに少なく、ほとんど機能していない状態である14。
地方の教育行政については、表7のようになっている。州教育事務所は、主に郡教育事務所の調整・支援・モニタリング・評価を担っている。また州教育事務所は高等学校を所管している。
表 7 地方の教育関連組織
| 機関名 | 役割 | |
| 州 | 教育事務所 (Regional Education Office) |
GESの州レベル機関。 郡レベル組織(郡教育委員会と 教育ユニット)の調整と支援、および評価・モニタリング。高等学校を管轄。 |
| 郡 | 郡教育事務所 (District Education Office) |
GESの郡レベル機関。 カリキュラム管理、就学率の強化、地域協力の促進、マネージメントの効率化、サーキット事務局の監督、現職教員研修の実施、学校の定期的モニタリングの実施、データ収集管理。 |
| 郡議会 (District Authority Assembly) |
施設計画や予算準備計画の調整、郡教育事務所の監督。 | |
| 教育ユニット (Education Units) |
宗教組織やSecurity Servicesにより創始された組織で、Unit Schoolを監督する。GESの下部組織のひとつ。 | |
| サーキット・スーパーバイイザー (Circuit Supervisor) |
学校(通常都市部20校、農村部10校)を訪問、アドバイスを与え監督する。 | |
| 学区 | 学校運営委員会 (School Management Committee) |
基礎教育レベルの学校サポート機関で、学校とGESのパイプ役となっており、主に学校環境の保全や改善の促進を通して学校運営を支援する。 メンバー:学校長、郡議会代表、地域開発委員会代表、コミュニティ代表、教員代表(小学校、中学校から各1名)、卒業生代表。 |
| 学校 | PTA | 保護者と教員の良好な関係を築く、家庭と学校の連携強化。 |
郡教育事務所の組織は全国ほぼ共通で、郡教育事務所長(District Director)のもとに、以下の4つの課を有し、それぞれに担当次長(Assistant Director)が配置されている。郡教育事務所は、郡内の幼稚園、小学校、中学校を管轄している15。
- Administration, Budget & Financial Control
- Planning & Monitoring, Data Collection, Research and Recode(Statistics)
- Manpower & Training
- Supervision & Management of Teaching and Learning, Guidance and Counseling and Inspection
3-3 教育財政
これまで国家予算の歳出(政府予算とドナー援助額)の全貌を把握することは、ドナーの援助額を把握できなかったため困難であった。しかし、2003年からMTEFが実施されて、各ドナーに援助額の開示を強く求めた結果、以前よりも正確な国家予算の歳出額が明らかになっている(図 5)(ただし、後述するプライベートセクターは含まず)。2003年のMTEF支出計画によると、2003年国家予算の総額は約14億ドルであり、そのうち教育省予算は3.7億ドルで、全予算の約27%18を占めており、教育省の予算規模が突出していることが分かる。
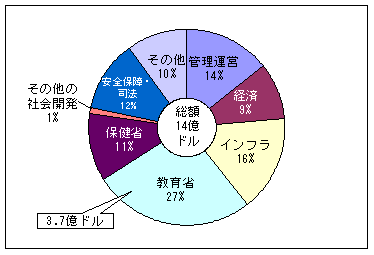
| 注: | 政府予算とドナー援助額を合計したもの。プライベートセクターは含まない。なお、現在ガーナでは39の省庁があるが、教育省と保健省以外は規模が小さいため、分野でまとめて提示した。 |
| 出所: | MTEF2001-2004予算のAppendixより作成。 |
他方、教育省が策定・公表している2004年のESP予算でみると(表8)、教育セクターの予算総額は約7億ドルである。その収入内訳は、教育省予算が約5億ドル19(72%)で、次にその他(GETファンド20、郡議会コモンファンド21等)約1億ドル(15%)、ドナー援助9,200万ドル(13%)となっている。
表 8 教育セクター財源(ESP2004年予算)
| 金額(ドル) | 割合(%) | |
| 教育省予算 | 498,901,283 | 72 |
| ドナー | 92,607,152 | 13 |
| その他 | 101,567,023 | 15 |
| 合計 | 693,075,458 | 100 |
| 出所: | AESOP2004-2006予算書(2003)より作成。 |
その支出内訳(図6)は、就学前教育4%、小学校31%、中学校13%、高等学校14%、教員養成校4%、TVET1%、高等教育19%、管理/助成金運営11%となっており、基礎教育の占める割合が合わせて48%と半数近くを占める一方、TVET、教員養成、管理/助成金運営に関する予算が際立って少ない。
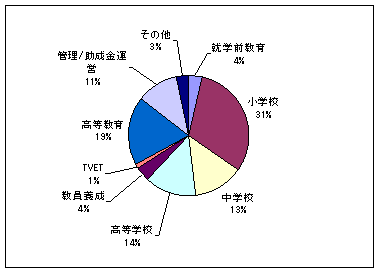
|
注:総額約7億ドル。 出所:AESOP2004-2006予算書(2003)より作成。 |
これら政府が把握している予算以外に、プライベートセクターにおける財源が存在する。それは、近年急増している私立学校における事業費22である。私立学校における事業費は正確に把握できていないが、いろいろな試算が試みられている。その1つであるESRの試算によると、現在ガーナの教育セクターの支出はGDPの約1割を占め、そのうち、公共セクター(政府予算等)が62%、プライベートセクターが31%、ドナー拠出が7%であるから、プライベートセクターの重要性は明らかである。
|
BOX 5 教育省予算以外の2つの財源 教育省予算以外に、法律によって支出が定められている予算(Statutory expenditure)がある。これはすなわち、国家予算から直接教育セクターに分配される予算のことである。その主なものは「GETファンド」と「郡議会コモンファンド」である。 GETファンドは、2000年に創設された基金で、付加価値税(VAT)の5%が基金に入れられ教育セクターへ配分される。GETファンドは、理事会によって管理運営されており、その使途については、理事会が案を作成し、議会が承認して決定されることとなっている。GETファンドの教育セクターへの活用は、2000年6月から始まっている。2000年は約2,480万ドル、2001年は4,667万ドル、2002年は5,200万ドルの拠出がそれぞれあった。 郡議会コモンファンドは、政府歳出の5%を直接郡議会へ配分するもので、日本の地方交付税にあたると理解される。政府はこの使途について、最低でも20%を教育セクター、そのほとんどを基礎教育に、配分するよう奨励している。つまり、政府歳出の1%(5%の20%)が郡議会コモンファンドを通じて教育セクターへ配分されることをねらっている。実際には、郡議会はこれ以上に教育セクターに支出している。推計によると、同ファンドを通じて2000年には545万ドル、2001年には909万ドル、2002年には1,128万ドルが教育セクターに分配されている。 財源別予算内訳(2004年ESP予算) (単位:セディ)
参考:ESR(2002)。 |
3-4 教育セクターの現状と課題
(1) 教育サービスの提供状況
最初に、ガーナ教育セクターにおけるサービス提供状況を、教育レベル別に、主な教育指標によって概観する(表9)。
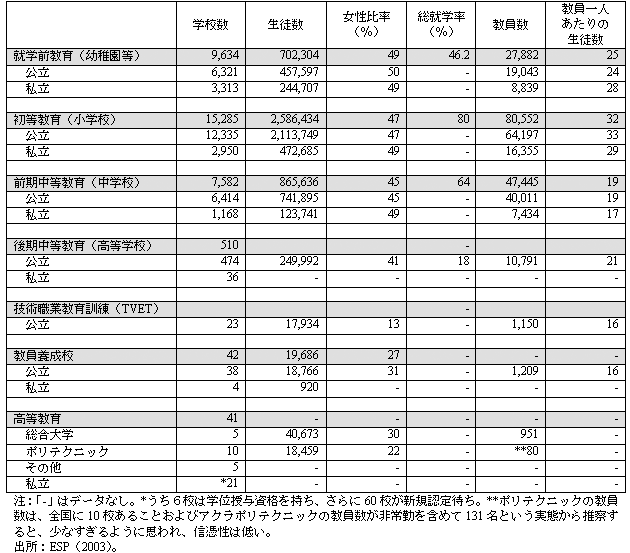
以下に、これらの教育指標から分かるガーナの教育サービスの提供状況について主な傾向を示す。なお、さらに詳細な分析は、5章の5-4「結果」も参照されたい。
- 総就学率をみると、初等教育80%、前期中等教育64%であり、基礎教育レベルにおいてもまだ改善が必要な状態である。
- 基礎教育においては、総就学者数に占める私立校の割合(初等教育19%、前期中等教育15%)が高い。これは、ガーナにおいては大学進学志向が強く、後述するように私立と比較して極端に質の低い公立校を避け、高い学費を払っても私立校に入れる親が多いためである。特に都市部においては、4割が私立校に就学している。この傾向は就学前教育にも拡大している23。
- 後期中等教育(公立のみ)の総就学率18%は、初等教育就学率が80%程度の国では低くない。なお後期中等教育には、ここに挙げた以外に、1990年代に創設された地域高校(Community Day Secondary School)が全国に35校ある24。
- 女性比率(女性の占める割合)は、初等教育47%、前期中等教育45%、後期中等教育(公立)41%、高等教育(総合大学)30%と、総じて男子より低い。さらに、TVETでは13%、ポリクテニックでは22%と低いなっている。この原因として、寄宿舎を含む女子のための施設の不足、コース設定や取得資格に柔軟性がないこと、女性教員の不足などが原因として挙げられている25。
- 教員一人あたりの生徒数は少なく(小学校32人、中学校19人)、非効率であることが指摘されている26。ESPでは、小学校で教員一人あたり35人を目標値としている。
(2) 教育へのアクセスに係る課題
教育へのアクセスに関しては、都市と農村の格差が依然大きな課題である。小学校の総就学率(2000年)は全国平均で78.6%であるが、州別でみると、最も高いセントラル州の89.2%に対して、北部3州ではアッパーウエスト州56.4%、ノーザン州61.6%、アッパーイースト州70.3%と、大きな格差がある。また、中学校については、全国平均が63.3%で、最も高いグレーター・アクラ州の78.1%に対して、最も低いアッパーイースト州は37.8%と、格差がさらに顕著になる(5章・図29参照)。加えて、北部3州は中学校における総就学者に占める女性比率も他州と比較して低く(図7)、ジェンダー格差がより深刻である。
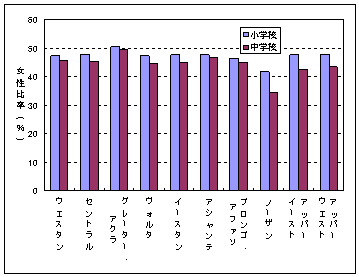
地域による就学率格差の1つの要因として、学校施設の不足が挙げられる。fCUBE以降、例えば1997~2000年の期間に、小学校が約2,000校以上、中学校が約1,400校増設されたが、ESPでは今後2015年までにさらに15%の小学校増設、また22%の中学校増設を目標としている。さらに世界銀行のFTI実施計画では、目標(2015年に小学校総就学率107.4%)を達成するために必要な小学校数は3,892校(23,356教室)と試算している。また、補修についても、ESPおよびFTI実施計画ともに、毎年相当数の教室の補修が必要であると試算している27。なお、ESPではこれらの施設の整備のためには、政府だけでなく、民間、地域、宗教団体、NGOなどが参加することが重要としている。
また地域格差を示すデータとして、中学校の学齢人口(12~14歳)に対する学校数をみてみると、例えばグレーター・アクラ州では234人に1校であるのに対して、アッパーイースト州では490人に1校となっており、明らかに格差があることが分かる。
教育省は就学率を上げる工夫として、2004年より「人頭補助金制度(Capitation Grants)」を導入する予定である。これは、就学率100%を目指し、現在諸経費の負担のために子どもを学校へやれない両親の経済的負担を軽減し「小学校の完全無償化(諸経費の撤廃)」を徹底するための施策である。これは同時に、地方分権化の流れの一環でもある。各小学校には、男子生徒1名につき約2.3ドル、女子生徒1名につき約4.6ドルが支給される。女子生徒の方が高いのには、女子の就学を促進する狙いがある。なお、この給付金は学校の口座に直接振り込まれ、使途は校長と学校運営委員会によって決定されることとなっている。
(3) 教育の質に係る課題
1) 低い学習到達度
現在のガーナの教育セクターにおける最大の課題は、教育の質の改善が進んでいないことである。小学生の学習到達度をみる全国試験として、「標準参照テスト(Criterion Reference Testing:CRT)」がある(詳細は5章の5-4(1)「9)中期目標1」参照のこと)。小学校6年生の5%を対象として、英語と理科で実施され、それぞれ合格ラインは、英語60%、数学55%となっている。2000年の同テストの合格率は、公立校(英語9.6%、数学4.4%)、私立校(英語77.9%、数学53.7%)となっており、公立・私立校間の格差は著しく、さらに公立校の合格率の低さは深刻な状態である。このように、いくら就学率が上がっても、子ども達に必要な学力がつかなければリソースの浪費につながるというという指摘28もあり、特に公立校における学習環境の向上が重要な課題となっている。
また中学校から後期中等教育へ進学するためには、BECEに合格しなければならない。BECEの合格率が、英語、理科、数学、社会のうち6割を超えているのは社会のみである(詳細は5章の5-4「中期目標1」を参照)。またBECEの合格率は近年、下降傾向にあるのも懸念される。さらにJOCVによると、高等学校においても九九ができない生徒が少なからずいる状況であり、学習到達度の低さの深刻さがうかがえる。
2) 低い教員の質
前述の子ども達の学習到達度の低さの最大の要因は、教員の質の低さにある。その背景には、ガーナ社会の学歴偏重の給与・昇進体系が指摘されている29。一般に、ガーナでは小中学校の教員の待遇は低く、決して尊敬を得る職業でないことから、収入の良い職業を得るためのキャリアパスの最初の一歩という認識が強い。また、教員養成校卒(小中学校教員資格授与)は大学卒より資格が低く、同じ教員でも給与・昇進に差がある。従って、成績が悪く大学に進学できない生徒がやむを得ず教員養成校に入学し、一旦教職についた後、「有給進学休暇制度(Granted Study Leave)」30を利用して大学へ進学するケースが多い。表10にみるように、2000年においては10,103人がこの制度を利用し、これは同年の新卒教員数(3,272人)の3倍以上であり、差し引き7,000人近い空きポストが発生している。また、現在の有給進学休暇制度では、GESが必要としている専攻と関係のない学科を学ぶ者が多いこと31、さらに学位取得後に給与のより高いレベル(高等学校や教員養成校等)の教員や他セクターに移っていくことが大きな問題として認識されている32。
表 10 有給進学休暇取得者数・新卒者・教職空ポストの関係
|
このような背景から、小中学校の教員は慢性的に不足しており、また教員が定着せず技能や経験が蓄積されていかないという構造的な問題を抱えている。因みに、技術協力プロジェクトの中間評価時の調査では、研修受講者の26%が同地域内の小中学校の教員の職から離れている。また研修受講者の12%が有給進学休暇制度を利用して大学に進学していた。さらに、同プロジェクトの他の調査では、研修受講者のプロフィールをみると在職年数5年以下の教員が全体の半数を占め、年齢も30歳以下の教員が43%を占めていた33。このような実態からも、小中学校に熟練の教員が非常に少ないこと、指導案や教授方法について現場レベルで蓄積されていないことがうかがえる。
慢性的な教員不足によって、「教育省2000/2001統計」によると公立小学校教員数64,197人のうち21.2%が無資格、公立中学校教員数40,011人のうち12.8%が無資格となっている。特に、教員に不人気の北部地域や農村部の学校においては教員不足が深刻で、中には教員のいない学校も存在する。このような状態が、北部地域や農村部の教育の質の低さを固定化しており、さらにポスト基礎教育進学率の低さにもつながっている。高等学校では、教員不足を補うためにナショナルサービス(National Service)34による教員が多数派遣されている。例えば、今回視察したJOCV派遣中のタマレ州の高等学校では15名の教員のうち5名がナショナルサービスによる教員であった。これらの教員は、教員のための専門の教育を受けておらず、一般に教育に対するモチベーションも低く、さらに教員間の相互学習の環境も育ちにくいといった条件が重なっている場合がほとんどであり、教育の質の向上を期待するのが困難である35。
この他、教育の質の低迷の要因として、教員のパフォーマンスの低さが指摘されている。教育審査・研究センター(Education Assessment and Research Centre)が2002年に実施した調査によると、公立・私立校の学力の差は一般に考えられる「資格の有無」や「給与の差」ではなく、「規定の授業時間に教壇に立っている時間」や「年間のシラバスを全部消化したかどうか」などの基本的な教員のパフォーマンスによるものであることが明らかになった。同調査では、これは校長の監督能力の差(教室を巡回指導したり、態度を改めない教員を解雇する等)によるところが大きいと分析している36。 これらの他にも、現職教員研修制度が未構築であること、教員養成課程と現職教育のリンクに問題があるなど、教員制度に関する問題は多く指摘されている。
3) 教科書に係る問題
小中学校における教科書不足も深刻である。2002年6月に新たな「基礎教育に係る教科書政策」が施行され、現在その実施の中での試行錯誤が続いている。同政策によると、小学校で新たに教科書が改訂される予定の教科は、「ガーナ語と文化」、「英語」、「算数」、「宗教と道徳」、「環境教育」の5科目で、「理科」は入っていない。また中学校では、「ガーナ語と文化」、「英語」、「算数」、「理科」、「農業」、「人生スキル」、「前職業スキル」、「前技術スキル」、「社会」、「フランス語」の10科目である。「英語」、「数学」、「理科」の教科書は児童・生徒1人当たり1冊、その他の科目は児童・生徒2人に1冊が貸与される予定となっている。しかし、現段階において、小学校の現場でほぼ行き届いていたのは、「算数」だけであった。また、中学校のカリキュラムは2001年9月に大幅に改訂されたが、教科書の改訂・制作作業は大幅に遅れているため、2003年10月現在も新しい教科書は不足した状態が続いており、旧カリキュラムの教科書がそのまま使われている。
さらに、教科書配布にかかるマネージメントの不備も深刻である。関係者の話によると、教科書の詳細な必要数など把握されていないのが現状である。また、「貸与される」という規定であるが、実際は一旦生徒に配布されるとリサイクルすることが難しく浪費につながっていると同時に、必要量の算定を難しくしている。さらに、印刷された教科書の配布システムが確立していないために、郡教育事務所に保管されたままになっていたり、さらに深刻なところでは校長のもとに山積みされ生徒に配布されないまま放置されている実態もある37。このような教科書配布にかかるマネージメント力の低さも、恒常的な教科書不足を招いている。
また、教科書問題に関しては、つねに教授言語の問題がつきまとっている。従来小学校1~3年生に関しては現地語で教授されていたが、現地語が多種(主なものでも8種)にわたるため対応できる教員が不足していることや、教科書の作成が難しいことなどにより、2002年5月時点で、教育省は全教育レベルを通して教授言語38を英語とするという方針の転換を打ち出した。これについて、fCUBE以降現地語教育を支援してきたGTZが反発するなどドナー間にも大きな波紋を投げかけていた。しかし、2003年11月の拡大ドナー会議において、再度担当大臣がこの方針を言明したことによって、最終的にこの方針が貫かれるものと思われる 。
(4) 教育マネージメントの問題
教育セクターのマネージメント能力がなかなか向上しないことも、大きな課題である。この問題について、GPRSでは以下の点が特に指摘されている。
1点目は、教育セクターに係る予算不足である。ESRによると、ガーナ教育セクターに支出している教育省予算はGDPの4%を占める規模である。しかし、2004年のESP予算でみると(5章・図24参照)、教育省予算の89%が給与に使われている。その結果、残りの11%を、行政運営管理費、教育活動費(教科書・教材等)、インフラ整備費などで分け合っている状況で、実質的にはこの分野はドナーに依存しているのが実態である。このような予算の慢性的な不足が、教育セクターマネージメント能力の向上に大きな障害となっている。また、先述した有給進学休暇制度は人件費の大きな部分を占めており、浪費の一端となっている。
2点目は、教育省および執行機関のキャパシティの問題である。ESPの分析では、教育サービスを提供している、教育省―GES―州教育事務所―郡教育事務所―学校―地域社会、の全レベルにおいて、キャパシティが不足しているとしている。この原因の1つには、前述した予算不足による人員の不足が挙げられる。次に挙げられるのが、ガーナにおいて教育行政官の計画・運営能力の重要性があまり認識されてこなかった点である。現にこれまで、教育省の管理職登用の尺度は教職在職年数であったことが、そのことを端的に表している。また、管理職を養成するための研修などもほとんど実施されてこなかった。教員のパフォーマンスが公立・私立高で異なるのは、校長の監督能力によるものであるという調査結果を紹介したが、このことは逆に言えば公立校の校長の監督能力の低さを物語っている。今回の現地調査においても、学校における管理職(校長・教頭)の管理能力の低さ、意欲の低さも、学校間で格差が大きいことが観察された。地域社会の学校運営への参加は、教育のパフォーマンスに大きな影響を与えることが知られているが、ガーナでは地域社会の教育への参加の強化を目指しており、地域によっては学校運営委員会やPTAが強化されているところもあるものの39、まだまだ地域格差が大きい40。
3点目は、各関係機関間の連携の不十分さである。例えば、政策決定機関である教育省と執行機関であるGESの関係、GESと各地方の出先機関(州教育事務所や郡教育事務所)の関係においてコミュニケーションが十分でない。各レベルは相互の信頼関係の上に、情報交換と問題の共有が不可欠であるが、現状は上から下へのトップダウン的な体質が強い。しかも、中央からの情報、例えばESRの結果やESPなど中央がとりまとめた実態情報や政策が、なかなか地方の末端まで正しく浸透していないという現実もある41, 42。また、現場の声を中央へ届ける仕組みも弱く、従って、中央は現場の実態を正確に把握できていない43。
4点目は、郡教育事務所の総体的な能力の低さである。各事務所の運営は教育事務所長の資質に左右されており、組織としての規範がなく、各職員にも多くの場合積極的な姿勢や行動が見られない。このような状況下で、現在内閣が改正作業を進めている地方自治法(Local Government Service Bill)が成立すると、高等教育以外の教育サービスは、教育の施策立案・執行・人事権の権限がすべて郡議会に移譲されることとなり、郡による格差がさらに拡大すると懸念する声は多い44。
以上の問題認識を基に、ESPでは教育マネージメントの改善の目標として「教育省・執行機関および学校が明確に定義された役割の下、少ない資源を最も効果的に活用し、新たな事業文化と支援、相互信頼を築く」を掲げている。また、そのための体制整備として、セクター全体の包括的なモニタリング体制の構築を進めており、最初のモニタリング結果が2004年5月に発表される予定である。
(5) 技術職業教育訓練(TVET)の改革
1987年の教育改革の大きなねらいの1つに、従来のアカデミック偏重の教育から、実用性を重視した教育を提供するというものがあった。しかし、その後、TVET分野の改革はほとんど進んでいない。
その背景には、国民の圧倒的な高学歴志向があり、高校や大学受験に関係のない職業に関する選択科目45は不人気という実態がある。また、後期中等教育レベルの技術学校や高等教育のポリテクニックなど、職業技術に関する専門学校はどちらかというと人気がなく、成績の悪い生徒が進学するところという認識が定着している。また、識者や教育者の中でも「前期中等教育の間は、読み書きや計算力をつける学習に集中すべきである」というTVET消極論がある46。
このような状況に対して、2001年に教育省と人材開発雇用省が共同で「ガーナTVET政策フレームワーク・ドラフト」を完成させ、ポスト基礎教育のためのTVETの拡大を打ち出した47。同ドラフトやESRによるレビューを総合すると、職業訓練機会の拡大に向けた課題として挙げられているのは、前期中等教育において実習室の不足や専門の教員が不足していること、後期中等教育において技術職業訓練校が52校と少ないこと(普通科高等学校は474校)、教育省の予算に占めるTVETの割合が約1.2%と非常に少ないこと、などである。さらに、TVET教育機関と産業界との結びつきが弱く、産業界が求める人材育成のための効果的な訓練プログラムが提供できていないことも問題となっている。
ESPRRによると、何らかの教育を受けた労働者のうち技術職業訓練校修了資格を有するものはわずか2%以下にすぎず48、技術職業分野における人材の不足が経済発展の障害となっていると分析されている。こうした結果と大統領の強い意向を反映して、TVETがESPの4本の柱の1に入れられたことから、今後の本格的な進展が期待されるところである。
|
BOX 6 学校運営委員会による教育制度の問題点
参考として、教育現場を地域でみている学校運営委員会が指摘している教育制度に関する問題点を紹介したい。本評価調査で実施した学校運営委員会メンバー(回答者44名)に対するインパクト調査によると、教育制度の問題点として感じているのは、多い順に「教科書不足」、「教員住宅不足」、「教員給与の低さ」、「生活言語と教育言語が異なる」、「親が子どもの教育に対する出費をしない」などとなっている。この傾向は、教育省やガーナの有識者などの認識と一致している。 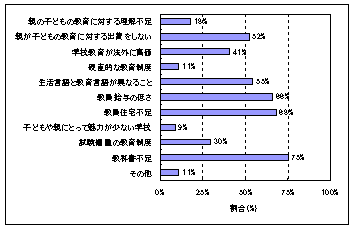 出所:インパクト調査より作成。詳細は巻末を参照。 |
3-5 他ドナーの援助動向
(1) 全体的動向
これまで保健セクターに比べてやや低調であった教育セクターのドナー協調であったが、2001年の新政権発足以降、急激に協調ムードが加速した。その後、一気にSWAP策定作業が進み、2003年5月のESP承認にこぎつけた。SWAP策定過程において、年2回のドナー会議を定期的に開催し、この他各種分科会が開催されるなど、緊密なコミュニケーション体制が確立している。ESP策定後初めて開催された2003年11月の拡大ドナー会議は、ESPの本格的始動に向けてのキックオフ会合となった。
ガーナの保健セクターで、1997年よりコモンファンドが設置されたSWAPが始動していることから類推するならば、教育セクターにおいてもその設置が期待されていると予想された。しかし、今回の調査においては、DFIDをはじめ他ドナーからも設置を強く求める声は聞こえてこなかった。また、ガーナ教育省次官のコメントでも積極的な意向は示されなかった。その背景としてはいくつかの要因が挙げられる。1つには、1990年代後半、fCUBE実施のプロセスでDFIDと世界銀行がそれぞれコモンファンドを設け一元化しようと試みたが、結局うまくいかなったという苦い経験がある。また2001年以降のSWAP策定過程において、コモンファンド設置よりもより多くの開発パートナーの参加を第一義としたことがある49。さらに近年、DFIDと世界銀行の両リーディングドナーがセクター別コモンファンドからMDBSに移行してきたことも大きく影響している。現在、各開発パートナーはセクターへの協力とMDBSへの投入のバランスを見極めようと思案している段階にあるといえよう。
以下に、本評価調査で把握できた範囲で、fCUBE以降の主要ドナーの実績を個別に整理する。
(2) 主要ドナーの実績
1) 世界銀行
世界銀行は、fCUBEに対する支援として、「基礎教育セクター向上プログラム(Basic Education Sector Improvement Program:BESIP)」を実施している。協力期間は1996~2002年(2000年までの予定を2年延長)、5,000万ドルの予算で実施した。BESIPの内訳は、初等教育支援88%、高等教育支援9%、中央政府支援3%である。BESIPは2002年12月に最終的に終了し、ガーナ側の借り入れ実行額は4,780万ドルであり、この内訳は 1)教育の質の向上:1,770万ドル、2)マネージメントの改善:1,090万ドル、3)アクセスと就学の改善:1,920万ドルとなっている。
具体的なプロジェクトとして、中央政府(特に資金調達を扱う「資金および調達監理課」)の制度構築・キャパシティ強化、郡レベルでは学校校舎の増改築・改修・校長用住宅建築、教科書・教材開発、教科書配布システム強化、郡レベルで教育統計を収集し最終的には全国な教育データベースを完成させるという「教育情報管理システム(Education Management Information System Project:EMIS)」の構築等が計画された。しかし、世界銀行が1999年4月に実施した中間評価(World Bank2003)によると、投資執行(disbursement)は計画の80%が遅れており、実施の進捗度と開発目標の両者において“不満足”の状態であり、大幅な計画の見直しが必要と指摘されている。原因はあまりに野心的なプログラムデザイン(14分野)によるものと判断されたため、プログラムのスコープを絞り、比較的順調に実施されているサブコンポーネントを残して全体のサブコンポーネント数を減らした。その結果残った主な協力分野は、学校建設と補修、教科書の配布、EMISの3分野のみとなった。また援助期間も1.5年延長された。残されたEMISも現在多くの問題が指摘され中断中である50。
また、「学校改善基金(School Improvement Fund:SIF)」は、教育実施プロセスへのコミュニティの参加とオーナーシップを醸成することを狙い、NGOを活用して、1996年から1998年に948万ドルが支出されたが、NGOへの高額な資金援助の割にはインパクトが弱いと、ガーナ側・世界銀行ともに評価が低く、予定されていたフェーズIIはまだ開始されていない。
またノンフォーマル教育においては、「ノンフォーマル識字プロジェクト(Non Formal Literacy Project)」を現在実施中で、期間は5か年(1999~2004年)、協力額は3,200万ドルである。主な内容は、1)識字教育(15のローカル言語)、2)英語教育(パイロット)、3)識字教育の基盤整備、である51。また、職業訓練・ノンフォーマルプロジェクトが1995~2001年の期間で実施されており、協力額は960万ドルであった。
この他、1994~1998年の教育セクターにおける世界銀行の融資は、基礎教育のみでなく、高等教育を含むものであり、校舎建設(全国2,031サイトにおいて11万以上の教室を建設)も実施された52。
世界銀行はBESIPが終了した現在、FTIにかかる追加的な資金供与に関する条件整備を進める一方で、高等教育支援 に向けた案件形成を行っている。
2) DFID
DFID(英国国際開発省)は、fCUBEに対する支援として、「教育セクター支援プログラム(Education Sector Support Programme:ESSP)」を実施している。協力期間は1998~2005年(2003年までの予定を2年延長)であり、協力額は9,175万ドル(5,000万ポンド)である。ESSPで特に重要視されているのは、1)地方行政組織のキャパシティ向上と、2)それに伴う地方分権化の推進であり、一定の条件を満たす郡に対しては直接財政支援(1998年時点で各郡1億セディ)を行っている。このため、活動拠点は郡教育事務所で、結果として5年間に440の小学校を支援した。DFIDは教育に関する具体的活動は郡教育事務所へ移管し、教育資源(人材・資金など)に関する権限を郡に移管すること、および学校レベルでの現職教員研修を組織化することを目指して、マネージメントレベルでの支援およびローカル・コンサルタント提供を行っている。
他方、DFIDの基本的な援助方針を示した「年国別援助計画2002-2005」では、PRSPを持つ国に対しては一般財政支援に大きくシフトすることを打ち出しており、DFIDアフリカ局においては、段階的に総援助額の75%を一般財政支援に切り替え、最終的には全額をMDBSを通じて一般財政支援にすることを目指している。この方針はガーナにおいても踏襲されており、MDBSの導入によって、MTEFと中央政府改革を連動させ、パートナーシップを重視したアプローチを採用している。ESSPの拠出の枠組みも、状況によりMDBSへ移行する予定である。
3) USAID
USAID(米国国際開発庁)は、fCUBEに対する支援として、「初等教育の質の向上プログラム(Quality Improvement in the Primary School:QUIPS」を実施中である。協力期間は1997~2004年であり、2001年までの協力額は5,050万ドルである。その後の予算は、670万ドル(2002年)、837.5万ドル(2003年)であり、2003年までの協力額を算出すると6,558万ドルとなる。2001年までの協力の内訳は、プロジェクト協力3,900万ドル、ノンプロジェクト協力1,400万ドルとなっている。QUIPSは、1)学校レベルにおける教育環境の改善(110郡においてそれぞれ3校ずつパイロット校を選定し校舎増改築等を実施)、2)授業の改善(教育の評価や生徒中心の教育の導入などによる)、3)コミュニティの巻き込み、4)教育政策改革支援(カリキュラムの開発、教育関連職員の管理、地方のキャパシティビルディング、学校に関するデータの収集と分析、の4分野)など、多岐にわたる活動を行っている。1)に関してはこれまでに郡レベルへの支援を通じて、88郡354校に協力している(2003年7月現在)。2001年の中間評価において結果に対する説明責任を強化する必要性が指摘されたため、今後2004年のQUIPS終了までの期間においては地方分権化の推進に一層の力を注ぐものとした。ノンプロジェクト協力としては、郡レベルのキャパシティビルディングの構築を図る目的で、2003年1月までに全110郡に対して財政支援を実施している。しかしこの成果が期待されるほどあがらなかったことから、USAIDは現在、財政支援に対して懐疑的な態度をとっている53。USAIDは、そのほか女子教育、読書プログラム、HIV/AIDS教育も実施している。
今後は、「地方分権化サポートプログラム」(2004~2010年)を立ち上げる予定である。同プログラムでは、学校レベルでの学習環境整備に対する説明責任を高めること、および行政官(中央・地方)のキャパシティを構築することが目指される。
4) UNICEF
UNICEF(国連児童基金)は、fCUBE等のガーナ側の政策に基づいて、「国家キャパシティ強化プログラム(NCE)」、「子ども・学校・地域プロセス(Childscope)」、「幼児心理社会理性化強化プログラム(EPSIS)」の3つのプログラムを実施している。協力期間は2001~2005年、予算は総額1,000万ドルを予定しているが、2003年までに計429万ドルを支出している。なお「子ども・学校・地域プロセス(Childscope)」は、1996~2001年にも総額910万ドル(予算180万ドル、賛助金730万ドル)の協力が実施されていた54。従って1996~2003年までの協力総額は、1,339万ドルとなる。
5) GTZ/KfW
GTZ(ドイツ技術協力公社)は、fCUBE支援として、「母語教育支援プロジェクト(以下、ASTEP)」を実施した。協力期間は1997~2001年、協力額は290万ドル(500万マルク)である。GES教師教育局をカウンターパートとし、理数科教育に係る教員訓練プログラムのための小学校1~3年生を対象とした母語(5言語)による補助教材作成を行ってきた。作成した補助教材を活用し、10のパイロット教員養成校で試験的に用いて改定し、最終的には郡レベルに配布した 。また、公立教員養成校における研修と教員教育局の強化を、協力期間2001~2005年、協力額261万ドル(450万マルク)の予定で実施している。
また、KfW(復興金融公庫)はガーナの全38校の公立教員養成校に対して、校舎建設・リハビリ(宿舎を含む)、家具などを含むインフラ整備を行った。総額2,088万ドル(3,600万マルク)の予算である 。
GTZとKfWの1997~2005年の協力額を合計すると、2,639万ドル(4,550万マルク)となる。
6) オランダ
オランダは、後期中等教育のみを支援しており、リソースセンタープロジェクトを実施している。実施期間は不明、協力額は2,000万ドルである。技術学校15校と後期中等教育技術学校(Senior Secondary Technical School)555校の教室増改築、ワークショップ開催、教材支給、教材等管理・修理法の研修、教職員研修、カリキュラム改定等を実施している56。
7) フランス
フランス大使館は中学校のフランス語教育のためのフランス語教員養成支援を、2001~2004年、協力額100万ドル(800万フラン)で実施している。その他、高等教育機関におけるフランス語教育への支援を、毎年87.5万ドル(700万フラン)行っている(協力期間は不明)57。
8) EU
EUは一般財政支援を実施しており、援助は主に初等教育とプライマリ・ヘルスケアに向けられている(内訳は不明)。そのうち毎年585万ドル(500万ユーロ)が、学校建設へと活用されており、年間に約260校が建設されている計算となる。また技術協力として、教育省キャパシティ強化(特に教育省の財務部門)のための支援を実施していた。協力期間は1997~2001年であり、協力額は不明である58。
9) NGO
ガーナの教育セクターでは国際的なNGO(非政府組織)をはじめ多様なNGOが活動を行っている。その主なものを紹介する。
「ケア・インターナショナル・ガーナ」は、2000年まで学校とコミュニティの関係を活性化させることに焦点をあてた「学校とコミュニティ志向教育(SCORE)」(30万ドル)の活動を実施した。その後、基礎教育に関する500万ドルの活動や、地域キャパシティビルディング支援に関する200万ドルの活動、その他の59.7万ドルの活動を実施している。
「アクションエイド・ガーナ」は、基礎教育に関する63万ドルの活動、HIV/AIDSの調査・アドボカシーに関する42.1万ドルの活動を行っている。さらに「プラン・インターナショナル・ガーナ」は、30万ドルの学校教育改善プログラムと、16.5万ドルの就学前開発プログラムを実施している。
その他の主なNGOとしては、「カソリック救援サービス・ガーナ」、「ワールドビジョンインターナショナル・ガーナ」、「アフリカ女性教育者フォーラム・ガーナ」などが挙げられる。
10) 各ドナーのシェア
以上のような各ドナーの援助額の概算をまとめたものが表11である。これはあくまで、本評価調査で得られた情報に基づくもので、主要ドナーの援助動向を把握するための試算である。しかし、日本のシェアがこの数値より大きく前後することはないと考えられる。なお、詳細な分析は5章の5-4にゆずり、ここでは簡単に傾向をみておくこととする。
主要ドナー全体の援助額は、総額が3億3,246万ドルで、そのうち、基礎教育(fCUBE)支援が73%と圧倒的に多い。その他は多い順に、ノンフォーマル教育10%、高等教育7%、後期中等教育7%、職業訓練3%、となっている。日本だけが、全教育レベルを支援している。一方、DFID、USAID、UNICEFは、基礎教育(fCUBE)のみを支援している。
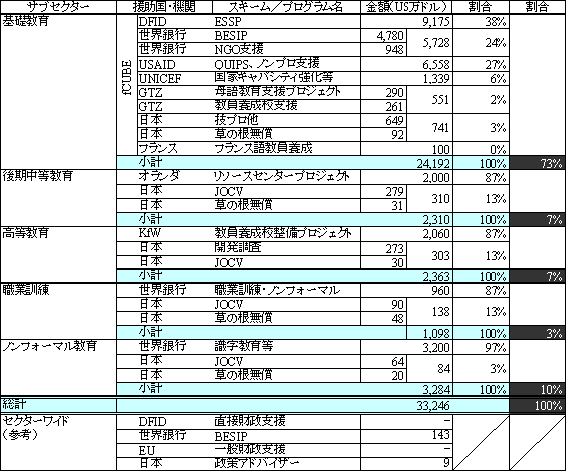
| 注: | 金額は2003年12月時点で把握できたもののみであり、すべて概算である。1ドル=110円、1ドル=8フラン、1ユーロ=1.17ドル、1マルク=1.72ドル、1ポンド=1.835ドルで換算。フランスの高等教育機関への支援は総額が確認できなかったため含んでいない。EUの技術協力は総額が確認できなかったため含んでいない。NGOは含んでいない。 |
| 出所: | 各ドナー資料、奥川(2002b)、松田(2002b)、同(2003b)、JICAガーナ事務所(2003 b)、拡大ドナー会議配布資料(2003年11月)、等より作成。 |
4 しかし、国の職業訓練機会の拡大に対する方策は、国内の有識者からも反論があり、さらに国民の間での大学進学意欲の高まり、ほとんどのドナーから支持を得られなかったことなどにより、1990年代はまったく低調なまま推移した。
5 横関他(2003)。
6 松田(2003b)による。
7 2003年11月拡大ドナー会合における出席者の発言、元GES副総裁およびドナーヒアリングによる。
8 Accra, Kumasi, Takoradi, Ho, CapeCoast, Tamale, Sunyani, Koforidua, Wa, Bolgatangaの10校。
9 ポリテクニックと同じレベルのdiplomaが授与される。
10 詳細は、5章5-4(1)10 中期目標2の項を参照のこと。
11 アクラポリテクニック校長、松田専門家コメントによる。
12 技術学校のみ。
13 1990年に創設。現在のスタッフ数は18名。関連する省・機関は8省・約30機関。
14 人材開発雇用省によるヒアリング、およびNACVETの局長との面談による。
15 北アクアピン郡の場合、幼稚園72校、小学校117校、中学校62校がある。
16 例えば、北アクアピン郡では7学区がある。
17 今回の、タマレ、北アクアピン郡の視察、および他ドナーのヒアリングによる。
18 実数で計算した結果。国家予算が10,442,100百万セディで、教育省予算が2,775,885百万セディ。
19 図5にみるように2003年の国家予算における教育省予算は3.7億ドルであるのに対して、2004年ESP予算における教育省予算は5億ドルと大きなギャップがある。
20 ガーナ教育信託基金(Ghana Education Trust Fund)のこと。詳細は、BOX5参照のこと。
21 District Assemblies Common Fund(DACF)のこと。詳細は、BOX5参照のこと。
22 すべて親の負担で賄われる。
23 ESR(2002)による。さらにESRでは、子どもを私立校に通学させているのは、経済的に裕福な家庭だけでなく、中流層にも及んでおり、その学費が家計を圧迫していると指摘している。在ガーナ日本大使館の運転手の場合も、月給と同じ程度の教育費をかけて子どもを私立校に通わせているということであった。教育費に関しては親族が援助するのが一般的なようである。
24 地域高校とは、通学可能な地元コミュニティのための高等学校で、寄宿舎費等がかからないことによる親の学費負担の軽減をねらったものである。寄宿施設がないため都会や他地域の生徒を惹きつけるのは難しく、定員割れの学校が多いことも問題となっている(ESRによる)。
25 ESR(2002)による。
26 World Bank(2003)による。
27 ファースト・トラック・イニシアティブ実施計画では、補修について、2003~2007年の期間に毎年7,200教室、2008~2015年の期間に毎年1,000教室の補修を目標に掲げている。
28 松田(2003b)。
29 横関他(2003)。
30 教員養成校卒業後3年間教職を経験したものは、有給の進学休暇を申請する権利を有する。制度利用者は、在学中、通常の教員給与が支給されるほか、低利の学生用融資(年間約117ドル)が受けられる。
31 近年改定された制度では、GESは候補者の選考の段階で専攻学科に枠を設けているが、それ以前は専攻に制約がなかった。また制度改定以降も、一旦受給認定を受けた後に勝手に専攻学科を変更してしまうことが問題とされている。
32 この有給進学休暇制度については、2002年に改訂が行われ、年間の制度利用者数の制限(年間5000人以下)、その学科別枠(数学、英語、理科など主要科目の教員に対する割合が大きい)が設けられた。また、現在審議中の教育基本法改正でさらに抜本的に見直される予定である。
33 横関他(2003)。
34 高等教育機関を卒業したものが義務として1年間の社会奉仕活動を行う制度。
35 タマレ州におけるJOCVヒアリングによる。
36 松田(2003b)による。
37 技プロ専門家ヒアリングによる。
38 ただし「ガーナ語と文化」の教科書はのぞく。
39 奥川(2002)による。
40 調査団によるタマレ、北アクアピン郡における現地調査視察およびヒアリング、さらにJOCVによるヒアリングによる。
41 2003年11月の拡大ドナー会議の教育長官の発言、奥川(2002)による。
42 ESP策定過程においは、JICAを含むドナー共催により全10州でそれぞれ大規模な地方説明会が開催され、情報の伝達と、地方教育関係者との意見交換が積極的に行われた(松田専門家)ことは高く評価される。しかし、これは教育行政の中央から地方への関係強化の足がかりをつけた段階であり、構造的な改革は今後の課題である。
43 調査団によるタマレ、北アクアピン郡における現地調査視察およびヒアリング、さらにJOCVによるヒアリングによる。
44 2003年11月の拡大ドナー会議の議論、ドナー個別ヒアリングによる。
45 中学校から、選択科目で「前職業スキル」・「前技術スキル」などの教科がある。
46 ESR(2002)による。ただし、松田専門家によるとTVET推進者の中にも読み書きや計算力を重視すべきという認識をもつ人もいるとのことである。
47 ESR(2002)による。
48 ESP(2002)による。
49 奥川(2002)による。
50 松田(2003b)による。
51 松田(2002)による。
52 国際協力事業団(1998)による。
53 USAIDヒアリングによる。
54 奥川(2002)による。
55 前出の技術学校との違いは不明。
56 奥川(2002)による。
57 奥川(2002)による。
58 奥川(2002)による。

