第2章 ガーナの一般概況
2-1 一般的概況
ガーナ共和国(以下、ガーナ)は、西アフリカの赤道よりやや北に位置しており、日本の本州より少し広い14万平方キロメートルの面積を有する。気候風土に関しては、南部の森林地帯は熱帯雨林気候で雨量も豊富で土壌もよく農業生産に適した地域であるが、北部および南部海岸地域はサバンナ気候で相対的に農業の条件としてはあまり恵まれていない地域である。
人口は、2002年現在2,010万人で、年人口増加率は2.2%(2000~2005年の平均)と高率である。また人口の多くは、首都アクラおよび第二の地方都市クマシのある南部地域に集中している。また同じ州内でも都市と農村の格差があり、農村地域が多い州ほど貧困問題が深刻である(図1)。宗教はキリスト教を中心に、イスラム教のほか、土着信仰も広く存在している。言語は、英語が公用語であるが、日常語には大きく分けると8つの現地語が使用されている。
図 1 州ごとの都市と農村の人口
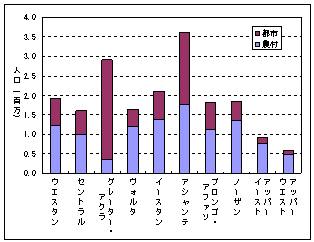
出所:2000 Population & Housing Census(2002)より作成。
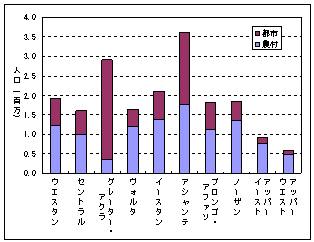
2-2 政治・経済状況
ガーナは、サハラ以南アフリカで最初に独立した国であり、1957年3月に旧宗主国イギリスより独立した。独立当初は世界最大のカカオ生産地であり、鉱業、林業、製造業ともに好調であったが、1970年代は、カカオの国際価格の急落、経済政策の失敗により赤字が拡大し、マイナス成長に苦しんだ。1981年末の2度の軍事クーデターにより政権についたローリングス氏率いる暫定国家防衛評議会(PNDC)は、1983年に経済復興計画を実施し、同時にIMFの構造調整融資を受け入れた。
その後、1985~1994年の間は年平均実質GDP成長率が3~5%と安定した成長を達成した(図2)。これによりガーナは“アフリカにおける構造調整の優等生”とIMFおよび世界銀行から評価されることとなった。
図 2 ガーナの実質GDP成長率の推移
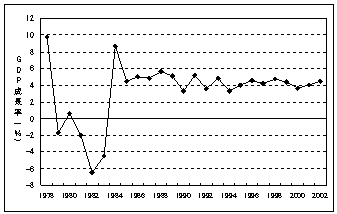
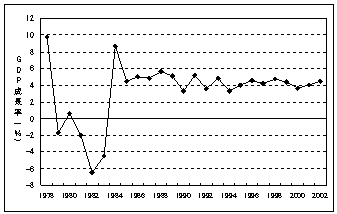
| 注: | データ出所の違いから、一部データ間の整合性がないものがある。 |
| 出所: | Corbo and Fisher (1995),PP.2906-7; World Bank, Trends in Developing Economies 1994, 1995; World Bank, 1993-2000はIMF、2001-2002はWorld Bankの各データより作成。 |
しかし、この安定した経済成長は、実のところ大量の援助流入により支えられたもので、国内産業の育成は遅れており、民間主導の成長構造とは程遠いものとなっている。また、高いインフレ率、過剰な累積債務、継続的な通貨(セディ)の下落、外貨準備高の減少というマクロ経済における構造的な問題を抱えており、結果として、2001年に債務削減措置の適用(拡大HIPCイニシアティブ 用語)を申請することを余儀なくされた。
政治面では、2000年12月に実施された大統領選挙と国民議会選挙の結果、野党のクフォー候補が新大統領に選出され、2001年1月にクフォー新政権が誕生した。この政権交代は、同国史上初めての選挙による政権交代であり、しかもその政権交代が平和裏に行われた点において大きな意義があり、ガーナの民主化の定着として内外から高く評価されている。
ガーナは独立以来、近隣諸国との関係を重視している。特に西アフリカ地域の平和と安定のために積極的に活躍しており、アフリカ統一機構(OAU)、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)等の地域機構において指導的役割を果たしている。また経済面においても、比較的充実した交通網や西アフリカ有数の近代的港湾設備を有するなどインフラ整備が進んでおり、西アフリカにおける拠点としての地位を固めつつある。
2-3 人間開発指数
国連開発計画(UNDP)の『人間開発報告2002』によれば、ガーナの人間開発指数は0.548で全世界対象国173国中の129番目、人間開発中位国に位置づけられている。出生時平均余命(56.8歳)、成人識字率(71.5%)、初・中・高等教育総就学率(42%)、一人あたりのGDP(購買力平価1964ドル)など、人間開発指数の算出に使われる指標は、すべてサハラ以南アフリカの平均より高くなっている。
しかし、人間開発指数は1985年を頂点として低下を続けている。これは、1980年代の構造調整政策を経て1990年代前半までは比較的良好な経済成長を遂げたにも関わらず、高い人口増加率等によって、国民一人あたりGDPの成長にブレーキがかけられていることが主な原因である。
2-4 貧困状況
貧困状況は、ガーナの生活状況を包括的に調査した「第三次ガーナ生活水準調査1992年」と「第四次ガーナ生活水準調査1999年」の結果から知ることができる。1992年から1999年の7年間に、貧困人口は51%から40%へと減少しており、全体としては貧困状況は改善しているといえる。しかしながら、改善の成果は一様ではなく、地域別貧困格差(都市部と農村部、北部と南部)および職業別貧困格差(都市労働者と食糧作物農民)は拡大している。特に北部サバンナ地域(ノーザン州、アッパーイースト州、アッパーウエスト州)など、農村の比重の高い州において(図1参照)、貧困問題が顕著でありガーナ政府の重要課題となっている。
2-5 国家開発計画
1990年代以降のガーナにおける国家開発計画としては、「長期国家開発計画(以下、Vision 2020)」(1995年策定)、「暫定版貧困削減戦略書(PRSP、後述)」(2000年策定)および現在の国家開発計画である最終版「ガーナ貧困削減戦略(GPRS、後述)」(2003策定)がある。以下、これらの国家開発計画を概説する。
(1) Vision 2020
Vision 2020は、1995年1月に発表された25年間の長期国家開発計画である。Vision2020では、2020年を目処に中所得国入りを実現するという大目標を掲げている。そして「人間中心の開発」をテーマに、(1)人材開発、(2)経済発展、(3)農村開発、(4)都市開発、(5)国家開発のための環境整備の5分野に重点をおいている。このうち人材開発の分野で、1)基礎教育の義務化・無償化、2)成人非識字率の引き下げ、3)女子就学率の向上、4)へき地教育の充実、5)科学・技術教育の強化、6)後期中等教育・高等教育の拡充、が提案されている。
その後、Vision2020を基に、5年間の中期計画「第一次中期経済社会開発計画1997-2000」が策定された。同中期計画は、すべての省庁、州、郡、市民社会の参加によって策定されたことに大きな特徴がある。しかし、Vision2020もその中期計画も、総花的であり、経済成長や財政の裏づけのない計画であったため、実効性のある計画とはなりえなかった。
このような中、90年代後半には、世界の援助潮流に呼応しセクターごとの開発計画の策定が活発化した。保健セクターでは他セクターに先駆け1997年にコモンファンド 用語を設置した「セクター・ワイド・アプローチ(Sector Wide Approach:SWAP)」用語が開始され、現在アフリカでもっとも進んだSWAPの1つといわれている。また、同時期、教育、農業、道路の各セクターにおいても、SWAP策定のための議論が進められた。
(2) 暫定版PRSP
1999年9月に世界銀行・IMFの総会で発案・合意された「貧困削減戦略書(Poverty Reduction Strategy Paper:PRSP)」用語の策定がガーナにおいても進められ、2000年6月に暫定版PRSPが完成した。
この後2001年1月に誕生したクフォー新政権においても、基本的に前政権の方針と世界の援助潮流を受け入れ、PRSPの策定が引き続き進められた。さらに新政権は、前政権とは異なり、重債務貧困国として、2001年3月に拡大HIPCイニシアティブを申請し、2002年2月に承認された。
(3) GPRS
2002年4月、世界銀行は2000年8月の国連総会で採択された「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals:MDGs)」用語の目標の1つである「2015年までに初等教育の完全普及(Education for All)(5章・BOX10)を促進するため、「ファースト・トラック・イニシアティブ(Fast Track Initiative:FTI)」用語を実施することを発表した。FTIは、MDGsへの取り組みが遅れている国を支援することを目的に、一定の基準を満たす国に対して、一定期間対外援助を集中させるというものである。ガーナもその対象国の1つに選定された2 。しかし、供与条件として完全版「貧困削減戦略書(PRSP)」の完成と、ドナーの承認を得た教育セクターのSWAPの策定が課せられた。そのため、ガーナ政府は完全版PRSPの策定を優先課題として取り組み、2002年6月に完全版PRSPである「ガーナ貧困削減戦略2002-2004(Ghana Poverty Reduction Strategy:GPRS2002-2004」を完成させた。このGPRS2002-2004は、Vision2020の基本的理念を受け継ぎ、またMDGsの目標も取り込んでいる。
さらに、その後「中期支出枠組み(Medium Term Expenditure Framework:MTEF)」用語(2-6参照)や、世界銀行の一般財政支援の新しい融資メカニズムである「Poverty Reduction Strategy Credit:PRSC」用語などと年度サイクルを合わせるために、内容をほぼ同じくした「GPRS 2003-2005」が完成した。これが2003年6月世界銀行・IMFに承認され、「最終版GPRS(以下、GPRS)」となり、現在の国家開発計画と位置づけられている。
このGPRSもこれまでの方針を踏襲し、Vision2020の基本的方向性とMDGsを取り入れたものとなっている。GPRSは国家目標として「経済成長による富の創出およびその平等な分配を通じての貧困削減」を掲げ、その達成のための優先分野として、1)インフラ整備、2)農村開発のための農業近代化、3)保健・教育を重視した社会サービスの強化、4)グッド・ガバナンス、5)民間セクター育成、を設定している。また、2004年度までに達成すべき数値目標を設定している(BOX 2参照)。
| BOX 2 GPRSにおける優先分野と達成目標 | |||||||||||||||||||
| 優先分野 1)インフラ整備 2)農村開発のための農業近代化 3)保健・教育を重視した社会サービスの強化 4)グッド・ガバナンス 5)民間セクター育成 |
| ||||||||||||||||||
2-6 行財政制度の新体制
ガーナは、前述したGPRSの下で、新しい行財政制度の包括的な体制づくりを進めてきた。教育セクター協力を検討する上でも大きな要因となりうるため、ここで行財政制度の新体制について簡単に説明する。
ガーナ政府は1997年に総合的な財政プロセスであるMTEFを策定していた。しかしながら、国家開発計画であるVision2020の中期計画が5年サイクルで策定されているのに対して、MTEFは3年サイクルであるなど両者の整合性が乏しく、ほとんど機能していなかった。しかし、クフォー新政権は、政策とMTEFを連動させるべく調整し、2003年についに3年をサイクルとするGPRSを完成させた。これによって、はじめて政策(GPRS)と財政(MTEF)がリンクした包括的な行財政システムが構築されることとなった。
具体的なプロセスは、「各省庁がGPRSに基づいて省の開発計画と予算案を作成し、財務省に提出する。財務省はこれを取りまとめ、国家予算をGPRSの優先順位にそって査定し、各省庁と折衝して、最終的なMTEFを決定する」、というものである。つまり、これまで各セクターで個別に策定されてきたセクター開発計画も、今後はGPRSの枠組みの中で策定されることとなった。また、各省庁の予算案作成にあたり、ドナーも翌年の援助額を開示することが求められるようになった3。
さらに、この包括的な行財政プロセスを支援する新しいモダリティとして、「一般財政支援方式(Multi-Donor Budgetary Support:MDBS)」が、2003年6月から導入された。これは、DFIDを中心とするドナーが推進してきたもので、国家の行財政システムにオーナーシップを持たせるために、財務省に直接、財政的支援をするというものである。また世界銀行はPRSCという別のメカニズムで一般財政支援に参加している。MDBSとPRSCが連動した新しい援助モダリティが2003年より開始されている。2003年9月現在のMDBS参加ドナーは、9か国・機関であり、表 3のような支援額を誓約している。
表 3 MDBS参加ドナーの一般財政支援誓約額 (百万ドル)
| 2003年 | 2004年 | |
| アフリカ開発銀行 | 29 | 29 |
| カナダ | 6.5 | 11 |
| デンマーク | 1.5 | 1.5 |
| EU | 45 | 30 |
| ドイツ | - | 6 |
| オランダ | 7.2 | 4.5 |
| スイス | 10 | 6 |
| 英国 | 52 | 60 |
| 世界銀行* | 128 | 125 |
| 合計 | 279.2 | 273 |
| 注: | *世界銀行はPRSC拠出額。 |
| 出所: | 橋本企画調査員「業務報告書(2003年3月27日~8月8日分)」。 |
以上のように、国家開発計画(GPRS)、国家財政(MTEF)、省庁の事業計画と予算案(SWAP)の3つが完全にリンクした行財政システムが2004年1月より始動し、また国家予算を支援する一般財政支援も本格的に稼動している。
2 対象国としてガーナを含む23か国が選定された。
3 日本も翌年の予定援助額を提示している。ただし、日本の場合、単年度予算であること、ガーナと会計年度のサイクルがずれていること、予算決定の時期が遅いこと、専門家派遣費、青年海外協力隊派遣費等の単価は通常公表していないこと等の理由により、開示できる予算額が限定されている。このため、MTEFに現れる援助額は実際より少ない。2004年度については、GTZ(ドイツ技術協力公社)など予算をまったく公表していないドナーもある。

