第1章 評価調査の概要
1-1 評価調査の目的
本評価調査は、わが国のガーナ教育分野に対する協力の実績を客観的に把握し、総合的かつ包括的に評価し、今後同分野への協力をより効果的かつ効率的に実施していくための教訓・提言を導き出すことを目的としている。また、評価結果を公表することにより、国民に対する説明責任(アカウンタビリティ)用語 を果たすことも目的である。
1-2 評価実施体制および評価手順
本評価調査は、株式会社アース アンド ヒューマン コーポレーションが、2名の監修者の協力を得て、実施した。評価者、監修者・オブザーバーおよび現地調査参加者は以下のとおりである。
評価者
監修者・オブザーバー
|
本評価調査は、「計画確定」、「国内調査」、「現地調査」、「分析・報告書作成」の4段階から構成されている。それぞれの実施日程は以下のとおりである。なお、現地調査(11月24日~12月4日)の詳細な行程については巻末資料を参照されたい。
本評価調査の日程
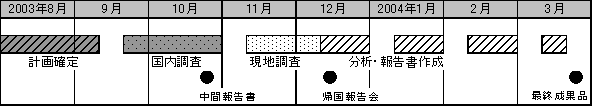
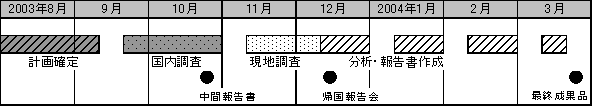
1-3 評価調査の手法
本評価調査は、『外務省評価ガイドライン』に基づき実施した。評価調査の手順としては、最初に「評価対象」を設定し、次に「評価の枠組み」と「評価スコープ」を検討した。さらに、本評価の限界についても考察した。
(1) 評価対象
評価調査対象期間は1998~2003年度上半期とし、この間に日本がガーナの教育分野(以下、教育セクター)において実施したODA事業の集合体を評価対象とする。また、基本的に教育省が所管する事業を対象としたが、一部、技術職業教育訓練に関しては教育省以外1でも実施されており、これも評価対象とした。具体的な評価対象は、表1の1)~7)の7事業である。また、8)ノンプロ無償用語 見返り資金のスキームについても、現在の対ガーナ教育セクター支援において重要な意味をもつため、参考として評価対象に含めた(第4章の4-2参照)。
表 1 評価対象
|
1) 技術協力プロジェクト「ガーナ小中学校理数科教育改善計画」 2) 研修員受入 3) アフリカ青年招聘計画 4) 教育省・政策アドバイザー型専門家(現地業務費による各種支援含む) 5) 青年海外協力隊 6) 開発調査「ガーナ国技術教育計画開発調査」 7) 草の根無償資金協力 <参考> 8) ノンプロ無償見返り資金 |
以下に、各事業の概要を簡単に解説する。なお、詳しい事業内容については4章の4-2を参照のこと。
| 1) | 技術協力プロジェクト「ガーナ小中学校理数科教育改善計画」(2000~2004年度) 技術協力プロジェクト(技プロ)では、小中学校の理数科教育における学力の向上を目指して、理数科教員を対象に現職教員研修が実施されている。協力対象地域は3郡である。 |
| 2) | 研修員受入 上記1)の技術協力プロジェクトのプログラム的協力の一環として位置づけられている。カウンターパート研修、国別特設、学位取得を目的とする長期研修等が実施されている。 |
| 3) | アフリカ青年招聘計画 国際協力機構(Japan International Coorperation Agency:JICA)が実施している青年招聘プログラム。1996年度より、ガーナ教育セクターから毎年3~4名の教員が日本に招聘されている。 |
| 4) | 教育省・政策アドバイザー型専門家 日本から教育省に政策アドバイザー型専門家が、1997年度より計3名派遣されている。各専門家の現地業務費によって、援助協調促進や連携事業など多様な支援も実施されている。 |
| 5) | 青年海外協力隊(JOCV) ガーナには1977年以降、青年海外協力隊(JOCV)が派遣されており、特に理数科隊員の派遣に実績がある。評価対象期間においては、教育セクターに計108名が派遣されている。 |
| 6) | 開発調査「ガーナ国技術教育計画開発調査」(1999~2001年度) 労働市場の変化に柔軟に対応できる高等教育レベルの技術教育の改革を目指す目的で開発調査が実施され、「技術教育改革マスタープラン」が作成された。 |
| 7) | 草の根無償資金協力 ガーナの教育セクターにおいては、草の根レベルに直接裨益する草の根無償資金協力が積極的に実施されている。評価対象期間においては、基礎教育レベルを中心に、教育セクターに計55件が実施されている。 |
本評価は、ガーナの教育セクターにおけるわが国のODA事業の集合体を、包括的に評価するものであり、プログラム(施策)レベルにおける「セクター評価」である。
これまでガーナの教育セクターにおけるわが国の協力は、プログラムを策定して実施するという方法がとられてこなかった。そのため、本評価では、最初に、評価対象期間にわが国が実施したODA事業を包括的に把握するための「目標体系図A」(5章・図8)を作成した。目標体系図Aは、ODA事業がどのような目的のために実施されたか、またそれぞれの事業がどのような関係にあったかを把握し、整理したものである。この目標体系図Aを、本評価の基本ツールとして活用した。
また、本評価では「目的」、「プロセス」、「結果」という3つの視点から多角的に評価する手法を採用した。各視点における「評価項目」、「評価内容・指標」、「主な情報入手手段」、「主な情報入手先」については「評価の枠組み」(表2)に整理した。
以下、本評価調査が設定した「目的」、「プロセス」、「結果」の各視点の評価項目・評価内容について、簡単に解説する。
「目的」に関する評価では、ガーナ教育セクターにおけるODA事業の集合体と「日本の上位政策との整合性」および「ガーナの開発政策との整合性」を評価項目に設定した。日本の上位政策との整合性を検証するために、「日本側 対ガーナ教育セクター開発課題体系図」(5章・図9)を作成して、これと目標体系図Aが整合しているかどうか確認した。また、ガーナの開発政策との整合性を検証するために、「ガーナ側 教育セクター開発課題体系図」(5章・図10)を作成して、これと目標体系図Aが整合しているかどうかを検証した。
「プロセス」に関する評価では、ガーナにおける一連の協力の「策定過程の妥当性」および「実施過程の妥当性」を評価項目に設定した。策定過程については、ガーナの援助ニーズと日本の戦略が協力策定にどのように反映されてきたかに着目しながら、教育セクター協力の発展プロセスを確認した。また、策定過程におけるステークホルダーの状況、他ドナーとの対話の適切さも確認した。さらに、協力の実施過程については、実施体制の適切さ、他ドナーとの連携状況を確認し、妥当性を判断した。
「結果」に関する評価では、「有効性」、「インパクト」、「自立発展性」の3つを評価項目として設定した。「有効性」では、目標体系図Aにさらに指標を設定した「目標体系図B」(5章・図13)を用いて、ガーナ教育セクター全体のマクロレベルでの変化と、日本の協力の効果と貢献の度合いを検証した。「インパクト」では、一連の協力実施によりガーナ・日本両国の上位政策への影響があったかどうか、またガーナ・日本両国の関係者に影響を与えたかどうかを把握した。「自立発展性」では、ガーナ教育セクターの自立発展性を予測し、またそれに対する日本の協力の貢献について考察した。以上が、評価の枠組みの概要である。
(3) 主な情報入手手段・主な情報入手先
本評価調査は、国内調査と現地調査(現地コンサルタントによるインパクト調査含む)の2つのパートに分けられる。各パートの「主な情報入手手段」、「主な情報入手先」は、以下のとおりである。
なお、技プロでは2002年12月の中間評価において詳細なインパクト調査(以下、中間インパクト調査)を実施しているため、このデータも適宜活用した。また、調査時点での現地の効果・インパクトを定量的に測定するために、現地コンサルタントによるインパクト調査(以下、インパクト調査)を実施した。これら2つのインパクト調査の詳細については、巻末資料に収録したので参照されたい。
| パート | 主な情報入手手段 | ||||||||||||
| 国内調査 |
| ||||||||||||
| 現地調査 | <調査団調査>
| ||||||||||||
|
<現地コンサルタントによるインパクト調査> 対象:草の根無償およびJOCV派遣裨益者 |
(4) 本評価調査の限界
本評価調査の限界としては、以下の3点が挙げられる。
- ガーナ側の教育セクター全体に関する制度の変遷や現状把握等の情報の未整備、統計や実績に関する一貫性の欠如、評価調査日程の限界等によって、現状認識に不正確な部分が含まれている可能性がある。
- ドナー関連の情報は、入手可能な既存文献・インターネットサイトおよび現地における短時間のヒアリングによるものから構成されており、詳細については事実と異なる部分が含まれている可能性がある。
- 日本の貢献の度合いを計った「日本の貢献指標」は、主に技プロの中間インパクト調査、今回の現地コンサルタントによるインパクト調査、現地視察により評価を行っているが、セクター全体の中での日本の貢献を定性的に把握するに留まること、またガーナ人の国民性としてよい回答をしたいという気持ちが無意識に働いてしまう傾向があることなどにより、正確性・客観性には限界がある。
|
BOX 1 評価スコープ 本評価では、より有益なフィードバックを導き出すために、評価調査時に特に念頭おくべき点、着目すべき点を「評価スコープ」として、以下の3点を設定した。一連の評価調査においては、これらのスコープを念頭において実施した。 スコープ1) 日本の援助はガーナにおける教育の質の向上に貢献しているか。 スコープ2) セクター・ワイドの援助協調の潮流に日本としてどう対応していくか。 スコープ3) ガーナの教育セクターにおける自立発展に、わが国としてどう支援していくか。 |
表 2 評価の枠組み(PDF)
1 第3章で詳述するとおり、ガーナでは人材開発雇用省、地方政府地域開発省、交通通信省などでも技術職業訓練教育を実施しており、わが国はこの分野に青年海外協力隊や草の根無償資金協力などのスキームで協力している。

