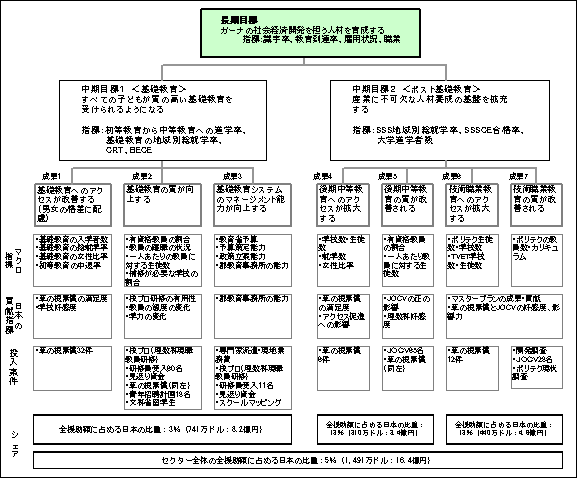要 約
第1章 評価調査の概要
1-1 評価調査の目的と手順等
本評価調査は、わが国のガーナ教育分野における協力を客観的に把握し、総合的かつ包括的に評価し、今後より効果的かつ効率的に実施していくための教訓・提言を導き出すことを目的としている。また、国民に対する説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことも目的である。評価調査は、(1)計画確定、(2)国内調査、(3)現地調査(11月24日~12月4日)および(4)国内での分析・報告書作成の4段階で行われ、調査期間は2003年8月~2004年3月である。
1-2 評価調査の手法
評価対象は、対象期間(1998~2003年度上半期)において、ガーナ教育分野(以下、セクター)で実施した以下の7案件(参考1件)である(詳細は、「4-2ガーナにおける援助状況」を参照のこと)。
(1)技術協力プロジェクト「ガーナ小中学校理数科教育改善計画」(2000~2004年度)
(2)研修員受入
(3)アフリカ青年招聘計画
(4) 教育省政策アドバイザー型専門家
(5)青年海外協力隊
(6)開発調査「ガーナ国技術教育計画開発調査」(1999~2001年度)
(7)草の根無償資金協力
(参考)ノンプロ無償見返り資金
本評価は、ガーナの教育セクターにおけるわが国のODA事業の集合体を包括的に評価するものであり、プログラム(施策)レベルにおける「セクター評価」と位置づけられる。これまでガーナ教育セクターにおいては日本のODA事業がプログラムとして実施されてこなかったため、本評価調査では最初にそれらがガーナ教育セクターにおいてどのような目的でどのような相互関係によって実施されてきたかを「目標体系図」(図2、後掲)を作成して整理し、評価の基本ツールとして活用した。
「評価の枠組み」は、外務省評価ガイドラインに基づいて、「目的」、「プロセス」、「結果」という3つの視点を採用し、各視点における「評価項目」、「評価内容・指標」、「主な情報入手手段」、「主な情報入手先」を設定し、これに基づいて評価を行った。詳細は、本文(P.6)の「評価の枠組み」に示すとおりである。
第2章 ガーナの一般概況
ガーナは西アフリカに位置し、気候は南部の多くは熱帯雨林気候で雨量も豊富で土壌もよく農業生産に適した地域であるが、北部および南部海岸地域はサバンナ気候で南部に比べ農業の条件としてはあまり恵まれていない。人口は2,010万人(2002年)で、人口の多くが南部地域に集中し、全人口の3割強が都市に居住する。南部と北部、都市と農村の社会経済格差が大きい。ガーナは、サハラ以南アフリカで最初に独立した国で(1957年)、近年は政治的に安定している。経済は、独立当初は好調であったが、カカオの国際価格の急落などによって1970年代後半以降マイナス成長に転じ、1983年にIMFの構造調整融資を受けるに至った。その後やや持ち直し90年代初頭までは比較的安定した成長を続けた。しかし、国内産業の育成が遅れており、高いインフレ率、過剰債務、通貨の下落などマクロ経済は構造的な問題を抱えている。2001年に誕生したクフォー政権はついに拡大HIPCイニシアティブの適用を申請した。
ガーナは独立以来、近隣諸国との関係を重視している。特に西アフリカ地域において平和と安定のために指導的役割を果たしており、経済面においても拠点としての地位を固めつつある。
国家開発計画としては、1995年に長期国家開発計画(Vision 2020)が、また2000年には暫定版貧困削減戦略書(PRSP)が策定され、その後2003年に最終版のガーナ貧困削減戦略(GPRS)が完成した。これらの開発計画では、「経済成長による富の創出およびその平等な配分を通じての貧困削減」を国家目標として掲げている。なお、2004年1月から、国家計画(GPRS)、国家財政(MTEF)、省庁の事業計画と予算案(SWAP)の3つが完全にリンクした行財政システムが始動し、それを支援する新しい援助モダリティである一般財政支援方式(MDBS)1 が本格的に稼動している。
第3章 ガーナの教育セクターの概況
3-1 政策・制度・財政
1961年に「教育基本法」が制定され、教育セクターの整備が進んだ。しかし、1970年代後半から80年代後半にかけて経済の低迷によって教育の質は後退した。そこで1987年に「教育改革」を断行し教育の効率化を図り、現在の6-3-3制を導入し、アカデミック偏重の教育から実用的な教育を目指した。その後、1990年の「万人のための教育に関する世界会議」を受け、国際教育目標「万人のための教育(EFA)」を実現するため、1992年に憲法を改正し“基礎教育(小学校・中学校)の義務化・無償化”を謳い、1996年より「基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム(fCUBE)」を開始した。他方、1991年には「高等教育改革」を打ち出し、高等教育へのアクセスの拡大に努めている。
2000年の世界教育フォーラムの「ダカール行動枠組み」、2001年の政権交代、2002年の世界銀行の「ファースト・トラック・イニシアティブ(FTI)」等の内外の変化を受けて、2002年に2つのセクターレビューが実施され、一気に教育の「セクター・ワイド・アプローチ(SWAP)」の流れが加速された。そして、2003年5月にすべての開発パートナーによって合意された教育SWAPである「教育戦略計画2003~2015(ESP)」が完成した。現在、このESPの本格的な取り組みが始まったところである。
ガーナの教育制度は6-3-3制で、基礎教育卒業以降は、アカデミックコースと職業コースを選択することができる。職業コースについては、教育省所管のもの以外に人材開発雇用省など他省の所管するものなどが多数あり、その全貌はガーナ側も正確には把握できていない。
教育行政は、教育省の政策立案・調整・監督の下、傘下の11の執行機関が実施している。その中でもガーナ教育サービス(GES)は人員・予算ともに一番大きく、就学前教育、初等教育、中等教育、技術職業教育訓練(TVET)の一部を管轄している。国家高等教育評議会(NCTE)は高等教育を、国家技術職業教育訓練調整委員会(NACVET)はTVETの一部とTVETに関する他省庁との総合調整を管轄している。地方においては、全国10州の州教育事務所の監督の下、110の市・郡にある教育事務所が実際のサービスを提供している。
教育セクター財源としては、教育省予算以外に、ガーナ教育信託基金(GETファンド)、郡議会コモンファンド、ドナー援助などがある。ESPの2004年度予算は総額約7億ドルで、財源は教育省予算(約5億ドル)、GETファンド・郡議会コモンファンド等(約1億ドル)、ドナー援助(約0.9億ドル)となっている。その支出内訳は、就学前教育・小学校・中学校48%、高等学校14%、教員養成4%、TVET1%、高等教育19%、管理/助成金運営11%となっており、TVET、教員養成、管理/助成金運営に関する予算が少ない。
3-2 教育セクターの現状と課題
ガーナの教育セクターの現状は、以下のとおりである。
- 総就学率は、初等教育80%、前期中等教育64%であり、まだ基礎教育レベルにおいても改善が必要な状態である。
- 基礎教育においては、総就学者数に占める私立校の割合(初等教育19%、前期中等教育15%)が高い。これは、ガーナにおいては大学進学志向が高く、そのため極端に質の低い公立校を避け高い学費を払っても私立校に入れる親が多いためである。特に都市部においては、4割が私立校に就学している。この傾向は就学前教育にも拡大している。
- 後期中等教育の総就学率18%(公立のみ)は、初等教育就学率が80%程度の国の中では低くない。
- 女子の割合は、初等教育47%、前期中等教育45%、後期中等教育(公立)41%、高等教育(総合大学)30%と、総じて男子より低い。TVETについては、女子の割合は13%と特に低い。
- 教員1人あたりの生徒数は少なく(小学校32人、中学校19人)、非効率であることが指摘されている。ESPでは、小学校で35人を目標値としている。
教育へのアクセスに関しては、都市と農村の格差が依然大きい。教育の質に関しては、低い学習到達度が最大の課題である。その大きな原因は教員の質の低さにある。背景には、ガーナの学歴偏重の給与・昇進体系の下で教員の平均的待遇が良くないこと、そのため有給進学休暇制度を利用する教員が多く離職率が高いこと、などがある。
教育マネージメントの向上も課題である。特に行政管理運営費や教育活動費の絶対的不足、教育省―GES-州教育事務所―郡教育事務所―学校―地域社会の全レベルにおけるキャパシティの不足、各機関の連携の不十分さが指摘されている。特に郡教育事務所の能力不足については、今後本格的な郡への権限委譲が予定されていることから、教育サービスの格差の拡大が懸念されている。
TVETについては、1987年の教育改革以降、従来のアカデミック偏重の教育から実用性を重視した教育を提供するという狙いのもとTVETの拡充を打ち出したが、その後ほとんど進展していなかった。しかし、クフォー新大統領の強い意向を受けて、ESPの4本の柱の1つにTVETが位置づけられたことから、今後の本格的な進展が期待されている。
3-3 他ドナーの援助動向
主なドナーのfCUBE以降の援助実績2は、本評価調査で得られた情報に基づくと、表1のとおりである。
表 1 主要ドナーの援助額とシェア(fCUBE以降)
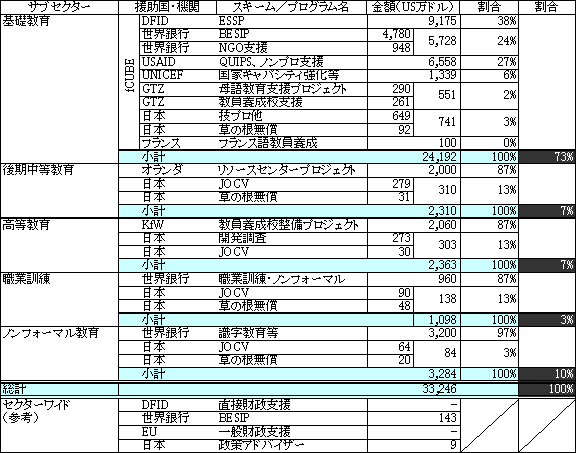
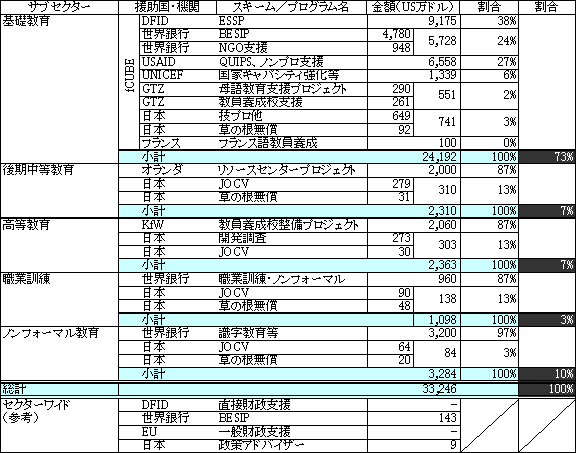
第4章 日本の援助動向
4-1 教育セクターにおける世界の援助潮流と日本の援助戦略
わが国のガーナ教育セクター協力は、世界的な援助潮流と日本の援助戦略に沿って実施されてきた。主な世界の援助潮流としては、1990年の「万人のための教育に関する世界会議」での「万人のための教育」、2000年の「世界教育フォーラム」での「ダカール行動枠組み」、同年のミレニアム開発目標(MDGs)などがある。一方、日本の教育セクターの援助戦略としては、1992年のJICA「開発と教育分野別援助研究会」設置以降、基礎教育重視が打ち出され、無償資金協力による小学校建設が急増した。さらに90年代後半になると理数科分野における技術協力が開始されハードからソフトへと軸足を移しつつある。このような実績を踏まえ、日本政府は、2002年6月のカナナスキス・サミットにおいて、新たな教育支援策である「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN)」を発表した。
4-2 ガーナにおける援助状況
ガーナにおいては、1988年から2001年の拡大HIPCイニシアティブ申請によって新規円借款が中止されるまで、わが国は二国間援助国において最大のドナーであった。しかし、教育セクターにおける援助は、1977年に開始された青年海外協力隊事業において長い実績がある以外は、投入規模の大きな案件として無償資金協力1件、開発調査1件、技プロ(実施中)など、多くはない。
評価対象案件の協力実績は、以下のとおりである。また、参考としてノンプロ無償見返り資金(見返り資金)も紹介する。
| (1) | 技術協力プロジェクト「ガーナ小中学校理数科教育改善計画」(技プロ) 本技プロは、fCUBEを支援するために、協力期間2000~2004年度の予定で開始された。プロジェクト目標は「プロジェクト対象地域の小中学校教員の指導力が向上する」、上位目標は「小中学校生徒の理数科学力が向上する」で、対象地域は、北アクアピン、タマレ、西アダンシの3郡である。主な活動は、教員養成校との連携による小中学校理数科教員に対する現職教員研修の実施、教材・シラバス・自習用補助教材の作成、理数科フェア(年1回)の開催等である。2002年12月の中間評価によって、プロジェクト終了後の自立発展のために、現職教員研修の国レベルでの制度化、校内研修の充実、運営資金に見返り資金を活用することなどが提言され、取り組まれることとなった。本プロジェクトの大きな特長は、研修員受入や草の根無償など多様な援助スキームと連携しプログラム的協力を展開していること、国内支援体制として「大学コンソーシアム方式」をとっていることなどである。協力総額(技プロ、研修員受入、見返り資金)は、2003年度までで約7.1億円である。2003年には、サハラ以内アフリカ諸国の理数科教育協力ネットワーク「SMASSE-WECSA」の第3回会合がガーナで開催され、ガーナ教育セクター関係者や技プロ関係者の士気を高めることに貢献した。 |
| (2) | 研修員受入 プログラム的協力の一環として、カウンターパート研修(2000~2003年度:計21名)と国別特設(1999~2003年度:計39名)が実施されている。その他、教育省・政策アドバイザー型専門家のカウンターパート研修(2001~2002年度:計5名)、学位取得を目的とする長期研修(2000年度~:計6名)が実施されている。 |
| (3) | アフリカ青年招聘計画 1993年に開催された第1回の「アフリカ開発会議」(TICAD I)の理念を受けて創設されたスキームで、1996年度以降毎年ガーナ教育分野から教員が日本へ招聘されている。評価対象期間においては、計18名が招聘されている。 |
| (4) | 教育省・政策アドバイザー型専門家 1997年度よりこれまでに、計3名の教育省・政策アドバイザー型専門家が教育省へ派遣され、ガーナ側の政策支援および日本の援助促進活動を行っている。また同専門家はこれまで現地業務費の活用によって、ドナー間の援助協調促進、連携事業など多様な支援を実施している。 |
| (5) | 青年海外協力隊(JOCV) ガーナにおける青年海外協力隊(JOCV)派遣は、1977年以来26年の歴史があり、特に高等学校への理数科隊員の派遣に実績がある。1998~2003年度においては、教育セクターに計108名が派遣され、協力総額はで約5.1億円である。その内訳は、高等学校(主に理数科隊員)が約6割、職業訓練分野が約2割などとなっている。 |
| (6) | 開発調査「ガーナ国技術教育計画開発調査」 労働市場の変化に柔軟に対応できる技術教育の改革を目指す目的で、1999~2001年度に実施され、協力総額は約3億円である。参加型アプローチを用いて「技術教育強化マスタープラン」が作成された。このマスタープランでは、技術教育機関とフォーマル・インフォーマル両部門を含む産業界の効率的な協力関係構築のために、CBT(Competency-Based Training)システム3が提案された。その基本的考え方がESPのTVET分野で取り入れられている。 |
| (7) | 草の根無償資金協力 草の根無償資金協力(草の根無償)は、日本大使館が中心となって行う資金協力事業で、ガーナにおいても積極的に実施している。評価対象期間においては、教育セクターで計55件、が実施され、協力総額は約2億円である。その内訳は、基礎教育(48%)、職業訓練(25%)、後期中等教育(16%)などとなっており、そのほとんどが校舎等の新築・増改築に活用されている。 |
ノンプロ無償見返り資金(見返り資金)は、日本政府が贈与した物資を現金化し裨益国の裁量で活用するものである。本来的には裨益国側の財源であるが、ガーナ側はESPの日本分予算として計上している。技プロを中心としたプログラム的展開の一環として活用された実績としては、2003年1月に第1回の活用(総額419万円、技プロ活動費等に充当)がある。教育省はさらに約1億円を財務省へ申請中である。この他、教育セクター全体では表2のような活用実績がある。
表 2 教育セクター全体のノンプロ無償見返り資金の活用実績
| US$ | 円 | 活用年 | |
| 国立コンピュータ・科学リソースセンター整備(全国) | 5,695,220 | 626,474,156 | 2003 |
| TTC(11か所)の教員住宅建設、車両、道路の整備 | 6,036,123 | 663,973,493 | 2003 |
| 基礎教育の教員住宅(40棟)(北部3州) | 6,346,667 | 698,133,333 | 2003 |
| 教室の補修、補助教材(アッパーイースト州の4郡) | 5,604,053 | 616,445,867 | 2003 |
| STD、HIV/AIDSに関するカウンセリング・教育(アクラ) | 566,667 | 62,333,333 | 2003 |
| 計 | 24,248,729 | 2,667,360,183 |
| 注: | $1=110円で計算 |
| 出所: | 国際協力事業団ガーナ事務所(2003b)「Background Study for policy dialogue on Japanese Official Development Assistance to Ghana: Supplementary Report」2003年7月 |
第5章 評価結果
5-1 目的
日本の対ガーナ教育セクター協力は、ODA大綱や中期政策などのODA基本政策と整合している。またこれらの基本政策に基づいて策定されたガーナ国別援助方針(1995~1999年版)およびガーナ国別援助計画(2000年策定)とも概ね整合している。さらに2002年6月に日本政府が新しい教育支援策として発表したBEGINともほぼ整合している。他方、ガーナ側の90年代後半の国家開発計画であるVision2020や、2003年に策定されたGPRSと整合している。また、ガーナの教育セクターにおける開発課題にも対応しており、妥当であると判断される。
以上の「目的」に関する評価の前提となったガーナ国別援助計画は2000年に策定されたものであるが、2001年以降、ガーナにおいては政権交代、拡大HIPCイニシアティブ申請、GPRS策定、ESP策定といった大きな政策的変化が生じている。また2004年1月からは、GPRS、MTEF、ESPおよびMDBSのすべてがリンクした総合的な体制が始動している。各ドナーの援助モダリティは、ガーナ側のオーナーシップを尊重する意味から、一般財政支援へと大きくシフトしつつある。従って、今後は教育セクター協力を考える際にも、このようなガーナの開発体系や援助モダリティの変化を抜きには考えられない状況にきている。
5-2 プロセス
| (1) | 案件策定における妥当性 日本の協力の案件策定プロセスは、大きく「初期の協力(1995年度以前)」、「本格的協力への準備(1996~1999年度)」、「本格的協力の開始(2000年度以降)」の3期に分けられる。それぞれの期において、国際的潮流、日本の援助戦略、ガーナ側の開発政策に対応しながら、ODAの既存スキームを柔軟に活用しかつ案件同士が相互に連携と調整を繰り返しながら発展しており、総じて適切であったと判断される。特に、1996年DAC新開発戦略でガーナを援助実施重点国に定めたことを受け、1997年より教育省・政策アドバイザー型専門家と援助協調対応の企画調査員を派遣したことは、ドナーコミュニティにおいて一定の存在感を確保し、またその後の日本の案件形成をスムーズにした大きな要因となったといえる。しかし、この時期はガーナ教育セクターでfCUBE支援が本格化し、同時に援助アプローチの変容も始まり、援助協調会議がほぼ毎日開催されるような状況であった。このようなガーナの情勢に対して、同専門家が一人で対応し、さらにもう1つの重要な任務である案件発掘・案件形成に当たらなければならなかったことを考えれば、援助策定・実施体制に十分な配慮があったとはいえない。 他方、日本・ガーナ双方の大学関係者が案件策定過程においては積極的に参加したことは、案件の質の向上に寄与している。また、現場レベルでは、学校現場の問題やニーズをよく把握しているJOCVの参加が、技プロ、開発調査、草の根無償の案件形成に大いに貢献している。ただし、それらは体系的になされているわけではなく、個人的な努力によるところが大きい。草の根無償とJOCVの案件策定過程においては、今回実施したインパクト調査の結果によると、JOCVは約半数、草の根無償は8割以上に住民の意向が反映されている。 |
| (2) | 実施過程の妥当性
実施体制については、図1のように整理される。在ガーナ日本大使館とJICAガーナ事務所(企画調査員、教育省・政策アドバイザー型専門家、技プロ専門家等含む)は、限られた人員の中で援助協調に対応するため緊密なコミュニケーションと連携を図ってきた。特に2003年春以降はタスクフォースを結成し、めまぐるしく変容するガーナの援助現場に対応するために連携を強めており、援助実施の効率性に寄与しているものと思われる。
図 1 実施体制図 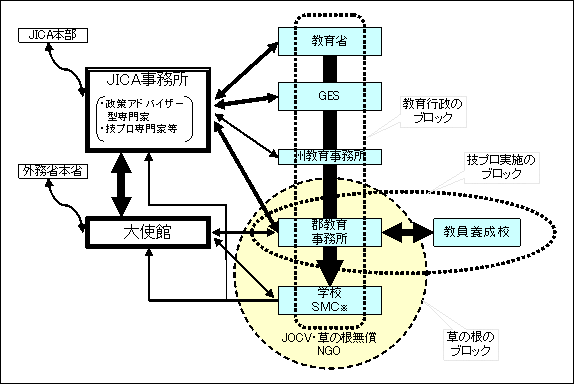 注:*SMCは、学校運営委員会の略。 また、図1にみる「教育行政のブロック」、「技プロ実施のブロック」、「草の根のブロック」という3つのレベルブロックに対して、日本の協力は相手方のオーナーシップを尊重し緊密な関係を保ちながら、それぞれに直接的に働きかけていることが特徴で、協力の効果を高めている。 さらに、各ブロックの主要カウンターパートを本邦研修に参加させることによって、日本の教育制度に対する尊敬と共感、JICAの支援体制やプロジェクトの協力方針への理解が深まり、日本の協力やプロジェクトの運営に積極的に関わるようになる姿勢が顕著となったことで、プロジェクト実施の効率性が高まったことは、特筆される。 他ドナーとの連携については、援助協調促進プロセスにおいて、規模はそれほど大きくはないがいくつかの実績があり、援助の効率性に貢献している。 |
| (1) | 有効性
|
||||||||||
| (2) | インパクト インパクトとしては、上位政策への影響として、開発調査のマスタープランの考え方や手法がESPに反映されている点が挙げられる。また、SMASSE-WECSA(アフリカ諸国の理数科教育協力ネットワーク)の第3回会議がガーナで開催され、ガーナ国内の理数科教育関係者の士気が高まり、自分達の経験を周辺諸国に伝えていきたいという意欲を持ち始めたことも特筆に価する。さらにSMASSE-WECSA会合の参加者がアフリカ全域に拡大したことは、日本がアフリカ域内において理数科教育協力のイニシアティブをとる下地づくりにもつながるであろう。 日本国内においては、ガーナにおける協力経験が間接的にBEGIN策定に影響を与えており、ODA政策へインパクトを与えているといえる。さらに国立大学が独立法人化する中で、国立大学がODAに積極的に参加していくという1つのモデルを提示している。加えて注目したいことは、ガーナ教育セクター協力では多くのガーナ人関係者を本邦研修員で受け入れているが、これらの研修員を受け入れている日本の大学(教員、学生)や、受け入れ地域の県教育委員会、地方自治体、住民、視察先小中学校児童・生徒等幅広い関係者に、国際交流と国際理解の機会の場を与えており、大きな正のインパクトを発現していることである。 |
||||||||||
| (3) | 自立発展性 ガーナの教育セクターの自立発展については、財源難という根本的な問題が解決しない限り難しいというのが実情である。しかし、日本のオーナーシップを大切にした協力姿勢は、実質的に人造りに寄与しており、自立発展の観点から高く評価される。 |
6-1 目的に関する教訓と提言
| (1) | ガーナ開発体系や援助モダリティの変化に対する適切な対応 日本のガーナ教育セクターに対する協力の基本方針は、1999年まではガーナ国別援助方針、2000年以降は2000年に策定されたガーナ国別援助計画に基づいている。しかし、2001年以降、ガーナにおいては、政権交代、拡大HIPCイニシアティブ申請、GPRSの策定といった大きな政策的変化が生じている。さらに、2004年1月からはGPRSとMTEF、そしてESPがすべてリンクした総合的な行財政システムが始動し、一般財政支援の新しい援助モダリティであるMDBSとも連動することとなる。このようにガーナ開発体系や援助モダリティは急激に変化している。以上のような情勢を考えると、今後の効果的な教育セクター協力を考えるためには、その前提であるガーナ国別援助計画の見直しを含めた日本の対ガーナ協力方針の根本的な見直しが必要である。 |
| (1) | 今後の案件策定について 2003年5月から教育SWAPであるESPが本格的に始動しており、今後の日本の教育セクターにおける案件策定はESPの枠組みの中で行われることが大前提である。案件策定過程においては、今まで以上にガーナ政府や他の開発パートナーと調整し、合意を得て案件を策定していくことが求められる。 その際、日本としては、これまでの協力の成果やアプローチの優位性をより説得力のある形で分析・整理し、今後の案件形成の軸としていくことが重要である。このような観点から、後述する6-3の(2)(基礎教育の質的向上への今後の支援に向けて)及び、(3)(「教育行政のブロック」への支援)で言及している2つの内容を提案する。 |
| (2) | 今後の案件策定における人員配置の見直し 上記6-1で述べたように、2004年よりガーナの開発体系や援助モダリティが新しい局面に入っており、援助方針の見直し作業や案件策定に関してはこれまで経験したことのない予測困難なプロセスを経ることが予想される。そのため、人員の拡充を含めた総合的な人員配置の見直しが必要である。その際、教育という1つのセクターだけでなく、MDBS支援も視野に入れたマルチセクターにおける日本の協力を総合的に把握し、案件策定および調整ができるような包括的な人員配置を考える必要がある。また、その際、ガーナの教育界に精通しかつ他ドナーの動向にも精通している人材(ガーナ人専門家含む)の登用が不可欠となるであろう。 |
| (3) | 案件策定過程における大学関係者・JOCVの活用 教育セクターの案件策定過程においては、ガーナ・日本双方の大学関係者の参加が案件の質を高めてきたため、今後も裨益国側と日本側双方の大学関係者のより積極的な参加が求められる。また、JOCVは現場の課題やニーズを掌握しており、その知見・情報をODAの質と効率性の向上のために組織的に活用していくべきである。 |
| (1) | 教育セクターの援助規模について ガーナ国別援助計画は、日本がガーナの教育セクターにおいて主導的な役割を果たすよう促している。しかし、評価対象期間における日本の援助総額は概算で17.4億円で、ドナー内で6番目である。さらに現在の案件策定・実施体制から考えると、今後2~3年の短期的なスパーンでみた場合、ガーナにおける援助モダリティ等の急激な変化に対応した新たな対ガーナ援助戦略なくして援助規模を拡大することは避けるべきである。当面は、MDBSへの他ドナーの動向を注視しつつ、日本としてもこの新しい援助モダリティにどう対応していくのか、またMDBSへ参加した場合の現地援助実施体制のあり方、モニタリング・評価手法などさまざまな検討課題に対する対応策を検討しておく必要がある。 |
| (2) | 基礎教育の質的向上への今後の支援に向けて ガーナ教育セクターの喫緊の課題は、基礎教育の質の改善、特に教員制度の構造的な問題への対応である。日本は、これまで技プロを中心とするプログラム的協力によってこの改善に寄与してきた。今後、現職教員研修の制度化など波及効果の拡大への取り組みが成功したとしても、技プロが終了する2005年以降、プロジェクトの出した芽をさらに大きく育てるための何らかのフォローアップが必要と考えられ、そのための方策を今から練っておくべきであろう。 他方、fCUBE開始以降、多くの開発パートナーが基礎教育の質的向上を目指して、相当規模の支援を実施してきているが、これまで開発パートナーが一堂に会してそれぞれの支援の具体的な成果、そのアプローチの有効性、あるいは反省点・改善方法など共有する場はなかった。そこで、日本がイニシアティブをとって、ESPのモニタリングと連動させ、支援手法について共同で議論できる場を設定することは有意義であろう。 |
| (3) | 「教育行政のブロック」への支援 現在、ガーナにおいては郡教育事務所のキャパシティの不足が課題とされている。また、本評価調査において、教育省―GES―州教育事務所―郡教育事務所―学校―コミュニティの縦のラインの連携が不十分であることが問題として浮かび上がった。 日本の協力は、これまでこの縦のラインである「教育行政のブロック」を一括して捉え、それぞれのレベルと直接パートナーシップを築きながら支援している。これが、日本の協力アプローチのユニークなところであり、キャパシティビルディングにつながっている。今後、教育セクターの総合的なキャパシティビルディングのために、この「教育行政のブロック」へのアプローチをより戦略的に活用し、体系的に支援していくことが考えられる。 |
| (4) | アフリカ域内の教育開発に向けて SMASSE-WECSAの会合は回を重ねるごとに規模が拡大し、日本のアフリカにおける理数科教育協力のプレゼンスを高めることに貢献している。今後、ガーナ教育セクターは、ますますSMASSE-WECSAの活動に積極的に関わり、アフリカ域内での教育開発の向上に資するための重要な役割を演じることが期待される。 また、ガーナは、政治的、経済的に西アフリカ地域において指導的立場を確立しようと努力している。このようなガーナ国内の気運の高まりを踏まえ、教育セクターにおいてもJICAスキームによる南南協力の展開が考えられる。他方、日本としてはガーナにおける協力経験を生かして、西アフリカ地域における理数科教育強化への新たな協力を展開していくことも考えられる。 加えて、日本はアフリカ域内の開発パートナーからADEA(アフリカ教育開発連合)への加盟が期待されており、わが国としては一刻も早くADEAへ加盟し、理数科教育強化支援を通じた教育の質の向上に努め、アフリカ域内における教育開発分野において一定の立場を築くことが期待される。 |
以上
1 世界銀行は、PRSCという新しい一般財政支援メカニズムで参加。
2 他ドナーの全援助実績を把握するのは極めて困難であるため、ここにまとめたデータはあくまで本評価調査で得られたデータによる概算である。
3 産業界が必要としている職務遂行能力・技術標準(Competency)の習得を目的とした教育訓練手法で、受講者は習得した能力・技術を実証することによってのみ、その成果を証明できる。このシステムでの訓練モジュールは、産業界のニーズに直結した技術訓練を多く含んでいるため、企業が提供する機会が増えることが予想される。