3.日本側実務家の評価
直接投資、貿易に関連する効果についてはそれに直接携わっている実務的な関係者からも其々の視点・論点から論及されている。今回の調査において日本の対中ビジネスなどの実務担当者等から聴き取り得た代表的な論点をまとめると、以下のようになる。
【論点1:外貨獲得に寄与し、その後の発展に貢献した初期の円借款】| ・ | 中国が改革開放政策を行った1980年代前半の対外経済関係における最大の政策課題は外貨の獲得であった。当時、中国政府は最有力の戦略的輸出産品として石炭を考えていたが、主要な炭坑地域は山西省などの内陸にあったため、鉄道の整備により、沿海の港湾までの輸送インフラの建設が焦眉の急であった。 この時期に初期の円借款供与は鉄道案件に注力し、また、その後の港湾建設への協力により、中国のこうした輸出戦略による外貨獲得に大きく貢献した。5 |
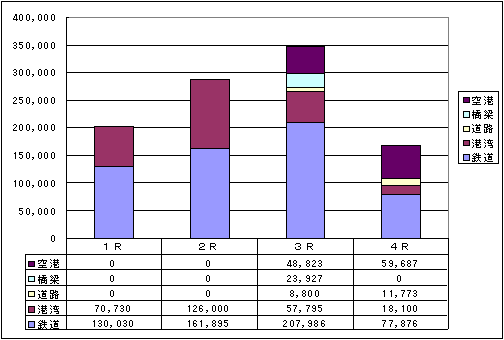
すなわち、山西省等における石炭を連雲港から輸出し、まだ加工製品を輸出する力が十分ではなかった中国の貴重な輸出産品となった。これによって初期の発展における外貨の獲得に大きな貢献を行った。
| 年 | 1980 | 1985 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱物性燃料輸出金額 (単位:億ドル) |
42.8 | 71.3 | 52.4 | 46.9 | 41.1 | 40.6 | 53.3 | 59.3 | 69.9 |
| 輸出に占める構成 (%) |
23.5 | 25.9 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 |
また、2000年に終わった第9次5ヵ年計画ではエネルギー交通のボトルネック解消が重視されており、円借款の供与方針は現在の発展戦略の前提として整合性をもっている。6
【論点2:総合的インフラは進出地域を決定する重要ファクター】
実際に円借款を含むさまざまな資金ソースにより、基礎的なインフラが整備され、企業進出が可能になったとの日系メーカーの指摘もある。具体的には中国での進出地域を決定する要因としては(財)日中投資促進機構の調査(図表IV-3)においても第一、第二がそれぞれ「外国企業優遇地区の存在」、「有望な市場の存在」であるが、それに次いで「インフラの整備状況」、「交通の便」などのようなインフラに関連した理由があり、同様な観点から大連、北京、威海、上海、広州、西安への製造拠点(合弁会社)が設立されているというものである。7進出目的が迂回輸出拠点としての進出の場合は港湾などのインフラが重要であることは周知の如くであるが、そうでない場合、すなわち進出目的が第三国への迂回輸出拠点というよりも消費者に密着して国内市場を狙う場合でも国内物流のためのインフラの整備状況が重要であるとされている。この観点から大連、北京、天津、河北、山東、上海、江蘇、杭州、広東に進出している家電メーカーもある。8
| ・ | また、中国のWTO加盟に伴い、外国企業にも交通運輸セクターへの投資が開放されるが、外資企業の運輸事業への投資を引き付ける前提となる道路建設は円借款や国際機関の借款が大きな役割を果たしたと評価されている。具体的には上海を起点とした道路網は非常に整備され、物流ビジネスを展開しやすい環境整備となった。上海周辺に進出している日系の製造業にとってもコスト競争力のある製品を上海から輸出できる。9日系メーカーサイドからの認識においても1995年前後より中国の物流事情は急激に好転し、鉄道、道路、橋梁の整備進展とトラックの質の向上により、現在では小口の定期便混載便を除いて物流問題の解決はそれほど困難ではないレベルに到達とされている。この結果、配送コスト削減が実現されたという。10 |
【論点3:直接投資を呼び込む顔として効果の大きい空港整備等の象徴的インフラ】
| ・ | 空港の整備により、投資家の印象を向上させ、直接投資を呼び込む力となっているとの指摘もある。例えば、在上海の日系商社駐在員によると、浦東空港の建設は日本企業にとってもプラスであると認識されている。空港は都市の「顔」であり、新しい国際空港が完成したことで上海が大きく変わったことを外来者に強く印象付け、投資を呼び込む力となる、という。11 |
|
図表IV-3:日本企業が中国進出の立地を決めた主な理由(%)
注:回答数499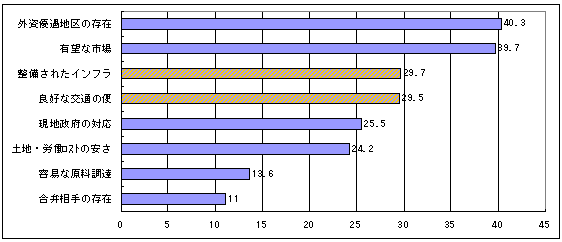 資料:第6次日系企業アンケート調査(日中投資促進機構2000年6月) |
いずれにしても、ともすれば「箱もの」建設として批判されがちなインフラであるが、日本企業をはじめとするビジネスの進出前の立地決定や進出後のオペレーションといった投資環境整備とそれに伴う経済発展・貧困削減に大きな影響を与えていると言うことが推測できる。
こうした直接投資によって、この20年間で輸出製品は大きく変わった。改革開放当初は最大の外貨獲得製品である石炭(鉱物性燃料)を輸出するために鉄道、港湾を整備して、経済発展の支柱としたが、現在、第二次製品(加工製品)の機械・輸送用機械が最大の輸出製品である。
また、この変化は単に製品の変化に止まらない。輸入を見ると前者は構成比でこの20年で50.3%→10.2%となったものの、後者は4.7%→30.2%に跳ね上がっている。すなわち、前者は単純な貿易取引きの製品であったが後者は外資企業などの垂直分業に関連する貿易、即ち投資関連貿易である。
OECDは2000年10月9日に1979年の改革開放政策の開始以来、中国への直接投資は約3060億ドルを超えたと発表した。これは米国に次ぎ第二位であり、過去20年間の世界中の対外直接投資の10%、発展途上国が吸収した直接投資の30%を占める。1992年以前は中国への外国資金流入といえば全体の60%が「借款」であったが、1992年の南巡講和以降は逆に「直接投資」が70%を占めるようになった。12
こうした中国への直接投資の増加はインフラなどのハード投資環境の整備が進んだことと、優遇措置、そして近年では市場の潜在力の顕在化によるところが大きい。即ち、当初の開発目的である石炭輸出による外貨獲得から直接投資の呼び込み、加工品の輸出へと貿易の高度化による開発政策になってきたが、こうした政策に円借款等のインフラ整備は合致し、政策を支えてきたと言うことができよう。
| 種類・年 | 鉱物性燃料・潤滑油(第一次産品) | 機械および輸送機械(第二次産品) | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 金額(億ドル) | 構成比(%) | 金額(億ドル) | 構成比(%) |
| 1980年 | 91.1 | 50.3 | 8.4 | 4.7 |
| 1985年 | 138.1 | 50.6 | 7.7 | 2.8 |
| 1990年 | 158.9 | 25.6 | 55.9 | 9.0 |
| 1994年 | 197.1 | 16.3 | 219.3 | 18.1 |
| 1995年 | 214.9 | 14.4 | 313.9 | 21.1 |
| 1996年 | 219.3 | 14.5 | 353.1 | 23.4 |
| 1997年 | 239.3 | 13.1 | 437.0 | 23.9 |
| 1998年 | 206.0 | 11.2 | 502.3 | 27.3 |
| 1999年 | 199.3 | 10.2 | 588.3 | 30.2 |
資料:中国対外経済貿易年鑑1999・2000年版、中国海関統計2000年
結論として、対中ODAの日本に対する効果は、援助が進出企業にとってより望ましい事業環境の実現に寄与し、現地での生産の円滑化・日本との分業体制の確立を通して日本に還元されていると指摘することができる。
| 5 | 経済産業省担当官 |
| 6 | 「MRI中国情報」2000年11月号 |
| 7 | 日本総合家電メーカーの例 |
| 8 | キャノン、松下電器等の例 |
| 9 | 経済産業省担当官、日本の大手物流会社などはこうしたインフラを背景に中国沿海部において日本と同じ程度の水準の配送サービス事業の展開を目指している。 |
| 10 | 斎藤智久氏(前上海花王有限公司董事長兼総経理)、「MRI中国情報」2000年3月号 |
| 11 | 日本大手商社上海駐在員談 |
| 12 | 中国証券報2000年10月11日 |

