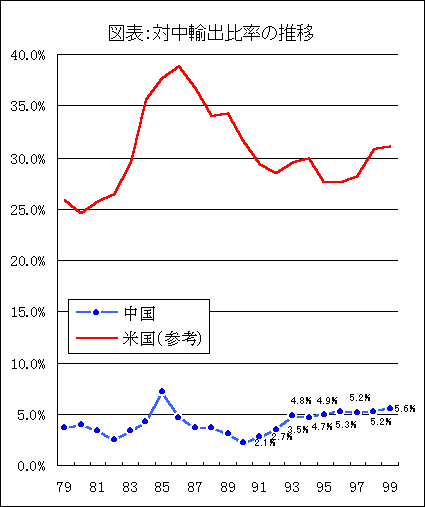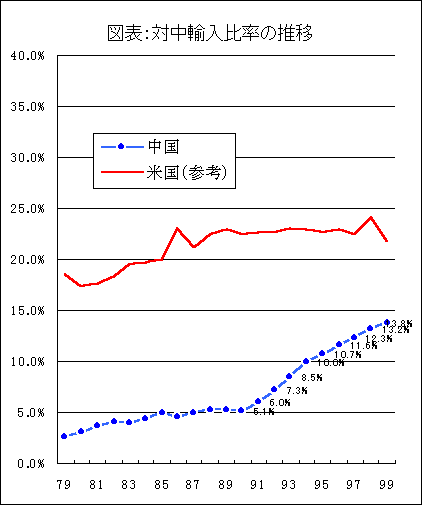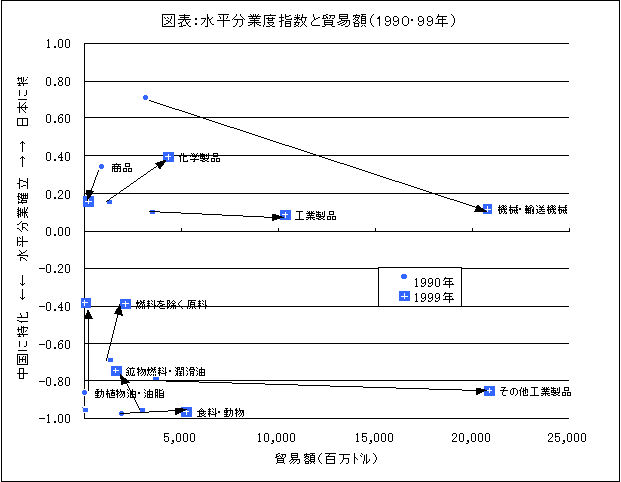3.日中貿易にみる経済の連携強化
日中貿易は近年大幅に拡大し、1991~97年は毎年史上最高記録を更新した。日本側の通関統計では、1998年の日中貿易総額(輸出+輸入)は1997年比円ベースで3%減、ドルベースで10%減となったが、1999年には総額665億ドル(7兆5,290億円)に回復した。2000年上半期では輸出・輸入とも二桁台の拡大が続いている。IMFの統計を用いて1979年以降の日本の対中輸出・輸入・貿易収支の推移を示したのが図表 III-7である。輸出は1995年以降横這いとなっている一方で、輸入の拡大が顕著である。貿易収支は1988年以降赤字(日本側の入超)が定着しており、1999年には196億ドルの赤字を記録した。このように、日本の対中貿易の構造は、近年大きな変化を遂げてきたことが窺える。
| 図表III-7 対中輸出・輸入・貿易収支の推移 |
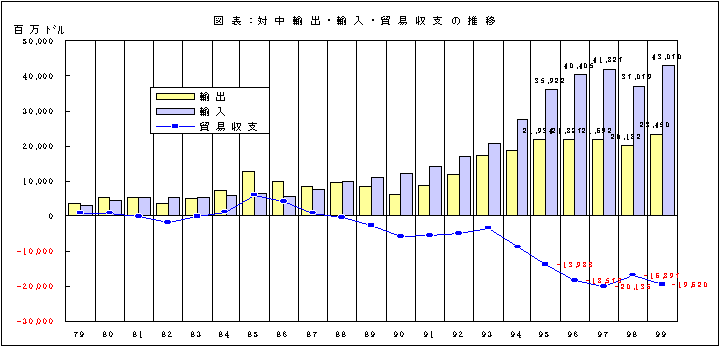 |
| 資料:IMF, “Direction of Trade Statistics” |
| 貿易規模の拡大によって、日本にとって中国は現在米国に次いで第2位の貿易相手国、中国にとって日本は第1位の貿易相手国となっている。しかし、輸出・輸入それぞれにおける中国の重要性はかなり異なる。グラフからも明らかなように、中国は日本の輸出相手国としてよりも、輸入相手国としての方がプレゼンスは大きい。 日本の輸出総額に占める対中輸出額は1993年以降ほぼ5%の水準で横ばいとなっている。最大の輸出相手国である米国のシェアが1986年のピーク時と比較すれば低下傾向にあるとはいえ、依然として3割程度を維持していることからすれば、対中輸出規模はその約6分の1に過ぎない。そして、近年の推移には両者の差が縮小して行く兆候は見られない。 一方で、対中輸入比率の上昇は顕著である。1980年代は輸出と同様にほぼ5%程度のシェアであったのが、1990年代に入り確実にそのシェアを拡大させている。1999年には日本の全輸入額の13.8%が中国からの輸入であった。米国のシェアは20%強で横這いとなっており、この傾向が今後も継続するのであれば、いずれ米国と中国のシェアが逆転することもありうると考えられる。
対中直接投資の項で触れたのと同様に、こうした日中間の貿易関係の変化と対中援助の間の因果関係は必ずしもダイレクトなものとしては解明できない。しかし、援助期間に中国の対日輸出の拡大が実現していることからは、中国の産業が世界市場に供給できるだけの輸出競争力を達成したといえる。因果関係を明確にできないまでも、中国がこのような自律的な成長軌道を実現しつつあることは、日本の援助目的にも合致する望ましい結果である。 【日中間の水平分業の進展】 本項では、貿易関係の変化の裏で進展していると思われる両国産業間における分業体制(産業内貿易)を統計データから分析することとする。2国間の貿易関係を分析する際に用いる指標としては、一般に顕示比較優位指数(RCA)、水平分業度指数(あるいは貿易特化係数、競争力係数などとも呼ばれている)などがある。 後者の水平分業度指数は、ある国の特定産業の特定国に対する輸出と輸入の差額(すなわち貿易収支)を貿易総額(すなわち輸出と輸入の和)で除したものである。日中間の貿易に基づく水平分業度指数は、0に近いほど水平分業体制が確立されている(両国間の特定の産業で相互に同程度の輸出入が行われている)ことを示し、+1に近いほど日本側が一方的に輸出している状態、-1に近いほど日本側が一方的に輸入している状態を表している。 水平分業度指数の定義
日本の継続的な対中援助が中国経済の自律的成長を促進してきたと仮定すれば、日本側が一方的に輸出していたような品目が、まず中国で少しずつ現地生産ができるようになり、そして日本に対しても輸出していくようなプロセスで産業が発展していくはずである。すなわち、産業ごとに貿易データをみたとき、かつては+1に近かった水平分業度指数が、ゼロ方向にシフトしていく動きが日中間の水平分業の確立、あるいは中国の輸出競争力の向上を示すと考えることができる。 もちろん、水平分業度指数による分析は、事後的な貿易構造の検証を行うためのものであり、その変化がどのような要因を反映し、実現しているかを知る指標ではない。 (a)貿易全体から見た水平分業度 OECDの品目別貿易統計データに基づいて日中間の水平分業度指数を算出したのが、次頁のグラフである。この中で最もはっきりした動きを示しているのは、機械・輸送機械分野(SITCコード1桁分類の第7分類)における水平分業度指数である。1990年代前半には0.6~0.7程度であった水平分業度指数は1999年には0.12まで低下した。すなわち、かつてこの産業分野では日本が中国に対して全面的に輸出していたが、その後中国からの輸入もかなり増加したことを示している。一方、中国に生産が特化している品目に関する水平分業度指数の推移を見ると、貿易規模が小さいいくつかの分類を除いて、中国側の圧倒的な出超は変わっていない。具体的には「その他工業製品(SITC8)」、「食料・動物(SITC0)」などである。SITCの第8分類に含まれるのは、家具、衣類、靴などであり、中国が全世界を相手に貿易を行っている品目である。水平分業度指数の問題点の一つとして指摘されるのは、国内生産規模に対して貿易額が極めて小さいケースでも、輸出と輸入の関係次第では指数が大きく変動し、水平分業体制の全体像を適切に表さない場合があることである4。したがって、水平分業度の変化と同時に、その分類の貿易がどの程度の規模なのかを把握しておくことも重要である。 |
| 図表III-10 日中間貿易からみた水平分業度 |
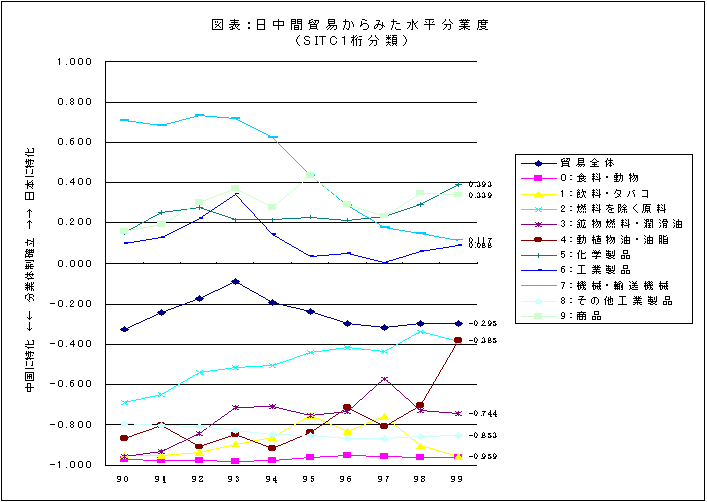 |
| 注:SITCコードによる貿易分類 資料:OECD, “International Trade by Commodity Statistics”より三菱総合研究所作成 |
日中貿易の場合、「工業製品(SITC第6分類-皮革・繊維・鉄鋼など)」、「機械・輸送機械(SITC第7分類)」、「その他工業製品(SITC第8分類)」など、工業関連製品のウェイトが圧倒的である。しかも、これら品目は1990年代において貿易規模が急拡大している。一方、上図で分業体制が進展しているかにみえる動植物油脂や原料類の貿易量はごくわずかであり、分業体制の確立を示しているわけではない。
(b)機械・輸送機械(SITC第7分類)における水平分業度 既にみたように水平分業が大きく進展しているSITCコードの7分類には、一般機械・輸送機械など従来から日本が特に高い輸出競争力を持っている製品が含まれている。この分野の水平分業をさらに細かく見るため、SITCコードの2桁分類で水平分業度指数を算出してみたのが次図である(7分類に属する品目のうち、そのシェアがこの分野の5%以下であるものは省略した)。 グラフが示すように、一般機械・輸送機械の分野に属する全ての品目分類で、1990年と比較すると1999年には日中間の分業体制が進展していることがわかる。特に、通信・録音機器に関しては、1996年に水平分業度指数がプラスからマイナスに転じていることから、日本の輸入規模が輸出規模を上回るようになったことを示している。事務機器・自動情報処理装置に関しても同様の状態であり、中国に対しては出超から入超へと転じている。この分類の中で比較的変化が少なかったのは特殊機械ぐらいであり、低下傾向にあるものの0.8のレベルは維持している。 水平分業度指数は、単にある産業分類の貿易が出超になっているかどうかを示すに過ぎず、生産コストや価格の情報はおろか、国内需要の大小による調整すら行っていないのであるから、国際競争力や水平分業の進展を正確に測定するものではないとする指摘もある。しかし、ここで得られた結果は、これまで日本が一方的に輸出していた財を中国側でも生産・輸出できるようになったことを明示している。この間に、日本企業の中国進出ラッシュという背景もあり、両国間で生産の分業体制が確立されつつあると考えることは極めて妥当であろう。 |
| 図表III-12 日中間貿易からみた水平分業度 | |||||||
 |
|||||||
| 注:(a)SITCコードによる貿易分類 (ただしこの分野におけるシェアが5%以下の項目を除く)。 (b)各分類の英文表記は以下の通り。
|
|
(c)その他工業品(SITC第8分類)における水平分業度 最後に中国が強力な競争力を有しているとされる、SITCコードの8分類「その他工業製品」を7分類で見たのと同様に2桁分類にブレイク・ダウンして分析する。 この分類は撮影機器類を除くと中国が圧倒的に優位な品目ばかりであり、その傾向は時間が経ても変化していない。例えば、8分類全体の貿易額の半分以上を占めるアパレル関連製品については、現在では日本からの輸出はほとんどなく、中国から一方的に大量に輸入されている。中国の衣料製品は安価であるだけではなく、品質の向上も広く認識されるようになってきており、日本の大手アパレルメーカー、商社などに対して大量に納入している。また、この分野の貿易総額の1割弱を占める靴製品に関しても同様であり、日本からの輸出はほぼゼロであるのに対して、中国からの輸入は巨額である。 |
| 図表III-13 日中間貿易からみた水平分業度 | |||||||
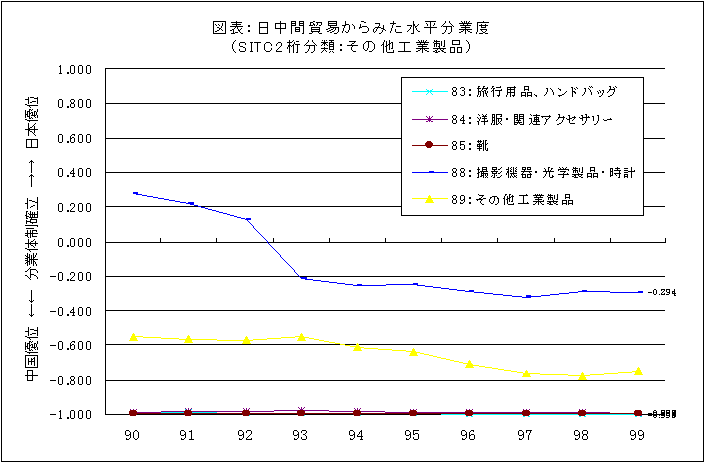 |
|||||||
|
|
これらの品目は、大量の低廉な労働力を有する中国が圧倒的な競争力を有する分野であり、将来にわたって日本と生産工程を分業していく可能性はほとんどないと考えてよい。日本の関わり方は企画・デザイン・マーケティングなどの分野であり、ノウハウや技術移転においては中国との協力体制の強化も可能であろう。 以上、貿易規模の大きいSITC7分類と8分類に焦点を当てて日中間の産業内貿易を概観したが、総括すると日中貿易においては、(a)日中間で分業が進展している貿易品目、(b)中国に輸出が特化する貿易品目、以上2つのグループに大別することができる。(a)の品目のほとんどは元来日本が特化していた品目といえるため、いずれの品目についても中国が競争力を強化・維持しているとみなすことができる。 留意すべき点は、このような分業体制の確立が、日本企業にとっても生産効率を向上させコスト競争力を確保させるメリットがあるという点である。ダイレクトな因果関係は示せないまでも、この背景に日本の対中援助が存在し、現地の経済インフラを整備することを通して、援助がさまざまな側面から現地の生産・輸出能力の強化に貢献したと考えることが可能である。それによって、最終的に日中間の産業内貿易が活発化しているのであれば、このことも対中援助の効果として捉えることができるだろう。 |
4この指標がしばしば使用される理由は、計算の容易さにあるといってよい。一般に、各国とも貿易統計は比較的整備されているのに対し、貿易統計の品目分類と工業統計の品目分類が簡単には対応しないという問題がある。