2. 対中直接投資にみる経済の連携強化
日本の対中直接投資が本格化したのは1990年代に入ってからのことであり、1992年に投資額が10億ドルを超すと対中投資ブームが一気に進展し、1995年のピーク時点では45億9,000万ドルを記録するまでに拡大した。その後アジア経済危機や長期化する日本の景気減退の影響もあり、1999年の投資金額は7億3,600万ドルと1990年代初頭のレベルにまで縮小した。しかし、中長期的に見れば、日本企業にとって中国が依然として魅力的な進出先であることは間違いない。
過去20年間の対中直接投資の動きを対中ODAと合わせて見ると、1990年代半ばに向けて拡大し、その後縮小するというトレンドは類似しているが、対中ODAの変動幅は直接投資の変動幅より遥かに小さい。1992年に直接投資とODAの金額が逆転してから通貨危機が発生する1997年までは、直接投資がODAを大きく上回る規模で推移していた。
しかし、通貨危機以降、直接投資が落ち込む中で、両者の規模は再び逆転している。
こうして見ると、ODAの規模も当然毎年変動しているものの、直接投資との比較においては中国にとってより安定的な資金の流入源ということができる。
下図にはもう一つの比較対象指標として、対ドル円レートも表示した。1985年のプラザ合意以降の円高急進後もしばらくの間は、1987年のような例外を除けば日本企業の関心はASEANに向けられており対中直接投資は必ずしも増大していない。しかし、ASEANへの進出が一巡すると、次は中国へのシフトが活発化し、円高が進展した1992年から1995年は対中直接投資も増加し、ついに1995年には最高額を記録している。このような流れを見る限りは、為替レートと直接投資の間にも何らかの因果関係があると推測される。
| 図表III-5 対中FDI・ODA・円ドルレートの推移 |
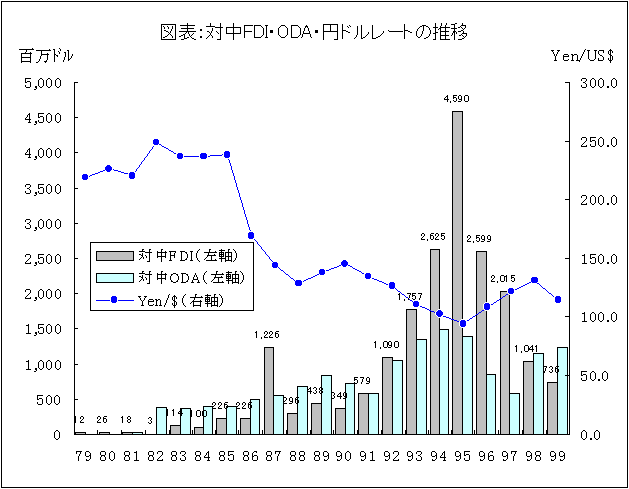 |
| 資料:IMF, “International Financial Statistics,” 大蔵省「国際金融年報」 注:FDI:外国からの直接投資 |
【対中直接投資の決定要因】
この為替レート以外にも、例えば対中ODAによって現地の投資環境が整えられ、日本からの企業進出を容易にしたと考えれば、対中投資の推移のある程度はODAの推移で説明することができるはずである。当然の事ながら、投資行動の決定要因としては、統計データで捉えられるもの以外にも様々な要因が関係していたと推察されるが、ここでは統計的に分析が可能である主要指標に限定し、日本の対中投資の決定要因を分析することを試みる。具体的には、基本的な重回帰分析によって、選択した説明変数が対中直接投資の動きをどれだけ説明しうるのか、またその中で対中ODAがどの程度の重要性を持っていたかを推計する。もちろん、対中援助は日本だけではないこと、データ系列として20年分しか分析対象として取り上げられないこと、その間にプラザ合意による円高急進、天安門事件、アジア通貨危機等の突発的な環境変化があったことなど、統計的な分析上のさまざまな制約があることは改めて指摘するまでもない。
まず以下では、対中直接投資を説明する要因の候補と想定される符号条件を示す。
| ○被説明変数 ・ 対中直接投資 ○説明変数(()内は想定される符合) ・ 対中ODA(+) 対中ODAによって現地のインフラ整備が促進され、投資環境が改善することから対中直接投資も拡大する。 ・ 対中輸出(+) 海外展開のステップとしては、いきなりリスクの高い直接投資を実施するよりも輸出でその市場参入の可能性を検討することが一般的である。したがって、輸出の拡大に併行して対中直接投資も増大することが考えられる。 ・ 中国のGDP成長率(+) 現地の経済が好況であるときこそ、ビジネスチャンスを狙った企業が数多く進出すると考えられる。 ・ 円ドル為替レート(-) 円高が進展するほどコスト競争力を維持するために、低コストを実現する海外の生産拠点へ生産をシフトすると考えられる。 ・ 日本のGDP成長率(+) 日本が好景気な時ほど企業業績も良好であり、海外進出に関わるリスクに耐えることができる体力があるため、直接投資が増大する。 |
これらの指標を説明変数の候補とし、いくつかの想定される組み合わせの中から、主要なケース5つに的を絞り、日本の対中直接投資関数の推計を行った。
変数の組み合わせに関してはさまざまな可能性があり、またそれによって推計結果も大きく異なるわけであるが、ここでは本調査の趣旨に沿って対中ODA、対中輸出などとの相関を重視しており、これら指標に関しては常に含むこととして分析を進めた。
図表III-6:日本の対中直接投資関数の推計結果
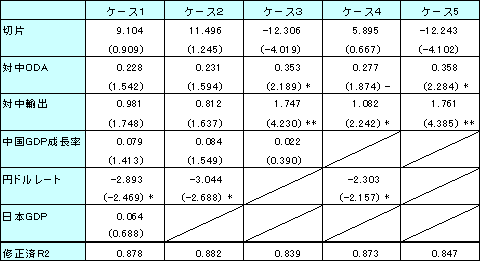
注1:(a)対数変換した変数による推計結果。推計期間は1979年から1999年まで。(b)上段は各説明変数の回帰係数、下段はt値を示す。(c)t値の右側に示された記号はそれぞれの有意水準を表す。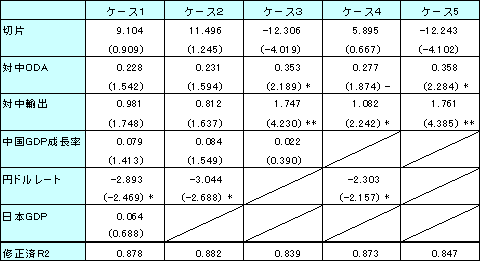
「**」:1%水準で有意 / 「*」:5%水準で有意 / 「-」:10%水準で有意
注2:対中直接投資の変化がどのような要因で変化するかを検証しており、ケース1は対中ODA、対中輸出、中国GDP成長率、円ドルレート、日本GDPの5要因で説明したケース。以下4つの要因、3つの要因、2つの要因を組み合わせを変えて推計している。統計上のケースで具体的な現象に基づくケース分類ではない。MRI試算。
いずれのケースにおいても、推計されたパラメータの符号条件は、全て想定した通りとなり、また決定係数の水準もほぼ問題ない水準となった。説明変数のうち対中ODAについてチェックしてみると、ケース3~5までの推計において5%水準ないし10%水準で有意という結果を得た。特にケース5は、対中ODAと対中輸出という相対的にはシンプルな2つの変数を採用していながら対中輸出は1%水準で有意となり、修正済み決定係数も0.847を達成しており、これら指標と直接投資の相関の強さを示している。
中国GDP成長率が有意にならなかったのは、投資の意思決定が単年度のマクロ経済状況からなされるものではなく、過去数年の大きな流れによって決定されるのが一般的である可能性もある。あるいは、中国の場合には、経済成長率が多少低下したといっても、長期間10%近い水準を維持しており、経済成長率の上下が直接投資にあまり影響を与えないことも関係しているのであろう。円ドルレートは符号がマイナスとなり、円高のときほど中国への進出が活発であったことを示している。
5つのケースの中では、援助・輸出・為替がバランスよく有意となったケース4がベストといえよう。対数変換された対中ODA、対中輸出の係数は、弾性値となっているため、対中ODAが1%増加した際には対中直接投資は約0.3%(0.277)増加、また対中輸出が1%増加した際には対中直接投資が約1.1%(1.082)増加するような関係を示している。対中輸出の影響力の方が大きいのは、その金額規模から考えても妥当な結果といえる。
本調査ではあくまでも試みとして対中直接投資の決定要因を分析したに留まり、説明変数の設定にはまだ検討の余地がある。例えば、上記の通り景気の判断と実際の直接投資実行までのタイムラグを設定することもその一つである。その他にも、説明変数の候補として、貸出金利、教育水準(現地での労働力の確保)なども候補に加えることができよう。
いずれにしても、手法上のさまざまな制約がある中で、対中ODAが直接投資の説明変数として統計的に有意であることが示されたことは興味深い。この結果からは、少なくとも過去20年間を振り返り、中国の投資環境の整備に日本の援助が貢献し、日本からの対中直接投資を促進した可能性を示唆している。しかし、その影響力は対中輸出や為替レートと比較すると極めて限定されたものに留まる。

