2.効果分析結果
(1) これまでの分析事例との比較
日本の開発途上国援助の経済効果に重点を置いた直近の研究事例としては、2000年12月に発表された経済企画庁の委託調査である「開発途上国の経済発展と円借款の役割に関する調査報告書」があげられる。この調査の結果の要約は、以下の通りである。
| 成長促進効果(注1) | 援助供与額=GDP増分に要する時間(注2) | |
|---|---|---|
| 援助全体 | 0.046% | 40年間 |
| 円借款 | 0.23% | 8年間 |
| 円借款以外のローン活動 | 0.11% | 18年間 |
| グラント | 0.00% | 390年間 |
注2:累積的な援助供与額が累積的なGDPの増加分に等しくなるまでの期間、異なる推計式の係数から算出した仮定計算である。
本調査から得られる結果は、経済企画庁委託調査などの先行研究例と比較すると、高い数値を示している。これには、以下のような理由が考えられる。
経済企画庁委託調査においては、アジア以外の地域を含む世界100ヶ国が調査対象とされており、過去に成長率のあまり高くなかった地域をも数多く包括するものである。一方、本調査においては、中国一国を詳細に扱った中国マクロモデルを開発し、分析に用いた。1980年代~90年代を通じて、中国は平均して世界でも有数の高い成長率を記録してきており、また援助を含めた外国からの資本が中国経済の発展に大きな影響を与えたことは、数多くの研究事例から指摘されるところである。これらの背景から、本調査研究において、中国が日本からの援助を活用して高い成果を挙げた、という結果が得られたものと考えられる。
これまで援助効果の分析においては、一国ではなくできるだけ多くの国の事例を集めてサンプル数を増やし、過去における蓄積の過程の効果を取り入れない静学的な分析を行うという方法が、通常行われてきた。一方、本報告のマクロモデルにおいては、過去の成長の蓄積効果を取り入れて時間の経過と共に拡大していく、動学的な分析を行う。動学的な動きを取り入れた他の分析では、静学的な分析よりも効果が3~5倍、あるいはそれ以上になる事例も報告されている。したがって、動学的マクロ分析を行った本調査では、先行研究例よりも高い数値が試算結果として得られたものと考えられる。
計量分析の全体フロー
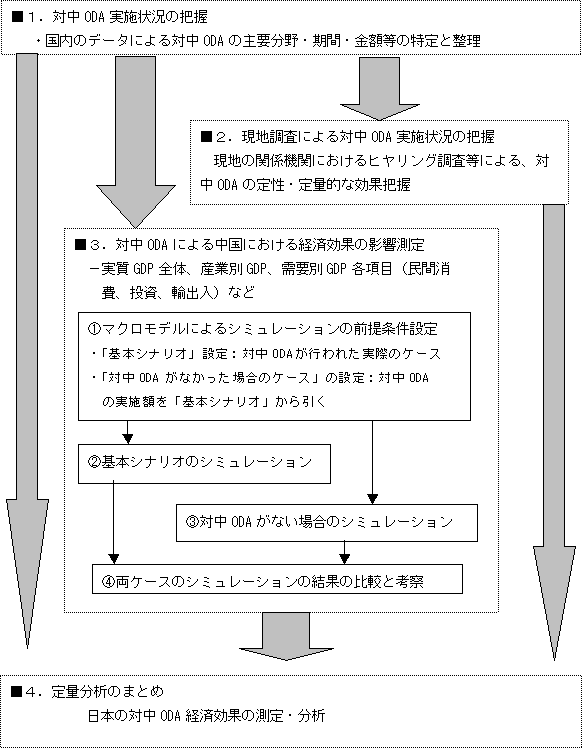
日本は過去20年間、中国に対して総額123億2900万ドル(円借款)という、多額の援助を行ってきた。円借款(有償資金)に無償資金および技術協力を加えた対中ODA総額の中国のGDPに占める割合は、最も高い時で約0.29%(1994年)、1998年と1999年は0.15%程度となっている。
日本は中国の開放政策直後の1979年から現在に至るまで援助を絶え間なく継続してきており、1999年においても日本の対中ODAのみで中国の実際使用政府借款全体の約14%を占めるに至っている。
|
図表II―1 中国のGDPに占める対中ODA比率の推移(元ベース)
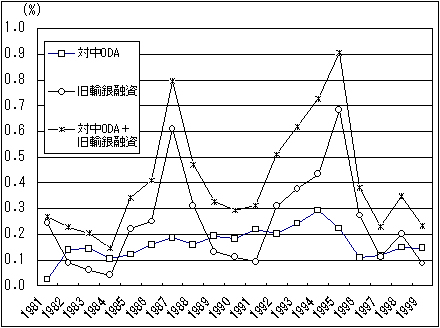 注1:対中ODAは、円借款(有償資金)と無償資金・技術協力の合計値を指す。 対中ODAは暦年、旧日本輸出入銀行融資分は(年度)である。 注2:日本の中国経済への貢献全体をみるために参考までに本グラフでは旧日本輸出入銀行 融資分も併せて表示している。 資料:「中国統計年鑑2000」、国際協力銀行。 |
(2) 試算結果による日本の対中援助の経済効果測定
【中国のGDPにもたらした効果】
図表II―2は対中ODAの名目GDP押上げ効果(%)を示したものであり、図表II―3は対中ODAの名目GDPの押上げ実額の推移を示したものである。既に図表II―1で示したように、日本の対中ODAの名目GDPに対する割合は1990年代前半が最も多く、1994年の0.29%をピークに、90年代後半になると割合としては低下し、1998年と1999年にはいずれも0.15%と、ピーク時に比較して約半分程度となっている。
しかし援助の効果は累積されて翌年以降にも継続していくことから、1992年から1996年にかけては0.94~0.95% のGDP押上げ効果が示され、1999年に至っても0.84%のGDP押上げ効果が示される。
図表II―2 名目GDPに対する押上げ効果 (元ベース)
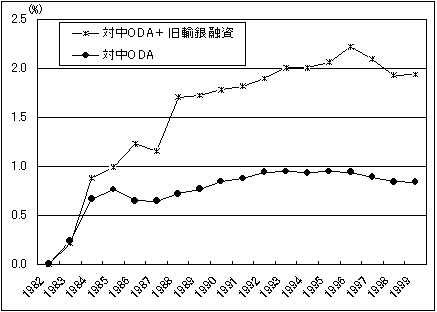
図表II―3 名目GDPの押上げ効果
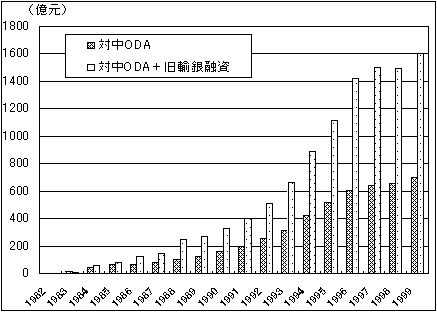
【産業別GDPにもたらした効果】
次に第一次産業、第二次産業、第三次産業別の押上げ効果の分析を行った。最も対中ODAの効果が強く出ているのが、第二次産業である(図表II―4)。第二次産業GDPにおける対中ODAの押上げ効果(%)と押上げ額の結果を示した。
ちなみに第一次産業では効果はほぼ順調に累積されていき、年を追うごとに効果は少しずつ大きくなっていく。押し上げ効果は1999年度末で0.58%という結果が得られる。
最も効果の大きい第二次産業では、対中ODAの対GDP比の最も大きい90年代半ばに押し上げ効果はピークに達し、最終年の1999年にも1.08%という押し上げ効果を持続する。
なお、第三次産業においては、対中ODAの効果は相対的に小さい。中国の第三次産業は、第一次・第二次産業と異なり、資本ストックや雇用量の割合に比較して付加価値の少ない産業である。1999年に至っても第三次産業のGDPは第二次産業のGDPの67%程度であり、1980年代、90年代にかけて中国経済で最も重要な地位を占めていたのが第二次産業であった。推計期間の最終年の1999年では、第三次産業では0.10%のGDP押し上げ効果が示される。
図表II―4 第二次産業における対中ODAのGDP押上げ効果
注:押し上げ効果は左軸、押し上げ額は右軸。以下同じ。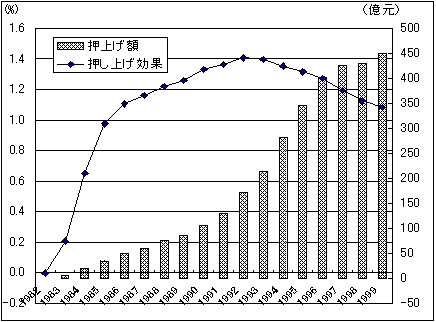 |
【消費・総固定資本形成にもたらした効果】
本モデルにおいては、中国の統計データの構成や、従来からの中国の経済統計の概念に基づき、産業別GDPを中国の公式なGDPとして、分析を行っている。しかし中国でも自国の統計データを他国の統計データの構造に近づける努力を進めつつあり、需要項目別アプローチによるGDP統計も発表するようになってきている。
本調査研究においても参考として、各需要項目における効果分析を実施した。消費・総固定資産投資などの各需要項目にも、日本の対中ODAの効果が見られる。図表II―5に中国全体・都市部・農村部の消費における押し上げ効果(%)、図表II―6に中国全体・都市部・農村部の消費における押し上げ額、図表II―7に国内投資(固定資産投資)における押し上げ効果と押し上げ額を示した。国内消費への押し上げ効果は1999年度末で都市部が0.97%の効果を示しているのに対し、農村部の消費は0.66%と、低くでる結果となった。国内消費全体では、1999年度末で押し上げ効果は0.83%である。
国内投資(固定資産投資)については、効果率は1999年度末で1.53%という結果がでた。
図表II―5 消費における対中ODAの押上げ効果
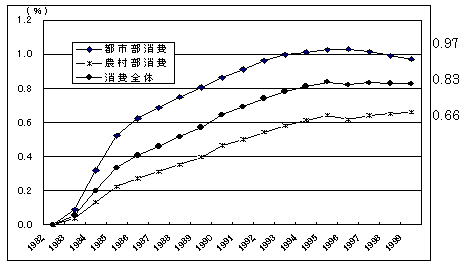
図表II―6 消費における対中ODAの押上げ額
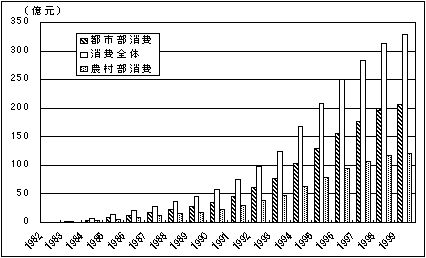
中国のGDPに占める固定資産投資のシェアは1999年でみると36%であり、固定資産投資に占める外資利用は8.8%である。さらに、外資利用のうち、日本のシェアは4%程度という構成から見るとき、ODAの固定資産投資への効果はやや低い結果といえるが、そのことは近年、中国の資金調達の多様化が起こっていることを示すものといえるであろう。
図表II―7 国内投資における対中ODAの押上げ効果および押上げ額
注:押し上げ効果は左軸、押し上げ額は右軸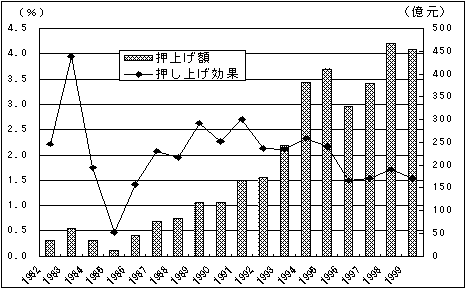 |
【輸出にもたらした効果】
図表II―8に、輸出(通関統計)における対中ODAの押し上げ効果と押上げ額を示した。輸出が中国経済の成長に果たす役割は、今後も大きいと考えられる。また直接投資は、輸出の牽引役となることが期待される。直接投資に対中ODAの効果が見られ、その直接投資が輸出に影響を与えていることから、間接的に日本の対中ODAが中国の輸出に与えた影響が計測される。
輸出への効果については、1995年をピークに若干低下してきているが、全体として効果額は増える傾向にある。しかし押し上げ効果率は逓減の傾向を示している。これは今日、中国の輸出の約半分は外資系企業が担うにいたっており、民間主導(直接投資)に変化していることから、直接には輸出に与える対中援助の効果が減少していることを示すものと考えられる。しかし、過去において、インフラなどへの援助が投資環境を改善し、間接的に企業進出の増大を支援し、輸出もそれにつれて急増するという循環を発生させたという過程は、注目すべきであろう。
図表II―8 輸出における対中ODAの押し上げ効果
注:押し上げ効果は左軸、押し上げ額は右軸。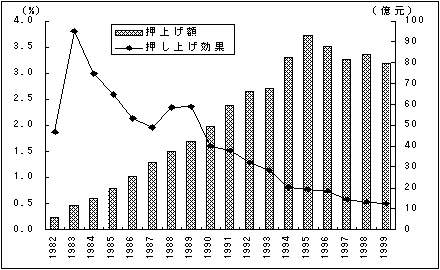 |
【地域別効果】
中国においては中央政府の決定権が強いことから、今回のモデル推計においては、推計された中国全体のGDPに基づき、地域別GDPの試算をいくつか試みた。例として、図表II―9に国有企業が相対的に多く、市場経済化のテンポが鈍い東北三省(黒龍江省、吉林省、遼寧省)、図表II―10に中国の中で最も経済水準の低い貴州省、図表II―11に中国の中で最も経済水準の高い上海のGDPにおける効果を示した。経済発展の高い上海市のみならず、東北部や内陸部へも対中経済援助の効果が及んでいることがわかる。
但し、その押上げ効果は先進地域において相対的に高く、今後はそれ以外の地域にODAの焦点を当てることによる経済格差の是正という課題に一定の寄与を示すことが出来る。
図表II―9 東北三省におけるGDP押上げ効果
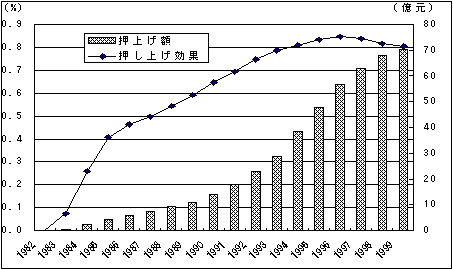
図表II―10 貴州におけるGDP押上げ効果
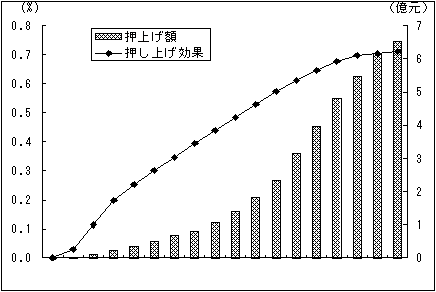
図表II―11 上海におけるGDP押上げ効果
注:押し上げ効果は左軸、押し上げ額は右軸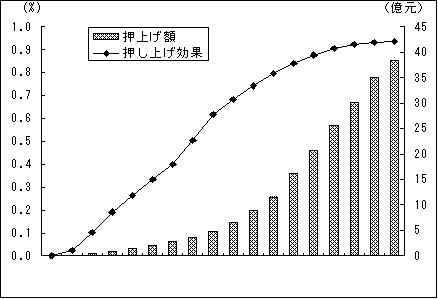 |

