第6章 1997年度における事後評価概要
2.JICAによる事業評価
(1)国別評価(ネパール)
日本は、ネパールとの伝統的友好関係、南西アジアで最も所得水準が低く開発ニーズが大きいことなどから、ネパールに対して、人的資源開発、社会分野、農業開発、経済基盤整備、環境保全の5分野を援助重点分野として、積極的に協力している。本評価調査では、この援助重点5分野におけるJICAのこれまでの協力がどのような効果をあげているのか調査・分析し、今後の同国に対する協力を実施していく上での教訓を導き出した。
援助の5重点分野におけるJICAの協力は、ネパールの開発計画に照らしても、また、ネパールの経済・社会状況から見ても同国のニーズに適合している。援助形態間の連携についても、多くのプロジェクトにおいて、開発調査と無償資金協力、無償資金協力とプロジェクト方式技術協力など、効果的な連携が図られ、大きな成果をあげている。 しかし、ネパールにおいては、程度の差はあれ全般的に、カウンターパートの頻繁な異動、運営費の不足など、プロジェクトの実施体制が脆弱であり、JICAの協力終了後の効果の持続・拡大に支障をきたしている傾向が見られるため、ネパール側に対して、機会あるごとに改善を促していく必要がある。
(2)合同評価
-
(イ)フィリピン:道路(JICA・OECF)
フィリピンでは、道路は旅客、貨物ともに最も多く利用されている交通機関である。同国の道路セクターにおいて、JICAはこれまで全国レベルおよびマニラ首都圏での重要かつ大規模な開発調査(マスタープラン調査、フィージビリティ調査)を実施し、総合的な交通体系の整備を支援してきた。そしてJICAやフィリピン政府が実施した、開発調査での提言を踏まえて、OECFにより円借款が供与され、事業化が図られてきた。
本評価調査では、JICAが実施した開発調査での提言が円借款により事業化された案件と、フィリピン政府が実施した開発調査での提言が円借款により事業化された案件の双方を評価対象として、JICAとOECFが合同で事後評価を実施した。
本評価調査の結果、道路の新設・改修等によって、マニラ首都圏では、公共輸送サービスの向上、商工業および物流の活性化等が図られ、地方部では都市・農村間の交通量増加、移動時間の著しい短縮(例えば、レイテのOrmoc-Taclobanの移動にかかる時間が4時間半から2時間に短縮)、輸送サービスの域内参入、さらにはビジネスおよび工場等の新規誘致等の事業効果が確認された。また、住民レベルでも、通学・通勤時間の短縮、各種サービスへのアクセス改善等の生活上の利便をもたらしている。
今後は、道路の維持管理体制を強化するために、公共事業道路省に対して、道路施工に関する予算、統計、基準、図面、施工要領等のデータベース化、組織運営の効率化、若手技術者の育成等の分野での協力が効果的と考えられる。
 (ロ)タイ:都市交通・都市計画
(ロ)タイ:都市交通・都市計画
この評価調査は、これまでにJICAが実施してきた都市交通・都市計画分野の技術協力全般(開発調査、個別専門家派遣、研修員受入)を対象として、タイ側と合同で検証を行い、今後のタイの本分野における協力のあり方について考察した。
JICAの技術協力は、タイの国家開発計画に常に整合するかたちで、タイ側のニーズに合致した協力が展開されてきた。また、個別専門家の開発調査に対する貢献も大きく、このようなJICAの協力は、タイ側から高く評価されている。
近年、タイ側のJICAの協力に対する期待は、従来のモノを作るといったハード面の技術移転から、インフラのマネージメントなどのソフト面の技術移転が主流になりつつある。また、タイ側は、高度技術分野における人材育成に対しても非常に熱心である。
JICAとしては、このようなタイ側のニーズの変化に的確に対応した協力を実施し、また、開発調査においては、提案したプロジェクトの事業化に向け、他ドナーとの連携を十分に考慮していくことが重要である。
(3)特定テーマ評価
-
 (イ)ASEAN:青年招へい
(イ)ASEAN:青年招へい青年招へい事業は、開発途上国の未来の国造りを担う青年を日本に招へいし、専門分野について学ぶとともに、日本の同世代の青年との交流を通じ相互理解を深めることを目的として1984年から開始された。
本事業に参加したASEAN6カ国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、マレーシア)の青年の本事業に対する満足度は高く、日本への印象も80%以上の青年が「良くなった」と答えている。また、アンケート調査の結果から、技術協力に関するプログラムに改善を加えることにより、より参加者のニーズにあった事業を実施できることが判明した。
さらに、ASEAN各国では同窓会が設立され、組織力も強化しつつある。ASEAN内の同窓会交流連絡会も毎年開催されており、これらの同窓会は、本事業の目標を超えた大きな効果を導き出す原動力となっている。
今後、本事業をいっそう効果的に進めていくための方法として、相互理解に関するプログラムにおいても分野別の観点から取り組むこと、日本人に対する開発教育的要素を取り入れること、合宿セミナーや専門分野研修の高度化を図ること、などが提言された。
-
(ロ)中南米:一般廃棄物処理
日本はODAにおいて、環境分野への貢献を積極的に進めているが、その取り組みの一つに、廃棄物処理関連での協力がある。人口増加と急激な都市化が進む中南米の国々では、都市における一般廃棄物処理能力向上のため、無償資金協力による清掃機材の供与が多数の国で行われている。本評価調査では、ドミニカ共和国とホンデュラスにおいて実施された清掃機材供与案件の効果を調査・分析し、今後の廃棄物処理分野の協力を行う上での教訓・提言を導き出した。
清掃機材が供与された結果、ゴミ収集率は大きく改善し、ホンデュラスの首都テグシカルパでは、清掃サービスの対象人口が84%増加したと推定され、都市衛生の向上に寄与している。また、ドミニカ共和国の首都サント・ドミンゴ市では、本機材供与が契機となって、同国初の衛生埋立処分場が建設された。
一方、清掃事業には多大な維持運営費用が必要となるにもかかわらず、両国とも料金徴収、予算手当の体制が脆弱であり、今後の事業継続には不安が残る。特に、機材の更新に備えての準備はなされておらず、機材が耐用年数を経過した後の清掃事業サービスの低下が懸念される。
今後、本分野においてより効果的な協力を実施していくためには、機材供与前に開発調査などと有機的に連携して相手側の実施運営体制やゴミの量・質などを十分に調査し、より適正な案件形成を行うこと、市政担当者(市長など)と十分なコミュニケーションを図り、プロジェクトに対して強力なコミットメントを得ることなどが重要である。
-
(ハ)西アフリカ:小学校建設
基礎教育の重要性に応えるため、近年、日本は学校建設への協力を積極的に行うようになっている。その中で、1990年代に入って大きな伸びを示しているのは、西アフリカ地域における小学校建設である。フランス語圏アフリカ諸国では、技術協力の実施が遅れていることもあり、小学校建設が基礎教育分野での協力の代表的なものとなっている。本評価調査は、今後の基礎教育分野への協力をさらに充実したものとするために、セネガルでの小学校建設案件のもたらした効果を調査・分析し、教訓・提言を導き出すことを目的として実施された。
無償資金協力により建設された施設は、目的どおり小学校教育に活用されており、初等教育における学習環境の改善に貢献している。より一層援助効果を高める観点から相手国側が責任を持ってソフト面での活動を行うような仕組みを工夫することや協力内容にソフト的な要素を組み込んでいくことが必要であると思われる。近年の日本の協力では、住民集会等を組み込んで住民参加を促しているが、このような努力を今後さらに充実していくことが望まれる。
また、西アフリカ地域において効果的な小学校建設案件を実施していくためには、ハード・ソフト面を組み合わせた協力、住民参加の促進、現地中小建設業者の積極的活用、適正な評価の実施、長期的な視野での戦略的な実施、中長期的な視野での日本の協力制度の見直しなどが引き続き重要である。
-
(ニ)インドネシア、タイ:農業分野高等教育
本評価調査では、インドネシア・ボゴール農科大学プロジェクトおよびタイ・カセサート大学プロジェクトを対象として、農業分野における高等教育に対する日本の協力の効果を検証するとともに効果発現の促進要因と阻害要因を分析し、将来の同分野での類似案件実施に資する教訓・提言を導き出した。
インドネシア、タイ両国とも、国家開発計画の中で農業振興を基幹政策と位置付け、農業技術者の育成に力を入れてきた。このような背景のもと、両国における最高水準の教育機関である両大学は、自国の農業界に多くの優秀な人材を輩出してきた。
両大学は、日本で研修を受けたカウンターパートの定着率も良く、日本人研究者との人脈を生かし研究活動を続けながら、これまでに、ボゴール農科大学では11名が、カセサート大学では8名が博士号を取得した。
カウンターパートの多くは、今日でもJICA専門家との交流を続け、研究成果の学会誌等への発表、農民や産業界等への研究成果の還元に取り組んでいる。
高等教育分野のプロジェクトにおいて、協力終了後も、日本での博士号取得者を中核として自立的な研究活動が継続されるようになるには、息の長い協力が必要である。また、研究協力型プロジェクトを円滑に進める上で、大学間交流協定等との有機的連携、日本側の組織的対応による支援等が重要である。
-
(ホ)パキスタン:灌漑農業
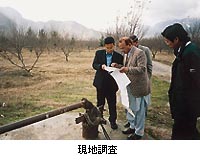 パキスタンでは、農業は国内総生産の26%、雇用人口の約50%を占める基幹産業であり、JICAもその重要性に鑑み、バロチスタン州、北西辺境州、パンジャブ州北部などの天水地域を中心に、灌漑農業分野の協力を実施してきている。本評価調査では、パキスタンにおける灌漑井戸掘削機材供与案件および灌漑農業技術普及センター設立案件を対象として、協力の効果を検証し、今後の本分野において類似案件を実施する上での教訓を導き出した。
パキスタンでは、農業は国内総生産の26%、雇用人口の約50%を占める基幹産業であり、JICAもその重要性に鑑み、バロチスタン州、北西辺境州、パンジャブ州北部などの天水地域を中心に、灌漑農業分野の協力を実施してきている。本評価調査では、パキスタンにおける灌漑井戸掘削機材供与案件および灌漑農業技術普及センター設立案件を対象として、協力の効果を検証し、今後の本分野において類似案件を実施する上での教訓を導き出した。供与された井戸掘削機材は、おおむね良好に使用されており、井戸を建設した農家では、農作物の生産量、収入とも大幅に増大している。
灌漑農業技術普及センターにおいては、現地に適した優良品種の選定・供給が、円滑にかつ効果的に行われており、対象地域の農民全てが、同センターで推奨した品種の米と小麦を使用し、生産性を向上させている。しかし、運営予算不足などにより農民への研修などの活動は十分ではなく、今後、パキスタン側の一層の自助努力が求められる。
今後、本分野の協力において、より大きな効果をあげていくためには、灌漑施設の建設・改修だけではなく、市場までのアクセス道、農作物の集荷場などの周辺インフラの整備を含む総合的な協力を検討していく必要がある。また、規模の大きいセンターを新規に設立する場合には、相手側の運営能力や進捗に対するモニタリングをいっそう強化していくことが必要で、場合によっては段階的に協力していくことが肝要である。
-
(ヘ)ザンビア:農業
本評価調査は、ザンビアの農業部門の長期的な開発課題を構成する3つの特徴に対する過去の協力について、評価を実施した。
「都市部への食糧供給能力の向上」を支援するために実施してきた地方道路の改修や穀物倉庫の建設は、自立発展性も高められており、おおむね良好な効果があがっている。
しかし、「未利用地の有効利用」および「農業生産の安定的な拡大」を支援するために行われた農村開発協力については、ザンビア側の事業実施体制・能力が十分でなく、事業の効果発現を遅らせる面もあった。
今後の協力の方向性として、JICA事務所の機能強化、他のドナーとの関係強化、流通への取り組みの重視、社会経済調査の実施、ザンビア人専門家の登用などが重要であると指摘している。
(4)第三者評価
-
(イ)ヨルダン:電力
ヨルダンは、中東和平の当事国として、この地域の歴史的動向に深く関わってきた国であり、同国の経済的発展は、中東和平プロセスを推進し中東全域の安定と安全を確保するために肝要である。そこで、中東地域の経済発展への貢献とそのための人造り協力の代表的事例として、電力訓練センター・プロジェクトを対象に、同地域の政治経済の専門家である橋本光平・PHP総合研究所研究部長に評価を依頼した。
同センターでは、プロジェクト方式技術協力終了後も、継続的に電力分野の人材育成が実施されており、従来、ヨルダンにおいて不足していた中堅技術者の育成に対し、大いに貢献している。さらに、第三国集団研修によって、中近東・アフリカ諸国からの研修員に対する技術訓練も実施されており、技術普及も図られている。しかし、プロジェクト方式技術協力の終了から7年が経過し、技術の陳腐化が始まっており、同センターが将来にわたってヨルダンおよび周辺アラブ諸国にとって有意義な訓練センターであり続けるためには、ヨルダン側による技術進歩に合わせた機材や教材、技術の提供への自助努力が必要である。
-
(ロ)インドネシア:組織・制度づくり・能力開発
JICAは、「人造り、国造り、心のふれあい」をスローガンに、開発途上国において様々な協力を実施している。本評価調査では、人造り協力における組織・制度造り/能力開発という視点から、内田康雄神戸大学教授に、インドネシアにおける2つのプロジェクトを対象とした評価を依頼した。
電話線路保全訓練センター・プロジェクトは、現在、インドネシア側実施機関が民営化され組織再編されたため、プロジェクトとしては活動していないが、相手側関係者からは、保全技術の移転のみならず、JICAの協力によってもたらされた保全要員の保全作業に対する意識変革について、高く評価されており、本プロジェクトをモデルとして円借款が実施された。意識改革や労働環境の整備などは、有益なノウハウとなって定着するものであり、開発途上国への技術移転、特に組織・制度造りにおいて重要な要素である。
スラバヤ電子工学ポリテクニック・プロジェクトは、本プロジェクトにおいてインドネシアで初めて導入された就職斡旋活動や適切な訓練カリキュラムの作成などにより、訓練生の就職率は90%前後と他のポリテクニックと比べて高く、大きな効果をあげている。
-
(ハ)南米:食糧・農業開発
現在、約18億トン(1994~1996年の平均)の穀物生産量で世界の約58億人の人口を養っているが、開発途上国における高い人口増加率や異常気象などによる農業生産性の低迷などによって、世界的規模での将来的な食糧不足、飢餓の不安は解消されていない。欧米やアジアなどの主要な食物生産地では既に潜在的な生産性はある程度まで達しているため、国土、人口、気象などに恵まれている南米諸国が、今後の主要食糧の供給拡大における重要性を持つと言われている。
こうした背景のもと、ブラジルおよびパラグアイにおいて食糧増産・供給の安定化を目指してJICAが実施した協力について、マクロ的観点から事後評価を行い、協力の効果を明らかにするとともに、今後の協力における教訓・提言を導き出した。
JICAの長期にわたる協力の結果、ブラジルでは、それまで未活用の土地であったセラード地帯が1,000万ヘクタール開発され、世界第2位のブラジルの大豆生産量の約49%に相当する1,300万トンを産み出す大農業地帯へと変貌した。パラグアイにおいても、大豆や小麦の生産性が向上し、大豆輸出量の増大(世界第4位)や小麦の自給達成が図られた。
両国における効果発現の大きな要因として、日系農家の存在・役割が挙げられる。日本側と相手側との間の潤滑油として、JICAの協力によって新たに開発された農業技術は日系農家を通じて周辺の一般農家へと効果的に伝播された。
なお、このような日系農家の貢献を通じ、特にパラグアイでは日本人に対する信頼・期待は大きく、ある世論調査結果では、パラグアイ国民の70%が一番信頼する国を日本と回答している。

