第6章 1997年度における事後評価概要
本章では、外務省、JICA、OECFによる事後評価の結果のうち、主な評価の概要を取りまとめた。
なお、外務省による「在外公館による評価」、「被援助国関係者による評価」、「現地コンサルタントによる評価」、JICAによる「在外事務所による評価」は、件数が多いため、本章には含めなかった。外務省による評価については本報告書の各論編、JICAについては「事業評価報告書」およびOECFについては「円借款案件事後評価報告書」に詳細を掲載する。
1.外務省による事後評価
(1)国別評価
-
(イ)パラグアイ
この調査は、細野昭雄・筑波大学国際政治経済学研究科長(教授)を団長に、遅野井茂雄・南山大学外国語学部助教授、田島久歳・城西国際大学人文学部専任講師、野口修司・システム科学コンサルタンツ社会開発部長、外務省員による調査団により実施された。
本調査では、パラグァイに対する日本のODAによる協力が、経済開発および民生向上と安定とに如何なる効果を上げたかを、マクロ的視点から評価した。
日本の対パラグアイODAは、1952年より開始され、有償資金協力、無償資金協力、技術協力の形態で幅広い分野で実施されており、その重点は、農林畜産、インフラ、人的資源、保健医療の4分野に投入されている。これらの重点分野は、パラグァイの状況とパラグアイの国家開発計画に合致したものであり、その中から選定された対象プロジェクトはおおむね妥当な援助事業であったと評価している。
今後の日本の協力については、最近のパラグアイの国内政治経済の重要な変化や同国を取り巻く国際環境の変化等から、従来の方式をそのまま延長する形で継続するのではなく、新たな変化と環境に対応する形でODAのあり方を見直して行く必要があると提言している。さらに、今後のパラグアイに対する援助政策を策定する上で留意すべき点として、同国の予算が不足していること、同国の省庁間の協力・調整が不足していること、また、日本人専門家が一層、カウンターパートとの意志疎通に心がけること、専門家同士が情報と意見交換の改善に心がけること等を提言している。
-
(ロ)フィリピン
 フィリピンは、1997年までの累積額で、第3位の日本のODA供与国であり、フィリピンに対する二国間援助の約5割が日本からのものである。今回、高橋彰・国士舘大学教授を団長に、鳥飼行博・東海大学教授、成家克徳・東京外国語大学講師という3名のフィリピン専門家に依頼し、フィリピンに対する日本のODA全体についての評価を実施した。
フィリピンは、1997年までの累積額で、第3位の日本のODA供与国であり、フィリピンに対する二国間援助の約5割が日本からのものである。今回、高橋彰・国士舘大学教授を団長に、鳥飼行博・東海大学教授、成家克徳・東京外国語大学講師という3名のフィリピン専門家に依頼し、フィリピンに対する日本のODA全体についての評価を実施した。評価報告は、まず、フィリピンの開発の歴史を概観した上で、フィリピン経済は未だに脆弱性を脱しておらず、依然として外国からの援助が必要であるとしている。そして、最大の問題は、社会的格差是正による貧困の削減であり、そのために不可欠な農地改革を日本としても本格的に支援することを検討すべきであるとしている。また、貧困対策、環境保全については依然として公的資金の導入が不可欠である一方、収益性の高い事業については民間部門との調整や民営化が必要であることを提言している。
(2)援助実施体制評価(ベトナム)
 1978年12月のベトナムによるカンボジア侵攻以降、日本政府のベトナムに対するODAは、一部協力を除き見合わされていたが、92年より再開されることとなった。日本政府は、(a)人造り、制度造り、(b)電力・運輸、(c)農業、(d)教育、保健医療、(e)環境を重点分野として協力を実施してきている。
1978年12月のベトナムによるカンボジア侵攻以降、日本政府のベトナムに対するODAは、一部協力を除き見合わされていたが、92年より再開されることとなった。日本政府は、(a)人造り、制度造り、(b)電力・運輸、(c)農業、(d)教育、保健医療、(e)環境を重点分野として協力を実施してきている。
本調査は、ODAによる援助再開後数年を経た同国を対象として、日本側および被援助国であるベトナムのODAの実施体制等、援助を取り巻く環境全般につき、問題点を明らかすることにより、今後のODA実施体制の効率化を図る目的で実施された。
調査団の構成は、千野忠男・野村総合研究所理事長を団長に、大野健一・埼玉大学大学院教授、竹内郁雄・アジア経済研究所地域研究部副主任調査研究員、藤田廣巳・国際開発高等教育機構事業部長、藤田伸子・同事業部主任、外務省員、JICA職員により構成された。評価の主な結果は次のとおりである。
現地でODAの実施に携わる日本国大使館、総領事館、JICA事務所およびOECF事務所では、援助再開後まだ日が浅い困難な状況の中でも的確に業務を実施し、相互の連携も緊密にとられている。また、国際機関等他ドナーとの連携も保たれており、マクロ経済政策策定では、日本が独自の研究成果を積み上げ、政策提言を行っている。
一方、援助実施にかかる課題として、日本側の更なる体制の拡充が必要とされ、特に南北に長いベトナムにあっては、南部の案件のフォローアップが現在体制の下では極めて困難であることから、南部の実施拠点の設置を検討する必要があること、さらに、日々案件実施に関わっている現地と、本部の間の情報の流れをより滑らかにして効率を高めるシステムを作ることが指摘された。また、広報についても、よりインパクトの強い公表のタイミング等につき、検討が必要である。
(3)特定テーマ評価(インドネシア)
本評価では、世界経営協議会に委託し、日本がインドネシアに対して供与したプロジェクトである「バンドン工科大学整備事業」と「貿易研修センター」の事後評価を行い、「教育・人材開発」分野への協力のあり方を検討した。
バンドン工科大学に対するOECFの協力の第1期事業として教育研究棟3棟の建設(情報・海洋工学、応用物理、化学・材料科学)、教育資機材調達等が行われ、第2期事業として教育研究棟7棟の建設(薬学、電気工学、地域・都市計画、建築学、測地工学、生物学、科学技術芸術センター)、下水道建設等の基礎インフラの整備、日本や欧米諸国への留学生派遣事業等が行われた。第1期、第2期協力事業により研究面、機材等ハード面の整備が図られ、第2期事業においては留学生派遣事業(修士、博士課程)に重点が置かれている。これはバンドン工科大学の講師に学位取得の機会を提供し、人材の育成に貢献している。日本に限らず欧米への留学も認めており、広く教育を受ける機会を提供している点が評価されている。
インドネシア政府は、また、貿易実務に必要な人材の不足、輸出産品の品質検査能力の低さなどから輸出促進に寄与する人材の育成の必要性を認識し、その改善に向けての協力を日本に要請し、1989年には無償資金協力により貿易研修センターが建設された。貿易研修センターの計画に基づき、派遣専門家は長期16名、短期22名の計38名が派遣された。研修コースには1992年度以降毎年1,000人を越える研修員が常に参加している。1994年度の段階で6,062人の受講者のうち、民間企業関係者の占める割合は6割以上にのぼっていた。これは各研修コースが着実に民間企業の評価を得ていることをうかがわせるものであり、研修生の満足度調査では80%以上が研修コースに満足していると回答している。
今後のインドネシア教育援助への取り組み方としては、教育セクターの分析・調査を行いインドネシアの最優先課題である中学校教育の義務化の実現、その後の高校、大学の拡充にむけて協力の内容を策定すること、インドネシア教育機関が財政的に自立発展できる見通しが立てば、研究費等の経常経費への援助の可能性を考慮すること、また、JICAとOECFとの連携により包括的なパッケージ型の援助を可能にすることを提言している。
(4)合同評価(英国国際開発省との合同評価、フィリピン)
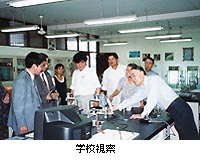 英国との間で、教育セクター案件に関する合同評価を実施することに合意し、この合同評価の目的を両国が供与した事業に対し、将来の開発援助の方向性や方法を捉えるため、実施の妥当性、目標達成度、効果、効率性および自立発展性の5つの評価視点に係わる実地検証および分析を行い、開発計画の策定に係わる教訓を得るとともに、可能な範囲で評価の方法・方式の改良を図ることとした。
英国との間で、教育セクター案件に関する合同評価を実施することに合意し、この合同評価の目的を両国が供与した事業に対し、将来の開発援助の方向性や方法を捉えるため、実施の妥当性、目標達成度、効果、効率性および自立発展性の5つの評価視点に係わる実地検証および分析を行い、開発計画の策定に係わる教訓を得るとともに、可能な範囲で評価の方法・方式の改良を図ることとした。
今回の評価調査は、2回に分けて実施する合同評価の第一段階として、日本がフィリピンにおいて実施した「学校校舎建設計画」、「教育施設拡充計画」および「中等学校教育機材整備計画」を対象として実施することとなった。
現地評価調査には、日本側:牟田博光・東京工業大学大学院教授(団長)、沼野太郎・国立教育研究所国際研究・協力部国際教育協力室主任研究官、新井司郎・オーバーシーズ・プロジェクト・マネージメント・コンサルタンツ顧問、外務省員、英国側:セリア・メール社会開発コンサルタント(団長)、スーザン・ダーストン・イギリス国際開発省在マラウィ地域学校プロジェクト首席顧問によりなる調査団を派遣した。
評価対象であった3つの無償資金協力案件は、いずれもフィリピンの国の政策に沿ったプロジェクトであり、教育の改善に資するものであると認められた一方で、改善すべき点も指摘された。「学校校舎建設計画」は、「面的」な施設建設援助を行った最初の事例であったが、供与された校舎は仕様水準が主な理由でコストがかかったが、その後、この経験に基づいて実施された「教育施設拡充計画」では大幅なコスト等の改善が見られた。また、受け入れ側の問題もあり、供与された機材が十分活用されていない例も見られたことから、ハード面のみならず、ソフト面との連携が必要であることが強調された。
この合同評価においては、英国が近年特に重視してきている社会開発面等の視点が加味されたことにより、評価視点の多様化および客観性の確保の面で大きな意義が認められた。
(5)NGOとの共同評価(バングラデシュ)
1996年4月に発足したNGO・外務省定期協議会では、両者間の協力・連携のあり方につき話し合いを行っている。「NGO・外務省相互学習と共同評価」は、同協議会における議論の中でNGOとODAとの具体的協力・連携の方向性を模索するための方策として提案されたものであり、NGO関係者とODA関係者が共同で、双方のプロジェクトを観ることにより、相互に学習・評価、提言することをその目的としている。この提案に基づき97年10月に調査団がバングラデシュに派遣された。
この最初の「NGO・外務省相互学習と共同評価」は、NGO実施プロジェクトとしてシャプラニール(市民による海外協力の会)の「総合的グループ育成プロジェクト」、ODA実施プロジェクトとして「農村開発実験(フェーズII)」および「モデル農村開発計画」を評価の対象とした。
調査団は、熊岡路矢・日本国際ボランティアセンター代表、長畑誠・シャプラニール海外活動担当、穂積智夫・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン・プログラム・コーディネーター、須田敏彦・農林中金総合研究所研究員、外務省員から構成された。
調査の結果を踏まえ、より効果的な援助実施のための情報交換の重要性、プロジェクト実施に際し、その地域において長期間の活動経験を持ち、成果をあげているNGOが計画段階から参加することが重要であることなどが指摘された。
この「NGO・外務省相互学習と共同評価」は、双方のプロジェクトの改善点を見出し、また、今後の両者による協力の展望を広げることにおいて非常に有効であるとして積極的に評価されている。
(6)有識者評価
-
(イ)中国:「青島港拡充計画」「青島(道路・通信)開発計画」
中国の経済発展のボトルネックとなってきた経済インフラの不備を解消していくにあたり、日本の援助がどのような効果をあげてきているのかを調査するため、開発経済学、国際経済学の専門家であり、援助評価検討部会のメンバーでもある小浜裕久・静岡県立大学国際関係学部教授に依頼して、沿岸地域の主要都市である青島に焦点を当て、運輸分野における2つのプロジェクトの評価を実施した。
「青島港拡充計画」は、河北地域の重要港である青島港に対する貨物輸送需要の増大に対応するため、前湾地区に新規バースを建設するとともに、後背地である膠県との間に約40キロメートルの鉄道を整備することにより、青島港の貨物取扱能力の増強を図ろうとしたものである。また、「青島(道路・通信)開発計画」のうち、今回の評価の対象とした道路部分は、新規バースが建設された前湾地区と旧港のある青島市街とを結ぶ全長67.8㎞の環膠州湾高速道路を建設したものである。
小浜教授は、「青島港拡充計画」の下で、市街地が近く拡張の難しい旧港地区ではなく、漁村地域で新規開発の余地のある前湾地区を開発したことは、開発計画の視点から経済合理的な選択だったと述べている。また、2つのプロジェクトにより、港、鉄道、道路の建設が一体となって、滞船費用の節減や貨物輸送時間の節減の効果をもたらし、青島港の貨物取扱量が増加するとともに、周辺地域の経済発展にも寄与したとしている。
-
(ロ)ヨルダン:「北ゴール灌漑近代化計画」「水道施設補修機材整備計画」
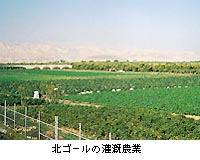 乾燥地域に位置するヨルダンの貴重な水資源を有効に利用するために、日本がいかなる援助を行うべきかを検討する目的で、アジア経済研究所において中東地域の研究を主導してきた清水学・宇都宮大学国際学部教授に依頼し、水供給分野の2つのプロジェクトの評価を実施した。
乾燥地域に位置するヨルダンの貴重な水資源を有効に利用するために、日本がいかなる援助を行うべきかを検討する目的で、アジア経済研究所において中東地域の研究を主導してきた清水学・宇都宮大学国際学部教授に依頼し、水供給分野の2つのプロジェクトの評価を実施した。灌漑用水の有効利用に関する「北ゴール灌漑近代化計画」は、近代的な灌漑方式を採用することにより、貴重な水資源を節約して利用するもので、乾燥地域の農業生産の安定化と向上を図ろうとしたものである。このプロジェクトについて、清水教授は、盗水や蒸発水が大幅に減少したとするとともに、農民の水利用意識に大きなインパクトを与えたことを指摘している。
一方、生活用水の有効利用に関する「水道施設補修機材整備計画」は、水道施設の老朽化による漏水を減少させるため、水道施設の補修機材を3つの修理工場に整備したものである。これについては、清水教授は、首都アンマン市の中央修理工場では、補修機材は全体としては有効に活用されており、修理に要する時間が短縮されるなど水道施設の補修能力が向上したとしている。ただし、イルビットの地方修理工場では、新しい工場施設の建設が現地政府の事情で遅れたことから、未だ活用されていない機材もあったと指摘している。
-
(ハ)ジンバブエ:「地方給水施設整備計画」「マシンゴ州中規模灌漑計画(2/5期)」「ムコトシ小学校整備計画」
河野健一・毎日新聞論説委員に依頼し、ジンバブエに対する今後の援助計画の策定、実施のための提言および教訓を引き出すことを目的として評価を実施した。
「地方給水施設整備計画」は無償資金協力により住民の生活向上を目的とした深井戸掘削のための機材を供与するとともに技術指導を実施することを事業内容とする。干魃時にも使用可能な深井戸309本が整備されたことにより、住民の生活は格段に改善された。援助効果を強化するために、生活用水に加え、灌漑面での援助を行うことを提言している。
「マシンゴ州中規模灌漑計画(2/5期)」は、無償資金協力により6つの灌漑用中規模ダムおよびダムから村落の調整池に至る送水路等付帯施設を整備することを事業内容とする。灌漑施設が整備されたことによりそれまで一毛作だったトウモロコシの三毛作が可能になるなど農業生産性が向上した。
「ムトコシ小学校整備計画」は、草の根無償によりムコトシ小学校の老朽した5棟の校舎を改修し、教育に必要な機材を供与することを事業内容とする。事業実施により教育環境が向上した。今後、日本がジンバブエに派遣している教員により音楽や体育などの指導を行うことを提言している。
これらの案件を踏まえ、限られたODA予算を活用し、よりインパクトのある援助を行うためには資金を「狭く、深く」分配する傾斜注入路線を採ることが必要であること、また、対アフリカ支援に対する国民の理解と支持を取り付けるために国民レベルにおいてアフリカに対する理解を深めることが重要であることなどを指摘している。
-
(ニ)セネガル・モーリタニア:「零細漁業振興計画」「沿岸漁業振興計画」
本評価は、国際経済学、経済学を専門分野とする大林 稔・龍谷大学教授が、セネガル、モーリタニアにおける水産分野の無償資金プロジェクト2件を評価した。
セネガルにおけるプロジェクトは、首都ダカールの南東約210キロメートルに所在するミシラ村に漁業支援のためのセンターを建設するとともに、製氷機、冷蔵庫、発電機、漁具、試験船等を供与したものである。
この調査では、センターへの機材の導入は、円滑に、また、その利用は適切に行われていると評価している。一方、本プロジェクトの目標、(a)漁業センター建設による水産物流通網の改善、(b)漁具資材・試験機材導入による零細漁業生産の増加と生産物の品質向上、(c)地域の経済開発と漁民の生活水準改善のうち、(a)についてはセンター自身の販売網が増加していること、また、(b)についてはミシラ地区全体の水揚げ量が92年値(1,522トン)において1989年度より約50%増加しプロジェクトは当初目標を達成した一方で、沿岸漁業資源全体が減少傾向にあるため、水揚げ量は停滞していること(92年水揚げ量は87年度計画の試算による見積り額の約70%)を指摘している。(c)についてはこのプロジェクト実施後、ミシラ村の人口は約2倍の2,600人に増加し、産院と診療所等が建設されるなど社会的基盤整備が順調に進んでおり目標を達成していることが報告されている。
モーリタニアのプロジェクトは、漁船、ディーゼル船外機、漁網、給水車等を供与し、このうち、漁網等漁業生産機材は、漁民に販売され、代金は零細漁業振興資金として管理・運用されるというものである。本プロジェクトの、3つの目標である(a)漁業生産活動の支援、(b)漁民の収入増加、生活条件の向上、就業機会の創出、(c)モーリタニア国民の食糧供給の増加のうち、(a)については資機材はほぼ順調に使用されており、(b)についても漁獲物が、商品価値の高いぼら等の魚種を中心としていることから、目標は達成されている。(c)についてはモーリタニアの漁民は輸出用のタコ、からすみや都市向けの漁獲を中心としているので、国民の食糧供給の増加という目標には貢献しているが、周辺住民の食糧増加には貢献していないと指摘している。
さらに、日本は世界遺産に指定されているバンダルゲン国立公園近隣地域での漁獲能力増強や人口増加につながる支援は控えること、他のドナーと協調して、モーリタニア政府と資源管理の支援の強化、沿岸開発の中長期的な計画とインパクトに関する調整を行うことを提言している(※1)。
(※1)1998年度の「零細漁村開発計画」において、国立公園への配慮から計画サイトを変更し、各国ドナーの理解を得た上で協力を実施している。また、同公園内の操業の取り締まりについても、主として独、EUによる監視船の供与により、モーリタニア漁業省の取り締まりが格段に向上している。
-
(ホ)エクアドル:「電気通信網拡充計画」「カタラマ川流域灌漑計画」「キト市南部上水道施設整備計画」
経済団体連合会の島本昭憲・国際本部長および早川勝・同統括グループ長に依頼して、エクアドルにおける経済インフラをテーマに評価を実施した。
「電気通信網拡充計画」は、中南米諸国で最も遅れていた電話の普及を図るためにエクアドル政府が策定した4か年計画(1985~88年)の一環として計画されたプロジェクトであるが、地震に起因する経済情勢の悪化と、政権交代に伴いコンサルタント契約の見直しが行われたこと等により93年10月の事業完成までに長い年月を要したことが指摘されている。
一方、導入された機器の性能は高く評価されており、電話普及率もプロジェクト実施中に100人あたり4台弱から6台程度に向上した。
「カタラマ川流域灌漑計画」は、食糧自給力増加が課題となっていたエクアドルにおいて、6,450ヘクタールの耕作面積の拡大と米、大豆、トウモロコシなどの増産を図り、農家所得の安定と地域経済の発展に役立つことを目的としたプロジェクトである。政権交代に伴う実施機関の交替や事業計画の見直し、工事業者入札をめぐる現地業者とブラジル業者の裁判により着工が大幅に遅れ、着工から約15カ月後の評価時点(1997年8月)では、工事の進捗率は、約10%程度である。完成後は用水管理が課題の一つとなるが、農民から管理費用を徴収するという考え方を工事中の段階から普及する必要があると提言している。
「キト市南部上水道施設整備計画」は、首都キト市南部の未給水地区への水道水供給および既存の給水区域の出水不良の解消を目的とするプロジェクトである。事前調査の段階から着工、工事まで順調に進捗し、日本側工事は1998年2月、エクアドル側工事は98年3月に完了した。
なお、今後の対エクアドルODAについては、官民が連携するとともに複数の専門家が協力しつつ日本側の限られた人的資源を活用できるような案件を発掘すること、将来のエネルギーおよび食糧問題をにらみ、ODAの被援助国として、エクアドルが太平洋にあることにもっと着目すること、協力分野としては自然保護(マングローブ林保全)が考えられるのではないか等の提言を行っている。
-
(ヘ)ボリビア:「サンタクルス総合病院」「サンタクルス医療供給システム」「サンタクルス総合病院建設計画」
 日本麻酔学会理事でもある天木嘉清・東京慈恵会医科大学麻酔科教授が、ボリビアにおける基幹病院であるサンタクルス総合病院支援プロジェクトについて評価した。
日本麻酔学会理事でもある天木嘉清・東京慈恵会医科大学麻酔科教授が、ボリビアにおける基幹病院であるサンタクルス総合病院支援プロジェクトについて評価した。サンタクルス病院は、現在サンタクルス市の医療の中核となっており第1次プロジェクトとしての本件病院の建設は適正であり、外来病室、手術室、調理室、検査室などの施設には大きな損傷は見あたらず十分に機能を果たしている。また、医療機材についても、故障の少ない管理の容易な機材の選定が成功し、病院機材のうち約90%が稼働中であると評価している。プロジェクトの具体的な効果は、病院の努力で、1994年に比べ、97年では乳児死亡率(1,000人当たり)が114人から70人に、妊婦死亡率(1,000人当たり)は、48人から35人にそれぞれ減少したことに表れている。
しかし、今後の自立発展性については、本病院の臨床的レベルは必ずしも高くないので、今後同病院が救急、集中治療、心臓外科などの三次治療に移行していくとすれば、機材、スタッフの支援の継続が必要であること、および、草の根無償資金協力による病院を増やし、これらの病院が第一次治療を受け持ち、第二次、三次の高度治療は本病院が受け持つという連携のシステムを構築していくとの案を提示している。
また、ボリビア側の問題として、特にストライキ問題、医師の給与問題、市・国の同病院に対する監督・命令系統の一元化への対応や、供与機材の維持管理のためのメインテナンスセンターの設立を検討することを提言している。
-
(ト)ミクロネシア:「零細漁業振興計画」「電力供給改善計画」「チューク州零細漁業振興計画」「ウエノ港拡張計画」
菊地靖・早稲田大学理工学部教授にミクロネシアにおける評価を依頼し、「零細漁業振興計画」、「電力供給改善計画」、「チューク州零細漁業振興計画」、「ウエノ港拡張計画」を対象案件として評価調査を実施した。
ポンペイ州における「零細漁業振興計画」では、製氷設備が供与されたことにより、水産物のみならず食品一般の保存に対する住民の意識が生まれた。他方、製氷に係る収支が明確になっておらず、また、氷運搬用トラックが十分に管理・運用されていない等の問題がみられた。
「電力供給改善計画」では、5MWの発電施設および配電施設が整備され、ポンペイ州のほとんどの世帯である3610世帯に送電が可能となった。電力プラントの維持管理については外国人技師に依存しており、電気技術者と経営管理の専門家の育成が必要となっている。また、独自の文化的背景から電気代の収集がスムーズに行われていない。
チューク州については、「零細漁業振興計画」として製氷・冷蔵施設等が供与されたが、氷についてはポンペイ州における案件同様、漁業のみならず一般住民に広く利益を与えている。水の確保と電圧制御装置が無いために2基の製氷機を同時に稼働できない。
「ウエノ港拡張計画」では、同港が十分その機能を果たすためには港の整備だけでは不十分であり、電力、道路交通機関等周辺の基礎インフラの整備が必要となっていると指摘されている。
菊池教授の専門分野である開発人類学の観点よりは、特にミクロネシアのように固有文化の影響を強く残している国への社会経済開発援助に際しては、地域の文化や時代的特殊性を考慮した開発計画の立案が必要であり、そのためには地域研究者が計画の立案段階より参加することが重要である旨指摘している。
(7)国際専門家による評価「第2次ギザ市モニブ地区上下水道網整備計画」
 評価手法の専門家としてヨーロッパを中心に活躍しているジャック・トゥールモンド氏に委託して、エジプトの大カイロ圏の衛生環境を改善するための「第2次ギザ市モニブ地区上下水道網整備計画」の評価を実施した。このプロジェクトは、大カイロ圏で最も貧しい地区であるモニブ地区において、南ギザ浄水場の拡張工事、配水管敷設、送水ポンプの建設を行うものであった。
評価手法の専門家としてヨーロッパを中心に活躍しているジャック・トゥールモンド氏に委託して、エジプトの大カイロ圏の衛生環境を改善するための「第2次ギザ市モニブ地区上下水道網整備計画」の評価を実施した。このプロジェクトは、大カイロ圏で最も貧しい地区であるモニブ地区において、南ギザ浄水場の拡張工事、配水管敷設、送水ポンプの建設を行うものであった。
プロジェクトの結果、以前は人口の50%しか飲料水の供給を受けていなかったのが、現在では20万人の地域住民のほぼ100%の世帯に、1人当たり130リットルの飲料水が供給されるようになった。また、排水管を敷設したことにより、汚水が路上にあふれることもなくなり、住民、とりわけ女性と子供の生活環境が非常に大きく改善された。
こうした点から、トゥールモンド氏は、このプロジェクトは、効果という点で、非常に成功したとしている。さらに、操業開始から1年以上が経過した時点では、施設はよく保守されており、水道料金も使用量に対応して徴収されるなど、プロジェクトの自立発展性が高いと評価している。

