第4章 事後評価結果の分析
1.指摘事項の整理
(2)指摘された問題点
対象評価の中で指摘された問題点は90項目であり、全体を分類すると下図のようになる。
問題点の分類
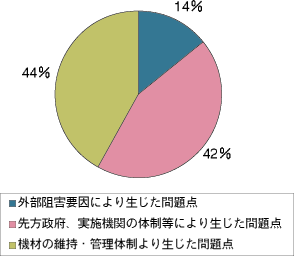
問題点は、「外部阻害要因」、「先方政府・実施機関の体制等により生じた問題点」、「機材の維持・管理等により生じた問題点」の以下の大きく3つに分けられる。
「外部阻害要因」とは、自然災害や政治・経済情勢の悪化などの不測の事態のことであり、プロジェクトの選定、実施における効率性,被援助国側の運営能力などプロジェクトに直接関わる環境に問題がない場合でも、この要因によりプロジェクトが、成功し得ない場合がある。外部阻害要因により生じた問題点は、問題点の全体の14%を占めた。
「先方政府、実施機関の体制等により生じた問題点」も、数多く認められ、全体の42%を占めた。先方機関による実施体制等による問題点としては、主に先方政府による予算の確保が出来ないことや、維持管理能力が低いことなどが報告された。これは、前節でも触れた経済的要因や基礎的能力の不足にも密接に関係していると考えられる。
「機材の維持・管理体制により生じた問題点」は、43%を占め、その多くが、スペアパーツの確保や現地における修理技術者の不足に関わることであった。
一方、評価5項目別に評価結果を分類すると、次の図のとおり、自立発展性にかかる問題点が最も多く全体の57%を占め、妥当性が20%、効率性が17%、目標達成度並びにインパクトがそれぞれ3%であった。協力相手国に引き渡した後の自立発展性に問題が多いことが判る。
以下では、上述のそれぞれの分類についてさらに詳しく整理する。
問題点の評価5項目別比率
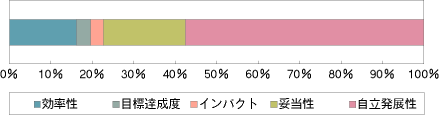
(イ)外部阻害要因により生じた問題点
外部阻害要因を種類別でみると、自然環境の変化によるものに干魃、サイクロン、漁獲量の変化、経済的要因には物価の上昇、経済危機、政治的要因に戦争、クーデター、内戦勃発、その他は電力事情、人口増加があげられた。
評価5項目でみると、効率性を阻害する要因が3項目、インパクトを阻害する要因が3項目、目標達成度を阻害する要因が1項目、自立発展性を阻害する要因が5項目で、合計12項目であった。具体的内訳は下表のとおりである。
(ロ)先方政府・先方実施機関の体制等により生じた問題点
先方政府・実施機関の体制等が、マイナス要因として大きく影響したことが報告された項目数は、38項目であった。その中でも特に、「先方政府・実施機関による予算措置が十分でないことにより、運営・維持管理が低下した」という指摘が16項目でもっとも多く、次に「実施機関の人材不足(技術者、教員等)により活動が低下した」が5項目「実施機関の運営管理・指導能力の低さにより、自立発展性も低い」が4項目、「先方政府の政策により実施機関の収入源である使用者からの徴収料金が低く抑えられているため、運営・維持管理費用が確保できない」が3項目、「先方実施機関の意思決定・承認手続きの遅さにより工期が延長した」が2項目、その他が10項目であった。
問題点の種類別では、先方政府の資金不足に関する問題が38項目中半数以上の21項目を占め、人材不足、運営管理・指導能力不足が9項目、実施体制にかかる問題が8項目であった。
「先方政府・先方実施機関の体制等により生じた問題点」全体に占める具体的問題項目ごとの比率
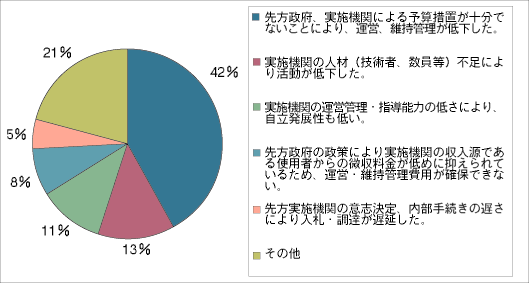
「先方政府・実施機関の体制・能力により生じた問題点」の中で最も多く指摘された「先方政府、実施機関による予算措置が十分でないことにより、運営、維持管理が低下した」という項目は、アフリカ地域で8項目報告されており他地域に比べ相対的な数が非常に多い。
これは、アフリカ地域において、ODAプロジェクトを効率的に実施・運営するためには、「先方政府・実施機関による予算措置」を確実に求めていくことが必要であることを示している(※)。
(※)「相対的に数が多い」は、指摘された問題点の合計にみる地域別または協力形態別の比率に比べ、特定の項目(この場合は「先方政府・実施機関……が低下した」)の指摘点数の同比率が高いことを示す。
また、評価5項目でみると、自立発展性にかかる問題点が、38項目の内30項目を占めている。これは、プロジェクト終了後の協力相手国による自立発展段階で問題が多く生じていることを示している。
実際に、先方政府・実施機関の予算措置にかかる問題が多かったことは前述のとおりである。
「先方政府・実施機関の体制等により生じた問題点」の評価5項目別比率
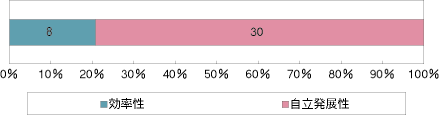
(ハ)機材の維持・管理体制により生じた問題点
上述の問題点以外のものとして報告されたのは、39項目であった。この内訳は、「スペアパーツの調達ルートが確立されていない」が9項目、「供与機材が老朽化している」および「修理技術者が不足している」がそれぞれ7項目、現地でのスペアパーツの入手が困難なため、一部機材が使用されていない」が5項目、「ニーズが少なく使用されていない機材がある」および「将来的にスペアパーツの不足が懸念される」がそれぞれ2項目、その他が7項目であった。
「機材の維持・管理体制等により生じた問題点」全体に占める具体的問題点ごとの比率
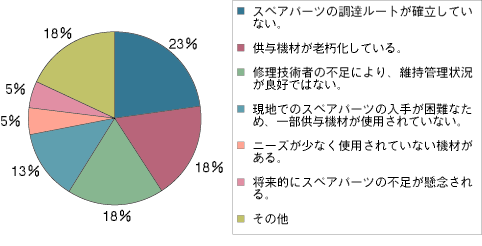
39項目の中で、最も項目数が多かった問題点の上位に占めているものは、供与機材に関係のある問題点がほとんどで、全体で26項目にも及ぶ。その中では特にスペアパーツに関係のある問題点が16項目と顕著である。次の表も示すとおり16項目のうち、8項目がアフリカ地域の問題点であり、その8項目のうち、7項目までが「スペアパーツの調達ルートが確立していない」ことが問題点である。
また、残りの10項目のうち、7項目までが「供与機材が老朽化している」という問題点であり、アジアをはじめ全地域から問題点として報告されている。これは1980年代に供与された機材が、90年代に入り、耐用年数を越えるまたは越えた時期にかかっていることを示し、相手国関係機関で機材を更新するための財政措置がとられていないことを示している。
また、この他、「修理技術者の不足により維持管理が良好ではない」という問題点7項目が報告されており、このうち4項目までがアフリカ地域の問題点である。
上述スペアパーツの調達ルートの問題や修理技術者不足の問題がアフリカ地域に多いことに、前述の「先方政府、実施機関による予算措置が十分でないことにより、運営、維持管理が低下した」という問題点がアフリカ地域に多いことも考え併せると、もちろん国・地域によって異なるが、アフリカ地域では一般に、供与機材の維持管理にかかる基盤が脆弱であることが確認される。また、同時に、対アフリカ地域における機材供与は、他地域に比べ機材の維持管理の支援体制を確保しつつ実施する必要性が高いことがわかる。
なお、無償資金協力の機材供与に関しては、現在、日本政府においても、支援体制構築を強化に努めており、その一環として「無償資金協力医療機材等維持管理情報センター」を99年2月に設置した。これにより、同センターが現地実施機関担当者から供与機材に関する問い合わせ受け、維持管理に必要な情報を提供し、日常の保守と機材維持にかかる基本的問題の解決のために、適切な対応ができる体制が整った。
「機材の維持・管理体制等により生じた問題点」の評価5項目別比率
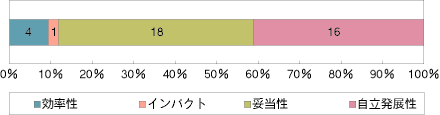
一方、評価5項目による比率をみると、妥当性と自立発展性にかかる問題点が多い。妥当性における問題点の比率が高いのは、スペアパーツの入手が困難な状況にある国に、機材を供与したことが妥当性の低さとして影響したことである。また、自立発展性の比率が高いのは、修理する技術者が不足していることに加え、将来的なスペアパーツ調達の問題や機材の老朽化による将来的な維持管理への懸念が大きく影響している。

