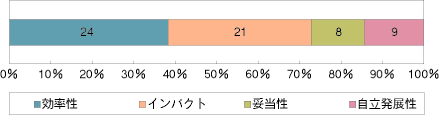第4章 事後評価結果の分析
1.指摘事項の整理
本章では、外務省、JICA、OECFによる評価結果を集計し、「プロジェクトが高い評価を得た要因」および「指摘された問題点」をまとめる。以下は、本章の対象である97年度における外務省、JICA、OECFの評価実施件数およびプロジェクト数である。
| 外務省評価 | JICA評価 | OECF評価 | 合計 | |
| 評価実施件数 | 110 | 32 | 20 | 162 |
| (プロジェクト数) | (154) | (114) | (30) | (298) |
以下では上表の評価結果から明らかにされた点を、次のように整理する。
- (1)プロジェクトが高い評価を得た要因
- (2)指摘された問題点:
- (イ)外部阻害要因による問題点
- (ロ)先方政府または先方実施機関の体制等により生じた問題点
- (ハ)機材の維持・管理体制等により生じた問題点
- (3)導き出された教訓
また、(1)および(2)については、前述の評価5項目(効率性、目標達成度、インパクト、妥当性、自立発展性)に分類し、プロジェクトの如何なる側面が成功したのか、または、問題があるのかを明確化した。
なお、本章で明らかにされた「プロジェクトが高い評価を得た要因」および「指摘された問題点」は、一評価につき複数指摘されている場合や全く指摘されていない評価もあることから、必ずしも指摘事項の合計数と評価件数は一致しないことを予め記しておく。
(1)プロジェクトが高い評価を得た要因
事後評価により明らかにされた「プロジェクトが高い評価を得た要因」は62項目であった。ここでの同要因は、プロジェクト計画時に期待されていた以上の効率性や効果等が認められたもの、あるいは、プロジェクト実施段階または運営段階において外部阻害要因があったにもかかわらずこれを克服したもの、等が含まれる。
次の図は同要因としてあげられた62項目の内訳である。最も多くあげられたものは、「副次的な社会的・経済的効果があった」であり、同要因全体の30%を占めた(副次的効果とは、当初プロジェクトに期待されていた効果以外に、プロジェクト実施により新たに生み出された効果のことである。具体例は次頁囲み参照)。
「プロジェクトが高い評価を得た要因」全体に占める具体的な要因の比率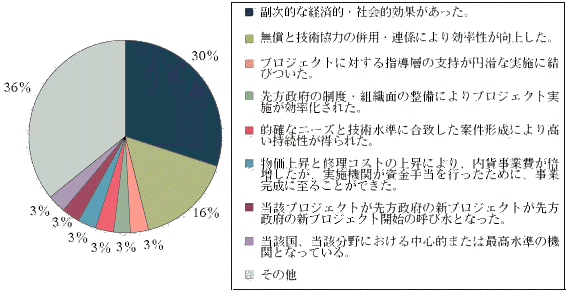
次に多く報告されたのは、「無償資金協力と技術協力の併用・連携により効率性が向上した」であり16%を占め(具体例は次頁囲み参照)、また、この他は「プロジェクトに対する指導層の支持が円滑な実施に結びついた」、「先方政府の制度・組織面の整備によりプロジェクト実施が効率化された」、「的確なニーズと技術水準に合致した案件形成により高い持続性が得られた」、などが報告された。
|
中国の「永安給水設備建設計画」(草の根無償)では、水道水の供給というプロジェクト目標が達成され、飲料水としても水質を確保して衛生面等での生活改善がなされたが、これによる副次効果として農民が水汲みから解放されて自由になった時間を農作物の販売等に活用し、現金収入も増加させたことが報告されている。 スリランカの「低所得者住宅改善計画」(無償資金協力)では、低所得者層の住環境の改善をもたらしたほか、副次的に地方電化の促進、治安の改善に資したことが報告されている。 マリの「バギンダ農業開発計画」(無償資金協力)では、水路の改修、農場の建設により、食糧自給の確保、雇用の創出、農村への人口定着等の効果を可能にしたが、さらに副次的に村民の水資源に対する重要性認識の啓発にも大きく貢献したことが報告されている。
|
|
1990、91年度に実施されたエジプトの「アラブ海運大学校新訓練船建造計画」(無償資金協力)は、76年から6年間にわたり実施されたプロジェクト方式技術協力による強固な「人」をベースとした協力関係や、85年度から10年間にわたり同施設で実施された第三国研修において、供与された訓練船が有効活用されたことにより、「ヒト」と「モノ」が有機的に連携し、極めて効率性の高い実施が可能となった。 |
「プロジェクトが高い評価を得た要因」を、評価5項目別の観点から分類すると、「目標達成度」とその他の4項目(「効率性」、「インパクト」、「妥当性」、「自立発展性」)に分けて考えることができる。
「目標達成度」に関しては、「効率性」や「妥当性」の高さにより、「目標を達成した」とするプロジェクトが非常に多く、全体の80%以上を占めた。目標を達成し得なかった理由をみると、「効率性」「妥当性」等が低かったことや後述する外部阻害要因によるものが多かった。いずれにしても、「目標達成度」には、その他の4項目が密接に関係していることがわかる。
なお、前述62項目にはこの「目標達成度」にかかる要因は含んでいないが、これは上述のとおり、「目標達成度」と他4項目は、前者が「結果」で後者が「原因」である場合が多いため、同列で考えにくいからである。
下図では、こうした高い比率の目標達成度を可能とした「妥当性」や「効率性」などを含む62項目の要因、すなわち評価5項目でいうと、「目標達成度」以外の4項目に含まれる要因を分類した。
これによると、効率性の向上による要因が全体の38%、インパクトにかかる要因が34%、妥当性の高さによる要因が13%、自立発展性の高さによる要因が15%であった。効率性の向上による要因24項目の中でも、最も多かったのは、異なった協力形態(有償資金協力・無償資金協力・技術協力)の連携による効率性向上であり、これらは24項目中13項目を占めた。インパクトにかかる要因の中では、前述の副次的な社会的・経済的効果があった項目が大半を占め(21項目中18項目)、この他、当該プロジェクトが、新規プロジェクト形成のモデルになったことや新規事業開始の呼び水になったことが報告されている。(詳細は以下の表を参照)
成功要因の評価5項目別比率