第2章 ODA事後評価活動
4.評価の形態
(1)評価形態の変遷
1990年代に入り、ODAの質がさらに問われるようになるにつれて、外務省は評価視点の多様化を図るため、試験的に新たな評価形態の導入を図ってきた。特に、97年度以降は、様々な視点からより客観的な評価結果を得るため、その形態をさらに拡充し、現在行っている評価形態は、次の表に示される12種類に及んでいる。
外務省の評価形態と変遷(年度)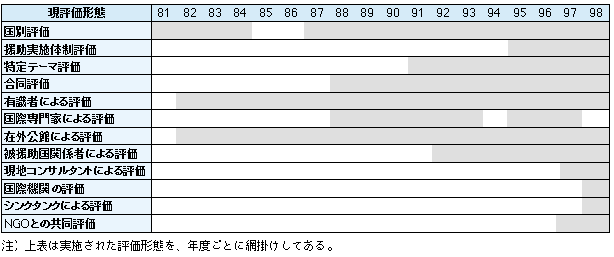
|
一方、JICAは、1982年度に事後評価を開始して以来、その拡充に努めている。99年度には、評価機能の拡充、特に、第三者の積極的活用により専門的かつ客観的な視点から有用な評価結果を導き出し、その結果を事業実施の改善に反映させることを目的として、新たに「外部機関による評価」が導入された。
JICA、OECFの事後評価形態と変遷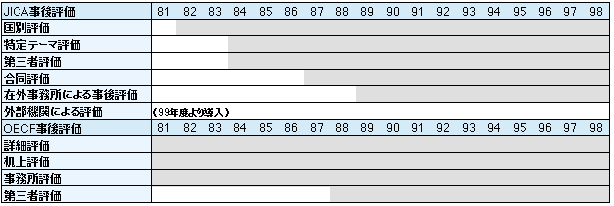
|
OECFでは1975年から評価事業を開始し、現有の評価形態は81年度から実施されている。詳細評価、机上評価、事務所評価は81年度から、第三者評価は88年度から実施されてきている。
(2)各機関の評価形態概要
以下では、上の表において示されている各機関の評価形態を、さらに詳しく説明する。
(イ)外務省の評価
外務省では、評価の公正性と客観性を確保し、質の高い効果的な評価を行うべく、以下の各種評価形態により評価を実施している。
(横断的視点で捉えた評価)(定義等の詳細は次節(3)にて説明)
(a)国別評価
主要な被援助国を対象に、日本のODA事業がその国の経済開発および民生の向上にどのような効果をもたらしたかをマクロ的視点から調査・分類する評価であり、評価結果は、被援助国に対する日本のODA政策策定の際に活用される。さらに、評価調査実施後、評価対象国において政府や民間の関係者などの参加を得てODA評価セミナーを開催し、評価結果の報告、討議を行うことにより、被援助国関係者への評価結果のフィードバックを行っている。
(b)援助実施体制評価
日本のODA主要受取国を対象とし、無償資金協力、技術協力、有償資金協力の援助全般に関わる資金の適正使用、援助実施手続きの適正さなど、評価対象国における援助実施体制、実施環境全般について調査し、改善すべき点などがあれば、これを是正・改善するような措置の勧告・提言を行う評価であり、政策、実務双方に通暁した有識者の協力を得て実施している。
(c)特定テーマ評価
国別評価同様、マクロ的視点からの評価であり、日本のODAおよびODA評価に関する経済協力団体に委託して実施する。特定セクターまたは援助形態をテーマとして日本のODAを横断的に捉え、援助効果や問題点を分析する。
(個別プロジェクト評価)
(d)合同評価
他のドナー国・国際機関と、双方の主要援助受取国におけるそれぞれの援助プロジェクト、あるいは援助協調プロジェクトを対象に、共同で作業を行う評価である。評価視点の多角化、評価手法の向上などの視点から有益であり、OECD(経済協力開発機構)のDAC(開発援助委員会)の場で、実施が推奨されている。
(e)有識者による評価
開発経済などの分野で高度な専門知識を有する学者をはじめ、文化人、報道関係者、NGO関係者など、外部の有識者に依頼して実施する評価である。それぞれの評価者の知識・経験を活かした独自の視点から評価が行われることが特色である。
(f)国際専門家による評価
開発援助などの外国人専門家に委嘱して実施する評価である。評価視点の多角化、外国の専門家の評価手法など学べることが特徴である。
(g)在外公館による評価
援助の実務に携わる日本大使館または総領事館の館員が、管轄国の日本のODAプロジェクトを対象に、ガイドライン(在外公館評価実施要領)に基づいて実施する評価である。外務省所管の限られた評価関係予算の中で、多数の評価調査を実施しており、援助プロジェクトの経済的・社会的効果、運営管理状況などの実状を効率的に把握できるものとして重要である。
(h)被援助国関係者による評価
被援助国関係者に委嘱して実施する評価である。被援助国側の視点でODAプロジェクトを評価することにより、被援助国関係者にODA活動の意義や解決すべき課題を認識する機会を提供し、日本のODAの一層の効果的・効率的実施に資する。
(i)現地コンサルタントによる評価
被援助国内の調査活動に実績を有する現地コンサルタントの社会・経済・文化事情などについての知見、情報収集力・分析力を活用して実施する評価である。
(j)シンクタンクによる評価
経済協力に関わる研究機関の有する情報収集力・分析力と外部の有識者の有する知識・専門性を活用することにより、評価視点の多角化、評価の総合化が期待できる。
(k)国際機関の評価
日本が継続的に支援してきている国際機関が実施してきているプロジェクトの活動・運営状況などについて調査・分析し、今後その国際機関のとるべき方向性を提言することを目的とした評価である。外部有識者または専門機関に委嘱して実施される。
(l)NGOとの共同評価
日本の政府およびNGOが実施している協力プロジェクトについてそれぞれのプロジェクトの成果と貢献度を双方の視点から共同学習することにより、今後の双方のプロジェクト形成・実施、援助方針・戦略などにフィードバックしつつ、これを通じてNGOとODAの協力推進を図ることを目的とした評価である。
(ロ)JICAの事後評価
JICAの行っている事後評価は、その内容と形態から次のように分類される。
(a)国別評価
JICAの協力を重点セクターごとに複数のプロジェクトを横断的に評価したうえで、評価対象国に対する効果および協力実施上の問題点を整理し、その結果を今後の当該国に対する国別事業計画や協力方法などの改善に反映させる。
(b)特定テーマ評価
特定分野、課題(環境、貧困、ジェンダーなど)および事業形態をテーマとして、幅広い視点から、当該テーマへの協力アプローチ、協力プロジェクトの効果や問題点を検討・分析し、その結果を今後の当該分野・課題への取り組みなどに反映させる。
(c)第三者評価
JICA事業の透明性と評価の客観性の確保、およびより幅広い視点からの評価を行うために、開発援助に精通し、JICA事業について見識を有する外部の第三者(学識経験者、民間有識者など)に依頼して、評価を行い、その結果を今後の事業実施に反映させる。
(d)合同評価
被援助国の関係機関、あるいは先進国援助機関や国際機関と合同で行う評価である。被援助国との合同評価は、プロジェクトの効果、問題点などについて、双方の認識の共有化が図られることに加え、被援助国側の評価手法の習得・向上にも貢献している。先進国援助機関や国際機関との合同評価は、評価手法の相互学習や連携強化を図ることができる。
(e)外部機関による評価(1999年度より導入)
各開発分野や開発の重点課題において専門的知見を有する外部の開発援助研究機関やコンサルタント会社に評価調査を委託し、それらの外部機関のノウハウを活用しつつ、評価の質および客観性の向上を図る。
(f)在外事務所による評価
JICAの在外事務所が、プロジェクトの評価手法や対象国の社会経済事情に精通した現地コンサルタントを活用して行う評価である。
(ハ)OECFによる評価
OECFの行っている事後評価は、その内容と形態から次のように分類される。
(a)詳細評価
OECF職員と外部専門家により構成された評価ミッションを現地に派遣して行う評価である。外部専門家の参加により、評価における客観性・専門性を高めることが可能となる。また、詳細評価のバリエーションとして、特定の地域・セクターの総合的な効果を把握するため複数の事業を一括して評価する「インパクト評価」、他の援助機関などと共同で現地調査を行う「共同評価」等があり、状況に応じて適宜行われている。
(b)机上評価
事後評価対象の全ての事業について現地へ評価ミッションを派遣して評価を行うことが困難なため、一部の事業については国内で評価作業を行っており、これを便宜的に机上評価とよんでいる。机上評価は国内で行われているため詳細評価と比べて相対的に情報量に限りがあるが、相手国政府から入手した文書情報およびその他の情報源を最大限に利用して情報収集を行うことにより、また、最近では可能な限り現地調査を行うなど評価の質を高めるべく留意している。
(c)事務所評価
OECFの現地駐在員事務所が、資料収集および現地調査を行い、これに基づいて評価を行うものである。必要に応じ、現地の専門家・調査機関の参加を求めることがある。
(d)第三者評価
外部有識者に評価を依頼して、現地調査を行うもので、有識者の有する知識・専門性を活用することにより、評価内容の多角化を図ることができる。
(3)評価形態別の評価視点
ここでは、上項において、説明した各々の評価を、さらに解り易くするため、評価視点別の分類を試みた。本項の分類は、本報告書作成時点での評価の現状を説明するために分類したものである。したがって、過去にODA評価の拡充が図られてきたように、今後、さらに、ODA評価が体系的に整理され、効率化されていくにつれて、ここでの分類も、変化していく可能性があることを前提とする。
本項では、各評価形態を次の二つの観点から分類している。
- (イ)評価が「横断的視点で捉えた評価」か、または「プロジェクト単位の評価」か。
- (ロ)評価結果が、外部有識者の視点(外部)によるものであるか、援助関係者の視点(内部)によるものであるか。
| 横断的視点による評価 | プロジェクト評価 | その他 | 外部有識者の評価視点 | 援助関係者の評価視点 | |
| 外務省 | |||||
| 国別評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 援助実施体制評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 特定テーマ評価 | ◯ | ◯ | |||
| 合同評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 有識者による評価 | ◯ | ◯ | |||
| 国際専門家による評価 | ◯ | ◯ | |||
| 在外公館による評価 | ◯ | ◯ | |||
| 被援助国関係者による評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 現地コンサルタントによる評価 | ◯ | ◯ | |||
| シンクタンクによる評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 国際機関の評価 | ◯ 国際機関が対象 | ◯ | ◯ | ||
| NGOとの共同評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| JICA | |||||
| 国別評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 特定テーマ評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 合同評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 第三者評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 在外事務所による評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 外部機関による評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| OECF | |||||
| 詳細評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 机上評価 | ◯ | ◯ | |||
| 事務所評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 第三者評価 | ◯ | ◯ | |||
| 注1) | ここでは、「横断的評価」を広義で捉えており、以下のいずれも横断的評価に含めた。 (1)マクロ的視点から複数の分野を横断的に捉えた評価 (2)特定プログラムの様々な種類の投入・成果および効果等を横断的に捉えて行う評価 (3)特定セクターの複数プロジェクトの投入・成果および効果等を横断的に捉えて提言を行う評価 |
| 注2) | 「プロジェクト評価」は、プロジェクトを個別に捉えて行う評価としている。 |
| 注3) | 「外部有識者」には、学者、専門家、文化人、報道関係者、NGO関係者、シンクタンク、民間コンサルタント、外国の専門家等を含む。また、「政府関係者」には日本政府関係者、被援助国政府関係者を含む。 |
前表からも明らかなように、各機関における評価視点は、評価形態により多様化しており、横断的視点によるものから、横断的視点とプロジェクト評価的な性質を併せ持ったもの、あるいは、各個別プロジェクト評価に限定しているものと様々である。
また、外部または内部の視点による評価か否かという観点からも、外部有識者と援助関係者の両視点から評価を行うもの、またはいずれか一方の視点によるもの、と評価形態により多様である。

