1.6 有識者評価
有識者評価は、開発経済などの分野で、高度な専門知識を有する学者をはじめ、文化人、報道関係者、NGO関係者、外国の専門家など、外部の有識者に依頼して実施する評価です。それぞれの評価者の知識・経験を生かした独自の視点から評価が行われることが特徴です。
|
1.ヴィエトナム・ストリート・チルドレン職業訓練センター機材供与計画等事業(1999年度) 評価者: 南条 俊二 読売新聞社論説委員 現地調査実施期間:2000年2月29日 |
■プロジェクトの目的
ヴィエトナム中部の旧都、フエ市内のストリートチルドレンなど生活困窮児童の生活、就業を支援する。
■評価結果
- (1)日本のNGO「ベトナムの「子どもの家」を支える会」がフエ市人民委員会と進めているプロジェクトに協力、同市地域の「子どもの家」の建設、ベッド、ミシン、コンピューターなどの機材一式を「草の根無償資金協力」により協力、さらに「開発福祉支援事業」として児童図書、音楽教育用キーボードの寄贈、さらに日本語教室、海外教室などの施設を増築した。現在、62人の子供たちを収容し、元気に通学し、勉学や技術習得に励んでいる。
- (2)プロジェクトの推進に当たっては、フエ市人民委員会が土地と職員を提供、施設建設は「支える会」と富士宮市中央ライオンズクラブ、日本政府、機材は日本政府が提供するなど、内外の連携が大きな成果を挙げている。地元のテレビ局、新聞もたびたび、その活動を報道して、市民の間に浸透している。地元の大学生や僧侶、理髪店経営者などが活動に協力、昨年秋の水害時には、市民からコメ200キログラムが寄贈されるなど、このプロジェクトを機に、ボランティア活動も育っている。
■提言
- (1)日本政府の草の根無償援助とJICA開発福祉支援事業がうまく繋がって、地元の人々に「顔の見える援助」として、成果を挙げている。今後の支援事業のモデルとして活用すべきだ。
- (2)今後は、日本からの人的資源を継続、充実していく必要があるが、その場合、NGOとともに、青年海外協力隊の若い力の活躍が望まれる。ただし、ヴィエトナムにおける協力隊の活動は開始されて5年余りであり、ヴィエトナム政府や地方政府、人民委員会にまだその趣旨が十分に理解されていない。ハノイ、ホーチミン両市で始まった活動を通して理解を得るとともに、日本政府としても相手側に正しい理解を求める必要がある。
- (3)フエ市の財政能力を充実させ、日本からの支援頼みをいつまでも続けることのないように、自らの財政力で企画、運営できるよう、自立を支援することを今後の課題として考えることも必要と思われる。
■■外務省からの一言■■
評価者の指摘にもある通り、草の根無償援助、NGO、JICA事業がミックスされて効果的な援助効果を生んだモデルであり、今後の支援事業にも十分活用していきたいと思います。
|
2.ヴィエトナム・カントー大学農学部改善計画(1999年度) 評価者: 南条 俊二 読売新聞社論説委員 現地調査実施期間:2000年3月3日~4日 |
■プロジェクトの目的
ヴィエトナム随一の農業地帯、メコン・デルタの農業生産の改善に大きな役割を果たすカントー大学農学部の施設、機材を抜本的に改善、充実する。
■評価結果
- (1)1968年に発足したカントー大学農学部は、講義棟など施設が老朽化し、機材も不足して、その使命である教育、研究活動に支障を生じていた。改善計画によって、農学科など3学科の共同講義棟、実験棟など施設が新設され、ゆとりをもって教育、研究活動ができるようになった。各種施設は今も清潔に維持され、教員、学生に好評を得ており、外部機関とのセミナーなど広がりをもった活動にも活用されている。
- (2)機材も実験、研究用に1万点が贈与された。それまでは、南ヴィエトナム時代の創立当初に日本から寄贈された機材が主体で、現在の基礎研究などに十分対応できなくなっていた。今回の贈与により、学生達が自分で実験などに機材を使用する機会が増え、教員も突っ込んだ研究ができるようになった。ただし、機材の一部が故障して利用されていないなど維持管理に改善の余地がある。
■提言
- (1) 現在、JICAのプロジェクト調整員の手で改善指導が行われているが、機材の維持管理を自らの手で十分に行う体制の確立、運用ができるようにする必要がある。
- (2)改善計画に続いて、「農業における環境教育向上ミニ・プロジェクト」が1999年4月から2003年3月の予定で始まっているが、施設・機材の充実とともに、こうしたソフト面での協力がますます重要になっている。大学当局も、相互留学などの拡充を望んでいる。農水省の研究所から3人の研究員が大学の研究所に出向して、長期研究を進めているが、ミニ・プロジェクトと研究課題で共通した部分も多く、連携を強める必要がある。
■■外務省からの一言■■
- (1)一部修理が必要な機材については、今年3月から、JICAフォローアップ事業の中で補修部品の供与を順次行っており、修理後有効に活用されることとなります。
- (2)評価者の指摘にある通り、ソフト面での協力を強化するとともに研究員との連携を強化したいと思います。
|
3.中国・北京市地下鉄建設事業(1999年度) (参考視察プロジェクト:北京市地下鉄第二期建設事業) 評価者: 伊能 忠敏 金沢工業大学教授 現地調査実施期間:1999年10月19日~26日 |
■プロジェクトの目的
北京市内の交通はバスに大きく依存しているが、1980年代後半、乗用車、自転車の利用台数が大幅に増加したことから著しい交通渋滞が発生し、効率的な公共交通手段の確保が急務であった。本件は、北京市地下鉄1号線を復興門・西単間(1.4キロメートル)延長し、かかる北京市の交通需要増加に対応するもの。
■評価結果
- (1)「北京市地下鉄建設事業」
計画通り実施され、北京市西方から市街地へと延びる1号線が西単まで延長された。他の交通機関等への乗り換え無しに直接繁華街にアクセスできるようになったことから、通勤や買い物等、多くの乗客に利用されている(一日あたりの利用客数:約50万人)。 -
(2)「北京市地下鉄第二期建設事業」(参考視察プロジェクト)
「北京市地下鉄建設事業」により西単まで延長された1号線をさらに四恵東まで(約11キロメートル)延長し、さらなる都市交通の改善を目的とする。1999年9月末、中国建国50周年記念にあわせ、時期を繰り上げて部分的に開通したが、通信設備関連の工事が未了のため、試験的に運行されているが、正式開通により既存路線との直通運転が行われるようになれば、乗客の増加が期待される。(99年10月時点) また、「北京市地下鉄第二期建設事業」では、最新式の車両が導入されているが、維持管理には技術訓練が不可欠である。(営団地下鉄が技術指導を実施している。)
■提言
- (1)車両の乗り心地、駅設備、乗換え施設等に更なる改善の余地が認められることから、今後実施される案件については、設計段階よりコンサルタントを活用することが望ましい。
- (2)都市交通の整備に向けて、地下鉄及び国鉄の一層の連携が必要である。
- (3)渋滞緩和及び排気ガスによる大気汚染を改善するため、公共交通機関の一層の整備が急務である。高架鉄道や路面電車の導入が望ましい。
■■外務省からの一言■■
評価時点では部分的な試運転であった1号線(苹果園~復興門~建国門~四恵東)ですが、2000年6月28日に全線開通し、1号線と環状線の乗り換えも可能となりました。北京のローカル各紙でも開通の記事は大きく取り上げられました。朝5時10分の始発から22時55分の最終まで、庶民の通勤、通学、買い物の足として、また中国のシンボルである天安門広場や故宮の足元を通る観光路線として利用されることが期待されています。
実施機関の北京市地下鉄総公司によれば、1時間当たりの平均乗客輸送人数は試運転時の4千~5千人であったものが、今回の全線開通により2万7千~2万8千人に急増する見込みです(中国公式英字紙China Daily 6月28日付け)。
去る6月5日には、谷野作太郎在中国大使が劉淇(りゅうき)・北京市長と会見し、今後の日本と北京との協力関係に関して意見交換を行いましたが、その際にも劉淇市長からは今回の地下鉄建設も含めた北京市に対する日本のODAは市民生活に大変役立っているとの謝意が述べられました。谷野大使からは、このように市民生活に密着する施設が日本のODAにより建設されていることがもっと広く北京市民に知られることを希望する旨が述べられました。
|
4.ネパール・「小学校建設計画」及び「第2次小学校建設計画」(1999年度) 評価者: 森 茂子 日本大学教授 現地調査実施期間:2000年3月18日~3月26日 |
■プロジェクトの目的
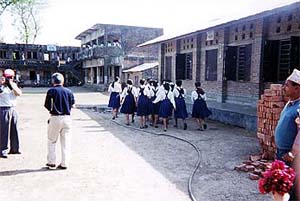
日本の援助で建設された小学校とそこで学ぶ子供
本件プロジェクトを通じた小学校建設により、ネパール政府が策定した「基礎・初等教育計画」の目的である(1)基礎・初等教育の質的改善、(2)教育機会へのアクセスの拡大、(3)組織の管理能力の強化に貢献する。
■評価結果
日本の援助として実施した本件プロジェクト(第一次(2年)、第二次(2年))により、合計2,958の教室の新規建設や、教員研修を目的とした41箇所のリソース・センターの建設が地方自治体の参加と共に実現した。その他、既存の教室のリハビリ、備品の供与も実施された。これらを通じて、生徒の受入人数の増加や、教育環境の向上をもたらした。
したがって本件プロジェクトは、初等教育機会へのアクセスの向上と、初等教育の質的改善に貢献したと評価できる。
■提言
- (1)今後、本件のような初等教育案件が検討・実施される場合に、以下に十分配慮されれば更なる効果が期待される。
- (2)対象地域住民による建設資材の運搬に対する支援、机や椅子等の備品の整備を援助対象として検討する。
- (3)プロジェクトを実施したことによる裨益効果について、対象地域別、男女別に分けた就学率等の変化等、何らかの数値的な裨益効果の把握方法の導入を検討していく。
- (4)他の援助国・機関とのより緊密な連携や情報共有を更に推進していく。
- (5)上記の小学校建設支援に加え、別途、教師養成、教科書開発、運営改善などに関するソフト面の支援を行なう。
■■外務省からの一言■■
無償資金協力では、プロジェクト実施において先方が負担できる部分は先方が負担することを方針としており、この点から運搬については検討しています。また、本件のようにサイトが数千に及ぶ場合、備品等については現況報告、供与後のモニタリングが困難であることから本件のようなプロジェクトの採択については、慎重に対処しています。
なお、1999年度から新たに開始した本件の第3次目となる一般プロジェクトでは、他の援助国の活動との連携をとりながら実施しています。
同国においては世銀による住民参加型学校建設が推進されていましたが、過度な住民負担、資機材の散逸・盗難・粗悪な施設の建設等により失敗したとされています。これらの事実も念頭に入れ、我が国としては従来からの技術移転、日本の「顔の見える援助」に加えて我が国を含むNGO活用についても検討しているところです。
|
5.コロンビア・「ボゴダ市上水道整備事業」(1999年度) 評価者: 中込 昭弘 公認会計士(太田昭和監査法人) 現地調査実施期間:1999年9月27日~30日 |
■プロジェクトの目的
本事業は第4次ボゴタ上下水道事業の一環であり、ボゴタ市の上水需要の増加に対応し安定した上水供給システムを整備し、併せて下水道施設の整備、洪水対策の推進等を行なうものである。
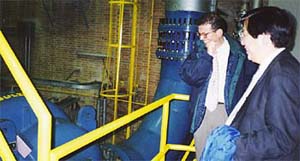
ポンプ上底部、左手に見えるのがモーター
■評価結果
- (1)計画の妥当性(事業が目的を達成するために妥当な論理構成を構築していたか)
世銀分を含めた当該プロジェクトは、ボゴタ市への水道安定供給及び上下水の配管・送配水網の整備を行なう上で優先度の高いプロジェクトである。また、1997年に起こったトンネルの落盤事故に対しても、サン・ラファエル貯水池が所期の機能を十分果たしたことから、サン・ラファエル貯水池建設の優先度は結果的にみても高かったといえる。 -
(2)目標達成度(当初想定された目標(主にアウトプット)が実現されたか)
プロジェクトの実施段階で実施した中間評価のため、現時点で、目標達成度に関する最終的な評価はしなかった。ただし、現在までのところ、貯水池並びにポンプ場の建設についてはほぼ予定通り完工している。 -
(3)効率性(得られた成果(=アウトプット(場合によってはインパクトも含む))と、事業実施にかかった費用を比較すると効率的であったと言えるか)
プロジェクト・コストについては計画変更等のため当初計画をオーバーしているといえる。ただし、オーバー分については自前で資金の手当を行なっている。また、工期遅延の原因は、当初予定に対し、公園建設の規模を大幅に拡張することにしたため、その設計変更に時間を要したことであり、土地所所有権に関する問題はまだ解決していない。もう少し早い段階からこの問題の発生を把握し、適切な対処ができなかったかという疑問が残る。 -
(4)インパクト (上位に位置する大目標(=事業の目的)はどの程度実現したと言えるか)
1997年にチューサ貯水池からの導水管トンネルにおいて2個所の落盤事故があり、それを修復する間の半年以上、サン・ラファエル貯水池が代替した。完成間もなかったこと及び当時の気象状況によりサン・ラファエル貯水池の水が満タンでなかったため、必要量の7割ほどの原水供給しかできなかったが、もし、この貯水池がなかった場合には、ボゴタ市全体の半分以上の住宅に、この間給水を行い得なかったことになり、この貯水池の建設は、ボゴタ市住民に対する安定的な水供給という点で非常に大きな効果があったといえる。サン・ラファエル貯水池は現在もメインの貯水池の補完として十分機能している。 -
(5)自立発展性(我が国ODAの供与が終了したあとも、自ら運営・維持管理していけるか)
EAABは過去の第一次から第三次上下水道事業においても、その実施能力の高さは評価されており、また今回のEAABとの協議及び現場視察さらに住民に対するインタビューを行なった結果からもその維持管理能力は問題ないものと思われる。

