7. 大洋州地域
太平洋島嶼(とうしょ)国は、日本にとって太平洋を共有する「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)〈注22〉を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域であるとともに、遠洋漁業にとって大切な漁場を提供しています。太平洋島嶼国の平和と繁栄は日本にとって重要です。
一方、太平洋島嶼国には比較的新しい独立国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。また、経済が小規模で、第一次産業に依存していること、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいことなど、小島嶼国に特有な共通の問題があります。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国の良きパートナーとして、自立的・持続的な発展を後押しするための支援を実施しています。
< 日本の取組 >

マーシャルのマジュロ環礁に位置する技術訓練センター。日本の草の根・人間の安全保障無償資金協力により改築された施設内で、伝統技術のアウトリガー・カヌー製作に取り組む学生たち。(写真:山崎秀幸/在マーシャル日本大使館)
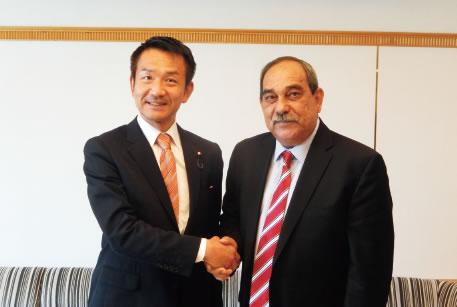
2016年10月、来日中のピーター・マーティン・クリスチャン・ミクロネシア連邦大統領を表敬する小田原外務大臣政務官
太平洋島嶼国における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的な脆ぜい弱じゃく性の克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)〈注23〉との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに日本と太平洋島嶼国との首脳会議である太平洋・島サミット(PALM)を開催しています。また、2010年以降、3年ごとに太平洋・島サミットの中間に中間閣僚会合を開催しているほか、2014年以降、毎年国連総会の機会をとらえ、日本・太平洋島嶼国首脳会合を開催しています。
2015年5 月に福島県いわき市で開催されたPALM7では、日本は、①防災、②気候変動、③環境、④人的交流、⑤持続可能な開発、⑥海洋・漁業、⑦貿易・投資・観光の7つの分野に焦点を当て、太平洋島嶼国との双方向のパートナーシップを促すための協力として、今後3年間で550億円以上の支援を提供するとともに、4,000人の人づくり・交流支援を行うことを表明しました。PALM8に向けた準備プロセスを開始するため、2017年1月に東京で開催された第3回中間閣僚会合では、PALM7で表明した支援のフォローアップと日本と太平洋島嶼国の共通の課題を踏まえた協力等について議論を行いました。
PALMで表明した支援方針を踏まえ、日本は、港湾といった基礎インフラ整備などの二国間の協力や、複数の国を対象とした広域協力を実施しています。重点分野の一つである「防災」については、太平洋島嶼国において災害に強靱(きょうじん)な社会を構築するため、日本の知見を活用しつつ、各国気象局の人材の育成や、住民が適切に避難できる体制づくりなどの包括的な防災支援を行っています。
また、太平洋島嶼国の気候変動問題への対処を支援するため、サモアにある地域国際機関である太平洋地域環境計画事務局(SPREP)〈注24〉と連携し、各国の気候変動対策に携わる人材の育成に向けた取組を進めています。
- 注22 : 排他的経済水域 EEZ:Exclusive Economic Zone
- 注23 : 太平洋諸島フォーラム PIF:Pacific Islands Forum
PIF加盟国・地域:オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア連邦、フランス領ポリネシア、ニューカレドニア - 注24 : 太平洋地域環境計画事務局 SPREP:Secreatariat of Pacific Regional Environment Programme
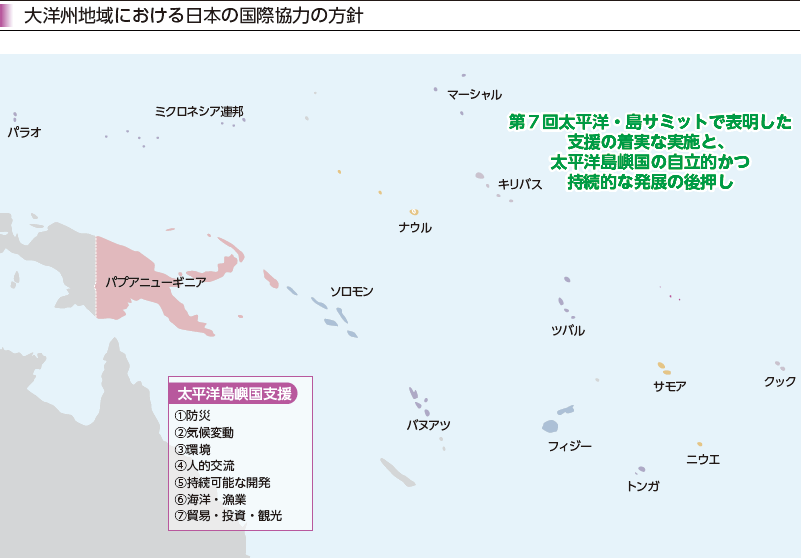
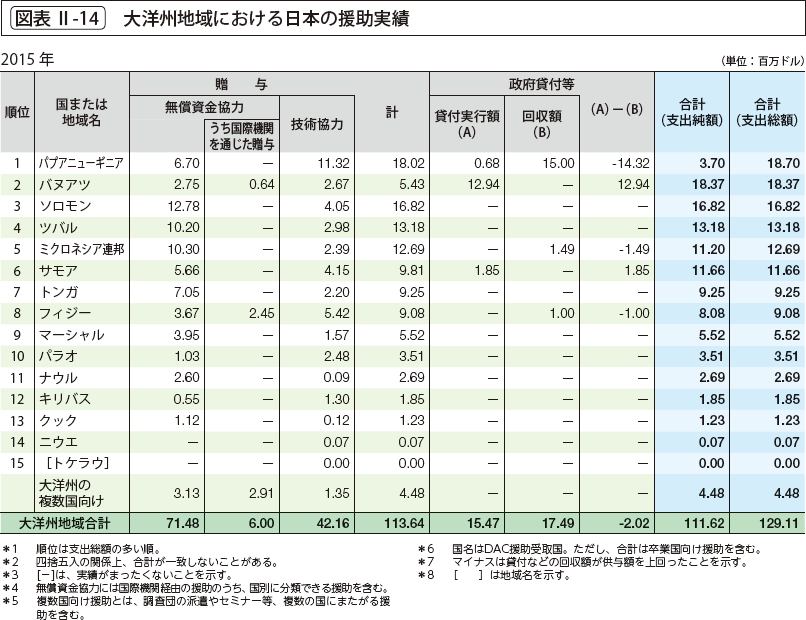
●サモア
沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト
技術協力プロジェクト(2014年8月~実施中)

適正な圧力で給水できるよう管路図面を用いて配水ブロックを再検討する専門家チーム(写真:富山健太/ JICA)
サモア水道公社( 以下、SWA:Samoa Water Authority)は、南太平洋に位置する島嶼(とうしょ)国サモアの全国民の約85%(16万人)に給水サービスを行っていますが、乾季の水不足、雨季の豪雨が引き起こす水質の汚濁とそれに伴う浄水処理への影響、さらには優秀な人材の流出など様々な問題を抱えています。近年、特に頭を悩ませているのは、給水した水量のうち、料金請求ができなかった“無収水量”の多さです。配水管の老朽化や杜撰(ずさん)な管路施工技術による漏水、一部の住民による違法接続(盗水)、水道メーターの不具合など、様々な要因が絡み合い、60 ~ 70%ともいわれる高い無収水率を招き、水道事業運営に悪影響を及ぼしていました。
日本は、島嶼特有の課題に取り組んできた沖縄県の強みを活かし、サモアへの水分野での協力をこれまでにも進めてきました。2010年から2013年にかけて沖縄県宮古島市が実施した草の根技術協力「サモア水道事業運営(宮古島モデル)支援協力」では、微生物の浄化作用(生物浄化法)に基づく正しい浄水場運転管理の技術移転や、圧力管理、管路図面の整備など漏水防止技術の向上に貢献しました。宮古島市の取組はサモア政府より高く評価され、継続的な協力要請を受けた日本政府は、沖縄がこの分野で培ってきた知恵と経験を結集した、「沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト」を2014年8月から開始しました。案件名に特定の県名が付くのは稀(まれ)なことで、これはサモア側からの強い要望だったそうです。
無収水の削減に主眼を置きつつ、水質管理と浄水場運転管理の強化も含めたこのプロジェクトでは、沖縄県内の水道事業体や関係機関から派遣された専門家が、現場指導を行うとともに各業務の知識や技術に係る標準作業手順書(SOP:Standard Operating Procedures)の整備を進め、SWA組織全体への普及・定着を図っています。これまでに8つのSOPが作成され、そのうち水圧と流量の調査手順を学び、実践に移したSWA市街課無収水対策班は、プロジェクト対象エリア内アラオア給水区の水圧と流量の傾向をモニタリングし、分析した結果、プロジェクト開始時24%だった適正圧力基準の達成率は現在65%まで改善しています。このプロジェクトは、並行して進められている無償資金協力「都市水道改善計画」とともに、サモアが安全で安定的な水の供給を受けられることを目指していきます。
(2016年8月時点)
●パプアニューギニア
マヌス州における太陽光発電海水淡水化設備事業
太平洋環境共同体基金を通じた支援(2016年4月~実施中)

マヌス州の離島に10基 設置された太陽光発電、海水淡水化設備(逆浸透膜法)の外観。水道・電力インフラが全くない場所でも、海水、地下水から浄化、WHO基準の飲料水をつくることができ、不安定で不衛生な雨水に依存しない生活が可能。(写真:双日株式会社)
世界で2番目に大きな島であるニューギニア島の東半分と、600の島々から成るパプアニューギニアは、赤道に近く、南太平洋に位置しています。ここでは約1,000もの部族が暮らしていますが、水道インフラが十分でないために、雨水や井戸水といった、不衛生で供給が安定していない水源を使用しています。また、乾期には井戸が干上がるなどの被害が出ており、安全な水の確保が差し迫った問題となっています。この問題を解決するため、太平洋環境共同体基金(PEC:Pacific Environment Community Fund)〈注1〉を活用し、株式会社アンジェロセックが、コンサルタントとしてフィージビリティ調査を実施し、双日株式会社・東レ株式会社がマヌス州における太陽光発電海水淡水化設備のプロジェクトを行うことになりました。このPEC基金は、第5回太平洋・島サミットにおいて、日本の提案で創設され、日本もこれに拠出しています。このうちパプアニューギニアには400万ドルが供与されました。
このプロジェクトにより、2016年度中に、マヌス州のビピ島・ムブケ島・ワール島において、10基の太陽光発電を電源とする据置型設備と5基の非常用の可搬式設備から成る海水淡水化設備が設置され、島民は衛生的な生活用水を安定的に利用できることになります。これらの設備で、約5,000人分の1日の飲料水に相当する10立方メートルの水(1日の最大処理能力)を供給できます。また、現地の人々の力で持続的に長期間設備を使用できるように、設備の維持管理にかかわる技術指導も双日株式会社の職員により実施されます。今後、学校や病院にも小型設備を設置し、パプアニューギニア政府とも連携することで、島の子どもたちが学校へ行くきっかけになり、島民の衛生レベルや生活の質にも良い影響を与えることが期待されています。
このプロジェクトは、パプアニューギニア政府の水供給、保健衛生計画および中期開発計画(MTDP:Medium Term Development Plan)に合致するものであり、パプアニューギニアの海岸に接する他の州はもちろんのこと、水資源に乏しい他の島嶼国(とうしょこく)にとっても有効な試験的プロジェクトであると評価されています。今後は、こうした試験的プロジェクトの成果や教訓も踏まえつつ、安全な水を確保していくための取組が期待されています。
(2016年8月時点)
- 注1 : 大洋州諸国が気候変動問題に対応するため創設された6,600万ドルの基金。
