6. 中南米地域
中南米地域は人口6億人、域内総生産約5.6兆ドル(2015年)の巨大市場であり、通商戦略上も重要な地域です。また、民主主義が根付き、鉄鉱、銅鉱、銀鉱、レアメタル(希少金属)、原油、天然ガス、バイオ燃料などの鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあり、国際社会での存在感を着実に高めています。平均所得の水準はODA対象国の中では比較的高いものの、国内での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多いことも、この地域の特徴です。また、アマゾンの熱帯雨林をはじめとする豊かな自然が存在する一方、地震、ハリケーンなど自然災害に脆弱(ぜいじゃく)な地域でもあることから、環境・気候変動、防災での取組も重要となっています。
< 日本の取組 >

エルサルバドルのサン・ビセンテ市内の学校で、青年海外協力隊の山口まどかさん(防災・災害対策)が倒壊した建物の下敷きになった被災者の救助法を指導する様子。同市は2001年大地震で大きな被害を受けた。(写真:エルネスト・マンサーノ/ JICA)

2016年9月、訪日中のフェルナンド・イェペス・ラッソ・エクアドル外務副大臣(当時)立ち会いの下、武井外務大臣政務官とレオナルド・カリオン・エギグレン駐日エクアドル大使との間で、供与額2億円の無償資金協力(経済社会開発計画)に関する書簡の交換が行われた

ベネズエラの西部、アプレ州のコロンビアとの国境付近にあるロス・バンコス学校で学習する子どもたち。日本の支援によって校舎や水道施設、トイレが整備された。(写真:加藤杏子/在ベネズエラ日本大使館)

2016年7月、パナマを訪問し、ロイ運河担当大臣兼メトロ公社総裁と会談をする黄川田前外務大臣政務官
中南米地域は、地震、津波、ハリケーン、火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防災の知識・経験を有する日本の支援は重要です。日本は、2010年1月のマグニチュード7.0の大地震により壊滅的な被害を受けたハイチに対する復旧・復興支援をはじめ、カリブ海上の国々および2016年4月に大地震の発生したエクアドルを含む太平洋に面した国々に日本の防災分野における知見を活かした地震、津波対策のための支援を行っています。ハイチに対しては、日本はこれまで総額約2.5億ドル超の復興支援を実施してきており、引き続き中長期的観点から、保健・衛生や教育といった基礎社会サービス分野を中心に復興支援を行っています。また、中米域内については、コミュニティ・レベルでの防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな成果を上げています。
中南米は、近年、生産拠点や市場としても注目されており、多くの日本企業が進出しています。メキシコの医師を対象とした心臓カテーテル技術*の研修を2011年に実施した後、同様の研修を2014年から2016年まで、メキシコのほか、アルゼンチン、コロンビアおよびブラジルの医師に対しても実施しました。これらの研修を通じて中南米地域における日本企業の技術がさらに普及することが期待されています。また、中南米諸国の経済開発のための基盤整備の観点から、首都圏および地方におけるインフラ整備も積極的に行っています。
環境問題に対しては、日本は、気象現象に関する科学技術研究、生物多様性の保全、アマゾンの森林における炭素動態〈注18〉の広域評価や廃棄物処理場の建設など、幅広い協力を行っています。近年注目を集めている再生可能エネルギー分野においては、太陽光発電導入への支援を多くの国で実施しており、コスタリカ等では地熱発電所の建設に向けた支援も行っています。
医療・衛生分野でも、日本は中南米に対して様々な協力を行っています。中米地域では、同地域特有の寄生虫病であるシャーガス病撲滅のための技術支援を行い、感染リスクの減少に貢献しています。ホンジュラスでは、2016年10月、感染症等の対策支援として、検査・サーベイランスを行う施設の建設、検査機材の供与等を行うための交換公文を締結しました。衛生分野でも、安全な飲料水の供給や生活用水の再利用のため、上下水道施設の整備への協力を数多く行っています。2016年9月には、安倍総理大臣がキューバを訪問し、日・キューバ首脳会談の成果として、本格的な無償資金協力の第1号案件となる、癌の診断機能および身体への負担が少ない治療の強化を目的とした医療機材の供与に係る交換公文を締結しました。それとともに、癌などの診断に対する医療体制の強化・改善を支援するための新たな技術協力の実施を表明しました。
今も多くの貧困が残存し、教育予算も十分でない中南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要です。日本は、小学校などの教育施設の建設への支援や、指導者の能力向上のためのボランティア派遣などを実施し、現地で高い評価を得ています。
カリブ諸国に対しては、気候変動や自然災害に対する小島嶼(とうしょ)開発途上国特有の脆弱(ぜいじゃく)性を克服するため、所得水準のみでは計ることのできない様々な支援ニーズに対応しています。環境・防災分野では、カリブ8国に対する広域の気候変動対策支援や防災分野の技術協力等を行っています。また、水産分野では、施設整備や専門家派遣を通じて限りある海洋生物資源の持続可能な利用促進に貢献しています。
長年の日本の開発協力の実績が実を結び、第三国への支援が可能な段階になっているブラジル、メキシコ、チリ、およびアルゼンチンの4か国は、南南協力*で実績を上げています。また、これらの国と日本はパートナーシップ・プログラムを締結し、たとえば、ブラジルと共に、アフリカのモザンビークにて、また、メキシコと共にパラグアイにて、三角協力*として農業開発分野の協力を実施しているほか、アルゼンチン、ドミニカ共和国等と協力し、震災後のハイチの復興支援などを行っています。
より効果的で効率的な援助を実施するため、中南米地域に共通した開発課題については中米統合機構(SICA(シカ))〈注19〉やカリブ共同体(CARICOM(カリコム))〈注20〉といった地域共同体とも協力しつつ、広い地域にかかわる案件の形成を進めています。
日本は官民連携で地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T方式)〈注21〉の普及に取り組み、2016年11月時点で中南米では13か国が、日本方式を採用しています。日本はこれら採用した国々に対して、同方式を円滑に導入できるよう技術移転を行い、人材育成を行っています。
2016年11月には、安倍総理大臣がペルー、およびアルゼンチンを訪問し、ペルーにおいては、環境・防災対策分野等で、またアルゼンチンにおいては、中小企業支援分野等で引き続き支援を行っていくことを表明しました。
半世紀以上国内紛争が続いたコロンビアに対しては、日本は地雷除去や被災者支援等の平和構築分野の支援をこれまで実施しており、和平プロセスの進展やサントス大統領のノーベル平和賞受賞で国際社会の関心が高まる中、2016年11月地雷除去に関する無償資金協力の実施を決定しました。
- *心臓カテーテル技術
- 具体的には、経橈骨(けいとうこつ)動脈冠動脈カテーテル技術。手首の大きな血管からカテーテルを挿入して、細くなったり、閉塞したりしている心臓の血管を広げる方法。
- *南南協力(三角協力)
- より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験と人材などを活用して、他の開発途上国に対して行う協力。自然環境・文化・経済事情や開発段階などが似ている状況にある国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナー(援助国)や国際機関が、このような開発途上国間の協力を支援する場合は、「三角協力」という。
- 注18 : 一定期間中における炭素量の変動。
- 注19 : 中米統合機構 SICA:Sistema de la Integración Centroamericana
- 注20 : カリブ共同体 CARICOM:Caribbean Community
- 注21 : 地上デジタル放送 ISDB-T:Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial
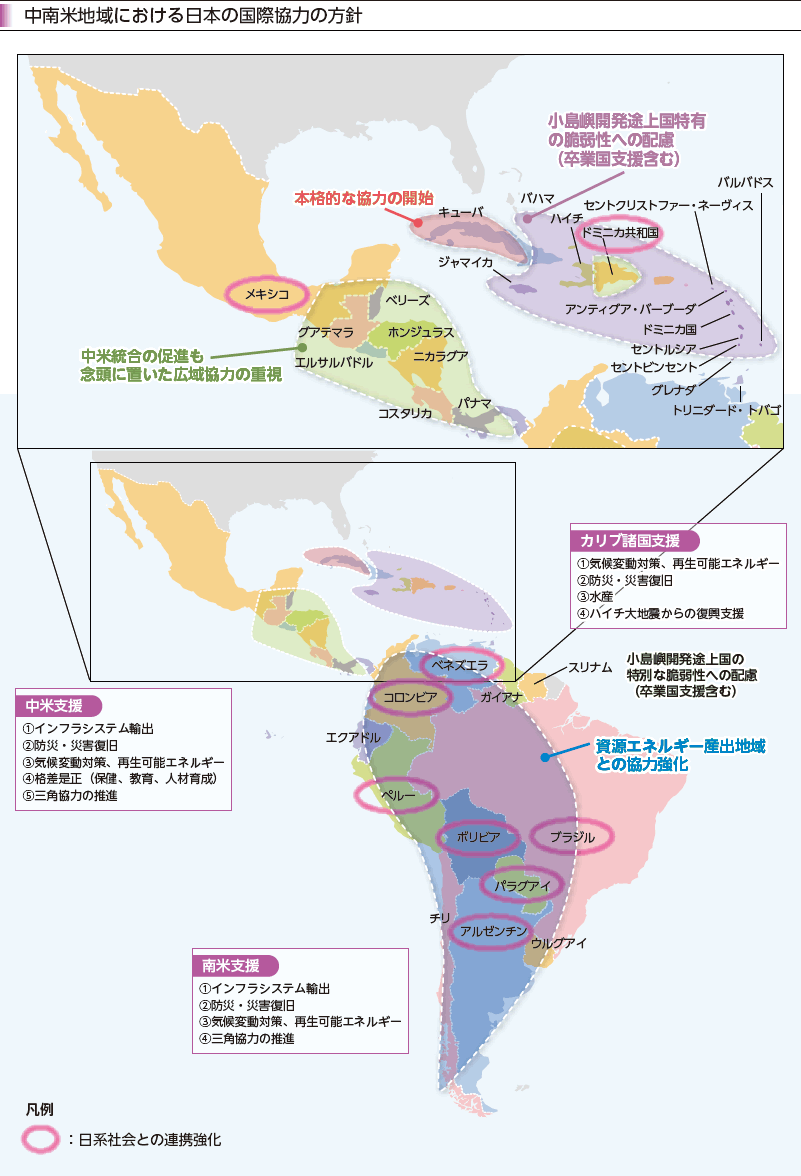
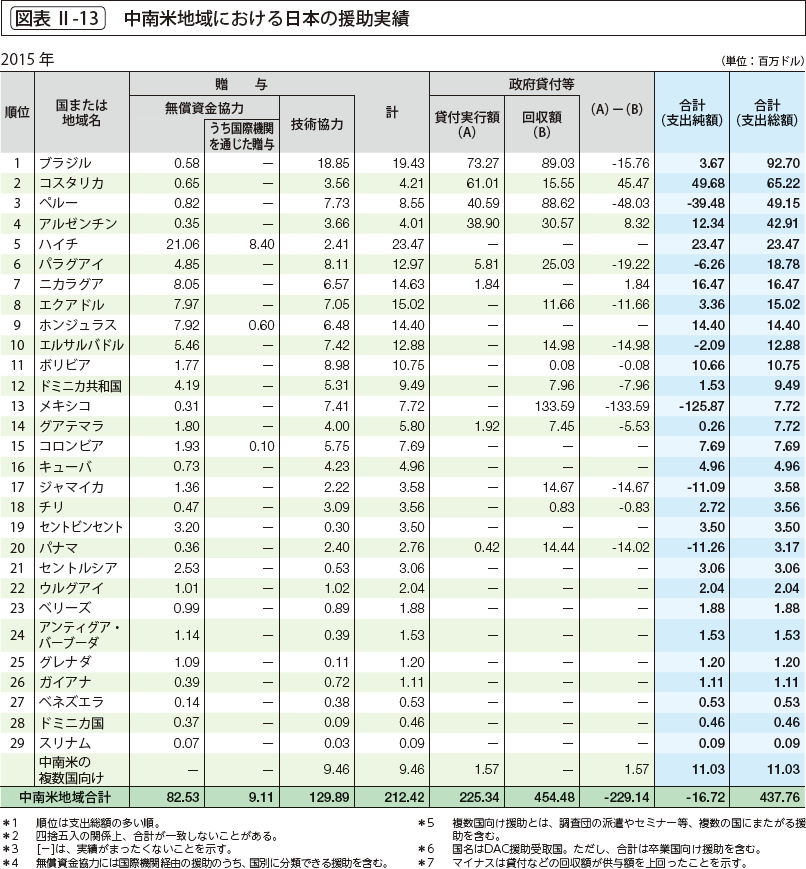

アルゼンチンの「フォルモーサ州での生物資源の持続可能な利用による地域住民の生計向上支援計画」でイエロー・アナコンダハンター・グループと議論するJICAの花井純一さんほか、プロジェクトスタッフメンバーたち(写真:安田将宏/一般財団法人自然環境研究センター)

ホンジュラスの首都テグシガルパ市にて草の根・人間の安全保障無償資金協力「ハポン小学校増改修計画」の引渡式で両国の国旗を振る子どもたち(写真:酒井宏美/在ホンジュラス日本大使館)
●ホンジュラス
地方開発のための自治体能力強化プロジェクト
技術協力プロジェクト(2011年10月~実施中)

子どもらが教室の中で勉強できるように地域資源を使った学校教室を増築(Intibuca県Yamaranguila市)(写真:FOCAL II プロジェクト)
ホンジュラスでは、地方分権化を通じた地方開発を推進してきましたが、多くの地方自治体は小規模で、財政・組織・行政能力に乏しく、これまで開発が思うように進んできませんでした。また、外部からの支援を待つ姿勢も、その開発の推進の妨げとなっていました。
日本は、先行プロジェクト「西部地域・開発能力強化プロジェクト」(通称:FOCALプロジェクト、2006年~2010年)において、西部地域を対象に、①住民参加によるコミュニティ現状調査、②コミュニティ開発計画策定、③市開発計画策定、④事業実施、の4段階の開発プロセス「FOCALプロセス」の導入を支援しました。これに続けて2011年から開始した「地方開発のための自治体能力強化プロジェクト」(通称:FOCAL IIプロジェクト)では、同プロセスを全国展開し、地方自治体とそこに参加する住民の能力強化を目指しています。
FOCAL IIプロジェクトでは、上記ステップにおける研修と実践を通じて、これまで市職員、市連合会〈注1〉職員、そして住民の能力強化を図ってきました。国内298市のうち、130市が住民と共に①コミュニティ現状調査を終え、89市が②コミュニティ開発計画を策定、83市が③市開発計画を策定し、これに基づいた④事業実施を進めています。
FOCALプロセスにおける鍵は、「住民参加」です。これまでの市の開発計画は外部コンサルタントを通じて作成されており、住民や市の参画意識が弱く、実用的ではないことがほとんどでした。コミュニティのことを一番知っているのは、そこに住む住民自身、また身近な市職員です。その彼ら自身が調査・計画をすることで住民が望んだ事業が実施に移されることになるため、事業に対する住民のオーナーシップが生まれ、彼ら自身が進んで事業に参加するようになり、そこに協力する市との信頼関係が醸成(じょうせい)され、好循環が生まれます。
コミュニティ開発計画に参加した住民は、自ら実施している活動について生き生きと語ってくれます。住民からは、「今までのように誰かの支援を待つのではなく、自分たちが行動を起こす」、「自分たちで課題を見つけて解決してゆく」、また、市職員からは、「住民が建設作業にも主体的に参加するので市の財政的負担が軽減した」、「住民が納税意識を高め、税収が倍増した」というコメントが聞かれます。FOCALプロセスによる地方自治体と住民の能力強化を通じた自立的な地方開発の進む様子が具体的に見え始めています。
(2016年8月時点)
- 注1 : 複数の市が負担金を出し合い、各構成市への技術的支援を実施する機関として設立。現在、全国に39の市連合会が実在し、機能している。
●ブラジル
E-Wasteリバースロジスティクス改善プロジェクト
技術協力プロジェクト(2014年9月~実施中)

パイロット事業の開始セレモニー。マスコットのDescartes君を囲んで。(写真:JICA)
急速な経済成長に伴って、ブラジルはモノの生産と消費が増加しています。そのため、廃棄物の量も急増しており、適切な廃棄物管理と減量化(Reduce)・再利用化(Reuse)・再資源化(Recycle)の3R活動の一層の取組が課題となっています。ブラジルでは、役割を終えて廃棄物となった家電製品(以下、E-waste、“Electronic waste”の略)のリサイクルや環境上適切な処分を考慮した循環システム(リバースロジスティクス、以下RL)を実施する施策が、国の法律で定められているものの、具体的な実施方法はまだ十分に検討されていません。RLとは、直訳すると「還元物流」で、廃棄後の製品を消費者から民間事業者(製造業者、流通業者等)へ還元し、再利用、再資源化、または適正な最終処理・処分を行う物流を確立することです。
サンパウロ州では、国の法律に先駆けて、2009年に「電気・電子機器廃棄物に係る州法」を施行して、通信会社と同州との間でRL構築に係る確約書を締結し、民間セクターが携帯電話のRLの構築を開始しました。今後はノートパソコンや白物家電についてもRL構築に向けた、メーカーとの交渉を検討しています。しかし、対象品目を広げるに当たり、より実効性を伴ったE-wasteのRLシステムを構築することが課題となっています。
そこで、この「E-Wasteリバースロジスティクス改善プロジェクト」では、パイロット事業の実施やその結果を踏まえたモニタリング体制の提案を行うことにより、RLを実施する上での改善のためのアクションを提示することとしています。これにより、サンパウロ州をはじめとして、全国においてRL実施が促進されることに寄与することが期待されます。
このプロジェクトの成功の鍵は、パイロット事業を通じてブラジル側が様々な障壁に気づき、問題解決のための実効性を持った制度の確立と合意の形成を行えるようになれるかどうかにあります。RLシステムの構築には、省庁、地方自治体、製造業者、流通業者、小売店等が多くかかわっていますが、これらのアクター(主体)はそれぞれ異なる利害や考えを有しています。日本が支援するパイロット事業では、民間を含めた多様な関係者との調整を行っており、そのプロセスを通じてブラジル側の計画や調整の能力が強化されていくことが重要です。
(2016年8月時点)
