8. 欧州地域
過去に共産主義体制にあった中・東欧、旧ソ連の欧州地域の多くの国々では、その後民主化と自由化を達成し、現在は民主的政権の下で市場経済に基づいた経済発展に取り組んでいます。日本は、これら地域および欧州全体の一層の安定と発展のため、また、普遍的価値(人権、民主主義、市場経済、法の支配)を共有する関係をさらに強化するため、市場経済化、経済インフラの再建および環境問題などへの取組に対する支援を行っています。
< 日本の取組 >
西バルカン諸国〈注25〉は、1990年代に発生した紛争の影響で改革が停滞していました。しかし、ドナー(援助国)や国際機関などの支援があり、また、それぞれの国が自身で改革のための努力を行ったことにより、復興支援を必要とする段階を卒業しました。現在は持続的な経済発展に向けた支援が必要な段階にあります。日本は2004年にEU(欧州連合)と共同で開催した西バルカン平和定着・経済発展閣僚会合で確認された「平和の定着」、「経済発展」、「域内協力」の3本柱を開発協力の重点分野として支援を展開してきました。引き続き、西バルカン諸国の開発途上国においては、特に「持続可能な経済成長の促進」を重点方針として支援しています。
旧ソ連諸国であるウクライナやモルドバは、ロシアとEUの間に位置するという地政学上の重要性を持っています。これら諸国の安定と持続的な発展は、欧州全体の安定にとってなくてはならないものです。民主主義が根付き、市場経済を確立させるための努力を支援する必要があります。これに関し、日本は2014年2月以降のウクライナ情勢の悪化を受け、ウクライナの国内改革を後押しするために、国別では最大規模となる約18.5億ドルの支援を表明し、着実に実施しています。また、政治危機に加え、ウクライナ東部情勢が悪化したことから、東部の社会サービスの早期復旧・平和構築支援として約600万ドル、東部の人道支援やインフラ復旧に対する支援として約3,000万ドル等を供与してきました。資金供与以外でも、技術協力を通じた行財政改革支援、汚職対策支援、メディア支援を含む民主化支援等を実施しています。
日本は、欧州地域内の経済発展の格差を踏まえ、EUに加盟した国々に対しては、援助を卒業したものとして、その支援を段階的に縮小させるとともに、ドナー(援助国)として欧州地域の開発途上国に対する開発協力に一層積極的に取り組むことを促していきます。日本は、ヴィシェグラード4か国〈注26〉を含むこれらの国々と援助国としての経験を共有するための取組も行っています。一方、西バルカン諸国やウクライナ等の開発途上国に対しては、各々の国の経済水準も踏まえながら、支援を実施しています。また、どの国に支援を行う場合にも、ドナー(援助国)および国際機関等の動きに注意を払いながら、日本の知識と経験を活かして、より成果を重視した効率的かつ効果的な支援を行っていくことに努めています。

ボスニア・ヘルツェゴビナ北東部に位置するゴルニ・ドラガリェバッツ村のステバン・ネマニャ小学校で日本の支援による暖房設備の整備を祝う学校関係者と子どもたち(写真:草山悟/在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本大使館)

2016年9月、モンテネグロにおける草の根・人間の安全保障無償資金協力「ポドゴリツァ市シュタンパル・マカリエ小学校校舎修復計画」の引渡式に出席する滝沢外務大臣政務官
- 注25 : 西バルカン諸国:アルバニア、クロアチア、コソボ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ
- 注26 : ヴィシェグラード4か国:ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロバキア
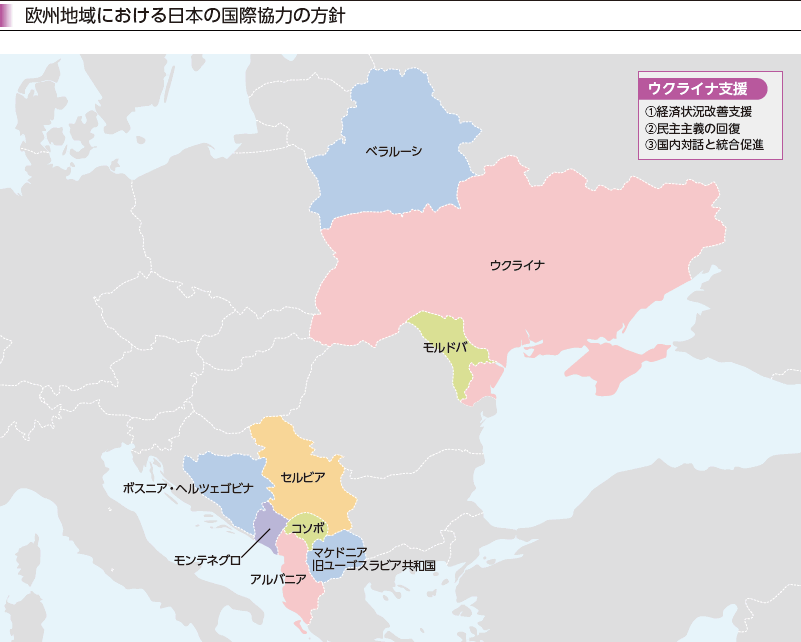
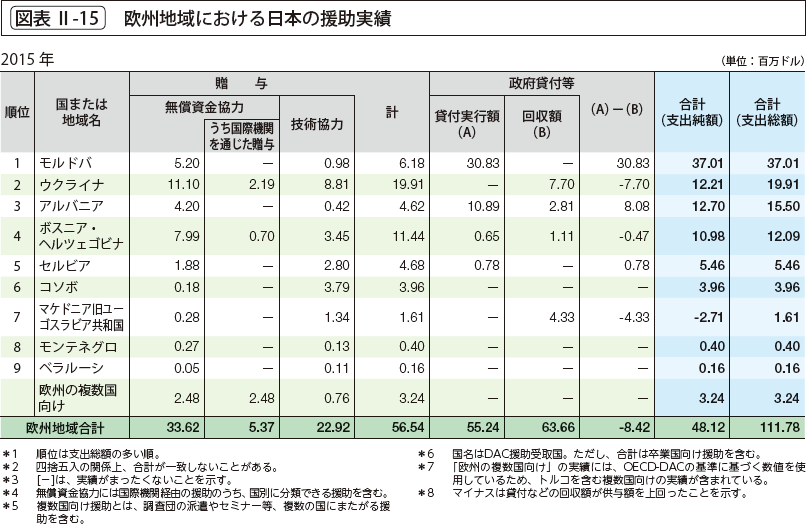
●セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ
西バルカン地域における中小企業メンターサービス構築・普及促進プロジェクト
技術協力プロジェクト(2013年4月~ 2016年5月)

モンテネグロのメンターと企業での研修風景(写真:JICA)
西バルカン地域に位置するセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの3か国は、2008年の世界金融危機の影響を受けマイナス成長に転じ、プラス成長に回復した2011年以降の経済成長率もおおむね1~3%程度にとどまっていました。このような状況から早期に回復し、経済を活性化させるためには、国内企業の大半を占め、国内雇用者の大多数を抱える中小企業の成長が不可欠です。しかし、西バルカン地域の中小企業は、金融へのアクセス、行政手続き、国内の不平等な競争等において問題を抱えている状態である上、中小企業の支援体制も脆弱(ぜいじゃく)であり、支援サービスを提供できる人材が不足していました。
そのような環境の改善のため、日本はセルビアにおいて中小企業に直接企業診断やアドバイスを行うメンター(指導者)制度を組織化し、定着させることを目的とした「メンター制度組織化計画プロジェクト」(2008年~2011年)を実施しました。同プロジェクトは、大きな成果を上げ、メンター制度はセルビア国内各地で導入されました。このメンター制度の評判が広がり、セルビアにおいてはメンター制度のさらなる普及・強化、ボスニア・ヘルツェゴビナとモンテネグロにおいてはメンター制度の構築を支援することになりました。
また、新たな試みとして、女性の社会進出を後押しするため、女性起業家を対象としたメンターによる相談会を実施しています。メンター制度に申し込んだオーガニック食品を扱うセルビア企業の女性経営者は、ビジネスは拡大しつつあったものの、従業員とのコミュニケーションがうまく取れておらず、このまま発展するのは難しいと感じていました。彼女は、メンターによるアドバイスで、上から下への意思決定(トップダウン)ではなく、現場の意見を尊重して活かしていくボトムアップで、業務をより良くするアイデアを従業員から得ることの重要性に気づいたといいます。また、あるメンターは「経営者が何でも一人で問題を解決することは、事業が大きくなるにしたがって難しくなる。この点で、メンターとの対話形式による経営へのサポートは有用です」と語っています。
このように中小企業支援体制の強化に焦点を当てた制度構築を日本が支援することにより、西バルカン地域で経済基盤が強化され、同地域の持続的な成長の実現が期待されています。

日本から提供された、セルビア・ベオグラード市内を走る黄色いバス。両国の架け橋として人々に利用されている。(写真:久野真一/ JICA)
