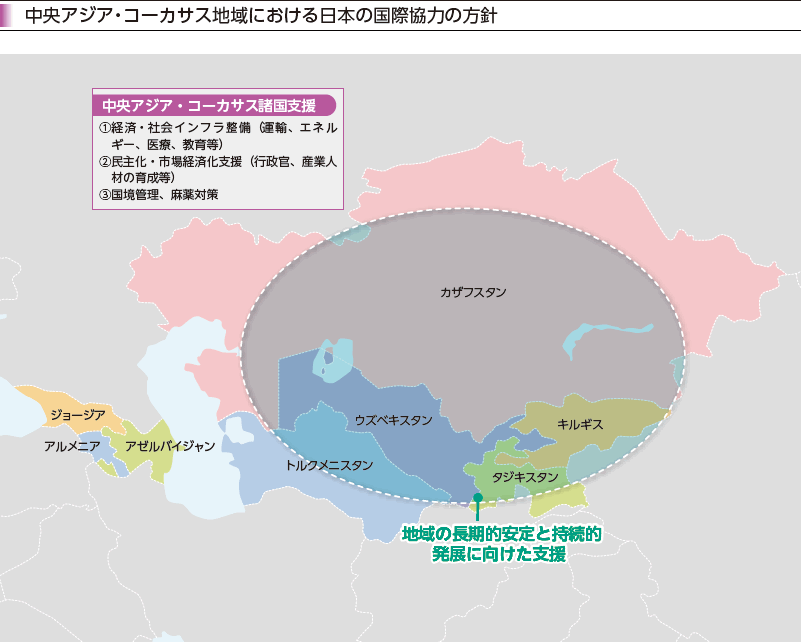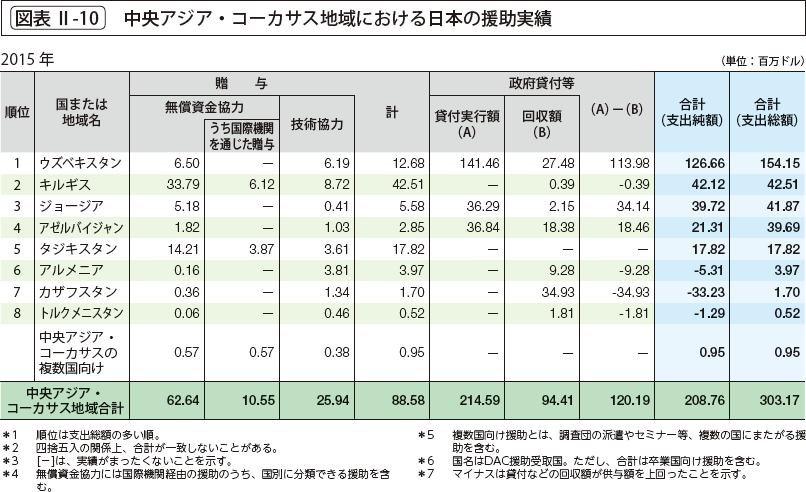3. 中央アジア・コーカサス地域
中央アジア・コーカサス地域は、ロシア、中国、南アジア、中東、欧州に囲まれていることから地政学的に重要な地域であり、この地域の発展と安定は、ユーラシア地域全体の発展と安定にとっても大きな意義を有しています。また、この地域には石油、天然ガス、ウラン、レアメタル(希少金属)などのエネルギー・鉱物資源が豊富な国も含まれることから、資源供給国の多様化を目指して、資源・エネルギー外交を展開する日本にとっても戦略的に重要な地域です。この観点から日本は、この地域の国々に人権、民主主義、市場経済、法の支配といった普遍的価値が根付くよう、そして同時にアフガニスタンやパキスタンなど、中央アジアに近接する地域を含む広域的な視点も踏まえつつ、この地域の長期的な安定と持続的発展のための国づくりを支援しています。
< 日本の取組 >

ウズベキスタン西部ホレズム州の世界遺産都市ヒバのイチャンカラ博物館の中にある女性の手作り絹製品販売店の女性たちが現地NGOビジネス・ウーマン協会から制作指導を受けているところ(写真:徳永由希子/東京農工大学)
日本は、計画経済体制から市場経済体制への移行と経済発展に向けた各国の取組を支援するため、経済発展に役立つインフラ(経済社会基盤)整備、市場経済化のための人材育成、保健医療など社会システムの再構築など様々な支援活動を行っています。
たとえば、日本はウズベキスタン、アゼルバイジャン、アルメニアにおける電力インフラやカザフスタン、キルギス、タジキスタン、ジョージアにおける運輸インフラの整備を支援してきました。人材育成の分野では、日本はウズベキスタン、キルギス、カザフスタンでは日本センター*を通じたビジネス人材の育成を支援しており、また、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンにおいては若手行政官の日本留学プログラムである「人材育成奨学計画」を実施してきています。このほか、2014年までに中央アジア・コーカサス諸国から10,878名の研修員を受け入れ、また、同諸国に対して2,603名の専門家を派遣しています。
2015年には、日本は民主化を進めるキルギスに対して選挙の際の投票者本人の確認手続を自動化するための機材供与、およびこれに係る人材育成に関する支援を実施しましたが、同年これらの機材を活用した議会選挙が成功裏に実施されたことから、この日本の協力はキルギスにおける民主主義の定着に大きく貢献したとして高く評価されています。
2015年10月、安倍総理大臣は日本の総理大臣として初めて中央アジア5か国すべてを訪問し、各国との二国間関係の抜本的強化、地域共通の課題への関与、およびグローバルな舞台での協力という日本の中央アジア外交の3本柱を示しました。この訪問において、日本は、電力、道路、空港、医療等のインフラ整備に対する支援を引き続き実施していくこと、高等専門学校をはじめとする日本型工学教育を活用した高度産業人材育成を支援していくことなど、各国の開発課題に応(こた)える協力を表明しました。
また、日本は、中央アジア各国との連携を強化し、中央アジアの地域協力を進めることを目的として「中央アジア+日本」対話の枠組みを2004年に設立し、これまで外相会合や高級実務者会合など様々なレベルで対話や協力を実施しています。日本は中央アジアにおける地域協力の重要分野である国境管理・麻薬対策、防災、農業の分野で、国連開発計画(UNDP)、国連食糧農業機関(FAO)、国連麻薬犯罪事務所(UNODC)等と連携しつつ、中央アジアに対する地域横断的な協力を推進しています。
- *日本センター
- 中央アジアやインドシナ地域の市場経済移行国における市場経済化を担う人材育成を目指し、日本の「顔の見える援助」として、また、日本との人脈を築く拠点として、市場経済を目指す9か国に10センターが設置され、現在、7か国8センターでJICAプロジェクトを継続中(プロジェクト終了の2センターも現地で活動を継続)。ビジネスコース、日本語コース、相互理解促進事業を活動の柱としている。
●タジキスタン
ヴァフシュ行政郡ルダキ地区サディシェロジ村第29中学校校舎建設計画
草の根・人間の安全保障無償資金協力(2014年4月~ 2015年12月)

新校舎完成を祝う、第29学校の児童・生徒(写真:伊達山光)
タジキスタンでは初等教育が広く普及しており、初等教育の就学率や成人の識字率は男女共に99%近くに上ります〈注1〉。ソ連時代には首都から遠く離れた地方にも学校が建設され、タジキスタンの子どもたちの多くは、現在もソ連時代に建設された学校で学んでいます。
一方で、学習環境は決して良いとはいえず、増加する子どもの数に対して学校の数が不足したり、行政側の資金不足のため老朽化する学校校舎の改修や教育のための備品の整備が十分でないなどの問題を抱えていました。
タジキスタン南部のハトロン州ヴァフシュ行政郡にある第29学校も同様の問題を抱えていた学校の一つです。1959年に設立された第29学校には、1年生から4年生まで約120名の児童が在籍していましたが、校舎は建設後50年以上が経過しており、床板が抜けている箇所があるなど危険な状態でした。また、同校には小さな教室が2部屋しかなく、教室不足のため5年生以上の児童は約7キロメートル離れた別の学校へ通う必要があるばかりでなく、通学路には不安定な吊り橋などもあるため、安全上の理由から進級を諦める児童もいました。特に、2011年には2人の女子児童が登校中に吊り橋から落ちて亡くなるという事故が発生し、それ以降、女子児童を学校へ通わせることに反対する保護者も多く現れ、女子児童の進級率が下がるという大きな問題を抱えていました。
このような状況下で、ヴァフシュ行政郡は、日本に対して、草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて、第29学校の新校舎建設計画の要請をしました。教室6部屋および職員室・校長室各1部屋から成る新校舎が建設された現在、保護者も安心して子どもを学校へ送り出すことができるようになり、現在では1年生から8年生まで約320名の児童・生徒が快適な環境で勉学に励んでいます。
- 注1 : 2016年世界銀行データ

キルギスにおける無償資金協力「ビシュケク・オシュ道路クガルト川橋梁架け替え計画」で完成したクガルト橋の前で、設計・建設を担当した岩田地崎建設(株)とセントラル・コンサルタント(株)の関係者たち(写真:グリナラ・テミロヴァ/在キルギス日本大使館)