2. 南アジア地域
南アジア地域には、世界最大の民主主義国家であるインドをはじめとして、大きな経済的潜在力を有する国があり、国際社会における存在感を強めています。地理的には、東アジア地域と中東地域を結ぶ陸上・海上の交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要であるほか、地球環境問題への対応という観点からも重要な地域です。また、テロおよび過激主義に対する国際的取組における役割といった観点からも、日本を含む国際社会にとって関心の高い地域です。
一方、南アジア地域には、道路、鉄道、港湾など基礎インフラの欠如、人口の増大、初等教育を受けていない児童の割合の高さ、水・衛生施設や保健・医療制度の未整備、不十分な母子保健、感染症、そして法の支配の未確立など取り組むべき課題が依然多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、この地域に住んでいる16億人を超える人口のうち約5億人が貧困層ともいわれ、世界でも貧しい地域の一つです。〈注14〉「持続可能な開発目標(SDGs)〈注15〉」達成を目指す上でもアフリカに次いで重要な地域となっています。
日本は、南アジア地域の有する経済的な潜在力を活かすとともに、拡大しつつある貧富の格差をやわらげるため、経済社会インフラ整備の支援を重点的に行っています。
なお、2016年7月に、バングラデシュにおいて、日本人の国際協力事業関係者が犠牲となったダッカ襲撃テロ事件が発生しました。南アジア地域においても、今後テロに屈することなく国際協力事業を進めていく上で、国際協力事業関係者の安全確保が喫緊の課題です。同年8月末に外務省およびJICAが関係省庁等と共に策定し、発表した国際協力事業関係者等の新たな安全対策を、相手国政府の協力も得つつ、着実に進めていく必要があります。
< 日本の取組 >

2016年11月、来日したインドのモディ首相と握手をする安倍総理大臣(写真:内閣広報室)
南アジア地域の中心的存在であるインドとは、「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づいて、経済協力をはじめ、政治・安全保障、経済、学術交流など幅広い分野で協力を進めています。インドは日本の円借款の最大の受取国であり、日本はインドにおいて電力や運輸などの経済インフラの整備等を支援しています。2014年9月の日印首脳会談において、今後5年以内に、日本の対インド直接投資とインド進出日系企業数の倍増を実現するために、インドに対し今後5年間でODAを含む3.5兆円規模の官民投融資を実現するとの意図を表明しました。
2015年12月には、安倍総理大臣がインドを訪問しモディ首相との間で、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道に日本の新幹線システムを導入することを確認しました。なお、2015年度の対インド円借款の供与額はインド向けとして過去最高に達しました。これらが日印間の経済協力関係の一層の推進に寄与することが期待されています。2016年11月には、モディ首相が訪日し、首脳会談において、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道計画の着実な進捗(しんちょく)が歓迎されるとともに、両首脳は兵庫県の新幹線工場を視察するなど、「日印新時代」の象徴として、同計画に対する高い期待が示されました。日本のODAは、インフラ開発、貧困対策、投資環境整備、人材育成等を通じ、インドの成長において大きな役割を果たしています。

2016年7月、ASEM首脳会合(於:モンゴル)の際、バングラデシュのハシナ首相と会談を行う安倍総理大臣(写真:内閣広報室)
近年、発展が目覚ましく、日本企業の進出も増加しているバングラデシュとは、2014年3月の岸田外務大臣のバングラデシュ訪問、5月のハシナ首相の訪日および9月の安倍総理大臣のバングラデシュ訪問という一連の要人往来の中で、5月に「包括的パートナーシップ」が立ち上げられました。また、その際、2014年よりおおむね4年から5年を目途に、バングラデシュに対し、最大6,000億円の支援を実施する意図を表明しました。このような二国間関係強化の中で、①バングラデシュの経済インフラの開発、②投資環境の改善、および③連結性の向上を3本柱とする「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想を中心に、政策対話を強化し、経済協力を進めています。2016年5月には、ハシナ・バングラデシュ首相が、G7伊勢志摩サミットのアウトリーチ会合参加のため訪日し、安倍総理大臣から、『日本は、バングラデシュの「2021年までの中所得国化」実現に向けて支援を継続していく』と述べた上で、その一環として、ジャムナ鉄道専用橋に関する支援やダッカ都市交通整備計画等への円借款(合計約1,735億円)の供与を通じたベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)構想の推進、両国間の人物交流の拡大や貿易・投資の一層の促進への期待等を表明しました。
2016年7月1日(現地時間)に発生したダッカ襲撃テロ事件で、日本人の国際協力事業関係者が犠牲となったことを受け、安倍総理大臣は、7月15日に実施された日バングラデシュ首脳会談において、日本人の犠牲者はすべて援助関係者であり、痛恨の極みとした上で、日本は今回の犠牲者の志を受け継ぎ、バングラデシュに対するODAを今後も継続すること、また、バングラデシュ側に対しては、徹底した真相の究明、関連情報の共有、犯人の厳正な処罰を求めるとともに、在留邦人・渡航者の安全確保の徹底、再発防止に全面的な協力を得たい旨を表明しました。また、これまでの取組を今一度検証し、新たな安全対策を策定するため、外務大臣の下に、外務省とJICAが関係省庁等と共に「国際協力事業安全対策会議」を立ち上げ、計5回の会合を開催した後、8月末に国際協力事業関係者等のための新たな安全対策を発表しました。
スリランカとの協力関係は、2014年9月の安倍総理大臣による日本の総理大臣として24年ぶりの訪問に続き、2015年1月の新政権樹立後も幅広い分野で深化・拡大しつつあります。2015年10月にはウィクラマシンハ首相が訪日し、両首脳は「包括的パートナーシップに関する共同宣言」を発表しました。この共同宣言は、①投資・貿易促進、②国家開発計画に係る協力、③国民和解・平和構築に係る三つのイニシアティブのほか、海洋協力、人材育成・人的交流等の促進を表明しています。また、2016年5月には、シリセーナ・スリランカ大統領がG7伊勢志摩サミットのアウトリーチ会合参加のため訪日し、安倍総理大臣から、「『質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ』の下、スリランカとも協力を強化していく」旨を述べた上で、全国送配電網整備およびアヌラダプラ県での上水道整備に係る総額約380億円の円借款を供与する意図を表明したほか、コロンボ港およびその周辺開発等に官民一体となって取り組む旨を述べました。
今後もスリランカの一層の経済発展とともに、進出している日系企業の活動環境の改善にも寄与する運輸・電力基盤などのインフラ整備の分野で協力を行っていきます。また、同国の紛争の歴史や開発の現状を踏まえ、後発開発地域を対象に生計向上や農業分野を中心とした産業育成など、国民和解に役立つ協力および災害対策への支援を継続していきます。
パキスタンは、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っており、アフガニスタンの安定にとって、パキスタンの協力は極めて重要です。これまで日本は、2009年4月に世界銀行と共に東京で開催したパキスタン支援国会合の際に表明した10億ドルの支援を実施したほか、空港・港湾の保安能力向上支援や、テロ掃討軍事作戦で発生した国内避難民への支援を実施しています。また、不正薬物取引および国際的な組織犯罪に対する国境管理能力強化のための支援や、平和構築・人道支援・テロ対策分野の機材、製品を供与する支援を実施しています。2013年6月に発足したシャリフ政権は、治安の改善に取り組むとともに、同年9月に承認された新規IMFプログラム(3年間、66.4億ドル)の下で、経済・財政の立て直しを進め、2016年9月、同プログラムを完了しました。また、2016年5月には、民間のゲイツ財団と連携したローン・コンバージョン方式にて、ポリオ撲滅に向けた支援として、約63億円の円借款を供与しました。
新憲法制定プロセスを通じて民主主義の定着と発展に向けた取組をしているネパールに対しては、2014年10月および2015年3月に訪日したパンディ外務大臣と岸田外務大臣との間で会談を行い、日本としてネパールの民主化への努力を継続的に支援していくとともに、政策面を含め様々な分野での協力をさらに拡大・強化することを表明しました。2014年10月の日・ネパール外相会談において立ち上げに合意した、日・ネパール外務省間政務協議を実施する〈注16〉など、二国間関係は近年飛躍的に深化しつつあります。2015年4月に発生したネパール大地震に対して日本は、国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供与および1,400万ドル(16.8億円)の緊急無償資金協力を実施したことに加え、総額2.6億ドル(約320億円超)規模の住宅、学校および公共インフラの再建を中心とする日本の支援策を表明し、ネパールの中長期の復興プロセスに、仙台の国連防災世界会議の成果である「より良い復興」のコンセプトを活用し、強靱なネパールの再建に向けて最大限の支援を実施しています。
また、2016年9月には、岸外務副大臣が日・ネパール外交関係樹立60周年の記念式典出席のためにネパールを訪問し、首都カトマンズと主要都市とを結ぶ幹線道路上に存在するナグドゥンガ峠にネパール第1号となるトンネルを建設する計画に対して、円借款を供与する方針を表明しました。

「ネパール地震復旧・復興プロジェクト」で、同国東部のシンドパルチョーク郡チョウタラで日本が監修・実施した住宅建設トレーニングを受ける建築技術者たち(写真:位坂和隆/ JICAネパール事務所)
●インド
インド工科大学ハイデラバード校 日印産学研究ネットワーク構築支援プロジェクト
有償勘定技術支援(2012年1月~実施中)

東京大学の学生との合同ワークショップ(写真:JICA FRIENDSHIPプロジェクト)
急速な経済発展を続けるインドでは、研究開発を先導して技術革新を進めるとともに、産業界のニーズにかなう知識と技能を持った人材の訓練・育成が重要な課題となっています。こうした中、インドから日本に対して理工学系高等教育機関の拡充に関する支援の要請がありました。これに対して日本は、2007年の安倍総理大臣訪印の際、新たなインド工科大学(IIT:Indian Institute of Technology)設立への協力を検討する作業部会設置に合意し、翌2008年にインドで10番目のIITとして開校したIITハイデラバード校(IIT-H)を対象に、円借款による新キャンパス整備や機材調達をはじめとする各種支援を行っています。
2012年より実施されている「インド工科大学ハイデラバード校 日印産学研究ネットワーク構築支援プロジェクト」では、日印産学ネットワークの構築を目的に、IIT-Hの学生を日本の大学の博士(または修士)課程に受け入れるための奨学金プログラムの実施、人材交流促進アドバイザーの派遣、インターンシップの実施や、共同研究の促進支援などを行っています。
このうち、人材交流促進アドバイザーの派遣は長期にわたって実施されており、学長をはじめIIT-Hの教授陣からも高い評価を得ています。その結果、インド工科大学と日本国内の大学との連絡が非常に円滑に進むようになったほか、普段から日本への留学や日本での研究を志す者に対して適切なサポートを行い、日本に対する親近感を学生の間で醸成(じょうせい)することに大きく寄与しています。奨学金を得てこれまでに日本に留学した学生の総数は50人(うち博士課程進学者は44名)に上り、修了生の中には日本企業への就職を決めた者や、さらに研究を続ける者など、その進路は様々です。
日本国内の企業の協力を得て行われているインターンシップは、本プロジェクトの特徴の一つです。これまでに合計12名の学生(日本の大学に留学中の学生も含む)が日本企業の職場に飛び込み、技術者として日本流の労働慣行に触れるなどして実務経験を深めています。また、インド工科大学を支援する日本国内の大学・企業との共同研究の件数の伸びも堅調で、現在11件が進行中です。
さらに、IIT-Hが、大規模な研究資金プログラムを獲得するための契機となる「共同研究資金提供プログラム」を実施するなど、より強固で継続性のある日印産学ネットワークの構築のための取組も続けられています。
(2016年11月時点)
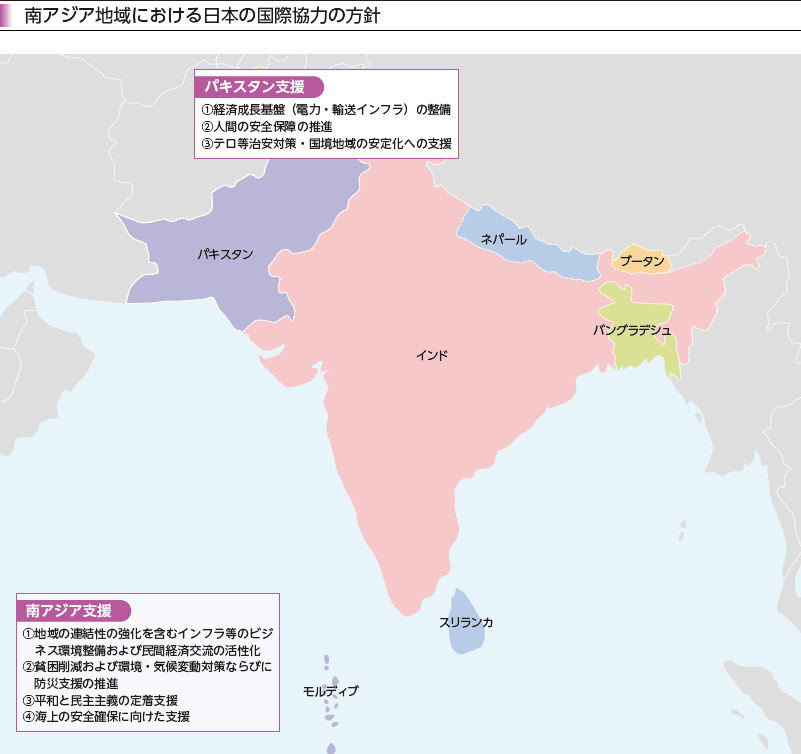
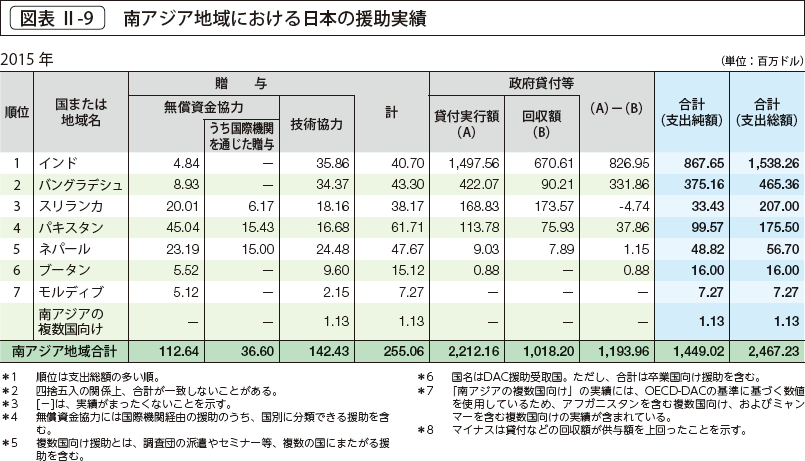
- 注14 : 2015年のMDGsレポートによれば、1日1.25ドル未満で生活する人の割合は17%(2015年)で、これはサブサハラ・アフリカに次いで高い数字である。
- 注15 : 持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)
- 注16 : 2015年3月第1回、2016年6月第2回を開催。
