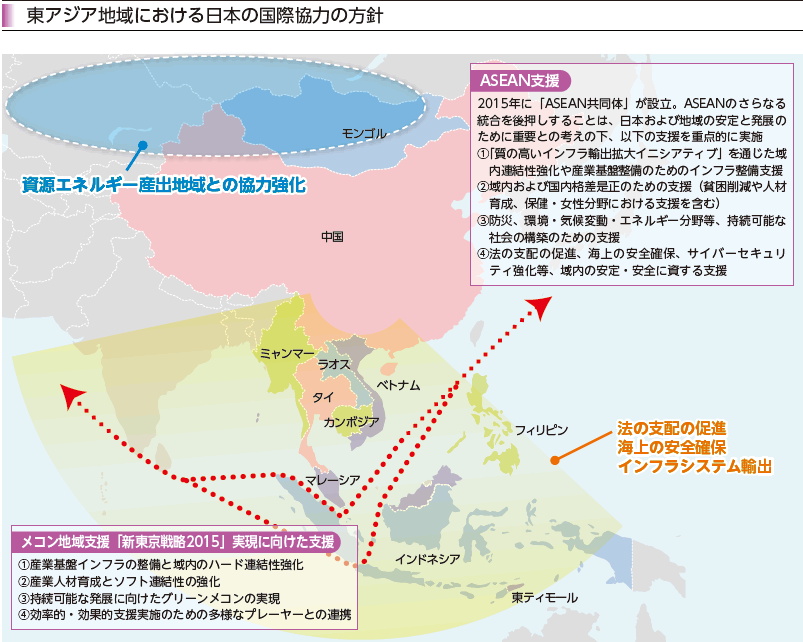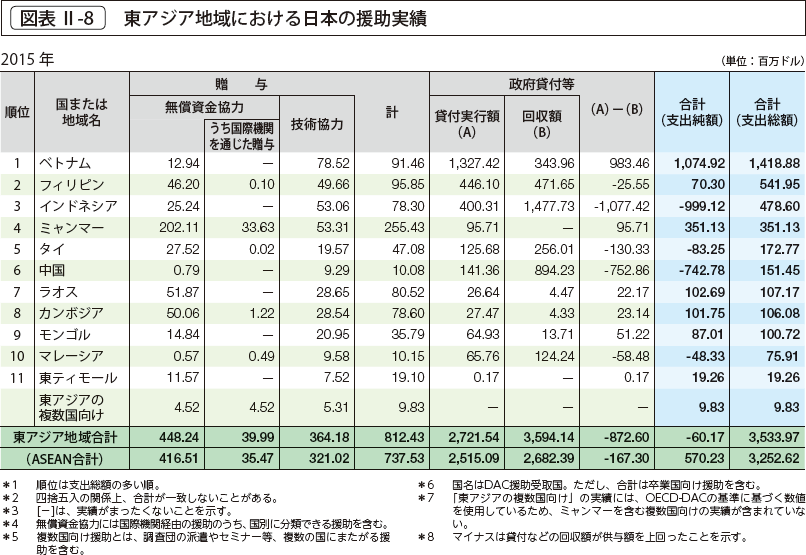第2節 地域別の取組
世界では国や地域によって抱える課題や問題が異なります。現在の国際社会における開発課題の多様化、複雑化、広範化、グローバル化の進展等に鑑みれば、世界全体を見渡しつつ、世界各地域に、その必要性と特性に応じた協力を行っていく必要があります。日本は、これらの問題の経済的、社会的背景なども理解した上で、刻一刻と変化する情勢に柔軟に対応しながら、重点化を図りつつ、戦略的、効果的かつ機動的に開発協力などを行って開発途上国の問題解決に取り組んでいます。
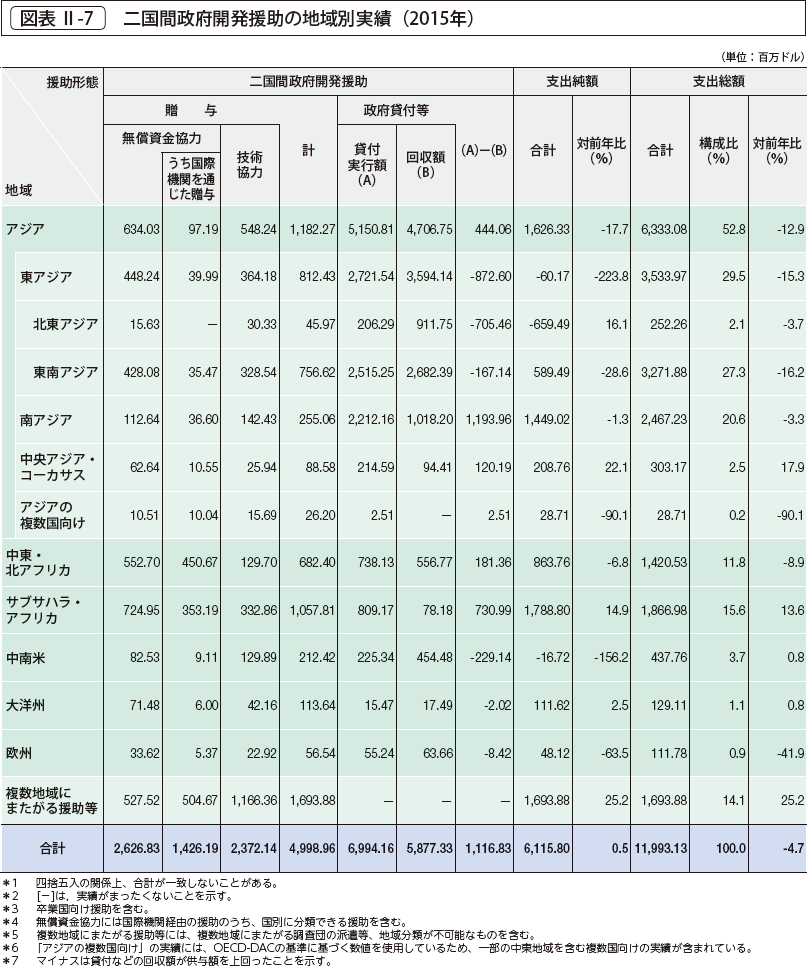
1. 東アジア地域
東アジア地域には、韓国やシンガポールのように高い経済成長を遂げ、既に開発途上国から援助供与国へ移行した国、カンボジアやラオスなどの後発開発途上国(LDCs)〈注1〉、インドネシアやフィリピンのように著しい経済成長を成し遂げつつも国内に格差を抱えている国、そしてベトナムのように市場経済化を進める国など様々な国が存在します。日本は、これらの国々と政治・経済・文化のあらゆる面において密接な関係にあり、この地域の安定と発展は、日本の安全と繁栄にも大きな影響を及ぼします。こうした考え方に立って、日本は、東アジア諸国の多様な経済社会の状況や、必要とされる開発協力内容の変化に対応しながら、開発協力活動を行っています。
< 日本の取組 >
日本は、インフラ(経済社会基盤)整備、制度や人づくりへの支援、貿易の振興や民間投資の活性化など、ODAと貿易・投資を連携させた開発協力を進めることで、この地域の目覚ましい経済成長に貢献してきました。現在は、基本的な価値を共有しながら開かれた域内の協力・統合をより深めていくこと、相互理解を推進し地域の安定を確かなものとして維持していくことを目標としています。そのために、これまでのインフラ整備と並行して、防災、環境・気候変動、法の支配の強化、保健・医療、海上の安全等様々な分野での支援を積極的に実施するとともに、大規模な青少年交流、文化交流、日本語普及事業などを通じた相互理解の促進に努めています。
日本と東アジア地域諸国がより一層繁栄を遂げていくためには、アジアを「開かれた成長センター」とすることが重要です。そのため、日本は、この地域の成長力を強化し、それぞれの国内需要を拡大するための支援を行っています。
●東南アジアへの支援

2016年9月にラオス・ビエンチャンで開催された日・ASEAN首脳会議(写真:内閣広報室)
東南アジア諸国連合(ASEAN(アセアン))諸国〈注2〉は、日本のシーレーン上に位置するとともに、多くの日系企業が進出するなど経済的な結びつきも強く、政治・経済の両面で日本にとって極めて重要な地域です。ASEANは2015年の共同体構築を最大の目標とし、ASEAN域内の連結性強化と格差是正に取り組んできました。日本は、こうしたASEANの取組を踏まえ、連結性強化と格差是正を柱として、インフラ整備、法の支配の強化、海上の安全、防災、保健・医療、平和構築等の様々な分野でODAによる支援を実施しています。
連結性の強化に関しては、2010年10月のASEAN首脳会議において、ASEAN域内におけるインフラ、制度、人の交流の三つの分野での連結性強化を目指した「ASEAN連結性マスタープラン」が採択されたことを踏まえ、日本は、マスタープランの具体化に向けてODAの活用や官民連携を通じて積極的に支援を行ってきました。メコン地域における東西・南部経済回廊の構築、インドネシア、マレーシア、フィリピン等における海洋ASEAN経済回廊の構築を二大構想として、道路・橋梁(きょうりょう)、鉄道、空港、港湾建設等のハードインフラの整備に加え、税関システムの向上等制度面、ソフトインフラの整備も推進しています。なお、2016年9月のASEAN関連首脳会議では、「ASEAN連結性マスタープラン」の後継文書である「ASEAN連結性マスタープラン2025」*が採択されました。日本は、この新しい文書に基づいて、引き続きASEAN連結性支援を行っていきます。
日・ASEAN友好協力40周年であった2013年には、12月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議において「日・ASEAN友好協力ビジョン・ステートメント」が採択され、日・ASEAN関係の強化に向けた中長期ビジョンが打ち出されました。この際、日本は、2015年の共同体構築を目指すASEANが掲げる「連結性の強化」、「格差是正」を柱に、5年間で2兆円規模のODAによる支援を行うことを表明しました。また、防災分野については、2013年11月に発生したフィリピン中部における台風ヨランダによる甚大な被害を受け、防災ネットワークの拡充や災害に対して強靱(きょうじん)な社会の実現に向けた支援の実施を内容とする日・ASEAN防災協力強化パッケージを発表し、ASEANにおける高品質な防災インフラ整備と災害対応能力向上のため、5年間で3,000億円規模の支援と1,000人規模の人材育成を実施することを表明しました。各国のニーズに沿った個別の支援を進めるとともに、2016年7月には、ASEAN全域を対象としてASEAN災害医療連携強化プロジェクトを開始し、今後ASEAN域内の災害医療に関する連携体制強化を進めていきます。
特にインフラ整備に関しては、日本は、東南アジア諸国に対するこれまでの支援の経験も踏まえ、「質の高いインフラ投資」の重要性を表明しています。2015年11月の日・ASEAN首脳会議では、安倍総理大臣が「質の高いインフラパートナーシップ」〈注3〉のフォローアップとして、円借款の手続の迅速化、新たな借款制度の創設など円借款や海外投融資の制度改善を行うことや、アジア開発銀行(ADB)〈注4〉との連携をさらに進め、国際協力銀行(JBIC)〈注5〉や日本貿易保険(NEXI)〈注6〉の制度改正・運用改善を行うことなど、抜本的な制度拡充策を発表しました。
また、2016年5月のG7伊勢志摩サミットに先立ち、安倍総理大臣は「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」を発表、アジアを含む世界全体のインフラ案件向けに、今後5年間の目標として、オールジャパンで約2,000億ドルの資金等を供給すると同時に、さらなる制度改善を進めていくことを表明しました。

タイ・バンコクにおける都市鉄道整備(高架鉄道)プロジェクト。総延長23Kmで、タイ国内に初の日本製車両が導入され、2016年8月に開業した。(写真:JICA)

2016年7月、ラオス・ビエンチャンにおいて開催された第9回日メコン外相会議に出席し、日メコン協力の進捗状況について述べる岸田外務大臣
こうした一連の取組もあり、2015年4月にはカンボジアにおける南部経済回廊の要であるネアックルン橋(通称「つばさ橋」)が開通式を迎え、2016年8月にはタイのバンコク首都圏における交通渋滞対策と大気汚染改善のための都市鉄道パープルラインが開業し、バンコク都市交通で初となる日本製車両が採用されるなどASEANにおける「質の高いインフラ投資」推進の取組は着実に成果を上げています。
さらに、アジアにおける持続的成長には、インフラ整備に加え、各国の基幹産業の確立や高度化を担う産業人材の育成が不可欠との考えの下、安倍総理大臣は、2015年11月の日・ASEAN首脳会議の場において今後3年間で4万人の産業人材の育成を行う「産業人材育成協力イニシアティブ」を発表、2016年夏までに、ASEAN地域において16,000人以上の産業人材育成を実施しており、日本は今後も、アジアにおける産業人材育成を積極的に支援していきます。加えて、2016年9月のASEAN関連首脳会議の際には、ASEANを含むアジア諸国と日本との間で、日本の大学等への留学、日本企業でのインターンシップ等を通じ、高度人材が環流することを日本政府がODAで支援し、アジア全体のイノベーションを促進するための「イノベーティブ・アジア」事業を発表し、ASEAN諸国から歓迎されました。この事業は「日本再興戦略2016」でも明記されており、2017年度から5年間で1,000人の優秀な学生を日本に受け入れる計画です。
ASEAN諸国の中でも特に潜在力に富むメコン地域〈注7〉に関しては、毎年開催している日本・メコン地域諸国首脳会議(日・メコン首脳会議)のうち日本で開催する回(おおむね3年に1度)において、地域に対する支援方針を策定しています。
2015年7月に開催された第7回日・メコン首脳会議(日本における開催は4回目)では、今後3年間の日メコン協力の方針として、①メコン地域における産業基盤インフラの整備と域内外のハード連結性の強化、②産業人材育成とソフト連結性の強化、③グリーン・メコン〈注8〉の実現、④多様なプレーヤーとの連携を4つの柱とする「新東京戦略2015」を採択しました。同時に、メコン地域に対して、包摂(ほうせつ)性、持続可能性、強靱性を兼ね備えた「質の高い成長」を実現するため、今後3年間で7,500億円のODAによる支援を実施する方針を表明し、同年8月に開催された第8回日・メコン外相会議では、「新東京戦略2015」の実現のための「日メコン行動計画」を採択し、特にハードインフラの整備を加速化させました。
2016年7月の第9回日・メコン外相会議においては、次のステージとして、物理的な連結性が十分に活用されるための制度的な連結性の強化(制度改善、経済特別区〈注9〉等の拠点整備、産業振興策、通関の円滑化等)、人的な連結性の強化に取り組むことを目指す「日メコン連結性イニシアティブ」の立ち上げを発表しました。このイニシアティブの下、同地域においてヒトやモノの流れを生み出す「生きた連結性」を実現し、成長の果実を地域全体に広げて地域統合とASEAN共同体強化を後押しすべく、2016年9月の第8回日・メコン首脳会議(ラオス)において、同イニシアティブの下で優先的に取り組むODAプロジェクトをとりまとめたリストを発表しました。この首脳会議では、ハード・ソフト両面における日本の取組に対する謝意が表明されるとともに「新東京戦略2015」の順調な滑り出しが高く評価されました。
メコン地域の中では、特に民主化の進展に取り組むミャンマーに対して、2012年4月、日本は経済協力の方針を見直し、急速に進むミャンマーの改革努力を後押しするため幅広い支援を実施していくこととしました。具体的には、少数民族に対する支援を含む国民の生活向上、法整備支援や人材育成、ヤンゴン・ティラワ経済特別区を中心とするインフラ整備などであり、日本はミャンマーに対して様々な支援を積極的に行っています。ティラワSEZ開発に関しては、2014年5月に経済特別区内の早期開発区域について土地使用権の販売が開始され、2015年9月には、麻生副総理大臣も出席して、開所式典が開催されました。日本は引き続き同特別区の周辺インフラ整備等を支援しており、2016年8月現在、世界から78社(そのうち39社が日本企業)が進出しています。日本の「質の高いインフラ投資」が世界からの信頼に結実した成功例といえます。
また、2016年11月にミャンマーからアウン・サン・スー・チー国家最高顧問が訪日した際には、ミャンマーの民主化の定着、国民和解、経済発展を、官民を挙げて全面的に支援するとの日本の方針に基づき、「日ミャンマー協力プログラム」*を踏まえて、官民合わせて2016年度から5年間で8,000億円規模の貢献を行うこと、その一環として国民和解の進展を支えるため、少数民族地域へ同じく5年間で400億円の支援を行うことを安倍総理大臣から表明しました。同時に、今後年間1,000人規模の交流・人材育成を行い、国づくりを支えていくことも伝えました。

ミャンマー・ティラワ経済特別区のエントランス・ゲート(写真:荒木裕/JICAミャンマー事務所)
●中国との関係
日本は、1979年以降、日中関係の柱の一つとして中国に対するODAを実施してきましたが、中国の経済的発展および技術水準の向上を踏まえ、既に一定の役割を果たしたとの認識の下、対中ODAの大部分を占めていた円借款および一般無償資金協力は、約10年前に新規供与を終了しました〈注10〉。過去の支援は、中国経済の安定的な発展に貢献し、ひいてはアジア・太平洋地域の安定、さらには日本企業の中国における投資環境の改善や日中の民間経済関係の進展に大きく寄与したと認識しています〈注11〉。
現在の中国に対するODAは、日本国民の生活に直接影響する越境公害、感染症、食品の安全等の協力の必要性が真に認められるものに絞って限定的に実施しています。技術協力(2015年度実績8.06億円)〈注12〉を中心とし、草の根・人間の安全保障無償資金協力(2015年度実績1.06億円)〈注13〉も実施しています。
技術協力については、たとえば、日本への影響も懸念されているPM2.5を含む大気汚染を中心とした環境問題に対処する案件や現地進出日本企業の円滑な活動にも資する中国の民法や特許法等の起草作業を支援する案件を実施しています。
また、中国の経済発展を踏まえた新しい協力の在り方として、最近は中国側が費用を負担する形での協力を進めています。たとえば、2013年に四川省で発生した芦山地震の被災地において、中国側が進める防災教育や防災館の建設において、日本は防災対策の共有や耐震免震技術の指導等の支援をしていますが、その費用は中国側が負担しています。
草の根・人間の安全保障無償資金協力については、少数民族地域等で、エイズ患者や障害者等の社会的弱者支援等を中心に実施しました。
- *ASEAN連結性マスタープラン2025
- 2015年を目標年とする「ASEAN連結性マスタープラン」(2010年採択)の後継文書として、2016年のASEAN首脳会議にて採択された、ASEAN連結性強化のための行動計画。2015年11月採択の「ASEAN2025:共に前進する」の一部と位置付けられている。同文書内は、「持続可能なインフラ」、「デジタル・イノベーション」、「シームレスなロジスティクス」、「制度改革」、「人の流動性」を5大戦略としており、それぞれの戦略の下に重点イニシアティブが提示されている。
- *日ミャンマー協力プログラム
- ミャンマーの開発を考える上で重要な主要9分野で取り組むべき課題を抽出したもので、具体的には、Ⅰ「地方の農業と農村インフラの発展」、Ⅱ「国民が広く享受する教育の充実と産業政策に呼応した雇用創出」、Ⅲ「都市部の製造業集積・産業振興」、Ⅳ「地方と都市を結ぶ運輸インフラ整備」、Ⅴ「産業発展を可能とするエネルギー協力」、Ⅵ「都市開発・都市交通」、Ⅶ「金融制度整備支援(政策金融/民間金融)」、Ⅷ「国民をつなぐツールとしての通信・放送・郵便」、Ⅸ「国民生活に直結する保健医療分野の改善」を柱としている。

モンゴル東部に位置するドルノド県の技術カレッジにて花き栽培と野菜栽培の実技指導を行っている青年海外協力隊の丸岡猛志さん。写真は学生たちにビニールハウスでキュウリの収穫の仕方を指導しているところ。(写真:塚越貴子)
- 注1 : 後発開発途上国 LDCs:Least Developed Countries
- 注2 : ASEAN諸国:ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム。(ただし、シンガポール、ブルネイはODA対象国ではない。)
- 注3 : 「質の高いインフラパートナーシップ」は、①日本の経済協力ツールを総動員した支援量の拡大・迅速化、②アジア開発銀行(ADB)との連携、③国際協力銀行(JBIC)の機能強化等によるリスク・マネーの供給倍増、④「質の高いインフラ投資」の国際的スタンダードとしての定着を内容の柱としている。
- 注4 : アジア開発銀行 ADB:Asian Development Bank
- 注5 : 国際協力銀行 JBIC:Japan Bank for International Cooperation
- 注6 : 日本貿易保険 NEXI:Nippon Export and Investment Insurance
- 注7 : メコン諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム)
- 注8 : 日本とメコン地域諸国が豊かな緑、豊富な生物多様性および自然災害への強靱性を有する「緑あふれるメコン(グリーン・メコン)」を達成しようとする取組。
- 注9 : 経済特別区 SEZ:Special Economic Zone
- 注10 : 円借款は2007年、一般無償資金協力は2006年にそれぞれ新規供与を終了している。
- 注11 : 2015年度までの有償資金協力の累計は33,165億円(約束額)、無償資金協力の累計は1,576億円(約束額)、技術協力は累計1,840億円(JICA支出額)。(ただし、円借款(有償資金協力)および一般無償資金協力は既に新規供与を終了している。)
- 注12 : 技術協力の近年の実績
34.68億円(2010年度)、32.96億円(2011年度)、25.27億円(2012年度)、20.18億円(2013年度)、14.36億円(2014年度)、8.06億円(2015年度) - 注13 : 草の根・人間の安全保障無償資金協力の近年の実績
14.66億円(2010年度)、8.43億円(2011年度)、2.88億円(2012年度)、2.84億円(2013年度)、0.85億円(2014年度)、1.06億円(2015年度)
●フィリピン
ルソン北部における零細稲作農民の営農改善を通じた農業収入向上事業
日本NGO連携無償資金協力(2015年12月~実施中)

ミミズ堆肥づくり研修に参加した約70名の農民(写真:ジーエルエム・インスティチュート)
ルソン島北部はフィリピン屈指の肥沃(ひよく)な農業地帯ですが、歴史的に貧富の差が大きい土地で、多くの零細稲作農民は条件の悪いわずかな土地を耕しており、自らの農地の収入だけでは生計を立てることが難しく、日雇い労働に従事し、常に借金を抱えるなど貧困から抜け出せない状況が続いています。
2015年12月、特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュートは、イザベラ州とヌエバ・ビスカヤ州において、営農改善を通じて、このような状況にある零細稲作農民の生計を向上させるプロジェクトを外務省の日本NGO連携無償資金協力により立ち上げました。
本事業では、零細農民に対して収支計算や営農計画策定方法などの指導を行った上で、稲作や野菜の栽培、有機肥料の生産と使い方、収穫後の作業に関する研修も実施し、農民は収入向上につながる営農技術を習得しています。さらに生産物の販売促進や販路拡大等により収入を増加できるようマーケティングの指導も行っています。
事業開始から約8か月後の2016年8月末の時点で、プロジェクト対象の地域において計25回の研修を実施しました。農業経営研修により、計123名の農民が収支計算や営農計画等の基礎的な知識を習得しました。また、稲作栽培技術研修では、田植えから病害虫防除までの知識を向上させ、有機肥料製造や農業機械の実習研修も行いました。
今後は、本事業の終了後も効果が持続するよう、現地政府関係機関等との連携を深めつつ、各研修に、より実践的な方法を取り入れていきます。また、雨期に農道が水没し農産物の輸送や農作業等ができないという課題に対応するため農道補修研修も実施し、生産活動と市場アクセスの確保、改善を図ります。これら事業活動の成果が有機的に結びつき、零細稲作農民の収入を向上させ、厳しい生活環境から脱することが期待されます。
(2016年8月時点)

フィリピンのラグナ州のサン・ペドロ校高等部で縫製の実技に取り組む生徒たち(写真:ハービィ・タパン/Third Eye Visual)