(4)格差是正(脆弱な立場に置かれやすい人々への支援)
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施に向けた取組が進められる中、大局的に国家レベルで見ると課題がどこにあるのかを特定して的確に対応することが困難であるという問題が顕在化しており、「格差の拡大」はその一つです。また、貧困・紛争・感染症・テロ・災害などの様々な課題から生じる影響は、国や地域、女性や子どもなど、個人個人の置かれた立場によって異なります。こうした状況に対しては、一人ひとりの立場に立った形でのアプローチが有効であり、不可欠といえます。
< 日本の取組 >
●人間の安全保障
このような背景から、日本が重視している理念が「人間の安全保障」です。これは、人間一人ひとりに着目し、人々が恐怖や欠乏から免れ、尊厳を持って生きることができるよう、個人の保護と能力強化を通じて、国・社会づくりを進めるという考え方です。
日本政府は、人間の安全保障の推進のため、①概念の普及と②現場での実践の両面で、様々な取組を実施しています。
①概念の普及について、日本は国際的な有識者委員会である「人間の安全保障委員会」およびその後継となる「人間の安全保障諮問委員会」の設置や、非公式・自由なフォーラムである「人間の安全保障フレンズ」の開催を主導してきました。また、2つの国連決議を主導し、概念の定義を整理することにも尽力しました。2012年9月には、日本が主導して、人間の安全保障の共通理解に関する国連総会決議が全会一致で採択されました。
②現場での実践について、日本は国連における「人間の安全保障基金」の設立(1999年)を主導しました。これまで日本は累計で約451.7億円を拠出し、88の国・地域で、国連機関が実施する人間の安全保障の確保に資するプロジェクト238件を支援してきました(数字はいずれも2016年12月末時点)。2015年2月に閣議決定された新たな開発協力大綱でも、人間の安全保障は、日本の開発協力の根本にある指導理念として位置付けられています。
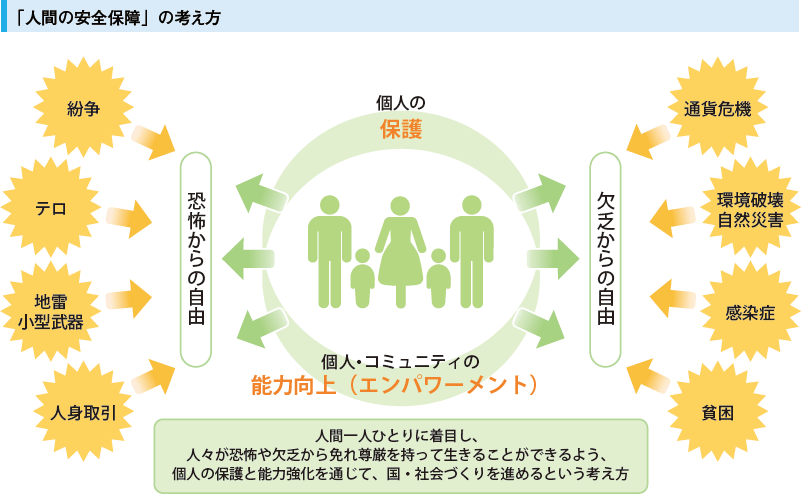
●障害者支援

モンゴル東部のドルノド県ヘルレンソム1番学校に配属され、障害のある子どもたちの指導を行っている青年海外協力隊の澤田明日香さん。図工の授業で子どもたちの発想を活かした制作活動を指導している。(写真:塚越貴子)
若者や女性など、社会において弱い立場にある人々、特に障害のある人たちが、社会に参加し、包容されるように、能力強化とコミュニティづくりを促進していくことも重要です。
日本は開発協力において、ODA政策の立案および実施に当たり、障害のある人を含めた社会的弱者の状況に配慮することとしています。障害者施策は福祉、保健・医療、教育、雇用等の多くの分野にわたっており、日本はこれらの分野で積み重ねてきた技術・経験などをODAやNGOの活動などを通じて開発途上国の障害者施策に役立てています。たとえば、鉄道建設、空港建設においてバリアフリー化を図った設計を行ったり、障害のある人のためのリハビリテーション施設や職業訓練施設整備、移動用ミニバスの供与を行ったりするなど、現地の様々なニーズにきめ細かく対応しています。

ヨルダンの首都アンマンにて、障害者の就労を進める上で重要なバリアフリー環境を整備。日本の支援により、ヨルダン労働省へのスロープの角度や材質、手すりなどを改善した。(写真:朝居八穂子/ JICA専門家)
また、開発途上国の障害者支援に携わる組織や人材の能力向上を図るために、JICAを通じて、開発途上国からの研修員の受入れや、理学・作業療法士やソーシャルワーカーをはじめとした専門家、青年海外協力隊の派遣などの幅広い技術協力も行っているところです。
2014年1月には、日本は障害者権利条約を批准しました。同条約は、独立した条項を設けて、締約国は国際協力およびその促進のための措置をとることとしています(第32条)。日本は、今後もODA等を通じて、開発途上国における障害者の権利の向上に貢献していきます。
●モンゴル
障害児のための教育改善プロジェクト
技術協力プロジェクト(2015年8月~実施中)

ウランバートル市第25特別学校のモンゴル語の授業(写真:大伴潔)
モンゴルでは、心身に障害のある児童の教育に関しては、障害の発見が遅れて必要な支援を受けられなかったり、保護者が安定した職業に就くことができず貧困に陥ったり、障害児の通える学校の数が不十分であるといった問題が存在しています。また、長らく、モンゴルの教員養成課程では、障害児への対応や指導法について専門的な指導がなされてきませんでした。そのため、障害の程度に即した教育を受けることができず、学校に通えない子どもも少なくありません。
これらの課題に対し、モンゴル政府は、障害のある人が障害のない人と等しく、あらゆる機会を得られるよう法制度の整備に努めてきました。さらに、障害のある子どもたちの発達支援、教育改善を図るため、日本政府に対して支援を要請し、2015年に「障害児のための教育改善プロジェクト」が開始されました。
このプロジェクトでは、ウランバートル市および地方都市から選定されるパイロット地域において障害の早期発見・発達支援の体制を整えるために、知的障害を対象とする特別学校4校および通常学校8校をパイロット校として選定し、パイロット校において質の高い教育が提供されるよう教員の能力強化に努め、障害の早期発見・発達支援・教育のモデルを構築することを目指しています。
障害の早期発見・発達支援体制の整備については、担当の機関である「障害児の保健・教育・社会保障委員会」などと協議を行い、障害の発見から発達支援までの流れと関係機関の役割についてマニュアルへのとりまとめを行っています。また、これまでモンゴルで用いられてきたスクリーニングやアセスメントのツールを見直し、今後、必要となるツールを検討しました。現在、日本で用いられている2つのツールについて、モンゴル版を開発中です。
教員の能力強化に関しては、パイロット特別学校4校の教員(約200名)に対し、1年目は月2回、2年目は月1回の頻度で勉強会を開催してきました。勉強会を通じて、個別教育計画のモンゴル版フォーマットを作成し、計画策定の意義についても理解を深めてもらいました。パイロット通常学校8校に対しては、特別学校との連携を促進し、障害のある子どもたちが地域の通常学校で学べる体制を整備するよう努めています。
今後も、子どもたちが個々のニーズに応じた適切な発達支援および教育を得られるよう活動を続けていきます。
2016年5月には、このプロジェクトとは別に「ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト」も開始され、障害者支援の「入口(早期発見)~出口(社会参加)」に至るまでの一貫した協力に取り組むことで、モンゴルにおける共生社会の実現を後押しします。
(2016年8月時点)
