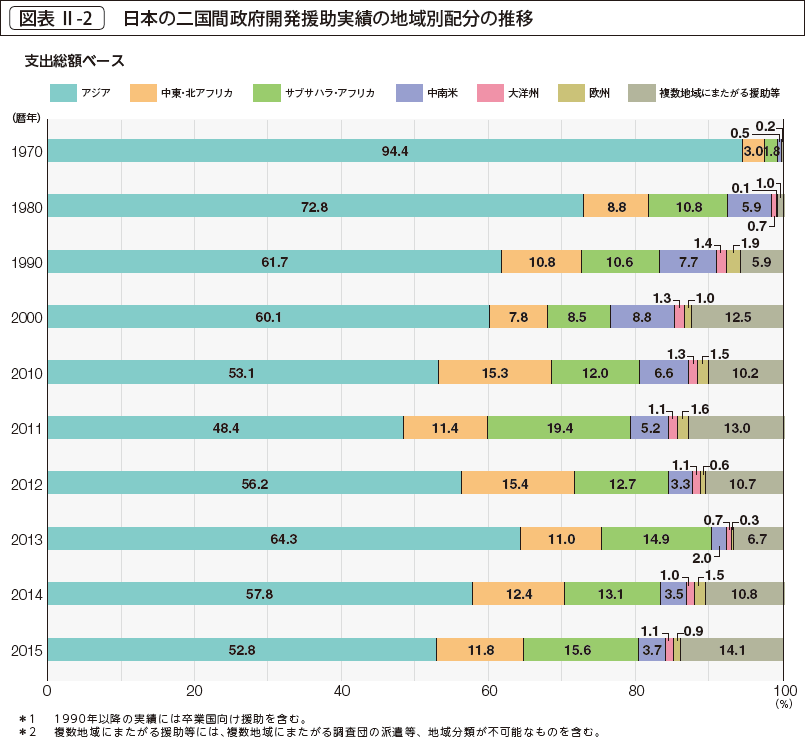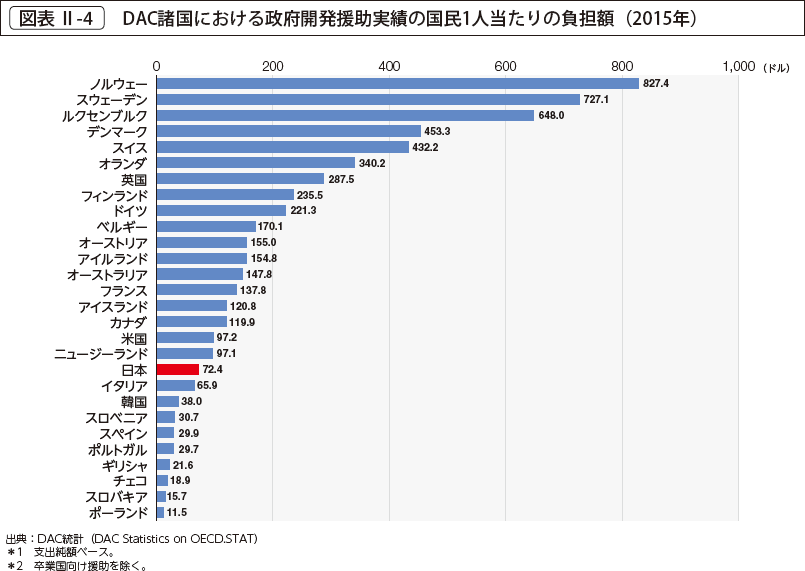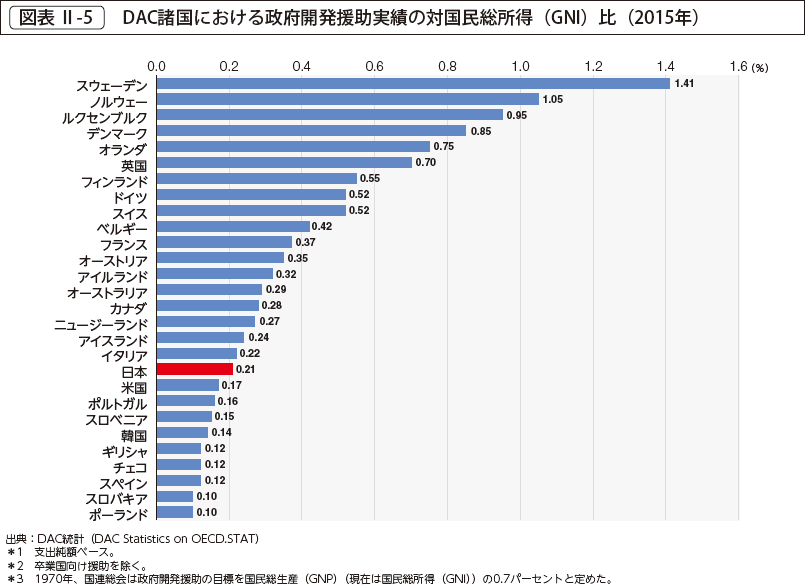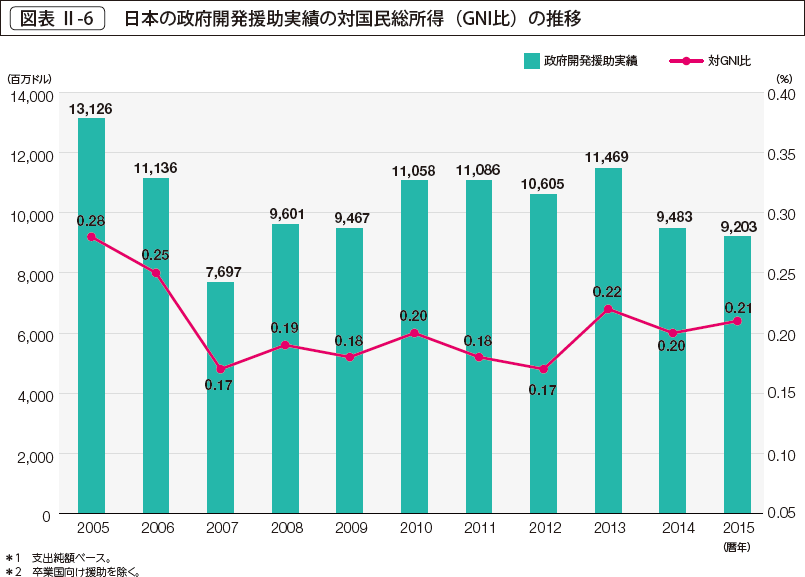第 Ⅱ 部 2016年の開発協力

ラオスの経済開放化、市場開放化の改革に伴い、法整備も急務になっている。ビエンチャンにて日本の法務司法専門家による、教材や執務マニュアルの製作支援が行われており、両国の専門家が活発に意見を出し合い、プロジェクトを進めている。(写真:久野真一/ JICA)
第1章 実績から見た日本の政府開発援助

課題別研修「生活改善アプローチを通じた持続的農村開発」を通じて、エルサルバドルのモラサン県グアロコクティ村の家族が提案したアクションプランを実施し、住居環境が改善したことを生活改善ネットワーク「REDCAM」の活動の受益者がJICAおよびFAO職員に説明している様子(写真:エルネスト・マンサーノ/ JICA)
2015年、日本の政府開発援助(ODA)の支出総額は約150億2,862万ドル(約1兆8,185億円)で世界第4位、政府貸付の回収額を差し引いた支出純額〈注1〉は約92億282万ドル(約1兆1,136億円)で世界第4位の実績でした。〈注2〉
< 実績の分析 >
2015年の日本のODA実績(支出総額ドルベース)は、前年(2014年)に比べ約5.6%減で、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC(ダック))〈注3〉加盟国における順位は、米国、ドイツ、および英国に次いで第4位となりました。また、支出純額ドルベースでも約3.0%減で、順位は、米国、英国、ドイツに次ぎ第4位となりました。
円ベースでのODA実績は、無償資金協力、技術協力、有償資金協力、多国間援助(国際機関への出資・拠出等)のいずれの援助形態においても前年比で増加していますが、為替がドル高円安方向に推移したことにより、ドルベースでのODA実績は支出総額、支出純額のいずれも前年に比べ微減となっています。
2015年ODA実績の内訳は、支出総額では二国間ODAが全体の約79.7%、国際機関に対するODAが約20.3%、支出純額では、二国間ODAが全体の約66.8%、国際機関に対するODAが約33.2%です。二国間ODAは、日本と被援助国との関係強化に貢献することが期待されます。一方、国際機関に対するODAでは、「日本の顔」も見える形で専門的知識や政治的中立性を持った国際機関を支えることを通じて、直接日本政府が行う援助が届きにくい国・地域への支援も可能になります。日本は、これらの支援を柔軟に使い分けるとともに相互の連携を図り、適切に援助が供与されるよう努力しています。
無償資金協力は、開発途上地域の開発を主たる目的として同地域の政府等に対して行われる無償の資金供与による協力です。また、無償資金協力では大きな災害が発生したときなど開発途上国や国際社会のニーズに迅速かつ機動的に対応することができ、国際社会の安定確保や日本のリーダーシップを発揮できる大きな政策的効果があります。技術協力は、日本の知識・技術・経験を活かし、開発途上地域における経済社会開発の担い手となる人材の育成を行う協力で、開発途上国の技術水準の向上、制度や組織の確立や整備などに役立ちます。また、技術協力は“人と人との接触”を通じて実現され、人の往来が基本となる援助形態であるため、両国国民レベルでの相互理解に果たす役割は大きいといえます。有償資金協力(政府貸付)は、資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう、金利、償還期間等について緩やかな条件が付された有償の資金供与による協力です。無償資金協力と比較して、有償資金協力には大規模な支援を行いやすく、開発途上国の経済社会開発に不可欠なインフラ建設等の支援に効果的です
以上の援助手法別に見ると、二国間ODAでは、無償資金協力として計上された実績が約26億2,252万ドル(約3,173億円)で、ODA支出総額の実績全体の約17.5%となっています。うち、国際機関を通じた贈与は、約14億2,285万ドル(約1,722億円)で全体の約9.5%です。技術協力は約23億6,865万ドル(約2,866億円)で、全体の約15.8%を占めています。政府貸付等については、貸付実行額は約69億8,207万ドル(約8,448億円)で、ODAの支出総額全体の約46.5%を占めています。貸付実行額から回収額を差し引いた純額は、約11億5,627万ドル(約1,399億円)となっています。また、債務救済については、2014年に引き続き、2015年も実績はありませんでした。
地域別の二国間ODAは次のとおりです。支出総額(支出純額)の順。
(以下の実績値は、卒業国向け援助を含む。)
◆アジア:約63億3,308万ドル(約16億2,633万ドル)
◆中東・北アフリカ:約14億2,053万ドル(約8億6,376万ドル)
◆サブサハラ・アフリカ:約18億6,698万ドル(約17億8,880万ドル)
◆中南米:約4億3,776万ドル(約-1,672万ドル)
◆大洋州:約1億2,911万ドル(約1億1,162万ドル)
◆欧州:約1億1,178万ドル(約4,812万ドル)
◆複数地域にまたがる援助:約16億9,388万ドル(約16億9,388万ドル)
(マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示します。)
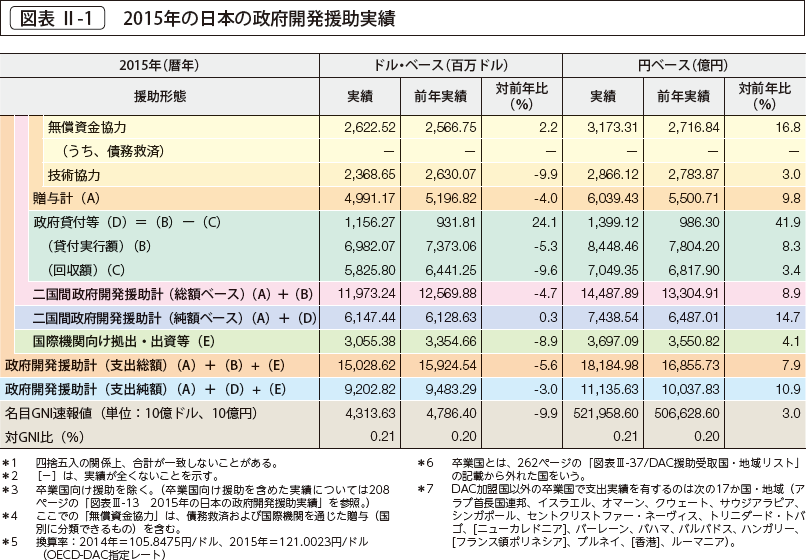
- 注1 : 支出総額(グロス)と支出純額(ネット)の関係は次のとおり。
支出純額=支出総額-回収額(被援助国から援助供与国への貸付の返済額)
援助実績の国際比較においては、通常支出純額が用いられている。 - 注2 : 卒業国向け援助を除く。「卒業国を含む」実績値について、詳しくは図表Ⅲ-13をご覧ください。
- 注3 : 経済協力開発機構(OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development) の開発援助委員会(DAC: Development Assistance Committee)