開発協力トピックス 01
ポスト2015年開発アジェンダと日本の取組
■ ミレニアム開発目標(MDGs)
~2015年までに達成すべき、国際開発目標~
ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)とは、2015年までに国際社会が開発分野において達成すべき共通の目標です。2000年に採択された国連ミレニアム宣言などをもとに策定されました。
MDGsでは、8つのゴールの下に、具体的な21のターゲットと60の指標が設定されています。これらの目標は1990年を基準年とし、2015年が達成期限です。
国際社会は、MDGsを開発分野の羅針盤として、一定の成果を上げてきましたが、母子保健など、達成の見込みの低い目標もあります。また、サハラ以南のアフリカなど、進捗の遅れが目立つ地域もあります。2015年中にMDGsを達成すべく、国際社会におけるより一層の努力が必要です。
■ 2015年より先、未来を見据えて
~ポスト2015年開発アジェンダ~
MDGsの後継の新しい国際開発目標(ポスト2015年開発アジェンダ)策定に向けた議論が、現在国際社会で活発に行われています。
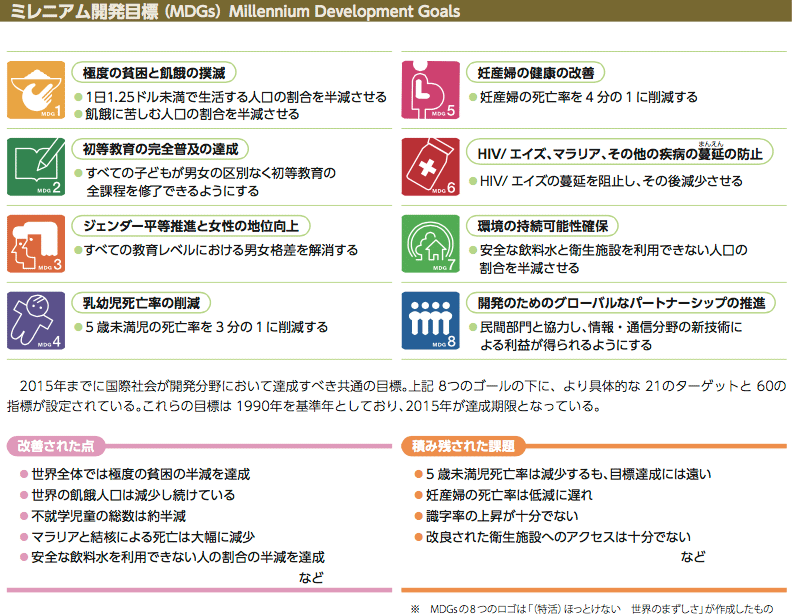
■ ポスト2015年開発アジェンダに関する日本の考え

パキスタンの識字普及員の女性とノンフォーマル小学校に通う子どもたち。一緒に笑顔を見せている大橋知穂さん。大橋さんの識字率向上のための奮闘は、「国際協力の現場から」をご覧ください(写真:大橋知穂)
ポスト2015年開発アジェンダの策定に当たっては、MDGsと同様に、簡素・明快さを保つ必要があります。また、MDGsでの経験と教訓を踏まえる必要があります。MDGs実施の過程で見えてきた地域差・国内差の課題に目を向けて、立場の弱い人々を取り残さないよう、人間の安全保障の理念に基づく新たな枠組みを作る必要があります。また、引き続き貧困撲滅を中心課題として、持続可能な開発にも配慮した目標とすべきです。
こうした観点を踏まえ、日本は、ポスト2015年開発アジェンダの下での開発協力が、「包摂(ほうせつ)性」、「持続可能性」、「強靱(きょうじん)性」の3つのキーワードに基づく人間中心のアプローチによって実施されることを重視しています。「包摂性」とは、誰一人として取り残さないことです。一人ひとりが開発の果実を享受する必要があります。「持続可能性」とは、経済・社会・環境の3つの側面において、持続可能な開発を達成することです。「強靱性」とは、個人やコミュニティの能力強化、インフラ整備を通じて、紛争や災害、経済危機といったリスクに負けない社会づくりです。
また、MDGsを策定してから十数年経ったことを踏まえ、国際社会の変化に対応する必要があります。MDGsで達成が遅れている保健などの分野の課題や指標を改善することが重要です。また、人口の半分を構成する女性も重要な開発の担い手として、女性のエンパワーメントとジェンダー平等を引き続き進める必要があります。さらに、MDGsには含まれていない防災等の課題にも対処する必要があります。
加えて、近年、先進国から途上国への資金フローとして、民間資金はODAの総額の2.5倍を占めます。政府間の協力のみならず、民間セクターの関与が必須です。また、様々な社会階層に雇用を創出して包摂的な成長を達成し、成長の果実を広く共有することが重要です。さらに、開発効果の向上を図るため、途上国自らがガバナンスを強化し、主体的に解決に取り組む努力も必要です。途上国内の資源の動員も重要です。日本の行っている法制度整備支援等は、ガバナンス強化に寄与するものです。
保健分野では、日本は、ポスト2015年開発アジェンダ策定に向けて、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の重要性を訴えています。2013年12月には、日世銀共同UHCハイレベル会合を東京で開催、麻生財務大臣、キム世銀総裁やチャンWHO事務局長のほか、各国から閣僚や専門家が集まり、日本を含む9か国のUHCに関する経験を共有しました。また、2014年9月に開催されたイベント「UHCの実現に向けて:なぜ今なのか」には岸田外務大臣が出席し、我が国のUHC推進に向けた様々な取組を紹介するとともに、UHC達成に向けてグローバルリーダーたちが連携して行動することの重要性を訴えました。参加者からは、UHC推進について日本のリーダーシップに対する高い評価が表明されました。
■ 策定に向けた動きと日本の取組
まだポスト2015年開発アジェンダに関する議論が本格的に始まる前の2011年12月、日本は様々な立場の国、国際機関、市民社会等がポスト2015年開発アジェンダについて意見交換を行うコンタクト・グループを立ち上げ、世界の議論をリードしました。立場にとらわれない自由な議論ができる場所として、高く評価されています。
その後2012年7月には、潘基文・国連事務総長が27名から成るハイレベル・パネルを立ち上げ、ポスト2015年開発アジェンダに関する議論が行われました。この議論には日本も参加し、2013年5月にその報告書が提出されました。また、2012年6月に開催された国連持続可能な開発会議(リオ+20)において、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)を策定し、それをポスト2015年開発アジェンダに統合することが決定されました。2013年3月にSDGsを検討するためのオープン・ワーキング・グループ(SDGs OWG)が、2013年8月に持続可能な開発に必要な資金を議論するためのファイナンス委員会がそれぞれ立ち上がり、日本も交渉に参加して、上記の日本の考えを反映させるよう努めました。SDGs OWGとファイナンス委員会は、2014年夏までにそれぞれ国連総会に報告書を出しました。これらの報告書も踏まえ、2015年にポスト2015年開発アジェンダを決定するための交渉が国連加盟国間で行われ、2015年9月の国連首脳会合で採択され、2016年から新しい目標の期間が始まる予定です。
