(3)食料・栄養
国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、および国連世界食糧計画(WFP)共同の報告「世界の食料不安と現状2014年報告(SOFI2014)(注15)」によると、世界の栄養不足人口は過去10年間で1億人以上、1990~92年以降では2億人以上減少しているという良好な傾向が確認されたものの、依然として約8億500万人(2012年~2014年、推計値)が慢性的な栄養不足に苦しんでいるとされています。
この報告書によれば、「適切かつ即時に対応が図られるならば」、2015年までに飢餓人口の割合を半減するというミレニアム開発目標(MDGs)は達成が可能な範囲であると示唆されています。また、社会的セーフティー・ネット(人々が安全で安心して暮らせる仕組み)の確立や栄養状態の改善、必要な食料支援や家畜の感染症への対策など、食料安全保障(すべての人が十分な食料を得る権利を持つことへの保障)を確立するための国際的な協調や多面的な施策が求められています。
さらに、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの1000日間における栄養改善は特に効果的であるため、そのための取組が進められています。
< 日本の取組 >

ケニアの首都ナイロビから北西に約70km離れた地方都市ナイバシャで、コミュニティ開発に携わる青年海外協力隊(村落開発普及員)の荒殿美香さんが野菜スーパーと連携してクッキング・デモンストレーションと試食会を開催した(写真:荒殿美香)
このような状況を踏まえ、日本は、食料不足に直面している開発途上国からの要請に基づき食糧支援を行っています。2013年度には、二国間食料支援として11か国に対し総額50.1億円の支援を行いました。
国際機関を通じた支援では、主にWFPを通じて、緊急食料支援、教育の機会を促進する学校給食プログラム、食料配布により農地や社会インフラ整備などへの参加を促し、地域社会の自立をサポートする食料支援などを実施しています。2013年には世界各地で実施しているWFPの事業に総額2億3,843万ドルを拠出しました。
また、15の農業研究機関から成る国際農業研究協議グループ(CGIAR)が行う品種開発等の研究にも支援を行うとともに、研究者間の交流を通じ連携を進めています。
また日本は、開発途上国が自らの食料の安全性を強化するための支援を行っています。口蹄疫(こうていえき)などの国境を越えて感染が拡大する動物の伝染病について、越境性感染症の防疫のための世界的枠組み(GF-TADs)など国際獣疫事務局(OIE)やFAOと連携しながら、アジア・太平洋地域における対策を強化しています。さらに、日本は国際的に栄養不良改善への取組を主導しているScaling Up Nutrition(SUN)ムーブメントに深く関与し、支援の強化を表明しました。
- 注15 : The State of Food Insecurity in the World 2014
●タイ
次世代の食料安全保障のための養殖技術研究開発
科学技術協力(SATREPS)(2012年5月~実施中)

人工授精のためのアカマダラハタの親魚の採卵(写真:クラビー沿岸漁業研究開発センター)
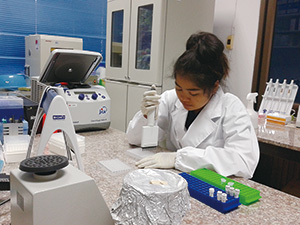
沿岸養殖研究機関での診断(写真:JST派遣研究員久保田諭)
世界の水産物生産は,漁業生産が頭打ちとなる中、養殖生産の割合が4割を超えており、養殖生産の増加が世界で伸び続ける水産物消費を支えています。東南アジアは世界の養殖生産量の約3割を占める世界的な養殖生産地域であり、タイはその中心的な役割を果たしています。
東南アジアの養殖業が持続的に発展するためには、ハタ、スズキ、クルマエビなど市場で人気の高い魚種の養殖技術の開発が不可欠です。一方、これらの技術開発への投資は、行政および民間の負担が大きい上に、高度な科学技術に関する知見も必要であることからなかなか進んでいません。
そこで日本は、東南アジアの養殖生産の中心であるタイにおいて、市場価値が高く、持続的かつ高品質な魚介類の養殖技術の開発を目的とした技術協力を行っています。具体的には、魚介類の感染症予防、分子遺伝学的情報を活かした新しい品種の開発、親とは異なる魚を生ませる「借り腹」養殖技術の確立、新しい餌の開発、水産物の安全性確保などが挙げられます。
このプロジェクトの研究成果として、東南アジアで深刻な被害を出しているエビの大量死の原因となる病原細菌の感染の有無を100%の精度で判別できる検査方法を確立しました。この検査技術が普及すれば、感染の早期発見と対策が可能となり、落ち込んでいる世界のエビ生産量の回復が見込まれるなど、世界のエビ養殖への大きな貢献が期待されます。(2014年8月時点)
