ベトナム「国別援助計画」改定に向けて
(資料4)
大野健一
2002年9月13日報告
-
1.問題提起
-
●現在の国別援助計画(2000年6月版)は、前半の概説部分と後半の5重点分野((1)市場経済化支援、(2)インフラ、(3)農業・農村開発、(4)教育・保健・医療、(5)環境)の提示からなるが、それをつなぐ分析がない。ゆえに外交・開発に関する戦略性が希薄である。●日本はベトナムのトップドナーであるにもかかわらず、(1)現地体制(大使館・JICA・JBIC)が十分に統合されていない、(2)政策決定における現地と東京の連携が必ずしも緊密でない、(3)世銀主導のパートナーシップにおいて援助供与額にふさわしい知的貢献ができていない、といった問題がみられる。
-
2.ベトナムの現状
(a)途上国ベトナムの特徴(他国と比較して)
-
●最貧国。民間部門が弱く、市場の未発達、現地企業の脆弱、国際競争の無理解などが一般的。ただし他最貧国と比べ社会的指標は優れている。1990年比貧困半減もすでに達成。●自由化と対外開放により過去10年間の成長率は高い。ODA・直接投資・越僑送金の流入で経済は活性化している。都市を中心に急激な社会変化が進行中。●トップダウンではなくコンセンサス型政治。政府は安定的で、主体性をもってドナーに接し、成長と公正を柱とする国家戦略をもつ。所得格差・少数民族などの問題に敏感。●経済政策の権限が縦横に分散されすぎており、政策の整合性・機動性に欠ける。一般方針を具体的行動に移すのが苦手。
-
(b)主要開発課題
ベトナムは2020年の「工業化・近代化」を国家目標とし、「五カ年計画」「十ヵ年戦略」からなる国家開発戦略をもち、成長と社会的公正をバランスを保って追求しようとしている。
-
(1)成長 ―― 国際統合・貿易自由化を推進しながら、直接投資導入などを通じて自国産業力を育成し、国際分業体制に意味のある参加を行い、高成長・雇用確保を実現する。 (2)社会的公正 ―― 最貧国として社会セクター問題に取り組む(貧困・環境・保健・教育他)。これには旧来の問題に加え、成長が生む新問題や成長果実の公平な分配も含む。
日本政府とベトナム政府は様々な機会を通じ、この2課題がともに重要であり、わが国の経済協力はそれを支援するものであることにつき合意・確認ずみ。またUNDP、EU、独、仏などもベトナム政府の開発戦略に理解を示している。
-
(c)パートナーシップ
-
●わが国とベトナム政府との二国間関係は、(1)トップドナーとしての量的貢献、(2)開発政策の方向性の一致、の2つの意味で良好である。●世界銀行の貧困削減政策(世界共通のCDF・PRSP)の推移と問題点>ベトナムは東アジア初のCDFパイロット国(1999年)となり、「貧困削減戦略書」(PRSP)を完成(2002年5月)。>世銀でなく越側がオーナーシップ(主導権)をもってPRSPを作成、また越側の要求で「包括的な貧困削減・成長戦略」(CPRGS)と改名された。>越政府は、(1)貧困対策のみの偏重は望ましくない、(2)PRSPは予算を縛る最高文書ではない、の点で、これらを主張する世銀・英・北欧等と対立を残す。●わが国はCDF・PRSP過程に一定の貢献をしてきたものの、トップドナーにふさわしい知的指導力は発揮できておらず、むしろ受動的であった。この原因は、(1)現地要員不足、(2)東京・現地双方における世銀政策対応方針が明確でなかった、の2点に求められる。
-
3.ベトナム「国別援助計画」改定への提言
(a)改定方法について
-
●国別援助計画の改定作業を通じ、現地(大使館・JICA・JBIC)を中心として、途上国政府・他ドナー・東京間の政策連携を強化しうる継続的体制を構築することが最も重要。●現地主導主義で行う。●以上を実現するために、開発戦略チームの創設を提言する。
これまでJICAベースで実施されてきた市場経済化支援や国別援助研究会のようなユニットを強化・常設化し、従来の調査研究に加えて、現地大使館等と連携しながら以下の3機能を継続的にもたせる。
(1)途上国政府との政策対話・提言(政策インパクト・人脈育成を重視)(2)他援助国・国際機関との協力(3)わが国の援助関連組織(省庁・実施機関・NPO・民間等)との情報交換・政策議論
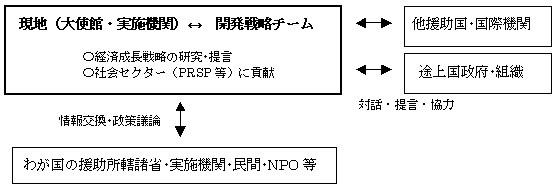
-
注)以上に向けての準備的努力として、現在ベトナムでは、JICA「貿易産業政策共同研究」(経済成長戦略について提言)と「成長戦略支援のマルチ化」(越政府との対話チャネルを他ドナーと共有)が進行中。
●国別援助計画の最終執筆責任者は政府とするが、実質的改定作業の大部分は開発戦略チームに依存することになる。両者の連携方法・作業分担を詰める必要あり。●当面の改定作業期間は1年とする。後続の模範となる方法・中身をもった文書を作成するにはある程度の時間がかかる(基礎調査が不十分な国においてはさらに長い期間が必要であろう)。ただし、中間成果を随時公表していくことは可能である。●ドラフト責任者(政策戦略チーム)は、作業の専門性に鑑み、必要な知見・技能をもつ人材から構成する。学者・ビジネス・NGO・官界などその出身は問わないが、出身分野のバランスをとるのではなく、あくまで専門性を基準に選択する。●ドラフトは広く国民一般やさらに多くの専門家に提示し、その意見を最終稿作成へのインプットとする。●他方で、ドラフトが各方面からコメントを受け、また現地→本省→政府とあがっていく過程で、総花化・省益化されない制度的工夫が必要である。●国別援助計画は毎年修正するとともに、5年ごと(あるいは大きな情勢変化があった際)に大きな改定を行う。
- (b)国別援助計画と実施機関方針の関係のイメージ
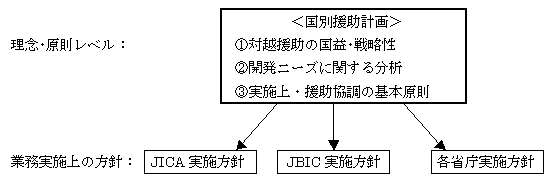
-
●国別援助計画の具体的な章構成は作成過程で検討する。ただし上の3点(援助目的・開発分析・実施原則)が含まれていなくてはならない。●JICA・JBIC・各省庁のそれぞれが実施する援助が、国別援助計画と整合的であり、また相互にも整合的であることを保証すること。
-
(c)改定のためのスケジュール(案)
-
2002年9月 : 大まかな策定方針決定
それをうけて現地体制構築・専門家チーム結成開始、準備作業に着手2002年12月 : CGにて、CPRGS貢献の一環としての国別援助計画の改定意図・概略を報告 2003年3月 : 国別援助計画ショートドラフト(叩き台)提示、内外から意見聴取開始 2003年9月 : ファイナルドラフト完成
注)速度より質・過程形成を重視すべき。方針決定・体制構築上の遅れなどがあれば、要調整。
-
(d)国別援助計画改定過程において議論されるべきテーマ(これに限定されるわけではない)
-
(1)援助目的 ―― わが国にとっての対越援助の国益と戦略性 > 対越援助の重視度を援助額増減方針に関する文章としてシグナル化することの可否 > 検討内容の一部は公開できない可能性あり (2)開発分析 ―― ベトナム経済社会の特徴および直面する国際環境に関する分析 > 一般論ではない、ベトナムに対する個別的・専門的知識を動員する > 既存の内外研究(わが国の研究を含む)を参照し、必要に応じ追加研究を企画・実施 (3)実施原則1 ―― 日本の対越支援体制 > 原則・重点分野・実施方針・個別案件の間の関係と整合性のつけかた > 東京・現地、および現地の大使館・JICA・JBICの連携・分担 > 現在ばらばらに行われている各省庁援助(対越技術協力については約半分を占める)の実態を把握し、透明性・説明責任を付与し、国別援助計画のもとに統合すべきこと (4)実施原則2 ―― ベトナム支援パートナーシップにおけるわが国の貢献・役割 > 国際開発潮流、国際機関・他ドナーの多様な見解、日本の比較優位などを念頭に、全体の中で日本は何をどう支援するか > CPRGS対処方針(たとえば成長を重点支援、社会セクターも支援、援助協調はケースバイケースで、等)
-
(e)ODA総合戦略会議の役割(案)
-
●国別援助計画策定の基本方針(改定手順、検討すべき内容など)を決定する。●国別援助計画策定の背景となるべき、援助目的に関わる基本問題を考察する。たとえば重点国選定基準、国際機関対応方針(MDG・PRSP・援助協調など)、成長支援と貧困削減の組み合わせ方、対アフリカ援助のあり方、「経済協力二分論」(私案)など。●国別援助計画作成の進行状況につき随時報告をうけ、必要に応じて議論・指示する。

