バングラデシュの竜巻災害で
バングラデシュの竜巻災害で使命感で集まった緊急医療チーム
被災者が目の前にいて、助けを求めている。そんな時、迅速で柔軟な救助の手をさしのべるのが国際緊急援助隊の使命である。
1996年5月13日夕刻、まさに日本の国際緊急援助隊の真価が問われる大災害が起こった。バングラデシュのタンガイル、ジャマルプール両県一帯を、猛烈な竜巻が襲ったのである。
死者500人以上、負傷者3万 4千人以上、損壊家屋3万軒以上。竜巻はたった20分ほどの間に、数百の村々を襲い、木々をなぎ倒し、木造家屋はもちろん、コンクリートの建物さえも瓦礫に変えてしまった。あたり一面がまるで爆撃にでも遭ったような有様となった。
バングラデシュ政府から日本政府に、国際緊急援助隊の出動要請があったのは5月16日のこと。日本政府の対応は早かった。医療チームの派遣、テント、毛布、ポリタンクなどの緊急援助物資の供与、20万ドルの緊急無償資金協力を即決したのである。
1996年5月13日夕刻、まさに日本の国際緊急援助隊の真価が問われる大災害が起こった。バングラデシュのタンガイル、ジャマルプール両県一帯を、猛烈な竜巻が襲ったのである。
死者500人以上、負傷者3万 4千人以上、損壊家屋3万軒以上。竜巻はたった20分ほどの間に、数百の村々を襲い、木々をなぎ倒し、木造家屋はもちろん、コンクリートの建物さえも瓦礫に変えてしまった。あたり一面がまるで爆撃にでも遭ったような有様となった。
バングラデシュ政府から日本政府に、国際緊急援助隊の出動要請があったのは5月16日のこと。日本政府の対応は早かった。医療チームの派遣、テント、毛布、ポリタンクなどの緊急援助物資の供与、20万ドルの緊急無償資金協力を即決したのである。
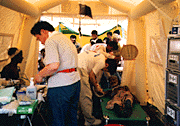
仮設テントで次々と訪れる被災者の手当をする緊急援助隊員 |
医療チームは団長 1人、医師4人、看護婦(士)7人、医療調整員4人の総勢16名。第一陣が首都ダッカ入りしたのは翌17日。18日にはすべての隊員が現地入りしている。
ところで、日本の国際緊急援助隊体制が整備されたのは「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」が制定された1987年。現在では、救助チーム(救出・救助活動)、医療チーム(医療・防疫活動)、専門家チーム(災害応急・復旧対策の助言)の3チームのほか、自衛隊の部隊(医療、浄水・給水、輸送活動)が出動に備え常時待機している。
この中で医療チームの隊員は、JICAに登録されている約500人のボランティアの中から選抜されるが、民間からの献身的な参加者が多いのが特徴だ。今回、バングラデシュに向かった医療チ ームのメンバーは、「明日の午前中に出発できますか」という呼びかけに、即断即決で参加を決め、成田空港に駆けつけたのだった。
ところで、日本の国際緊急援助隊体制が整備されたのは「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」が制定された1987年。現在では、救助チーム(救出・救助活動)、医療チーム(医療・防疫活動)、専門家チーム(災害応急・復旧対策の助言)の3チームのほか、自衛隊の部隊(医療、浄水・給水、輸送活動)が出動に備え常時待機している。
この中で医療チームの隊員は、JICAに登録されている約500人のボランティアの中から選抜されるが、民間からの献身的な参加者が多いのが特徴だ。今回、バングラデシュに向かった医療チ ームのメンバーは、「明日の午前中に出発できますか」という呼びかけに、即断即決で参加を決め、成田空港に駆けつけたのだった。
猛暑の中の医療活動
さて日本の医療チームの拠点となったのは、被災地近くのタンガイル総合病院。ここに日本から携行した医療用仮設テントを2基設営、臨時の診療所として本格的な診療活動に入った。
負傷者のほとんどは、鋭利な刃物で深く切りつけられたように傷口がぱっくり開いていた。竜巻で舞い上がったトタン屋根が、人間めがけて襲ってきたというのである。
日本の医療チームが到着する前、バングラデシュ政府も軍の6つの医療チームを現地に派遣したが、負傷者の数が甚大な上に、照明も消毒液も足りない。止血処置で手一杯だった。患者の中には止血のために傷口を縫合してあるだけで、消毒不足から傷口が化膿・腐敗しかけている者も多かった。放置すればまちがいなく壊疽(えそ)にかかる。手遅れになれば患部切断か死に至る恐ろしい外傷だ。
日本の医療チームは、そうした患者たちを抱えて、連日、40度を超す猛暑の中、懸命に医療活動を続けた。そのお陰で一命を取り止めることができた患者は数え切れない。
負傷者のほとんどは、鋭利な刃物で深く切りつけられたように傷口がぱっくり開いていた。竜巻で舞い上がったトタン屋根が、人間めがけて襲ってきたというのである。
日本の医療チームが到着する前、バングラデシュ政府も軍の6つの医療チームを現地に派遣したが、負傷者の数が甚大な上に、照明も消毒液も足りない。止血処置で手一杯だった。患者の中には止血のために傷口を縫合してあるだけで、消毒不足から傷口が化膿・腐敗しかけている者も多かった。放置すればまちがいなく壊疽(えそ)にかかる。手遅れになれば患部切断か死に至る恐ろしい外傷だ。
日本の医療チームは、そうした患者たちを抱えて、連日、40度を超す猛暑の中、懸命に医療活動を続けた。そのお陰で一命を取り止めることができた患者は数え切れない。
番外の救助活動劇
日本の医療チームが10日間にわたって診療した患者数は、重症患者216人の手術を含め、合計で過去最高の955人にのぼった。
日本の医療チームは、地元住民から「患者に対して公平、迅速、丁寧」との評価を受け、チームのメンバーの中には、付近の住民から食卓に招かれる者もあったほどである。
たまたま付近の道路で子供が交通事故に遭い、緊急援助隊のスタッフが応急処置を施して一命を取り止めるという“番外の救助活動”もあった。地元住民との信頼関係がさらに深まったことは言うまでもない。
5月27日、日本の医療チームの現地撤収に当たって、タンガイル総合病院が感謝式を開いてくれた。隊員一人ひとりに花束が贈られ、席上、ラシット院長は「ありがとう。皆さんのお陰で助かった。私たちは皆さんのことを生涯忘れない」と述べた。
緊急援助隊の活動期間は短かかったが、こうした人と人との真剣なふれあいは、日本の「目に見える協力」の大きな成果と言えるだろう。
日本の医療チームは、地元住民から「患者に対して公平、迅速、丁寧」との評価を受け、チームのメンバーの中には、付近の住民から食卓に招かれる者もあったほどである。
たまたま付近の道路で子供が交通事故に遭い、緊急援助隊のスタッフが応急処置を施して一命を取り止めるという“番外の救助活動”もあった。地元住民との信頼関係がさらに深まったことは言うまでもない。
5月27日、日本の医療チームの現地撤収に当たって、タンガイル総合病院が感謝式を開いてくれた。隊員一人ひとりに花束が贈られ、席上、ラシット院長は「ありがとう。皆さんのお陰で助かった。私たちは皆さんのことを生涯忘れない」と述べた。
緊急援助隊の活動期間は短かかったが、こうした人と人との真剣なふれあいは、日本の「目に見える協力」の大きな成果と言えるだろう。

