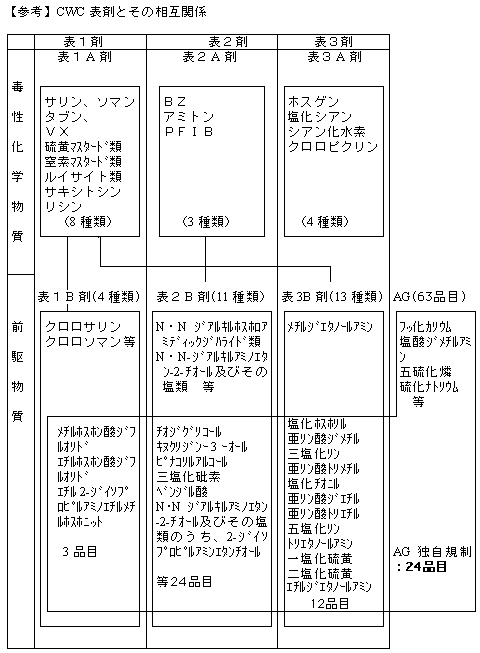軍縮・不拡散・原子力の平和的利用
化学兵器の拡散防止
(化学兵器禁止条約(CWC)とオーストラリア・グループ(AG))
平成25年8月
(はじめに)
- CWCとAGは、化学兵器の国際的規制を行うための仕組みである。しかし、詳しく見ると、両者の目的、性格、参加国は異なっており、また、夫々の輸出管理の対象も同一ではない。
- 一言で言えば、CWCが、化学兵器の完成品に近い部分(毒性化学物質そのもの)を規制しようとしているのに対し、AGは、その前段階の中間生産物(前駆物質。即ち、毒性化学物質の生産のいずれかの段階で関与する化学反応体)、それらの生産に資する設備・技術をも規制の対象とする(より上位の規制)。
- CWCには全世界の全ての国が参加しているわけではなく、また締約国により100%遵守されていない可能性もある。AGはこのような認識に立ち、CWCを補完する追加的努力を行う場であると言える。
以下に、CWCとAGにおいて、化学兵器拡散防止のための仕組みがどのようになっているかを比較考察し、その共通点と相違点を明らかにすることとしたい。
1 化学兵器の拡散防止にかかる国際社会の取組
- 化学兵器(CW)は、安価かつ比較的容易に生産が可能。他の大量破壊兵器と違い、これまでにも実戦で頻繁に使用されていることから、使用に際しての心理的敷居も低いとされる。
- CW拡散防止に対する国際社会の取組としては、1925年のジュネーブ議定書が戦争におけるCWの使用を禁止。しかし、当時はその生産、開発、保有等に関する規制は設けられなかった。また、締約国の多くが、非締約国に対する使用や報復使用の権利を留保していたため、第二次世界大戦後に至っても大量のCWが貯蔵される状況が続いた。
- 80年代に入り、イラン・イラク戦争(80~88年)においてCW(マスタードガス及びタブン)の使用が確認された。これを契機に、オーストラリアが主要先進国間での化学兵器関連物資に関する輸出管理協調の実施を呼びかけ、85年にオーストラリア・グループ(AG)が設立された。湾岸戦争後の93年には、CWの全面的禁止及び既存のCWの全廃を定める多数国間の条約として化学兵器禁止条約(CWC)が作成された。97年、CWCの発効に伴い、CWCの実施状況を検証することを主な任務とする化学兵器禁止機関(OPCW)がハーグに設立された。
- 当初、AGはCWC成立までの暫定的措置との位置づけであった。CWC交渉において、一部途上国よりAG参加国による輸出規制が産業発展を阻害するとの懸念が表明された際には、AGはジュネーブ軍縮会議において「CWCの実施状況に照らし、CWCを完全に遵守している締約国に対してはAG規制を撤廃する方向で見直す」旨のステートメントを発出した。しかし、AG参加国は、CWC成立後も、ア AGはCWCのような普遍的条約を補完し、CW不拡散をより効果的なものとしていく上で重要な要素である、イ CWの調達・開発の試みが複雑・巧妙になってきている現状に鑑み、輸出管理に関するノウハウ、経験を有する国からなるAGは有効なレジームであるとの認識の下、その存続の必要性を確認している。
2 CWCとAGの概要
(1)CWC
- 現在189か国が締結している国際協定。
- 締約国に化学兵器(CW)の開発、生産、取得、保有、移譲(移転)、使用を禁止すると共に、他の者によるCWの開発・生産に援助を与えることを禁止。
- CWを一定期間内に全廃
- 各締約国がCWC上の義務を遵守していることを確認するために、化学兵器禁止機関(OPCW)による検証措置を適用。その概要は以下の通り。
- CWC締約国はOPCWに対し、CWCリストに定められている化学物質の生産量、輸出・輸入量等の情報を提供(申告)。OPCWは現地査察を通じ申告された情報を確認。化学物質がCWCによって禁止されている活動のために転用されていないこと等を検証する。
- 条約違反の疑いに対するチャレンジ査察の制度を有する。
- 検証措置の対象となる毒性化学物質及び前駆物質を表の1~3に区分(表剤と呼ばれる)。右区分は、それら物質が化学兵器として生産される危険性の高さ及びその民生用途としての使用の度合いとを考慮して決定されている。この区分に応じ、検証措置が実施される際の厳格さにも差が表れる。
- 表剤の概要は以下の通り。
- 表1剤:サリンガス、マスタードガス、タブン、VX等、12種類。
-
- A剤:化学兵器として開発、生産、貯蔵、使用されたことのある化学物質
B剤:その前駆物質。 - 民生用途ほとんどなし。
- A剤:化学兵器として開発、生産、貯蔵、使用されたことのある化学物質
- 表2剤:アミトン、BZ等、14種類。
-
- A剤:表1剤の主要原材料及び毒性が高く、今後化学兵器として使用可能な化学物質
B剤:その前駆物質。 - 民生用途小。
- A剤:表1剤の主要原材料及び毒性が高く、今後化学兵器として使用可能な化学物質
- 表3剤:ホスゲン、シアン化水素等、17種類。
-
- A剤:化学兵器目的としても使用可能な民生用化学物質
B剤:その前駆物質。 - 民生用途大。
- A剤:化学兵器目的としても使用可能な民生用化学物質
- 条約で禁止されていない目的のための表剤の移転制限は以下の通り。
- 表1剤:
-
- 非締約国への移転禁止。
- 締約国間では、特定の目的(研究、医療、製薬、防護)及び数量制限の下に移転が許可。
- 移転する際には30日前までに輸出締約国と輸入締約国が当該移転につき化学兵器禁止機関(OPCW)に通報。
- 第三国への再輸出は禁止。
- 表2剤:
-
- 非締約国への移転禁止(若干の例外あり)。
- 表3剤:
-
- 非締約国への移転の際には非締約国に対して最終用途証明書(再移転しないことについても記載)の提出を要請。
(2)AG
- 40か国が参加。一種の紳士協定に基づく枠組であり、法的拘束力は有さない。
- 参加国は、生物・化学兵器関連汎用品・技術に関して合意されたリストの品目について輸出管理を実施。特定の対象国・地域に的を絞ることなく全地域が対象とされる。輸出管理の実施は国内法令(我が国においては、外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令等。)に基づく参加国の主権行為(national discretion)とされる。
- 規制対象は(1)化学・生物剤、(2)関連設備(貯蔵タンク、攪拌機等)及び(1)、(2)の関連技術。化学剤に関してはCWC表の前駆物質に加え、独自に定めた前駆物質(24品目)を規制。
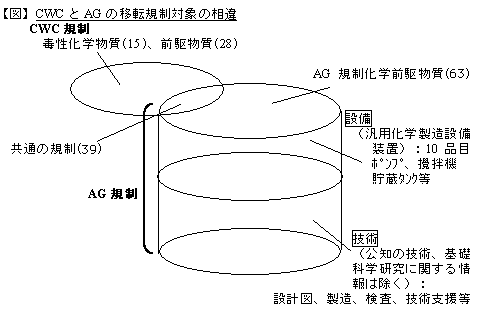
(3)我が国の化学兵器関連輸出管理
CWC表1A、2A、3A剤はAGの枠内での輸出管理の対象となっていない。一方、CWCは締約国間の移転は認めている。我が国では、CWC規制化学物質及びAG独自規制化学物質の輸出管理につき以下のような措置を取っている。
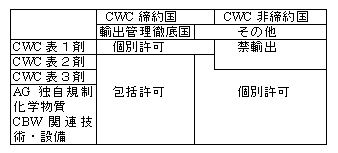
- (注)輸出管理徹底国(いわゆるホワイト国)
「輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域」であり、具体的には、
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国。 - (注)包括許可と個別許可
- 包括許可:特定の貨物を特定の仕向国(輸出管理徹底国)に輸出する場合、1回の許可で3年間有効となる制度。
- 個別許可:売買契約毎に輸出許可申請を行う制度。
3 比較
| 化学兵器禁止条約(CWC) | オーストラリア・グループ(AG) | |
|---|---|---|
| (1)目的 | 化学兵器(CW)の開発、生産、取得、保有、移譲、使用の禁止を通じ、究極的にCWの廃絶を目指す。 | CW(及びBW)の原材料や製造設備の輸出規制を行うことにより、CBWの拡散を食い止めることを目的とする。 |
| (2)参加国 | 189か国(2013年8月現在) | 40か国 |
| (3)移転制限の対象 | 化学剤(毒性化学物質及び前駆物質) |
|
| AG規制対象の化学剤は原則としてCW製造の目的で実際に取得が試みられた前駆物質をリストアップしている。このため、広く工業生産されているものも含まれ、必ずしも条約の下で行われる監視の対象に適しているとは言えない。また、CW製造に使用可能な前駆物質としてCWC表剤に掲載されたものでも、実際に取得の可能性の低いものについてはAGの品目リストからは外されている。 | ||
| (4)移転規制対象品目リストの性格 | 国際的監視が目的 (条約上規定された検証措置の対象となる物質を列挙) |
輸出規制が目的 (懸念国による原材料等入手を困難にする。状況に応じ新たに規制すべき剤が追加される) |
| (5)移転規制の態様 | 一定の要件(前記2(1)参照)の下で移転が可能。 (注)CWCにおいては、ア 申告・査察につき、敷居値が設けられていることから、一定の生産量以下の場合には、申告・査察の対象から外れる、イ 通常、査察の対象は申告を行った施設のみであり、申告漏れをキャッチすることは実質的に困難。締約国の申立てによる抜き打ち査察(チャレンジ査察)はまだ発動されたことがない。ウ 輸出管理体制が整っていない国でも条約締結は可能、といった問題点がある。 |
|
| (6)移転規制品目の見直し、追加 | 執行理事会の勧告に対し、いずれの締約国からも異議がない場合には修正可能。異議がある場合には、締約国会議の3分の2以上の多数による議決で修正可能。但し、今まで修正されたことはない。 | 参加国の合意を得れば規制品目の追加が可能。 毎年の総会で規制品目の見直しが行われ、実際に追加されてきている。 |
| (7)制裁 | CWC第12条が制裁につき定める。(注) | ガイドラインの趣旨に則り、各参加国が責任を持って輸出管理を行うことが要求されている。右を実行しなかった場合でもレジームの性格上強制的措置は取り得ない。 |
- (注)CWC第12条
- 条約遵守状況につき、執行理事会が是正を求め、改められない時は、締約国会議が当該締約国の本条約に基づく権利や特権を制限又は停止できる。
- 重大な違反の場合は、締約国会議は国際法に適合する集団的な措置を勧告できる。
- 締約国会議は、特に重大な場合には、国連総会及び国連安保理の注意を喚起する。
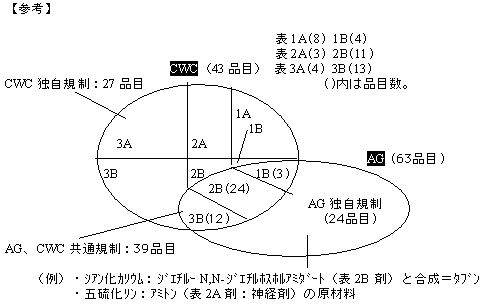
規制対象化学物質につき、AGは個別物質名(例:フッ化ナトリウム)で表示し、CWCは個別物質名及びファミリー(例:硫黄マスタード類)で表示している。
(例)CWC表1B剤ではアルキルホスホニルジフルオリド類として規制されている品目につき、AGではそのファミリーの中の個別の品目(メチルホスホン酸ジフルオリド、エチルホスホン酸ジフルオリド)を規制している。