4 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の実施状況
ハーグ条約は、子の利益を最優先するという考えの下、国境を越えた子供の不法な連れ去りや留置をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子供を元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力などについて定めた条約である。
この条約は、日本については2014年4月1日に発効し、2019年12月末現在、日本を含む101か国がこの条約に加盟している。
条約は、各締約国の「中央当局」として指定された機関が相互に協力することにより実施されている。日本では外務省が中央当局として、様々な分野の専門家を結集し、外国中央当局との連絡・協力、子の所在特定、問題の友好的解決に向けた協議のあっせんなどの当事者に対する支援を行っている。
ハーグ条約発効後2019年12月末までの5年9か月間に、外務大臣は、子の返還を求める申請を235件、子との面会交流を求める申請を143件、計378件の申請を受け付けた。日本から外国への子の返還が求められた事案のうち、40件において子の返還が実現し、35件において返還しないとの結論に至った。外国から日本への子の返還が求められた事案については、39件において子の返還が実現し、24件において返還しないとの結論に至った。
2019年2月には、ハーグ条約の実施に携わる日本の関係者に専門的知見を習得する機会を提供するため、米国でのハーグ条約事案の裁判手続などに詳しい米国人弁護士を招へいし、講演会などを開催した。また、6月には東京大学で、「ハーグ条約締結5周年記念シンポジウム」を開催し、日本のハーグ条約実施状況や今後の課題などについて議論を深めた(291ページ 特集参照)。
このほかにも、在外公館と連携し、海外で在留邦人向け啓発セミナーを積極的に実施しているほか、国内の地方自治体や弁護士会などの関係機関や在京外交団向けセミナーを実施するなど、広報活動に力を入れている。
また、2月にはハーグ条約に関する広報動画を公開するなど、より幅広い層へ条約を周知すべく取り組んでいる。
| 返還援助申請 |
面会交流 援助申請 |
|
|---|---|---|
| 日本に所在する子に関する申請 | 128 | 111 |
| 外国に所在する子に関する申請 | 107 | 32 |
世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、国際社会においては、1970年代頃から一方の親による子の連れ去りなどの問題が指摘されるようになり、1980年、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が成立しました。1970年には年間約5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚が1980年代後半から急増したことも踏まえ(2017年は約21,000件)、国内での様々な議論を経て、2014年4月1日、日本においてハーグ条約が発効しました。
2019年、ハーグ条約が日本で発効してから5年が経過したことを受け、6月10日、外務省は東京大学で「ハーグ条約締結5周年記念シンポジウム『ハーグ条約と日本』~子ども中心の国際家事手続に向けて~」を開催しました。家事手続とは、家庭内の紛争などを解決する手続のことです。

(6月10日、東京)
同シンポジウムは、①ハーグ条約や子供の連れ去り問題について、より多くの方々に正しい知識を身につけていただくこと、②5年間の日本での実施状況をよく知っていただくこと、③子供をめぐる家事手続のあり方について国民的な議論を深めるきっかけとすること、の3点を目的に開催しました。
同シンポジウムには、弁護士や裁判所関係者などハーグ条約の実施を担う関係者のほか、在京外交団、研究者、学生など190人を超える聴衆が参加し、二つのセッションにおいて、子供をめぐる家事手続のあり方について活発な議論が展開されました。
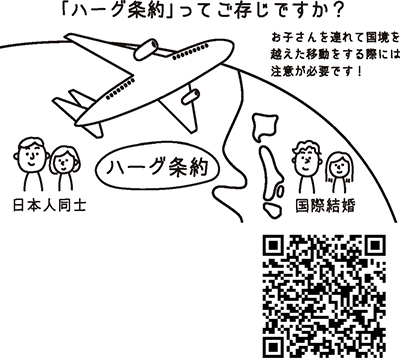
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000835.html)
基調講演では、日本における5年間のハーグ条約実施状況、ハーグ条約に関する日本の裁判実務、日米間のハーグ条約事案について、外務省、最高裁判所、米国国務省の関係者からそれぞれ説明がなされました。続いてハーグ条約に基づく返還申立事件の代理人を多数務めた経験がある弁護士や有識者がパネルディスカッションに加わり、条約を実施する上で日本がこれまでに直面した困難やそれを克服した方策について議論したほか、条約に基づく手続を迅速に行うための工夫や強制執行手続の実効性を高めるための仕組みなど、今後、日本が取り組むべき課題などについて議論を深めました。
基調講演では、国際家族法を専門とする英国の教授から、連れ去られた子に及ぼす長期的な影響や親子が再統合した後の子供のケアの重要性などについて、また、日本の家事調停委員のための研修を実施した経歴がある米国の弁護士兼調停人から、異なる国籍や文化的背景をもつ当事者が関わる国際的な家事事案において国際家事調停を活用することのメリットなどについて説明がなされました。続くパネルディスカッションでは、弁護士及び有識者が加わり、家事手続のあり方に関し、子の利益を最優先に考えること、子の声を聴くことの重要性などについて議論を深めました。
今回のシンポジウムを通じて、日本におけるハーグ条約の仕組みや裁判手続などについて、幅広い参加者の理解が深まっただけでなく、これまでの日本におけるハーグ条約の実施状況などについて、参加者から様々な評価や意見を頂くことができました。引き続き、日本としてはハーグ条約の着実な実施に努めていきます。
