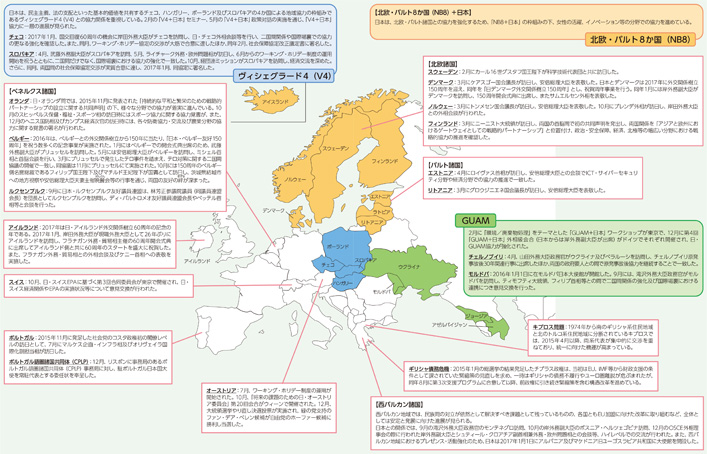1 地域情勢
(1)欧州連合(EU)
EUは、世界のGDPの約22%、総人口約5億1,000万人を擁する28加盟国から成る政治・経済統合体であり、日本と基本的価値・原則を共有し、日本が地球規模の諸課題に取り組む上で重要なパートナーである。
前年に引き続き、難民流入やテロ事件の多発といった諸課題への対応を迫られる中、EUは、6月の英国におけるEU残留・離脱に関する国民投票の結果、加盟国の離脱という欧州統合史上初の事態に直面することとなった。英国を除くEU27か国は、6月、9月及び12月に非公式首脳会合を開催し、離脱交渉に係るEU側の手続及び体制に関し議論するとともに、離脱後の英国が単一市場にアクセスするためには、人、物、資金及びサービスの「4つの自由」の全てを受け入れる必要があり、「いいところ取り」は認めないとの立場を明確にした。
また、EUは、加盟各国内でEUに懐疑的な勢力が伸長していることも踏まえ、難民問題での効果的な対応策を提示する必要に迫られた。3月のEU・トルコ合意に加え、9月には、ブラチスラバ(スロバキア)において、EU27か国の首脳が難民への対応に関する目標と具体的措置を記したブラチスラバ宣言及びロードマップが採択された。さらにEUは、トルコやアフリカ諸国との協力強化、約1,500人規模の欧州国境・沿岸警備隊の設立、難民のEU域内での再移転の促進、難民庇護申請等の手続迅速化のための集中対処施設の設置等、矢継ぎ早の対応を見せた。
安全保障面では、6月の英国のEU離脱決定の数日後、モゲリーニ外交・安全保障政策上級代表のイニシアティブによるEUの外交・安全保障政策のためのグローバル戦略が発表され、欧州の一体性を強調するとともに、グローバル・プレーヤーとして国際社会が抱える諸課題に積極的に貢献する姿勢を改めて明確にした。10月、EU外務理事会は、同戦略が今後数年間EUの対外政策を導くことを明言し、同戦略実施に際し優先分野を定めた。その後、同理事会は、防衛協力やEU・NATO協力の強化に取り組んでいる。
さらに、EU及び欧州諸国は、欧州への移民・難民流入の一因となっているシリアやリビア情勢等の改善に取り組むとともに、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」等による欧州におけるテロへの対策を強化した。また、ウクライナ問題については、当事者にミンスク合意の履行を促すなど、情勢の改善に取り組んだ。
アジアについても、EUは更なる関与の姿勢を見せた。前述のグローバル戦略において、経済面のみならず安全保障面でもアジアへの関与を高めることを明記するとともに、緊迫化した南シナ海情勢を踏まえ、3月及び7月の2回にわたり、海洋における法の支配の重要性を強調する声明が、EU加盟28か国を代表してモゲリーニ上級代表から発出された。
経済面では、ユーロ圏において、全体的に力強さを欠いているものの緩やかな回復が続いた。その一方で、南欧諸国における高失業率や一部の金融機関での財政体質の脆弱(ぜいじゃく)性が指摘されており、危機的状況には至っていないものの、様々なリスクを抱えながらの1年となった。
2016年は両首脳間の信頼関係が更に強化され、前年に続いて日・EU関係の包括的な強化に向けた大きな進展が見られた。5月、ブリュッセルを訪問した安倍総理大臣は、トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州委員会委員長との間で日・EU首脳会談を開催した。また、7月、ウランバートル(モンゴル)で開催されたASEM首脳会合時にも、年内2回目となる首脳会談が実施された。この会談では、6月の英国のEU離脱に関する国民投票の結果を受け、安倍総理大臣から、不透明感の払拭と今後の予測可能性を高めるために、EUと英国が協調して今後の交渉の見通しを明確にするよう求めた。また、両首脳は、日EU経済連携協定(EPA)及び日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)の早期大枠合意を目指すことで一致した。
経済面では、日EU・EPAの締結に向け、5月及び7月に行われた日・EU首脳会談のほか、5月のG7伊勢志摩サミットの際に発出した共同ステートメントにおいて、首脳レベルでの強いコミットメントを再確認した。2016年12月までに、日・EU間で計17回の交渉会合を開催し、物品貿易、サービス貿易、知的財産権、非関税措置、政府調達、投資等、広範な分野について議論を行った(詳細は3-3-1(1)参照)。
(2)英国
キャメロン首相が2015年5月の下院総選挙で公約とした、EU残留・離脱を問う国民投票が、2016年6月23日に実施された。同首相はEU残留を訴えたが、国民投票の結果は、離脱支持が過半数(離脱51.9%、残留48.1%)となった。背景には、英国議会が意思決定に関与できないEUレベルの規制の増加に対する不満や、EU拡大に伴う中・東欧諸国からの移民増加への不満が中間層を中心とする英国民にあったことなどが指摘されている。この結果を受けてキャメロン首相は辞任し、保守党党首選挙を経て、7月13日にメイ内務相が首相に就任した。英国政府は2017年3月末までにEUに対して離脱の意思を正式に通知する予定としており、その通知から原則2年以内に英国の脱退に関する取決めを定める協定を締結すべく、交渉が開始される。日本としても移民の規制や単一市場へのアクセス等の論点をめぐり、どのような関係が構築されるかを注視するとともに、適時に日本の立場を伝えていく(3-3-2(4)参照)。2017年1月の英国最高裁判決において、EUへの離脱通知には議会の承認が必要であると判示されたことに伴い、2月2日に英国政府は議会に対して「EU離脱通知法案」を提出した。また、メイ首相は1月17日、英国のEU離脱の方向性について演説を行い、英国が引き続き自由貿易を推進し、グローバルな役割を積極的に担うことを強調した。
日英両国は、首脳、外相を始め様々なレベルでの政策協調や交流を通じ、二国間関係を強化してきている。安倍総理大臣は、5月に英国を訪問し、英首相官邸及び英首相公式別荘(チェッカーズ)にてキャメロン首相と日英首脳会談を実施するとともに、エリザベス2世女王陛下に拝謁した。また、両首脳は、5月のG7伊勢志摩サミットに際するキャメロン首相の訪日時にも首脳会談を行った。安倍総理大臣は、後に就任したメイ首相とも、9月のG20杭州(こうしゅう)サミット(於:中国)の際には立ち話を、国連総会の際には首脳会談を行った。岸田外務大臣とハモンド外務・英連邦相は、G7広島外相会合の際に日英外相会談を行い、2016年1月に第5回外相戦略対話を実施した。7月にメイ新内閣において前ロンドン市長のジョンソン氏が外務・英連邦相に就任し、9月の国連総会の際に岸田外務大臣との外相会談が行われた。
近年、日英間で安全保障・防衛協力が大きく進展している。2016年1月に東京で開催された第2回外務・防衛閣僚会合(「2+2」)では、幅広い分野での安全保障・防衛協力の推進が確認されるとともに、世界各地の地域情勢について認識の共有が行われた。10月から11月、タイフーン戦闘機を含めた英国空軍部隊が訪日し、三沢自衛隊基地を拠点に航空自衛隊と共同訓練を行った。これは、航空自衛隊が国内を拠点に米国以外の国と実施する初の共同訓練であった。また、第2回「2+2」の合意を受けて、東南アジア及びアフリカ諸国の能力構築支援での連携にも進展が見られ、日英共催ASEAN諸国向け人道支援/災害救援セミナー(1月、フィリピン)、アンゴラにおける地雷除去に関する連携(8月)、チュニジアの空港における国境管理能力向上支援に関する連携(9月)等が実現した。さらに、2017年1月にはロンドンにて、ジョンソン外相と鶴岡公二駐英大使の間で日・英物品役務相互提供協定(日英ACSA)への署名が行われた。
(3)フランス
内政面では、10%を超える失業率の改善がオランド政権の最重要課題となっており、8月、政府は、国民による大規模な抗議活動に遭いつつも、硬直的な労働市場を見直す労働法改正法を成立させた。テロ対策に関しては、2015年11月のパリにおける連続テロ事件を受け、政府は緊急事態宣言を発出し、現在その宣言を2017年7月まで延長してテロ対策を強化しているものの、2016年7月には南フランスのニースで85人の犠牲者を出したテロ事件が発生するなど、中東・北アフリカ等から流入する難民対策とともに、テロ対策は依然として重要な課題となっている。また、2017年4月から5月に行われる大統領選挙を控えて、左派、右派共に選挙運動が活発化している。11月には、最大野党である共和党による予備選挙が実施され、フィヨン元首相が候補として選出される一方で、政権与党の社会党内では、12月、オランド大統領が次期大統領選挙への不出馬を表明するとともに、ヴァルス首相が出馬を表明し、首相を辞任した。これに伴い、12月にカズヌーヴ前内務相を首班とする新内閣が発足した。
外交面では、6月に中東和平に関する閣僚級会合を主催し、10月にはモスル(イラク)の安定化に向けた閣僚級会合をイラクと共催するなど、中東問題に関し国際社会において主導的な役割を果たした。
日本との関係では、3月に岸田外務大臣が訪仏した際、エロー外務・国際開発相と会談を実施し、4月のG7広島外相会合に向けた協力を確認した。同会合に出席するためにエロー外相が訪日した際には、岸田外務大臣との間で外相会談が行われ、アフリカにおける日・フランス協力に関する共同プレスリリースが発出された。5月、安倍総理大臣が訪仏した際には、オランド大統領と首脳会談を行い、G7伊勢志摩サミットの成功に向けた協力を確認するとともに、2018年に日本文化の粋を集め、大規模に紹介する「ジャポニスム2018」をフランスで開催することで一致した。
これらに加え、8月にケニアで開催された第6回アフリカ開発会議(TICADVI)においては、初となる日・フランス共催の公式サイドイベント「アフリカのための日仏パートナーシップ」が開催された。また、安全保障・防衛協力分野でも協力が進展しており、2017年1月にパリで行われた第3回外務・防衛閣僚会合(「2+2」)では、物品役務相互提供協定(ACSA)の交渉開始に合意するとともに、12月に発効した日仏防衛装備品・技術移転協定に基づく日・フランス間の初めての協力案件の具体化を確認した。また、自由で開かれたインド太平洋を確保すべく緊密に連携していくことで一致した。
(4)ドイツ
ドイツでは、2015年以降、移民・難民の流入数が急激に増加したことを受け、市民の間に治安悪化への懸念や不安が広がり、難民受入れ上限設定を否定するメルケル首相の支持率が下落した。2016年春以降は、国境管理の強化やEU・トルコ間合意等によって難民流入数が大幅に減少し、メルケル首相への風当たりは一時弱まったが、7月にドイツ南部で移民・難民の背景を持つ者によるテロ事件等が相次ぐと、批判が再燃した。
11月下旬、メルケル首相は、不透明で不安定な時期において、自らの経験と力が求められているとして、2017年秋頃の連邦議会選挙に首相候補として再出馬することを表明した。その約1か月後の12月下旬、難民申請が却下されていたチュニジア人の男がベルリン市内のクリスマス・マーケットにトラックを突入させ多数の死傷者を出すテロ事件が発生し、ドイツ国内では、治安対策や難民政策に対する懸念が再び高まっている。
こうした流れの中で、2016年春から秋にかけて実施された5州の州議会選挙で、メルケル首相率いる与党キリスト教民主同盟(CDU)が敗北する中、メルケル首相の難民政策を批判する政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が大きく躍進した。2016年末現在、AfDは全ドイツ16州中10州において議席を有している。
経済面では、英国のEU離脱問題等による先行きの不透明感がある中でも堅調な成長を維持した。連邦政府は、2016年の実質GDP成長率を1.8%と予測し、その比較的強い成長の理由として、難民の大量流入への対応による政府支出の増大、低い石油価格及びユーロ安を挙げた。また労働市場も拡大しており、失業者数は36か月連続で減少し、失業率は5.8%(2016年12月現在)と歴史的に低い数値を維持している。
外交面では、国際情勢が大きく変化するとともに、EU主要国を含む各国の首脳が交代する中、メルケル首相による長期政権と堅調な経済成長等に支えられたドイツの地位と存在感は、欧州のみならず国際社会においても上昇しており、ウクライナ問題、難民問題、中東・北アフリカ情勢、英国のEU離脱問題等、国際社会が直面する各種の危機への対応を実質的に主導している。
日本との関係では、シュタインマイヤー外相の訪日(4月、G7広島外相会合)、安倍総理大臣の訪独(5月)、メルケル首相の訪日(5月、G7伊勢志摩サミット)、ガウク大統領の訪日(11月)等、2015年に引き続き、ハイレベルの要人往来が数多く実現した。4月の外相会談においては、地域情勢について議論するとともに、国連安保理改革において具体的成果を得るべく、緊密に連携していくことで一致した。5月の安倍総理大臣・メルケル首相間の首脳会談及び11月の安倍総理大臣・ガウク大統領間の首脳会談においては、二国間関係、ウクライナ情勢を始めとする地域情勢など様々な分野について議論するとともに、世界の平和と安定に向け日本とドイツが国際社会と協調しながら一層緊密に連携していくことを確認した。また、5月の首脳会談の合意を受け、日独サイバー協議が立ち上がり、初回会合が9月に東京で開催された。
(5)イタリア及びスペイン
ア イタリア
2016年は、日本とイタリアが1866年に日伊修好通商条約を締結してから150年の記念の年であり、「日伊国交150周年」と銘打って両国で数々の記念行事を実施した(コラム「日本イタリア国交150周年」91ページ参照)。要人往来も活発に行われ、3月には岸田外務大臣がイタリアを訪問し、ジェンティローニ外相と会談を行うとともに、日伊情報保護協定に署名を行った(6月に発効)。4月には、ジェンティローニ外相がG7広島外相会合出席のため訪日し、東京及び広島を訪問した。5月には、安倍総理大臣がレンツィ首相の地元フィレンツェを訪問して首脳会談を行い、G7サミットの現・次期議長国として緊密に協力していくことを確認した。同じく5月、レンツィ首相がG7伊勢志摩サミット出席のため訪日した。
1866年に両国が国交を樹立した8月25日に合わせ、岸田外務大臣とジェンティローニ外相は、日・イタリア各メディアに同時に寄稿を行った。岸田外務大臣は、その寄稿の中で、日・イタリア間での防衛装備・技術移転の分野での潜在的な協力の可能性を指摘しつつ、安全保障・防衛分野における両国の協力の深化を呼びかけた。
内政面では、レンツィ首相が、2016年12月に実施された憲法改正法案への賛否を問う国民投票の否決を受けて辞任し、ジェンティローニ外相が新首相に指名され、12月に改革路線を引き継ぐジェンティローニ政権が誕生した。
イ スペイン
スペインは、2015年12月に実施された上下両院の総選挙で、与党民衆党が過半数を獲得できず、その後の連立交渉が難航し、2016年6月に再選挙が実施された。与党民衆党は再び過半数を獲得できなかったが、ラホイ首相の指名投票において最大野党の社会労働者党が棄権した結果、11月に第2次ラホイ政権が成立した。
日本とスペイン両国間の渡航者数は増加し続けており、10月には、東京・マドリード間の直行便が約20年ぶりに再開された。
(6)ウクライナ
ウクライナ東部では、一時的な情勢改善も見られたが(5月及び9月)、1年を通じて停戦違反が絶えず、不安定な状況が継続した。10月、ウクライナ、ドイツ、フランス及びロシアの4か国首脳会談が1年ぶりに開催され、ミンスク合意の履行に向けた「ロードマップ」の作成について合意したが、12月に入っても、当事国間の調整は難航した。
内政面では、4月、ヤツェニューク首相が支持率の低迷を背景として辞任し、フロイスマン前最高会議議長を首相とする新内閣が発足した。同内閣は、汚職対策や司法改革等を優先改革分野に掲げ、6月の司法分野での憲法改正法案の採択や9月の公務員資産の電子申告制度開始等、改革加速への努力を継続してきた。
外交面では、1月のEUとの「深化した包括的自由貿易協定(DCFTA)」の適用開始及びこれを受けた独立国家共同体(CIS)自由貿易協定(FTA)のロシア・ウクライナ間の効力停止等により、ウクライナの貿易全体におけるEUのシェアが増加し、ロシアのシェアは減少した。また、EUとの間では査証自由化に向けた交渉が進展し、欧州統合路線を継続するとともに、ロシアとの間では2015年11月以降、ロシア産天然ガスの購入を停止するなど、エネルギー分野でもロシア依存からの脱却を図ってきた。
日本との関係では、4月のポロシェンコ大統領訪日、9月の国連総会の際の日・ウクライナ首脳会談、10月のアヴァコフ内務相訪日、11月のクービウ第一副首相兼経済発展・貿易相の訪日等、数多くのハイレベル交流が実現した。また、11月には第6回日・ウクライナ経済合同会議、12月には第4回日・ウクライナ原発事故後協力合同委員会や日・ウクライナ安保理協議等が開催され、二国間関係は着実に発展した。対ウクライナ支援では、1月に約15億円の追加支援を決定したほか、財務相アドバイザーとして日本人専門家をウクライナへ派遣した。