2 中東・北アフリカ情勢
(1)エジプト
アラブの国として北アフリカに位置し、地中海を隔てて欧州に接するエジプトは、中東・北アフリカ地域の安定に重要な役割を有する大国である。そのエジプトで、2011年1月25日、直前にチュニジアで発生した政変の影響を受けた青年活動家が中心となり、ムバラク大統領の退陣や経済改革等を求める大規模な反体制デモが各地で発生した。ムバラク大統領は、内閣刷新、副大統領任命、自身の次期大統領選挙不出馬等の改革を打ち出したが、あくまでもムバラク大統領の辞任を要求する民衆のデモは更に拡大した。こうした一連のデモの結果、2月11日、ムバラク大統領は辞任し、国軍最高会議への国政統括権委譲が発表され、約30年続いたムバラク政権は崩壊した。
タンターウィ国防相を議長とする国軍最高会議は、3月19日、大統領選出等に関する憲法改正に関する国民投票を実施し、7割を超える圧倒的多数の賛成を得た。11月下旬から翌2012年2月にかけては、人民議会及び諮問評議会両選挙が順次実施される等、改革が進められている。タンターウィ国軍最高会議議長は、同年6月末までに大統領選挙を終了する旨発表しており、大統領選出の後に民政移管が完了することとなる。
経済面では、政変前のエジプトの経済成長率は、2005年から2008年にかけて約7%台を達成し、2008年秋以降の世界的景気低迷の中でも、2009/2010年度は約5%の成長率を維持していた。しかし、公式統計で約10%に上る高失業率、貧富の格差拡大、補助金や国内債務利払い等による財政逼(ひっ)迫などの構造的問題を抱えており、こうした経済状況も、2011年1月の反体制デモ発生の要因の一つとなった。一連のデモ及び政権崩壊に伴う観光収入の落ち込み、海外直接投資の減少等経済活動の減速により、2010/2011年度の成長率は1.8%(暫定値)と、前年度を大きく下回っている。また、失業率は、経済活動の停滞に加え、リビア政変に伴うエジプトへの出稼ぎ労働者の帰還などを受け、増加傾向が続くと考えられる。
日本との関係では、2011年5月、徳永外務大臣政務官が政変後の最初の日本政府要人としてエジプトを訪問し、同国政府関係者に加え、各政党関係者と幅広い意見交換を行った。7月には、カイロで、日・エジプト戦略対話第一回次官級協議を実施したほか、日・エジプト人権対話第一回会合を開催した。また、同月、国際協力機構(JICA)が「民主化と政治システム」と題するセミナーを実施したほか、11月以降実施された人民議会選挙のための選挙支援団を派遣したり、選挙公報のためのセミナーを実施するなどして、エジプトの民主化を支援している。
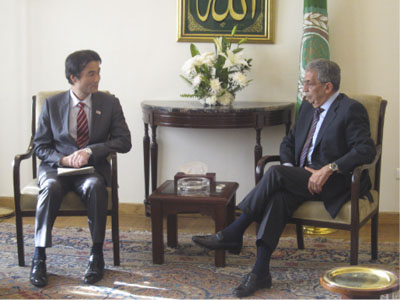
(2)リビア
2011年2月中旬、東部ベンガジを中心に起きた反政府デモをカダフィ政権は徹底的に弾圧した。カダフィ政権から離脱したアブドルジャリル氏(法相)とジブリール氏(経済開発理事会総裁)を中心に、反政府派はリビア国民暫定評議会(NTC)を結成した。国際社会は、自国民へ銃を向けるカダフィ政権を強く非難した。国連安保理は、カダフィ政権に対する資産凍結等の経済制裁の実施を決定したほか、リビアの一般市民を保護するために一定の措置を国連加盟国に認める決議を採択し、この決議に基づいて、米国、英国、フランスを中心とした多国籍軍が軍事行動を開始した。欧米やアラブ諸国を中心に反政府派であるNTCを支援し、リビア・コンタクト・グループ会合等を開催し、カダフィ政権に対する圧力の強化とNTCへの支援を確認した。カダフィ政権とNTCの間の戦闘は半年にわたって膠着状態が続いたが、8月下旬、NTCが首都トリポリを制圧したことにより、カダフィ政権は事実上崩壊に至り、10月20日にカダフィ指導者が死亡したことを受け、10月23日、NTCはリビア全土の解放を宣言した。10月31日に移行期における暫定政権の首相に選出されたアブドルラヒム・キーブ氏を中心に、2012年6月までに制憲議会選挙が実施される予定である。リビアの国づくりの今後の課題は、①公平公正な民主化の推進、選挙の実施、②法治国家の建設、憲法の制定や法の整備、③カダフィ指導者によって子供や女性にまで持たされた銃・武器の回収とされている。
2011年3月、日本は、深刻化するリビア情勢を受けて、避難民支援として500万ドルの緊急無償資金協力を実施したことに加え、リビア・コンタクト・グループ会合の場やリビアへの使節団派遣を通じ、NTCとの対話を重ね、支援する意向を伝えてきた。トリポリ陥落後、9月には医療支援として200万米ドルの緊急無償資金協力を実施したほか、日本が凍結したカダフィ政権の資産44億米ドルのうち15億米ドルをNTCがリビアの新しい国づくりに使用できるよう、凍結を解除し、その後、12月には凍結資産全額の凍結を解除した。2012年1月には、官民合同経済使節団をトリポリに派遣し、日本がリビアの復興事業に参加する可能性について意見交換した。
(3)シリア
シリアでは、3月以降南部に端を発した反政府デモの広がりを受け、治安当局との衝突により多数の死傷者が発生した。国連は、2012年2月までの死者数は5,400名以上と発表したものの、死者数の急増により、把握することが不可能としている。また、一部地域では激しい戦闘により、子供を含む一般市民の犠牲者も増えており、こうした事態の打開は、国際社会全体にとっても差し迫った課題である。これまでも、多くの国が様々な形でシリア政府に対し、一般市民に対する弾圧の即時停止・民主化に向けた抜本的改革の早期着手等を要求してきたが、アサド大統領は、国民対話を呼びかけ、政党法や選挙法の改正を行うなどの施策を打ち出すものの、一向に収束の見通しは立っていない。
こうした事態を受け、アラブ連盟も対シリア制裁や監視団の派遣に加え、大統領から副大統領への権限委譲を含む政権移行の行動計画を発表した。また、2012年2月、国連安全保障理事会において、シリアの人権侵害の即時停止及びアラブ連盟の取組を支持する決議案が採択に付されたが、ロシア、中国の拒否権の行使により否決された。
日本は、2011年5月にシリアに対する経済協力を見直し、8月には国際社会と歩調を合わせる形で、アサド大統領は道を譲るべきものと考えるという内容の外務大臣談話を発出した。これに加え、シリア問題の解決を目指す国際的な努力に寄与するため、9月にアサド政権関係15個人6団体に資産凍結等の措置を実施し、12月には、3個人6団体を措置の対象として追加した。
(4)チュニジア・アルジェリア・モロッコ
チュニジアでは、2010年12月17日、地方都市の街頭で20代の男性が野菜を販売していたところ、販売の許可がないとして、女性警官が商品を没収したことに抗議し、男性が焼身自殺を図ったことを契機に、抗議活動が発生した。2011年1月5日、男性の葬列を警察が阻止し、男性の親族がその様子を写した動画をインターネットに投稿したことで、抗議活動は全国に拡大した。同月11日には首都チュニスでデモが発生し、14日にはベン・アリ大統領が国外に脱出した。憲法に従い就任したムバッザア暫定大統領の下で選挙準備が進められ、同年10月、大きな混乱なく制憲国民議会選挙が実施された。日本は、チュニジアの改革・民主化努力を支援するとの考えから、同選挙に際して浜田和幸外務大臣政務官を団長とする選挙監視団を派遣したほか、同選挙に先立って専門家3名を派遣し、日本の民主化経験等に関するセミナーを開催した。選挙で全体の約41%の議席を獲得し第一党となった穏健なイスラム主義政党エンナハダ及び同党と連立を組む中道左派2政党を中心とした新内閣の下、1年以内をめどに憲法策定作業が行われる予定である。また、12月に就任したマルズーキ大統領は、人権の擁護や腐敗のない政治国家の構築の意思を表明した。今後、新政府が政治・経済・社会諸改革を順調に進めていくことが期待される。
アルジェリアでは、2011年1月以降、各地で焼身自殺事件や抗議デモが発生した。アルジェリア政府は、国民の不満を抑えるために、食料品価格高騰への対策として、減税措置や小麦の大量輸入等を実施した。同年2月以降も、一部野党勢力が首都アルジェでのデモ行進を試みたものの、規模としては小規模なものにとどまった。そうした中、2月24日、アルジェリア政府は、テロ活動への対応として1992年以来発令したまま維持していた非常事態宣言を解除した(1)。続いて、4月15日、ブーテフリカ大統領は国営テレビで演説を行い、政治・行政・経済改革を行う方針を表明し、同大統領主導の下で、選挙の透明性確保等のための選挙法改正などの改革が進行している。
モロッコでは、周辺諸国の影響を受け、2011年2月頃から、政治・経済・社会改革を要求する全国一斉デモが発生した。しかし、3月の憲法改正の実施表明や7月の国民投票による新憲法採択等、モハメッド六世国王が素早い対応をとったことが功を奏したこともあり、民主化要求デモは激化することなく収束した。11月、衆議院選挙が平穏裏に実施され、新憲法に従って、第一党になった穏健イスラム派の「公正と発展党」党首であるベンキラン氏が首相に任命された。2012年1月には連立4党を中心とした新内閣が発足する等、民主化が進展した。日本は、選挙支援の一環で、選挙に先立って専門家を派遣した。また、2011年3月、第2回日・モロッコ合同委員会がモロッコで開催されたほか、今後太陽エネルギー分野における協力促進が期待される。
(5)レバノン・ヨルダン
レバノンでは、2005年のハリーリ元首相暗殺の真相解明のために設置された国際法廷である、レバノン特別法廷(STL)の起訴状発出をめぐり、国内で緊張が高まり、1月に親シリア派の野党系閣僚が一斉辞任し、内閣崩壊につながった。5か月間内閣不在の状態が続いたが、6月にヒズボラなど親シリア派グループの擁立を受け、ミーカーティー首相率いる内閣が発足した。8月にはSTLの起訴状の中身が公開され、ヒズボラの幹部を含む4名の被告の氏名が明らかにされた。ヒズボラ系政治グループなどからは、STLへのレバノン分担金(全体の49%)拠出拒否の圧力が高まっていたにもかかわらず、11月にミーカーティー首相はSTLへの拠出を表明した。
ヨルダンはイスラエル及びパレスチナと隣接しており、中東の平和と安定のため非常に重要な位置にある。伝統的に親欧米派、アラブ穏健派の国で、アラブ世界ではイスラエルと外交関係を有する数少ない国(エジプトとヨルダンのみ)である。さらに、日本とヨルダンは、両国の皇室・王室の親密な関係を含め、伝統的に友好関係にある。
ヨルダンでも、1月中旬以降、チュニジアの動きを受け、金曜日にイスラム教の礼拝で人々が集まるのをきっかけに、物価上昇への対応、汚職の摘発、首相退陣等を求めるデモが各地で発生した。2月に発足したバヒート内閣は、国王の指導の下、政治・経済改革の推進を図り、10月1日には改正憲法が発効した。しかし、国民の不満は解消されず、デモは鎮静化の傾向にあるが継続している。10月17日にはバヒート内閣が総辞職し、後継のハサーウネ内閣が、選挙法や政党法の改正など政治改革に取り組んでいる。また、経済面では、大規模インフラプロジェクト(原子力、水、鉄道、再生可能エネルギーなど)を国家事業として掲げ、国家開発を進めている。
(6)湾岸諸国(イエメンを含む)
ア いわゆる「アラブの春」と政治改革の緩やかな進展
(ア)イエメン
いわゆる「アラブの春」の影響を受け、イエメンでは、2011年2月以降、サーレハ大統領の退陣を要求するデモが頻発した。4月にGCCがGCCイニシアティブ(大統領は副大統領に権限移委譲する代わりに訴追を免除されるとの内容の仲介案)への署名を大統領に働きかけたが、大統領は拒否し続けた。このため対立と混乱が続いていたが、11月に大統領はGCCイニシアティブに署名し、2012年2月21日に大統領選挙を実施することとなった。大統領選挙を支援するため、日本は約114万米ドルを拠出することを決定した。
(イ)バーレーン
バーレーンでは、国民の約7割を占めるシーア派国民を中心とした、改革を求める反政府デモが2月に発生した。警察とデモ隊の衝突で死者も発生し、「王制打倒」の要求も出た。3月には、バーレーン政府の要請を受けたGCC合同軍のバーレーン派遣、バーレーン政府による非常事態宣言発出を経て、バーレーン政府がデモ隊を強制排除した。この結果、事態はやや沈静化し、同国政府は6月に非常事態宣言を解除した。7月に実施された「国民対話」は、下院の権限強化、腐敗防止といった提言を国王に提出した。また、11月には、独立調査委員会(2~3月のデモへの政府の対応における人権侵害を調査)が報告書を国王に提出した。報告書は、不当逮捕や拘留者への拷問、過度の武力行使などを認定した上で、法執行機関の改革などを提言した。これに対し国王は、事件を二度と起こさないとの決意を示すとともに、提言を早急に検討すると表明した。これらの動きを踏まえ、2012年1月、国王は演説で「国民対話」の合意事項を実現するための憲法改正に言及した。
(ウ)その他の湾岸諸国
カタールでは5月に地方自治評議会選挙、アラブ首長国連邦では9月に連邦国民評議会選挙、オマーンでは10月に諮問議会選挙が行われ、それぞれ大きな混乱なく終了した。
3月、サウジアラビアで、インターネットを通じ、反政府デモを呼びかける動きがあったが、これに応じる動きはほとんど見られなかった。小規模な抗議活動が発生したが、情勢は平穏に推移している。この例に見られるように、イエメンとバーレーンを除く湾岸諸国の中では、いわゆる「アラブの春」に呼応するような動きは表面化しなかった。
イ 東日本大震災に際しての湾岸諸国からの支援
東日本大震災に際しては、クウェートから500万バレルの原油の無償供与を受け、10月には原油贈呈式典が日本にて行われた。また、サウジアラビアからは2,000万米ドル相当の液化石油ガスの無償提供など、カタールからは400万トンの液化天然ガスの追加供給及び1億米ドルの支援金の申し出があった。
ウ 玄葉外務大臣の新興国・湾岸諸国訪問
2012年1月、玄葉外務大臣は、トルコ、アフガニスタンに加え、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦を訪問した。訪問では、各国要人との間でエネルギー安全保障や、中東・北アフリカ地域情勢等について議論した。特に、エネルギー安全保障に関しては、各国に対し現下の中東情勢を踏まえ、また東日本大震災からの復興に向けて、日本の必要とする原油の供給と価格の安定を要請し、いずれの国も日本が必要とする原油・液化天然ガスの供給を行う用意があると表明し、原油価格の安定についても、協力の意向を表明した。GCCとの関係では、2010年及び2011年にニューヨークにおいて開催された二度の日・GCC戦略対話を経て、玄葉外務大臣のサウジアラビア訪問の機会に、日・GCC間の協力及び戦略対話に関する覚書に署名し、日・GCC関係を抜本的に強化することで一致した。
(7)トルコ
エルドアン首相率いる公正発展党(AKP)政権が2002年以来継続しているトルコでは、G20の一国として高い経済成長率を維持し、国際社会でますます存在感を高めている。2011年6月の総選挙において、AKPは約50%の得票率を獲得し、翌7月には第3次エルドアン政権が発足した。引き続き安定した政権運営が期待されるAKPの下、今後は新憲法制定等が内政の焦点になると予想される。
トルコは、周辺諸国に対する積極的な外交(「ゼロ・プロブレム(2)」外交)路線を継続しており、変動する中東情勢においても、7月の第4回リビア・コンタクト・グループ主催(於:イスタンブール)やエルドアン首相によるエジプト、リビア、チュニジア歴訪等、地域の安定やアラブ諸国の新政権への支援等において積極的な役割を果たしている。また、8月、エルドアン首相は、干ばつによる飢饉(きん)が深刻化しているソマリアを訪問し、積極的な支援姿勢を示すなど、対アフリカ外交も活発に行っている。さらに、トルコは、対アフガニスタン支援でも重要な役割を果たしており、11月にはアフガニスタン地域協力に関するイスタンブール会合を開催したほか、7~12月にかけて、日本と協力し、トルコにおいてアフガニスタン警察官訓練を実施した。
一方、2010年5月に発生したガザ支援船事件(3)をめぐる対応で、トルコ・イスラエル関係が悪化しており、また、12月にフランス国民議会が過去のオスマン帝国による「アルメニア人虐殺」の事実を否定する者に刑罰を科す法案を可決したことから、トルコ・フランス関係が急速に悪化している。
日・トルコ関係は、「2010年トルコにおける日本年」後も活発かつ良好に推移しており、11月のG20カンヌ・サミットにおいて日トルコ首脳会談が実施されたほか、2012年1月には玄葉外務大臣がトルコを訪問し、二国間関係強化と、国際場裏での協力などについて意見交換を行った。
2011年3月に発生した東日本大震災では、トルコ首相府から派遣された救助・支援隊が宮城県七ヶ浜町等で3週間にわたり活動した。その後11月にババジャン副首相が訪日した際に七ヶ浜町議会でスピーチを行った。10月にトルコ東部で発生した東部地震において、日本政府からテント500張及び仮設住宅用の緊急無償資金協力1,000万米ドルを供与するなど、震災を通して両国の支援・協力関係が一層強化されている。
(8)イスラエル
イスラエルでは、7月頃から、住宅費及び物価全般の高騰に対する批判を発端に、「社会的公正(social justice)」を求める運動が全国的に広がっていたが、9月3日の大規模デモを転機に右運動はほぼ終息した。このデモはイスラエル史上最大のデモといわれている。これを受け、ネタニヤフ首相が8月に設置した有識者特別パネルは、9月に改革案を内閣に提言するなどの対応をした。
日・イスラエル関係では、3月の東日本大震災の際に、イスラエルは医療支援チームを派遣し、宮城県栗原市の協力により、同南三陸町で活動を行い、活動終了時には本国から携行した医療機材を南三陸町の被災者に提供した。また、医療支援チームの派遣に加え、毛布等の物資支援も行った。また、12月には第4回日・イスラエル経済作業部会が実施され、二国間経済関係の深化に向けた協議が実施された。
(9)イラン
イランの核問題の平和的・外交的解決に向け、国際社会は「対話」と「圧力」のアプローチで対応してきた。2010年12月、EU3+3(4)とイランとの協議(於:ジュネーブ(スイス))に続き、2011年1月、イスタンブールにおいて再度協議が行われたものの、具体的な成果には至らなかった。「対話」面で進展が見られない中、5月、米国及びEUは資産凍結対象の拡大を行い、同月のG8サミット首脳宣言では、イランの行動次第で追加的措置の必要性について決定すると表明した。6月、米国は、石油化学分野における対イラン制裁措置等を発表し、イランに対する「圧力」が高まった。10月、米当局が駐米サウジアラビア大使暗殺計画にイランが関与していたとの疑いを発表したことから、核問題とは別に、イランに対する圧力が高まった。また、11月にイランの核計画に関する未解決の問題について、深くかつ増大する懸念を表明する国際原子力機関(IAEA)理事会決議が採択されたことを踏まえ、米国、英国、カナダ、EU、韓国等がイランに対する更なる措置を実施した。こうした中、在イラン英国大使館等に対するデモが行われた際に、一部のデモ参加者により同大使館の敷地等への侵入し、破壊行為等が行われるという事案が発生した。また、12月、米国において、イラン原油取引の決済を行うイラン中央銀行等と相当の取引を行う外国金融機関を制裁対象とする国内法(国防授権法)が成立した。これに対し、イラン側がホルムズ海峡の封鎖に言及するなど、反発を強めている。
日本は、中東地域の大国であるイランが同地域や国際社会の平和と安定のため一層建設的な役割を果たすよう、同国との伝統的な関係に基づき働きかけを行っている。特に核問題については、国際的な核不拡散体制を堅持する必要がある等の立場から、2010年8月に安保理決議第1929号の決定事項を履行する措置を実施したのに続き、同年9月及び2011年12月に資産凍結対象の追加等の金融措置を中心とする同決議に付随する措置を実施するなど、安保理決議を厳格に実施している。一方で様々なレベル・分野においてイランと対話を行い、安保理決議の遵守、IAEAとの完全な協力等イランによる建設的な対応を強く働きかけている。
2011年3月の東日本大震災に際しては、イランから数多くのお見舞いのメッセージが寄せられたほか、缶詰5万個の緊急物資の提供や東京にあるイラン大使館による炊き出し支援など、多くの支援が寄せられた。
(10)アフガニスタン
ア 政治・治安情勢
アフガニスタンでは、2001年のタリバーン政権崩壊後、近代的な国家構築のための復興努力が続けられている。カルザイ大統領率いるアフガニスタン政府は、国際社会の支援を受け、国軍や警察の拡大や強化に取り組んでいるが、治安は不安定の度合いを強めており、特に、南部、南東部、東部の治安は依然として厳しい。12月の国連事務総長報告は、治安事件発生件数は前年の同期(1月~11月)に比べ21%増加したと報告している。また、2011年9月にはラバニ和平高等評議会議長が自爆テロにより殺害されたことを受け、アフガニスタン政府とタリバーンを含む反政府武装勢力との和解も今後の見通しは不透明な状況である。
2011年1月9日現在、アフガニスタンには、米軍が率いる連合軍のほか、50か国計約13万名に及ぶ国際治安支援部隊(ISAF)が駐留しており、治安確保などの任務に当たっている。アフガニスタンでは、ISAFからアフガニスタン側に対する治安権限の移譲が2010年7月から段階的に開始されており、2010年11月に発表になった第2対象地域を含め、アフガニスタンの全人口の半分を超える地域で実施されるまでに至っている。今後、この権限移譲は、現地の治安情勢等を踏まえつつ2014年末の終了を目指して進められる予定である。また、米国は2011年中に1万人、2012年夏までに3万3,000人の兵員の削減を発表するなど、治安権限の移譲の進捗に併せて、各国のアフガニスタンからの撤収が開始されている。
イ 経済・社会状況
アフガニスタン及び国際社会の復興努力の結果、難民帰還や教育分野、基礎医療分野等で成果が見られるが、過去数十年にわたり続いた内戦のため、今後の復興・開発に不可欠な基礎的インフラは未整備の部分が多く、地方への支援拡大も課題となっている。世界のケシ生産量の92%を占めているとされる麻薬問題の解決は、最重要課題の一つである。
ウ 日本の復興支援策
こうした経済・社会状況を抱えるアフガニスタンの安定と復興は、国際社会にとって最重要課題の一つである。日本はこれまでに、政治プロセス、治安改善、復興の全てにわたる支援を行っており、2001年10月から2011年末までに約32.5億米ドル(3,477億円)を支援した。また、全土で活動する各国の地方復興チーム(PRT)(5)と連携した支援に加え、2009年5月以降、ゴール県のチャグチャランPRTに日本の文民を派遣するなど、地方支援も強化している。
また、日本は2009年11月、アフガニスタン・パキスタンに対する支援策「テロの脅威に対処するための新戦略」を発表した。アフガニスタンに関しては、①治安能力の向上、②元タリバーン末端兵士の社会への再統合、③開発の三つを柱として、2011年末までに約17.7億米ドル(約1,777億円)を支援した。
2011年12月のアフガニスタンに関するボン会議(於:ドイツ)では、治安権限の移譲の終了後の2015年から2024年までの「変革の10年」における治安及び経済面での課題について、国際社会としてアフガニスタンを支援していくとの強い政治的意思が示された。日本は、同会議において、アフガニスタンの持続可能な成長・開発戦略と、当面の民生支援の調整及び地域経済協力を主要テーマとした閣僚級会合を2012年7月に東京において主催する用意があることを表明した。
2012年1月には、玄葉外務大臣がアフガニスタンを訪問し、カルザイ大統領等と会談を行い、日本は東日本大震災にもかかわらずアフガニスタン支援を継続すること、7月の東京会議に向けて両国で緊密に協議することなどを確認した。
なお、東日本大震災に際して、アフガニスタンからは、カルザイ大統領を始めとした政府高官から哀悼のメッセージが寄せられたほか、バーミヤンを含む各都市で日本へエールを送る集会が行われた。また、総額約125万米ドルに及ぶ義援金が日本に対して支援された。

(11)イラク
ア イラク情勢
2010年12月21日、主要な政治勢力全てが参加し、マーリキー首相が率いる新政権が発足した。新政権は、治安対策、係争地の帰属問題、クルドとの政治的緊張の継続、石油収入の配分を決定する石油・ガス法案等の重要法案の成立、公共サービスの改善、汚職の撲滅などを求めるデモへの対応など、取り組むべき課題が依然として多い。
2011年12月、米軍戦闘部隊がイラクからの撤収を完了した。イラクの治安は、2007年夏以降全般的には改善の傾向にあるが、米軍撤退後も依然としてテロ事案が散発している。
イ 日本の取組
イラクの安定は、中東地域ひいては国際社会の安定に不可欠であることから、日本は国際社会の責任ある一員としてふさわしい支援を行うため、ODA等による幅広い取組を行ってきた。特に、2011年11月、マーリキー首相が訪日した際に行われた日・イラク首脳会談では、これまでの援助からビジネスへと日・イラクの経済関係を転換し、日・イラク関係を新たな段階に引き上げることなどで一致した。イラクの安定化と発展に伴い、イラクに対する日本の協力は、無償資金協力から円借款事業によるインフラ整備、技術協力及び経済・ビジネス関係の強化に移行しつつある。
(ア)ODAによる支援
日本は、2003年10月、15億米ドルの無償資金、経済社会インフラ整備等の中期的な復興需要に対する円借款を中心とする最大35億米ドルの支援からなる、最大50億米ドルのイラク復興支援を表明した。このほか、約67億米ドルの債務救済支援を実施し、2010年末までに4,700人以上のイラク人に研修を実施したほか、2007年からイラクの国民融和へ向けた努力への支援として、「イラク国民融和セミナー」を日本国内で3回実施している。
2011年11月にマーリキー首相が訪日した際、野田総理大臣は、石油、通信及び保健の分野の新規4案件のために、約670億円(約7億5,000万米ドル)の円借款の供与に必要な措置をとることを表明した。
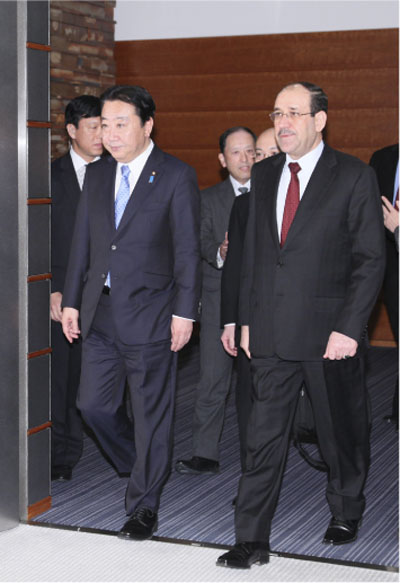
(イ)経済・ビジネス関係の強化
イラクとの経済・ビジネス関係の強化を目的として、日本は、2011年2月にバグダッドへ、6月にバスラへ官民経済使節団を派遣した。11月には、バグダッドで開催された国際見本市に、日本ブースを開設するとともに3度目の官民経済使節団を派遣した。また、11月のマーリキー首相訪問の際、日・イラク投資協定が原則合意された。
(ウ)エネルギー分野での協力強化
2011年11月のマーリキー首相訪日の際には、エネルギー分野でも二国間協力を強化し、ガッラーフ油田、東バグダッド油田、ナーシリーヤ油田について協力と対話を促進することで一致した。また、マーリキー首相より、緊急時の原油供給と液化天然ガスの安定的供給に関する申し出があった。
ウ 東日本大震災に際してのイラクからの支援
東日本大震災後に際し、イラクから日本に対して1,000万米ドルの義援金の提供があり、またイラクは、日本企業の輸入需要を充足するための日本への原油の優先的輸出を行うことを決定した。

1 同宣言は、テロ対策という名目の下、政治的自由(首都アルジェでのデモ行進禁止等)を制限するものであったため、2011年1月から、非常事態宣言解除を求める声が一部野党や市民グループを中心に高まっていた
2 決まった定義があるわけではないが、ダーヴトオール外相が提唱する外交の基本方針。周辺諸国との問題を積極的に解決し、地域の安定を実現することにより、トルコの政治・経済力を一層高めることを目指す。
3 イスラエルが海上封鎖するパレスチナ自治区のガザに支援物資を搬入しようとした船団を、イスラエル軍が攻撃し、トルコ人乗船者9名を射殺した事件。国連の調査委員会は、イスラエル軍による過剰な武力行使があったものの、船側からも組織的・暴力的な抵抗があったとの報告書を提出した。
4 イランの核問題に関するEU3か国(英国、フランス、ドイツ)と、米国、中国、ロシア3か国を合わせた6か国による対話の枠組み。
5 軍人及び文民復興支援関係者から構成される軍民混成の組織。