アジア
南アジア地域協力連合(SAARC)
平成26年12月1日
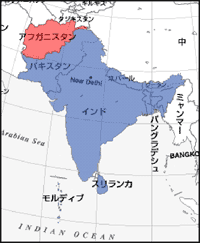
1.設立経緯
- (1)南アジア地域協力連合(SAARC:South Asian Association for Regional Cooperation)は、南アジアにおける比較的緩やかな地域協力の枠組み。1980年にバングラデシュのジアウル・ラーマン大統領が行った提案に基づき、1985年12月に開催された首脳会議(於:バングラデシュ)で正式に発足した。常設事務局(secretariat)は、1987年以降カトマンズ(ネパール)に設置されている。
2.加盟国
- (1)原加盟国は、南西アジアの7か国(インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ)。2005年11月の第13回首脳会議でアフガニスタンの加盟が原則承認され、2007年4月の第14回首脳会議において正式加盟した。
- (2)オブザーバーとして、日本、中国(第13回首脳会議で承認)、米国、EU、韓国(2006年8月の外相会合で承認)、イラン(第14回首脳会議で承認)、モーリシャス(2007年12月の外相会合で承認)、豪州、ミャンマー(第15回首脳会議で承認)が参加している。
3.SAARCの組織
- 首脳会議(Summit、隔年開催)
- 閣僚理事会(外相会合)(Council of Ministers、最低年1回開催)
- 大臣特別会合(Specialized Ministerial Meetings)
- 常任委員会(外務次官級)(Standing Committee、最低年1回開催)
- プログラム委員会(外務省局長級)(Programming Committee、最低年2回開催)
- 専門委員会(Technical Committee)
- 作業部会(Working Group)
4.目的及び活動
- (1)SAARC憲章は、SAARCの目的として、南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力、協調等の促進等を規定している。これまで、経済、社会、文化等の分野を中心に協力を行っており、1983年に第1回外相会合で採択され、2000年に再編された統合行動計画(Integrated Programme of Action)は、7分野(農業・農村開発、運輸通信、社会開発、環境気象、科学技術、人材開発、エネルギー)を対象としている。
- (2)SAARCの枠組みの下、「南アジア自由貿易圏」(SAFTA)や「SAARC開発基金」(SDF)が創設された他、テロや女性及び児童の人身売買防止に関する地域協定等が締結されている。
- (3)SAARCの首脳会議、閣僚理事会は、SAARC諸国の首脳、外相が一堂に会する機会であり、これらの会合の機会を活用して各国間の首脳・外相会談が活発に行われている。
なお、SAARC憲章によれば、係争事項及び二国間事項は取り上げないこととなっている。また、SAARCでは全ての決定は全会一致により行われる。
5.域外国、国際機関との関係
- (1)2005年11月の第13回首脳会議では、アフガニスタンの加盟、我が国及び中国のオブザーバー参加が原則認められ、その後米国、EU、韓国、イラン、モーリシャス、豪州及びミャンマーのオブザーバー参加が承認された。
- (2)また、UNCTAD、UNICEF、UNDP、EU等の国際機関及びカナダ(CIDA)との間で協力協定を締結している。
6.我が国との関係
- (1)我が国は、経済成長を続け、民主主義、自由、法の支配といった基本的価値観を共有する南アジアを重視し、各国との良好な二国間関係を基礎に、同地域の域内協力を支援している。2011年11月にモルディブで開催された第17回首脳会議では、中野外務大臣政務官(当時)より、東日本大震災に際する各国の支援への謝意及び環境、気候変動、自然災害の分野における具体的な支援を表明した。また、2014年11月にネパールで開催された第18回首脳会議では、エネルギー、青少年交流、民主化・平和構築、防災の分野における日SAARC協力の強化に関する岸田外務大臣ステートメントを小川駐ネパール大使兼SAARC常駐代表が代読した。
- (2)我が国は、SAARCが南アジア地域の安定と発展の枠組みを提供し得る機構として重要であるとの観点から、SAARCの活動と基盤強化のため、1993年に「日本・SAARC特別基金」を設立し、各種支援及び交流事業を実施してきている。特に、人的交流事業に関しては、2007年1月にフィリピンで開催された東アジア首脳会議(EAS)で安倍総理が提唱した「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYSプログラム)」の一環として、本件特別基金による青少年交流事業を実施し、2007年から2011年の5年間にSAARC諸国から理工系学生、日本語学習者・教師、高校生等910名の青少年を招聘した。これに続き、2012年度には「キズナ強化プロジェクト」によりSAARC諸国から大学生・高校生等433名の青少年を招聘した。また、2013年1月にインドネシア訪問中の安倍総理は、2007年から実施したJENESYSの後継として、アジア大洋州諸国及び地域との間で青少年交流事業「JENESYS2.0」を実施することを発表し、これまでSAARC諸国から1,247名の青少年を招聘している。
- (3)我が国は、SAARC諸国の共通の課題である電力の安定供給に向けた取組を支援するために、域内関係者の協議・提言の場として「日・SAARCエネルギー・シンポジウム」を開催している。2005年11月の第13回SAARC首脳会議においてSAARCへのオブザーバー参加が認められたことを機に、我が国は、2006年以来過去7回に亘りシンポジウムを開催した。各シンポジウムでは、協議の内容が提言にまとめられ、SAARC事務局等と共有されている(各日・SAARCシンポジウムの提言参照)。
【参考】最近のSAARC首脳会議及び域内協力の概要
- 1998年7月にコロンボで開催された第10回SAARC首脳会議は、直前の印パ両国の核実験により地域の緊張が高まり、一時開催も危ぶまれたが、同首脳会議の場で、核実験後初の印パ二国間首脳会談が実現した。
- 2002年1月、カトマンズにおいて3年半振りに第11回首脳会議が開催され、テロ防止に関するSAARC地域協定へのコミットメント再確認、南アジア自由貿易地域(SAFTA)枠組みの早期構築、女性及び児童の人身売買禁止に関するSAARC地域協定締結等が合意された。なお、同首脳会議は、2001年12月のインド国会議事堂襲撃事件により印パ関係が著しく緊張する中で開催されたため、本格的な会談には至らなかったものの、会議の合間に両国首脳が非公式に接触する等、印パ関係の悪化に歯止めをかける上で一定の成果を生む機会となった。
- その後、インド側カシミールにおいてイスラム過激派による越境テロが頻発したため、2002年5月から6月にかけ、印パ関係は一触即発の危機に瀕した。その後、同年8月、開催国であるパキスタンは、次回SAARC首脳会議を2003年1月にイスラマバードにて開催することを提案したが、インドほかの参加表明が遅れたこともあり、開催は実現しなかった。
- 2003年に入り、大使の交換(7月)や、ニューデリー・ラホール間のバス運行再開(7月)など、印パ関係改善に向けた具体的措置がとられる中で、7月9日、SAARC常設委員会(次官級)において、2004年1月に次回SAARC首脳会議を行うことで合意。この合意に基づき、2004年1月、イスラマバードにて第12回SAARC首脳会議が開催され、SAFTA(南アジア自由貿易地域)枠組協定、テロ防止地域協定追加議定書、SAARC社会憲章が採択されたほか、会期中に、バジパイ・インド首相とムシャラフ・パキスタン大統領及びジャマリ同首相との会談がそれぞれ実現したことにより、印パ両国間の対話が開始されることとなった。
- 経済面での加盟国間の協力に関しては、1995年12月に発効した南アジア特恵貿易協定(SAPTA)による域内での関税引き下げにより、域内貿易活発化及び域内経済協力の強化を目指し、1998年11月、約5500品目を対象とする第3ラウンドの交渉が終了した。また、2003年末までに第4ラウンドの交渉が終了し、インド・パキスタン間で最多品目の関税譲許が合意された。
2004年1月の首脳会議で枠組協定が合意されたSAFTAにより、インド、パキスタン、スリランカは2006年1月から7年間で、またそれ以外の加盟国は10年間で、関税率を0-5%にすることに合意した。SAFTAは、発効の条件であったSAARC全加盟国の署名・批准が行われたことにより、2006年1月1日から発効した。SAARC各国は、SAPTAでは特定品目においてのみ特恵関税を提供していたが、SAFTAにおいては原則として(今後作成されるネガティブ・リスト上の品目を除き)域内関税率を0-5%にすることになる。 - 2005年1月、バングラデシュにおいて創立20周年を記念する第13回首脳会議が開催されることになっていたが、その前年末に発生した大地震・津波により、SAARC加盟国が多大なる被害を受けたため、延期された。2月に日程が再調整されたものの、今度は開催地ダッカ(バングラデシュ)の治安情勢が不安定になったことに加え、ネパールでギャネンドラ国王がデウバ首相を解任、主要政党関係者の自宅軟禁などの措置を取ったため、インドのマンモハン・シン首相はSAARC首脳会議への不参加を表明、結果的にSAARC首脳会議が延期された。
- 2005年11月、バングラデシュにて第13回首脳会議が開催された。同会議では、アフガニスタンの加盟及び日本と中国のオブザーバー参加が原則承認された。また、「ダッカ宣言」が採択され、今後10年を「行動の10年」とする旨宣言したほか、SAARC開発目標(SDGs)を承認し、SAARC貧困削減基金(SAPF)の設立を決定した。
- 2007年4月、インドにて第14回首脳会議が開催され、オブザーバーとして我が国と中国、並びに米国、EU及び韓国(これらの国は前年8月の外相会合でオブザーバー参加が承認)が初めて参加した。同会議では、アフガニスタンの新規加盟及びイランのオブザーバー参加が承認された。また、開会式では、麻生外務大臣(当時)が南アジアを「自由と繁栄の弧」の中心として位置づけるとともに、我が国として民主化・平和構築、域内連携促進、人的交流促進の各分野におけるSAARC支援を実施することを表明した。また、同会議では、「ニューデリー宣言」が採択され、域内連結性(Connectivity)の重要性を確認したほか、広域運輸インフラの整備、SAFTA(南アジア自由貿易圏)の実施、SDF(SAARC開発基金)の早期運用開始、テロ対策等の分野における協力を推進していくことで一致し、また、南アジア大学、SAARC食糧銀行の設置等について合意がなされた。
- 2007年12月にデリーで開催された外相会合においてモーリシャスのオブザーバー参加が承認された。
- 2008年8月、スリランカにおいて第15回首脳会議が開催され、我が国からは小原外務省アジア大洋州局参事官が出席し、民主化・平和構築、域内連携促進、人的交流促進での具体的協力を内容とする高村外務大臣のメッセージを発出した。同会議では、「人民の成長のためのパートナーシップ」と題するSAARC首脳会議宣言および「食糧安全保障に関するコロンボ声明」が採択された。また、「オブザーバー国との協力に関するガイドライン」が承認された他、豪州及びミャンマーのオブザーバー参加が承認された。その他、南アジア自由貿易圏(SAFTA)へのアフガニスタン加盟に関する議定書の署名、SAARC開発基金(SDF)憲章への署名とSDF事務局のブータン設置、SAARC犯罪共助条約の署名、南アジア地域標準機関(SARSO)設立協定の署名、南アジア大学の2010年までの開校合意等の成果があった。
- 2009年2月、スリランカで外相会合が開催され、テロとの闘いに関するSAARC内メカニズム強化に関する専門家グループの設置や、世界的経済危機の途上国経済への影響緩和のため国際機関及び開発パートナーに対する返済モラトリアムの必要性につき合意された。
- 2010年、ブータンにおいて第16回首脳会議が開催され、我が国からは西村外務大臣政務官(当時)が出席し、気候変動・環境分野での具体的な支援や南アジアの安定と発展に資する支援を引き続き行う旨を内容とするスピーチを行った。同会議では、「緑豊かで幸せな南アジアに向けて」と題する首脳宣言および「気候変動に関するティンプー宣言」が採択された。また、SAARC開発基金(SDF)常設事務局(於:ブータン)の開所式の開催、貿易協力の促進と地域経済の統合のための「サービス貿易に関するSAARC協定」署名等の成果があった。
- 2011年11月、モルディブにおいて第17回首脳会議が開催され、我が国からは中野外務大臣政務官が出席し、東日本大震災に際する各国の支援への謝意及び環境、気候変動、自然災害の分野における具体的な支援を内容とするスピーチを行った。同会議では、 「架け橋を渡す」と題する首脳宣言が採択された。また、「災害緊急対応に関するSAARC協定」、「適合性評価認知に係る多国間取決めに関するSAARC協定」、「地域基準実施に関するSAARC協定」、「種子バンクに関するSAARC協定」署名等の成果があった。
- 2014年11月、ネパールにおいて第18回首脳会議が開催され、我が国からは小川駐ネパール大使兼SAARC常駐代表が出席し、エネルギー、青少年交流、民主化・平和構築、防災の分野における日SAARC協力の強化に関する岸田外務大臣ステートメントを代読した。同会議では、SAARC加盟国首脳により、「電力に関するSAARCエネルギー協力協定」に署名がなされた他、今次首脳会議のテーマである「平和と繁栄のための統合の深化」のための南アジア自由貿易圏(SAFTA)及びSAARCサービス貿易協定(SATIS)の効果的な実施、SAARC開発基金(SDF)の強化、今後3ヶ月以内の自動車に関する協定及び鉄道に関する協定案の確定に向けた関係閣僚会合の開催など合計27項目の協力方針を含む「カトマンズ宣言」が採択された。

