欧州安全保障協力機構(OSCE)
欧州安全保障協力機構(Organization for Security and Co-operation in Europe)の概要
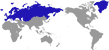
1 OSCEとは
- (1)欧州安全保障協力機構(OSCE:Organization for Security and Co-operation in Europe)は、欧州、中央アジア、北米の57か国から成る世界最大の地域安全保障機構。OSCEは、幅広い安保問題の政治的対話を行う場の提供と、個人・社会の生活改善のための共同の行動により、紛争予防、危機管理、紛争後の再建を通じて、加盟国間の相違を橋渡しし、信頼醸成を行う機関。事務局をウィーンに置き、毎週、常設理事会(大使級)を開催している。
- (2)OSCEの安全保障についての包括的な認識は、政治・安全保障、経済・環境及び人権・人道という三つの「側面(dimensions)」を包含するものである。そのため、OSCEの活動は、政治・軍事、経済・環境、人権・人道分野等を含む包括的なアプローチにより、各種課題(軍備管理、テロ対策、良い統治、エネルギー安保、人身売買対策、民主化、報道の自由、少数民族保護)に取り組んでいる。なお、包括的アプローチとは、安全保障を軍事、経済・環境、人権・人道分野等を含む包括的なものと捉えた活動のこと。
2 成立の経緯とその後の発展
(1)欧州安全保障協力会議(CSCE:Conference on Security and Co-operation in Europe))の成立
1954年、モロトフ・ソ連外相が米英仏ソ4か国外相会議において、欧州の安全保障に関する国際会議の開催を初めて提唱。その後、東西ブロック間の種々の交渉を経て、1975年にヘルシンキにて首脳会合が開催され、安全保障及び相互協力に関する「(注)最終文書(Final Act)」を採択し、CSCEが設置された。
【ヘルシンキ最終文書の主要点】
ア 欧州における安全保障に関する諸問題(「第1バスケット」)
- 加盟国の相互関係を律する諸問題(主権平等、武力行使または武力による威嚇の禁止、国境不可侵、領土保全、紛争の平和的解決、内政不干渉、人権並びに基本的自由の尊重、民族の平等及び自決、国家間の協力、国際法上の義務の誠実な履行)
- 安全保障(軍事演習の事前通告及び軍事演習へのオブザーバー相互交換等の信頼醸成措置)
イ 経済、科学技術及び環境の分野における協力(「第2バスケット」)
ウ 人道及びその他の分野における協力(「第3バスケット」)
- 人的接触(離散家族の再会、異なる国の市民との結婚等)
- 情報(新聞等の刊行物の配布、ジャーナリストのビザ取得等)
- 文化協力と交流
(2)CSCEの制度化・組織化
ヘルシンキ首脳会合以降、CSCEの枠内では、「最終文書」のフォロー・アップのため、ベオグラード、マドリッド、ウィーンで包括的な再検討会議が開催されたほか、紛争の平和的解決、地中海問題、経済協力、環境、情報、人権、文化遺産等に関する各種の専門家会合、フォーラム等が開催されてきた。
その後、ソ連の崩壊、東欧諸国の民主化、ドイツ統一等の欧州情勢の激変を受けて開かれた1990年11月のパリ首脳会合においては、東西冷戦の終焉を宣言するとともに、これまで会議の連続体であったCSCEの新たな役割と制度・組織が規定された。1992年7月には、制度化されたCSCEにおける初めての首脳会合がヘルシンキにおいて開催され、共通の基本的価値観に基づく域内の安定を追求する枠組みとして、1)紛争予防、危機管理及び紛争解決のための機能強化、特に平和維持活動の創設、2)安全保障協力フォーラムの設立等について合意した。また、政治宣言では域外国(日本及び地中海諸国)との関係を規定した。
(3)OSCEへの発展
1994年12月のブダペスト首脳会合では、CSCEの機構化の必要性が認識され、1995年1月より「欧州安全保障協力機構(Organization for Security and Co-operation in Europe)」と名称を変更することが決定されるとともに、外相理事会や常設理事会等の役割や議長国の任期等につき規定された。
その後OSCEは、加盟国の安全を守る第一義的な役割ではなく、多くの加盟国を擁する政治安全保障フォーラムとして、米、加及び欧州から中央アジアに至る57か国が加盟する欧州の地域的国際機構として、軍事的な側面からの安全保障のみならず、経済から人権に至るまでの包括的な分野を対象として、コンセンサス・ルール、予防外交(紛争当事者に対する早期警告、事実調査など)、非強制的手段(第三国により構成されるミッションの派遣、紛争に対する加盟国の共通の意思表明等)を基本とした活動を行っており、各国での選挙支援・選挙監視任務もOSCEの中心的活動の1つになっている。
3 加盟国
- (1)現加盟国 57か国
- (2)加盟国数の変化(原加盟国数は35か国)
- 1990年10月:ドイツ統一により34か国。
- 1991年6月:アルバニアの参加により35か国。
- (1991年7月:ワルシャワ条約機構、解体議定書に署名し消滅。)
- 1991年9月:バルト3国の参加により38か国。
- 1992年1月:ロシア(ソ連の地位を承継)及び旧ソ連10か国(グルジアを除く)が参加し48か国。
- 1992年3月:クロアチア、スロヴェニア、グルジアが参加し51か国。
- 1992年4月:ボスニア・ヘルツェゴビナが参加し52か国。
- (1992年7月:ユーゴ(現セルビア・モンテネグロ)の代表権を停止。)
- 1993年1月:チェコ、スロバキア分離独立により53か国。
- 1995年10月:マケドニアの参加により54か国。
- 1996年4月:アンドラの参加により55か国。
- (2000年11月:ユーゴの参加(新規加盟扱い))
- 2006年6月:ユーゴがセルビアとモンテネグロに分離独立したことにより56か国。
- 2012年11月:モンゴルの参加により57か国。
4 機構・各種会合
(1)機構等
ア 議長国
OSCEの運営の中心であり、議長国の外相が議長を務める。議長国は1年毎に交代。議長国を補佐する組織として、トロイカ(現議長国、前議長国及び次期議長国の3か国により構成)、個人代表制度を設けている。議長国は就任3年前の外相理事会で決定されるのが最近の慣行となっている。
イ 事務総長(SG:Secretary General)
OSCE諸機関を管理・統括するとともに、OSCEとしての諸策の立案・履行に関してOSCE議長の補佐等を行う。任期は3年(再任可能)。全加盟国によるコンセンサスにより選出。
ウ 事務局等
OSCEの諸活動の実施を補佐する機関で、紛争予防センター(CPC:Conflict Prevention Center))等から構成される。OSCEの事務局及び諸機関は、約560名のスタッフから成る(その他、各種ミッションを含めると合計約2,480名)。
エ 民主制度・人権事務所(ODIHR:Office for Democratic Institutions and Human Rights、ワルシャワ)
民主主義制度の発展のための助言や各種会議の開催、選挙管理・監視、憲法・法規則の起草支援、人権関連コミットメントの履行の監視等、人権分野を中心とした活動を実施。
オ 少数民族高等弁務官(HCNM:High Commissioner on National Minorities、ハーグ)
少数民族問題をめぐる紛争を未然に防止するため、早期警告を発出するとともに、関係当事者に対して助言、勧告を行う。
カ メディアの自由に関するOSCE代表(ウィーン)
民主主義の発展にはメディアの適切な発展が必要との観点から、OSCE加盟国のメディアの活動に関してモニターを行い、これが侵害される恐れがある場合には早期警告を行うが法的な権限はない。
(2)各種会合等
ア 首脳会合(Summit)
OSCEの最高意思決定機関。議長国トロイカを中心として企画・運営され、原則として隔年毎に開催されることとされていたが、1999年11月のイスタンブール首脳会合後は、2010年12月にアスタナ首脳会合が開催されたのみ。
イ 外相理事会(Ministerial Council)
首脳会合に次ぐ上位の意思決定機関。OSCEに係る諸問題の協議や決定を行う政治的協議を外相レベルで行うためのフォーラムであり、原則として少なくとも年1回開催するとされている。
ウ 常設理事会(PC : Permanent Council)
週1回ウィーンにて開催される大使級会合。OSCEの施策の継続性を図るため、1994年1月に設置され、安全保障協力フォーラムとともにOSCEの実質的な政策決定機関。準備委員会(Preparatory Committee)、経済・環境小委員会等の下部機関を有する。2007年より、前年の外相理決定に基づき、OSCEの3つのバスケットに対応する3つの小委員会が設置された。
エ 安全保障協力フォーラム(FSC:Forum for Security Cooperation)
週1回ウィーンにて開催される大使級会合で、軍備管理・軍縮や信頼・安全醸成に関する事項を協議。1992年9月に設置された。
オ 経済・環境フォーラム(Economic and Environmental Forum)
プラハにおいて従来年1回開催され、OSCEによる包括的安全保障の3本柱の一つである「経済・環境の側面」の諸問題を中心に協議。政策決定機能は有さないフォーラムとして開催されている。
カ その他
OSCEには経済フォーラムのほか主要な年次行事として、年次安全保障レビュー会合(例年6月、於:ウィーン)、人的側面履行会合(於:ワルシャワ)がある。
5 我が国及び域外国との関係
(1)我が国との関係
ア 経緯及び意義
我が国は、冷戦終焉後の新たな国際新秩序の構築、価値を共有する日米欧間の協力関係の強化、我が国に直接・間接に影響のある問題への立場の表明等の観点より、CSCE(当時)との関係強化を追求し、その結果、1992年7月のヘルシンキ首脳会合で「制度的対話の枠組み」が構築された。
イ 我が国の地位
我が国は、1992年のヘルシンキ首脳会合政治宣言及び同附属文書において、首脳会合、外相理事会、高級理事会、その他の会議に招待され、会議においては発言権を有することが規定された。ただし、決定及びその準備には関与できない。現在は、2006年11月に採択された手続規則に基づき、日本は恒常的に常設理事会、安全保障協力フォーラムに参加できるほか、準備委員会(Preparatory Committee)や3つの小委員会にも参加が認められている。
ウ OSCE諸活動への参加状況
- 首脳会合:
- 1992年7月、松永政府代表(当時)(主催国フィンランドの「特別ゲスト」)
- 1994年12月、松永政府代表(当時)(於:ハンガリー)
- 1996年12月、松永政府代表(当時)(於:ポルトガル)
- 1999年11月、有馬政府代表(当時)(於:トルコ)
- 2010年12月、伴野外務副大臣(当時)(於:カザフスタン)
- 外相理事会:
- 1992年12月、斉藤外務審議官(当時)(於:スウェーデン)
- 1993年11月、福田外務審議官(当時)(於:イタリア)
- 1995年12月、柳井外務審議官(当時)(於:ハンガリー)
- 1997年12月、丹波外務審議官(当時)(於:デンマーク)
- 1998年12月、丹波外務審議官(当時)(於:ノルウェー)
- 2000年11月、有馬政府代表(当時)(於:オーストリア)
- 2001年12月、高野外務審議官(当時)(於:ルーマニア)
- 2002年12月、高野外務審議官(当時)(於:ポルトガル)
- 2003年12月、田中外務審議官(当時)(於:オランダ)
- 2004年12月、川口総理大臣補佐官(当時)(於:ブルガリア)
- 2005年12月、塩崎外務副大臣(当時)(於:スロベニア)
- 2006年12月、岩屋外務副大臣(当時)(於:ベルギー)
- 2007年11月、小野寺外務副大臣(当時)(於:スペイン)
- 2008年12月、伊藤外務副大臣(当時)(於:フィンランド)
- 2009年12月、田中駐オーストリア大使(当時)(於:ギリシャ)
- 2011年12月、飯村政府代表(当時)(於:リトアニア)
- 2012年12月、榛葉外務副大臣(当時)(於:アイルランド)
- 2013年12月、飯村政府代表(当時)(於:ウクライナ)
- 2014年12月、河野政府代表(於:スイス)
- 2015年12月、武藤外務副大臣(当時)(於:セルビア)
- 2016年12月、岸外務副大臣(於:ドイツ)
- 2017年12月、中根外務副大臣(当時)(於:オーストリア)
- 2018年12月、阿部外務副大臣(当時)(於:イタリア)
- 2019年12月、中谷外務大臣政務官(於:スロバキア)
- OSCEとパートナー国との共催会議
- 2000年12月、河野外務大臣(当時)(於:日本)
- 2001年3月、神余外務省欧州局審議官(当時)(於:韓国)
- 2002年6月、神山駐オーストリア大使館参事官(当時)(於:タイ)
- 2004年2月、川口外務大臣(当時)(於:日本)
- 2005年4月、篠田外務省欧州局審議官(当時)(於:韓国)
- 2006年4月、高須人間の安全保障大使(当時)(於:タイ)
- 2007年6月、片上外務省欧州局参事官(当時)(於:モンゴル)
- 2008年11月、佐藤駐アフガニスタン大使(当時)(於:アフガニスタン)
- 2009年6月、中曽根外務大臣(当時)(於:日本)
- 2010年5月、川村外務省欧州局政策課長(当時)(於:韓国)
- 2011年5月、上月外務省欧州局参事官(当時)(於:モンゴル)
- 2012年2月、上月外務省欧州局審議官(当時)(於:タイ)
- 2013年3月、引原外務省欧州局参事官(当時)(於:豪州)
- 2014年6月、岸田外務大臣(於:日本)
- 2015年6月、武藤外務省欧州局参事官(当時)(於:韓国)
- 2016年6月、相木外務省欧州局審議官(於:タイ)
- 2017年6月、宮川外務省欧州局審議官(於:ドイツ)
- 2018年11月、在豪大古谷公使(於:豪州)
- 2019年9月、阿部副大臣(当時)(於:日本)
- 安全保障協力フォーラム:1992年10月以降、駐オーストリア大使等が出席(週1回開催)。
- 常設理事会:1994年1月以降、駐オーストリア大使等が出席(週1回開催)。
- ODIHR選挙監視ミッションへの要員派遣:1992年に旧ユーゴスラビアへ派遣して以来、マケドニア、ボスニア、クロアチア、コソボ、ウクライナ、キルギス、カザフスタン等での選挙監視などに要員を派遣。



