外交史料館
戦前期「外務省記録」
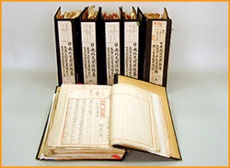
戦前期「外務省記録」は外交史料館所蔵史料の主要なものです。
外交活動にともなう在外公館との往復電報・公信類をはじめとする貴重な史料が、外務省創立以来第2次大戦終結までの約80年にわたり、約4万を越えるファイルに整理・編さんされています。
このうち明治・大正期の記録は、1門(政治)、2門(条約)、3門(通商)など8門に、また昭和戦前期の記録は、第2次大戦終戦関係も含み、A門(政治・外交)、B門(条約)、E門(経済)など16門にそれぞれ分類されています。
外交史料館ではこれら戦前期「外務省記録」を、原則として原本で閲覧することができます。
また、アジア歴史資料センターのホームページでは、同ファイルをインターネットで閲覧することができます。
2017年8月現在、明治・大正期の1門・2門・3門(8類、9類を除く)・5門・6門(1類8項3-6号まで)・7門、昭和戦前期のA門・B門・C門・E門・F門・G門・H門・I 門・M門・N門・Z門が掲載されております。あわせてご利用ください。
- 戦前期外務省記録分類表
解説:「外務省記録」について
1 外務省記録とは
外務省では、創設当時から外交活動にともなう記録文書の重要性を認め、創立の翌年、1870年(明治3年)には「編輯掛」を設置し、外務省独自の分類方法を用いて執務書類の整理・分類事務を始めていました。
以来、その整理・分類方法には何度か改訂が加えられましたが、現行の外務省文書整理方法の基礎ともいえる1931年(昭和6年)作成の「外務省文書編纂規定」をもとに「外務省記録」を説明すると、まず公信、電信、契約書、諸帳簿等、公務に関するすべての書類のうち執務上処理済となったものを「記録文書」とし、この「記録文書」を事件・事項別に編纂(ファイリング)したものを「記録」としています。
したがって「外務省記録」とは、一件ずつの書類を示すのではなく、処理済の書類(記録文書)を事件・事項別に編纂(ファイリング)したもの、つまりファイルの単位を指しています。
2 外務省記録の保存と消失
(1)外務省記録の保存
外務省では前述のように記録の重要性を認めると同時に、これら記録の保存に細心の注意を払ってきました。すなわち、大正期に建設した防火・防災設備を完備した鉄筋コンクリート4階建の書庫によって、関東大震災の折にも、外務省記録はほとんど消失することはありませんでした。また、戦時中は膨大な記録を埼玉県、神奈川県の数箇所の倉庫に疎開させることなどによって、空襲等の戦禍を免れることに努めました。
(2)外務省記録の消失
このような記録保存の努力にもかかわらず、外務省記録は過去数回消失の被害を受けています。1942年(昭和17年)1月の外務省の火災、1945年(昭和20年)5月から8月の空襲等では、書庫内の記録には被害はありませんでしたが、執務用として各局課に貸出中であった貴重な記録が多く消失しました。
また、戦後は1946年(昭和21年)2月ワシントン・ドキュメント・センター(W.D.C)による記録の接収、および極東軍事裁判に際しての記録の押収等によって、貴重な記録が消失してしまいました。なお、このようにして消失した記録の主なものには、2門の条約改正関係、A門の対中国関係、B門の通商条約関係の記録等があります。
(3)「松本記録」による消失記録の補填
上記のような消失記録を補填しうる史料として挙げられるのが「松本記録」です。
「松本記録」とは、故松本忠雄元衆議院議員が、外務参与官および外務政務次官在任中(昭和8年12月より14年1月)に、政治、外交、条約関係等の重要文書を筆写し、所蔵していたもので、戦後、遺族より外務省に寄贈されました。
この記録類は筆写文書であるため、本来の「記録文書」とは異なる性質のものですが、前述の戦災等で消失した重要な記録文書を補填する上で貴重なものであることから、記録分類法に倣って分類番号を付し、「松本記録」として本来の記録とは区別して整理しました。
3 外務省記録の特徴
(1)事件・事項別編纂
外務省記録は事件・事項別に編纂されているということが大きな特徴です。したがって、各外交官が在職中に係わった執務文書を個人別にまとめたり、諸外国に設置された大使館、総領事館別に電報や公信類をまとめるという形態にはなっていません。
(2)分類番号と件名
外務省記録には、外務省独自の分類方法によって設定された分類番号と、記録の中に収録されている記録文書の内容を示す件名が付けられています。
記録の分類方法は階層式分類で、まず大項目である「門」が設定され、それぞれの「門」の中に中項目であるいくつかの「類」が設けられ、さらに「類」はいくつかの「項」に分類されています。
昭和期の記録に関しては、この「項」の次に細項目として「目」が設定されています。そして、最後に一件ごとの記録を示す「号」が付されています。なお、この分類番号および件名は、各時代に文書編纂事務を担当した部署(たとえば記録局)において記録編纂時に付されたものです。
(3)「本冊」と「別冊」
事件の経過にともない、その関係記録文書の内容が多面化したため、記録の基本的なまとまりである「本冊」から独立して、「別冊」という形をとって枝分れしていった記録もあります。
たとえば「倫敦海軍会議一件」(分類番号B.12.0.0.1)という記録ファイルには、「条約批准関係」(B.12.0.0.1-1)という別冊があり、この「条約批准関係」という記録にはさらに「米国ノ部」(B.12.0.0.1-1-1)や「英国ノ部」(B.12.0.0.1-1-2)、「日本ノ部」(B.12.0.0.1-1-3)等の別冊があります。これらはすべて本冊である「倫敦海軍会議」、そして別冊である「条約批准関係」に係わる記録です。なお、これら別冊には、本冊との関係が明確になるように、分類番号上に「号」の次に「-1」のように枝番号が付されています。また、本冊の中身がすべて独立して別冊になったため、本冊は「0冊」となってその件名だけが存在する記録も多くあります。
4 外務省記録の分類方法の変遷
明治初年以来、記録の分類方法は数回改変されていますが、1922年(大正11年)の「8門式分類法」の採用時に、明治初年以来の記録文書をすべて整理・編纂しなおしたので、明治・大正期の記録文書はすべて、「8門式分類」によって分類される結果となりました。
その後、多様化した外交問題に則した記録文書の編纂を目指し、大正末期より検討を続けた結果、1930年(昭和5年)から「ABC式分類」による編纂が開始されました。その際、「8門式分類法」により分類済の明治・大正期の記録は再編纂せず「旧記録」と総称し、新たに「ABC式分類法」によって編纂された昭和期の記録を「新記録」と称し、2つの記録群に区別しました。
「旧記録」「新記録」の特徴は以下のとおりです。
(1)「旧記録」(明治・大正期)
旧記録は、「政治」「条約」「通商」等の8つの門に大別され、記録の件名の多くが具体的に事件を表わす(一件体)ようになっています。なお、8門のうち第3門「通商」が、貿易、商業から交通、土地、博覧会等まで広範囲にわたる15の「類」に分類されていることも特徴の一つです。
(2)「新記録」(昭和戦前期)
この分類方法では、「政治・外交」「条約」「交通」「文化」等AからO、そしてZの16の門に大別されていますが、PからYまでの門は、新たに大項目を必要とする問題が発生することを考慮して未設定門となっています。
また、旧記録とは異なり、あらかじめ「類」「項」「目」までの項目を設定し、その中に該当文書を編纂していく方法をとったため、分類上は設定されていても実際に分類される記録がない分類項目もあります。そして、旧記録にはなかった「0類」「0項」という総記の意味をもつ「0」の分類項目を設けている(例、B門0類0項0目)こと、記録の件名が、機能的な分類法に倣って機能的に付けられていることなども特徴です。




