外交史料館
外交史料 Q&A
明治期
1890年代(明治23年~32年頃)
Question
1891年(明治24年)に来日したロシアのニコライ皇太子(Nikolai Aleksandrovich Romanov、後の皇帝ニコライ2世)が、警備の日本人巡査に襲われた、いわゆる大津事件に関する史料はありますか。
Answer
ニコライ皇太子は、シベリア鉄道起工式参加の途上、従兄弟にあたるギリシャのゲオルギオス親王(Prince Georgios)と共に親善のため来日し、長崎、鹿児島、京都など各地で大歓迎を受けました。しかし、1891年5月11日、琵琶湖遊覧の帰途、突如警備の巡査の一人であった津田三蔵(つだ・さんぞう)にサーベルで斬りつけられ、頭部を負傷しました。さらに斬りつけようとする津田に対して、ニコライ皇太子を乗せた人力車の車夫向畑治三郎(むこうはた・じさぶろう)と、ゲオルギオス親王を乗せた車夫北賀市市太郎(きたがいち・いちたろう)、そしてゲオルギオス親王の三人がニコライ皇太子を守り、津田を取り抑えるため活躍しました。この事件の概要および事後処理に関しては外務省記録「露国皇太子滋賀県大津ニ於テ遭難一件」に関連記録があり、主要なものは『日本外交文書』第24巻にも収録されています。
ニコライ皇太子の負傷は軽傷ですみましたが、事件後犯人津田の処罰をめぐって問題が生じました。大津事件の前年に日本人によるロシア公使館への投石事件があったため、駐日露国公使シェーヴィッチ(Dmitrii E..Schevich)は、ニコライ皇太子の来日に合わせて臨時に刑法を改正し、外国の皇族に対する暴力、暴行を日本の皇族に対するそれと同様に処罰するよう、青木周蔵(あおき・しゅうぞう)外務大臣に要請しており、青木外務大臣は、ニコライ皇太子を傷つける者は日本の皇族に対する罪と同様に処罰すると約束していたのです(ロシア公使館投石事件については、外務省記録「在本邦露国公使館ニ対シ本邦人暴行一件」に関連記録があります)。そのため、政府内では、津田に対しては大逆罪の適用等による死刑が妥当との意見が大勢を占めました。
しかし、大審院長であった児島惟謙(こじま・いけん)は、謀殺未遂を適用することを主張して、5月27日津田には無期懲役の判決が下りました。この判決に対してロシア皇帝アレクサンドル3世(AleksandrIII)は、7月3日、日本政府の処置に満足していると告げ、日本側はようやく安堵しました。
なお、事件後ニコライ皇太子は二人の車夫に年金としてそれぞれ1,000円ずつ下賜して、感謝の意を表しました。外務省記録「外国皇室並元首ヨリ金品下賜関係雑件 露国皇帝ヨリ向畑治三郎、北ヶ(ママ)市市太郎ヘ年金下賜ノ件」には、この年金の授受に関する記録などがあります。
1900年代~1912年(明治33年~45年頃)
Question
ベトナム民族運動の指導者として知られるファン・ボイ・チャウ(潘佩珠)が執筆した「海外血書」はありますか。
Answer
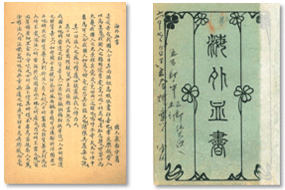 「海外血書」
「海外血書」
外務省記録「仏国内政関係雑纂 属領関係 印度支那関係 安南王族本邦亡命関係」に含まれています。
フランス植民地主義に抵抗し、1904年(明治37年)に「越南維新会」を結成したファン・ボイ・チャウは、翌1905年(明治38年)4月、ベトナム独立への援助を求めて日本に渡りました。日本では、大隈重信(おおくま・しげのぶ)や犬養毅(いぬかい・つよし)のほか、中国の変法運動に挫折し日本へ亡命していた梁啓超(りょうけいちょう)らと接触し、人材の育成が急務であるとの認識から、ベトナム青年の日本留学を呼びかけました。これに応じて来日したベトナム留学生は約200人を超えたとされ、こうした動きは「東遊運動」(トンズーうんどう)と称されます。
「海外血書」は、チャウが日本滞在中の1906年(明治39年)に執筆したもので、原稿はベトナムに送られて、ハノイに設立された「東京義塾」によって印刷・配布されました。その内容は、フランスの目的がベトナム人種の絶滅にあるとして、ベトナム人の民族的な自覚と魂の回復を促したもので、ベトナム人の中から福沢諭吉(ふくざわ・ゆきち)やルソーのような人物が現れることを期待する言葉で結ばれています。
外務省記録に含まれている「海外血書」は、1909年(明治42年)2月に東京の印刷所で550部印刷された小冊子で、漢字、字喃(チュノム/漢字を使用した民族文字)、国語(クオックグー/ラテン語を使用した民族文字)の3種類の文字で書かれています。この小冊子は警察から「危激ノ印刷物」とみなされ警告を受けますが、その際チャウは、法令の範囲内で今後も「本国人教育」のための出版物の発行および本国への発送を希望する旨を伝えています。しかしチャウは、日仏協約(1907年)を背景に反仏ベトナム人の取締り強化を日本に要求するフランスの動きなどもあり、翌3月に日本を離れて、活動の拠点を香港へと移しました。

