寄稿・インタビュー
BBCワールドニュース「Impact and Newsday」(英国)による川村外務報道官インタビュー
(2016年9月21日)
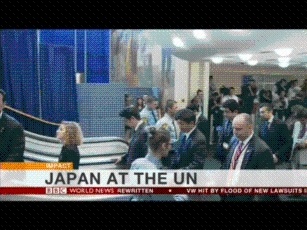
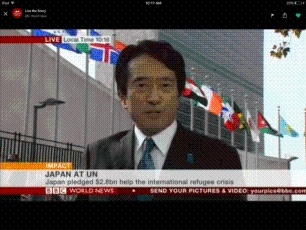
(アンカー)我々は国連内での重要な進展についてアップデートするが,安保理における世界の指導者達の関心は,シリア情勢に集中しているようだ。ニューヨークに集った指導者達は,停戦で残されたものを救おうとしている。しかし,シリア国内に援助を届けることに加え,戦火から逃げる人々をいかに助けるかという問題もある。オバマ大統領は世界的難民危機を「我々の共通する人間性の試練」と呼んだ。この点に関して,本日,日本の安倍晋三総理から重要な発表があった。今回は,スポークスパーソンである川村泰久外務報道官の話を伺う。彼にはニューヨークの国連本部から出演して頂く。お時間を頂き御礼申し上げる。シリアの人道状況につき,日本はどのような支援ができると表明したのか。
(川村外務報道官)まず,今般のアレッポでの人道支援団への攻撃に深い哀悼の意を表したい。国際社会全体で援助と状況の改善のために結束しなくてはならない。本日,我々はシリア情勢についてハイレベルで議論を交わす。日本の安倍総理は,現在このハイレベル会合に出席している。安倍総理はこの会合で追加の支援策を国際社会に提示する予定である。日本には二つの対策がある。一つは難民及び近隣国に緊急援助を提供すること,もう一つは,同時にこれらの国々によって進められている社会及び経済状況の再建向上に向けて取り組むことである。
(アンカー)難民に関して言えば,昨年日本は3人のシリア難民を受け入れた一方で,99%の難民申請を却下したと承知している。この状況は変化するのか。
(川村外務報道官)まず我々は中東及びシリア情勢の全体的な問題に取り組まなくてはならない。暴力的過激主義,テロ,そして難民の流出,また周辺国の抱える窮状や困難には根本的な原因がある。そのため,国際社会全体がこうした包括的な問題に効果的に取り組まなければならない。緊急の援助と同時に,これら根本的原因を除去すべく,周辺国の社会経済の再建を支援する政策や取組を日本は実施している。
(アンカー)全体像についての考え方は理解した。地域に対する日本の援助及び救援活動ということであろう。しかし難民について再度お伺いしたい。バラク・オバマ大統領が来年36万人の難民を受け入れる旨の50か国による公約を発表したばかりである。もし日本が昨年受け入れたのがシリア人難民たった3人であったのだとすれば,これは日本が支援できるようなことではないように思われる。
(川村外務報道官)日本は実際,これまでアジアその他の地域から難民を受け入れてきた。よって,難民に対し我々のドアは閉ざされていない。シリアや中東地域の難民については,こうした国々及び難民自身の負担を軽減するという我々の使命を実現するため,我々は引き続き国際社会と議論する。我々は,難民受入れ数を増加する旨発表する。日本は約150人のシリア人学生を受け入れ,これらの学生のご家族も同様に受け入れる。我々は取組を進めている。我々のドアが閉ざされることはない。しかし難民の問題,シリア及び周辺諸国の危険と安全に関する問題は切迫しており,そのため国際社会全体が団結してこの問題に対処する必要がある。ゆえに,志を同じくする各国,国連,米国及びその他コミュニティとともに,日本は引き続き協力していく。
(アンカー)より日本と関連した安全保障についてお聞きしたい。日本が懸念する問題のひとつは東シナ海での中国との緊張であると承知している。
(川村外務報道官)昨日,G7の外相がここニューヨークに集まり,現在の東シナ海の状況と南シナ海の諸問題に関し,国際社会に懸念を喚起するたなステートメントを発出した。問題は,法の支配を貫徹し,秩序を維持すべきである,ということである。力を用いるべきではない。現状変更のために強制力を用いてはならない。法の支配には,ハーグの国際仲裁裁判所による最近示された最終判断を含む。これらにかんがみ,国際社会はこの問題に対処すべきと考える。私達は,このように海における法の支配を貫徹し,これらの海域の平和と安定を維持するために,引き続き国際社会の注意を促していく。
(アンカー)日本に関する視聴者の最大の関心事の一つは,先月御自身の健康や退位の可能性について国民に語られた天皇陛下のことである。陛下の御健康面にかんがみ,この問題を議論するための政府の有識者会合はいつ開催されるのか。緊急性はあるのか。
(川村外務報道官)陛下の御言葉の後,安倍総理は数次にわたり,陛下の御言葉を踏まえ政府として何が可能かを検討していきたい,と明確に述べている。政府内でこの議論が継続されていくこととなる。
(アンカー)本日は国連総会で大変お忙しいなか時間を割いて頂いたことに御礼申し上げる。
(注:本仮訳はBBCが作成したものではなく,外務省契約業者が作成したものです。)

