「学生と語る」
令和2年度外務省セミナー「学生と語る」
開催報告

令和3年2月10日(水曜日)、令和2年度外務省セミナー「学生と語る」を開催しました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、今回は初のオンラインでの開催となりましたが、日本国内の各地から、さらには海外からも多くの方にご参加いただきました。
開会挨拶

鈴木 隼人 外務大臣政務官
鈴木政務官は、コロナ禍にあっても、外務省は変革に向けた新たなチャンスも見いだし、一丸となって、ポストコロナの新たな秩序・ルール作りに向けて、主導的に取り組んでいく決意であると述べるとともに、今日のこの講演が、参加者の学生の皆さんにとって、日本外交への理解を深めるのみならず、日本の歩むべき道について考える良い機会になることを期待していると、参加者にエールを送りました。
基調講演

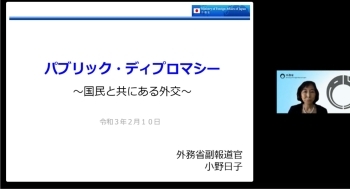
テーマ:パブリック・ディプロマシー、国民と共にある外交
講師:小野 日子 外務副報道官
本セッションでは、近年、認知度が高まってきている、広報文化外交(パブリック・ディプロマシー)について、その目的、伝統的な外交との違い、我が国のパブリック・ディプロマシーの具体的な活動等について、日々最前線でパブリック・ディプロマシーの推進に当たる、小野日子外務副報道官が講演しました。参加者からは、コロナ禍におけるパブリック・ディプロマシーのあり方や、国民と共にある外交の実践において重要なことについて等、多くの質問がありました。
参加者の感想
- 昨今の情勢の中で、日本の正しいイメージ、良いイメージを世界中の人に持ってもらうために非常に重要な施策であることを学べた。また、コロナ禍でも、様々な施策が行われていることに感心した。その一方で、ソフトパワーだけでは解決しない問題もあること、ハードパワーと組み合わせることの重要性についても語られ、新たな視点を得ることができた。
- SNSが重要なツールになってきている中で、どのようにして海外で親日的な世論を醸成していくのかという点に関して理解を深めることができた。
- 相手の事を考えた上での発信の大切さに大変共感した。
- ターゲットやメッセージの明確化、媒体の選択、迅速性、継続性などは、あらゆる課題に用いることのできるとても良い基準だと思う。
- 闇雲に行うのではなく、戦略を持って(対象、メッセージ、手段、タイムリー、継続的)、パブリック・ディプロマシーがなされていることを知り、より一層同分野に関心を持った。
- 外務省だけでなく、日本人一人一人が発信や交流をそれぞれの形で行う事がいかに重要か理解できた。
- 大学で学んだソフトパワーが実際に外交の現場でも用いられていることがリアルに実感できた。
講演
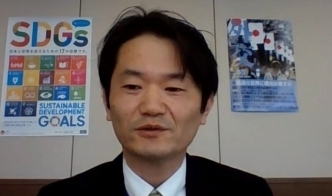

テーマ:コロナ禍におけるSDGsと国際協力
春田 博己 国際協力局地球規模課題総括課 課長補佐
既に国際社会の共通言語となっている「SDGs」。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中での位置付けや今後の課題、我が国としてこれをどのように進めて行く方針であるのかといった点について、直接この問題に携わる外務省員が説明を行いました。参加者からは、コロナの前後で国際協力やSDGsの推進にどのような変化があったのか、国際保健分野での日本の協力はどうなっているかなど、多くの質問が寄せられ、このテーマに対する関心の高さがうかがえました。
参加者の感想
- 「誰一人取り残さない」とは、裏返せば「一人ひとりが考えなければならない」という話が印象に残った。
- SDGsについての理解が深まったとともに、コロナ禍であるからこそ世界の課題解決への変革・行動を起こしていく必要があることを学ぶことができた。
- SDGsの様々なゴールは互いに連関しているため、多角的に考える必要があるという点が大変勉強になった。ある目標を追求しすぎると、その一方で別の目標が衰退する可能性もある中で、どのようにそのバランスを保っているのかということも考えてみたい。
- SDGsには全ての人々が取り組まなければいけないという言葉が印象に残った。コロナ禍においては各国で自国優先主義が台頭しているように思うが、互いに協力し合っていかなければならないと感じた。
- SDGs達成と今回のコロナ禍の関連性が明確に説明されており、分かりやすかった。イベント中に何度か登場していた「外交は政府だけで行うものではない」というフレーズが、その最たるものではないかと考える。
外務省員による体験談


パネリスト:森谷 泰韻 大臣官房人事課 課長補佐
新城 佳世 アジア大洋州課局南西アジア課 課長補佐
入省10年目にあたる省員2名が、これまでの外務省での自身のキャリアパスについての紹介に続き、事前及び講演中に参加者から寄せられた数々の質問に一問一答形式で答えていきました。「働く場」としての外務省の課題、10年を経て思う外務省の仕事の魅力、これまでで特に印象に残っている業務、コロナ前後の働き方の変化、学生へのアドバイス等、様々な質問が寄せられ、中堅職員として組織を支えつつ、外交の最前線で活躍している二人が、自らの体験談や思いを語りました。
参加者の感想
- 10年間のキャリアを経られた二人の話をとおして、自分の将来を想像する契機になった。今の仕事を楽しみ、やりがいを感じているのが伝わった。
- ネットで調べただけでは知り得ないような貴重な体験談を聞くことができた。自分もいずれはそうして世界を舞台に働きたい。
- 質疑応答の終盤で二人が述べていた内容「これさえあればいいといった万能薬のような経験というものは存在しないが、思わぬ経験が役に立つ時がある。」「好きなことに積極的に取り組み、その経験やそこで得た視点などをどう活かしていくかが大切である」が印象に残った。最後の学生に向けたメッセージも、自身の今後について再度考えさせられると同時に、勇気を与えてくれる言葉だった。
- 質疑応答の形式だったため、他の参加者の質問を聞け、自分では思いつかないような観点からも話を聞くことができた。
- 将来について不安に感じることや本当にこれで良いのかと感じることが多々あったが、今回の講演を通して自分のやりたいことに正直に努力していこうと感じた。
閉会挨拶
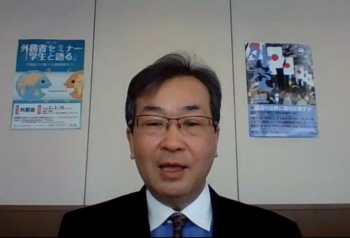
吉田 朋之 外務報道官
吉田外務報道官が、本日の講演テーマについて総括した後、参加者の皆さんから非常に熱のこもった、そして内容の充実した質問が多数寄せられ、日本の外交政策や国際情勢等に対する関心の高さや問題意識がひしひしと感じられた、これからも日本の将来を担う皆さんお一人おひとりが、様々な立場から、外交にかかわっていただき、日本国内そして国際社会でご活躍してほしい、と述べてセミナーを締めくくりました。
参加者の感想(全体)
- オンライン開催なので、地方から参加することができ、非常に貴重な話を聞けた。
- これまでにも国家公務員ガイダンスなど様々な省庁に関する話を聞いてきたが、やはり特定の省庁に限定された機会ではより深みのある話を聞くことができる。また、本来であれば東京で実施されるこのセミナーがコロナの影響でオンライン開催されたことは、地方在住者にとってはとても幸運なことであった。
- 学生同士での交流はなかったものの、他の学生の質問を聞いて、自分にはなかった視点を学ぶという発見もあり、間接的に交流できたと感じた。
- 今まで参加したことがなかったが、オンラインにより初めて出席でき、貴重な話を聞けた。今回のセミナーだけで完結するのではなく、今後に生かせる内容だったと思う。
- 自分自身も15年近く海外で生活をしてきたが、このセミナーをとおして国際関係について新たな視点を得ることができた。
- 新型コロナウイルス感染拡大の中、自分がどのように国際社会を考えて、将来を考えるべきなのか、その指針のヒントを得ることができた。
- 次回は「自分が思ってもいない場所に赴任した時の経験」という話から登壇者オリジナルの経験談や考え方について聞きたい。
- 本日のセミナーを通じて、新型コロナウイルスという世界の脅威が外交にどのような影響を及ぼし、変化をもたらしているかという点について理解を深められた。

