採用情報
国際協力局国別開発協力第三課 課長補佐 竹鼻千尋様
(文責:磯貝茉莉衣,川端万貴)
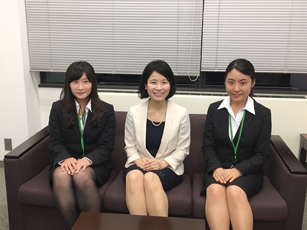


磯貝茉莉衣(京都大学公共政策大学院1年・経済安全保障課インターン),川端万貴(東京大学教養学部4年・中東第1課インターン)の2名の平成29年度外務省インターン生が,外務省で過ごす中で感じた印象や疑問点について,国際協力局国別開発協力第三課の竹鼻千尋さん(入省10年目)にお話を伺いました。
多様な人材の集まるチャレンジングな職場環境,在外公館でのユニークな経験など,外務省で働くことの魅力を,熱く語っていただくことができました。その座談会の模様を紹介したいと思います。
1 竹鼻様の今までのご経歴をお聞かせください。
2008年に入省し,今年ではや10年目になります。実は大学生の時に,皆さんと同じく外務省でインターンを行い,「インターンが見た外務省」の第一回目のインタビューを行ったので,今日こうしてインタビューを受ける側になったことがとても感慨深いです。
「見習い」から担当官へ
最初に配属されたのは,経済局の国際貿易課です。当時は,WTOドーハラウンド交渉が大詰めを迎えていた頃。国内で様々な意見が対立する中,常に「国益とは何か」を問いながら,日本としての方針をまとめるべく関係省庁と議論を尽くしました。最終的に妥結には至りませんでしたが,2年目には,交渉の一分野である「環境と貿易」を担当することに。まだ見習い気分でいたある日,当時の上司に,「君が日本の方針を立てなくて,誰が立てるんだ!」と渇を入れられ,仕事に対する意識が180度変わりました。上司が責任を取りつつ若手を育てようとする姿勢は,外務省の魅力の一つだと思います。
フランスでの出会い
3年目からは,語学研修のため,フランス国立行政学院(ENA)に留学。世界各国から同世代の行政官が集まる環境は,さながらミニチュアの国連のようでした。自国の立場を踏まえつつも本音で語り合った友人とは,その後国際会議などで再会することもあり,私の一生の財産です。また,カリキュラムの一環として,在モロッコ・フランス大使館でインターンをし,外交大国を自負するフランスの手法を間近に垣間見ることもできました。
初めての大使館勤務
研修後は,フランス語圏であるアルジェリアの大使館に赴任したのですが,着任早々,テロ事件が発生し,邦人が巻き込まれるという事態に陥りました。初めての通訳機会が,東京から駆けつけた大臣政務官がアルジェリアの外務大臣に「人命を最優先に」と訴える会談となり,メモを取る手が震えたのを思い出します。このような事態を未然に防ぐのが外務省の責務ではありますが,極限下で危機管理のなんたるかをたたき込まれました。
中堅職員として 環境,パブリック・ディプロマシー
帰国後は,環境条約の策定から実施を担う地球環境課に配属され,1年の3分の1近くは,ジュネーブやワシントンDC,ナイロビなど各地で開催される国際会議に出張していました。その後は広報文化外交戦略課に異動し,パブリック・ディプロマシー強化のため,日本の政策や,歴史認識,領土問題などに関する立場を発信しました。
外務省初,女性秘書官に
2016年8月,内閣改造が行われると,外務省初の女性秘書官として,外務大臣政務官を支えることになりました。「政治主導」が叫ばれて久しいですが,そもそも,官僚が政策オプションを提示し,政治家が決断するのは議院内閣制の下での自然な姿です。政務官との日々のやり取りは,このプレゼンの方法を磨く訓練になるともに,「国民の視点」を改めて想起させてくれました。また,一年間で22か国に出張し(移動距離はなんと地球6周分に相当!),「地球儀を俯瞰する外交」の一翼を担いました。印象的だったのは,日本では必ずしも知名度が高くない国の首脳たちが,自分自身の経験から,日本への感謝や期待を述べていたことです。こうした信頼感は日本外交の大きな強みであり,先人たちが築いた財産を絶やしてはいけないと気が引き締まりました。
2 外務省を志されたきっかけは何ですか。
アメリカの高校に留学中,高校生版のサミットに参加し,日本の現状が他国に正しく伝わっていないのではないか,また翻って我々日本人も世界の現状を把握できていないのではないか,と危機感を感じたのが直接のきっかけです。この状況に一石を投じたい,世界には日本の,日本には世界の正しい姿を伝えたいと思いました。メディアにも関心がありましたが,外務省の国際報道官室でのインターンシップを経て,自分は報道する側よりも報道されるものをつくる側になりたいと思い,外務省に決めました。
3 インターンをしていた時と入省後で外務省に対する印象は変わりましたか。
インターンでいた時には,外務省には,自分の信念に沿って自由に仕事をしている人が多いと感じました。入省後もその印象は大きく変わりませんが,その水面下には,様々な日々の分析や関係者との調整があるということを知りました。
4 現在の課ではどのようなお仕事を担当されていますか。
現在は,中東・アフリカ・欧州への経済協力を担う部署で,TICAD閣僚会合に向けた準備をしています(インタビュー当時)。アフリカでは,国際資源価格の低下を受け,モノカルチャーからの脱却が喫緊の課題となっています。日本は,持続可能な開発がアフリカの将来を支えるという考え方の下,日本の技術を用いた質の高いインフラの整備や,「カイゼン」方式の共有をとおして,アフリカの取組みを後押ししています。アフリカの国々とこのような協力関係を築くことは,日本のソフトパワー増進のみならず,国際場裏における連携を強化する観点からも大切です。
5 外務省における仕事の特色,またご自身の今後の目標についてお聞かせください。
外務省の仕事の特徴の一つに,言葉が道具という点があると思います。民間企業が物やサービスを生み出し,他省庁が法律を作るのに対し,言葉で人を,国を動かすのが私たちの仕事です。
このことを実感する場面の一つが,会談において通訳をしている時です。私の場合はフランス語ですが,先方の母国語でコミュニケーションを取ることで,相手の懐に入り,より多くを引き出せたと感じることが少なからずあります。一方,格調や正確なニュアンスを欠いたフランス語で訳しては逆効果となってしまいます。時間が限られた会談においては最初の数分が大きな決め手になることも少なくなく,これからも言葉を磨いていきたいと思います。
また,小さな一歩であれ,歴史に痕跡を残すことができた時にはやりがいを感じます。WTOドーハラウンド交渉はまだ続いていますが,当時担当官として打ち出した日本提案が,数年後APECに引き継がれて結実したことを知った時には感慨深く思いました。
外交が扱う分野は多岐にわたります。その全てに通じるとともに,特定分野の専門性も兼ね備えた,「T字型の人間」になることが自分の目標です。
6 外務省にはどのような人材が求められているとお考えですか。また外務省を目指す学生にひとことお願いします。
世界がますます混沌とし,簡単に答えが見つからない中,外交に限らずあらゆる分野において,自分の頭で考え,説得力をもって発信できる人材が必要とされると思います。学生時代は,将来の選択肢を限定することなく,いろんな世界に飛び込んで,ぜひその材料を増やしていってください。その結果,外務省の門戸を叩こうと思われたなら,私たちはいつでもみなさんをお待ちしています。
貴重なお話をありがとうございました。

