3.3 二国間関係へのインパクト~貿易・投資関係を中心として~
日本との二国関係について、ここでは、民間直接投資と貿易等が与えたインパクトに焦点をあてて分析を進めていく。市場経済化のなかでの、経済システムの改革、インフラ整備、法整備等、経済産業環境の整備状況と援助の役割をレビューしつつ、ベトナムの産業構造の改革に与えた日本の民間企業の役割についても分析していく。
ここでは、外国投資及びそれを取り巻く経済システム改革の動向について見ていく。
(1)外国投資の動向
1980年代後半以降、大企業から中小企業までわが国企業のアジア投資は大きく拡がってきたが、その投資の主要対象であった、NIESやASEAN諸国における高成長の中での人件費をはじめとする大幅なコストアップや人材不足、インフラの不足が、進出企業の深刻な経営問題となってきた。
そうした中で、90年代に入って、アジアにおけるわが国企業の投資ニューフロンティアとして急浮上してきたのが、社会主義計画経済から市場経済に向かって変革を進めてきたベトナムであった。
同国が、外国企業の新たな投資対象として、大きな関心を集めてきた背景には、以下のような点が指摘できる。
(1)低コスト(最低賃金は大都市部で45米ドル、中規模都市で40米ドル、その他地域では35米ドル)で高水準(ASEANに劣らぬ国民教育の普及、識字率90%で小学校終了75~80%)の労働力の存在、(2)石油をはじめとする各種鉱物資源、農林水産資源の存在、(3)共産主義体制ではあるが、宗教、民族といった面で深刻な国内問題を抱えていない、また、ASEAN加盟など国際社会にも復帰している、(4)アジア地域の中央でかつ3,200キロメートルという長い海岸線を持つ地理的優位性、(5)ドイモイによる経済政策面での改革に加えて、投資インセンティブや法制度面でも整備が進みつつある、(6)人口7,800万人と中長期的には国内市場の成長も期待できる。
こうしたベトナムの中長期的にみた投資ポテンシャルは、日本のみならず欧米、アジア各国の企業が立地拠点として十分評価するところである。
1989年から2000年の間、軽工業、食品加工、電気・電子、輸送機械、建設など約300件のわが国からの直接投資が認可済みである。ホーチミン市およびハノイ市には日本商工会が結成されており、それぞれ214社、115社の日系企業が会員として加盟している。
以下に、1988年から2001年9月に行われたベトナムへの外国投資の累計を示した。総額18,485百万米ドルである。なお、日本が外国投資額のトップを占めているが、僅差で台湾、韓国、シンガポールなどアジアの新興経済国が続いていることがわかる。
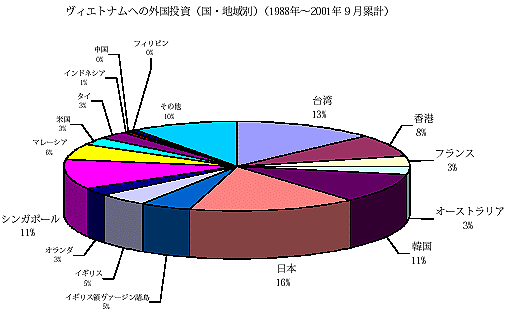
(2)変化する投資トレンド
ベトナムへの外国投資は90年代に入って急増を続けてきた。1988年の外国投資法施行以来、2001年9月までに累計で約2,943件、377億ドルの外国投資が認可(実行金額は185億ドル)されている。1994年には343件、1995年には370件とピークを打った後、1996年以降は共産党大会の開催や外国投資法の改正などの影響による投資認可手続きの遅れや、多くの業種での進出企業間の競争激化による投資一巡などから、落ち込みをみせた。さらに、1997年にはアジア金融危機・経済危機の悪影響が加わり、1997年は前年比44%減、1998年は同14%減、1999年は同60%減と3年連続の低迷が続いた。2000年以降は、ベトナムおよび周辺国がアジア経済危機後の経済低迷から脱出したことなどから、外国投資もようやく回復基調に転じているが、従来のような大企業の進出や大型案件の投資は減少している。
業種別には建設、ホテル・観光が中心となっていることに変わりはないが、自動車、電気・電子、機械、セメントをはじめとする機械・重工業が近年件数、金額とも急増している。他方、繊維、雑貨などの軽工業では1994年をピークに減少傾向にある。
投資国別では、累計ベースでみて、件数では台湾のほか香港、韓国、日本、シンガポールのアジア近隣5カ国で全体の約6割を占めている。金額ベースでも同様にこの5カ国で6割弱を占めている。ASEAN加盟、米国との国交正常化もあってタイ、インドネシアおよび米国からの投資が増加基調にあり、投資国は広がりをみせている。
投資受入地域別では、累計ベースでホーチミン市及び近隣のドンナイ省、ビンズオン省などが従来より過半を占めており、これにハノイ市を加えると外国投資の大半を吸収していると言える。ホーチミン、ハノイに次ぐ特別市であるハイフォンとダナンは、現状では少ないままにとどまっている。
現状のベトナム投資をみると回復基調にあるものの、明らかに90年代前半までのブーム状況とは違っており、今後の外国投資の基調には流動的な側面も増大している。
1997年以降の外国投資認可をみると、ようやく2000年の投資件数が1996年の水準にまで回復をみせたものの、金額ベースでは同ピーク時1996年の5分の1にとどまっている。これまで90年代に入ってからベトナム投資ブームを支えてきた台湾、香港、シンガポールなどのホテル、オフィス、工業団地などの大型インフラ関連プロジェクトが供給過剰で、1996年以降急速に冷え込んできたこと、さらには前述のとおり、1997年タイに始まったアジア経済危機の悪影響も加わって製造業分野でも大型投資が減少したためと考えられる。
換言すれば、ベトナム投資も、開発初期のインフラ、観光関連、また、軽工業、中心の投資から、第二段階の自動車、電気・電子など、部品産業を含む、加工組立型産業を中心とした製造業投資が投資の牽引力となり、継続的伸びを示すのかどうか重要な転換点を迎えているといえよう。中国その他近隣諸国と生産拠点としてグローバルなベースでの競争やAFTAによる域内貿易自由化や今後具体化が予想されるWTO加盟のスケジュールなどもにらみつつ新たな産業政策やそのための法制度、行政システムの整備、人材育成などが緊要の課題となりつつある。
(3)外国投資法基本的枠組みと改正
政府は、1996年、外国投資法を大幅改正し、外資受け入れ基準をより明確にした。外国投資法は、1987年に制定され、その後1990年及び1992年に2度改正されている。この改正は1996年11月12日に第9期第10回国会で採択されたものであり、それまで投資家の間で規制が多いと批判されていた点を含めかなり投資環境は改善されている。その後は、2000年に再度外国投資法を改正しさらに規制緩和を実施している。
(4)行政改革と外資関連の法改正
経済開発関連の行政手続に関しても、従来から進出企業などから、許認可権限や担当分野が明確に区分されておらず、極めて複雑でわかりにくいとの指摘がなされていた。元来ベトナムには経済分野を一元的に管理する行政組織はなく、今後の産業開発政策を効果的に実施し、市場経済への移行をスムーズに進めていくためには、行政の簡素化など改革が不可欠となっていた。
こうした中で、政府は1995年、経済関連の6省と2委員会を3省に統合している。
国家計画委員会(SPC)と国家協力投資委員会(SCCI)を計画投資省(MPI)とし、これが外国投資の受入窓口ともなっている。軽工業省、重工業省とエネルギー省を工業省に、また、農業食品工業省、林業省、水資源省を農業・地方開発省に統合している。
これまで立法化された、外資関連の主要な法制度をあげると「土地法」(1993年7月制定)、「破産法」(1993年12月制定)、「労働法典」(1994年6月制定)、「民法典」(1995年12月制定)がある。その後も「銀行法」、「証券法」、「商法」、「税法」、「保険法」、「仲裁法」などの立法化を進めてきている。
知的財産権の関連では、民法典により工業所有権及び著作権の保護が規定されている。工業所有権は先願主義で、保護対象としては、特許権(発明15年、実用新案6年)、意匠権(工業デザイン 5年、2回まで更新可)、商品権(商標・サービスマーク 10年、更新可)、原産地証明(無期限)となっている。他方、著作権に関しては、保護対象が明確でなく、今後の改正作業が必要となっている。
(5)経済システムの改革
1988年、金融システムの改革がスタートし、従来、中央銀行が商業銀行を兼営していたものが、中央銀行と商業銀行とに、基本的役割が明確に区分されることになった。
1990年には、金融制度の枠組を新たに規定する「中央銀行法」と「商業銀行、ファイナンスカンパニー及び信用組合法」が、1991年には「外国銀行支店、合弁銀行法」が制定されている。1991年には、中央銀行の直接貸付が取りやめとなったほか、翌92年には国営企業への赤字ファイナンス(補助金)も取りやめとなっている。 金融改革は全般に遅れており、民間銀行48行に対して政府の財務検査が実施され、2000年末までに13行が特別管理下に置かれている
ベトナムでは、80年代のハイパー・インフレ(1986年は500%弱)とそれに伴う実質金利のマイナス、また、1991年の信用組合の倒産などによる金融機関に対する信頼の欠如などから、家計の貯蓄構造も預金ではなく、金、不動産、現金など実物資産が中心となっている。家計の貯蓄構造において、金は44.0%、不動産は20.1%、現金は10.0%を占めているのに対し、国営銀行預金は7.4%、その他銀行預金は0.3%、信用組合預金は0.2%を占めているにすぎない。米ドルは、ベトナムでの日常生活において通貨として、通貨ドンより、むしろ強い信用力を有しているが、金はそのドル同様通貨として使用されている。金の需要のうち装飾向けや資産向けを除いて60~70%は通貨としての需要で、不動産、自動車など高額商品売買の決済に使用されている。
また、金融改革の中で民間銀行の設立を認めてきたものの、銀行預金の大半が国営銀行に集中している。金利水準はインフレの鎮静化とともに、近年低下傾向にある。中央銀行は商業銀行の預金金利の最低水準と貸出金利の最高水準を決めている。預金金利については法人よりも個人を高めに設定して、金、ドルなどの形態でのいわゆるタンス預金など個人預金の動員をはかろうとしている。他方、貸出金利は、短期資金、運転資金よりも設備資金、長期資金を優遇するように定められている。したがって、長期資金へ需要が集中するが、短期資金に比べ金利スプレッドが小さく収益性の低い長期貸付には金融機関の意欲は低く、政府の支援また結び付きの強い国営企業向けが優先され(長期貸出しのうち国営企業のシェア85%)、中小企業など民間部門では資金不足が解消されないままにある。
証券市場については、当初1993年の証券取引所開設が予定されていたが、大幅な延期となりようやく2000年にホーチミン証券市場が開設され、2002年3月現在12社が上場しており、最近では外国投資家の取引も増加している。なお、国営企業の株式化が進められているが、上場にともない従来国営企業として享受してきた様々な恩典が失われることを懸念し、上場には消極的姿勢をとっている国営企業もあるとのことである。

