2.2.3 ベトナムが過去10年に掲げた目的・目標とその達成度合
日本が対ベトナム援助を本格的に再開した1992年当時の開発政策は以下の内容と目標を設定していた。
‘市場メカニズムの導入による経済運営と、全方位外交の展開’により、GDP成長率6.0%以上を達成する。 ではどうやって?↓ ● 食料自給をまず実現し、畜産物の増産、農産物輸出(米、加工肉、ゴム、綿、茶、コーヒー等)による外貨の獲得などにより、農業生産の成長率4.0-4.5%以上を達成する。 ● 外国との合弁による加工品の生産と輸出の増加、日用品(繊維製品)の生産増加、エネルギー源の新規開発などにより、工業生産の成長率10-11%以上を達成する。 ● (上記の生産・輸出の増加を下支えするために)主要都市を結ぶ幹線道路の整備、空港および港湾の拡充・近代化、国内電力網の整備、電話網の整備を推進する。 |
次に実績を見ると、農業生産の年平均成長率4.5%、工業生産の年平均成長率13.3%を達成したうえ、稼ぎ出した外貨が投資に回ることによって経済成長に貢献する外需(輸出)が20.2%の高い伸びを示したことにより、国内総生産が年平均8.2%の高い伸びを示し、当初設定された目標は達成された。これによって国内総生産は計画期間スタート時の1990年に比べ、およそ1.5倍の規模となった(実質ベース)。
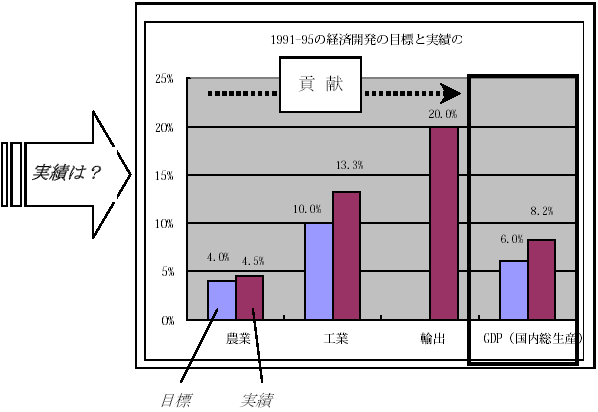
続く1996-2000年の開発政策は以下の内容と目標を設定していた。なお、この期間中にアジア通貨危機が発生し、計画の達成に影響を与えることとなった。
‘工業化・近代化の推進を推進し、迅速・効果的・強固な経済発展を目指しつつ、社会面における緊急諸問題の解決にも配慮’して、GDP成長率9.0%以上を達成する。 ではどうやって?↓ ● 農業生産の量的増加と質的改善、商品作物・果樹の育成を実現しながら、栄養失調の緩和、食料保障などにも配慮して、農業生産の成長率4.5-5.0%以上を達成する。 ● 国営企業改革、農産品加工地区の整備、石油・ガスの開発、電気・コンピューター・通信産業の育成、工業製品及び部品の生産の促進、工業団地の建設を実現しながら、地方及び近郊部における経済の活性化にも配慮して、工業生産の成長率14-15%以上を達成する。 ● 輸出品の生産増加、原材料品の輸出の削減、国内供給可能な産品の輸入削減、工業化・近代化に必要な資機材等の輸入の増加、直接投資と ODAの活用を実現して、輸出額を年28%増加させる。 ● (上記の生産・輸出の増加を下支えするために)幹線ルートにおける円滑な交通の実現、各地域の電力・水・輸送の各需要の充足を実現しつつ、(社会面の配慮として)山間部・農村部における社会経済インフラの整備も実施する。 (他、サービス産業、環境、教育、保健医療、地域別開発、貧困の削減などについて記述あり) |
次の実績を見ると、農業生産の年平均成長率5.0%、工業生産の年平均成長率12.2%を達成したうえ、外貨を稼ぎ出す外需(輸出)が18.6%の高い伸びを示したことにより、国内総生産が年平均7.0%の高い伸びを示した。これは当初の目標には届かなかったが、アジア通貨危機により周辺諸国が軒並みマイナス成長を経験したことと比較すると例外的に高い成長だったと評価されるのが妥当であろう。なお、この成長率によって、国内総生産は10年前の1990年に比べ、およそ2倍の規模となった(実質ベース)。
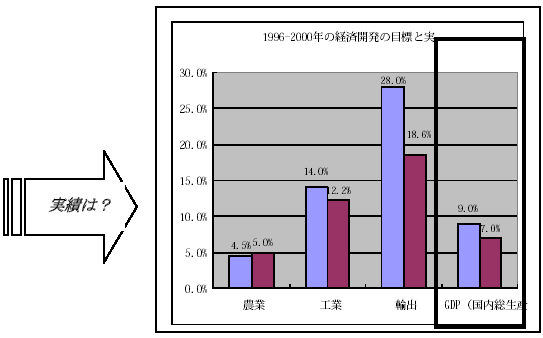
なお、第7次5カ年計画(2001-2005)については、第4章で別途解説する。

