第3章 対タイ援助政策の理論に関する評価
この章では、日本の対タイ援助政策の理論に関する評価として、当該政策が妥当な理論的根拠に基づいたものであるかどうかについて検証した。
3.1 対タイ援助政策の目標の体系図
第1章でも述べたように、対タイ援助政策の理論に関する評価においては、対タイ国別援助計画を対象とする26
。対タイ国別援助計画の理論的根拠として、同計画とODA大綱27
、ODA中期政策28
及びタイの国家開発計画との整合性の検証を行うことによって、対タイ援助政策の理論の妥当性を評価する。方法としては、理論評価のためのツールである「目標の体系図」を作成する。「目標の体系図」とは、国別援助計画において目指している全体的方向性を「最終目標」とし、そこから派生している主要課題を「重点分野」、それを更に細分化している項目を「重点課題」、そのまた下位項目を「重点的に取り上げる事項」と表し、樹形図上に示したものである29
。
対タイ国別援助計画においては、“我が国援助の目指すべき方向”の中で掲げられている「自立的発展」、「アジア経済危機からの中・長期的回復」、「人材育成の強化」の3つが最終目標となる。そして、“重点分野・課題別援助方針”の中で掲げられている「社会セクター支援(教育・エイズ対策を中心とする)」、「環境保全」、「地方・農村開発」、「経済基盤整備」、「地域協力支援(南南協力支援)」の5つが重点分野、更にこの5重点分野の中で細分化されている項目が重点課題、重点的に取り上げる事項となる。このようにして作成した「対タイ援助政策の目標体系図」を次頁に示す(図3-1)。
3.2 ODA政策との整合性
対タイ国別援助計画が妥当な理論的根拠に基づいているかどうかを検証するために、同計画とその上位の政策であるODA大綱及びODA中期政策との整合性について検証を行った。
3.2.1 ODA大綱との整合性
政府開発援助大綱(以下、ODA大綱)は、日本のODAの理念と原則を明確にすることを目的に、1992年6月閣議によって決定された。日本の過去の援助の実績、経験、教訓を踏まえ、援助方針を集大成したODAに関する最重要の基本文書と位置付けられている。内容は6部で構成され、「基本理念」、「原則」、「重点事項」、「政府開発援助の効果的実施のための方策」、「内外の理解と支持を得る方策」、「実施体制」から成っている。ここでは「基本理念」及び「重点事項」と対タイ国別援助計画の整合性について検証した。
基本理念は以下の3点である。
| 1) | 自助努力への支援を基本とする |
| 2) | 広範な人造り、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー(経済社会基盤)及び基礎生活分野の整備等を通じてこれらの国における資源配分の効率と公正や良い統治の確保を図り、その上に健全な経済発展を実現する |
| 3) | 環境保全を達成しつつ、地球的規模での持続可能な開発が進められるよう努める |
重点事項としては以下の項目が挙げられている。
| 1) | 地球的規模の問題31 への取り組み |
| 2) | 基礎生活分野(Basic Human Needs: BHN)32 等 |
| 3) | 人造り及び研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力 |
| 4) | インフラストラクチャー33 整備 |
| 5) | 構造調整34 等 |
対タイ国別援助計画とODA大綱との整合性を検証する作業として、同計画の目標体系図において特定された最終目標及び重点分野が、上記のODA大綱の項目と整合性が取れているかどうかについてそれぞれ照合していく35 。
対タイ国別援助計画の最終目標の「自立的発展」については、ODA大綱の基本理念の「1) 自助努力への支援を基本とする」及び「2) 広範な人造り、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー(経済社会基盤)及び基礎生活分野の整備等を通じてこれらの国における資源配分の効率と公正や良い統治の確保を図り、その上に健全な経済発展を実現する」と整合している。対タイ国別援助計画の重点分野の「社会セクター支援」は、ODA大綱の重点事項の「1) 地球的規模の問題への取り組み」及び「2) BHN等」に対応している。「環境保全」は「1) 地球的規模の問題への取り組み」に対応し、「経済基盤整備」は「4) インフラストラクチャー整備」及び「5) 構造調整等」に対応している。以上の対比を図に示した(図3-2)。
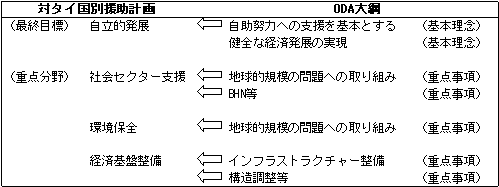
| 出所:調査団作成 |
対タイ国別援助計画の最終目標の中には図3-2には示されていないものの、ODA大綱中の重点事項との間に整合性が見られるものがある。例えば「アジア経済危機からの中・長期的回復」については、ODA大綱の本文中に「アジア地域の安定と発展」及び「構造調整」に関わる記述が詳細になされており、高い整合性を有した目標設定になっていると言える。「人材育成の強化」についても、重点事項の「3) 人造り及び研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力」が対応している。
重点分野の「地方・農村開発」と直結する表現はODA大綱では特に言及されてはいないが、重点事項として「基礎生活分野」が取り上げられていることから整合性は保持されているものと見る。また「地域協力支援」についても、ODA大綱の中の“地域別援助のあり方”において「地域における広域的な開発の取組み及び南南協力への支援」と記載されていることから整合性は保たれていると考える。
以上のように、対タイ国別援助計画ではODA大綱の中で謳われている、社会・経済両分野におけるバランスの取れた支援、環境に配慮した開発等の精神が活かされていることが分かる。
3.2.2 ODA中期政策との整合性
ODA中期政策は、経済協力開発機構(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)の開発援助委員会(Development Assistance Committee: DAC)が1996年5月に策定した「新開発戦略」を受け、同戦略が掲げている目標36 を念頭において策定され、1999年8月に公表されている。同中期政策は、「概要」、「基本的考え方」、「重点課題」、「地域別の援助のあり方」、「援助手法」、「実施・運用上の留意点」から構成されている。その中で援助方針を示しているのは、「重点課題」を基にしている「地域別の援助のあり方」における地域毎の支援方針である。
中期政策の「地域別の援助のあり方」の中で、東アジア地域への支援として以下の点が挙げられている。
| 1) | 経済構造調整をはじめとした経済危機克服と経済再生のための支援 |
| 2) | 国民生活及び国内の安定に資するための社会的弱者への積極的支援 |
| 3) | 裾野産業育成や適切な経済・社会運営のための人材育成と制度造り等の支援 |
| 4) | 貧困対策、経済・社会インフラ整備、環境保全対策、農業・農村開発における各国の実情に応じた援助の実施 |
| 5) | 地域における広域的な開発(ASEAN域内協力、APEC地域協力、メコン河流域開発等)の取組み及び「南南協力」への支援 |
上記支援方針のうち、対タイ国別援助計画における最終目標の「人材育成の強化」は「3) 裾野産業育成や適切な経済・社会運営のための人材育成と制度造り等の支援」に対応し、「アジア経済危機からの中・長期的な回復」は「1) 経済構造調整をはじめとした経済危機克服と経済再生のための支援」に対応している。
重点分野の「社会セクター支援」は「2) 国民生活及び国内の安定に資するための社会的弱者への積極的支援」及び「4) 貧困対策、経済・社会インフラ整備、環境保全対策、農業・農村開発における各国の実情に応じた援助の実施」に対応している。「環境保全」、「地方・農村開発」、「経済基盤整備」の3目標については「4) 貧困対策、経済・社会インフラ整備、環境保全対策、農業・農村開発における各国の実情に応じた援助の実施」にそれぞれ対応し、「地域協力支援」は「5) 地域における広域的な開発(ASEAN域内協力、APEC地域協力、メコン河流域開発等)の取組み及び『南南協力』への支援」に対応している。以下に両者の対応図を示す(図3-3)。
対タイ国別援助計画の各項目
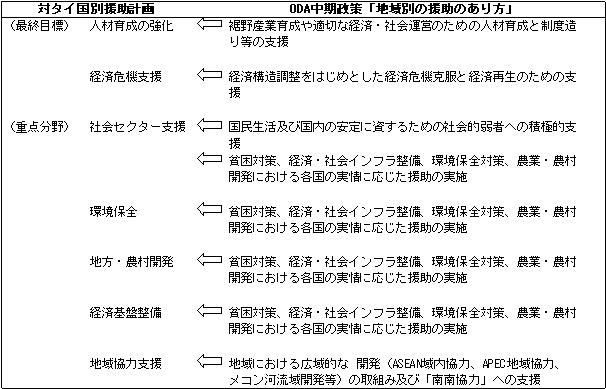
| 出所:調査団作成 |
図3-3では示していないが、対タイ国別援助計画の最終目標である「自立発展」は“地域別援助のあり方”の「東南アジアの中で近年まで高い成長を示していた諸国については現下の困難な状況を乗り越え、順調な経済発展を回復し、政治社会的安定を維持しうるよう支援する」という基本的考え方に合致していると考えられる。
以上のように、対タイ国別援助計画における最終目標及び重点分野は、ODA中期政策における「東アジア地域への支援方針」に対応していることが確認できる。対タイ国別援助計画はODA中期政策における方針・課題を幅広く取り入れ、同中期政策を十分に参照しつつ作成されているものと考えられる。
3.3 タイ開発計画との整合性
次に、対タイ国別援助計画とタイの開発計画との整合性について検証する。
先述のODA大綱及びODA中期政策では、我が国が世界中の様々な国に対して行う政府開発援助全体の方針や方策などの記載がなされており、タイ一国に対する我が国の具体的援助政策は対タイ国別援助計画にて詳述されている。つまり我が国の対タイ国別援助計画は、ODA大綱及びODA中期政策と同様政策文書ではあるもののそれらと比べ、タイ国の開発政策であるタイの開発計画により近い次元の文書であると推定する。従って対タイ国別援助計画とタイの開発計画の整合性検証は、前項までの検証とは違い、ほぼ同次元の文章同士の検証であるという点に留意しつつ実施した37 。
第2章でも触れたように、タイの開発計画は、1957年の世界銀行の提言に基づいて第1次国家経済社会開発計画(1961~66年)が策定されたのを始めとして、現在、第9次開発計画まで策定・実施されている。タイ国家経済社会開発庁(National Economic and Social Development Board: NESDB)が作成している。日本の対タイ国別援助計画が策定されたのは2000年3月で、当時のタイ開発計画は第8次計画(1996年10月~2001年9月)にあたるため、ここでは第8次計画との整合性について検証する。尚、施行期間が2001年10月~2006年9月である第9次計画の概要を参考として添付資料3とした。
タイ第8次国家経済社会開発計画は、「概要」と7つの開発戦略である「人的資源の開発」、「人間開発支援を可能とする環境の創設」、「生活の質的向上を促進するための地域・農村開発の強化」、「人間開発と生活の質的向上を促進するための経済競争力の強化」、「自然資源と環境管理」、「国民に支持される政府の確立」、「第8次計画の効率的運営と実施統治開発」にて構成され、英語版で150頁にも及ぶ膨大な計画となっている。尚、同計画は1997年のアジア経済危機により一部修正された。次頁に第8次計画の概要を示す(図3-4)。
概要の特徴に示されているように、第8次計画は国民生活の質の向上に重点を置く「人間中心の開発」が基本理念として打ち出され、これまで以上に社会的側面が意識された計画であった。しかし1997年の経済危機発生に伴い、「人間中心の開発」という基本理念は維持されつつも、マクロ経済の安定化、産業構造改革の推進、経済危機の国民生活への影響の緩和、行政改革の推進等に重点を置く方向に修正がなされた。また、GDP成長率を始めとする経済指標については、IMFとの協議を通じて大幅な下方修正が行われるなど、当面の経済危機の乗り切りが最重要課題とされた。
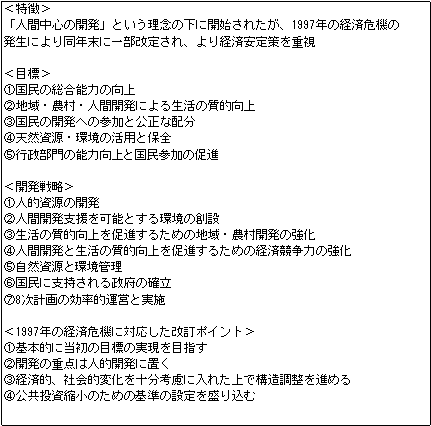
| 出所:NESDB, The Eighth National Economic and Social Development Plan (1996, rev. 1997)、バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況1996/1997年版、1998/1999年版」を基に調査団作成 |
第8次計画は「貧困者比率を10%以下(95年は11.5%)」、「義務教育を6年から9年に拡大し、更に12年への拡大を準備」等、成果重視の開発目標を示しており、DACの「新開発戦略」と同様に、具体的な達成すべき目標値を設定している。次頁に第8次計画のマクロ目標値の一部と、参考として第7次計画の数値(目標値、実績値)を示す(表3-1)。
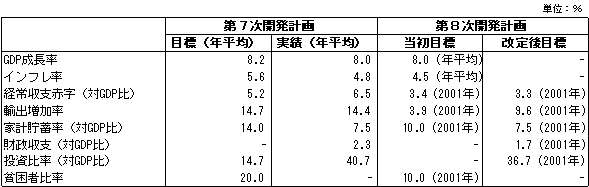
|
出所:NESDB, The Eighth National Economic and Social Development Plan (1996, rev. 1997)、バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況1996/1997年版、1998/1999年版」を基に調査団作成 注)タイ開発計画は対象5年間の年毎の目標値を設定しているが、表中に年平均と記されているのは5年間の平均の目標値、西暦が記されているのはその年における目標値を示している。 |
タイ第8次開発計画と我が国の対タイ国別援助計画とがどの程度整合しているのかを検証するために、両計画の上位レベルの内容を照らし合わせてみた(図3-5)。この照合は、タイの開発計画における開発戦略が、我が国対タイ国別援助計画における重点分野と同じレベルにあるという前提で作成した。
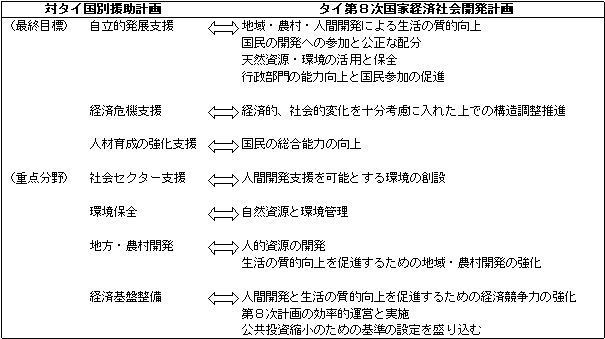
| 出所:調査団作成 |
我が国対タイ国別援助計画とタイ開発計画は、最終目標レベルでは全てにおいて整合することが分かる。また重点分野レベルでも“地域協力支援”を除き、全てが整合する。尚、地域協力に関わるタイ開発計画の本文中の記載としては、「環境保全における国際協力の推進」という程度ではあるが存在する。これは、タイの開発計画が基本的には自国の開発のあり方を規定するために作成しており、タイ自身による周辺国への協力方針を示すための文書ではない、ということに因るものだと考える。
タイの開発計画は経済から社会、グッド・ガバナンス38 に至るまで非常に幅広い分野を範囲としていて、100以上の開発課題を有している。我が国の対タイ国別援助計画において重点とする課題等の多くがタイの広範な開発課題の中に含まれるという結果になっている。これは、我が国がタイの自助努力を前提とした開発を後押しすることを眼目に、タイ政府が優先したいと考える開発の分野と要請される案件の傾向に常に注意を払ってきた結果、タイが目指す開発の方向性と我が国が重視する対タイ援助分野双方が互いに収斂されてきた結果であるのだとも言える。
3.4 他ドナーの対タイ援助方針とタイ開発計画との整合性
最後に、タイに援助を行っている他ドナーの対タイ援助方針を取り上げ、それらとタイ開発計画との整合性もみることによって、対タイ国別援助計画の理論評価の参考とする。対象とする他ドナーは、世界銀行、アジア開発銀行(Asian Development Bank: ADB)、国連開発計画(United Nations Development Programme: UNDP)とする。
世界銀行
世界銀行における国毎の援助方針を示したものは、「Country Assistance Strategy (CAS)」である。対タイCASは3年毎に作成されており、世界銀行本部の上位政策、タイ政府の意向及び政策、現地NGOの意見等を踏まえている。現在の対タイCAS(1999-2001)は、1998年6月に策定された。その中で、対タイ支援の中期的戦略として以下の3つの目標及びそれらの目標を達成するための戦略が掲げられている。
| 1) | 競争力の回復 ・ 効率的な仲介のための金融セクター改造 ・ 熟練労働力開発 ・ インフラストラクチャーの障害除去と貿易の円滑化 ・ 企業リストラの促進 |
| 2) | 統治改善 ・ マクロ経済運営の改善 ・ 公共資源管理の強化と分権化促進 ・ 法制度改革 ・ 効率化のための公共生産部門の再編 |
| 3) | 成長の利益の共有と生活の質の保証 ・ 社会的弱者・貧困層保護 ・ 都市・地方間格差是正 ・ 社会保障制度構築 ・ 天然資源・環境保護 |
ADB
ADBにおける国毎の援助方針は、「Country Assistance Plan (CAP)」である。対タイCAPはマニラ本部で3年に1度、NESDB、タイ大蔵省の公的債務管理局(Public Debt Management Office: PDMO)と財政政策局(Fiscal Policy Office: FPO)との協議等を踏まえ、約1年間かけて作成される。現在の対タイCAP(1999-2001)は1998年11月に策定され、対タイ支援戦略として以下の3つの目標が掲げられている。
| 1) | 成長過程に回帰するための安定化・調整 |
| 2) | 効率的で地域のバランスが取れ、かつ持続的な成長を達成するための競争力強化 |
| 3) | 生活の質の改善 |
また、これら上位目標達成のために以下の3つの必要性が挙げられている。
| 1) | 金融改革、社会セクター、地方・農業セクターへのプログラムを優先する必要性 |
| 2) | 地域的には北部・東北部・南部を優先する必要性 |
| 3) | プロジェクト優先の支援から、プロジェクトとプログラムを併用した支援へ、また経済インフラ中心の支援から、金融・社会・農業支援に移行する必要性 |
UNDP
UNDPでは、タイ第8次開発計画に基づいて策定された「Country Cooperation Framework (CCF) 1997-2001」と呼ばれる援助方針の枠組みがある。その枠組みの中で、以下の3つの協力重点分野が掲げられている。
| 1) | 貧困緩和のための持続可能な人間開発 |
| 2) | 緊急課題への対応 |
| 3) | 地域の開発パートナーとしての役割(三角協力) |
以上の重点分野に加え、山岳民族支援及び生物多様性保全等の国境開発を中心としたメコン河の流域開発、またアジア地域に対する共通課題として、貿易・投資、運輸・通信、エネルギー、環境、持続可能農業分野の支援等にも取り組んでいる。
他ドナーの対タイ援助方針はタイの開発計画等を踏まえて作成されており、援助内容もタイの開発課題に原則沿うようになっている。しかし、これらのドナーの対タイ援助方針は各々の本部において作成されている。他ドナーはタイを含めた全世界を共通とした援助戦略を有しており、現地事務所は援助を通してそれら戦略を実現していくことを本部からは期待されている。上記3ドナーのような国際機関の本部が策定する援助戦略は、彼等が援助する国にとって、必ずしも100%受容可能な内容になるとは限らない。国際機関本部はタイ以外にも何十という国々を包含する戦略を策定しなくてはならない。その結果、国際機関本部が策定する援助戦略と被援助国の開発方針との間には若干の食い違いが生じたとしても仕方がないものと考えられる。そのような現象はタイでも起こっている。
国際金融機関である世界銀行、ADBの対タイ援助方針はタイの開発計画を踏まえて作成されているものの、外国援助借入れをどの分野や課題とすべきなのかという考え方においては、タイ政府と食い違いがあるようである。具体的には、タイ政府は経済インフラ等では借入れを希望するものの、世界銀行やADBは可能な限り経済インフラ以外の分野に優先的に貸し出しを行いたい、という違いである。例えば、ADBはマニラ本部の方針によって経済インフラから地方開発、貧困削減に事業の方向性を絞ろうとしている。貧困削減等はタイの重要な開発課題であるものの、タイ側としてはドナーにこれらの分野に急激に援助の方向性を転換してほしいとは考えていないようである。タイ側はADBの方針を完全・直ちに受け入れることができる状態にはなく、ADBの対タイ援助プログラムはこの数年、タイ政府の了承を得られないために棚上げ状態となっている。しかしADBは時間をかけつつ、タイ政府と粘り強い交渉を重ねながら、徐々にではあるが、ここで述べたような違いを解消する努力を継続してきたことが確認されている。
3.5 結論と考察
3.5.1 結論
以上の検証から、対タイ国別援助計画は、ODA大綱及びODA中期政策の中で謳われている人材育成、教育・保健等社会セクター分野への支援、環境保全を目的とする協力、経済インフラ分野への支援等の精神を特に具現化した内容であると言える。加えて、対タイ国別援助計画とタイの国家開発計画との間にも高い整合性が見られた。よって、対タイ援助政策の理論に関する評価として、対タイ国別援助計画は妥当な理論的根拠に基づいたものであると評価する。
3.5.2 考察
タイ政府は各開発課題の中で、自国予算によって行いたい分野と対外借入れによって行いたい分野の区別を持っている。タイ政府は、我が国の対タイ国別援助計画の重点分野である「社会セクター」、「地方・農村開発」、「地域協力」分野の開発事業については、為替リスクのある外貨を借り入れるよりも内貨によって実施し、外貨が必要な経済インフラ事業において借り入れを行いたいという意向を持っているようである39 。タイが認識する開発課題については、我が国が重要と考える分野と齟齬はないが、タイが同国の財政事情全体を考慮し掲げている対外借入方針の枠内で、外国援助資金を経済インフラ以外に対しても如何に効率的・効果的に配分するかという点については、今後は一層木目細かな対話の積み重ねが必要になってくるのだと言える。タイ政府当局との地道な会話を通じ、今以上にタイ政府の意向と高い整合性を持った対タイ国別援助計画に仕上げることは、効率的なODA事業の実施に繋がるだけでなく、我が国にとって重要なパートナーであるタイとの関係を更に良好なものとする上でも有効だと考えられる40 。
有用な対話には、政治・経済・社会情勢に関する情報収集と分析、また開発課題に関する分析等が必要である。前者に関しては既に大使館内で体制が確立されているものと推測されるが、開発課題に関しては、次章でも言及するように、多分に援助実施機関であるJICAとJBICの協力を基に情報収集や分析等を行っているものと見られる。今後はそのようなJICA、JBICとの協力関係を、より明確なものとすることを提案する。具体的な提案については次章にて述べる。
26 第1章でも脚注にて説明しているように、本評価では、対タイ国別援助計画は1995年度以降の対タイ援助政策である対タイ援助方針を集大成したものとみなし、評価分析においては対タイ国別援助計画について検証を行っている。
27 我が国のODAの理念と原則を明確にするために、援助の実績,経験,教訓を踏まえ、日本の援助方針を集大成したODAの最重要の基本文書であり、平成4年6月30日に閣議決定された。内容は、基本理念、原則、重点事項、政府開発援助の効果的実施のための方策、内外の理解と支持を得る方策及び実施体制の6部から構成される(外務省ホームページより)。
28 ODA大綱に基づき向こう5年程度を目途に中期的な政策・プログラムの方向性を示した文書(外務省ホームページより)。
29 この分析方法は「政策レベル及びプログラム・レベル評価の手法等に関する調査研究」(2000年12月、外務省委託、財団法人国際開発センター・株式会社コーエイ総研)を参考としている。
30 目標体系図は、1995?98年度の対タイ国別援助方針と1999年度作成の対タイ国別援助計画を基に作成した。5つの文書を精査すると、重点分野は同一であるが、重点課題において若干の違いのあることが確認された。例えば、国別援助方針では「社会セクター支援」の重点課題に「薬物対策支援」ではなく、代わりに「援助の際のWID配慮やNGO支援」という項目が使用されている。年毎に援助の動向を反映させた結果の差異と推定され、体系図全体のあり方に影響を与えるものではないと考える。
31 環境、人口、エイズ、WID、麻薬など、影響が地球的規模に及ぶものや、解決には国際的な協力が不可欠な課題をいう(国際協力事業団年報2002)。
32 経済開発を重視した従来の援助ではなく、低所得層の民衆に直接役立つものを援助しようとする援助概念。衣食住など、生活するうえで必要最低限の物資や安全な飲み水、衛生設備、保健、教育など、人間としての基本的なニーズ(国際協力事業団年報2002)。
33 経済活動を支える各種の基盤。社会資本。通常、エネルギー、道路、港湾、河川、通信、農業基盤、鉄道・空港などの経済インフラと、公衆衛生、教育、住宅、上下水道などの社会インフラに区分される(国際協力事業団年報2002)。
34 累積債務問題などに見られる開発途上国経済の悪化は過度な政府介入が経済合理性を歪めるためであるという認識から、国際通貨基金(IMF)や世界銀行などがとった市場経済メカニズムに依拠した一連の経済化改革政策(「国際協力用語集第2版」国際開発ジャーナル)。
35 重点分野より下位レベルの事項についての整合性の検討は、上位レベルでの整合性が取れていれば下位目標の整合性も取れているものと推定し割愛した。
36 1) 2015年までの貧困人口割合の半減、2) 2015年までの初等教育の普及、3) 2005年までの初等・中等教育における男女格差の解消、2015年までの4) 乳幼児死亡率の1/3までの削減、5) 妊産婦死亡率の1/4までの削減、6) 性と生殖に関する健康(リプロダクティブ・ヘルス)に係る保健・医療サービスの普及、7) 2005年までの環境保全のための国家戦略の策定、8) 2015年までの環境資源の減少傾向の増加傾向への逆転。
37 我が国援助は被援助国の自助努力を大切にしているので、開発援助は被援助国の開発ニーズが重視されることが望ましいという点にも留意しつつ分析した。
38 日本語では「良い統治」と言う。政治や行政において、効率性、効果、透明性、法の支配、市民社会との会話、過度な軍事支出の削減などを確保すること。日本のODAでは、環境と開発との両立、基礎生活分野(BHN)への援助なども含む(国際協力事業団年報2002)。
39 このような意向は、本調査の評価対象期間後に成立しているタクシン政権が、より明確にしていったものと考えられる。
40 対タイ国別援助計画の改訂等の検討を頻繁に行うことは、同文書が政策レベルのものであり多くの日本側関係者との協議等の過程を経る必要がある点から、多大のコストが発生すると考えられ、留意は必要であろう。

