第2章 タイの開発と日本の協力
第3~5章における評価・分析に進む前に、タイの開発の推移と、我が国によるタイに対する協力の概要をまとめた。
2.1 タイ経済構造の推移
タイのGDPの年平均実質成長率は、1960年代が8.0%、70年代は6.8%、80年代は7.8%、90年代は1995年までの5年間が8.6%である。1997年の経済危機により、1997年、1998年はマイナス成長になったものの、1999年は4.2%のプラス成長へと回復した14。タイは長期的に高い経済成長を続けてきたと言える。
この長期経済成長の主な要因は、タイが農業中心から工業中心へと産業構造を転換させたことであろう。工業中心へと比重を移すことに伴い、付加価値の一層大きい製品をつくり、国内で販売または輸出し、高い経済成長を実現した。次の表2-1に示す通り、1960年時点のGDPに占める各部門の付加価値生産額の割合は、農林水産業39.8%、製造業12.5%であった。しかしその割合は、1999年には農林水産業10.5%、製造業35.5%となった。1960年から1999年までの40年間に、農林水産業と製造業の割合が逆転したことになる。
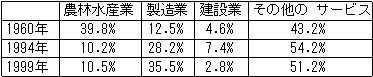
| 出所:バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況1996/1997年版、2000/2001年版」 |
しかし依然として、タイ経済において雇用の面では農業の比重は大きい。表2-2のように、1999年時点で就業者の45.3%が農林水産業に従事している。また国土に占める農地の割合は40%を越えている15。
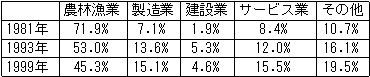
| 出所:バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況2000/2001年版」 |
2.2 タイの国家開発計画16
タイの開発計画は、国家経済社会開発5ヶ年計画として策定されている。1957年の世界銀行の提言に基づいて第1次計画が1961年から始められ、40年以上、この5ヶ年計画を続けている。現在は第9次計画(2001年10月~ 2006年9月)を実施中である。
5ヶ年計画を作成している機関は国家経済社会開発庁(National Economic and Social Development Board: NESDB)である。後述するように、NESDBはタイ各省庁からの有償資金協力要請案件を5ヶ年計画等に基づき審査する機能を持っている。
タイ国家経済社会開発計画の第1次(1961-66年)、第2次計画(1967-71 年)は、経済成長による開発を強調した。同期間(1960年代)にGDP年平均成長率8.0%という高度経済成長を実現したものの、同時に所得格差など負の部分も現れたので、その後タイ政府は経済開発に加えて社会開発、環境保全等も重視してきた。第8次では、経済発展の追求よりも「人間中心の開発」が、第9次計画においては「足るを知る経済」17等の考え方が強調されている。
2.3 日本の対タイ援助実績
2.3.1 援助の規模
タイが外国からの援助受入を本格化させたのは1961年からである。1960年代は米国からの贈与と世界銀行の借款が主体であった。70年代以降は、世界銀行、アジア開発銀行、日本からの借款が増加していった。
日本のタイに対する援助は2000年度までの累計で、技術協力1,751億円、有償資金協力1兆9,129億円、無償資金協力1,619億円が実施された18。本評価の対象期間を含む1991年以降の我が国の技術協力、有償資金協力、無償資金協力の対タイ援助額は、図2-1の通りである。
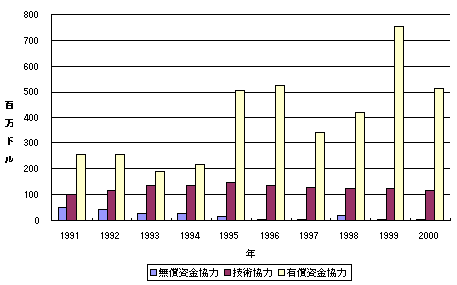
| 出所:外務省経済協力局編「我が国の政府開発援助(ODA白書)」(1999、2000年) |
現在、我が国の援助額は二国間/多国間の対タイ援助全体において、圧倒的に大きな割合を占めている。例えば1997~99年の日本の援助額は、同期間のDAC(Development Assistance Committee)諸国や国際機関による援助総額の82%を占めている19。これは、これまでの緊密な二国間関係を反映したものであると同時に、日本の援助において資金規模の大きい有償資金協力の占める比率が高いことが主因であると考えられる。図2-2は、タイにおける主要ドナーの援助実績(1995~98年の累計支出純額)である。日本の援助額は第2位のドイツに比べ、約20倍という大きさである。
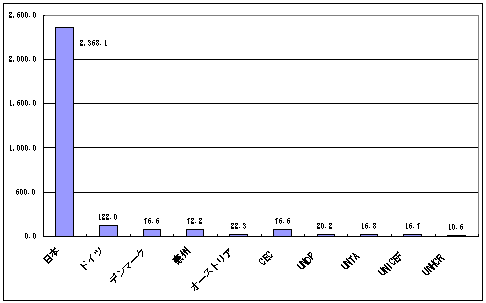
| 出所:外務省経済協力局編「我が国の政府開発援助(ODA白書)」(1999、2000年) |
このように、対タイ援助全体に占める日本の援助額の割合は他のドナーと比較して非常に大きいものである。但し表2-3のように、日本の援助額をタイの国家財政支出と比較すると、1995~99年のタイの国家支出に対する日本の援助額の割合は1.6~4.0%程度である20 21。
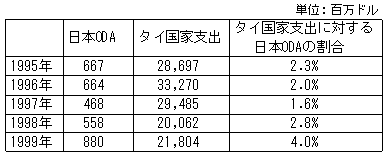
| 出所:外務省経済協力局「我が国の政府開発援助(ODA白書)2000」、Thailand in Figures (2000-2001) |
2.3.2 援助の内容
我が国の対タイ援助は、技術協力ではプロジェクト方式技術協力により、農林水産業、エイズ対策を含めた保健・衛生、大学や職業訓練などの人造り、環境保全等、多岐に渡る分野で実施されている。また開発調査では、これまで道路・港湾等の経済インフラ整備や農林水産分野を中心にハード的な協力が行われてきたが、近年はタイの持続的成長、都市問題や環境問題及び地方格差是正を支援するソフト的案件が拡大してきている。1995~99年度までの対タイ技術協力の分野別経費実績を見ると、農林水産業、公共・公益事業、計画行政、鉱工業、人的資源、保健医療の各分野への支出が多い(図2-3)。
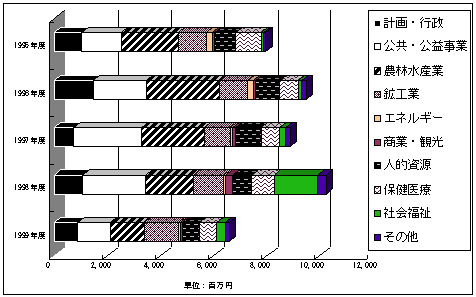
| 出所:JICA年報資料(1996、1997、1998、1999、2000年) |
一方、タイ自身が徐々に被援助国から援助国としての役割を果たしていくことを目的とした形の支援も行われている。1994年8月に署名された「技術協力における日・タイパートナーシッププログラム(Japan-Thailand Partnership Program: JTPP)」は、日本とタイが周辺国の開発努力を支援するために、共同で技術協力を実施する南南協力の枠組みを定めたものである。タイが経費の一部を負担することによってタイで第三国研修を実施したり、共同で専門家派遣を行ったりしている。
有償資金協力では、経済インフラの整備が中心に行われた。有償資金協力における対タイ円借款承諾累計額の部門別構成を1994年度末と2000年度末の時点で示したのが、次の図2-4である。2000年度末時点では、運輸、電力・ガス、社会サービスの3部門で有償資金協力累計額全体の70%以上を占めている。
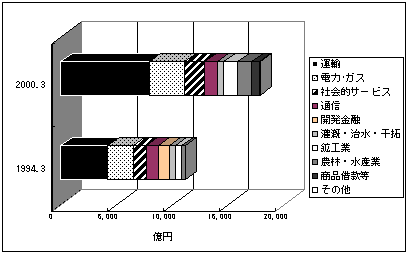
| 出所:JBIC「円借款活動レポート2000年」、「年次報告書別冊」、海外経済協力基金「年次報告書1994年」 |
無償資金協力では、大学や病院の建設・施設拡充、環境分野等への協力が行われてきた。しかし、タイは1993年までに一人当りGDPが安定して2000ドルを越えるに至ったこともあり、1994年度以降、文化無償、草の根無償資金協力、緊急無償援助を除き、無償資金協力は原則実施していない。
2.3.3 タイ経済危機への対応22
1997年に起こったアジア経済危機においては、タイ、インドネシア等の危機当事国に対して、我が国はこれまでに総額約820億ドルの支援策を表明した23 。
タイに対する支援概要は、短期の経済の安定化を目指すものと中長期の経済成長軌道の回復を目指すものの二つの課題に応えるものとなった。前者に関しては、小規模プロジェクトを多数実施する事業への有償資金協力の実施、セクタープログラムローン24 、ノン・プロジェクト無償資金協力25 などからなっていた。また後者の支援についてはインフラ整備のための有償資金協力と人材育成プログラムからなっていた。尚、1998~2000年度に供与が決定された21件の有償資金協力案件のうち、経済の安定化のための割合は3割を占めていた。
技術協力の分野では、研修事業を通した受け入れ人数の大幅な増加があった。1997年度に日本及びタイ国内で研修を受けた人数は686人であったが、1998年度及び1999年度にはそれぞれ5491人、2136人と急増している。
タイ政府関係者に行ったアンケート調査によれば、9割近くが“日本の支援はタイのアジア通貨危機の克服に貢献した”と回答している。具体的な便益としては、雇用創出、更なる経済悪化の防止、人材育成を挙げる回答が多かった。またタイ政府の政策担当者への面談より、有償資金協力が、公共投資計画において不足する資金分を補填したことにより、雇用の確保と景気悪化を食い止めることに貢献したとのことである。
14 バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況2000/2001年版」71頁
15 バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況2000/2001年版」184頁
16 以下、バンコク日本人商工会議所「タイ国経済概況2000/2001年版」113-123頁を参照した。
17 英語では“Sufficiency Economy”と訳されている。1997年12月5日のタイ国王誕生日に集まったタイ国民に対し、通貨危機克服のための勇気を与えるために国王が語った話の中に登場。Made-in-Thaiの勧め、借金生活の戒め、身の丈に合った投資の重要性、過度な市場経済への依存の戒め、自給自足的生活の再評価、国際協調の重要性等を説いている(館逸志「第9次経済社会開発5ケ年計画の策定について」、盤谷日本人商工会議所2000.5より)。
18 外務省ホームページ
19 外務省経済協力局編「政府開発援助(ODA)国別データブック」50頁
20 第5章の効果評価においては、この点に留意しつつ分析を行った。
21 会計年度が両国間で違う点、また日本のODAの金額は実際の支出ではない点から推計値である。
22 以下は、(株)パシフィック・コンサルタンツ・インターナショナル「外務省委託・アジア通貨危機支援評価最終報告書」(2002年3月)を参照した。
23 1997年7月から98年11月末までに表明したアジア支援策:440億ドル、新宮沢構想にもとづく資金援助330億ドル、特別円借款:50億ドルである。これら支援策のうち、タイ、インドネシア等の危機当事国全体に対して総額約680億ドルが具体化された(1999年12月時点
24 借入国の国際収支支援および国内経済安定を目的として融資される商品借款を融資すると同時に、開発途上国の重点セクターの開発政策を支援するため、そこからもたらされる見返り資金を当該セクターの開発計画の投資に振り向けるもの(JBIC年次報告書2001)。
25 無償資金協力の一種で、開発途上国の経済構造改善努力を支援する事を主目的に実施される(財団法人日本国際協力システムホームページ参照)。

