(12) 2年間の活動期間(帰国隊員対象)
図2-34は、「Q.協力隊の2年間の活動期間が適切な長さであるか」という問いに対する結果を示したものである。2年間が“適当である”という回答は全体では56.7%、“やや短い”と“短い”の計は40.3%、“長い”と“やや長い”の計は2.1%であった。しかしながら。配属先の位置付けで分類すると、マンパワー提供型は約8割が2年間の活動期間を“適当である”と回答し、“長い”という回答も3%あった。一方、指導型と共同活動型は、“適当である”という割合がともにほぼ53%、“やや短い”と“短い”の計はそれぞれ44.1%、42.5%であった。この相違は、マンパワー提供型は、活動が単調に陥り易く、またカウンターパートや住民の技術や生活の向上などの進展が見られない場合が多いため、2年間の活動で十分とする意見が多数派を占めたと考えられる。一方、指導型や共同活動型では、技術・知識の移転を行うには、2年間の活動期間では不足と感じる隊員も多いと想定できる。
アンケートへのコメントで「活動期間の前半1年間は語学の習得や生活・活動に慣れるために費やされ、実際の活動は後半1年に集中している」という内容が非常に多く見受けられた。また活動期間が“短い”とする理由は、「やっと活動が軌道に乗り始めた頃に帰国なのであと半年、あるいは1年ほしい」「必要であれば、もっと簡単に延長をさせてほしい」という意見が多かった。また「活動を考えれば3年間ほしいが、帰国後のことを考えると2年が限界」という意見も見受けられた。
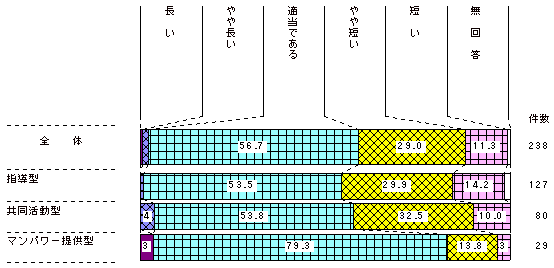
図2-34 配属先の位置付け別2年間の活動期間について
図2-35は、同質問を職種別(部門別)に分類した結果である。ここでは、農林水産部門と保守管理部門において “やや短い”“短い”とする回答が多かった。これは、農林水産部門と保守操作部門の職種は技術移転や技術指導が主たる活動になることが多いため、より時間をかけた活動を要求する声が多いと想定できる。また特に農林水産部門は動植物の成長(速度や時節)とも絡むため、2年間の活動期間が短いという意見が多いと想定できる。
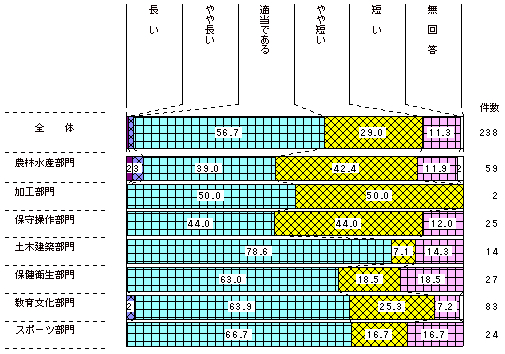
図2-35 部門別 2年間の活動期間について (帰国隊員)

