第4章 分野別経済協力の特徴と評価・分析
上述した通り、我が国は基礎生活分野、雇用創出、インフラ整備、社会資本整備への支援を行っており、1993年-98年9月までの援助総額ベース(MOPICのデータによる)でみても、保健・医療(6,216万ドル、全援助額の21.8%)、教育(4,808万ドル、同15.7%)、組織構築(4,173万ドル、同13.6%)、水資源・汚水処理(1,871万ドル、同6.1%)、一般(道路)インフラ(1,692万ドル、同5.5%)の5分野への援助が上位を占めている(人道的援助を除く)。本節では、比較的定量的評価を行いやすい組織構築以外の4分野のインパクト評価について述べる。本評価では、分野別に援助の総効果を測定するが、今回の調査の性格上、シンプルに我が国援助の実施前と実施後の指標値の比較を行い、その差異を援助の総効果とする。
4-1 保健・医療分野
パレスチナ自治区におけるパレスチナ人の健康指標は比較的良好で、所得水準が同レベルにある他の開発途上国と比較すると高いレベルにあり、平均寿命、乳児死亡率等は中東・北アフリカ諸国平均値を上回っている。これら良好な健康指標は、過去20年間の間NGOならびにUNRWAによりプライマリー・ヘルス・ケアに重点を置いた支援が継続されてきた結果であると言える。しかし、高い人口増加率、高所得経済への移行に伴う疾病の増加(ガン、心臓病等)、保健・医療部門への政府予算の逼迫等の要因により、これら良好な現状を維持していくことは容易なことではない。
表4-1 パレスチナ自治区における保健・医療関連指標の推移
| 1980年 | 1991年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 中東・北アフ リカ平均* |
||
| 人口(千人) | ガザ | 457 | 676 | 886 | 941 | 983 | 1,064 | - | |
| 西岸 | 724 | 1,006 | 1,328 | 1,404 | 1,480 | 1,600 | - | ||
| 合 計 | 1,181 | 1,682 | 2,214 | 2,345 | 2,463 | 2,664 | - | ||
| 乳児死亡率 (出生児千人当り) |
ガザ | - | - | 35.3 | 34.2 | 33.2 | 32.3 | - | |
| 西岸 | - | - | 39.4 | 38.1 | 35.5 | 34.4 | - | ||
| 平均 | - | 42 | 37.0 | 36.9 | 35.6 | 34.5 | - | 48 | |
| 平均寿命(年) | ガザ | - | - | 67.8 | 68.1 | 68.3 | 68.6 | - | |
| 西岸 | - | - | 67.8 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | - | ||
| 平均 | 61 | 66 | 67.8 | 68.1 | 68.4 | 68.7 | - | 67 | |
| 医療ベッド数 | ガザ | - | - | 925 | - | 945 | - | 1,652 | |
| 西岸 | - | - | 1,655 | - | 1,664 | - | 1,898 | ||
| 合計 | - | - | 2,580 | - | 2,609 | - | 3,550 | ||
| 医療ベッド数(千人当り) | ガザ | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | |
| 西岸 | - | - | 1.2 | - | 1.1 | - | - | ||
| 平均 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | - | 1.1 | - | - | ||
出典:人口はイスラエル中央統計庁(Israeli Central Bureau of Statistics)、乳児死亡率と平均寿命は世銀、医療ベッド数は「Hospital Strategic Plan (1999-2003)」、パレスチナ保健庁による
このような現状のもと、ドナー国/機関の約半数が保健・医療部門への支援を行ってるが、表4-2に示すように我が国からの援助が最も多く、援助総額の31.6%を占める6,528万ドルをこれまでに拠出している。
表4-2 各援助国の保健・医療分野への支援状況(1993年-98年9月、実施額ベース)
| 主要援助国 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 合 計 |
| 日本 | 8,900 | 16,010 | 18,820 | 18,420 | 3,136 | 65,286 |
| スペイン | 8,820 | 7,460 | 6,420 | 6,330 | 4,493 | 33,523 |
| サウディアラビア | 15,000 | - | - | - | 6,000 | 21,000 |
| デンマーク | 3,190 | 3,741 | 1,897 | 4,959 | 596 | 14,383 |
| EU | 1,792 | 5,705 | 6,091 | - | - | 13,588 |
| イタリア | 3,127 | 3,945 | 2,668 | 3,069 | 300 | 13,109 |
| スウェーデン | 2,402 | - | 5,543 | 1,297 | 1,920 | 11,162 |
| フランス | 605 | 1,744 | 861 | 492 | 557 | 4,259 |
| オーストリア | 247 | 360 | 865 | 1,532 | 1,117 | 4,121 |
| 米国 | 2,556 | 1,500 | - | - | - | 4,056 |
| イギリス | - | 672 | 1,790 | 1,169 | 16 | 3,647 |
| ベルギー | 1,381 | 677 | 592 | 85 | - | 2,735 |
| ノルウェー | - | - | - | 1,406 | 908 | 2,314 |
| オランダ | 470 | 340 | 370 | 300 | 666 | 2,146 |
| スイス | 2,041 | - | - | - | - | 2,041 |
| オーストラリア | 867 | 481 | 328 | 228 | 61 | 1,965 |
| ルクセンブルク | - | 1,000 | - | 732 | 220 | 1,952 |
| ギリシャ | 1,140 | 20 | 715 | 50 | - | 1,925 |
| トルコ | - | - | 640 | 500 | - | 1,140 |
| その他 | 688 | 543 | 909 | 249 | 146 | 2,535 |
| 合計 | 53,226 | 44,198 | 48,509 | 40,818 | 20,136 | 206,887 |
我が国からの保健・医療分野に関する援助実績(1998年度以前)として以下のものが挙げられる。
1)無償資金協力
- エリコ病院への医療機材供与(1993年度、250万ドル)
- ガザ医療機材整備計画(シーファ病院、ハーン・ユーニス病院、小児病院、眼科医院、1995年度、1,283万ドル)
- エリコ病院建設計画(1996年度、2,012万ドル)
- 西岸地域医療機材整備計画(ジェニン病院、トゥルカレム病院、ワタニ病院、ラフィディア病院、ラマッラー病院、ベイトジャラ病院、ベツレヘム病院、ヘブロン病院、維持管理センター、1997年度、1,520万ドル)
- トゥルカレム病院改修計画(405万ドル)
4)WHOへの緊急災害援助(医療品、医療機材、ワクチン、救急車供与等、合計340万ドル)
5)赤十字国際委員会への拠出(プライマリー・ヘルス・ケア・プロジェクト等、合計100万ドル)
6)草の根無償資金協力(病院改善、機材供与を中心に16件、合計80万ドル)
7)研修員受入(実績47名、60万ドル)
これら援助のインパクトを定量的に算出することは難しいが、日本が援助を本格化した1993年あるいは1994年の健康指標と1997年の指標とを比較すると、表4-1に示すように、乳児死亡率は1993年の37人から1997年には34.5人に低下(パレスチナ保健庁によると、1993年の31.9人から1998年には22人に低下)、平均寿命は1994年の67.8歳から1997年には68.7歳へと上昇(パレスチナ保健庁によると1993年の64歳から1998年には71歳に上昇)している。これら指標データの向上は、保健・医療分野への援助総額の約3分の1を占める日本からの援助が重要な役割を果たしたことは明確である。また、医療ベッド数の増加が人口増加に追いつかず、人口千人当たりのベッド数は減少傾向にある現状(1991年の1.4から1997年には1.1へ減少)を鑑みると、1996年に開始されたエリコ病院の建設は、現状改善に則した援助であり、医療設備の質とともに量の改善にも貢献したものと言える。
また、パレスチナにおける医療政策の重点が2次、3次医療へ移行し、ややもすれば富裕層に対する医療レベルの向上に偏る傾向があったにもかかわらず、我が国が、貧困層の健康レベル向上に向け、従来のプライマリー・ヘルス・ケアならびに予防医療への支援の継続を赤十字国際委員会への拠出を通じて行ってきたこと、また地方における保健・医療レベルの向上を目的とした草の根無償資金協力を実施してきたことは高く評価でき、これら援助がパレスチナ自治区全体の健康指標の向上・維持に果たしてきた役割は大きい。
さらに、表4-3に示すようにパレスチナにおける健康保険加入世帯数は1993年の13.4万世帯から1997年には22.8万世帯へと増加している(加入率は38.5%から55%へ上昇)。自治政府の保健・医療部門への支出割合は、年々減少傾向にあり1997年の予算ベースでは11%を占めるにとどまっているが、医療部門への財源を健康保険からの収入で賄うことは、同分野における自立的・持続的運営につながるものである。保健・医療分野の質の向上が健康保険加入者増加につながるわけであるが、そういった意味で我が国の医療機材供与、あるいは病院の新設は大いに貢献していると言えよう。
表4-3 保健・医療部門支出と健康保険加入状況
| 1993年 | 1997年 | |
| 医療分野への政府支出額(百万ドル) | 60 | 97.3 |
| 予算に占める医療部門支出の割合(%) | 21 | 11 |
| 健康保険への加入世帯数 | 134,000 | 227,809 |
| 健康保険加入率(%) | 38.5 | 55.0 |
保健・医療部門での援助では上述の「もの」だけではなく人造りの面においても大きな貢献を果たしてきた。他国による研修プログラムが短期間であることに比べ、我が国が実施している研修プログラム、特にジョルダンにおける第3国研修はサイクル的にパレスチナの技術者、エンジニアを派遣するなど、効果的に技術、能力を向上させており、高い評価を受けている。
個々のプロジェクトに目を向けるとマイナーな問題は存在する。機材の補修・交換に関しては現地にエージェンシーが存在しないため日数を要し、供与機材の利用を妨げる、あるいは供与機材が高度化するにつれ通常の研修では完全に使いこなすことができない、などの問題が挙げられる。また、近い将来にはメンテナンス、消耗品補給等に係る資金の問題も生じてくると思われる。供与された機材等はパレスチナ側が自助努力により使用していくことが前提であるが、援助後の持続性を確保するためには、スペアパーツの数量を当初よりあらかじめ増加させておくこと、あるいはやや長めの期間においてスペアパーツの補給を日本側が行い徐々に補給率を下げていく方法も考えられる。また、機材供与先の病院、クリニックなどを定期的に巡回モニタリングするシステム(現状では難しいが将来的には専門家あるいは青年海外協力隊員による)の導入も有効であろう。
また援助配分としては、機材供与等により2次、3次医療の質のさらなる向上ならびに健康保険加入者増加による自立的・持続的経営に貢献するとともに、今後増加するであろう成人病対策としての予防医療の拡充(高額医療出費の削減にもつながる)、地方住民の健康レベル向上に向けてのプライマリー・ヘルス・ケアの充実を継続させていくことが重要であり、これらのバランスを考え援助を実施していく必要があろう。
4-2 教育
パレスチナの教育部門は現在初等・中等教育を管轄する教育庁と高等教育を管轄する高等教育庁の2つの組織により管理されている。初等教育は10年間で、その後2年間の中等教育があり、生徒は中等教育開始時に科学、文学、職業の3つの分野の何れかに進むことになる。中等教育終了後の試験(Tawjihi)に合格した生徒は高等教育レベルへ進学することができる。表4-4に示すように、中等教育までの教育主体は現在、政府、UNRWA、民間/NGOの3つに大きく分類され、特に幼稚園は国際NGOによってのみ運営されている。
表4-4 パレスチナ自治区における主体別教育指標(1998年度)
| 学校数 | クラス数 | 生徒数 | |||||||
| 公立 | UNRWA | 私立/NGO | 公立 | UNRWA | 私立/NGO | 公立 | UNRWA | 私立/NGO | |
| 幼稚園 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 2,843 | 0 | 0 | 77,173 |
| 初等教育 | 811 | 265 | 128 | 13,689 | 4,555 | 1,843 | 487,738 | 210,759 | 48,417 |
| 中等教育 | 419 | 0 | 68 | 1,944 | 0 | 238 | 61,666 | 0 | 4,142 |
パレスチナ人の識字率は高く、1997年の15歳以上の識字率は84%で、中東・北アフリカ諸国平均値の61%を大きく上回る。また世銀によると、就学率も比較的高く、初等教育レベルで91%、中等教育レベルで65%となっている(共に1997年値)。また、過去約60名であった1クラス当たりの平均生徒数も減少傾向にあり、最近では36名程度に落ち着いており、ダブルシフトを必要とする学校数も全体の約18%にとどまっている。これら指標の安定・向上は、下述するように各援助国/機関からの支援によるところが非常に大きい。
しかしながら、特にガザ地域における高出産率により、初等教育入学年齢層の数が急増する傾向にあり、現在の教育指標レベルを維持していくには、さらに学校数、クラス数、教師数等を増やしていく必要がある。また、UNRWA管理下の学校では1クラス当たりの生徒数は依然として多く、パレスチナ統計局によると、1998年平均値で46.3名、特にガザ地域では49.6名となっており、1997年時点の状況(46名、ガザ地域50名)は改善されていない。また、西岸ではジョルダンの教育カリキュラム、ガザではエジプトのカリキュラムが導入されており、これら両地区におけるカリキュラムの不整合の改善とともに、パレスチナの教育水準に合致した教育カリキュラムの確立が急がれている状況にある。
表4-5 パレスチナ自治区における教育関連指標の推移(1994-98年度)
| 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | ||
| 学校数 | 初等教育 | 1,141 | 1,098 | - | - | 1,204 |
| 中等教育 | 333 | 372 | - | - | 487 | |
| 合計 | 1,474 | 1,470 | 1,532 | 1,611 | 1,691 | |
| クラス数 | 初等教育 | 15,436 | 16,336 | - | 18,871 | 20,087 |
| 中等教育 | 1,502 | 1,462 | - | 2,047 | 2,182 | |
| 合計 | 16,938 | 17,798 | 19,485 | 20,918 | 22,269 | |
| 生徒数 | 初等教育 | 572,529 | 611,857 | 656,353 | 702,382 | 746,914 |
| 中等教育 | 45,339 | 50,770 | 56,467 | 61,085 | 65,808 | |
| 合計 | 617,868 | 662,627 | 712,820 | 763,467 | 812,722 | |
| 教員数 | 19,846 | 21,563 | 23,853 | 26,045 | 27,461 | |
| クラス当り生徒数 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | |
| 教員一人あたり生徒数 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | |
| 中途退学率(%) | - | 2.8 | 2.2 | 2.1 | - | |
| 識字率(%) | - | 78.6 | 83.9 | 84.0 | - | |
教育レベルの向上はパレスチナの経済発展、貧困緩和に向けて重要な役割を果たすことが期待されるが、同部門への政府財政支出の割合は非常に高く、外国からの援助が必要な状態が続いている。教育部門への支援は、学校建設/改修、教員訓練、奨学金付与などが主であり、現在までに29の援助国/機関が援助を実施している。表4-6に示すようにEUが最大のドナーであり、教育分野への援助総額の43.6%を占める1億2,800万ドルを拠出している。国単位では我が国からの援助が最も多く約4,900万ドルで、総額の16.6%を占めている。
表4-6 各援助国の教育分野への支援状況(1994年-98年9月、実施額ベース)
| 主要援助国 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 合 計 |
| 1 EU | 22,240 | 33,172 | 62,335 | 10,253 | - | 128,000 |
| 2 日本 | 4,444 | 23,250 | 850 | 19,531 | 568 | 48,643 |
| 3 オランダ | 3,430 | - | 5,000 | 6,821 | 4,650 | 19,901 |
| 4 スイス | 3,741 | 3,356 | 1,956 | 4,494 | 703 | 14,250 |
| 5 ノルウェー | - | 2,934 | 5,919 | 1,547 | 844 | 11,244 |
| 6 米国 | 920 | 5,030 | 3,600 | - | - | 9,550 |
| 7 イタリア | 730 | 500 | 4,571 | 2,300 | 1,000 | 9,101 |
| 8 フランス | 1,113 | 1,619 | 2,004 | 2,347 | 1,412 | 8,495 |
| 9 ドイツ | 5,120 | 373 | 561 | 453 | 640 | 7,147 |
| 10スペイン | 280 | 700 | 1,480 | 2,378 | 1,450 | 6,288 |
| 11サウディアラビア | 2,500 | 2,500 | - | - | - | 5,000 |
| 12ベルギー | 3,330 | - | 312 | 750 | - | 4,392 |
| 13イギリス | - | 656 | 1,303 | 2,048 | - | 4,007 |
| 14オーストリア | 157 | 1,269 | 74 | 577 | 988 | 3,065 |
| 15アイルランド | 288 | 348 | 938 | 862 | - | 2,436 |
| その他 | 6,138 | 353 | 1,149 | 2,340 | 2,187 | 12,167 |
| 合 計 | 54,431 | 76,060 | 92,052 | 56,701 | 14,442 | 293,686 |
我が国からの教育分野に関する援助実績(1998年度以前)として以下のものが挙げられる。
1)無償資金協力
- 高等教育機材整備計画(アル・アズハル大学、デルバラ短期大学、1995年度、891万ドル)
- ガザ地域小中学校建設計画I(7つの小中学校建設、1997年度、1,631万ドル)
- ガザ地域小中学校建設計画II(3つの小中学校建設、1998年度、726万ドル)
- アル・コドゥス大学医学部機材整備計画(1998年度、429万ドル)
- エリコ学校・文化施設改善計画(1-3期、合計325万ドル)
- 西岸・地方学校校舎改善計画(1995年、200万ドル)
- ヘブロン市教育・公共施設改善計画(1996年度、200万ドル)
- アル・ビレア文化施設改善計画(1998年度、100万ドル)
- 高等教育のための奨学金等(総額282万ドル)
- ジフトレック共学学校建設(1993、94年度、98万ドル)
- パレスチナ帰還者のための初中等学校建設(1994年度、160万ドル)
- 3学校の建設ならびに機材整備(1995年度、250万ドル)
- エズベット・ベイト・ハヌーン難民キャンプにおける2学校改善計画(1996年度、25万ドル)
- ビーチ・ヤンプ初等学校建設(1997年度、87.1万ドル)
- ガザ男子幼稚園建設(1997年度、100万ドル)
5)草の根無償資金協力(小中高等学校改善等多数)
6)研修員受入(教員育成) 要確認
これら援助による直接的インパクトとしては、当然のことながら学校数の増加(無償資金協力による10校とUNRWAへの拠出による学校建設分)と、それに伴うクラス数の増加あるいは校舎改善によるクラス数の増加が挙げられる。また、これら援助によるクラス数の増加は、パレスチナ自治区、特にガザ地区における教育の質の維持・向上に貢献していることも明確である。
例えば、表4-7に示すように、ガザ地区における初中等学校におけるクラス当たりの生徒数は、生徒数の急増にもかかわらず1994年以降約45人で安定的に推移している。これは我が国とEUが中心となり学校建設等に対する支援を継続してきた結果であり、これら援助がなければガザ地区における教育環境は急速に悪化の道を辿っていったと考えられる。また、ダブルシフト導入の学校数も減少しており、学校単位でのカリキュラムの充実、課外クラブ活動の導入に貢献している(ダブルシフト導入校ではクラス時間の短縮、教育の詰め込みが不可避となる)。
表4-7 ガザ地区における初中等学校クラス当たり生徒数の推移(1994-98年度)
| 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | |
| 初等・中等生徒数 | 234,921 | 259,254 | 281,255 | 304,386 | 327,232 |
| 初等・中等クラス数 | 5,242 | 5,742 | 6,272 | 6,715 | 7,279 |
| 1クラス当たり生徒数 | 44.8 | 45.2 | 44.8 | 45.3 | 45.0 |
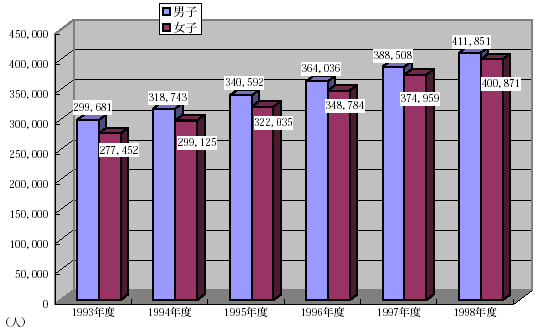
出典:パレスチナ統計局(Palestinian Central Bureau of Statistics)資料より調査団作成
また、パレスチナ自治区においては学校数が相対的に不足していたために、特に村落レベルにおいては通学距離等の問題(他村落学校への通学の必要性とその困難性)があり、これが中途退学者の多い原因の1つとなっていた。しかし、表4-5に示すように、中途退学者率は1995年の2.8%から1997年の2.1%へと減少しており、援助による学校数の増加ならびに学校施設の改善による効果がここにも現れている。また、学校数の増加は、これまで教育機会がやや男子に偏っていいた現状をも改善しつつある。図4-1に示すように、女子生徒の増加率が男子生徒の増加率を上回っており、男女生徒数の割合は年々に均衡状態に近づきつつある。男女教育機会の均等はパレスチナ暫定自治政府の政策にも合致するものであり、また女性の教育レベルの向上は貧困問題の解決、あるいは人的開発レベルの底上げに直結することから非常に重要である。そういった意味でも教育分野において2国間レベルで最大である我が国の援助は大いに評価されるべきであろう。また、これら援助は教員数の増加にもつながっており、雇用創出にも貢献している。しかし、この点については教員の質の低下につながらぬよう注意を払う必要がある。特に理系教員の数が不足しており、我が国としても理系教員の育成に向けた支援を行っていく必要があろう。
高等教育関連では、現在8つの大学と16の短期大学が設置されているが、湾岸戦争(1990-91年)以前は高等教育財源の約4分の3を占めていた周辺アラブ諸国からの援助が急減したことから、国際社会からの援助が必要となっている。我が国は、主に機材供与、特に医学関連機材の供与を中心に行ってきたが、これら援助は大学・短大における教育の高度化に貢献していると言える。また、これら機材は、教育庁、高等教育庁、労働庁の3庁で実施している職業・技術教育の一環としても使用されており、学生はもちろん技術者のレベル向上にも役立っている。高等教育に係る問題点としては、やはり卒業生の就職難であり、入学者を増加させ授業料等による高等教育機関の自立的経営に向けては、労働市場の拡大が重要となる。
小中学校建設計画に関しては、現在これらプロジェクトにより建設された小中学校の開校が始まりつつある状況であり、特に際立った問題は起こっていない。今後は施設、機材等のメンテナンスの問題が出てくると考えられる。現地ヒアリングによると、現在設定されている授業料は年間40-50シェケル(約1,200-1,500円)であり、これら財源によりメンテナンスを行っていくとされている。高等教育関連機材に関しては、すでにスペアパーツの入手が問題になりつつある。また、機器で使用する原材料がパレスチナの特殊性により入手が困難なケース(核開発への使用疑惑等)も見られることから、今後の援助実施に際してはこれらの点を考慮に入れる必要がある。また、機材の運転・活用についても内容が高度であるが故に、技術者の能力がついていかないケースもあり、今後はワークショップの設置など機材使用に係る研修の充実を図る必要がある。
パレスチナ自治区では、現在職業学校(日本で言う工業高校)への進学者が全体の約3%にとどまっている(注5)。また、高等教育においても理系・工学系の学生が少なく、社会科学系の学生が大部分を占めている。パレスチナ暫定自治政府としては、今後の労働市場で必要となろうこれら分野の学生の割合を全体の12%まで引き上げたいとしており、我が国としても、今後上述の理系教員の育成、あるいは理系教育関連機材供与等について協力できる可能性がある。
4-3 水資源
表4-8に示すように、パレスチナ暫定自治区では世帯数の約86%が上水道網へ接続されている。しかしながら、水供給量は1990年代に入り減少しており、特に西岸では一人あたりの水供給量は国連の最低必要量基準を下回っている(注6)。暫定自治区における水供給は、イスラエルの管理下(厳密にはイスラエル企業である「Mekoroth」の管理下)にあり、パレスチナ人による新規地下水井戸の掘削は制限されている。また、暫定自治区内の新規水源からの水資源の分配はMekorothにより行われており、イスラエル人入植者への水供給量はパレスチナ人の約4倍と推定されている。パレスチナ暫定自治政府とイスラエル政府間で締結された暫定合意では、パレスチナ自治区において年間2,860万m3の水の使用が承認されているが、水関連大規模プロジェクトの実施が予定されているC地区ではプロジェクトの承認(合同水委員会(Joint Water Committee)による技術関連承認と行政面での承認が必要となる)までに最低2ヶ月かかっており、これがプロジェクトの遅延や中止の原因となっている(注7)。これら政治的理由に加え、地下水面の低下による塩水化、汚水や農薬による水汚染など起こっており、状況をさらに悪化させている。
国際社会は、これら状況の改善に向け約80の水供給プロジェクトを実施しており、その援助総額は1998年9月までの実施額ベースで約2.5億ドルとなっている。水資源・衛生部門に対しては21の国/機関が援助を実施を実施しているが、表4-9に示すように米国からの援助が最も多く、同部門への援助総額の約44%を占める1.08億ドルの支援を行っており、ドイツが3,219万ドル(総額の約13%)でこれに続く。我が国は同分野において米国、ドイツに次ぐ第3位の援助国であり、援助額は2,043万ドル(総額の約8%)で、その大部分はUNDPを通じた援助プロジェクトにより実施されている。
表4-8 パレスチナ暫定自治区における取水源(1998年)
| 世帯数 | 上水道ネットワーク | 地下水井戸 | 貯水タンク | 貯水池 | ||||||
| 世帯数 割合 |
水使用量 | 世帯数 割合 |
水使用量 | 世帯数 割合 |
水使用量 | 世帯数 割合 |
水使用量 | |||
| 西岸(北部) | 1,022 | 73.5% | 20.4 | 10.7% | 13.2 | 47.8% | 8.3 | 1.7% | 10.4 | |
| 西岸(中部) | 649 | 96.9% | 19.6 | 1.0% | 6.4 | 11.1% | 8.9 | 1.7% | 11.6 | |
| 西岸(南部) | 630 | 78.7% | 19.1 | 10.5% | 10.3 | 61.8% | 6.2 | 0.5% | 6.3 | |
| 西岸地域全体 | 2,301 | 82.2% | 19.8 | 7.6% | 11.9 | 39.9% | 7.5 | 1.4% | 10.5 | |
| ガザ地域全体 | 918 | 97.6% | 24.7 | 0.1% | - | 1.9% | 31.3 | - | - | |
| 暫定自治区全体 | 3,219 | 85.9% | 21.2 | 5.8% | 11.8 | 30.7% | 7.9 | 1.1% | 10.5 | |
出典:パレスチナ統計局(Palestinian Central Bureau of Statistics)資料より調査団作成
表4-9 各援助国/機関の水資源・衛生分野への支援状況(1994年-98年9月、実施額ベース)
| 主要援助国/国際機関 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 合 計 |
| 1 米国 | 1,130 | 21,000 | 32,537 | 45,474 | 7,995 | 108,136 |
| 2 ドイツ | 6,436 | 6,056 | 3,619 | 8,188 | 7,895 | 32,194 |
| 3 日本 | 5,650 | 4,200 | 5,174 | 3,250 | 2,155 | 20,429 |
| 4 フランス | 7,216 | 2,315 | 3,104 | 6,738 | 4 | 19,377 |
| 5 ノルウェー | 89 | 1,313 | 2,481 | 8,343 | 3,986 | 16,212 |
| 6 世銀 | - | - | 2,888 | 4,966 | 5,956 | 13,810 |
| 7 イギリス | - | 238 | 2,226 | 3,282 | - | 5,746 |
| 8 イタリア | 2,900 | 1,250 | 780 | 680 | 5,610 | |
| 9 スイス | 1,837 | 2,587 | - | 680 | 159 | 5,263 |
| 10オランダ | 410 | 540 | 990 | 1,200 | 1,008 | 4,148 |
| 11ベルギー | 619 | 2,626 | - | - | - | 3,245 |
| 12フィンランド | 370 | 350 | 392 | 1,077 | 982 | 3,171 |
| 13カナダ | 725 | - | 1,812 | 529 | - | 3,066 |
| 14スペイン | - | 430 | 500 | 395 | 510 | 1,835 |
| 15スウェーデン | - | - | 533 | 929 | 190 | 1,652 |
| 16オーストリア | - | - | - | - | 1,606 | 1,606 |
| 17UNDP | 144 | 233 | 63 | - | 113 | 553 |
| その他 | 0 | 80 | 1 | 1 | 160 | 242 |
| 合 計 | 24,626 | 44,868 | 57,570 | 85,832 | 33,399 | 246,295 |
我が国からの水資源・衛生分野に関する援助実績(1998年度以前)として以下のものが挙げられる。
1)無償資金協力
- ゴミ処理機材整備計画(1998年度、1,125万ドル)
- ハーン・ユーニス地域衛生改善計画(1998年度、240万ドル)
- ハーン・ユーニス上水道改善計画(1993-97年度、合計495万ドル)
- ガザ北部の汚水処理・再生利用計画(1993年度、95年度、合計310万ドル)
- トウカレム配水システム改善計画(1993年度、95年度、合計70万ドル)
- ガザ地区道路・上下水道整備計画(1996年度、200万ドル)
- 西岸北部水供給改善計画(1997年度、25万ドル)
- ガザ地域東部村落井戸・給水網開発計画(1997年度、100万ドル)
- デール・エル・バラハ市給水網改善計画(1997年度、100万ドル)
- 西岸地域水資源開発計画(1998年度、50万ドル)
- ヘブロン地域農村給水網改善改革(1998年度、200万ドル)
- エリコ地域井戸掘削計画(1998年度、100万ドル)
- 上下水整備(1993年度、200万ドル)
- 西岸上下水道開発(1997年度、25万ドル)
6)開発調査
- ハーン・ユーニス市下水道整備計画調査(1995年度より)
表4-10に示すように、我が国援助により1995年度から98年度にかけて新たに整備された上水道網は22.4kmに及んでおり、上水道への新規接続世帯数も同期間で1,109世帯増加している。下水については、同じく1995年度から98年度にかけて新たに整備された下水網は10kmで下水網への新規接続世帯数は同期間において907件増加している。
表4-10 我が国のUNDP経由援助による上下水道整備状況(1995-98年)
| 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 合 計 | ||
| 上水 | 新規水道網(m) | 10,819.4 | 1,977.6 | 6,886.5 | 2,713.6 | 22,397.1 |
| 新規水道接続世帯数 | 591 | 132 | 202 | 184 | 1,109 | |
| 下水 | 新規下水網(m) | 1,521.3 | 912.4 | 4,178.0 | 3,399.7 | 10,011.4 |
| 新規下水接続世帯数 | 278 | 166 | 162 | 301 | 907 | |
また表4-11に西岸地区各都市において水道網へアクセスしている村落数の推移を示すが、総数では1993年の293村から1997年には340村へと増加しており、各村落における水道網へのアクセス世帯率平均も1993年の60%から1997年には69%へと上昇している。特に我が国が重点を置き援助を実施してきたトゥルカレム、ヘブロンにおいて大きな改善効果が見られる。トゥルカムでは、水道網へのアクセス村落数は1993年の33から1997年には53へと大きく増加しており、アクセス世帯率も1993年の37%から1997年には53%と16%上昇している。また、ヘブロンにおいてもアクセス村落数は1993年から97年の間に12増加し、総世帯の半数以上が水道網へのアクセスを得る状況となっている。
表4-11 西岸地区各都市における水道配管網へのアクセス村落数の推移
| 都市名 | 1993年 | 1997年 | ||
| 村落数 | アクセス率(%) | 村落数 | アクセス率(%) | |
| ジェニン | 24 | 34 | 34 | 49 |
| トゥルカレム | 33 | 37 | 48 | 53 |
| ナブルス | 26 | 49 | 30 | 57 |
| ジョルダン・バレー | 11 | 79 | 12 | 86 |
| ラマッラ | 79 | 86 | 84 | 91 |
| ベツレヘム | 66 | 93 | 66 | 93 |
| ヘブロン | 54 | 44 | 66 | 54 |
| 合計293 | 平均 60 | 合計340 | 平均 69 | |
これら統計値からも明らかなように、我が国援助はパレスチナ暫定自治区における水資源供給網整備に大いに貢献している。我が国の対パレスチナ援助に関しては、ガザ地区と西岸地区における援助量のバランスに配慮し援助を実施していることから、水資源供給に関しても、プロジェクト件数では両地区においてほぼ同数の援助が実施されている。ガザ地区では地下水の汚染が特に深刻であることや地下水汲上げ量が安全容量を大きく越えていること、また西岸地区(特に北部と南部)では上水道網へのアクセス割合が低いという状況を鑑み、我が国が両地区において、それら現状改善に即した援助を実施してきたことは大いに評価できる。今後は、上水道整備に加え、下水処理に係るインフラの整備が急務とされており、すでに実施しているハーン・ユニス市下水道整備計画も含め、我が国としても協力の可能性を検討する段階に来ていると思われる。
上下水道設備のメンテナンスに関しては、比較的規模の大きな都市ではそれなりの規模のワークショップを設置し管理を行っているが、小規模都市に関しては、ワークショップはあるもののすべてをカバーできるだけの能力は備えていない。人材に関しては、若いエンジニアが多数存在することから、今後は、経済的観点も考慮に入れた形で水道料金の見直しを図ることにより収益を増やし、オペレーション/メンテナンスコストをカバーしていく必要がある。また、これら水道料金の見直しは、水資源の乏しいパレスチナにおいて重要となる節水へのインセンティブにもなる。
上述したように、我が国の水資源関連援助は、主にUNDP経由で実施されている。これはUNDPのノウハウ、ローカルコネクション等により、より効率的/効果的な援助が期待できるためであり、現に期待に背かない形で援助が実施されている。しかし、ややもすれば我が国が直接モニタリングできる範囲も限られ、UNDPにまかせた形になってしまう現実も否めない。水資源関連分野ではドナー間の調整不足、パレスチナ開発計画との整合性の欠如といった点が指摘されることもあることから、UNDPと日本大使館との間のローカルベースでのコンタクトを密にとる必要がある。
4-4 一般(道路)インフラ
表4-12に示すように、パレスチナ暫定自治区における道路ネットワークは、主要幹線が600km、地域間道路(中小都市を結ぶ)が700km、地方道路が1,200kmであり、総延長は約2,500kmとなっている。これら道路ネットワークの大部分は1967年のイスラエル占領以前に建設されたものであり、イスラエルによるメンテナンスがほとんどなされなかったため、道路の状態は非常に悪い。主要幹線においては56%にあたる336kmが劣悪な状況であり、地方道路に至っては64%に相当する768kmにおいて損傷が激しい状態にある。従って暫定自治区における道路はネットワークとしても不十分な状態にある。パレスチナの社会経済活動の活性化
表4-12 パレスチナ暫定自治区における道路の現況(1998年現在)
| 道路状態 | 主要幹線 | 地域間道路 | 地方道路 | ||||||
| ガザ | 西岸 | 合計 | ガザ | 西岸 | 合計 | ガザ | 西岸 | 合計 | |
| 良好 | 23 | 56 | 79(13) | 24 | 98 | 122(17) | 33 | 150 | 183(15) |
| 普通 | 20 | 165 | 185(31) | 18 | 262 | 280(40) | 32 | 217 | 249(21) |
| 劣悪 | 56 | 280 | 336(56) | 23 | 275 | 298(43) | 65 | 703 | 768(64) |
| 総延長 | 99 | 501 | 600 | 65 | 635 | 700 | 130 | 1,070 | 1,200 |
に向けては、これら道路ネットワークの改修・修復が非常に重要となるが、上述の通り暫定自治区面積の多くを占めるC地区はイスラエルが行政権限を維持していることから、ドナー国/機関の援助プログラムは、パレスチナ自治政府管理下地域の道路、言い換えれば地方道路、の改修/修復を中心に実施されている(注8、注9)。
一般インフラ関連への援助総額は1998年9月までの実施額ベースで総額約9,000万ドルとなっている。表4-13に示すように世銀経由の支援が最も多く、総額の約31%に相当する2,762万ドルの援助を行っている。2国間ベースでは、我が国からの援助が最も多く、同部門への援助総額の約24%にあたる2,124万ドルの支援を行っている。
表4-13 各援助国/機関の一般インフラ分野への支援状況(1994年-98年9月、実施額ベース)
| 主要援助国/国際機関 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 合 計 |
| 1 世銀 | - | - | 7,280 | 5,980 | 14,360 | 27,620 |
| 2 日本 | 5,000 | 4,000 | 4,915 | 3,000 | 4,329 | 21,244 |
| 3 EU | - | 769 | 211 | 9,469 | 9,205 | 19,654 |
| 4 ノルウェー | 2,700 | 2,700 | 4,501 | 1,647 | 1,909 | 13,457 |
| 5 スペイン | - | 1,000 | 350 | - | 520 | 1,870 |
| 6 スウェーデン | 89 | - | 1,612 | 72 | 53 | 1,826 |
| 7 ギリシャ | - | - | - | 1,700 | 1,700 | |
| 8 オランダ | - | - | 1,440 | - | - | 1,440 |
| 9 中国 | - | - | - | 780 | 780 | |
| 10アルゼンチン | - | - | 119 | 226 | 104 | 449 |
| 11韓国 | - | - | - | 20 | 20 | |
| 合 計 | 7,789 | 8,469 | 20,428 | 20,394 | 32,980 | 90,060 |
我が国からの一般インフラ関連援助は、UNDP経由のプロジェクト並びに直接援助による機材供与等がある。具体的な援助実績として以下のものが挙げられる。
1)無償資金協力
- ガザ地域主要道路改善整備計画(1996年度、522万ドル)
- 西岸地域主要道路改善整備計画(1998年度、505万ドル)
- ガザ道路舗装雇用創出プロジェクト(1994年度、500万ドル)
- ガザ市街地インフラ整備(1995年度、100万ドル)
- ナブルス舗道整備(1995年度、200万ドル)
- パレスチナ市町村支援(1996年度、125万ドル)
- ジェニーン地区地方村落開発計画(1996年度、200万ドル)
- ハーン・ユーニス地区インフラ整備計画(1996年度、300万ドル)
- ベツレヘム地区雇用創出・経済開発計画(1996年度、500万ドル)
- ガザ地域北部インフラ改修雇用創出計画(1997年度、300万ドル)
- 西岸地域土地開拓雇用創出計画(1997、98年度、合計400万ドル)
- クァルキルヤ地区地方村落開発計画(1998年度、100万ドル)
- ガザ空港整備計画・人材育成計画(1998年度、442万ドル)
- ラファラ通行所及びカルニ通行所修復・建設計画(1998年度、236万ドル)
- エレツ通行所整備計画(1998年度、675万ドル)
- 3)草の根無償資金協力
- タンムーン町町内道路補修計画(1999年度、9万ドル)
4)研修員受入
UNDP経由の援助では、表4-14に示すように約13km2の道路の舗装ならびに4.7km2の歩道建設が行われている。また、直接援助により道路建設用機材の供与がなされたことにより、ガザ、西岸の両地区においてメンテナンス体制が整った。暫定自治区では効果的/効率的にメンテナンスを実施するために、道路状況に係るデータバンクがあり、この情報に基づき毎年メンテナンス道路の選定、予算措置、工程計画策定が行われる。我が国援助によりメンテナンス体制が整ったことから、今後はよりスムーズに道路の補修/改修が行われることになると思われる。供与機材により、道路舗装のみならず、交差点/ロータリーの整備も進められており、我が国援助は、交通のスムーズ化、交通事故死の減少にも貢献している。
表4-14 我が国のUNDP経由援助による道路インフラ整備状況(1995-98年)
| 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 合 計 | |
| 新規舗装道路面積(m2) | 33,779.0 | 14,630.7 | 45,734.3 | 38,030.0 | 132,174.0 |
| 新規建設歩道面積(m2) | 19,614.8 | 4,547.3 | 16,873.3 | 6,951.6 | 47,987.0 |
供与機材のコンディションは現在のところ良好であるが、ガザ地区については、機材の供与から約2年が経過したことから、メンテナンスの必要性が高まっており、ワークショップの立上げを計画中である。現段階ではオイル交換などの防御メンテナンスをこまめに行っているが、今後はエンジンにオーバーホール、トランスミッションの調整等、定期的メンテナンスを行う必要性が出てくると予想される。スペアパーツに関しては、現時点では日本の援助により入手済みであるが、将来的には自助努力による入手が必要となる。
道路関連技術者の能力については、特に問題はなく、その意味からも我が国からの供与機材は適切なものであったと言える。これら技術者の研修はエジプトにおける第3国研修にて行われており、1994-98年の間に約100名が研修を受けている。高度技術の取得については、さらなる研修が必要との声も聞かれたことから、我が国としては機材供与と並行して技術者の研修に係る支援も継続していく必要がある。
一般インフラ関連分野への援助は、水資源部門と同様、UNDP経由による支援が多いことから、各プロジェクトのモニタリングの観点からも、UNDPと日本大使館との間のローカルベースでのコンタクトを密にとる必要がある。
一般インフラ関連援助はパレスチナ暫定自治区における雇用創出にも大いに貢献している。イスラエルの封鎖政策と和平進展に伴う難民の帰還により、1995年以降パレスチナ人の失業者数は急増し、前年の約12.5万人から15.3万人へ、さらに1996年には18.4万人へと増加した(表4-15参照)。UNDP経由の我が国援助プロジェクトでは、延べ人数ではあるものの、表4-16に示すように総数で約58,547人の雇用を創出しており、パレスチナにおける失業者数増加に対する一定の歯止め効果を有している。
表4-15 パレスチナにおける労働指標(1995-98年)
| 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | ||
| 労働人口 | 527 | 548 | 553 | 585 | |
| 雇用確保者数 | 374 | 364 | 399 | 431 | |
| うちガザ、西岸地区 | 32 | 22 | 38 | 44 | |
| うちイスラエル | 342 | 342 | 361 | 387 | |
| 失業者数 (労働人口-雇用確保者数) |
153 | 184 | 154 | 154 | |
表4-16 我が国のUNDP経由援助による雇用創出効果(1995-98年度)
| 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 合 計 | |
| 雇用者数(人) | 26,091 | 6,481 | 8,984 | 16,991 | 58,547 |
脚注
5 1)アカデミック的に不適格な生徒が進学するというイメージ、2)イスラエルが職業教育に力を入れなかった、3)男性向けの学校というイメージ、などの理由が挙げられる。
6 世銀によるとパレスチナ自治区における水供給量/日/人は約90リットル以下、ジョルダンでは約140リットル、イスラエルでは約280リットルとされている。
7 西岸においては自治権の度合に応じて、地域がA、B、C地区の3地域にわけられており、C地区では土地に関する一般行政、治安維持の双方ともイスラエルから行政権限は委譲されていない。
8 道路建設に関しては、イスラエルと共同で技術委員会を設置しており、会合を月に2回開催している。また、C地域においても道路メンテナンスのためのワークショップの設置は認められている。
9 ガザにおける道路建設では、砂利を西岸地区より入手する必要がある。しかしながらイスラエル側の戦略により砂利輸送費が非常に高くつく仕組みとなっており、ガザ地区における道路舗装の障害の1つとなっている。

