第3章 対パレスチナ援助実績と他の援助国・国際機関の援助動向
第3章 対パレスチナ援助実績と他の援助国・国際機関の援助動向
3-1 対パレスチナ援助の国際的動向
1993年9月にパレスチナ暫定自治合意に関する原則合意宣言(the Declaration of Principles)がパレスチナ解放機構(PLO)とイスラエルにより署名されたことを受け、国際社会より3年間で総額24億ドルの支援が表明された。これら支援は和平地域の安定を目的に、当初はパレスチナの自治に不可欠である、1)組織制度構築、2)インフラ整備、3)人的資源開発、の3つを重点分野とし実施されてきた。しかし、その後のイスラエルによる封鎖政策の影響によりパレスチナ自治区における経済は悪化し、失業率は1993年の10%から約25-35%へ上昇、特にガザ地区では50%を越える結果となった。このような状況下、パレスチナ支援アドホック連絡委員会(AHLC:Ad-Hoc Liaison Committee)は1994年10月に対パレスチナ支援政策の見直しを図り、緊急雇用創出プログラムに援助の重点を移した。1995-1997年にかけては、雇用創出プログラムに加えインフラ改善を援助重点分野とし、封鎖政策による影響が一段落した1997年後半からは持続的経済発展に向け、再度、組織・制度造りならびに人的資源開発に支援の焦点が当てられている。1993年10月から1998年9月までの5年間援助総額はコミットメントベースで38.2億ドル、実施額は26.4億ドルとなっている。
パレスチナとドナー国/機関との主要調整機関としては、主要援助国/機関(ノルウェー(議長国)、世銀(事務局)、EU、日本、サウディアラビア、米国)とパレスチナ自治政府、イスラエルから成る上述のAHLCがあり、1993年に設立されて以来、対パレスチナ国際援助の受入れ、ドナー間の援助調整、パレスチナ側とドナー国/機関との対話促進、などを主に行っている。1994年には主要ドナー国/機関、パレスチナ、イスラエルの間の政策レベル調整を促進ならびに3者間アクションプラン(TAP:Tripartite Action Plan)の監視を行うためにパレスチナ計画国際協力庁(MOPIC:Ministry of Planning and International Cooperation)を議長とする共同連絡委員会(JLC:Joint Liaison Committee)がAHLCにより設置されている。また、支援国会議としては世界銀行が議長を務める諮問グループ会議(CG: the Consultative Group)があり、約50のドナー国/機関が参加する年1回の会合では、援助重点分野の設定、重点援助プログラム/プロジェクトの選定、特定ドナーからの支援表明などが行われる。現地レベルにおける調整組織としては、世銀、ノルウェー政府、UNSCO(United Nations Special Coordinator's Office)の各現地代表が同議長を努める現地援助調整委員会(LACC:Local Aid Coordination Committee)があり、12の分野(注1)でワーキンググループが設置されている。
| 援助国 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年* | 実施済援助総額 | ||||||
| 1 | 日本 | 91,894 | (91,894) | 68,824 | (68,824) | 77,024 | (77,024) | 66,681 | (66,681) | 17,452 | (53,156) | 321,875 |
| 2 | 米国 | 84,902 | (112,642) | 67,846 | (75,796) | 63,920 | (80,656) | 68,681 | (27,629) | 30,031 | (25,381) | 315,380 |
| 3 | ノルウェー | 35,671 | (35,671) | 44,322 | (44,322) | 56,691 | (59,592) | 55,553 | (54,417) | 52,491 | (52,833) | 244,728 |
| 4 | ドイツ | 97,490 | (143,949) | 26,264 | (42,263) | 33,426 | (46,602) | 42,420 | (59,797) | 20,482 | (66,184) | 220,082 |
| 5 | サウディ | 69,700 | (100,000) | 2,500 | (65,500) | 20,000 | (20,000) | 39,700 | (22,500) | 7,250 | (0) | 139,150 |
| 6 | オランダ | 16,368 | (20,718) | 16,630 | (49,745) | 52,487 | (54,037) | 17,051 | (18,527) | 13,741 | (16,332) | 116,277 |
| 7 | スペイン | 14,081 | (13,976) | 26,630 | (26,600) | 16,700 | (14,950) | 15,828 | (28,183) | 12,932 | (9,519) | 86,171 |
| 8 | スイス | 22,144 | (27,646) | 17,295 | (17,984) | 15,598 | (14,254) | 18,016 | (14,921) | 11,148 | (15,442) | 84,201 |
| 9 | スウェーデン | 7,023 | (30,761) | 2,480 | (10,320) | 28,536 | (28,292) | 14,022 | (14,570) | 14,688 | (14,151) | 66,749 |
| 10 | イタリア | 12,996 | (23,696) | 10,445 | (20,529) | 18,693 | (30,969) | 15,553 | (1,985) | 5,820 | (20,085) | 63,507 |
| 11 | フランス | 16,730 | (16,659) | 10,112 | (18,662) | 11,677 | (20,572) | 18,410 | (19,982) | 3,243 | (4,940) | 60,172 |
| 12 | デンマーク | 6,125 | (26,875) | 23,156 | (6,641) | 11,287 | (5,870) | 10,312 | (10,315) | 5,726 | (7,195) | 56,606 |
| 13 | イギリス | 6,976 | (6,943) | 5,593 | (4,744) | 12,893 | (14,808) | 13,023 | (13,744) | 1,120 | (45,722) | 39,605 |
| 14 | カナダ | 15,859 | (15,859) | 4,680 | (4,680) | 11,915 | (11,915) | 2,364 | (10,394) | 3,175 | (3,175) | 37,993 |
| 15 | クウェート | 20,000 | (20,000) | 4,000 | (4,000) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 24,000 |
| 16 | オーストリア | 4,153 | (6,547) | 2,701 | (307) | 1,876 | (10,113) | 5,205 | (3,634) | 5,365 | (4,747) | 19,300 |
| 17 | UAE | 15,000 | (15,000) | 0 | (0) | 0 | (0) | 4,000 | (4,000) | 0 | (0) | 19,000 |
| 18 | ベルギー | 6,974 | (6,868) | 7,022 | (10,406) | 1,820 | (7,127) | 1,447 | (11,179) | 0 | (1,944) | 17,263 |
| 19 | ジョルダン | 16,430 | (16,430) | 0 | (3,780) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 16,430 |
| 20 | エジプト | 5,330 | (5,330) | 0 | (30) | 180 | (1,850) | 10,000 | (10,000) | 267 | (267) | 15,777 |
| 21 | イスラエル | 6,500 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 7,060 | (0) | 13,560 |
| 22 | オーストラリア | 3,642 | (3,726) | 2,448 | (2,363) | 1,772 | (1,772) | 1,669 | (1,669) | 1,487 | (1,675) | 11,018 |
| 援助機関 | ||||||||||||
| 1 | EU | 60,406 | (92,018) | 73,211 | (99,214) | 99,749 | (108,189) | 54,141 | (76,136) | 10,795 | (43,750) | 298,302 |
| 2 | 世銀 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 37,779 | (25,000) | 37,779 |
| 3 | EU投資銀行 | 0 | (0) | 0 | (29,545) | 0 | (0) | 0 | (17,045) | 7,955 | (115,909) | 7,955 |
| 4 | UNDP | 275 | (275) | 721 | (721) | 1,134 | (1,134) | 2,613 | (2,613) | 3,053 | (3,055) | 7,796 |
| 5 | WFP | 0 | (0) | 1,167 | (1,167) | 0 | (0) | 3,082 | (3,094) | 1,506 | (5,072) | 5,755 |
| 6 | IFC | 0 | (3,800) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3,800 | (0) | 0 | (0) | 3,800 |
| その他 | 16,257 | (47,810) | 14,330 | (26,114) | 9,398 | (87,504) | 9,278 | (26,549) | 11,098 | (10,975) | 60,360 | |
| 合 計 | 652,926 | (885,093) | 432,377 | (634,257) | 546,776 | (697,230) | 492,849 | (519,564) | 285,664 | (546,509) | 2,410,591 | |
注2:順位は実施済援助総額に基づく
* 1998年は9月までの実績
出典:「MOPIC'S 1998 Forth Quarterly Monitoring Report of Donors' Assistance」, MOPIC, 1998.12より作成
表3-1に示すように、パレスチナへのODA実施総額(ローンは除く)は年間約5億ドル平均で推移している。援助主体別では、日本と米国が双へきであり、両国共これまでの援助実施額は約3.2億ドルとなっている。次いでノルウェー、ドイツ、サウディアラビア、オランダ、スペインの順で続き、サウディアラビアを除きEU諸国が上位を占めている。EU各国はEU全体としても援助を実施しており、その実施総額は約3億ドルである。国際機関では、世銀、EU投資銀行、UNDPの順で援助額が大きいが、これら援助額とは別枠で、世銀、UNDP、UNRWA(United Nations Relief and Works Agency)などの国際機関は各ドナー国からの拠出金等により独自の援助プログラムを実施している。尚、1998年11月に開催されたパレスチナ支援閣僚会議では、日本、米国、ノルウェー、EU、カナダ、サウディアラビア、イスラエル、スウェーデンを中心に総額約33億ドルの支援(日本は2年間で2億ドル、米国は5年間で9億ドル、EUは5年間で4.7億ドル等)の事前通報がなされている。
また分野別の援助実績を表3-2に示すが、パレスチナ自治区における情勢が安定傾向にあることを受け、全体的にみると人道的援助や難民支援等の緊急措置的な援助からやや中長期的展望を見越した援助へと移行しつつある。総額ではマルチセクター(有望産業セクター開発)、教育、組織・制度構築、水資源/衛生、保健・医療分野への援助が多いが、上述したような援助重点分野の移行を受け、最近では特に組織・制度構築、社会開発/人材育成への援助が急増している。また、経済発展のためのより直接的な支援の重要性から製造部門開発、工業開発に向けての援助も
| 分 野 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 合計 |
| マルチセクター | 251,486 | 115,653 | 132,341 | 81,818 | 33,327 | 614,625 |
| 教育 | 54,431 | 76,060 | 92,052 | 56,701 | 14,442 | 293,686 |
| 組織・制度構築 | 60,485 | 33,736 | 50,722 | 88,638 | 24,910 | 258,491 |
| 水資源/衛生 | 24,626 | 44,868 | 57,570 | 85,832 | 33,399 | 246,295 |
| 保健・医療 | 53,226 | 44,198 | 48,509 | 40,818 | 20,136 | 206,887 |
| 人道的援助 | 33,798 | 31,013 | 23,775 | 21,764 | 10,658 | 121,008 |
| 警察 | 56,549 | 19,956 | 10,954 | 5,483 | 1,173 | 94,115 |
| 製造部門開発 | 12,595 | 16,082 | 11,859 | 33,753 | 16,887 | 91,176 |
| インフラ | 7,789 | 8,470 | 20,428 | 20,394 | 32,980 | 90,061 |
| 住宅 | 43,658 | 16,017 | 10,160 | 16,021 | 3,671 | 89,527 |
| 民主化支援 | 12,387 | 7,228 | 29,128 | 15,557 | 12,196 | 76,496 |
| 社会開発/人材育成 | 3,559 | 2,174 | 9,025 | 12,297 | 27,601 | 54,656 |
| 運輸・交通 | 1,812 | 10,592 | 24,951 | 9,492 | 2,214 | 49,061 |
| エネルギー | 1,366 | 8,450 | 10,437 | 14,504 | 14,155 | 48,912 |
| 農業 | 4,474 | 5,875 | 12,991 | 11,498 | 6,545 | 41,383 |
| 観光資源開発 | 416 | 2,939 | 8,086 | 7,326 | 7,113 | 25,880 |
| 難民支援 | 10,803 | 2,509 | 8,441 | 910 | 2,277 | 24,940 |
| 工業開発 | 0 | 107 | 437 | 6,995 | 11,237 | 18,776 |
| 廃棄物処理 | 4,225 | 4,651 | 2,840 | 3,204 | 2,209 | 17,129 |
| WID | 1,406 | 2,032 | 2,798 | 2,979 | 4,309 | 13,524 |
| 環境 | 1,815 | 1,010 | 1,300 | 2,952 | 2,110 | 9,187 |
| 法的整備 | 0 | 158 | 915 | 418 | 339 | 1,830 |
| 民間セクター支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| その他 | 14,109 | 2,514 | 4,370 | 949 | 911 | 22,853 |
増加傾向にある。雇用創出にもつながるインフラ部門への支援は1995年の847万ドルから1996年には2千万ドルに急増し、以後安定的に推移している。一方、総額では上位を占める社会サービス分野(教育、保健・医療)への援助は減少傾向にある。
トップドナー国である日本からの援助は、UNDP、UNRWAへの拠出金を通じた援助に加え、1995年度からは病院や学校の建設、医療/教育機材供与、道路整備/消防機材供与などを中心とした直接支援も実施している(詳細は次節にて述べる)。日本と並び最大のドナー国である米国は、米国国際開発庁(USAID:Agency for International Development)が中心となり、1)経済発展、2)水資源開発、3)民主化支援、の3分野を重点分野とし援助を実施している。経済開発ではガザ工業団地開発や小規模ビジネス支援、水資源開発ではガザ汚水処理プロジェクトやガザ沿海地下水管理等を実施している。これら2国に次ぐ援助国であるノルウェーは、1)組織・制度造り、2)エネルギー、3)水資源開発、4)教育、の4分野に重点を置き、計画国際協力庁の組織・制度構築、西岸北部の電力整備ならびに電力庁支援、エリコ市やラファ市の水道整備ならびに水資源庁支援、西岸やアブ・ディス市における学校建設等を行っている。また、ドイツは援助形態を5つのカテゴリー(インフラ整備、技術協力、ドイツNGO支援、パレスチナNGO支援、研修)に分類して直接援助を実施し、主に水資源・汚水処理、組織造り、民間セクター支援、教育分野への支援を行っている。ドイツはEU諸国の一員としてEUを通じた援助も行っている。そのEUは各セクターにバランスよく援助を行っているが、特に教育分野、組織造りへの援助が多い。政治的理由からサウディアラビアからの援助も多く世銀、国連機関、イスラム開発銀行を通じて教育、保健・医療、住宅、組織・制度造り、マルチセクター支援等への支援を行っている。
国際機関としては、援助金額では世銀が対パレスチナ最大のドナー機関であるが、プロジェクトとしては、製造部門開発に係る財務庁への基金、ガザにおける水資源・衛生関連プロジェクトの実施とベツレヘム2000プロジェクトへの2,500万ドルのコミットのみであり、ドナー国からの受託による事業が主要業務となっており、他の国際機関についても同様である。UNDPは、1978年の国連決議に基づき「パレスチナ支援計画(PAPP:Programme of Assistance to the Palestinian People)」を開始しており、基礎インフラ整備(学校/病院改修、水供給、下水処理、電力整備等)、人的資源開発、組織造り、行政能力強化、技術移転など幅広いプロジェクトを実施している。同プログラムを通じてのこれら援助は、総額約3億ドルに達している。UNRWAも1950年以来ガザ、西岸において難民支援を行っている。教育、医療、その他社会サービス関連プログラムの実施とともに、特別プログラムとして学校、病院等の施設建設・改修、難民住宅の補修、小規模ビジネスならび女性支援プログラムへの融資を行っている。
3-2 我が国の対パレスチナ援助動向
我が国は「中東地域の社会的安定と和平に向けた政治環境造りへの貢献」を行うにあたって対パレスチナ援助の重要性から、1993年より対パレスチナ支援を本格化させている。以来、国際機関を通じての間接的援助を主体とした支援を実施、特に1988年にUNDPに設立した日本パレスチナ開発基金を通じての支援、UNRWAを通じての難民支援がその中心であり、また赤十字国際委員会、ホルスト基金(注2)、世銀の人材開発プログラムへの拠出も行ってきた。その後、1996年よりパレスチナ暫定自治政府に対する直接援助を開始しており、基礎生活分野、雇用創出、インフラ整備、社会資本整備等への支援ならびにパレスチナ暫定自治政府の行政経費支援が主たる
図3-2 我が国の対パレスチナ支援額の推移
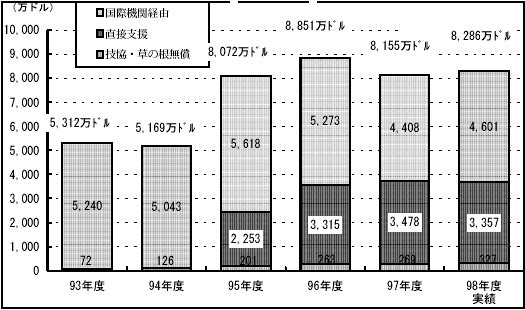
援助となっている。外務省中近東一課によると、1993-98年度までの対パレスチナ累計援助実績は約4.5億ドルで、うち国際機関への拠出が2.9億ドル(68.4%)、直接援助(無償資金協力)が1.2億ドル(28.6%)、技術協力が0.1億ドル(3.0%)となっている(図3-2参照)。
国際機関経由の援助は、上述の通りUNDPとUNRWAを通じての援助が中心となっている。我が国はUNDPのパレスチナ支援プログラムを支援しており、1998年度は日本パレスチナ開発基金を通じ約800万ドル(直接拠出)を拠出した。UNDPも含め国際機関経由の1998年度援助の内訳を表3-3に示す。
表3-3 我が国の国際機関等経由対パレスチナ支援内訳(1998年度)
| 拠 出 先 | 使 途 (*印:行政経費) | ||||
| UNDP 日本・パレスチナ 開発基金への拠出 |
通常 拠出 |
797万ドル | *在外パレスチナ人を通じた技術支援計画フェイズ4 | 50万ドル | |
| 地方村落開発計画フェイズ2 | 100万ドル | ||||
| *自治政府行政・訓練支援計画フェイズ2 | 100万ドル | ||||
| *パレスチナ環境庁行政支援計画フェイズ2 | 50万ドル | ||||
| 西岸地域水資源開発計画フェイズ2 | 50万ドル | ||||
| *パレスチナ人材開発計画策定フェイズ2 | 50万ドル | ||||
| エル・ビーレ文化施設建設計画フェイズ1 | 100万ドル | ||||
| ガザ地域東部村落給水計画フェイズ2 | 100万ドル | ||||
| *自治政府コンピュータセンター等改善計画(第2期) | 100万ドル | ||||
| ロザリー修道会学校建設計画 | 77万ドル | ||||
| ドナー援助評価及び援助調整改善のための調査 | 20万ドル | ||||
| 緊急 無償 支援 |
2,033万ドル | ガザ空港整備計画・人材育成計画 | 442万ドル | ||
| ラファハ通行所及びカルニ通行所修復・建設計画 | 236万ドル | ||||
| エレツ通行所整備計画 | 675万ドル | ||||
| 西岸農村部第一次医療施設改修計画 | 180万ドル | ||||
| ヘブロン地域農村給水網改善計画 | 200万ドル | ||||
| エリコ地域井戸掘削計画 | 100万ドル | ||||
| 西岸土地開拓プロジェクト(フェーズ2) | 200万ドル | ||||
| UNRWA | 拠 出 | 1,024万ドル | 一般基金 | 1000万ドル | |
| イヤーマーク事業 | CSP(高等教育のための奨学金等) | 7万ドル | |||
| 和平促進プログラム | 17万ドル | ||||
| 食糧援助 | 678万ドル | 678万ドル | |||
| 赤十字国際委員会(ICRC) | 69万ドル | イヤーマーク事業 | 69万ドル | ||
| 世銀人材開発プログラム (PHRD) |
121万ドル | 組織作り支援 | 38万ドル | ||
| 情報科学支援 | 18万ドル | ||||
| ベツレヘム2000支援 | 20万ドル | ||||
| 金融分野開発フェーズ2 | 46万ドル | ||||
| 1998年度合計 | 4,722万ドル | ||||
無償資金協力(直接援助)では、教育・医療機材、消防機材、道路改修機材などの供与、学校や病院建設、並びに緊急援助、食料増産援助などを実施している。1998年度には、ごみ処理機材供与やハーン・ユーニス地域の衛生改善計画など、衛生分野の援助が実施されている(表3-4参照)。また、援助開始当初から草の根無償も供与されており、1998年度までの総額は約521万ドルとなっている。地方におけるクリニックの整備・改善、小中学校の改修を中心に援助を実施しており、プロジェクトあたりの金額は小さいものの効果的な援助がなされている。技術協力では、人的資源開発、組織・制度造りの観点から、1998年度までに587名の研修生を受入れており、特に行政、公益事業、通信・放送、工業、エネルギー分野での受入が多い。専門家の派遣についてはイスラエルとの関係もあり、現時点では開発計画の短期専門家1名の派遣に留まっている。また、開発調査として1995年度より「ハーン・ユーニス市下水道整備計画」が実施されている。
表3-4 我が国の対パレスチナ直接援助(無償資金協力)
| 直 接 支 援 (無 償 資 金 協 力) | ||
| 平成 7年度 |
ガザ医療機材整備計画 | 約1,283万ドル |
| 高等教育機材整備計画 | 約891万ドル | |
| 小 計 | 約2,173万ドル | |
| 平成 8年度 |
エリコ病院建設計画 | 約2,012万ドル |
| 文化無償協力(パレスチナ文化庁への音響機材供与) | 約48万ドル | |
| ガザ地域主要道路改善整備計画 | 約522万ドル | |
| ガザ地域消防機材整備計画 | 約321万ドル | |
| 食糧増産援助 | 約412万ドル | |
| 小 計 | 約3,315万ドル | |
| 平成 9年度 |
ガザ地域小中学校建設計画 | 約1,631万ドル |
| 西岸地域医療機材整備計画 | 約1,520万ドル | |
| 食糧増産援助 | 約327万ドル | |
| 小 計 | 約3,478万ドル | |
| 平成 10年度 |
ガザ地域小中学校建設計画 | 約726万ドル |
| 文化無償協力(パレスチナ青年スポーツ庁に対するスポーツ器材) | 約35万ドル | |
| 食糧増産援助 | 約297万ドル | |
| ゴミ処理機材整備計画 | 約1,125万ドル | |
| アル・コドゥス大学医学部機材整備計画 | 約429万ドル | |
| 西岸地域主要道路改善整備計画 | 約505万ドル | |
| ハーン・ユーニス地域衛生改善計画 | 約240万ドル | |
| 小 計 | 約3,357万ドル | |
| 直 接 支 援 総 額 | 約12,324万ドル | |
尚、1998年11月の日米首脳会談にて小渕総理より1999年と2000年の2年間で2億ドルの支援が表明されており、特にパレスチナの人造り、法組織造り、インフラ整備に焦点を当てるとともに、援助重点分野として、1)基礎生活支援(教育、環境、医療サービス、水資源など)、2)緊急雇用促進プロジェクト、3)地方自治体等小規模コミュニティーによる小規模プロジェクト、4)日本、パレスチナ、イスラエルの3者間信頼醸成プロジェクト(注3)、5)パレスチナ難民支援(周辺国における難民も含む)、の5つが挙げられている。
3-3 パレスチナの援助吸収能力
パレスチナ暫定自治区における社会経済発展が和平の進展に向けての大きな要素であるという認識から、国際社会は対パレスチナ援助を継続してきた。これら援助は、イスラエルの封鎖政策による経済へのマイナス影響を押し上げる形で、暫定自治区におけるGDPを何とか一定水準に保つことに貢献してきた。1998年には実質GDP成長率が3%となり、これまでのイスラエル依存経済から独自経済の構築に一歩踏み出した段階にきたと言える。しかし、貯蓄投資ギャップに伴う財政赤字と国際収支の不均衡を埋めるための外国援助の役割はまだまだ重要であり、政府資本投資を援助資金が賄う傾向は当面続くことになろう。
パレスチナにおける援助吸収/実施に関しては、パレスチナ内部の要因、パレスチナ暫定自治政府の地位に係る要因(対イスラエルとの関係に起因)、ドナー国/機関側の要因、の3つに分けて考えることができる。
(パレスチナ内部の要因)
パレスチナ自治政府の援助吸収能力に関しては、援助実施に係る組織の効率性・透明性・管理能力の不足、援助に関する制度の未整備、人材の不足、担当庁間の調整不足・利権争い、透明性の不足に伴う汚職の増加など様々な問題が存在する。
特に援助の制度・組織面にかかる問題が援助実施にあたっての最大のネックとなっている。提案されたプロジェクト内容とプロジェクト実施計画管理が十分でないことから、援助資金の投入が遅延し、各種援助プロジェクトの実施の遅れ、あるいは実施不履行につながるケースもある。ドナー側が制度面に関しては過剰に評価していたこともあり、当面はプロジェクトデザインをより単純なものに変更する等の措置が必要であろう。
人材に関しては、パレスチナ人は比較的教育水準、技術水準ともに高いとされているが、援助実施を含む行政面に関しては管理部門、技術部門の人材共、経験不足の感が否めない。和平進展に伴い外国に暮らす優秀なパレスチナ難民が帰還することにより、この穴埋めを果たす可能性もあろうが、並行して援助受入に係る人材の確保/育成が急務であり、研修システムを充実する必要がある。
援助受入窓口となる機関の利権争いも援助実施にあたり大きな障害となっている。援助受入機関としては、原則合意を受け1993年に設立されたパレスチナ開発復興経済評議会(PECDAR: Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction)があるが、同機関は政治的色彩の強い組織となっている。その後パレスチナ自治政府により計画国際協力庁(MOPIC)が設立され、ドナー、パレスチナ自治政府双方から援助受入機関として承認されたが、両機関の対立は現在も続いており援助実施の妨げとなっている。加えて大統領府も多くの援助プロジェクトや経済政策に大きな影響を持っていることから、事態をより複雑にしている。
援助吸収に係る財政面の能力は、主に暫定自治政府の経常予算の支出能力、すなわち援助受取後の経常費用の負担能力によって規定される。直接的な収益創出機能を持たない援助案件の増加は、暫定自治政府の予算の圧迫につながることから、社会インフラサービスの向上と事業の財務的自立化の両立を目的とした総合的な視点から援助が実施されることが理想であるが、現実的には容易ではない。パレスチナにおける学校・病院建設、上下水道網整備等に関しては、適切な料金設定と経営管理がもたらされれば財務的自立は可能となろう。一方、機材供与プロジェクトに関しては、プロジェクト終了後に必要となる運転・維持管理コストは暫定自治政府の財政負担となる4。これらコストは援助受入側の自助努力によりカバーされるべきであろうが、プロジェクトの持続性を維持するためは、プロジェクト終了後一定期間は必要に応じドナー側による補てん・管理システムを維持することも考慮すべきであろう。
(パレスチナ暫定自治政府の地位に係る要因)
過去において対パレスチナ援助の効果を妨げてきた要因として、パレスチナ暫定自治政府の地位、すなわちイスラエルの対パレスチナ政策が挙げられる。これは、イスラエル政府による「封鎖政策」に起因するものと、パレスチナ暫定自治政府による「自治権の制限」に起因するものとの2つに大別できる。
封鎖政策により、イスラエル内にて雇用を保持していたパレスチナ人労働者は職を失い、多くの失業者を生むこととなった。また、封鎖の影響による輸出(特に農産物輸出)の減少ならびに暫定自治区内の商業活動の停滞は、暫定自治政府の財政収入を減少させる一方、暫定自治区内の社会サービス向上や失業者対策としての公務員数の増加等により支出を増加させ、財政を逼迫させることとなった。建築材料をはじめとする物資の輸送や援助に係るローカルスタッフの移動も制限を受けることになり、援助プロジェクトの実施に大きな悪影響を及ぼすこととなった。封鎖政策とは直接関係はないものの、援助に係る機材調達に際してイスラエル経由にて搬入を行う場合は、イスラエルの規格に合致するもののみ通関が可能となる。従って、供与機材が制限を受ける可能性がある。また、専門家の入国に際しても査証やその他の必要書類承認に時間を要する等の障害がある。
自治権の制限に関しては、水資源、物流(港湾、道路等)といった基礎インフラ関連の開発は、イスラエル側の許認可をなくしては進めることができないのが実態である。従って、これら部門における援助プロジェクトを実施するにあたっては、必要に応じてイスラエル政府機関との協議が不可欠となる。また、自治権の割合が地域によって違っており、特に西岸地区においては、A地区(完全自治)、B地区(一般行政はパレスチナ側、治安維持はイスラエル側)、C(イスラエルが一般行政、治安維持とも権限保持)の3つの地域に分けられている。ガザ地区においても農村部に飛び火した形でイスラエル人入植地が作られており、両地区間あるいは地区内拠点間の移動の自由が保障されておらず、援助の実施も含めパレスチナの自立発展的な開発を大きく阻害している。
(ドナー側の要因)
現地においてはドナー側にもマイナーではあるが課題は存在する。まずはドナー各国が暫定自治区において援助の旗揚げ競争の様相を呈している点であり、このことはパレスチナ側高官とのヒアリングでも聞かれた。この点に関連するが、援助実施にあったっては各国により機材等の規定が違うためパーツの種類が多様化するなど現地での管理を難しくしている。また、図3-1に示したように、パレスチナにおける援助調整機関/組織は、援助政策レベルの協議を行うAHLCとCGと現場レベルでの援助調整に重点を置くJLCとLACCがあり、構造的には効率的であると言える。しかし、現状はAHLC、CGとも援助政策協議組織というよりも和平推進に向けた政治的協議を中心に行う組織となっていっる感は否めない。また、LACCに属する分野別ワーキンググループにおいては、分野によりその活動内容に差異が大きいなどの問題の他に、援助内容に関する情報交換は行うものの、将来における援助調整の場とまでには至っていないとの批判もある。また、コミットした援助の遅延がしばしば問題にされるが、これはパレスチナに係る情勢の不透明さ・流動性が要因である。援助実施国の情勢が流動的である場合は、本部からの指示よりも現地担当者にその責務を譲渡することにより、より迅速でスムーズな援助が行える。この点に関する各ドナーの対応遅れが援助実施遅延等の要因の1つとなっていたが、時間の経過とともに解決の方向に向かうものと思われる。
脚注
1 運輸・通信、インフラ・住宅、保健・医療、雇用創出、教育、民間セクター支援、警察、国家財政、観光、農業、制度造り、環境の12分野。
2 パレスチナ自治政府の立ち上げ支援の目的で設立された基金であり、パレスチナ財政庁、パレスチナ開発復興経済評議会が資金の受手となっている。
3 パレスチナ国際問題アカデミー(NGO)にて開催される日パ中東セミナーにおけるイスラエル人講師の参加や、砂漠化防止に向けての共同研究等が挙げられる。
4 最終地位交渉の終結に伴いこれまでUNRWAによって実施されてきたサービスコストも自治政府の負担となると思われる。

